複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (25)
えだ【枝】🔗⭐🔉
え‐だいこ【柄太鼓】🔗⭐🔉
え‐だいこ【柄太鼓】
柄をつけた太鼓。
えだ‐うち【枝打ち】🔗⭐🔉
えだ‐うち【枝打ち】
樹木の枯枝・下枝などを切り落とすこと。主に、節のない材を得るために行う。枝下ろし。打ち枝。
えだ‐うつり【枝移り】🔗⭐🔉
えだ‐うつり【枝移り】
鳥が枝から枝へと飛び移ること。
えだ‐えだ【枝枝】🔗⭐🔉
えだ‐えだ【枝枝】
①多くの枝。
②兄弟・親族・子孫など一族の人々。栄華物語紫野「―栄え出でさせ給ふを」
えだ‐おうぎ【枝扇】‥アフギ🔗⭐🔉
えだ‐おうぎ【枝扇】‥アフギ
葉のついたままの枝を扇に代用したもの。枕草子12「なしの木…もとより打ち切りて定澄僧都の―にせばや」
えだ‐おとり【枝劣り】🔗⭐🔉
えだ‐おとり【枝劣り】
(幹から出た枝が幹よりは劣っていることから)父祖より子孫の劣っていること。宇津保物語祭使「今日よりや―すと人のいふらむ」
えだ‐おろし【枝下ろし】🔗⭐🔉
えだ‐おろし【枝下ろし】
(→)「枝打ち」に同じ。
えだ‐かき【枝掻き】🔗⭐🔉
えだ‐かき【枝掻き】
ウルシの枝木から漆を採取すること。
えだ‐がき【枝柿】🔗⭐🔉
えだ‐がき【枝柿】
①枝のついたままの柿の実。好色五人女2「唐瓜―かざる事のをかし」
②つるし柿。誹風柳多留15「―の種を出すのに目がすわり」
えだ‐がみ【枝神・裔神】🔗⭐🔉
えだ‐がみ【枝神・裔神】
末社の神。
えだ‐かもじ【枝髢】🔗⭐🔉
えだ‐かもじ【枝髢】
髪を長く見せるためにつぎ足す髢。
えだ‐がわ【枝川】‥ガハ🔗⭐🔉
えだ‐がわ【枝川】‥ガハ
本流に対して、支流。えだながれ。
えだ‐がわり【枝変り】‥ガハリ🔗⭐🔉
えだ‐がわり【枝変り】‥ガハリ
枝など植物体の一部分が母体と変わった形質になること。花の色変り、葉の斑入りと同様、体細胞突然変異の一種。その部分の種子または接穂はその変異形質を遺伝する。これを利用して果樹などの品種改良を行う。温州蜜柑から早生温州の生じたのは、その例。芽条変異。
え‐だくみ【画工】ヱ‥🔗⭐🔉
え‐だくみ【画工】ヱ‥
絵かき。絵師。
⇒えだくみ‐の‐つかさ【画工司】
えだくみ‐の‐つかさ【画工司】ヱ‥🔗⭐🔉
えだくみ‐の‐つかさ【画工司】ヱ‥
律令制で、中務なかつかさ省に属し、絵画・彩色などの事をつかさどる役所。えどころのつかさ。
⇒え‐だくみ【画工】
えだ‐ぐり【枝栗】🔗⭐🔉
えだ‐ぐり【枝栗】
枝のついた栗の実。
えだ‐げ【枝毛】🔗⭐🔉
えだ‐げ【枝毛】
毛髪の先が枝のように分岐したもの。
え‐だこ【絵凧】ヱ‥🔗⭐🔉
え‐だこ【絵凧】ヱ‥
絵模様の描いてある凧。→字凧
六角凧(新潟)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 村上凧(新潟)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
村上凧(新潟)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
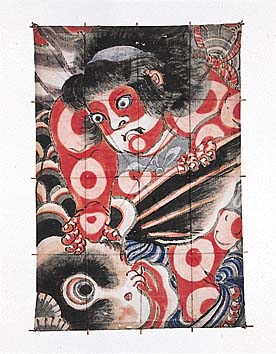 津軽凧(青森)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
津軽凧(青森)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 絵凧(愛媛)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
絵凧(愛媛)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 絵凧(東京)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
絵凧(東京)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 絵凧(秋田)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
絵凧(秋田)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)

 村上凧(新潟)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
村上凧(新潟)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
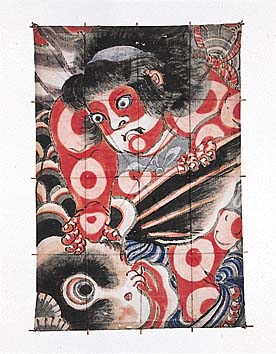 津軽凧(青森)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
津軽凧(青森)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 絵凧(愛媛)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
絵凧(愛媛)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 絵凧(東京)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
絵凧(東京)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 絵凧(秋田)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
絵凧(秋田)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)

えだ‐ごう【枝郷】‥ガウ🔗⭐🔉
えだ‐ごう【枝郷】‥ガウ
中世・近世、開発により新しくできた村の称。元の村である本郷(元郷)に対していう。枝村。
えだ‐さし【枝差】🔗⭐🔉
えだ‐さし【枝差】
草木の枝のさし出たようす。えだぶり。宇津保物語楼上下「―をかしう、めづらかなる木ども」
えだ‐ざし【枝挿し】🔗⭐🔉
えだ‐ざし【枝挿し】
枝を取って挿木とするもの。
えだ‐さんご【枝珊瑚】🔗⭐🔉
えだ‐さんご【枝珊瑚】
木の枝の形をした珊瑚。
えだ‐した【枝下】🔗⭐🔉
えだ‐した【枝下】
樹木の最も下の枝から地表までの長さ。
えだ‐しゃくとり【枝尺蠖】🔗⭐🔉
えだ‐しゃくとり【枝尺蠖】
(→)「しゃくとりむし」に同じ。
大辞林の検索結果 (49)
えだ【枝】🔗⭐🔉
えだ 【枝】
■一■ [0] (名)
(1)植物の主幹から分かれた茎。側芽や不定芽の発達したもの。「―が茂る」
(2)ものの本体・本筋から分かれ出たもの。「本筋からはずれた―の話」
(3)からだの手や足。四肢。「―を引き闕(カ)きて/古事記(中訓)」
(4)一族。子孫。「北家のすゑ,いまに―ひろごり給へり/大鏡(道長)」
■二■ (接尾)
助数詞。
(1)木の枝を数えるのに用いる。「一―の梅」
(2)細長い物を数えるのに用いる。「長持三十―/平家 10」
(3)〔昔,贈り物を木の枝に添えて差し出したことから〕
贈り物を数えるのに用いる。「雉一―奉らせ給ふ/源氏(行幸)」
え-だいこ【柄太鼓】🔗⭐🔉
え-だいこ [2] 【柄太鼓】
柄のつけてある太鼓。
→団扇(ウチワ)太鼓
えだ-うち【枝打ち】🔗⭐🔉
えだ-うち [0] 【枝打ち】 (名)スル
発育を促したり,節のないよい材を得るために樹木の下枝を切りはらうこと。枝下ろし。「庭木を―する」
えだ-うつり【枝移り】🔗⭐🔉
えだ-うつり [0] 【枝移り】 (名)スル
鳥などが枝から枝へと移ること。
えだ-おとり【枝劣り】🔗⭐🔉
えだ-おとり 【枝劣り】
〔幹より枝の方が劣っていることから〕
父祖より子孫の劣っていること。「もと見れば高き桂も今日よりや―すと人のいふらむ/宇津保(祭の使)」
えだ-おろし【枝下ろし】🔗⭐🔉
えだ-おろし [3] 【枝下ろし】 (名)スル
「枝打(エダウ)ち」に同じ。
えだ-がみ【枝神・裔神】🔗⭐🔉
えだ-がみ 【枝神・裔神】
末社に祀(マツ)られている神。
えだ-がわ【枝川】🔗⭐🔉
えだ-がわ ―ガハ [0] 【枝川】
(本流に対して)支流。
えだ-がわり【枝変(わ)り】🔗⭐🔉
えだ-がわり ―ガハリ [3] 【枝変(わ)り】
植物体の一部の枝のみが他と異なる遺伝形質を示す現象。芽の始原細胞における体細胞遺伝子の突然変異によって起こる。長十郎ナシから二十世紀ナシを得たのがこの例である。芽条変異。
えだ-ぎ【枝木】🔗⭐🔉
えだ-ぎ [0] 【枝木】
木の枝。
えだきり-ばさみ【枝切り鋏】🔗⭐🔉
えだきり-ばさみ [5] 【枝切り鋏】
樹木の剪定(センテイ)に用いる鋏。
え-だくみ【画工】🔗⭐🔉
え-だくみ  ― 【画工】
絵かき。絵師。「―白加(=人ノ名)/日本書紀(崇峻訓)」
― 【画工】
絵かき。絵師。「―白加(=人ノ名)/日本書紀(崇峻訓)」
 ― 【画工】
絵かき。絵師。「―白加(=人ノ名)/日本書紀(崇峻訓)」
― 【画工】
絵かき。絵師。「―白加(=人ノ名)/日本書紀(崇峻訓)」
えだくみ-の-つかさ【画工司】🔗⭐🔉
えだくみ-の-つかさ  ― 【画工司】
律令制で,中務(ナカツカサ)省に属し,宮廷の絵の用具や絵画・彩色をつかさどった役所。808年廃止され,のち絵所(エドコロ)となった。
― 【画工司】
律令制で,中務(ナカツカサ)省に属し,宮廷の絵の用具や絵画・彩色をつかさどった役所。808年廃止され,のち絵所(エドコロ)となった。
 ― 【画工司】
律令制で,中務(ナカツカサ)省に属し,宮廷の絵の用具や絵画・彩色をつかさどった役所。808年廃止され,のち絵所(エドコロ)となった。
― 【画工司】
律令制で,中務(ナカツカサ)省に属し,宮廷の絵の用具や絵画・彩色をつかさどった役所。808年廃止され,のち絵所(エドコロ)となった。
えだ-ぐり【枝栗】🔗⭐🔉
えだ-ぐり [0] 【枝栗】
枝のついたまま折り取った栗の実。
えだ-げ【枝毛】🔗⭐🔉
えだ-げ [0] 【枝毛】
毛髪の先が枝のように裂けたもの。
えだ-ざし【枝差し】🔗⭐🔉
えだ-ざし 【枝差し】
枝振り。「竜胆(リンドウ)は,―などもむつかしけれど/枕草子 67」
えだ-ざし【枝挿し】🔗⭐🔉
えだ-ざし [0] 【枝挿し】
挿し木の一。枝を挿し穂として用いるもの。
えだ-さんご【枝珊瑚】🔗⭐🔉
えだ-さんご [3] 【枝珊瑚】
枝の形をしたサンゴ。
えだ-した【枝下】🔗⭐🔉
えだ-した [0] 【枝下】
地面から力枝までの幹の部分。
えだ-しゃく【枝尺】🔗⭐🔉
えだ-しゃく [0] 【枝尺】
シャクガ科エダシャク亜科のガの総称。後ろばねの第五脈を欠くことが特徴。幼虫はシャクトリムシで,広葉樹の葉を食う。エダシャクトリ。エダシャクガ。
えだ-じろ【枝城】🔗⭐🔉
えだ-じろ [0] 【枝城】
(本城を根城と呼ぶのに対して)出城(デジロ)。支城。
えだ-ずみ【枝炭】🔗⭐🔉
えだ-ずみ [0] 【枝炭】
ツツジなどの細い木の枝を焼いてつくった炭。火のおこりを早くするために茶道で用いる。上に胡粉(ゴフン)を塗った白炭(シロズミ)と,塗らない山色(ヤマイロ)の二種がある。
え-だち【役】🔗⭐🔉
え-だち 【役】
(1)古代,朝廷が人民に課した労役。律令制では特に歳役・雑徭(ゾウヨウ)をいう。夫役(ブヤク)。「―を罷(ヤ)めしめたまふ/日本書紀(顕宗訓)」
(2)戦役。戦い。徴兵。「此の―に至りて意(ミココロ)に窮誅(コロ)さむと欲(オモホ)す/日本書紀(神武訓)」
えだ-ちょうし【枝調子】🔗⭐🔉
えだ-ちょうし ―テウシ [3] 【枝調子】
雅楽で,基本の六調子に対して,主音は同じで音階の違う調子。壱越(イチコツ)調に対しての沙陀(サダ)調,黄鐘(オウシキ)調に対する水調など五種がある。
えだ-づか【枝束】🔗⭐🔉
えだ-づか [2][0] 【枝束】
小屋組で,真束(シンヅカ)と陸梁(ロクバリ)の接点から斜めに出て,合掌を支えている方杖(ホウヅエ)。小屋方杖。
えだ-つき【枝付き】🔗⭐🔉
えだ-つき [0] 【枝付き】
枝のつき具合。枝ぶり。
えだ-つぎ【枝接ぎ】🔗⭐🔉
えだ-ながれ【枝流れ】🔗⭐🔉
えだ-ながれ [3] 【枝流れ】
支流。分流。枝川。
えだ-にく【枝肉】🔗⭐🔉
えだ-にく [0] 【枝肉】
家畜を屠殺(トサツ)後,放血して皮をはぎ,頭部・内臓と四肢の先端を取り除いた骨付きの肉。普通,脊柱に添って左右に二分したものをいう。
えだ-にょう【支繞】🔗⭐🔉
えだ-にょう ―ネウ [0] 【支繞】
⇒しにょう(支繞)
えだ-ね【支根】🔗⭐🔉
えだ-ね [0] 【支根】
主根から分かれ出た根。しこん。側根。
えだ-の-しゅじつ【枝の主日】🔗⭐🔉
えだ-の-しゅじつ 【枝の主日】
⇒棕櫚(シユロ)の主日(シユジツ)
えだ-は【枝葉】🔗⭐🔉
えだ-は [0] 【枝葉】
(1)枝と葉。
(2)物事の本質的でない,ささいな部分。枝葉末節。「―にこだわる」
(3)本家から分かれた者。また,家来・従者。「―の者は追つての御沙汰/人情本・梅児誉美(後)」
えだ-はらい【枝払い】🔗⭐🔉
えだ-はらい ―ハラヒ [3] 【枝払い】
伐採した木の枝を幹から切り離すこと。
→枝打ち
えだ-はり【枝張(り)】🔗⭐🔉
えだ-はり [0] 【枝張(り)】
樹木の枝の広がり具合。
えだ-ばり【枝針】🔗⭐🔉
えだ-ばり [0] 【枝針】
釣りで,胴突き仕掛けなどのように幹糸の途中から出してある針。
えだ-ばん【枝番】🔗⭐🔉
えだ-ばん [0] 【枝番】
〔「枝番号」の略〕
分類や順番を示す番号を,さらに細かく分けるときに付ける番号。
えたふなやま-こふん【江田船山古墳】🔗⭐🔉
えたふなやま-こふん 【江田船山古墳】
熊本県玉名郡菊水町江田にある前方後円墳。五世紀後半から六世紀初頭のもので,刀背に銘文を銀象眼した鉄製大刀が出土。
えだ-ぶり【枝振り】🔗⭐🔉
えだ-ぶり [0] 【枝振り】
枝の伸びたありさま。枝のかっこう。えださし。「―のいい松」
えだ-まめ【枝豆】🔗⭐🔉
えだ-まめ [0] 【枝豆】
まだ熟していない青い大豆を枝ごととったもの。さやのままゆでて食べる。[季]秋。
えだ-みち【枝道・岐路】🔗⭐🔉
えだ-みち [0] 【枝道・岐路】
(1)本道から分かれた道。横道。
(2)物事の本筋からはずれたところ。「話が―にそれる」
えだ-みや【枝宮】🔗⭐🔉
えだ-みや [0] 【枝宮】
「末社(マツシヤ)」に同じ。
エダム Edam
Edam 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
エダム [1]  Edam
Edam オランダ西部,エダム産の硬質のナチュラル-チーズ。球状で,表面を赤く着色。赤玉チーズ。
オランダ西部,エダム産の硬質のナチュラル-チーズ。球状で,表面を赤く着色。赤玉チーズ。
 Edam
Edam オランダ西部,エダム産の硬質のナチュラル-チーズ。球状で,表面を赤く着色。赤玉チーズ。
オランダ西部,エダム産の硬質のナチュラル-チーズ。球状で,表面を赤く着色。赤玉チーズ。
えだ-むら【枝村】🔗⭐🔉
えだ-むら [0] 【枝村】
江戸時代,開拓などによって本村から分立した村。元の村は親村・親郷という。
えだぶり【枝ぶりのよい松】(和英)🔗⭐🔉
えだぶり【枝ぶりのよい松】
a shapely pine tree.
えだまめ【枝豆】(和英)🔗⭐🔉
えだまめ【枝豆】
green soybeans.
広辞苑+大辞林に「えだ」で始まるの検索結果。もっと読み込む