複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (9)
はい‐かん【稗官】‥クワン🔗⭐🔉
はい‐かん【稗官】‥クワン
①低い官職。小役人。
②昔、中国で民間の風聞を集めて王に奏上した役。「―小説」→稗史
はい‐し【稗史】🔗⭐🔉
はい‐し【稗史】
昔、中国で稗官はいかんが集めて記録した民間の物語。転じて、広く小説をいう。仮名垣魯文、高橋阿伝夜刃譚「断然架空の業を廃し、―の筆を机上に投棄なげすて」
ひえ【稗・穇】🔗⭐🔉
ひえ【稗・穇】
イネ科の一年草。中国原産で、日本には古く渡来。種子はやや三角形の細粒。強健なため、古来、救荒作物として栽培、粒を食用とした。粒・茎葉は飼料としてすぐれているが、今は栽培が少ない。水田などに稲の雑草として混じる。〈[季]秋〉。万葉集11「打つ田には―はあまたにありといへど」
ひえ


ひえだ【稗田】🔗⭐🔉
ひえだ【稗田】
姓氏の一つ。
⇒ひえだ‐の‐あれ【稗田阿礼】
ひえだ‐の‐あれ【稗田阿礼】🔗⭐🔉
ひえだ‐の‐あれ【稗田阿礼】
天武天皇の舎人とねり。記憶力がすぐれていたため、天皇から帝紀・旧辞の誦習しょうしゅうを命ぜられ、太安万侶おおのやすまろがこれを筆録して「古事記」3巻が成った。
→文献資料[古事記]
⇒ひえだ【稗田】
ひえつき‐ぶし【稗搗節】🔗⭐🔉
ひえつき‐ぶし【稗搗節】
宮崎県の民謡。東臼杵郡椎葉村地方の稗搗き唄。歌詞は「庭の山椒さんしゅの木に鳴る鈴かけて」に始まり、現行のものには同村鶴富屋敷にまつわる平家落人伝説を含む。宴席歌として広まる。
→稗搗節
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
ひえ‐まき【稗蒔】🔗⭐🔉
ひえ‐まき【稗蒔】
鉢に綿などを敷いて水にひたしたものにアワ・ヒエなどを蒔き、その幼苗を青田のさまに見せる盆栽。絹糸草。〈[季]夏〉
ひえ‐めし【稗飯】🔗⭐🔉
ひえ‐めし【稗飯】
稗を米にまぜて炊いた飯。
[漢]稗🔗⭐🔉
稗 字形
 〔禾部8画/13画/4103・4923〕
〔音〕ハイ(漢)
〔訓〕ひえ
[意味]
①穀物の名。ひえ。「稗飯ひえめし」
②小さく砕けた米。転じて、こまごましている。「稗史・稗官」
〔禾部8画/13画/4103・4923〕
〔音〕ハイ(漢)
〔訓〕ひえ
[意味]
①穀物の名。ひえ。「稗飯ひえめし」
②小さく砕けた米。転じて、こまごましている。「稗史・稗官」
 〔禾部8画/13画/4103・4923〕
〔音〕ハイ(漢)
〔訓〕ひえ
[意味]
①穀物の名。ひえ。「稗飯ひえめし」
②小さく砕けた米。転じて、こまごましている。「稗史・稗官」
〔禾部8画/13画/4103・4923〕
〔音〕ハイ(漢)
〔訓〕ひえ
[意味]
①穀物の名。ひえ。「稗飯ひえめし」
②小さく砕けた米。転じて、こまごましている。「稗史・稗官」
大辞林の検索結果 (9)
ひえ【稗・ 】🔗⭐🔉
】🔗⭐🔉
ひえ [1][2] 【稗・ 】
イネ科の一年草。草状はイネに似,高さ1〜1.5メートル。実は黄色く細い粒で,食用・鳥の飼料用。丈夫で災害に強く,やせ地にも育つので,古来,備荒作物として栽培する。[季]秋。
稗
】
イネ科の一年草。草状はイネに似,高さ1〜1.5メートル。実は黄色く細い粒で,食用・鳥の飼料用。丈夫で災害に強く,やせ地にも育つので,古来,備荒作物として栽培する。[季]秋。
稗
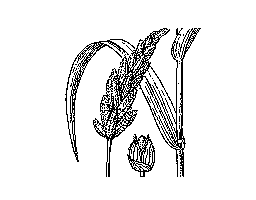 [図]
[図]
 】
イネ科の一年草。草状はイネに似,高さ1〜1.5メートル。実は黄色く細い粒で,食用・鳥の飼料用。丈夫で災害に強く,やせ地にも育つので,古来,備荒作物として栽培する。[季]秋。
稗
】
イネ科の一年草。草状はイネに似,高さ1〜1.5メートル。実は黄色く細い粒で,食用・鳥の飼料用。丈夫で災害に強く,やせ地にも育つので,古来,備荒作物として栽培する。[季]秋。
稗
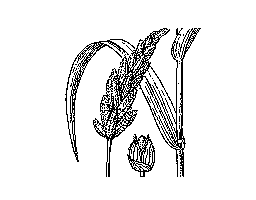 [図]
[図]
ひえだ【稗田】🔗⭐🔉
ひえだ 【稗田】
姓氏の一。
ひえだ-の-あれ【稗田阿礼】🔗⭐🔉
ひえだ-の-あれ 【稗田阿礼】
天武天皇の舎人(トネリ)。文字・文章の読解力・記憶力に優れ,帝皇日継・先代旧辞の誦習を命ぜられた。のちに太安万侶(オオノヤスマロ)が,元明天皇の命によりこれを撰録して古事記とした。生没年未詳。
ひえつき-ぶし【稗搗き節】🔗⭐🔉
ひえつき-ぶし 【稗搗き節】
宮崎県の民謡で,東臼杵郡椎葉村の仕事唄。ヒエの穂先を臼に入れ,手杵(テキネ)で搗(ツ)く時に唄われた。源流は江戸末期にはやった甚句の系譜。
ひえ-まき【稗蒔き】🔗⭐🔉
ひえ-まき [0][2] 【稗蒔き】
水盤や箱などにヒエをまき,芽の出たのを青田に見立てて涼感をめでるもの。[季]夏。《―に眼をなぐさむる読書かな/高橋淡路女》
→絹糸草
ひえ-めし【稗飯】🔗⭐🔉
ひえ-めし [0][2] 【稗飯】
ヒエを炊いた飯。またヒエを米にまぜて炊いた飯。
ひえ【稗】(和英)🔗⭐🔉
ひえ【稗】
a barnyard millet.
広辞苑+大辞林に「稗・」で始まるの検索結果。