複数辞典一括検索+![]()
![]()
【干】🔗⭐🔉
【干】
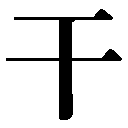 3画 干部 [六年]
区点=2019 16進=3433 シフトJIS=8AB1
《常用音訓》カン/ひ…る/ほ…す
《音読み》 カン
3画 干部 [六年]
区点=2019 16進=3433 シフトJIS=8AB1
《常用音訓》カン/ひ…る/ほ…す
《音読み》 カン
 〈g
〈g n〉
《訓読み》 ほす/ひる/ほこ/たて/おかす(をかす)/もとめる(もとむ)/かかわる(かかはる)
《名付け》 たく・たて・ほす・もと・もとむ
《意味》
n〉
《訓読み》 ほす/ひる/ほこ/たて/おかす(をかす)/もとめる(もとむ)/かかわる(かかはる)
《名付け》 たく・たて・ほす・もと・もとむ
《意味》
 {動}ほす。かわかす。▽乾カンに当てた用法。〈対語〉→湿。「干物(=乾物)」
{動}ほす。かわかす。▽乾カンに当てた用法。〈対語〉→湿。「干物(=乾物)」
 {動}ひる。かわいて水気がなくなる。〈同義語〉→旱。〈対語〉→湿・→潤。「干潮(引き潮)」
{動}ひる。かわいて水気がなくなる。〈同義語〉→旱。〈対語〉→湿・→潤。「干潮(引き潮)」
 {名}ほこ。武器にするこん棒。また、敵を突くための柄つきの武器。〈同義語〉→杆・→桿。
{名}ほこ。武器にするこん棒。また、敵を突くための柄つきの武器。〈同義語〉→杆・→桿。
 {名}たて。敵の武器から身を守るたて。〈類義語〉→盾ジュン/タテ・→楯ジュン/タテ。「干戈カンカ(たてと、ほこ。武器のこと)」
{名}たて。敵の武器から身を守るたて。〈類義語〉→盾ジュン/タテ・→楯ジュン/タテ。「干戈カンカ(たてと、ほこ。武器のこと)」
 {動}おかす(ヲカス)。障害を越えて突き進む。「干犯カンパン」
{動}おかす(ヲカス)。障害を越えて突き進む。「干犯カンパン」
 {動}もとめる(モトム)。むりをして手に入れようとする。「干禄=禄ヲ干ム」
{動}もとめる(モトム)。むりをして手に入れようとする。「干禄=禄ヲ干ム」
 カンス{動}かかわる(カカハル)。他者の領域にまではいりこむ。「干渉」「不相干=アヒ干セズ」
カンス{動}かかわる(カカハル)。他者の領域にまではいりこむ。「干渉」「不相干=アヒ干セズ」
 {動}まもる。「干城=城ヲ干ル」
{動}まもる。「干城=城ヲ干ル」
 「欄干ランカン」とは、外にはみ出ないように棒を渡した、てすりのこと。
「欄干ランカン」とは、外にはみ出ないように棒を渡した、てすりのこと。
 「十干ジッカン」とは、甲・乙・丙・丁・戊ボ・己・庚コウ・辛シン・壬ジン・癸キのこと。▽幹に当てた用法。
《解字》
「十干ジッカン」とは、甲・乙・丙・丁・戊ボ・己・庚コウ・辛シン・壬ジン・癸キのこと。▽幹に当てた用法。
《解字》
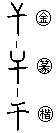 象形。ふたまたの棒を描いたもの。これで人を突く武器にも、身を守る武具にも用いる。また、突き進むのはおかすことであり、身を守るのはたてである。干は、幹(太い棒、みき)・竿カン(竹の棒)・杆カン・桿カン(木の棒)の原字。乾(ほす、かわく)に当てるのは、仮借である。
《類義》
→犯・→盾
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
象形。ふたまたの棒を描いたもの。これで人を突く武器にも、身を守る武具にも用いる。また、突き進むのはおかすことであり、身を守るのはたてである。干は、幹(太い棒、みき)・竿カン(竹の棒)・杆カン・桿カン(木の棒)の原字。乾(ほす、かわく)に当てるのは、仮借である。
《類義》
→犯・→盾
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
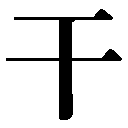 3画 干部 [六年]
区点=2019 16進=3433 シフトJIS=8AB1
《常用音訓》カン/ひ…る/ほ…す
《音読み》 カン
3画 干部 [六年]
区点=2019 16進=3433 シフトJIS=8AB1
《常用音訓》カン/ひ…る/ほ…す
《音読み》 カン
 〈g
〈g n〉
《訓読み》 ほす/ひる/ほこ/たて/おかす(をかす)/もとめる(もとむ)/かかわる(かかはる)
《名付け》 たく・たて・ほす・もと・もとむ
《意味》
n〉
《訓読み》 ほす/ひる/ほこ/たて/おかす(をかす)/もとめる(もとむ)/かかわる(かかはる)
《名付け》 たく・たて・ほす・もと・もとむ
《意味》
 {動}ほす。かわかす。▽乾カンに当てた用法。〈対語〉→湿。「干物(=乾物)」
{動}ほす。かわかす。▽乾カンに当てた用法。〈対語〉→湿。「干物(=乾物)」
 {動}ひる。かわいて水気がなくなる。〈同義語〉→旱。〈対語〉→湿・→潤。「干潮(引き潮)」
{動}ひる。かわいて水気がなくなる。〈同義語〉→旱。〈対語〉→湿・→潤。「干潮(引き潮)」
 {名}ほこ。武器にするこん棒。また、敵を突くための柄つきの武器。〈同義語〉→杆・→桿。
{名}ほこ。武器にするこん棒。また、敵を突くための柄つきの武器。〈同義語〉→杆・→桿。
 {名}たて。敵の武器から身を守るたて。〈類義語〉→盾ジュン/タテ・→楯ジュン/タテ。「干戈カンカ(たてと、ほこ。武器のこと)」
{名}たて。敵の武器から身を守るたて。〈類義語〉→盾ジュン/タテ・→楯ジュン/タテ。「干戈カンカ(たてと、ほこ。武器のこと)」
 {動}おかす(ヲカス)。障害を越えて突き進む。「干犯カンパン」
{動}おかす(ヲカス)。障害を越えて突き進む。「干犯カンパン」
 {動}もとめる(モトム)。むりをして手に入れようとする。「干禄=禄ヲ干ム」
{動}もとめる(モトム)。むりをして手に入れようとする。「干禄=禄ヲ干ム」
 カンス{動}かかわる(カカハル)。他者の領域にまではいりこむ。「干渉」「不相干=アヒ干セズ」
カンス{動}かかわる(カカハル)。他者の領域にまではいりこむ。「干渉」「不相干=アヒ干セズ」
 {動}まもる。「干城=城ヲ干ル」
{動}まもる。「干城=城ヲ干ル」
 「欄干ランカン」とは、外にはみ出ないように棒を渡した、てすりのこと。
「欄干ランカン」とは、外にはみ出ないように棒を渡した、てすりのこと。
 「十干ジッカン」とは、甲・乙・丙・丁・戊ボ・己・庚コウ・辛シン・壬ジン・癸キのこと。▽幹に当てた用法。
《解字》
「十干ジッカン」とは、甲・乙・丙・丁・戊ボ・己・庚コウ・辛シン・壬ジン・癸キのこと。▽幹に当てた用法。
《解字》
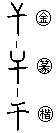 象形。ふたまたの棒を描いたもの。これで人を突く武器にも、身を守る武具にも用いる。また、突き進むのはおかすことであり、身を守るのはたてである。干は、幹(太い棒、みき)・竿カン(竹の棒)・杆カン・桿カン(木の棒)の原字。乾(ほす、かわく)に当てるのは、仮借である。
《類義》
→犯・→盾
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
象形。ふたまたの棒を描いたもの。これで人を突く武器にも、身を守る武具にも用いる。また、突き進むのはおかすことであり、身を守るのはたてである。干は、幹(太い棒、みき)・竿カン(竹の棒)・杆カン・桿カン(木の棒)の原字。乾(ほす、かわく)に当てるのは、仮借である。
《類義》
→犯・→盾
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
漢字源 ページ 1420 での【干】単語。