複数辞典一括検索+![]()
![]()
え‐と【干支】🔗⭐🔉
え‐と【干支】
(「兄え弟と」の意)
①十干十二支。十干を五行(木・火・土・金・水)に配当し、陽をあらわす兄え、陰をあらわす弟とをつけて名とした、甲きのえ・乙きのと・丙ひのえ・丁ひのと・戊つちのえ・己つちのと・庚かのえ・辛かのと・壬みずのえ・癸みずのとに、十二支を組み合わせたもの。甲子きのえね・乙丑きのとうしなど60種の組合せを年・月・日に当てて用いる。
干支(表)
 ②十二支。年、特に生年や方位・時刻に当てる。「今年の―は丑うしだ」
②十二支。年、特に生年や方位・時刻に当てる。「今年の―は丑うしだ」
 ②十二支。年、特に生年や方位・時刻に当てる。「今年の―は丑うしだ」
②十二支。年、特に生年や方位・時刻に当てる。「今年の―は丑うしだ」
から‐もの【乾物・干物】🔗⭐🔉
から‐もの【乾物・干物】
ひもの。干魚。宇津保物語貴宮「なまもの、―」
かん【干】🔗⭐🔉
かん【干】
①(幹の意)五行の干支えとに用いる語。
②雅楽の横笛おうてき・高麗笛・神楽笛の歌口から6番目の孔。徒然草「横笛…―の穴は平調」
③能管の歌口に最も近い孔。
④古代中国の八佾はちいつ舞の武舞に用いる装飾のある盾。→戚せき2
かん‐か【干戈】‥クワ🔗⭐🔉
かん‐か【干戈】‥クワ
①たてとほこ。武器。
②転じて、いくさ。
⇒干戈を交える
かん‐がい【干害・旱害】🔗⭐🔉
かん‐がい【干害・旱害】
ひでりによって受ける農作物などの損害。
○干戈を交えるかんかをまじえる🔗⭐🔉
○干戈を交えるかんかをまじえる
戦う。戦争をする。
⇒かん‐か【干戈】
かん‐かん
①金属質の堅い物が連続して打ち当たる澄んだ音。「踏切の警報機が―と鳴る」
②太陽や火などの熱が強烈であるさま。「日が―と照りつける」「炭火を―におこす」
③人が激しているさま。「―になって怒る」
⇒かんかん‐いし【かんかん石】
⇒かんかん‐でり【かんかん照り】
⇒かんかん‐ぼう【かんかん帽】
⇒かんかん‐むし【かんかん虫】
かん‐かん
(幼児語)
①髪。
②かんざし。浮世風呂3「―をさして」
③かわいいこと。かわいいもの。
④下駄。かっこ。
かん‐かん【汗簡】
(→)汗青かんせいに同じ。
かん‐かん【肝管】‥クワン
肝臓で作られた胆汁を輸送する管。肝臓の左右両葉から各1管が出て肝門で合流する。
かん‐かん【侃侃】
剛直なさま。
⇒かんかん‐がくがく【侃侃諤諤】
かん‐かん【看官】‥クワン
見る人。読者。観官。尾崎紅葉、紅子戯語「字を大きくして行ぎょうをあらくしたのは―の読みいゝ為めにと」
かん‐かん【看貫】‥クワン
①品物の量目をはかって、斤量を定めること。
②看貫秤の略。
⇒かんかん‐ばかり【看貫秤】
かん‐かん【桓寛】クワンクワン
前漢の儒者。字は次公。河南汝南の人。宣帝・昭帝に仕え、賢良・文学の士と丞相・御史などの時務を論じ、また「塩鉄論」を編纂した。
かん‐かん【閑官】‥クワン
職務のひまな官職、また官吏。
かん‐かん【閑閑】
心しずかに落ち着いているさま。心ののどかなさま。「悠々―」
かん‐かん【寛緩】クワンクワン
ゆるやかなさま。おおようなさま。
かん‐かん【感官】‥クワン
(sense イギリス・Sinn ドイツ)感覚器官とその知覚作用。生理作用と心理作用を統一的に考える場合に用いる語。感覚器官は外界知覚に関するものであるから外官と呼ぶ場合があり、これに対して意識内部を知覚する能力を内官と呼ぶ。
かん‐かん【漢奸】
中国で、敵に通じる者。裏切者。売国奴。
かん‐かん【関関】クワンクワン
鳥ののどかな声。→関雎かんしょ
かん‐かん【緩緩】クワンクワン
ゆるやかなさま。いそがぬさま。太平記10「―の沙汰を致さば」
かん‐かん【韓幹】
唐代の画家。河南開封の人。王維に認められ、天宝(742〜755)年間に宮廷画家。画馬を得意とし、画牛の韓滉かんこう(723〜787)とともに著名。
かん‐かん【観官】クワンクワン
読者。看官。椿説弓張月後編「冀こいねがわくは四方の―、嗣篇しへん発兌はつだの日を俟まちて、更に高評を加くわえ給へかし」
カンカン【cancan フランス】
舞曲の一種。19世紀中葉パリを中心に広がった4分の2拍子の速いテンポの舞踊曲、またその踊り。オペレッタに用いられ、ムーラン‐ルージュなどのダンスホールで盛行。フレンチ‐カンカン。
かん‐がん【汗顔】
大いに恥じて顔に汗をかくこと。極めて恥かしく感ずること。「―の至り」
かん‐がん【肝癌】
「肝臓癌」参照。
かん‐がん【宦官】クワングワン
東洋諸国で後宮に仕えた去勢男子。特に中国で盛行、宮刑に処せられた者、異民族の捕虜などから採用したが、後には志望者をも任用した。常に君主に近接し、重用されて政権を左右することも多く、後漢・唐・明代にはその弊害が著しかった。宦者。寺人じじん。閹官えんかん。閹人。刑余。閽寺こんじ。
かん‐がん【還願】クワングワン
神仏にかけた願を解くこと。願解がんほどき。
がん‐がん
①金属質の堅い物が連続して打ち当たるやかましい音。「ドラム缶を―叩く」
②小言などをやかましく言うさま。「大声で―言う」
③勢いが盛んではげしいさま。「ストーブを―燃やす」「―仕事を進める」
④頭の中で鐘が鳴りひびくような痛みを感じるさま。頭に強くひびくさま。「頭が―する」
がん‐がん【巌巌】
①山や岩などのけわしくそばだつさま。
②人格の高尚なさま。
かんかん‐いし【かんかん石】
讃岐岩さぬきがんの別称。
⇒かん‐かん
かんかん‐おどり【看看踊】‥ヲドリ
(「かんかんのう」云々の歌詞から、そう呼ばれる)(→)唐人踊に同じ。
かんかん‐がくがく【侃侃諤諤】
(→)侃諤かんがくに同じ。「―の議論」
⇒かん‐かん【侃侃】
かん‐かんけい【関漢卿】クワン‥
雑劇の作者。元曲四大家の随一。大都(北京)の人。作「竇娥寃とうがえん」「救風塵」など。生没年不詳。
がんがんさん
神社・寺を意味する小児語。がんが。歌舞伎、色競かしくの紅翅べにがき「ヲヽ此のをばが、―へ連ていて」
かんかん‐しき【観艦式】クワン‥
海軍の威容をその国の元首などが親閲する儀式。
かんかん‐でり【かんかん照り】
夏、日光が強く照りつけること。
⇒かん‐かん
かんかんのう
「かんかんおどり(看看踊)」参照。
かんかん‐ばかり【看貫秤】‥クワン‥
(→)台秤だいばかりに同じ。
⇒かん‐かん【看貫】
かんかん‐ぼう【かんかん帽】
かたく編んだ麦わら帽子。
⇒かん‐かん
かんかん‐むし【かんかん虫】
艦船・タンク・煙突などに虫のようにへばりつき、ハンマーでかんかん叩いて、さびとり作業をする者。
⇒かん‐かん
かんき【甘輝】
浄瑠璃「国性爺合戦こくせんやかっせん」中の人物。韃靼国だったんこくの将軍で、錦祥女きんしょうじょを妻とし、獅子城にいたが、妻の義に感じて和藤内の明朝再興の挙を助けた。
かん‐き【刊記】
和漢の刊本で、出版の年月・所・刊行者など、出版に関する事項を記した部分。多くは巻末にあるが、見返し・序文末・目次末などにある場合もある。現代の奥付や洋書の標題紙に相当する。
かん‐き【官紀】クワン‥
官吏の服務上守るべき紀律。
かん‐き【官記】クワン‥
任官した者に授与される辞令書。
かん‐き【乾季・乾期】
一年の中で雨の少ない季節。特に、東南アジア・インド・アフリカなどは、乾季と雨季とがはっきり分かれている。
かん‐き【勘気】
主君や父からのとがめ。勘当。東鑑4「義経…御―を蒙るの間」。「―が解ける」
かん‐き【喚起】クワン‥
よび起こすこと。「注意を―する」
かん‐き【換気】クワン‥
空気を入れかえること。「部屋を―する」
⇒かんき‐こう【換気口】
⇒かんき‐せん【換気扇】
⇒かんき‐とう【換気塔】
かん‐き【寒気】
さむさ。〈[季]冬〉。「―がゆるむ」
⇒かんき‐りんれつ【寒気 冽】
かん‐き【感喜】
感じて喜ぶこと。
かん‐き【管窺】クワン‥
[晋書王献之伝「管中に豹を窺うかがうに、時に一斑を見るのみ」](管の穴から豹を見ると、その皮の一つのまだらしか見えないことから)見識の狭いこと。管見。
かん‐き【歓喜】クワン‥
①大そうよろこぶこと。よろこび。「―のあまり涙を流す」
②⇒かんぎ
かん‐き【韓琦】
北宋の宰相。字は稚圭。河南安陽の人。仁宗・英宗・神宗に歴仕し、英宗の時に魏国公に封。范仲淹はんちゅうえんと共に韓范と並称される。神宗の時に上疏して王安石の新法の非を説いたが入れられず、病死。著「安陽集」「韓魏公集」。(1008〜1075)
かん‐ぎ【官妓】クワン‥
官に属する芸妓。特に高麗王朝以後の朝鮮で、医薬・裁縫・歌舞・妓楽をもって宮廷・地方官庁に仕えた女性をいう。妓生キーセン。
かん‐ぎ【冠儀】クワン‥
元服の儀式。
かんぎ【寛喜】クワン‥
[後魏書]鎌倉中期、後堀河天皇朝の年号。安貞3年3月5日(1229年3月31日)改元、寛喜4年4月2日(1232年4月23日)貞永に改元。
⇒かんぎ‐の‐ききん【寛喜の飢饉】
かん‐ぎ【関木】クワン‥
かんぬき。関の木。
かん‐ぎ【歓喜】クワン‥
〔仏〕宗教的なよろこび。「―踊躍ゆやく」
⇒かんぎ‐おん【歓喜園】
⇒かんぎ‐じ【歓喜地】
⇒かんぎ‐だん【歓喜団】
⇒かんぎ‐てん【歓喜天】
かん‐ぎ【諫議】
天子を諫いさめて政治を議すること。
⇒かんぎ‐たいふ【諫議大夫】
がん‐き【顔輝】
南宋末・元初の画家。字は秋月。江西廬陵の人。道釈人物を得意とし、多くの作品が日本に渡来。代表作「蝦蟆鉄拐図」(京都知恩寺蔵)。
がん‐ぎ【雁木】
(雁の行列のように、ぎざぎざの形をしたもの)
①橋の上の桟。雁歯。
②船着場の階段のある桟橋。
③雪深い地方(主として新潟県)で、町屋の軒から庇ひさしを長く張り出し、その下を通路としたもの。雁木造。〈[季]冬〉
④木挽こびきの用いる大きな鋸のこぎり。おが。
⑤雁木鑢がんぎやすりの略。雁木鑢は押しても引いても物を削るところから、両方で損すること。浮世風呂4「先が銭を出さねえときてゐるから―だアス」
⑥人の気づかない所に出ていて邪魔になる棒。
⇒がんぎ‐えい【雁木鱝】
⇒がんぎ‐がしら【雁木頭】
⇒がんぎ‐ぐるま【雁木車】
⇒がんぎ‐ざとり【雁木悟り】
⇒がんぎ‐だな【雁木棚】
⇒がんぎ‐だま【雁木玉】
⇒がんぎ‐ばしご【雁木梯子】
⇒がんぎ‐やすり【雁木鑢】
がんぎ‐えい【雁木鱝】‥エヒ
ガンギエイ科の海産の軟骨魚。全長約1.5メートル。体は菱形で尾部は細長い。背面は褐色。腹部は白色。青森以南に産する。夏、美味。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かんぎえん【咸宜園】‥ヱン
広瀬淡窓が豊後国日田郡堀田村に開いた漢学塾。1817年(文化14)開設。各層に広く開放し、儒学・作詩を教えた。競争試験による進級制を採用。門人総数は数千を数え、江戸時代最大の私塾となる。97年(明治30)まで存続。
かんぎ‐おん【歓喜園】クワン‥ヲン
(カンギエンとも)
①忉利天とうりてんの帝釈たいしゃくの居城にある四園の一つ。天人たちが園内に入れば自然に歓喜の念が生ずるという。
②インド迦毘羅衛かびらえ城における釈尊降誕の園。ルンビニーの別名。
⇒かん‐ぎ【歓喜】
がんぎ‐がしら【雁木頭】
鋸歯状または剣先をならべたような形や文様。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かん‐ぎく【釻菊】クワン‥
(「釻」は「鐶」の当て字)紋所の名。菊花の形を座とし、これに鐶を添えたもの。
かん‐ぎく【寒菊】
アブラギクを改良した黄花の園芸品種。冬咲き。ほかに、晩生のキクで、冬まで開花を続けるものをもいう。残菊。冬菊。〈[季]冬〉。〈日葡辞書〉
かん‐ぎく【観菊】クワン‥
菊の花を観賞すること。菊見。
⇒かんぎく‐かい【観菊会】
かんぎく‐かい【観菊会】クワン‥クワイ
毎年11月中旬頃、赤坂離宮のち新宿御苑で行われた天皇主催の観菊の行事。1937年(昭和12)廃止されたが、53年皇室園遊会として復活。観菊御宴。
⇒かん‐ぎく【観菊】
がんぎ‐ぐるま【雁木車】
①積荷の揚げ卸しに用いる滑車の一種。材の横面をくりぬき、車をはめこみ細引を通して、高い所に吊って使用する。
雁木車
冽】
かん‐き【感喜】
感じて喜ぶこと。
かん‐き【管窺】クワン‥
[晋書王献之伝「管中に豹を窺うかがうに、時に一斑を見るのみ」](管の穴から豹を見ると、その皮の一つのまだらしか見えないことから)見識の狭いこと。管見。
かん‐き【歓喜】クワン‥
①大そうよろこぶこと。よろこび。「―のあまり涙を流す」
②⇒かんぎ
かん‐き【韓琦】
北宋の宰相。字は稚圭。河南安陽の人。仁宗・英宗・神宗に歴仕し、英宗の時に魏国公に封。范仲淹はんちゅうえんと共に韓范と並称される。神宗の時に上疏して王安石の新法の非を説いたが入れられず、病死。著「安陽集」「韓魏公集」。(1008〜1075)
かん‐ぎ【官妓】クワン‥
官に属する芸妓。特に高麗王朝以後の朝鮮で、医薬・裁縫・歌舞・妓楽をもって宮廷・地方官庁に仕えた女性をいう。妓生キーセン。
かん‐ぎ【冠儀】クワン‥
元服の儀式。
かんぎ【寛喜】クワン‥
[後魏書]鎌倉中期、後堀河天皇朝の年号。安貞3年3月5日(1229年3月31日)改元、寛喜4年4月2日(1232年4月23日)貞永に改元。
⇒かんぎ‐の‐ききん【寛喜の飢饉】
かん‐ぎ【関木】クワン‥
かんぬき。関の木。
かん‐ぎ【歓喜】クワン‥
〔仏〕宗教的なよろこび。「―踊躍ゆやく」
⇒かんぎ‐おん【歓喜園】
⇒かんぎ‐じ【歓喜地】
⇒かんぎ‐だん【歓喜団】
⇒かんぎ‐てん【歓喜天】
かん‐ぎ【諫議】
天子を諫いさめて政治を議すること。
⇒かんぎ‐たいふ【諫議大夫】
がん‐き【顔輝】
南宋末・元初の画家。字は秋月。江西廬陵の人。道釈人物を得意とし、多くの作品が日本に渡来。代表作「蝦蟆鉄拐図」(京都知恩寺蔵)。
がん‐ぎ【雁木】
(雁の行列のように、ぎざぎざの形をしたもの)
①橋の上の桟。雁歯。
②船着場の階段のある桟橋。
③雪深い地方(主として新潟県)で、町屋の軒から庇ひさしを長く張り出し、その下を通路としたもの。雁木造。〈[季]冬〉
④木挽こびきの用いる大きな鋸のこぎり。おが。
⑤雁木鑢がんぎやすりの略。雁木鑢は押しても引いても物を削るところから、両方で損すること。浮世風呂4「先が銭を出さねえときてゐるから―だアス」
⑥人の気づかない所に出ていて邪魔になる棒。
⇒がんぎ‐えい【雁木鱝】
⇒がんぎ‐がしら【雁木頭】
⇒がんぎ‐ぐるま【雁木車】
⇒がんぎ‐ざとり【雁木悟り】
⇒がんぎ‐だな【雁木棚】
⇒がんぎ‐だま【雁木玉】
⇒がんぎ‐ばしご【雁木梯子】
⇒がんぎ‐やすり【雁木鑢】
がんぎ‐えい【雁木鱝】‥エヒ
ガンギエイ科の海産の軟骨魚。全長約1.5メートル。体は菱形で尾部は細長い。背面は褐色。腹部は白色。青森以南に産する。夏、美味。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かんぎえん【咸宜園】‥ヱン
広瀬淡窓が豊後国日田郡堀田村に開いた漢学塾。1817年(文化14)開設。各層に広く開放し、儒学・作詩を教えた。競争試験による進級制を採用。門人総数は数千を数え、江戸時代最大の私塾となる。97年(明治30)まで存続。
かんぎ‐おん【歓喜園】クワン‥ヲン
(カンギエンとも)
①忉利天とうりてんの帝釈たいしゃくの居城にある四園の一つ。天人たちが園内に入れば自然に歓喜の念が生ずるという。
②インド迦毘羅衛かびらえ城における釈尊降誕の園。ルンビニーの別名。
⇒かん‐ぎ【歓喜】
がんぎ‐がしら【雁木頭】
鋸歯状または剣先をならべたような形や文様。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かん‐ぎく【釻菊】クワン‥
(「釻」は「鐶」の当て字)紋所の名。菊花の形を座とし、これに鐶を添えたもの。
かん‐ぎく【寒菊】
アブラギクを改良した黄花の園芸品種。冬咲き。ほかに、晩生のキクで、冬まで開花を続けるものをもいう。残菊。冬菊。〈[季]冬〉。〈日葡辞書〉
かん‐ぎく【観菊】クワン‥
菊の花を観賞すること。菊見。
⇒かんぎく‐かい【観菊会】
かんぎく‐かい【観菊会】クワン‥クワイ
毎年11月中旬頃、赤坂離宮のち新宿御苑で行われた天皇主催の観菊の行事。1937年(昭和12)廃止されたが、53年皇室園遊会として復活。観菊御宴。
⇒かん‐ぎく【観菊】
がんぎ‐ぐるま【雁木車】
①積荷の揚げ卸しに用いる滑車の一種。材の横面をくりぬき、車をはめこみ細引を通して、高い所に吊って使用する。
雁木車
 ②ぎざぎざの歯が並んだ歯車。機械式時計などのように、間欠的かつ規則的に回転させる機構に用いられる。→アンクル(図)。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かんき‐こう【換気口】クワン‥
室内のよごれた空気と外気とを交換し、また温度調節などのため設ける孔。通気孔。天井または床下に設けたものは「風抜き」ともいう。
⇒かん‐き【換気】
がんぎ‐ざとり【雁木悟り】
だんだんに悟りを開くこと。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かんぎ‐じ【歓喜地】クワン‥ヂ
〔仏〕菩薩十地じゅうじの第1。菩薩が修行によって煩悩を断じ、心に歓喜を生ずる位。初歓喜地。初地。堪忍地。
⇒かん‐ぎ【歓喜】
かんき‐せん【換気扇】クワン‥
室内の空気の入れ換えを簡易に行うためとりつけるプロペラ形ファン。
⇒かん‐き【換気】
かんぎ‐たいふ【諫議大夫】
①中国の官名。天子を諫め、政治の得失を論じた官。
②参議の唐名。
⇒かん‐ぎ【諫議】
がんぎ‐だな【雁木棚】
床脇の棚の一形式。左右から入れちがいに架したもの。
雁木棚
②ぎざぎざの歯が並んだ歯車。機械式時計などのように、間欠的かつ規則的に回転させる機構に用いられる。→アンクル(図)。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かんき‐こう【換気口】クワン‥
室内のよごれた空気と外気とを交換し、また温度調節などのため設ける孔。通気孔。天井または床下に設けたものは「風抜き」ともいう。
⇒かん‐き【換気】
がんぎ‐ざとり【雁木悟り】
だんだんに悟りを開くこと。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かんぎ‐じ【歓喜地】クワン‥ヂ
〔仏〕菩薩十地じゅうじの第1。菩薩が修行によって煩悩を断じ、心に歓喜を生ずる位。初歓喜地。初地。堪忍地。
⇒かん‐ぎ【歓喜】
かんき‐せん【換気扇】クワン‥
室内の空気の入れ換えを簡易に行うためとりつけるプロペラ形ファン。
⇒かん‐き【換気】
かんぎ‐たいふ【諫議大夫】
①中国の官名。天子を諫め、政治の得失を論じた官。
②参議の唐名。
⇒かん‐ぎ【諫議】
がんぎ‐だな【雁木棚】
床脇の棚の一形式。左右から入れちがいに架したもの。
雁木棚
 ⇒がん‐ぎ【雁木】
がんぎ‐だま【雁木玉】
主として古墳時代にガラスで作られた丸玉で、2色以上のガラスを合わせて縞模様を表したもの。→蜻蛉とんぼ玉。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かん‐きだん【寒気団】
寒冷な気団。一般に冬季、高緯度の地表面付近で形成され、中緯度へ移動する。
かんぎ‐だん【歓喜団】クワン‥
歓喜天に供える菓子の名。穀類・薬種などをこね合わせて油で揚げたもの。これを寺からもらって帰り近所に配ると、食べた人々の福がみな自分に集まるという。歓喜丸。
⇒かん‐ぎ【歓喜】
かんき‐ちく【寒忌竹】
タデ科の低木状多年草。ソロモン諸島原産。高さ約1メートル。茎は扁平で帯状、竹に似た節があり、枝を分岐。葉はほとんどない。茎が緑色で同化作用を営む。夏、節々に緑白色の花を開く。果実は三稜形、紅紫色。観賞用に栽培。対節草。
かんきちく
⇒がん‐ぎ【雁木】
がんぎ‐だま【雁木玉】
主として古墳時代にガラスで作られた丸玉で、2色以上のガラスを合わせて縞模様を表したもの。→蜻蛉とんぼ玉。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かん‐きだん【寒気団】
寒冷な気団。一般に冬季、高緯度の地表面付近で形成され、中緯度へ移動する。
かんぎ‐だん【歓喜団】クワン‥
歓喜天に供える菓子の名。穀類・薬種などをこね合わせて油で揚げたもの。これを寺からもらって帰り近所に配ると、食べた人々の福がみな自分に集まるという。歓喜丸。
⇒かん‐ぎ【歓喜】
かんき‐ちく【寒忌竹】
タデ科の低木状多年草。ソロモン諸島原産。高さ約1メートル。茎は扁平で帯状、竹に似た節があり、枝を分岐。葉はほとんどない。茎が緑色で同化作用を営む。夏、節々に緑白色の花を開く。果実は三稜形、紅紫色。観賞用に栽培。対節草。
かんきちく
 かんきつ‐るい【柑橘類】
ミカン類の常緑樹、特に果樹・果実の総称。原産は東南アジアで、数十種の野生種が知られる。分類学上はミカン属・キンカン属・カラタチ属に分けられ、特にミカン属には重要な果樹が多い。→オレンジ
かんぎ‐てん【歓喜天】クワン‥
仏教の護法神の一つ。ヒンドゥー教のガネーシャ(Gaṇeśa)が仏教に入ったもの。障害をなす魔神を支配する神とされ、財宝・子宝・安産を祈るためにまつられた。形像は象頭人身で、単身像と妃を伴う男女双身像がある。妃は十一面観音が魔神としての働きを封じるために現した化身だという。歓喜自在天。大聖歓喜天、略して聖天しょうてんしょうでんともいう。
歓喜天
かんきつ‐るい【柑橘類】
ミカン類の常緑樹、特に果樹・果実の総称。原産は東南アジアで、数十種の野生種が知られる。分類学上はミカン属・キンカン属・カラタチ属に分けられ、特にミカン属には重要な果樹が多い。→オレンジ
かんぎ‐てん【歓喜天】クワン‥
仏教の護法神の一つ。ヒンドゥー教のガネーシャ(Gaṇeśa)が仏教に入ったもの。障害をなす魔神を支配する神とされ、財宝・子宝・安産を祈るためにまつられた。形像は象頭人身で、単身像と妃を伴う男女双身像がある。妃は十一面観音が魔神としての働きを封じるために現した化身だという。歓喜自在天。大聖歓喜天、略して聖天しょうてんしょうでんともいう。
歓喜天
 ⇒かん‐ぎ【歓喜】
かんき‐とう【換気塔】クワン‥タフ
室内の汚染空気を排除するために、屋上などに設けた塔。
⇒かん‐き【換気】
かんきのう‐けんさ【肝機能検査】
肝障害の有無および程度を調べるため、尿・血液について行う生化学的検査。胆汁排泄機能について血清ビリルビン値、尿ビリルビン・ウロビリノゲン、色素排泄能についてBSP・ICG試験、蛋白代謝について血清蛋白・アルブミン値など、糖質代謝についてブドウ糖・ガラクトース負荷試験、脂質代謝について血清コレステロール、肝細胞障害についてトランスアミナーゼ(AST(GOT)・ALT(GPT))・γ‐グルタミル‐トランスペプチダーゼ(γ‐GTP)など、肝炎ウイルスについてHB抗原・HA抗体など。その種類は200種に及ぶ。
かんぎ‐の‐ききん【寛喜の飢饉】クワン‥
寛喜2年(1230)から翌年にかけての大飢饉。特に北陸・四国の被害は大きく、秋から翌年にかけ餓死者が続出。京都は屍に埋まったという。幕府も伊豆・駿河の農民救済のため出挙すいこ米を貸し出した。
⇒かんぎ【寛喜】
がんぎ‐ばしご【雁木梯子】
1本の太い材に段を刻み出すか、またはその材に数本の横木をつけた梯子。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かん‐きゃく【閑却】
打ち捨てておくこと。なおざりにすること。「今や―を許さない事態」
かん‐きゃく【鉗脚】
「はさみ(鋏・剪刀)2」参照。
かん‐きゃく【還却】クワン‥
返すこと。
かん‐きゃく【観客】クワン‥
見物人。特に、映画・演劇・スポーツなどを見る人。看客。
がんぎ‐やすり【雁木鑢】
太くて目のあらい鑢。→雁木5
⇒がん‐ぎ【雁木】
かん‐きゅう【官給】クワンキフ
官府から金銭・物品を給与すること。「―品」
かん‐きゅう【竿球】‥キウ
旗竿の上端に付ける球状の飾り。
かん‐きゅう【貫休】クワンキウ
唐末五代の禅僧・詩人・画家。俗姓は姜。字は徳隠。婺ぶ州蘭渓(浙江)の儒家の生れ。仏門に入り、各地を巡り、晩年は成都に移る。夢幻的な詩と、水墨画風をとり込んだ特異な十六羅漢図で著名。禅月大師。(832〜912)
かん‐きゅう【感泣】‥キフ
深く感じて泣くこと。「師の恩情に―する」
かん‐きゅう【緩急】クワンキフ
①ゆるやかなことときびしいこと。遅いことと速いこと。「―よろしきを得る」
②(「緩」は語調を整える語)急なこと。危急の場合。まさかの場合。「一旦―あれば」
⇒かんきゅう‐きごう【緩急記号】
⇒かんきゅう‐じざい【緩急自在】
⇒かんきゅう‐しゃ【緩急車】
かん‐きゅう【緩球】クワンキウ
野球で、打者のタイミングをはずすゆるい投球。スローボール。
かん‐きゅう【還給】クワンキフ
物を所有者に返付すること。
がん‐きゅう【眼球】‥キウ
脊椎動物の視覚器。球形で、眼窩がんか内にあり、外には強膜・角膜、中間に脈絡膜みゃくらくまく・毛様体および虹彩こうさい、内に網膜の3層から成り、その内部に水晶体および硝子しょうし体などを含む。眼球の周囲に付着している眼筋によって運動する。光線は透明な角膜を通り、虹彩のかこむ瞳孔を経て内部に入る。水晶体はレンズの働きをし、網膜に像が映り、視神経を経て大脳に伝えられる。めだま。→水晶体→虹彩→瞳孔。
眼球
⇒かん‐ぎ【歓喜】
かんき‐とう【換気塔】クワン‥タフ
室内の汚染空気を排除するために、屋上などに設けた塔。
⇒かん‐き【換気】
かんきのう‐けんさ【肝機能検査】
肝障害の有無および程度を調べるため、尿・血液について行う生化学的検査。胆汁排泄機能について血清ビリルビン値、尿ビリルビン・ウロビリノゲン、色素排泄能についてBSP・ICG試験、蛋白代謝について血清蛋白・アルブミン値など、糖質代謝についてブドウ糖・ガラクトース負荷試験、脂質代謝について血清コレステロール、肝細胞障害についてトランスアミナーゼ(AST(GOT)・ALT(GPT))・γ‐グルタミル‐トランスペプチダーゼ(γ‐GTP)など、肝炎ウイルスについてHB抗原・HA抗体など。その種類は200種に及ぶ。
かんぎ‐の‐ききん【寛喜の飢饉】クワン‥
寛喜2年(1230)から翌年にかけての大飢饉。特に北陸・四国の被害は大きく、秋から翌年にかけ餓死者が続出。京都は屍に埋まったという。幕府も伊豆・駿河の農民救済のため出挙すいこ米を貸し出した。
⇒かんぎ【寛喜】
がんぎ‐ばしご【雁木梯子】
1本の太い材に段を刻み出すか、またはその材に数本の横木をつけた梯子。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かん‐きゃく【閑却】
打ち捨てておくこと。なおざりにすること。「今や―を許さない事態」
かん‐きゃく【鉗脚】
「はさみ(鋏・剪刀)2」参照。
かん‐きゃく【還却】クワン‥
返すこと。
かん‐きゃく【観客】クワン‥
見物人。特に、映画・演劇・スポーツなどを見る人。看客。
がんぎ‐やすり【雁木鑢】
太くて目のあらい鑢。→雁木5
⇒がん‐ぎ【雁木】
かん‐きゅう【官給】クワンキフ
官府から金銭・物品を給与すること。「―品」
かん‐きゅう【竿球】‥キウ
旗竿の上端に付ける球状の飾り。
かん‐きゅう【貫休】クワンキウ
唐末五代の禅僧・詩人・画家。俗姓は姜。字は徳隠。婺ぶ州蘭渓(浙江)の儒家の生れ。仏門に入り、各地を巡り、晩年は成都に移る。夢幻的な詩と、水墨画風をとり込んだ特異な十六羅漢図で著名。禅月大師。(832〜912)
かん‐きゅう【感泣】‥キフ
深く感じて泣くこと。「師の恩情に―する」
かん‐きゅう【緩急】クワンキフ
①ゆるやかなことときびしいこと。遅いことと速いこと。「―よろしきを得る」
②(「緩」は語調を整える語)急なこと。危急の場合。まさかの場合。「一旦―あれば」
⇒かんきゅう‐きごう【緩急記号】
⇒かんきゅう‐じざい【緩急自在】
⇒かんきゅう‐しゃ【緩急車】
かん‐きゅう【緩球】クワンキウ
野球で、打者のタイミングをはずすゆるい投球。スローボール。
かん‐きゅう【還給】クワンキフ
物を所有者に返付すること。
がん‐きゅう【眼球】‥キウ
脊椎動物の視覚器。球形で、眼窩がんか内にあり、外には強膜・角膜、中間に脈絡膜みゃくらくまく・毛様体および虹彩こうさい、内に網膜の3層から成り、その内部に水晶体および硝子しょうし体などを含む。眼球の周囲に付着している眼筋によって運動する。光線は透明な角膜を通り、虹彩のかこむ瞳孔を経て内部に入る。水晶体はレンズの働きをし、網膜に像が映り、視神経を経て大脳に伝えられる。めだま。→水晶体→虹彩→瞳孔。
眼球
 視神経
水晶体
角膜
虹彩
毛様体
網膜
硝子体
脈絡膜
強膜
⇒がんきゅう‐きん【眼球筋】
⇒がんきゅう‐しんとう【眼球振盪】
がん‐きゅう【龕柩】‥キウ
死骸を納める棺。ひつぎ。
かんきゅう‐きごう【緩急記号】クワンキフ‥ガウ
〔音〕速度標語のうち、速度の変更を指示する記号。リタルダンドなど。
⇒かん‐きゅう【緩急】
がんきゅう‐きん【眼球筋】‥キウ‥
(→)眼筋に同じ。
⇒がん‐きゅう【眼球】
かんきゅう‐じざい【緩急自在】クワンキフ‥
ゆるめたりひきしめたり、どのようにでも操れること。「―の投球」
⇒かん‐きゅう【緩急】
かんきゅう‐しゃ【緩急車】クワンキフ‥
客車および貨車のうち、運転中に常用するブレーキ装置と留置中の転動を防止するブレーキ装置を備えたもの。
⇒かん‐きゅう【緩急】
かんぎゅう‐じゅうとう【汗牛充棟】‥ギウ‥
[柳宗元、陸文通墓表](牛が汗をかくほどの重さと、棟につかえるほどの量、の意)蔵書の非常に多いこと。転じて、多くの書籍。
がんきゅう‐しんとう【眼球振盪】‥キウ‥タウ
(nystagmus ラテン)眼球の不随意性・律動的な往復運動。生理的にも見られるが、病的には眼・脳・神経疾患の際に現れ、水平・垂直・回転などの方向性また衝動性・振子様などの運動様式に分類される。眼球震盪。眼振。
⇒がん‐きゅう【眼球】
かん‐きゅうちゅう【肝吸虫】‥キフ‥
キュウチュウ目の吸虫。体は扁平、長い木葉状、体長6〜20ミリメートル。幅2〜5ミリメートル。口吸盤は前端に、腹吸盤は前部腹面にある。人・犬・猫・豚などの胆管に寄生。卵からかえった幼虫はマメタニシ、次いでコイ科の淡水魚に寄生したのち人体などに入りこむ。淡水魚の調理には注意が必要。日本・中国・東南アジアなどに分布。肝臓ジストマ。
かん‐きょ【函渠】
断面が長方形の暗渠。
かん‐きょ【官許】クワン‥
政府の許可。政府が特定の人に特定の事を許すこと。
かん‐きょ【乾薑】
カンキョウの訛。
かん‐きょ【閑居】
①閑静な住居。
②ひまでいること。世事を離れてのんびりと暮らすこと。「小人―して不善をなす」
③名物茶碗の一つ。楽焼で千宗室判の黒茶碗。
かん‐ぎょ【扞禦】
ふせぐこと。防御。
かん‐ぎょ【乾魚・干魚】
ほした魚。ひもの。ほしざかな。
かん‐ぎょ【還御】クワン‥
①天皇・三后などが行幸啓ぎょうこうけい先から帰ることの尊敬語。
②将軍・公卿が他行先から帰ることを、分を越えて用いた語。
かん‐ぎょ【鹹魚】
塩漬にした魚。塩魚。塩物。
かん‐きょう【奸凶・姦凶】
わるだくみをするわる者。
かん‐きょう【乾薑・乾姜】‥キヤウ
ショウガの根を蒸して乾したもの。漢方生薬の一つで、体を温める効がある。乾生薑かんしょうが。狂言、煎じ物「陳皮―葉甘草」
かん‐きょう【寒郷】‥キヤウ
①さびしい里。
②自分の居住地や故郷の謙称。
かん‐きょう【寒蛩】
秋の末のこおろぎ。
かん‐きょう【感興】
興味を感ずること。面白がること。また、その興味。「―をもよおす」「―をそがれる」
かん‐きょう【漢鏡】‥キヤウ
漢代の鏡。ほとんどが円盤形の青銅製品。草葉文鏡・連弧文鏡・四神鏡・神獣鏡・画像鏡などが代表的。→漢式鏡
かん‐きょう【緩頬】クワンケフ
①顔色をやわらげること。また、顔色をやわらげておだやかに話すこと。婉曲に話すこと。
②「緩頬を煩わす」の略。
⇒緩頬を煩わす
かん‐きょう【還郷】クワンキヤウ
ふるさとにかえること。帰郷。かんけい。
かん‐きょう【環境】クワンキヤウ
①めぐり囲む区域。
②四囲の外界。周囲の事物。特に、人間または生物をとりまき、それと相互作用を及ぼし合うものとして見た外界。自然的環境と社会的環境とがある。「恵まれた―に育つ」
⇒かんきょう‐アセスメント【環境アセスメント】
⇒かんきょう‐えいきょう‐ひょうか【環境影響評価】
⇒かんきょう‐えいせい【環境衛生】
⇒かんきょう‐かいけい【環境会計】
⇒かんきょう‐かがく【環境科学】
⇒かんきょう‐きじゅん【環境基準】
⇒かんきょう‐きほん‐ほう【環境基本法】
⇒かんきょう‐きょういく【環境教育】
⇒かんきょう‐きょうせい【環境共生】
⇒かんきょう‐けいざいがく【環境経済学】
⇒かんきょう‐けん【環境権】
⇒かんきょう‐こうこがく【環境考古学】
⇒かんきょう‐しょう【環境省】
⇒かんきょう‐ぜい【環境税】
⇒かんきょう‐せいぎ【環境正義】
⇒かんきょう‐だいじん【環境大臣】
⇒かんきょう‐ちょう【環境庁】
⇒かんきょう‐なんみん【環境難民】
⇒かんきょう‐ビデオ【環境ビデオ】
⇒かんきょう‐ふか【環境負荷】
⇒かんきょう‐へんい【環境変異】
⇒かんきょう‐ホルモン【環境ホルモン】
⇒かんきょう‐よういん【環境要因】
⇒かんきょう‐ようりょう【環境容量】
⇒かんきょう‐リスク【環境リスク】
⇒かんきょう‐りん【環境林】
⇒かんきょう‐りんりがく【環境倫理学】
かん‐きょう【艦橋】‥ケウ
(bridge)艦船の甲板上に高く設けられた望楼状の構築物で、航行中、操船・通信などを指揮する所。船橋。ブリッジ。
かん‐ぎょう【官業】クワンゲフ
政府が管理・経営する事業。日本では、国有林野やかつての国鉄など。広義には特殊法人や地方公共団体の経営する公営事業をも含む。官営事業。↔民業。
⇒かんぎょう‐はらいさげ【官業払下げ】
かん‐ぎょう【寒行】‥ギヤウ
寒中に寒さに耐えてする修行・苦行。水垢離みずごり・念仏・誦経ずきょうをなし、または薄着・裸体・裸足で社寺に詣で祈願する。〈[季]冬〉
かん‐ぎょう【勧業】クワンゲフ
農業・工業などの産業を勧めはげますこと。
⇒かんぎょう‐ぎんこう【勧業銀行】
かん‐ぎょう【諫暁】‥ゲウ
〔仏〕諫いさめ諭さとすこと。相手の誤りを指摘して迷妄を開き、正しい道に導くこと。
かん‐ぎょう【観行】クワンギヤウ
〔仏〕観念修行のこと。観心かんじんの行法。
かん‐ぎょう【観経】クワンギヤウ
①(→)看経かんきんに同じ。
②観無量寿経の略称。
がん‐きょう【眼鏡】‥キヤウ
めがね。
がん‐きょう【頑強】グワンキヤウ
頑固で屈せず強いこと。てごわいこと。「―に抵抗する」「―な反対運動」
がん‐ぎょう【丸桁】グワンギヤウ
⇒がぎょう
がんぎょう【元暁】グワンゲウ
(ゲンギョウとも)新羅の学僧。入唐を志したが途中で止め、妻帯して俗人のような生活を送りながら、華厳経・大乗起信論の注釈など多くの著作を著し、日本でも南都仏教において尊重された。和諍わじょう国師。(617〜686)
がんぎょう【元慶】グワンギヤウ
(ガンキョウ・ゲンケイとも)平安前期、陽成・光孝天皇朝の年号。貞観19年4月16日(877年6月1日)改元、元慶9年2月21日(885年3月11日)仁和に改元。
⇒がんぎょう‐じ【元慶寺】
がん‐ぎょう【願行】グワンギヤウ
〔仏〕果報を願い求めること(願)と、その果報を得るため修すること(行)。誓願と修行。
かんきょう‐アセスメント【環境アセスメント】クワンキヤウ‥
(environmental impact assessment)(→)環境影響評価に同じ。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐えいきょう‐ひょうか【環境影響評価】クワンキヤウ‥キヤウヒヤウ‥
開発が環境に及ぼす影響の内容と程度および環境保全対策について事前に予測と評価を行い、保全上必要な措置の検討をすること。環境アセスメント。EIA
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐えいせい【環境衛生】クワンキヤウヱイ‥
健康生活維持のため環境の保全・改善をはかること。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐かいけい【環境会計】クワンキヤウクワイ‥
(environmental accounting)企業等が、事業活動における環境保全のための投資・経費やその効果を定量的に把握し、それを企業内外の利害関係者に伝達する会計。日本では、環境省・経済産業省が、ガイドラインを公表。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐かがく【環境科学】クワンキヤウクワ‥
自然環境やその破壊を人間や生物とのかかわりにおいてとらえる総合科学。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きじゅん【環境基準】クワンキヤウ‥
大気・土壌の汚染、水質の汚濁、騒音などの環境条件について、健康を守り生活環境を保つうえで維持されるべき基準。環境基本法などに基づく。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きほん‐ほう【環境基本法】クワンキヤウ‥ハフ
環境保全に関する施策の基本を定めた法律。1993年、公害対策基本法に代わって制定。従来の公害対策だけでなく、地球環境保全問題への対処も含む。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きょういく【環境教育】クワンキヤウケウ‥
自然環境の有限性に注目し、環境破壊を防ぎ、環境問題を解決し、自然との調和に基づく、持続的な社会づくりを目的とする教育。2003年環境保全活動環境教育推進法が成立。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きょうせい【環境共生】クワンキヤウ‥
環境保全に配慮し、また周辺の自然環境との調和を重視すること。「―住宅」
⇒かん‐きょう【環境】
かんぎょう‐ぎんこう【勧業銀行】クワンゲフ‥カウ
日本勧業銀行の略称。
⇒かん‐ぎょう【勧業】
かんきょう‐けいざいがく【環境経済学】クワンキヤウ‥
環境問題を経済のメカニズムや法則によって研究し、環境政策を論ずる経済学の一分野。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐けん【環境権】クワンキヤウ‥
よい環境を享受し、これを支配する権利。法律上は、その内容がいまだ不明確で具体的権利として確立されてはいないが、環境保全のための基本的な法理として主張されている。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐こうこがく【環境考古学】クワンキヤウカウ‥
自然環境の変化と人間生活や社会の変化との相関関係を明らかにすることをめざす考古学の一分野。
⇒かん‐きょう【環境】
がんぎょう‐じ【元慶寺】グワンギヤウ‥
京都市山科区にあった真言宗の寺(今はガンケイジといい、天台宗)。868年(貞観10)陽成天皇誕生の時、遍昭の創建。9世紀には安然などが住し隆盛。986年(寛和2)花山天皇は藤原道兼に謀られ、ここに潜幸して出家。別称、花山寺かざんじ。
⇒がんぎょう【元慶】
かんきょう‐しょう【環境省】クワンキヤウシヤウ
地球環境の保全、公害の防止、自然環境の保護その他の環境の保全を任務とする中央行政機関。環境大臣を長とする。2001年環境庁から昇格。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ぜい【環境税】クワンキヤウ‥
二酸化炭素、硫黄・窒素酸化物、有害廃棄物などの環境汚染物質の排出を抑制する手段として課される租税の総称。炭素税の類。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐せいぎ【環境正義】クワンキヤウ‥
(environmental justice)環境破壊の被害に経済的・人種的差別が関係している現状を克服し、実現するべき社会的正義。アメリカにおいて、1980年代にアフリカ系アメリカ人居住地域に有害廃棄物処理施設が集中していることへの抗議として提唱され、92年に連邦環境保護庁に環境正義局が開設された。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐だいじん【環境大臣】クワンキヤウ‥
内閣各省大臣の一つ。環境省の長。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ちょう【環境庁】クワンキヤウチヤウ
環境省の前身。総理府の外局として1971年設置。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐なんどう【咸鏡南道】‥キヤウ‥ダウ
⇒ハムギョン‐ナムド
かんきょう‐なんみん【環境難民】クワンキヤウ‥
環境破壊によって居住地を離れることを余儀なくされた人々。難民条約(1951年採択)が規定する難民とは異なる。
⇒かん‐きょう【環境】
かんぎょう‐はらいさげ【官業払下げ】クワンゲフハラヒ‥
明治10〜20年代を中心に、明治政府が行なった官営工場・鉱山などの民間への払下げ政策。経営難を背景に低価格で行われたため、財閥形成の契機となった。
⇒かん‐ぎょう【官業】
かんきょう‐ビデオ【環境ビデオ】クワンキヤウ‥
室内の環境を演出するために流すビデオ。主に自然の風景などを映し出す。インテリア‐ビデオ。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ふか【環境負荷】クワンキヤウ‥
人間活動が自然環境に与える負担のこと。廃棄物・干拓・焼畑・人口増加の類。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐へんい【環境変異】クワンキヤウ‥
同一の生物集団の個体間において、生育環境の差や、発育途上の偶然の要因などの影響で生じる量的な変異で、遺伝しないもの。一般に変異の大きさは、ある値を中心に連続的に分布し、彷徨変異ともいう。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ほくどう【咸鏡北道】‥キヤウ‥ダウ
⇒ハムギョン‐プクト
かんきょう‐ホルモン【環境ホルモン】クワンキヤウ‥
(→)内分泌攪乱物質に同じ。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐よういん【環境要因】クワンキヤウエウ‥
生物個体または集団の環境を構成する諸要素のこと。生物間の相互作用も含めた、有機的な要因(生物的環境)と無機的な要因(光・温度・水分・土壌など)とがある。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ようりょう【環境容量】クワンキヤウ‥リヤウ
①特定の種が、ある環境のもとで維持しうる最大の個体数。環境収容力。
②環境が自然に浄化できる汚染の許容量。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐リスク【環境リスク】クワンキヤウ‥
人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれ。地震など自然環境から発生するものと、化学物質による汚染など人為的に発生するものとがある。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐りん【環境林】クワンキヤウ‥
水資源の涵養、土砂流出の防止、大気浄化などの環境保全機能の高い森林。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐りんりがく【環境倫理学】クワンキヤウ‥
環境問題を解決するため、自然と人間との関係を倫理的観点から考察しようとする学問。自然の生存権、世代間倫理、資源の有限性などを主張。
⇒かん‐きょう【環境】
視神経
水晶体
角膜
虹彩
毛様体
網膜
硝子体
脈絡膜
強膜
⇒がんきゅう‐きん【眼球筋】
⇒がんきゅう‐しんとう【眼球振盪】
がん‐きゅう【龕柩】‥キウ
死骸を納める棺。ひつぎ。
かんきゅう‐きごう【緩急記号】クワンキフ‥ガウ
〔音〕速度標語のうち、速度の変更を指示する記号。リタルダンドなど。
⇒かん‐きゅう【緩急】
がんきゅう‐きん【眼球筋】‥キウ‥
(→)眼筋に同じ。
⇒がん‐きゅう【眼球】
かんきゅう‐じざい【緩急自在】クワンキフ‥
ゆるめたりひきしめたり、どのようにでも操れること。「―の投球」
⇒かん‐きゅう【緩急】
かんきゅう‐しゃ【緩急車】クワンキフ‥
客車および貨車のうち、運転中に常用するブレーキ装置と留置中の転動を防止するブレーキ装置を備えたもの。
⇒かん‐きゅう【緩急】
かんぎゅう‐じゅうとう【汗牛充棟】‥ギウ‥
[柳宗元、陸文通墓表](牛が汗をかくほどの重さと、棟につかえるほどの量、の意)蔵書の非常に多いこと。転じて、多くの書籍。
がんきゅう‐しんとう【眼球振盪】‥キウ‥タウ
(nystagmus ラテン)眼球の不随意性・律動的な往復運動。生理的にも見られるが、病的には眼・脳・神経疾患の際に現れ、水平・垂直・回転などの方向性また衝動性・振子様などの運動様式に分類される。眼球震盪。眼振。
⇒がん‐きゅう【眼球】
かん‐きゅうちゅう【肝吸虫】‥キフ‥
キュウチュウ目の吸虫。体は扁平、長い木葉状、体長6〜20ミリメートル。幅2〜5ミリメートル。口吸盤は前端に、腹吸盤は前部腹面にある。人・犬・猫・豚などの胆管に寄生。卵からかえった幼虫はマメタニシ、次いでコイ科の淡水魚に寄生したのち人体などに入りこむ。淡水魚の調理には注意が必要。日本・中国・東南アジアなどに分布。肝臓ジストマ。
かん‐きょ【函渠】
断面が長方形の暗渠。
かん‐きょ【官許】クワン‥
政府の許可。政府が特定の人に特定の事を許すこと。
かん‐きょ【乾薑】
カンキョウの訛。
かん‐きょ【閑居】
①閑静な住居。
②ひまでいること。世事を離れてのんびりと暮らすこと。「小人―して不善をなす」
③名物茶碗の一つ。楽焼で千宗室判の黒茶碗。
かん‐ぎょ【扞禦】
ふせぐこと。防御。
かん‐ぎょ【乾魚・干魚】
ほした魚。ひもの。ほしざかな。
かん‐ぎょ【還御】クワン‥
①天皇・三后などが行幸啓ぎょうこうけい先から帰ることの尊敬語。
②将軍・公卿が他行先から帰ることを、分を越えて用いた語。
かん‐ぎょ【鹹魚】
塩漬にした魚。塩魚。塩物。
かん‐きょう【奸凶・姦凶】
わるだくみをするわる者。
かん‐きょう【乾薑・乾姜】‥キヤウ
ショウガの根を蒸して乾したもの。漢方生薬の一つで、体を温める効がある。乾生薑かんしょうが。狂言、煎じ物「陳皮―葉甘草」
かん‐きょう【寒郷】‥キヤウ
①さびしい里。
②自分の居住地や故郷の謙称。
かん‐きょう【寒蛩】
秋の末のこおろぎ。
かん‐きょう【感興】
興味を感ずること。面白がること。また、その興味。「―をもよおす」「―をそがれる」
かん‐きょう【漢鏡】‥キヤウ
漢代の鏡。ほとんどが円盤形の青銅製品。草葉文鏡・連弧文鏡・四神鏡・神獣鏡・画像鏡などが代表的。→漢式鏡
かん‐きょう【緩頬】クワンケフ
①顔色をやわらげること。また、顔色をやわらげておだやかに話すこと。婉曲に話すこと。
②「緩頬を煩わす」の略。
⇒緩頬を煩わす
かん‐きょう【還郷】クワンキヤウ
ふるさとにかえること。帰郷。かんけい。
かん‐きょう【環境】クワンキヤウ
①めぐり囲む区域。
②四囲の外界。周囲の事物。特に、人間または生物をとりまき、それと相互作用を及ぼし合うものとして見た外界。自然的環境と社会的環境とがある。「恵まれた―に育つ」
⇒かんきょう‐アセスメント【環境アセスメント】
⇒かんきょう‐えいきょう‐ひょうか【環境影響評価】
⇒かんきょう‐えいせい【環境衛生】
⇒かんきょう‐かいけい【環境会計】
⇒かんきょう‐かがく【環境科学】
⇒かんきょう‐きじゅん【環境基準】
⇒かんきょう‐きほん‐ほう【環境基本法】
⇒かんきょう‐きょういく【環境教育】
⇒かんきょう‐きょうせい【環境共生】
⇒かんきょう‐けいざいがく【環境経済学】
⇒かんきょう‐けん【環境権】
⇒かんきょう‐こうこがく【環境考古学】
⇒かんきょう‐しょう【環境省】
⇒かんきょう‐ぜい【環境税】
⇒かんきょう‐せいぎ【環境正義】
⇒かんきょう‐だいじん【環境大臣】
⇒かんきょう‐ちょう【環境庁】
⇒かんきょう‐なんみん【環境難民】
⇒かんきょう‐ビデオ【環境ビデオ】
⇒かんきょう‐ふか【環境負荷】
⇒かんきょう‐へんい【環境変異】
⇒かんきょう‐ホルモン【環境ホルモン】
⇒かんきょう‐よういん【環境要因】
⇒かんきょう‐ようりょう【環境容量】
⇒かんきょう‐リスク【環境リスク】
⇒かんきょう‐りん【環境林】
⇒かんきょう‐りんりがく【環境倫理学】
かん‐きょう【艦橋】‥ケウ
(bridge)艦船の甲板上に高く設けられた望楼状の構築物で、航行中、操船・通信などを指揮する所。船橋。ブリッジ。
かん‐ぎょう【官業】クワンゲフ
政府が管理・経営する事業。日本では、国有林野やかつての国鉄など。広義には特殊法人や地方公共団体の経営する公営事業をも含む。官営事業。↔民業。
⇒かんぎょう‐はらいさげ【官業払下げ】
かん‐ぎょう【寒行】‥ギヤウ
寒中に寒さに耐えてする修行・苦行。水垢離みずごり・念仏・誦経ずきょうをなし、または薄着・裸体・裸足で社寺に詣で祈願する。〈[季]冬〉
かん‐ぎょう【勧業】クワンゲフ
農業・工業などの産業を勧めはげますこと。
⇒かんぎょう‐ぎんこう【勧業銀行】
かん‐ぎょう【諫暁】‥ゲウ
〔仏〕諫いさめ諭さとすこと。相手の誤りを指摘して迷妄を開き、正しい道に導くこと。
かん‐ぎょう【観行】クワンギヤウ
〔仏〕観念修行のこと。観心かんじんの行法。
かん‐ぎょう【観経】クワンギヤウ
①(→)看経かんきんに同じ。
②観無量寿経の略称。
がん‐きょう【眼鏡】‥キヤウ
めがね。
がん‐きょう【頑強】グワンキヤウ
頑固で屈せず強いこと。てごわいこと。「―に抵抗する」「―な反対運動」
がん‐ぎょう【丸桁】グワンギヤウ
⇒がぎょう
がんぎょう【元暁】グワンゲウ
(ゲンギョウとも)新羅の学僧。入唐を志したが途中で止め、妻帯して俗人のような生活を送りながら、華厳経・大乗起信論の注釈など多くの著作を著し、日本でも南都仏教において尊重された。和諍わじょう国師。(617〜686)
がんぎょう【元慶】グワンギヤウ
(ガンキョウ・ゲンケイとも)平安前期、陽成・光孝天皇朝の年号。貞観19年4月16日(877年6月1日)改元、元慶9年2月21日(885年3月11日)仁和に改元。
⇒がんぎょう‐じ【元慶寺】
がん‐ぎょう【願行】グワンギヤウ
〔仏〕果報を願い求めること(願)と、その果報を得るため修すること(行)。誓願と修行。
かんきょう‐アセスメント【環境アセスメント】クワンキヤウ‥
(environmental impact assessment)(→)環境影響評価に同じ。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐えいきょう‐ひょうか【環境影響評価】クワンキヤウ‥キヤウヒヤウ‥
開発が環境に及ぼす影響の内容と程度および環境保全対策について事前に予測と評価を行い、保全上必要な措置の検討をすること。環境アセスメント。EIA
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐えいせい【環境衛生】クワンキヤウヱイ‥
健康生活維持のため環境の保全・改善をはかること。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐かいけい【環境会計】クワンキヤウクワイ‥
(environmental accounting)企業等が、事業活動における環境保全のための投資・経費やその効果を定量的に把握し、それを企業内外の利害関係者に伝達する会計。日本では、環境省・経済産業省が、ガイドラインを公表。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐かがく【環境科学】クワンキヤウクワ‥
自然環境やその破壊を人間や生物とのかかわりにおいてとらえる総合科学。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きじゅん【環境基準】クワンキヤウ‥
大気・土壌の汚染、水質の汚濁、騒音などの環境条件について、健康を守り生活環境を保つうえで維持されるべき基準。環境基本法などに基づく。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きほん‐ほう【環境基本法】クワンキヤウ‥ハフ
環境保全に関する施策の基本を定めた法律。1993年、公害対策基本法に代わって制定。従来の公害対策だけでなく、地球環境保全問題への対処も含む。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きょういく【環境教育】クワンキヤウケウ‥
自然環境の有限性に注目し、環境破壊を防ぎ、環境問題を解決し、自然との調和に基づく、持続的な社会づくりを目的とする教育。2003年環境保全活動環境教育推進法が成立。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きょうせい【環境共生】クワンキヤウ‥
環境保全に配慮し、また周辺の自然環境との調和を重視すること。「―住宅」
⇒かん‐きょう【環境】
かんぎょう‐ぎんこう【勧業銀行】クワンゲフ‥カウ
日本勧業銀行の略称。
⇒かん‐ぎょう【勧業】
かんきょう‐けいざいがく【環境経済学】クワンキヤウ‥
環境問題を経済のメカニズムや法則によって研究し、環境政策を論ずる経済学の一分野。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐けん【環境権】クワンキヤウ‥
よい環境を享受し、これを支配する権利。法律上は、その内容がいまだ不明確で具体的権利として確立されてはいないが、環境保全のための基本的な法理として主張されている。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐こうこがく【環境考古学】クワンキヤウカウ‥
自然環境の変化と人間生活や社会の変化との相関関係を明らかにすることをめざす考古学の一分野。
⇒かん‐きょう【環境】
がんぎょう‐じ【元慶寺】グワンギヤウ‥
京都市山科区にあった真言宗の寺(今はガンケイジといい、天台宗)。868年(貞観10)陽成天皇誕生の時、遍昭の創建。9世紀には安然などが住し隆盛。986年(寛和2)花山天皇は藤原道兼に謀られ、ここに潜幸して出家。別称、花山寺かざんじ。
⇒がんぎょう【元慶】
かんきょう‐しょう【環境省】クワンキヤウシヤウ
地球環境の保全、公害の防止、自然環境の保護その他の環境の保全を任務とする中央行政機関。環境大臣を長とする。2001年環境庁から昇格。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ぜい【環境税】クワンキヤウ‥
二酸化炭素、硫黄・窒素酸化物、有害廃棄物などの環境汚染物質の排出を抑制する手段として課される租税の総称。炭素税の類。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐せいぎ【環境正義】クワンキヤウ‥
(environmental justice)環境破壊の被害に経済的・人種的差別が関係している現状を克服し、実現するべき社会的正義。アメリカにおいて、1980年代にアフリカ系アメリカ人居住地域に有害廃棄物処理施設が集中していることへの抗議として提唱され、92年に連邦環境保護庁に環境正義局が開設された。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐だいじん【環境大臣】クワンキヤウ‥
内閣各省大臣の一つ。環境省の長。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ちょう【環境庁】クワンキヤウチヤウ
環境省の前身。総理府の外局として1971年設置。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐なんどう【咸鏡南道】‥キヤウ‥ダウ
⇒ハムギョン‐ナムド
かんきょう‐なんみん【環境難民】クワンキヤウ‥
環境破壊によって居住地を離れることを余儀なくされた人々。難民条約(1951年採択)が規定する難民とは異なる。
⇒かん‐きょう【環境】
かんぎょう‐はらいさげ【官業払下げ】クワンゲフハラヒ‥
明治10〜20年代を中心に、明治政府が行なった官営工場・鉱山などの民間への払下げ政策。経営難を背景に低価格で行われたため、財閥形成の契機となった。
⇒かん‐ぎょう【官業】
かんきょう‐ビデオ【環境ビデオ】クワンキヤウ‥
室内の環境を演出するために流すビデオ。主に自然の風景などを映し出す。インテリア‐ビデオ。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ふか【環境負荷】クワンキヤウ‥
人間活動が自然環境に与える負担のこと。廃棄物・干拓・焼畑・人口増加の類。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐へんい【環境変異】クワンキヤウ‥
同一の生物集団の個体間において、生育環境の差や、発育途上の偶然の要因などの影響で生じる量的な変異で、遺伝しないもの。一般に変異の大きさは、ある値を中心に連続的に分布し、彷徨変異ともいう。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ほくどう【咸鏡北道】‥キヤウ‥ダウ
⇒ハムギョン‐プクト
かんきょう‐ホルモン【環境ホルモン】クワンキヤウ‥
(→)内分泌攪乱物質に同じ。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐よういん【環境要因】クワンキヤウエウ‥
生物個体または集団の環境を構成する諸要素のこと。生物間の相互作用も含めた、有機的な要因(生物的環境)と無機的な要因(光・温度・水分・土壌など)とがある。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ようりょう【環境容量】クワンキヤウ‥リヤウ
①特定の種が、ある環境のもとで維持しうる最大の個体数。環境収容力。
②環境が自然に浄化できる汚染の許容量。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐リスク【環境リスク】クワンキヤウ‥
人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれ。地震など自然環境から発生するものと、化学物質による汚染など人為的に発生するものとがある。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐りん【環境林】クワンキヤウ‥
水資源の涵養、土砂流出の防止、大気浄化などの環境保全機能の高い森林。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐りんりがく【環境倫理学】クワンキヤウ‥
環境問題を解決するため、自然と人間との関係を倫理的観点から考察しようとする学問。自然の生存権、世代間倫理、資源の有限性などを主張。
⇒かん‐きょう【環境】
 冽】
かん‐き【感喜】
感じて喜ぶこと。
かん‐き【管窺】クワン‥
[晋書王献之伝「管中に豹を窺うかがうに、時に一斑を見るのみ」](管の穴から豹を見ると、その皮の一つのまだらしか見えないことから)見識の狭いこと。管見。
かん‐き【歓喜】クワン‥
①大そうよろこぶこと。よろこび。「―のあまり涙を流す」
②⇒かんぎ
かん‐き【韓琦】
北宋の宰相。字は稚圭。河南安陽の人。仁宗・英宗・神宗に歴仕し、英宗の時に魏国公に封。范仲淹はんちゅうえんと共に韓范と並称される。神宗の時に上疏して王安石の新法の非を説いたが入れられず、病死。著「安陽集」「韓魏公集」。(1008〜1075)
かん‐ぎ【官妓】クワン‥
官に属する芸妓。特に高麗王朝以後の朝鮮で、医薬・裁縫・歌舞・妓楽をもって宮廷・地方官庁に仕えた女性をいう。妓生キーセン。
かん‐ぎ【冠儀】クワン‥
元服の儀式。
かんぎ【寛喜】クワン‥
[後魏書]鎌倉中期、後堀河天皇朝の年号。安貞3年3月5日(1229年3月31日)改元、寛喜4年4月2日(1232年4月23日)貞永に改元。
⇒かんぎ‐の‐ききん【寛喜の飢饉】
かん‐ぎ【関木】クワン‥
かんぬき。関の木。
かん‐ぎ【歓喜】クワン‥
〔仏〕宗教的なよろこび。「―踊躍ゆやく」
⇒かんぎ‐おん【歓喜園】
⇒かんぎ‐じ【歓喜地】
⇒かんぎ‐だん【歓喜団】
⇒かんぎ‐てん【歓喜天】
かん‐ぎ【諫議】
天子を諫いさめて政治を議すること。
⇒かんぎ‐たいふ【諫議大夫】
がん‐き【顔輝】
南宋末・元初の画家。字は秋月。江西廬陵の人。道釈人物を得意とし、多くの作品が日本に渡来。代表作「蝦蟆鉄拐図」(京都知恩寺蔵)。
がん‐ぎ【雁木】
(雁の行列のように、ぎざぎざの形をしたもの)
①橋の上の桟。雁歯。
②船着場の階段のある桟橋。
③雪深い地方(主として新潟県)で、町屋の軒から庇ひさしを長く張り出し、その下を通路としたもの。雁木造。〈[季]冬〉
④木挽こびきの用いる大きな鋸のこぎり。おが。
⑤雁木鑢がんぎやすりの略。雁木鑢は押しても引いても物を削るところから、両方で損すること。浮世風呂4「先が銭を出さねえときてゐるから―だアス」
⑥人の気づかない所に出ていて邪魔になる棒。
⇒がんぎ‐えい【雁木鱝】
⇒がんぎ‐がしら【雁木頭】
⇒がんぎ‐ぐるま【雁木車】
⇒がんぎ‐ざとり【雁木悟り】
⇒がんぎ‐だな【雁木棚】
⇒がんぎ‐だま【雁木玉】
⇒がんぎ‐ばしご【雁木梯子】
⇒がんぎ‐やすり【雁木鑢】
がんぎ‐えい【雁木鱝】‥エヒ
ガンギエイ科の海産の軟骨魚。全長約1.5メートル。体は菱形で尾部は細長い。背面は褐色。腹部は白色。青森以南に産する。夏、美味。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かんぎえん【咸宜園】‥ヱン
広瀬淡窓が豊後国日田郡堀田村に開いた漢学塾。1817年(文化14)開設。各層に広く開放し、儒学・作詩を教えた。競争試験による進級制を採用。門人総数は数千を数え、江戸時代最大の私塾となる。97年(明治30)まで存続。
かんぎ‐おん【歓喜園】クワン‥ヲン
(カンギエンとも)
①忉利天とうりてんの帝釈たいしゃくの居城にある四園の一つ。天人たちが園内に入れば自然に歓喜の念が生ずるという。
②インド迦毘羅衛かびらえ城における釈尊降誕の園。ルンビニーの別名。
⇒かん‐ぎ【歓喜】
がんぎ‐がしら【雁木頭】
鋸歯状または剣先をならべたような形や文様。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かん‐ぎく【釻菊】クワン‥
(「釻」は「鐶」の当て字)紋所の名。菊花の形を座とし、これに鐶を添えたもの。
かん‐ぎく【寒菊】
アブラギクを改良した黄花の園芸品種。冬咲き。ほかに、晩生のキクで、冬まで開花を続けるものをもいう。残菊。冬菊。〈[季]冬〉。〈日葡辞書〉
かん‐ぎく【観菊】クワン‥
菊の花を観賞すること。菊見。
⇒かんぎく‐かい【観菊会】
かんぎく‐かい【観菊会】クワン‥クワイ
毎年11月中旬頃、赤坂離宮のち新宿御苑で行われた天皇主催の観菊の行事。1937年(昭和12)廃止されたが、53年皇室園遊会として復活。観菊御宴。
⇒かん‐ぎく【観菊】
がんぎ‐ぐるま【雁木車】
①積荷の揚げ卸しに用いる滑車の一種。材の横面をくりぬき、車をはめこみ細引を通して、高い所に吊って使用する。
雁木車
冽】
かん‐き【感喜】
感じて喜ぶこと。
かん‐き【管窺】クワン‥
[晋書王献之伝「管中に豹を窺うかがうに、時に一斑を見るのみ」](管の穴から豹を見ると、その皮の一つのまだらしか見えないことから)見識の狭いこと。管見。
かん‐き【歓喜】クワン‥
①大そうよろこぶこと。よろこび。「―のあまり涙を流す」
②⇒かんぎ
かん‐き【韓琦】
北宋の宰相。字は稚圭。河南安陽の人。仁宗・英宗・神宗に歴仕し、英宗の時に魏国公に封。范仲淹はんちゅうえんと共に韓范と並称される。神宗の時に上疏して王安石の新法の非を説いたが入れられず、病死。著「安陽集」「韓魏公集」。(1008〜1075)
かん‐ぎ【官妓】クワン‥
官に属する芸妓。特に高麗王朝以後の朝鮮で、医薬・裁縫・歌舞・妓楽をもって宮廷・地方官庁に仕えた女性をいう。妓生キーセン。
かん‐ぎ【冠儀】クワン‥
元服の儀式。
かんぎ【寛喜】クワン‥
[後魏書]鎌倉中期、後堀河天皇朝の年号。安貞3年3月5日(1229年3月31日)改元、寛喜4年4月2日(1232年4月23日)貞永に改元。
⇒かんぎ‐の‐ききん【寛喜の飢饉】
かん‐ぎ【関木】クワン‥
かんぬき。関の木。
かん‐ぎ【歓喜】クワン‥
〔仏〕宗教的なよろこび。「―踊躍ゆやく」
⇒かんぎ‐おん【歓喜園】
⇒かんぎ‐じ【歓喜地】
⇒かんぎ‐だん【歓喜団】
⇒かんぎ‐てん【歓喜天】
かん‐ぎ【諫議】
天子を諫いさめて政治を議すること。
⇒かんぎ‐たいふ【諫議大夫】
がん‐き【顔輝】
南宋末・元初の画家。字は秋月。江西廬陵の人。道釈人物を得意とし、多くの作品が日本に渡来。代表作「蝦蟆鉄拐図」(京都知恩寺蔵)。
がん‐ぎ【雁木】
(雁の行列のように、ぎざぎざの形をしたもの)
①橋の上の桟。雁歯。
②船着場の階段のある桟橋。
③雪深い地方(主として新潟県)で、町屋の軒から庇ひさしを長く張り出し、その下を通路としたもの。雁木造。〈[季]冬〉
④木挽こびきの用いる大きな鋸のこぎり。おが。
⑤雁木鑢がんぎやすりの略。雁木鑢は押しても引いても物を削るところから、両方で損すること。浮世風呂4「先が銭を出さねえときてゐるから―だアス」
⑥人の気づかない所に出ていて邪魔になる棒。
⇒がんぎ‐えい【雁木鱝】
⇒がんぎ‐がしら【雁木頭】
⇒がんぎ‐ぐるま【雁木車】
⇒がんぎ‐ざとり【雁木悟り】
⇒がんぎ‐だな【雁木棚】
⇒がんぎ‐だま【雁木玉】
⇒がんぎ‐ばしご【雁木梯子】
⇒がんぎ‐やすり【雁木鑢】
がんぎ‐えい【雁木鱝】‥エヒ
ガンギエイ科の海産の軟骨魚。全長約1.5メートル。体は菱形で尾部は細長い。背面は褐色。腹部は白色。青森以南に産する。夏、美味。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かんぎえん【咸宜園】‥ヱン
広瀬淡窓が豊後国日田郡堀田村に開いた漢学塾。1817年(文化14)開設。各層に広く開放し、儒学・作詩を教えた。競争試験による進級制を採用。門人総数は数千を数え、江戸時代最大の私塾となる。97年(明治30)まで存続。
かんぎ‐おん【歓喜園】クワン‥ヲン
(カンギエンとも)
①忉利天とうりてんの帝釈たいしゃくの居城にある四園の一つ。天人たちが園内に入れば自然に歓喜の念が生ずるという。
②インド迦毘羅衛かびらえ城における釈尊降誕の園。ルンビニーの別名。
⇒かん‐ぎ【歓喜】
がんぎ‐がしら【雁木頭】
鋸歯状または剣先をならべたような形や文様。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かん‐ぎく【釻菊】クワン‥
(「釻」は「鐶」の当て字)紋所の名。菊花の形を座とし、これに鐶を添えたもの。
かん‐ぎく【寒菊】
アブラギクを改良した黄花の園芸品種。冬咲き。ほかに、晩生のキクで、冬まで開花を続けるものをもいう。残菊。冬菊。〈[季]冬〉。〈日葡辞書〉
かん‐ぎく【観菊】クワン‥
菊の花を観賞すること。菊見。
⇒かんぎく‐かい【観菊会】
かんぎく‐かい【観菊会】クワン‥クワイ
毎年11月中旬頃、赤坂離宮のち新宿御苑で行われた天皇主催の観菊の行事。1937年(昭和12)廃止されたが、53年皇室園遊会として復活。観菊御宴。
⇒かん‐ぎく【観菊】
がんぎ‐ぐるま【雁木車】
①積荷の揚げ卸しに用いる滑車の一種。材の横面をくりぬき、車をはめこみ細引を通して、高い所に吊って使用する。
雁木車
 ②ぎざぎざの歯が並んだ歯車。機械式時計などのように、間欠的かつ規則的に回転させる機構に用いられる。→アンクル(図)。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かんき‐こう【換気口】クワン‥
室内のよごれた空気と外気とを交換し、また温度調節などのため設ける孔。通気孔。天井または床下に設けたものは「風抜き」ともいう。
⇒かん‐き【換気】
がんぎ‐ざとり【雁木悟り】
だんだんに悟りを開くこと。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かんぎ‐じ【歓喜地】クワン‥ヂ
〔仏〕菩薩十地じゅうじの第1。菩薩が修行によって煩悩を断じ、心に歓喜を生ずる位。初歓喜地。初地。堪忍地。
⇒かん‐ぎ【歓喜】
かんき‐せん【換気扇】クワン‥
室内の空気の入れ換えを簡易に行うためとりつけるプロペラ形ファン。
⇒かん‐き【換気】
かんぎ‐たいふ【諫議大夫】
①中国の官名。天子を諫め、政治の得失を論じた官。
②参議の唐名。
⇒かん‐ぎ【諫議】
がんぎ‐だな【雁木棚】
床脇の棚の一形式。左右から入れちがいに架したもの。
雁木棚
②ぎざぎざの歯が並んだ歯車。機械式時計などのように、間欠的かつ規則的に回転させる機構に用いられる。→アンクル(図)。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かんき‐こう【換気口】クワン‥
室内のよごれた空気と外気とを交換し、また温度調節などのため設ける孔。通気孔。天井または床下に設けたものは「風抜き」ともいう。
⇒かん‐き【換気】
がんぎ‐ざとり【雁木悟り】
だんだんに悟りを開くこと。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かんぎ‐じ【歓喜地】クワン‥ヂ
〔仏〕菩薩十地じゅうじの第1。菩薩が修行によって煩悩を断じ、心に歓喜を生ずる位。初歓喜地。初地。堪忍地。
⇒かん‐ぎ【歓喜】
かんき‐せん【換気扇】クワン‥
室内の空気の入れ換えを簡易に行うためとりつけるプロペラ形ファン。
⇒かん‐き【換気】
かんぎ‐たいふ【諫議大夫】
①中国の官名。天子を諫め、政治の得失を論じた官。
②参議の唐名。
⇒かん‐ぎ【諫議】
がんぎ‐だな【雁木棚】
床脇の棚の一形式。左右から入れちがいに架したもの。
雁木棚
 ⇒がん‐ぎ【雁木】
がんぎ‐だま【雁木玉】
主として古墳時代にガラスで作られた丸玉で、2色以上のガラスを合わせて縞模様を表したもの。→蜻蛉とんぼ玉。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かん‐きだん【寒気団】
寒冷な気団。一般に冬季、高緯度の地表面付近で形成され、中緯度へ移動する。
かんぎ‐だん【歓喜団】クワン‥
歓喜天に供える菓子の名。穀類・薬種などをこね合わせて油で揚げたもの。これを寺からもらって帰り近所に配ると、食べた人々の福がみな自分に集まるという。歓喜丸。
⇒かん‐ぎ【歓喜】
かんき‐ちく【寒忌竹】
タデ科の低木状多年草。ソロモン諸島原産。高さ約1メートル。茎は扁平で帯状、竹に似た節があり、枝を分岐。葉はほとんどない。茎が緑色で同化作用を営む。夏、節々に緑白色の花を開く。果実は三稜形、紅紫色。観賞用に栽培。対節草。
かんきちく
⇒がん‐ぎ【雁木】
がんぎ‐だま【雁木玉】
主として古墳時代にガラスで作られた丸玉で、2色以上のガラスを合わせて縞模様を表したもの。→蜻蛉とんぼ玉。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かん‐きだん【寒気団】
寒冷な気団。一般に冬季、高緯度の地表面付近で形成され、中緯度へ移動する。
かんぎ‐だん【歓喜団】クワン‥
歓喜天に供える菓子の名。穀類・薬種などをこね合わせて油で揚げたもの。これを寺からもらって帰り近所に配ると、食べた人々の福がみな自分に集まるという。歓喜丸。
⇒かん‐ぎ【歓喜】
かんき‐ちく【寒忌竹】
タデ科の低木状多年草。ソロモン諸島原産。高さ約1メートル。茎は扁平で帯状、竹に似た節があり、枝を分岐。葉はほとんどない。茎が緑色で同化作用を営む。夏、節々に緑白色の花を開く。果実は三稜形、紅紫色。観賞用に栽培。対節草。
かんきちく
 かんきつ‐るい【柑橘類】
ミカン類の常緑樹、特に果樹・果実の総称。原産は東南アジアで、数十種の野生種が知られる。分類学上はミカン属・キンカン属・カラタチ属に分けられ、特にミカン属には重要な果樹が多い。→オレンジ
かんぎ‐てん【歓喜天】クワン‥
仏教の護法神の一つ。ヒンドゥー教のガネーシャ(Gaṇeśa)が仏教に入ったもの。障害をなす魔神を支配する神とされ、財宝・子宝・安産を祈るためにまつられた。形像は象頭人身で、単身像と妃を伴う男女双身像がある。妃は十一面観音が魔神としての働きを封じるために現した化身だという。歓喜自在天。大聖歓喜天、略して聖天しょうてんしょうでんともいう。
歓喜天
かんきつ‐るい【柑橘類】
ミカン類の常緑樹、特に果樹・果実の総称。原産は東南アジアで、数十種の野生種が知られる。分類学上はミカン属・キンカン属・カラタチ属に分けられ、特にミカン属には重要な果樹が多い。→オレンジ
かんぎ‐てん【歓喜天】クワン‥
仏教の護法神の一つ。ヒンドゥー教のガネーシャ(Gaṇeśa)が仏教に入ったもの。障害をなす魔神を支配する神とされ、財宝・子宝・安産を祈るためにまつられた。形像は象頭人身で、単身像と妃を伴う男女双身像がある。妃は十一面観音が魔神としての働きを封じるために現した化身だという。歓喜自在天。大聖歓喜天、略して聖天しょうてんしょうでんともいう。
歓喜天
 ⇒かん‐ぎ【歓喜】
かんき‐とう【換気塔】クワン‥タフ
室内の汚染空気を排除するために、屋上などに設けた塔。
⇒かん‐き【換気】
かんきのう‐けんさ【肝機能検査】
肝障害の有無および程度を調べるため、尿・血液について行う生化学的検査。胆汁排泄機能について血清ビリルビン値、尿ビリルビン・ウロビリノゲン、色素排泄能についてBSP・ICG試験、蛋白代謝について血清蛋白・アルブミン値など、糖質代謝についてブドウ糖・ガラクトース負荷試験、脂質代謝について血清コレステロール、肝細胞障害についてトランスアミナーゼ(AST(GOT)・ALT(GPT))・γ‐グルタミル‐トランスペプチダーゼ(γ‐GTP)など、肝炎ウイルスについてHB抗原・HA抗体など。その種類は200種に及ぶ。
かんぎ‐の‐ききん【寛喜の飢饉】クワン‥
寛喜2年(1230)から翌年にかけての大飢饉。特に北陸・四国の被害は大きく、秋から翌年にかけ餓死者が続出。京都は屍に埋まったという。幕府も伊豆・駿河の農民救済のため出挙すいこ米を貸し出した。
⇒かんぎ【寛喜】
がんぎ‐ばしご【雁木梯子】
1本の太い材に段を刻み出すか、またはその材に数本の横木をつけた梯子。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かん‐きゃく【閑却】
打ち捨てておくこと。なおざりにすること。「今や―を許さない事態」
かん‐きゃく【鉗脚】
「はさみ(鋏・剪刀)2」参照。
かん‐きゃく【還却】クワン‥
返すこと。
かん‐きゃく【観客】クワン‥
見物人。特に、映画・演劇・スポーツなどを見る人。看客。
がんぎ‐やすり【雁木鑢】
太くて目のあらい鑢。→雁木5
⇒がん‐ぎ【雁木】
かん‐きゅう【官給】クワンキフ
官府から金銭・物品を給与すること。「―品」
かん‐きゅう【竿球】‥キウ
旗竿の上端に付ける球状の飾り。
かん‐きゅう【貫休】クワンキウ
唐末五代の禅僧・詩人・画家。俗姓は姜。字は徳隠。婺ぶ州蘭渓(浙江)の儒家の生れ。仏門に入り、各地を巡り、晩年は成都に移る。夢幻的な詩と、水墨画風をとり込んだ特異な十六羅漢図で著名。禅月大師。(832〜912)
かん‐きゅう【感泣】‥キフ
深く感じて泣くこと。「師の恩情に―する」
かん‐きゅう【緩急】クワンキフ
①ゆるやかなことときびしいこと。遅いことと速いこと。「―よろしきを得る」
②(「緩」は語調を整える語)急なこと。危急の場合。まさかの場合。「一旦―あれば」
⇒かんきゅう‐きごう【緩急記号】
⇒かんきゅう‐じざい【緩急自在】
⇒かんきゅう‐しゃ【緩急車】
かん‐きゅう【緩球】クワンキウ
野球で、打者のタイミングをはずすゆるい投球。スローボール。
かん‐きゅう【還給】クワンキフ
物を所有者に返付すること。
がん‐きゅう【眼球】‥キウ
脊椎動物の視覚器。球形で、眼窩がんか内にあり、外には強膜・角膜、中間に脈絡膜みゃくらくまく・毛様体および虹彩こうさい、内に網膜の3層から成り、その内部に水晶体および硝子しょうし体などを含む。眼球の周囲に付着している眼筋によって運動する。光線は透明な角膜を通り、虹彩のかこむ瞳孔を経て内部に入る。水晶体はレンズの働きをし、網膜に像が映り、視神経を経て大脳に伝えられる。めだま。→水晶体→虹彩→瞳孔。
眼球
⇒かん‐ぎ【歓喜】
かんき‐とう【換気塔】クワン‥タフ
室内の汚染空気を排除するために、屋上などに設けた塔。
⇒かん‐き【換気】
かんきのう‐けんさ【肝機能検査】
肝障害の有無および程度を調べるため、尿・血液について行う生化学的検査。胆汁排泄機能について血清ビリルビン値、尿ビリルビン・ウロビリノゲン、色素排泄能についてBSP・ICG試験、蛋白代謝について血清蛋白・アルブミン値など、糖質代謝についてブドウ糖・ガラクトース負荷試験、脂質代謝について血清コレステロール、肝細胞障害についてトランスアミナーゼ(AST(GOT)・ALT(GPT))・γ‐グルタミル‐トランスペプチダーゼ(γ‐GTP)など、肝炎ウイルスについてHB抗原・HA抗体など。その種類は200種に及ぶ。
かんぎ‐の‐ききん【寛喜の飢饉】クワン‥
寛喜2年(1230)から翌年にかけての大飢饉。特に北陸・四国の被害は大きく、秋から翌年にかけ餓死者が続出。京都は屍に埋まったという。幕府も伊豆・駿河の農民救済のため出挙すいこ米を貸し出した。
⇒かんぎ【寛喜】
がんぎ‐ばしご【雁木梯子】
1本の太い材に段を刻み出すか、またはその材に数本の横木をつけた梯子。
⇒がん‐ぎ【雁木】
かん‐きゃく【閑却】
打ち捨てておくこと。なおざりにすること。「今や―を許さない事態」
かん‐きゃく【鉗脚】
「はさみ(鋏・剪刀)2」参照。
かん‐きゃく【還却】クワン‥
返すこと。
かん‐きゃく【観客】クワン‥
見物人。特に、映画・演劇・スポーツなどを見る人。看客。
がんぎ‐やすり【雁木鑢】
太くて目のあらい鑢。→雁木5
⇒がん‐ぎ【雁木】
かん‐きゅう【官給】クワンキフ
官府から金銭・物品を給与すること。「―品」
かん‐きゅう【竿球】‥キウ
旗竿の上端に付ける球状の飾り。
かん‐きゅう【貫休】クワンキウ
唐末五代の禅僧・詩人・画家。俗姓は姜。字は徳隠。婺ぶ州蘭渓(浙江)の儒家の生れ。仏門に入り、各地を巡り、晩年は成都に移る。夢幻的な詩と、水墨画風をとり込んだ特異な十六羅漢図で著名。禅月大師。(832〜912)
かん‐きゅう【感泣】‥キフ
深く感じて泣くこと。「師の恩情に―する」
かん‐きゅう【緩急】クワンキフ
①ゆるやかなことときびしいこと。遅いことと速いこと。「―よろしきを得る」
②(「緩」は語調を整える語)急なこと。危急の場合。まさかの場合。「一旦―あれば」
⇒かんきゅう‐きごう【緩急記号】
⇒かんきゅう‐じざい【緩急自在】
⇒かんきゅう‐しゃ【緩急車】
かん‐きゅう【緩球】クワンキウ
野球で、打者のタイミングをはずすゆるい投球。スローボール。
かん‐きゅう【還給】クワンキフ
物を所有者に返付すること。
がん‐きゅう【眼球】‥キウ
脊椎動物の視覚器。球形で、眼窩がんか内にあり、外には強膜・角膜、中間に脈絡膜みゃくらくまく・毛様体および虹彩こうさい、内に網膜の3層から成り、その内部に水晶体および硝子しょうし体などを含む。眼球の周囲に付着している眼筋によって運動する。光線は透明な角膜を通り、虹彩のかこむ瞳孔を経て内部に入る。水晶体はレンズの働きをし、網膜に像が映り、視神経を経て大脳に伝えられる。めだま。→水晶体→虹彩→瞳孔。
眼球
 視神経
水晶体
角膜
虹彩
毛様体
網膜
硝子体
脈絡膜
強膜
⇒がんきゅう‐きん【眼球筋】
⇒がんきゅう‐しんとう【眼球振盪】
がん‐きゅう【龕柩】‥キウ
死骸を納める棺。ひつぎ。
かんきゅう‐きごう【緩急記号】クワンキフ‥ガウ
〔音〕速度標語のうち、速度の変更を指示する記号。リタルダンドなど。
⇒かん‐きゅう【緩急】
がんきゅう‐きん【眼球筋】‥キウ‥
(→)眼筋に同じ。
⇒がん‐きゅう【眼球】
かんきゅう‐じざい【緩急自在】クワンキフ‥
ゆるめたりひきしめたり、どのようにでも操れること。「―の投球」
⇒かん‐きゅう【緩急】
かんきゅう‐しゃ【緩急車】クワンキフ‥
客車および貨車のうち、運転中に常用するブレーキ装置と留置中の転動を防止するブレーキ装置を備えたもの。
⇒かん‐きゅう【緩急】
かんぎゅう‐じゅうとう【汗牛充棟】‥ギウ‥
[柳宗元、陸文通墓表](牛が汗をかくほどの重さと、棟につかえるほどの量、の意)蔵書の非常に多いこと。転じて、多くの書籍。
がんきゅう‐しんとう【眼球振盪】‥キウ‥タウ
(nystagmus ラテン)眼球の不随意性・律動的な往復運動。生理的にも見られるが、病的には眼・脳・神経疾患の際に現れ、水平・垂直・回転などの方向性また衝動性・振子様などの運動様式に分類される。眼球震盪。眼振。
⇒がん‐きゅう【眼球】
かん‐きゅうちゅう【肝吸虫】‥キフ‥
キュウチュウ目の吸虫。体は扁平、長い木葉状、体長6〜20ミリメートル。幅2〜5ミリメートル。口吸盤は前端に、腹吸盤は前部腹面にある。人・犬・猫・豚などの胆管に寄生。卵からかえった幼虫はマメタニシ、次いでコイ科の淡水魚に寄生したのち人体などに入りこむ。淡水魚の調理には注意が必要。日本・中国・東南アジアなどに分布。肝臓ジストマ。
かん‐きょ【函渠】
断面が長方形の暗渠。
かん‐きょ【官許】クワン‥
政府の許可。政府が特定の人に特定の事を許すこと。
かん‐きょ【乾薑】
カンキョウの訛。
かん‐きょ【閑居】
①閑静な住居。
②ひまでいること。世事を離れてのんびりと暮らすこと。「小人―して不善をなす」
③名物茶碗の一つ。楽焼で千宗室判の黒茶碗。
かん‐ぎょ【扞禦】
ふせぐこと。防御。
かん‐ぎょ【乾魚・干魚】
ほした魚。ひもの。ほしざかな。
かん‐ぎょ【還御】クワン‥
①天皇・三后などが行幸啓ぎょうこうけい先から帰ることの尊敬語。
②将軍・公卿が他行先から帰ることを、分を越えて用いた語。
かん‐ぎょ【鹹魚】
塩漬にした魚。塩魚。塩物。
かん‐きょう【奸凶・姦凶】
わるだくみをするわる者。
かん‐きょう【乾薑・乾姜】‥キヤウ
ショウガの根を蒸して乾したもの。漢方生薬の一つで、体を温める効がある。乾生薑かんしょうが。狂言、煎じ物「陳皮―葉甘草」
かん‐きょう【寒郷】‥キヤウ
①さびしい里。
②自分の居住地や故郷の謙称。
かん‐きょう【寒蛩】
秋の末のこおろぎ。
かん‐きょう【感興】
興味を感ずること。面白がること。また、その興味。「―をもよおす」「―をそがれる」
かん‐きょう【漢鏡】‥キヤウ
漢代の鏡。ほとんどが円盤形の青銅製品。草葉文鏡・連弧文鏡・四神鏡・神獣鏡・画像鏡などが代表的。→漢式鏡
かん‐きょう【緩頬】クワンケフ
①顔色をやわらげること。また、顔色をやわらげておだやかに話すこと。婉曲に話すこと。
②「緩頬を煩わす」の略。
⇒緩頬を煩わす
かん‐きょう【還郷】クワンキヤウ
ふるさとにかえること。帰郷。かんけい。
かん‐きょう【環境】クワンキヤウ
①めぐり囲む区域。
②四囲の外界。周囲の事物。特に、人間または生物をとりまき、それと相互作用を及ぼし合うものとして見た外界。自然的環境と社会的環境とがある。「恵まれた―に育つ」
⇒かんきょう‐アセスメント【環境アセスメント】
⇒かんきょう‐えいきょう‐ひょうか【環境影響評価】
⇒かんきょう‐えいせい【環境衛生】
⇒かんきょう‐かいけい【環境会計】
⇒かんきょう‐かがく【環境科学】
⇒かんきょう‐きじゅん【環境基準】
⇒かんきょう‐きほん‐ほう【環境基本法】
⇒かんきょう‐きょういく【環境教育】
⇒かんきょう‐きょうせい【環境共生】
⇒かんきょう‐けいざいがく【環境経済学】
⇒かんきょう‐けん【環境権】
⇒かんきょう‐こうこがく【環境考古学】
⇒かんきょう‐しょう【環境省】
⇒かんきょう‐ぜい【環境税】
⇒かんきょう‐せいぎ【環境正義】
⇒かんきょう‐だいじん【環境大臣】
⇒かんきょう‐ちょう【環境庁】
⇒かんきょう‐なんみん【環境難民】
⇒かんきょう‐ビデオ【環境ビデオ】
⇒かんきょう‐ふか【環境負荷】
⇒かんきょう‐へんい【環境変異】
⇒かんきょう‐ホルモン【環境ホルモン】
⇒かんきょう‐よういん【環境要因】
⇒かんきょう‐ようりょう【環境容量】
⇒かんきょう‐リスク【環境リスク】
⇒かんきょう‐りん【環境林】
⇒かんきょう‐りんりがく【環境倫理学】
かん‐きょう【艦橋】‥ケウ
(bridge)艦船の甲板上に高く設けられた望楼状の構築物で、航行中、操船・通信などを指揮する所。船橋。ブリッジ。
かん‐ぎょう【官業】クワンゲフ
政府が管理・経営する事業。日本では、国有林野やかつての国鉄など。広義には特殊法人や地方公共団体の経営する公営事業をも含む。官営事業。↔民業。
⇒かんぎょう‐はらいさげ【官業払下げ】
かん‐ぎょう【寒行】‥ギヤウ
寒中に寒さに耐えてする修行・苦行。水垢離みずごり・念仏・誦経ずきょうをなし、または薄着・裸体・裸足で社寺に詣で祈願する。〈[季]冬〉
かん‐ぎょう【勧業】クワンゲフ
農業・工業などの産業を勧めはげますこと。
⇒かんぎょう‐ぎんこう【勧業銀行】
かん‐ぎょう【諫暁】‥ゲウ
〔仏〕諫いさめ諭さとすこと。相手の誤りを指摘して迷妄を開き、正しい道に導くこと。
かん‐ぎょう【観行】クワンギヤウ
〔仏〕観念修行のこと。観心かんじんの行法。
かん‐ぎょう【観経】クワンギヤウ
①(→)看経かんきんに同じ。
②観無量寿経の略称。
がん‐きょう【眼鏡】‥キヤウ
めがね。
がん‐きょう【頑強】グワンキヤウ
頑固で屈せず強いこと。てごわいこと。「―に抵抗する」「―な反対運動」
がん‐ぎょう【丸桁】グワンギヤウ
⇒がぎょう
がんぎょう【元暁】グワンゲウ
(ゲンギョウとも)新羅の学僧。入唐を志したが途中で止め、妻帯して俗人のような生活を送りながら、華厳経・大乗起信論の注釈など多くの著作を著し、日本でも南都仏教において尊重された。和諍わじょう国師。(617〜686)
がんぎょう【元慶】グワンギヤウ
(ガンキョウ・ゲンケイとも)平安前期、陽成・光孝天皇朝の年号。貞観19年4月16日(877年6月1日)改元、元慶9年2月21日(885年3月11日)仁和に改元。
⇒がんぎょう‐じ【元慶寺】
がん‐ぎょう【願行】グワンギヤウ
〔仏〕果報を願い求めること(願)と、その果報を得るため修すること(行)。誓願と修行。
かんきょう‐アセスメント【環境アセスメント】クワンキヤウ‥
(environmental impact assessment)(→)環境影響評価に同じ。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐えいきょう‐ひょうか【環境影響評価】クワンキヤウ‥キヤウヒヤウ‥
開発が環境に及ぼす影響の内容と程度および環境保全対策について事前に予測と評価を行い、保全上必要な措置の検討をすること。環境アセスメント。EIA
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐えいせい【環境衛生】クワンキヤウヱイ‥
健康生活維持のため環境の保全・改善をはかること。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐かいけい【環境会計】クワンキヤウクワイ‥
(environmental accounting)企業等が、事業活動における環境保全のための投資・経費やその効果を定量的に把握し、それを企業内外の利害関係者に伝達する会計。日本では、環境省・経済産業省が、ガイドラインを公表。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐かがく【環境科学】クワンキヤウクワ‥
自然環境やその破壊を人間や生物とのかかわりにおいてとらえる総合科学。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きじゅん【環境基準】クワンキヤウ‥
大気・土壌の汚染、水質の汚濁、騒音などの環境条件について、健康を守り生活環境を保つうえで維持されるべき基準。環境基本法などに基づく。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きほん‐ほう【環境基本法】クワンキヤウ‥ハフ
環境保全に関する施策の基本を定めた法律。1993年、公害対策基本法に代わって制定。従来の公害対策だけでなく、地球環境保全問題への対処も含む。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きょういく【環境教育】クワンキヤウケウ‥
自然環境の有限性に注目し、環境破壊を防ぎ、環境問題を解決し、自然との調和に基づく、持続的な社会づくりを目的とする教育。2003年環境保全活動環境教育推進法が成立。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きょうせい【環境共生】クワンキヤウ‥
環境保全に配慮し、また周辺の自然環境との調和を重視すること。「―住宅」
⇒かん‐きょう【環境】
かんぎょう‐ぎんこう【勧業銀行】クワンゲフ‥カウ
日本勧業銀行の略称。
⇒かん‐ぎょう【勧業】
かんきょう‐けいざいがく【環境経済学】クワンキヤウ‥
環境問題を経済のメカニズムや法則によって研究し、環境政策を論ずる経済学の一分野。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐けん【環境権】クワンキヤウ‥
よい環境を享受し、これを支配する権利。法律上は、その内容がいまだ不明確で具体的権利として確立されてはいないが、環境保全のための基本的な法理として主張されている。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐こうこがく【環境考古学】クワンキヤウカウ‥
自然環境の変化と人間生活や社会の変化との相関関係を明らかにすることをめざす考古学の一分野。
⇒かん‐きょう【環境】
がんぎょう‐じ【元慶寺】グワンギヤウ‥
京都市山科区にあった真言宗の寺(今はガンケイジといい、天台宗)。868年(貞観10)陽成天皇誕生の時、遍昭の創建。9世紀には安然などが住し隆盛。986年(寛和2)花山天皇は藤原道兼に謀られ、ここに潜幸して出家。別称、花山寺かざんじ。
⇒がんぎょう【元慶】
かんきょう‐しょう【環境省】クワンキヤウシヤウ
地球環境の保全、公害の防止、自然環境の保護その他の環境の保全を任務とする中央行政機関。環境大臣を長とする。2001年環境庁から昇格。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ぜい【環境税】クワンキヤウ‥
二酸化炭素、硫黄・窒素酸化物、有害廃棄物などの環境汚染物質の排出を抑制する手段として課される租税の総称。炭素税の類。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐せいぎ【環境正義】クワンキヤウ‥
(environmental justice)環境破壊の被害に経済的・人種的差別が関係している現状を克服し、実現するべき社会的正義。アメリカにおいて、1980年代にアフリカ系アメリカ人居住地域に有害廃棄物処理施設が集中していることへの抗議として提唱され、92年に連邦環境保護庁に環境正義局が開設された。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐だいじん【環境大臣】クワンキヤウ‥
内閣各省大臣の一つ。環境省の長。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ちょう【環境庁】クワンキヤウチヤウ
環境省の前身。総理府の外局として1971年設置。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐なんどう【咸鏡南道】‥キヤウ‥ダウ
⇒ハムギョン‐ナムド
かんきょう‐なんみん【環境難民】クワンキヤウ‥
環境破壊によって居住地を離れることを余儀なくされた人々。難民条約(1951年採択)が規定する難民とは異なる。
⇒かん‐きょう【環境】
かんぎょう‐はらいさげ【官業払下げ】クワンゲフハラヒ‥
明治10〜20年代を中心に、明治政府が行なった官営工場・鉱山などの民間への払下げ政策。経営難を背景に低価格で行われたため、財閥形成の契機となった。
⇒かん‐ぎょう【官業】
かんきょう‐ビデオ【環境ビデオ】クワンキヤウ‥
室内の環境を演出するために流すビデオ。主に自然の風景などを映し出す。インテリア‐ビデオ。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ふか【環境負荷】クワンキヤウ‥
人間活動が自然環境に与える負担のこと。廃棄物・干拓・焼畑・人口増加の類。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐へんい【環境変異】クワンキヤウ‥
同一の生物集団の個体間において、生育環境の差や、発育途上の偶然の要因などの影響で生じる量的な変異で、遺伝しないもの。一般に変異の大きさは、ある値を中心に連続的に分布し、彷徨変異ともいう。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ほくどう【咸鏡北道】‥キヤウ‥ダウ
⇒ハムギョン‐プクト
かんきょう‐ホルモン【環境ホルモン】クワンキヤウ‥
(→)内分泌攪乱物質に同じ。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐よういん【環境要因】クワンキヤウエウ‥
生物個体または集団の環境を構成する諸要素のこと。生物間の相互作用も含めた、有機的な要因(生物的環境)と無機的な要因(光・温度・水分・土壌など)とがある。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ようりょう【環境容量】クワンキヤウ‥リヤウ
①特定の種が、ある環境のもとで維持しうる最大の個体数。環境収容力。
②環境が自然に浄化できる汚染の許容量。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐リスク【環境リスク】クワンキヤウ‥
人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれ。地震など自然環境から発生するものと、化学物質による汚染など人為的に発生するものとがある。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐りん【環境林】クワンキヤウ‥
水資源の涵養、土砂流出の防止、大気浄化などの環境保全機能の高い森林。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐りんりがく【環境倫理学】クワンキヤウ‥
環境問題を解決するため、自然と人間との関係を倫理的観点から考察しようとする学問。自然の生存権、世代間倫理、資源の有限性などを主張。
⇒かん‐きょう【環境】
視神経
水晶体
角膜
虹彩
毛様体
網膜
硝子体
脈絡膜
強膜
⇒がんきゅう‐きん【眼球筋】
⇒がんきゅう‐しんとう【眼球振盪】
がん‐きゅう【龕柩】‥キウ
死骸を納める棺。ひつぎ。
かんきゅう‐きごう【緩急記号】クワンキフ‥ガウ
〔音〕速度標語のうち、速度の変更を指示する記号。リタルダンドなど。
⇒かん‐きゅう【緩急】
がんきゅう‐きん【眼球筋】‥キウ‥
(→)眼筋に同じ。
⇒がん‐きゅう【眼球】
かんきゅう‐じざい【緩急自在】クワンキフ‥
ゆるめたりひきしめたり、どのようにでも操れること。「―の投球」
⇒かん‐きゅう【緩急】
かんきゅう‐しゃ【緩急車】クワンキフ‥
客車および貨車のうち、運転中に常用するブレーキ装置と留置中の転動を防止するブレーキ装置を備えたもの。
⇒かん‐きゅう【緩急】
かんぎゅう‐じゅうとう【汗牛充棟】‥ギウ‥
[柳宗元、陸文通墓表](牛が汗をかくほどの重さと、棟につかえるほどの量、の意)蔵書の非常に多いこと。転じて、多くの書籍。
がんきゅう‐しんとう【眼球振盪】‥キウ‥タウ
(nystagmus ラテン)眼球の不随意性・律動的な往復運動。生理的にも見られるが、病的には眼・脳・神経疾患の際に現れ、水平・垂直・回転などの方向性また衝動性・振子様などの運動様式に分類される。眼球震盪。眼振。
⇒がん‐きゅう【眼球】
かん‐きゅうちゅう【肝吸虫】‥キフ‥
キュウチュウ目の吸虫。体は扁平、長い木葉状、体長6〜20ミリメートル。幅2〜5ミリメートル。口吸盤は前端に、腹吸盤は前部腹面にある。人・犬・猫・豚などの胆管に寄生。卵からかえった幼虫はマメタニシ、次いでコイ科の淡水魚に寄生したのち人体などに入りこむ。淡水魚の調理には注意が必要。日本・中国・東南アジアなどに分布。肝臓ジストマ。
かん‐きょ【函渠】
断面が長方形の暗渠。
かん‐きょ【官許】クワン‥
政府の許可。政府が特定の人に特定の事を許すこと。
かん‐きょ【乾薑】
カンキョウの訛。
かん‐きょ【閑居】
①閑静な住居。
②ひまでいること。世事を離れてのんびりと暮らすこと。「小人―して不善をなす」
③名物茶碗の一つ。楽焼で千宗室判の黒茶碗。
かん‐ぎょ【扞禦】
ふせぐこと。防御。
かん‐ぎょ【乾魚・干魚】
ほした魚。ひもの。ほしざかな。
かん‐ぎょ【還御】クワン‥
①天皇・三后などが行幸啓ぎょうこうけい先から帰ることの尊敬語。
②将軍・公卿が他行先から帰ることを、分を越えて用いた語。
かん‐ぎょ【鹹魚】
塩漬にした魚。塩魚。塩物。
かん‐きょう【奸凶・姦凶】
わるだくみをするわる者。
かん‐きょう【乾薑・乾姜】‥キヤウ
ショウガの根を蒸して乾したもの。漢方生薬の一つで、体を温める効がある。乾生薑かんしょうが。狂言、煎じ物「陳皮―葉甘草」
かん‐きょう【寒郷】‥キヤウ
①さびしい里。
②自分の居住地や故郷の謙称。
かん‐きょう【寒蛩】
秋の末のこおろぎ。
かん‐きょう【感興】
興味を感ずること。面白がること。また、その興味。「―をもよおす」「―をそがれる」
かん‐きょう【漢鏡】‥キヤウ
漢代の鏡。ほとんどが円盤形の青銅製品。草葉文鏡・連弧文鏡・四神鏡・神獣鏡・画像鏡などが代表的。→漢式鏡
かん‐きょう【緩頬】クワンケフ
①顔色をやわらげること。また、顔色をやわらげておだやかに話すこと。婉曲に話すこと。
②「緩頬を煩わす」の略。
⇒緩頬を煩わす
かん‐きょう【還郷】クワンキヤウ
ふるさとにかえること。帰郷。かんけい。
かん‐きょう【環境】クワンキヤウ
①めぐり囲む区域。
②四囲の外界。周囲の事物。特に、人間または生物をとりまき、それと相互作用を及ぼし合うものとして見た外界。自然的環境と社会的環境とがある。「恵まれた―に育つ」
⇒かんきょう‐アセスメント【環境アセスメント】
⇒かんきょう‐えいきょう‐ひょうか【環境影響評価】
⇒かんきょう‐えいせい【環境衛生】
⇒かんきょう‐かいけい【環境会計】
⇒かんきょう‐かがく【環境科学】
⇒かんきょう‐きじゅん【環境基準】
⇒かんきょう‐きほん‐ほう【環境基本法】
⇒かんきょう‐きょういく【環境教育】
⇒かんきょう‐きょうせい【環境共生】
⇒かんきょう‐けいざいがく【環境経済学】
⇒かんきょう‐けん【環境権】
⇒かんきょう‐こうこがく【環境考古学】
⇒かんきょう‐しょう【環境省】
⇒かんきょう‐ぜい【環境税】
⇒かんきょう‐せいぎ【環境正義】
⇒かんきょう‐だいじん【環境大臣】
⇒かんきょう‐ちょう【環境庁】
⇒かんきょう‐なんみん【環境難民】
⇒かんきょう‐ビデオ【環境ビデオ】
⇒かんきょう‐ふか【環境負荷】
⇒かんきょう‐へんい【環境変異】
⇒かんきょう‐ホルモン【環境ホルモン】
⇒かんきょう‐よういん【環境要因】
⇒かんきょう‐ようりょう【環境容量】
⇒かんきょう‐リスク【環境リスク】
⇒かんきょう‐りん【環境林】
⇒かんきょう‐りんりがく【環境倫理学】
かん‐きょう【艦橋】‥ケウ
(bridge)艦船の甲板上に高く設けられた望楼状の構築物で、航行中、操船・通信などを指揮する所。船橋。ブリッジ。
かん‐ぎょう【官業】クワンゲフ
政府が管理・経営する事業。日本では、国有林野やかつての国鉄など。広義には特殊法人や地方公共団体の経営する公営事業をも含む。官営事業。↔民業。
⇒かんぎょう‐はらいさげ【官業払下げ】
かん‐ぎょう【寒行】‥ギヤウ
寒中に寒さに耐えてする修行・苦行。水垢離みずごり・念仏・誦経ずきょうをなし、または薄着・裸体・裸足で社寺に詣で祈願する。〈[季]冬〉
かん‐ぎょう【勧業】クワンゲフ
農業・工業などの産業を勧めはげますこと。
⇒かんぎょう‐ぎんこう【勧業銀行】
かん‐ぎょう【諫暁】‥ゲウ
〔仏〕諫いさめ諭さとすこと。相手の誤りを指摘して迷妄を開き、正しい道に導くこと。
かん‐ぎょう【観行】クワンギヤウ
〔仏〕観念修行のこと。観心かんじんの行法。
かん‐ぎょう【観経】クワンギヤウ
①(→)看経かんきんに同じ。
②観無量寿経の略称。
がん‐きょう【眼鏡】‥キヤウ
めがね。
がん‐きょう【頑強】グワンキヤウ
頑固で屈せず強いこと。てごわいこと。「―に抵抗する」「―な反対運動」
がん‐ぎょう【丸桁】グワンギヤウ
⇒がぎょう
がんぎょう【元暁】グワンゲウ
(ゲンギョウとも)新羅の学僧。入唐を志したが途中で止め、妻帯して俗人のような生活を送りながら、華厳経・大乗起信論の注釈など多くの著作を著し、日本でも南都仏教において尊重された。和諍わじょう国師。(617〜686)
がんぎょう【元慶】グワンギヤウ
(ガンキョウ・ゲンケイとも)平安前期、陽成・光孝天皇朝の年号。貞観19年4月16日(877年6月1日)改元、元慶9年2月21日(885年3月11日)仁和に改元。
⇒がんぎょう‐じ【元慶寺】
がん‐ぎょう【願行】グワンギヤウ
〔仏〕果報を願い求めること(願)と、その果報を得るため修すること(行)。誓願と修行。
かんきょう‐アセスメント【環境アセスメント】クワンキヤウ‥
(environmental impact assessment)(→)環境影響評価に同じ。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐えいきょう‐ひょうか【環境影響評価】クワンキヤウ‥キヤウヒヤウ‥
開発が環境に及ぼす影響の内容と程度および環境保全対策について事前に予測と評価を行い、保全上必要な措置の検討をすること。環境アセスメント。EIA
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐えいせい【環境衛生】クワンキヤウヱイ‥
健康生活維持のため環境の保全・改善をはかること。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐かいけい【環境会計】クワンキヤウクワイ‥
(environmental accounting)企業等が、事業活動における環境保全のための投資・経費やその効果を定量的に把握し、それを企業内外の利害関係者に伝達する会計。日本では、環境省・経済産業省が、ガイドラインを公表。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐かがく【環境科学】クワンキヤウクワ‥
自然環境やその破壊を人間や生物とのかかわりにおいてとらえる総合科学。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きじゅん【環境基準】クワンキヤウ‥
大気・土壌の汚染、水質の汚濁、騒音などの環境条件について、健康を守り生活環境を保つうえで維持されるべき基準。環境基本法などに基づく。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きほん‐ほう【環境基本法】クワンキヤウ‥ハフ
環境保全に関する施策の基本を定めた法律。1993年、公害対策基本法に代わって制定。従来の公害対策だけでなく、地球環境保全問題への対処も含む。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きょういく【環境教育】クワンキヤウケウ‥
自然環境の有限性に注目し、環境破壊を防ぎ、環境問題を解決し、自然との調和に基づく、持続的な社会づくりを目的とする教育。2003年環境保全活動環境教育推進法が成立。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐きょうせい【環境共生】クワンキヤウ‥
環境保全に配慮し、また周辺の自然環境との調和を重視すること。「―住宅」
⇒かん‐きょう【環境】
かんぎょう‐ぎんこう【勧業銀行】クワンゲフ‥カウ
日本勧業銀行の略称。
⇒かん‐ぎょう【勧業】
かんきょう‐けいざいがく【環境経済学】クワンキヤウ‥
環境問題を経済のメカニズムや法則によって研究し、環境政策を論ずる経済学の一分野。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐けん【環境権】クワンキヤウ‥
よい環境を享受し、これを支配する権利。法律上は、その内容がいまだ不明確で具体的権利として確立されてはいないが、環境保全のための基本的な法理として主張されている。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐こうこがく【環境考古学】クワンキヤウカウ‥
自然環境の変化と人間生活や社会の変化との相関関係を明らかにすることをめざす考古学の一分野。
⇒かん‐きょう【環境】
がんぎょう‐じ【元慶寺】グワンギヤウ‥
京都市山科区にあった真言宗の寺(今はガンケイジといい、天台宗)。868年(貞観10)陽成天皇誕生の時、遍昭の創建。9世紀には安然などが住し隆盛。986年(寛和2)花山天皇は藤原道兼に謀られ、ここに潜幸して出家。別称、花山寺かざんじ。
⇒がんぎょう【元慶】
かんきょう‐しょう【環境省】クワンキヤウシヤウ
地球環境の保全、公害の防止、自然環境の保護その他の環境の保全を任務とする中央行政機関。環境大臣を長とする。2001年環境庁から昇格。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ぜい【環境税】クワンキヤウ‥
二酸化炭素、硫黄・窒素酸化物、有害廃棄物などの環境汚染物質の排出を抑制する手段として課される租税の総称。炭素税の類。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐せいぎ【環境正義】クワンキヤウ‥
(environmental justice)環境破壊の被害に経済的・人種的差別が関係している現状を克服し、実現するべき社会的正義。アメリカにおいて、1980年代にアフリカ系アメリカ人居住地域に有害廃棄物処理施設が集中していることへの抗議として提唱され、92年に連邦環境保護庁に環境正義局が開設された。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐だいじん【環境大臣】クワンキヤウ‥
内閣各省大臣の一つ。環境省の長。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ちょう【環境庁】クワンキヤウチヤウ
環境省の前身。総理府の外局として1971年設置。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐なんどう【咸鏡南道】‥キヤウ‥ダウ
⇒ハムギョン‐ナムド
かんきょう‐なんみん【環境難民】クワンキヤウ‥
環境破壊によって居住地を離れることを余儀なくされた人々。難民条約(1951年採択)が規定する難民とは異なる。
⇒かん‐きょう【環境】
かんぎょう‐はらいさげ【官業払下げ】クワンゲフハラヒ‥
明治10〜20年代を中心に、明治政府が行なった官営工場・鉱山などの民間への払下げ政策。経営難を背景に低価格で行われたため、財閥形成の契機となった。
⇒かん‐ぎょう【官業】
かんきょう‐ビデオ【環境ビデオ】クワンキヤウ‥
室内の環境を演出するために流すビデオ。主に自然の風景などを映し出す。インテリア‐ビデオ。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ふか【環境負荷】クワンキヤウ‥
人間活動が自然環境に与える負担のこと。廃棄物・干拓・焼畑・人口増加の類。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐へんい【環境変異】クワンキヤウ‥
同一の生物集団の個体間において、生育環境の差や、発育途上の偶然の要因などの影響で生じる量的な変異で、遺伝しないもの。一般に変異の大きさは、ある値を中心に連続的に分布し、彷徨変異ともいう。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ほくどう【咸鏡北道】‥キヤウ‥ダウ
⇒ハムギョン‐プクト
かんきょう‐ホルモン【環境ホルモン】クワンキヤウ‥
(→)内分泌攪乱物質に同じ。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐よういん【環境要因】クワンキヤウエウ‥
生物個体または集団の環境を構成する諸要素のこと。生物間の相互作用も含めた、有機的な要因(生物的環境)と無機的な要因(光・温度・水分・土壌など)とがある。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐ようりょう【環境容量】クワンキヤウ‥リヤウ
①特定の種が、ある環境のもとで維持しうる最大の個体数。環境収容力。
②環境が自然に浄化できる汚染の許容量。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐リスク【環境リスク】クワンキヤウ‥
人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれ。地震など自然環境から発生するものと、化学物質による汚染など人為的に発生するものとがある。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐りん【環境林】クワンキヤウ‥
水資源の涵養、土砂流出の防止、大気浄化などの環境保全機能の高い森林。
⇒かん‐きょう【環境】
かんきょう‐りんりがく【環境倫理学】クワンキヤウ‥
環境問題を解決するため、自然と人間との関係を倫理的観点から考察しようとする学問。自然の生存権、世代間倫理、資源の有限性などを主張。
⇒かん‐きょう【環境】
かん‐ぎょ【乾魚・干魚】🔗⭐🔉
かん‐ぎょ【乾魚・干魚】
ほした魚。ひもの。ほしざかな。
かん‐けん【乾繭・干繭】🔗⭐🔉
かん‐けん【乾繭・干繭】
保存のため、乾燥機で蛹さなぎを殺した繭。↔生繭。
⇒かんけん‐とりひき【乾繭取引】
かん‐じゅ【干珠】🔗⭐🔉
かん‐じゅ【干珠】
海に投げ入れれば、潮が干ひるという珠。しおひのたま。↔満珠
かん‐しゅつ【干出】🔗⭐🔉
かん‐しゅつ【干出】
干潮時に海水面上に現れること。ノリ網・岩礁などにいう。
かん‐しょう【干渉】‥セフ🔗⭐🔉
かん‐しょう【干渉】‥セフ
①[後漢書東夷伝、濊]他人の物事に強いて立ち入り、自己の意思に従わせようとすること。「子に―しすぎる」「内政―」
②〔理〕(interference)波動に特有な現象で、二つ以上の同一種類の波動が同一点に会した時、その点において起こる相互作用。波動が同位相では互いに強め合い、反対の位相では互いに弱め合う。
⇒かんしょう‐けい【干渉計】
⇒かんしょう‐じま【干渉縞】
⇒かんしょう‐しょく【干渉色】
かん‐じょう【干城】‥ジヤウ🔗⭐🔉
かん‐じょう【干城】‥ジヤウ
[詩経周南、兎罝](干たてと城との意)国家を守る武士・軍人。
かんしょう‐けい【干渉計】‥セフ‥🔗⭐🔉
かんしょう‐けい【干渉計】‥セフ‥
電磁波の干渉を利用して、波長・波長分布の測定、2地点間の距離、物体の長さ・屈折率の精密測定などに応用する装置。
⇒かん‐しょう【干渉】
かんしょう‐じま【干渉縞】‥セフ‥🔗⭐🔉
かんしょう‐じま【干渉縞】‥セフ‥
光の干渉のために生じる縞模様。単色光では明暗の縞、白色光では干渉色が見られる。
⇒かん‐しょう【干渉】
かんしょう‐しょく【干渉色】‥セフ‥🔗⭐🔉
かんしょう‐しょく【干渉色】‥セフ‥
白色光どうしの干渉によって生じる色。しゃぼん玉やコンパクト‐ディスクなどで見られる。厚さの測定にも利用。
⇒かん‐しょう【干渉】
かんしょう‐ばくや【干将莫耶・干将莫邪】‥シヤウ‥🔗⭐🔉
かんしょう‐ばくや【干将莫耶・干将莫邪】‥シヤウ‥
①中国古代の二振りの名剣。呉の刀工干将は呉王の嘱により剣を作るとき、妻莫耶の髪や爪を炉に入れるなどして初めて作り得た名剣二振りに、陽を「干将」、陰を「莫耶」と名づけたという。
②転じて、広く名剣の意。
かん‐たく【干拓】🔗⭐🔉
かん‐たく【干拓】
湖沼・海浜などを、堤防を築き排水して、陸地や耕地にすること。「沼を―する」
⇒かんたく‐ち【干拓地】
かんたく‐ち【干拓地】🔗⭐🔉
かんたく‐ち【干拓地】
干拓工事をして造成した陸地、耕作地。
⇒かん‐たく【干拓】
かん‐ちょう【干潮】‥テウ🔗⭐🔉
かん‐ちょう【干潮】‥テウ
潮がひいて海水面が最低に達した状態。低潮。ひしお。↔満潮。
⇒かんちょう‐せん【干潮線】
かんちょう‐せん【干潮線】‥テウ‥🔗⭐🔉
かんちょう‐せん【干潮線】‥テウ‥
海潮の最も降下した時の汀線ていせん。→汀線
⇒かん‐ちょう【干潮】
かん‐てん【干天・旱天】🔗⭐🔉
かん‐てん【干天・旱天】
ひでりの空。夏の照りつける空。〈[季]夏〉
⇒かんてん‐の‐じう【干天の慈雨】
かんてん‐の‐じう【干天の慈雨】🔗⭐🔉
かんてん‐の‐じう【干天の慈雨】
ひでりの時に降るありがたい雨。苦しい時の救いや待ち望んでいたことの実現にいう。
⇒かん‐てん【干天・旱天】
かん‐ぱん【干犯】🔗⭐🔉
かん‐ぱん【干犯】
干渉して他の権利を犯すこと。「統帥権―」
かん‐ぴょう【干瓢・乾瓢】‥ペウ🔗⭐🔉
かん‐ぴょう【干瓢・乾瓢】‥ペウ
ユウガオの果肉を、細く薄く長くむいて乾した食品。栃木県の名産。
かん‐まん【干満】🔗⭐🔉
かん‐まん【干満】
潮のみちひ。干潮と満潮。「―の差」
かん‐よ【干与】🔗⭐🔉
かん‐よ【干与】
あずかること。たずさわること。関与。
かん‐れつ【乾裂・干裂】🔗⭐🔉
かん‐れつ【乾裂・干裂】
①かわきさけること。ひわれること。
②泥土の薄層が乾燥して生ずる多角形の亀裂。
かん‐ろく【干禄】🔗⭐🔉
かん‐ろく【干禄】
(「干」は求める意)
①さいわいを求めること。
②仕えて禄を求めること。仕官を願うこと。「―字書」
かんろくじしょ【干禄字書】🔗⭐🔉
かんろくじしょ【干禄字書】
中国の字書。1巻。唐の顔元孫撰。漢字800字余を韻別に配列し、その楷書の字体の正・俗・通を弁じたもの。後世、字体の正俗を論ずる典拠に用いられる。
ひ【乾・干】🔗⭐🔉
ひ【乾・干】
ひること。かわき。「―のよい海苔」
ひ‐あが・る【干上がる・乾上がる】🔗⭐🔉
ひ‐あが・る【干上がる・乾上がる】
〔自五〕
①全くかわききる。「田が―・る」
②すっかり潮がひいてしまう。
③生計が立たなくなる。飢える。「あごが―・る」
ひ‐うお【干魚・乾魚】‥ウヲ🔗⭐🔉
ひ‐うお【干魚・乾魚】‥ウヲ
魚のひもの。魚の内臓を取りのぞいて乾したもの。ひいお。
ひ‐がし【干菓子・乾菓子】‥グワ‥🔗⭐🔉
ひ‐がし【干菓子・乾菓子】‥グワ‥
生菓子に対する、水分の少ない和菓子の総称。粔籹おこし・落雁らくがん・煎餅せんべいの類。
干菓子
撮影:関戸 勇


ひ‐がた【干潟】🔗⭐🔉
ひ‐がた【干潟】
遠浅の海岸で、潮が引いて現れた所。ひかた。潮干潟。〈[季]春〉
⇒ひがた‐じ【干潟地】
ひがた‐じ【干潟地】‥ヂ🔗⭐🔉
ひがた‐じ【干潟地】‥ヂ
干潟になった土地。
⇒ひ‐がた【干潟】
ひ‐から・びる【乾涸びる・干涸びる】🔗⭐🔉
ひ‐から・びる【乾涸びる・干涸びる】
〔自上一〕[文]ひから・ぶ(上二)
①全くかわく。かわききる。ひあがる。「みかんが―・びる」
②うるおい・張りがなくなる。「才能が―・びる」
ひ‐かわ・く【干乾く】🔗⭐🔉
ひ‐かわ・く【干乾く】
〔自四〕
水気がぬけてかわく。ひからびる。撰集抄「天がした日照りて、すべて絶えせぬ清水などもみな―・きて」
ひ‐ざかな【干魚・乾魚】🔗⭐🔉
ひ‐しお【干潮】‥シホ🔗⭐🔉
ひ‐しお【干潮】‥シホ
潮が干ること。ひきしお。かんちょう。宇治拾遺物語4「―にひかれて、はるかにみなとへ出でにけり」
ひ‐じに【乾死に・干死に】🔗⭐🔉
ひ‐じに【乾死に・干死に】
うえじに。餓死。平家物語3「頼豪はやがて―に死ににけり」
ひ‐し・ぬ【乾死ぬ・干死ぬ】🔗⭐🔉
ひ‐し・ぬ【乾死ぬ・干死ぬ】
〔自ナ変〕
餓えて死ぬ。餓死する。
ひ‐ぞり【乾反り・干反り】🔗⭐🔉
ひ‐ぞり【乾反り・干反り】
①乾いてそりかえること。また、そのもの。浄瑠璃、今宮の心中「―仕直し上下を盤にかけて打ちけるが」
②すねて怒ること。意地悪を言うこと。浄瑠璃、新版歌祭文「お前がいやであらうといふ、―の文ぶんぢや」
③ひどい貧乏。
⇒ひぞり‐ごと【乾反り言】
⇒ひぞり‐ごま【乾反り独楽】
⇒ひぞり‐だいじん【乾反り大尽】
ひ‐ぞ・る【乾反る・干反る】🔗⭐🔉
ひ‐ぞ・る【乾反る・干反る】
〔自五〕
(ヒソルとも)
①かわいてそりかえる。「板が―・る」
②すねる。意地悪くする。洒落本、聖遊廓「―・りかけたらつめつておかしやれ」
③当たった矢などがささらずにすべりおちる。〈日葡辞書〉
ひ‐そん【干損】🔗⭐🔉
ひ‐そん【干損】
田畑が乾いて収穫が減ること。旱損。
ひ‐だい【干鯛】‥ダヒ🔗⭐🔉
ひ‐だい【干鯛】‥ダヒ
薄塩をかけて干した鯛。鯛の干物。礼式の贈物に鮮魚の代りに用いる。
ひ‐だら【干鱈・乾鱈】🔗⭐🔉
ひ‐だら【干鱈・乾鱈】
タラの乾燥品。ほしだら。棒鱈・開き鱈・掛鱈など。〈[季]春〉
ひ‐つ・く【干付く・乾付く】🔗⭐🔉
ひ‐つ・く【干付く・乾付く】
〔自四〕
かわいて付く。ひからびる。ひっつく。
ひっ‐つ・く【干っ付く】🔗⭐🔉
ひっ‐つ・く【干っ付く】
〔自四〕
ヒツクの促音化。狂言、水掛聟「これで某それがしが田が―・く程に、爰ここを切り明けて水を仕かけう」
ひ‐ば【干葉・乾葉】🔗⭐🔉
ひ‐ば【干葉・乾葉】
①枯れて乾いた葉。
②ほした大根の茎や葉。〈[季]冬〉
ひ‐ふぐ【干河豚】🔗⭐🔉
ひ‐ふぐ【干河豚】
フグの干物。
ひ‐ぼし【干乾し】🔗⭐🔉
ひ‐ぼし【干乾し】
食物がなくて飢えやせること。「―になる」
ひ‐もの【干物・乾物】🔗⭐🔉
ひ‐もの【干物・乾物】
保存がきくよう、魚・貝などを干して作った食品。「鰺あじの―」
ひる【干る・乾る】🔗⭐🔉
ひる【干る・乾る】
〔自上一〕
(奈良時代には終止形「ふ」で上二段活用)
①かわく。古今和歌集恋「夕さればいとどひがたき我が袖に」
②海・川の水が涸かれて底が現れる。古今和歌集物名「涙川沖ひむ時や底は知られん」
③終わる。果てる。尽きる。天草本伊曾保物語「我と身を大きにほむる者は、まだその言葉もひぬうちに面目を失ふものぢや」
ひ‐われ【干割れ・日割れ】🔗⭐🔉
ひ‐われ【干割れ・日割れ】
①乾きすぎてひびや割れ目が入ること。また、その割れ目。
②立木が、初春または晩冬の昼と夜との温度差が著しい時、幹に沿って縦に割れ裂けること。
ひ‐わ・れる【干割れる】🔗⭐🔉
ひ‐わ・れる【干割れる】
〔自下一〕
かわいて割れ目ができる。かわいて裂ける。ひびが入る。「柱が―・れる」
○火を挙ぐひをあぐ
[晏子雑上]火をもやす。転じて、生活する。
⇒ひ【火】
○日を改めるひをあらためる
別の日にする。「続きは日を改めて行う」
⇒ひ【日】
○非を打つひをうつ
悪いところを指摘する。非難をする。
⇒ひ【非】
○日を追ってひをおって
日がたつにつれて。日一日。「―体力が回復する」
⇒ひ【日】
○火を落とすひをおとす
①火を弱める。火を消す。
②調理場や窯かまの仕事を終える。
⇒ひ【火】
○日を同じくして論ずべからずひをおなじくしてろんずべからず
[史記游侠伝]両者の間に大差があり、同様に考えることができない。くらべものにならないほど異なっていること。
⇒ひ【日】
○火を易うひをかう
忌服きぶくの終わった日などに、けがれた火を打ちかえて清浄にする。
⇒ひ【火】
○火を掛けるひをかける
火をつける。火を放つ。
⇒ひ【火】
○火を失すひをしっす
あやまって火事を出す。失火する。
⇒ひ【火】
○火を摩るひをする
内面はきわめて不和であることのたとえ。誹風柳多留初「家老とは―顔の美しさ」
⇒ひ【火】
○火を散らすひをちらす
戦いや論争などのはげしいことにいう。火花を散らす。
⇒ひ【火】
○火を付けるひをつける
①点火する。また、放火する。
②騒ぎのきっかけをつくる。また、刺激して怒らせる。「二人の関係に―」「怒りに―」
⇒ひ【火】
○火を通すひをとおす
煮たり焼いたりして、食物に熱を加える。
⇒ひ【火】
○非を鳴らすひをならす
激しく非難する。
⇒ひ【非】
○火を吐くひをはく
火をふき出す。また、そのように弁論のはげしいさまにいう。
⇒ひ【火】
○火を放つひをはなつ
放火する。
⇒ひ【火】
○火を吹くひをふく
①激しく燃え出す。
②火をおこすために息を強く吹きかける。
③炊事をする。また、生計を立てる。
⇒ひ【火】
○火を吹く力も無いひをふくちからもない
気力の全くないたとえ。また、貧乏の甚だしいことのたとえ。
⇒ひ【火】
○火を振るひをふる
①灯火や燃え木をかきたてる。
②仲たがいする。日葡辞書「ペドロトパウロハヒヲフル」
⇒ひ【火】
○火を見たら火事と思えひをみたらかじとおもえ
警戒の上に警戒を加えよということのたとえ。
⇒ひ【火】
○火を見るよりも明らかひをみるよりもあきらか
物事の道理や結果などがきわめて明白で、疑う余地のないことにいう。「どちらが正しいかは―だ」
⇒ひ【火】
ほし【乾し・干し】🔗⭐🔉
ほし【乾し・干し】
太陽熱や火熱にあてて水分をとり去ること。「かげ―」「物―」
ほし‐あ・げる【乾し上げる・干し上げる】🔗⭐🔉
ほし‐あ・げる【乾し上げる・干し上げる】
〔他下一〕[文]ほしあ・ぐ(下二)
①日光や火力で水分をとりさる。平家物語8「源氏の舟五百余艘を―・げたるを…おろしけり」
②食物を奪って飢えさせる。
③水や酒などを飲みほす。
ほし‐あわび【乾鮑・干鮑】‥アハビ🔗⭐🔉
ほし‐あわび【乾鮑・干鮑】‥アハビ
鮑の肉をほしたもの。
ほし‐あん【乾餡・干餡】🔗⭐🔉
ほし‐あん【乾餡・干餡】
(→)「さらしあん」に同じ。
ほし‐いい【乾飯・干飯・糒】‥イヒ🔗⭐🔉
ほし‐いい【乾飯・干飯・糒】‥イヒ
乾燥して貯えておく飯。水に浸せば、すぐに食べられる。かれいい。かれい。ほしい。〈[季]夏〉。宇津保物語俊蔭「―唯少し餌袋に入れて」
ほし‐いお【乾魚・干魚】‥イヲ🔗⭐🔉
ほし‐いお【乾魚・干魚】‥イヲ
⇒ほしうお。〈倭名類聚鈔16〉
ほし‐いも【乾芋・干芋】🔗⭐🔉
ほし‐いも【乾芋・干芋】
(→)乾燥芋に同じ。
ほし‐うお【乾魚・干魚】‥ウヲ🔗⭐🔉
ほし‐うお【乾魚・干魚】‥ウヲ
背・腹を開き、または開かずにほした魚。ひうお。ひもの。
ほし‐うどん【乾饂飩・干饂飩】🔗⭐🔉
ほし‐うどん【乾饂飩・干饂飩】
ほして保存できるようにした饂飩。
ほし‐えび【乾蝦・干海老】🔗⭐🔉
ほし‐えび【乾蝦・干海老】
エビをゆでて乾したもの。
ほし‐がき【乾柿・干柿】🔗⭐🔉
ほし‐がき【乾柿・干柿】
渋柿の皮をむき、ほして甘くしたもの。ころがき。〈[季]秋〉。「―をつるす」
乾柿
撮影:関戸 勇


ほし‐かた・める【乾し固める・干し固める】🔗⭐🔉
ほし‐かた・める【乾し固める・干し固める】
〔他下一〕[文]ほしかた・む(下二)
ほして固くする。源平盛衰記47「一子の娘を先立てて、その身を―・めて頸に懸けて歩きけり」
ほし‐がれい【乾鰈・干鰈】‥ガレヒ🔗⭐🔉
ほし‐がれい【乾鰈・干鰈】‥ガレヒ
はらわたを抜いてほした鰈。骨が透き通って見える。ひがれい。〈[季]春〉
○星が割れるほしがわれる
犯人が判明する。
⇒ほし【星】
ほし‐くさ【乾草・干草】🔗⭐🔉
ほし‐くさ【乾草・干草】
家畜の飼料として、夏の間に刈り、ほして貯蔵する草。ほしぐさ。〈[季]夏〉
ほし‐ぐり【乾栗・干栗】🔗⭐🔉
ほし‐ぐり【乾栗・干栗】
栗の実をゆで、ほし固めたもの。
ほし‐こ【乾海鼠・干海鼠】🔗⭐🔉
ほし‐こ【乾海鼠・干海鼠】
ナマコのはらわたを取り去り、茹ゆでてほしたもの。ほしなまこ。いりこ。
ほし‐ころ・す【乾し殺す・干し殺す】🔗⭐🔉
ほし‐ころ・す【乾し殺す・干し殺す】
〔他四〕
飢えさせて殺す。〈日葡辞書〉
ほし‐ざお【干し棹・干し竿】‥ザヲ🔗⭐🔉
ほし‐ざお【干し棹・干し竿】‥ザヲ
物を干すさお。物干しざお。
ほし‐じし【乾肉・干肉】🔗⭐🔉
ほし‐じし【乾肉・干肉】
ほした肉。ほしし。〈新撰字鏡1〉
ほし‐だいこん【乾大根・干大根】🔗⭐🔉
ほし‐だいこん【乾大根・干大根】
まるのままほした大根。〈[季]冬〉
ほし‐だら【乾鱈・干鱈】🔗⭐🔉
ほし‐だら【乾鱈・干鱈】
(→)「ひだら」に同じ。
ほし‐どり【乾鳥・干鳥】🔗⭐🔉
ほし‐どり【乾鳥・干鳥】
ほした鳥の肉。宇津保物語藤原君「雲雀の―」
ほし‐な【乾菜・干菜】🔗⭐🔉
ほし‐な【乾菜・干菜】
ほした菜。特に、大根の葉や蕪菜かぶらなを陰干しにしたもの。懸菜。〈[季]冬〉。西鶴織留5「―も細かに切つておいたり」
ほし‐なつめ【乾棗・干棗】🔗⭐🔉
ほし‐なつめ【乾棗・干棗】
なつめの実をほしかためた食品。
ほし‐なまこ【乾海鼠・干海鼠】🔗⭐🔉
ほし‐なまこ【乾海鼠・干海鼠】
(→)「ほしこ」に同じ。
ほし‐にく【乾肉・干肉】🔗⭐🔉
ほし‐にく【乾肉・干肉】
ほした肉。保存食品。
ほし‐のり【乾海苔・干海苔】🔗⭐🔉
ほし‐のり【乾海苔・干海苔】
うすく漉すいてかわかした海苔。〈[季]春〉
乾海苔
撮影:関戸 勇
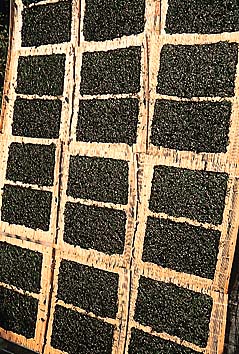
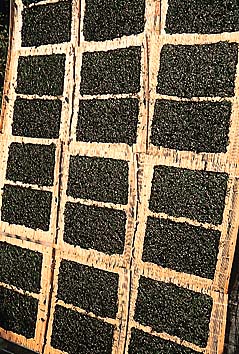
ほし‐ぶどう【乾葡萄・干葡萄】‥ダウ🔗⭐🔉
ほし‐ぶどう【乾葡萄・干葡萄】‥ダウ
ほした葡萄の実。
ほし‐みせ【乾店・干店・露肆】🔗⭐🔉
ほし‐みせ【乾店・干店・露肆】
道路の側に出す臨時のみせ。露店。大道みせ。守貞漫稿「京坂にて―といふ。江戸にて、てんたうぼしといふ。路上に筵敷き諸物を並べ商ふをいふ」
ほし‐もの【乾し物・干し物】🔗⭐🔉
ほし‐もの【乾し物・干し物】
日にほしてかわかすこと。また、そのもの。特に洗濯や染色の場合にいう。「―を取り込む」
ほし‐わらび【乾蕨・干蕨】🔗⭐🔉
ほし‐わらび【乾蕨・干蕨】
ほして貯蔵できるようにした蕨。〈[季]春〉
○星を挙げるほしをあげる
①犯罪容疑者や犯人を検挙する。
②相撲で、勝って白星を得る。
⇒ほし【星】
○星を戴くほしをいただく
朝早く星の見える頃から、または、夜暗くなるまで、出て働く。
⇒ほし【星】
○星を落とすほしをおとす
相撲で、勝負に負ける。「痛い―」
⇒ほし【星】
○星を稼ぐほしをかせぐ
点数をかせぐ。成績をあげる。
⇒ほし【星】
○星を食わすほしをくわす
図星を指す。見当があたる。傾城禁短気「返事はどうぢやと星をくはされ」
⇒ほし【星】
○星を指すほしをさす
言いあてる。図星を指す。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「さぞ本望でござらうのと星を指いたる大星が詞に本蔵目を見開き」
⇒ほし【星】
○星をつぶすほしをつぶす
(相撲の星取表を黒く塗りつぶすところから)勝負に負ける。
⇒ほし【星】
○星を列ぬほしをつらぬ
威儀を正して高い位の人の居並ぶさまをいう。
⇒ほし【星】
○星を唱うほしをとなう
元旦の四方拝に天皇がその年の属星ぞくしょうを唱える。
⇒ほし【星】
○星を拾うほしをひろう
ほとんど負けかけた相撲に勝つ。
⇒ほし【星】
ほ・す【乾す・干す】🔗⭐🔉
ほ・す【乾す・干す】
〔他五〕
①風や太陽に当てて水気を去る。かわかす。万葉集1「春過ぎて夏来たるらし白妙の衣―・したり天の香具山」。「洗濯物を―・す」
②涙をかわかす。源氏物語椎本「二所うち語らひつつ―・す世もなくて過ぐし給ふに年も暮れにけり」
③中にあるものをすっかりとり去る。飲みつくす。「池の水を―・す」「杯を―・す」
④飲食物をとらずに空からにする。また、食物をとらせずにおく。落窪物語2「只今は―・させまほしくぞある」。日葡辞書「ハラヲホス」「ノドヲホス」
⑤仕事などを与えないでおく。「役を―・される」
[漢]干🔗⭐🔉
干 字形
 筆順
筆順
 〔干部0画/3画/教育/2019・3433〕
〔音〕カン(呉)(漢)
〔訓〕ほす・ひる・おかす
[意味]
①かわく。かわかす。ほす。ひる。「干満・干潮・干拓・干瓢かんぴょう」▶「旱」(=ひでり)の現代表記としても用いる。「干天・干魃かんばつ・干害」
②自分からはたらきかけて、それにかかわる。おかす。「干渉・干与・干犯」
③相手に何かを求める。「干禄かんろく」
④武器の、盾たて。「干戈かんか・干城」
⑤みき。(同)幹。「十干・干支」
[解字]
解字
〔干部0画/3画/教育/2019・3433〕
〔音〕カン(呉)(漢)
〔訓〕ほす・ひる・おかす
[意味]
①かわく。かわかす。ほす。ひる。「干満・干潮・干拓・干瓢かんぴょう」▶「旱」(=ひでり)の現代表記としても用いる。「干天・干魃かんばつ・干害」
②自分からはたらきかけて、それにかかわる。おかす。「干渉・干与・干犯」
③相手に何かを求める。「干禄かんろく」
④武器の、盾たて。「干戈かんか・干城」
⑤みき。(同)幹。「十干・干支」
[解字]
解字 先がふたまたの棒を描いた象形文字で、人を突いたり身を守ったりする武器すなわち④の意を表し、転じて、②③の意となる。①は仮借。現代中国語では「乾」「幹」の簡体字。
[下ツキ
十干・若干・水干・欄干・闌干・射干しゃが
[難読]
干支えと・干潟ひがた
先がふたまたの棒を描いた象形文字で、人を突いたり身を守ったりする武器すなわち④の意を表し、転じて、②③の意となる。①は仮借。現代中国語では「乾」「幹」の簡体字。
[下ツキ
十干・若干・水干・欄干・闌干・射干しゃが
[難読]
干支えと・干潟ひがた
 筆順
筆順
 〔干部0画/3画/教育/2019・3433〕
〔音〕カン(呉)(漢)
〔訓〕ほす・ひる・おかす
[意味]
①かわく。かわかす。ほす。ひる。「干満・干潮・干拓・干瓢かんぴょう」▶「旱」(=ひでり)の現代表記としても用いる。「干天・干魃かんばつ・干害」
②自分からはたらきかけて、それにかかわる。おかす。「干渉・干与・干犯」
③相手に何かを求める。「干禄かんろく」
④武器の、盾たて。「干戈かんか・干城」
⑤みき。(同)幹。「十干・干支」
[解字]
解字
〔干部0画/3画/教育/2019・3433〕
〔音〕カン(呉)(漢)
〔訓〕ほす・ひる・おかす
[意味]
①かわく。かわかす。ほす。ひる。「干満・干潮・干拓・干瓢かんぴょう」▶「旱」(=ひでり)の現代表記としても用いる。「干天・干魃かんばつ・干害」
②自分からはたらきかけて、それにかかわる。おかす。「干渉・干与・干犯」
③相手に何かを求める。「干禄かんろく」
④武器の、盾たて。「干戈かんか・干城」
⑤みき。(同)幹。「十干・干支」
[解字]
解字 先がふたまたの棒を描いた象形文字で、人を突いたり身を守ったりする武器すなわち④の意を表し、転じて、②③の意となる。①は仮借。現代中国語では「乾」「幹」の簡体字。
[下ツキ
十干・若干・水干・欄干・闌干・射干しゃが
[難読]
干支えと・干潟ひがた
先がふたまたの棒を描いた象形文字で、人を突いたり身を守ったりする武器すなわち④の意を表し、転じて、②③の意となる。①は仮借。現代中国語では「乾」「幹」の簡体字。
[下ツキ
十干・若干・水干・欄干・闌干・射干しゃが
[難読]
干支えと・干潟ひがた
広辞苑に「干」で始まるの検索結果 1-89。もっと読み込む