複数辞典一括検索+![]()
![]()
【著聞】🔗⭐🔉
【著聞】
チョブン・チョモン 世の中によく知られていること。
【著積】🔗⭐🔉
【著積】
チョセキ たくわえ。〈同義語〉貯積。
【著録】🔗⭐🔉
【著録】
チョロク  名前などを名簿に記載する。
名前などを名簿に記載する。 でしのこと。門人。▽名簿に名前を記載された人の意。
でしのこと。門人。▽名簿に名前を記載された人の意。 「著作」と同じ。
「著作」と同じ。
 名前などを名簿に記載する。
名前などを名簿に記載する。 でしのこと。門人。▽名簿に名前を記載された人の意。
でしのこと。門人。▽名簿に名前を記載された人の意。 「著作」と同じ。
「著作」と同じ。
【荻】🔗⭐🔉
【荻洲】🔗⭐🔉
【荻洲】
テキシュウ おぎの生えている川のす。
【荻浦】🔗⭐🔉
【荻浦】
テキホ おぎの生えている水辺。
【荻生徂徠】🔗⭐🔉
【荻生徂徠】
オギュウソライ〔日〕〈人名〉1666〜1728 江戸時代中期の儒学者。名は双松ナベマツ、字アザナは茂卿モケイ、号は徂徠のほかに・赤城翁など。別に物徂徠ブツソライとも称した。郡山コオリヤマの柳沢侯に仕えた。はじめ朱子学を学び、のち、古文辞学をおさめ、先学の説をはげしく批判した。著に『弁道』『弁名』『論語徴』などがある。
【荼】🔗⭐🔉
【荼】
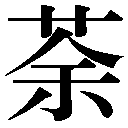 10画 艸部
区点=7224 16進=6838 シフトJIS=E4B6
《音読み》
10画 艸部
区点=7224 16進=6838 シフトJIS=E4B6
《音読み》  ト
ト /ド
/ド 〈t
〈t 〉/
〉/ ダ
ダ /ジャ(ヂャ)
/ジャ(ヂャ) /タ
/タ 《訓読み》 にがな
《意味》
《訓読み》 にがな
《意味》

 {名}にがな。草の名。茎が中空で、にがい汁がある。花は黄色で菊に似て、晩春から初夏にかけて咲く。のげし。
{名}にがな。草の名。茎が中空で、にがい汁がある。花は黄色で菊に似て、晩春から初夏にかけて咲く。のげし。
 {名}ちがやの穂。つばな。
{名}ちがやの穂。つばな。
 {名}荻オギの穂。
{名}荻オギの穂。
 {名}あれくさ。雑草。
{名}あれくさ。雑草。
 {名}にがい思い。つらさ。苦しみ。
{名}にがい思い。つらさ。苦しみ。
 {名}芽をはやくつんだ茶。また、茶の木。▽おそくとったものを茗メイという。〈同義語〉→茶。
《解字》
会意兼形声。「艸+音符余(のびる、ゆるやかにする)」。からだのしこりをのばす薬効のある植物のこと。のち、一画をはぶいて茶と書き、荼(にがな)と区別するようになった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}芽をはやくつんだ茶。また、茶の木。▽おそくとったものを茗メイという。〈同義語〉→茶。
《解字》
会意兼形声。「艸+音符余(のびる、ゆるやかにする)」。からだのしこりをのばす薬効のある植物のこと。のち、一画をはぶいて茶と書き、荼(にがな)と区別するようになった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
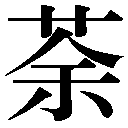 10画 艸部
区点=7224 16進=6838 シフトJIS=E4B6
《音読み》
10画 艸部
区点=7224 16進=6838 シフトJIS=E4B6
《音読み》  ト
ト /ド
/ド 〈t
〈t 〉/
〉/ ダ
ダ /ジャ(ヂャ)
/ジャ(ヂャ) /タ
/タ 《訓読み》 にがな
《意味》
《訓読み》 にがな
《意味》

 {名}にがな。草の名。茎が中空で、にがい汁がある。花は黄色で菊に似て、晩春から初夏にかけて咲く。のげし。
{名}にがな。草の名。茎が中空で、にがい汁がある。花は黄色で菊に似て、晩春から初夏にかけて咲く。のげし。
 {名}ちがやの穂。つばな。
{名}ちがやの穂。つばな。
 {名}荻オギの穂。
{名}荻オギの穂。
 {名}あれくさ。雑草。
{名}あれくさ。雑草。
 {名}にがい思い。つらさ。苦しみ。
{名}にがい思い。つらさ。苦しみ。
 {名}芽をはやくつんだ茶。また、茶の木。▽おそくとったものを茗メイという。〈同義語〉→茶。
《解字》
会意兼形声。「艸+音符余(のびる、ゆるやかにする)」。からだのしこりをのばす薬効のある植物のこと。のち、一画をはぶいて茶と書き、荼(にがな)と区別するようになった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}芽をはやくつんだ茶。また、茶の木。▽おそくとったものを茗メイという。〈同義語〉→茶。
《解字》
会意兼形声。「艸+音符余(のびる、ゆるやかにする)」。からだのしこりをのばす薬効のある植物のこと。のち、一画をはぶいて茶と書き、荼(にがな)と区別するようになった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源 ページ 3780。
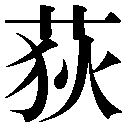 10画 艸部
区点=1814 16進=322E シフトJIS=89AC
《音読み》 テキ
10画 艸部
区点=1814 16進=322E シフトJIS=89AC
《音読み》 テキ 〉
《訓読み》 おぎ(をぎ)
《意味》
{名}おぎ(ヲギ)。草の名。水辺・湿地に自生する。葦アシに似ている。
《解字》
会意兼形声。「艸+音符狄テキ(低くかりたおす、低くふせる)」。
《熟語》
〉
《訓読み》 おぎ(をぎ)
《意味》
{名}おぎ(ヲギ)。草の名。水辺・湿地に自生する。葦アシに似ている。
《解字》
会意兼形声。「艸+音符狄テキ(低くかりたおす、低くふせる)」。
《熟語》