複数辞典一括検索+![]()
![]()
【負薪】🔗⭐🔉
【負薪】
フシン  シンヲオウ薪を背負う。生活のための雑用や、力仕事をすること。
シンヲオウ薪を背負う。生活のための雑用や、力仕事をすること。 身分の低い卑しい人。
身分の低い卑しい人。
 シンヲオウ薪を背負う。生活のための雑用や、力仕事をすること。
シンヲオウ薪を背負う。生活のための雑用や、力仕事をすること。 身分の低い卑しい人。
身分の低い卑しい人。
【負羈】🔗⭐🔉
【負羈】
フキ〈人名〉春秋時代、曹ソウの大夫。姓は僖キ。晋シンの重耳チョウジ(後の文公)が曹を通ったとき、料理の中に璧タマを入れて贈り、誼ヨシみを通じた。
【貢】🔗⭐🔉
【貢】
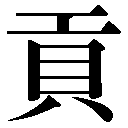 10画 貝部 [常用漢字]
区点=2555 16進=3957 シフトJIS=8D76
《常用音訓》ク/コウ/みつ…ぐ
《音読み》 コウ
10画 貝部 [常用漢字]
区点=2555 16進=3957 シフトJIS=8D76
《常用音訓》ク/コウ/みつ…ぐ
《音読み》 コウ /ク
/ク 〈g
〈g ng〉
《訓読み》 みつぐ/みつぎもの
《名付け》 すすむ・つぐ・みつ・みつぎ・みつぐ
《意味》
ng〉
《訓読み》 みつぐ/みつぎもの
《名付け》 すすむ・つぐ・みつ・みつぎ・みつぐ
《意味》
 コウス{動・名}みつぐ。みつぎもの。朝廷に地方の産物をたてまつる。また、その産物。「朝貢」「諸侯春不貢=諸侯春ニ貢セズ」〔→杜甫〕
コウス{動・名}みつぐ。みつぎもの。朝廷に地方の産物をたてまつる。また、その産物。「朝貢」「諸侯春不貢=諸侯春ニ貢セズ」〔→杜甫〕
 コウス{動}すぐれた人材を朝廷に推薦する。「貢挙」「貢薦」
《解字》
会意兼形声。工コウは、上下の二線の間を縦の棒でつきぬいた姿を示す指事文字で、つらぬいて直通する意味をふくむ。貢は「貝+音符工」で、地方でとれた物産をかついで朝廷におさめること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
コウス{動}すぐれた人材を朝廷に推薦する。「貢挙」「貢薦」
《解字》
会意兼形声。工コウは、上下の二線の間を縦の棒でつきぬいた姿を示す指事文字で、つらぬいて直通する意味をふくむ。貢は「貝+音符工」で、地方でとれた物産をかついで朝廷におさめること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
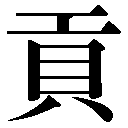 10画 貝部 [常用漢字]
区点=2555 16進=3957 シフトJIS=8D76
《常用音訓》ク/コウ/みつ…ぐ
《音読み》 コウ
10画 貝部 [常用漢字]
区点=2555 16進=3957 シフトJIS=8D76
《常用音訓》ク/コウ/みつ…ぐ
《音読み》 コウ /ク
/ク 〈g
〈g ng〉
《訓読み》 みつぐ/みつぎもの
《名付け》 すすむ・つぐ・みつ・みつぎ・みつぐ
《意味》
ng〉
《訓読み》 みつぐ/みつぎもの
《名付け》 すすむ・つぐ・みつ・みつぎ・みつぐ
《意味》
 コウス{動・名}みつぐ。みつぎもの。朝廷に地方の産物をたてまつる。また、その産物。「朝貢」「諸侯春不貢=諸侯春ニ貢セズ」〔→杜甫〕
コウス{動・名}みつぐ。みつぎもの。朝廷に地方の産物をたてまつる。また、その産物。「朝貢」「諸侯春不貢=諸侯春ニ貢セズ」〔→杜甫〕
 コウス{動}すぐれた人材を朝廷に推薦する。「貢挙」「貢薦」
《解字》
会意兼形声。工コウは、上下の二線の間を縦の棒でつきぬいた姿を示す指事文字で、つらぬいて直通する意味をふくむ。貢は「貝+音符工」で、地方でとれた物産をかついで朝廷におさめること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
コウス{動}すぐれた人材を朝廷に推薦する。「貢挙」「貢薦」
《解字》
会意兼形声。工コウは、上下の二線の間を縦の棒でつきぬいた姿を示す指事文字で、つらぬいて直通する意味をふくむ。貢は「貝+音符工」で、地方でとれた物産をかついで朝廷におさめること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
【貢士】🔗⭐🔉
【貢士】
コウシ  地方の長官が才能・学識のある人物を官吏として中央政府に推薦すること。また、推薦された人。貢挙の士。
地方の長官が才能・学識のある人物を官吏として中央政府に推薦すること。また、推薦された人。貢挙の士。 科挙(官吏登用試験)の会試に合格した者。
科挙(官吏登用試験)の会試に合格した者。 〔国〕明治維新のとき、藩主から選抜されて公議所に出仕した武士。
〔国〕明治維新のとき、藩主から選抜されて公議所に出仕した武士。
 地方の長官が才能・学識のある人物を官吏として中央政府に推薦すること。また、推薦された人。貢挙の士。
地方の長官が才能・学識のある人物を官吏として中央政府に推薦すること。また、推薦された人。貢挙の士。 科挙(官吏登用試験)の会試に合格した者。
科挙(官吏登用試験)の会試に合格した者。 〔国〕明治維新のとき、藩主から選抜されて公議所に出仕した武士。
〔国〕明治維新のとき、藩主から選抜されて公議所に出仕した武士。
【貢生】🔗⭐🔉
【貢生】
コウセイ 明ミン・清シン代、府県の長官から中央の太学に推挙された、地方の学校の学生のこと。
漢字源 ページ 4218。