複数辞典一括検索+![]()
![]()
【阮籍】🔗⭐🔉
【阮集之】🔗⭐🔉
【阮集之】
ゲンシュウシ・ゲンダイセイ〈人名〉大[セイ]は本名。?〜1641 明ミン末の文人。懐寧(安徽アンキ省)の人。集之シュウシは字アザナ、号は円海・百子山樵ヒャクシサンショウ。戯曲に巧みで、『燕子箋エンシセン』『春灯謎』などがある。
【防】🔗⭐🔉
【防】
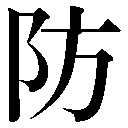 7画 阜部 [五年]
区点=4341 16進=4B49 シフトJIS=9668
《常用音訓》ボウ/ふせ…ぐ
《音読み》 ボウ(バウ)
7画 阜部 [五年]
区点=4341 16進=4B49 シフトJIS=9668
《常用音訓》ボウ/ふせ…ぐ
《音読み》 ボウ(バウ) /ホウ(ハウ)
/ホウ(ハウ) 〈f
〈f ng〉
《訓読み》 ふせぐ/ふせぎ/つつみ
《名付け》 ふせ
《意味》
ng〉
《訓読み》 ふせぐ/ふせぎ/つつみ
《名付け》 ふせ
《意味》
 {動}ふせぐ。中心から両方にはり出して、来るものをおさえふせぐ。〈類義語〉→妨・→禦ギヨ・→拒。「予防」「防之未然=コレヲ未然ニ防グ」「防其邪物=ソノ邪物ヲ防グ」〔→礼記〕
{動}ふせぐ。中心から両方にはり出して、来るものをおさえふせぐ。〈類義語〉→妨・→禦ギヨ・→拒。「予防」「防之未然=コレヲ未然ニ防グ」「防其邪物=ソノ邪物ヲ防グ」〔→礼記〕
 {名}ふせぎ。侵入や破壊をふせぐ備え。「辺防(国境の備え)」「河防策(黄河のはんらんをふせぐ策)」
{名}ふせぎ。侵入や破壊をふせぐ備え。「辺防(国境の備え)」「河防策(黄河のはんらんをふせぐ策)」
 {動・名}くらべる。ならぶ。匹敵するもの。「維此仲行、百夫之防=コレ此ノ仲行ハ、百夫ノ防」〔→詩経〕
{動・名}くらべる。ならぶ。匹敵するもの。「維此仲行、百夫之防=コレ此ノ仲行ハ、百夫ノ防」〔→詩経〕
 {名}つつみ。左右に長くはり出して、水流をおさえるつつみ。〈類義語〉→堤。「堤防」「防有鵲巣=防ニハ鵲ノ巣有リ」〔→詩経〕
{名}つつみ。左右に長くはり出して、水流をおさえるつつみ。〈類義語〉→堤。「堤防」「防有鵲巣=防ニハ鵲ノ巣有リ」〔→詩経〕
 {名}左右にはり出したついてたてや、へい。〈類義語〉→屏ヘイ。
《解字》
会意兼形声。方は、左右に柄のはり出たすきを描いた象形文字。防は「阜(積んだ土)+音符方」で、中心点から左右に土を長くつみ固めて、水流をおさえる堤防のこと。→方
《単語家族》
方向の方(左右にはり出す)
{名}左右にはり出したついてたてや、へい。〈類義語〉→屏ヘイ。
《解字》
会意兼形声。方は、左右に柄のはり出たすきを描いた象形文字。防は「阜(積んだ土)+音符方」で、中心点から左右に土を長くつみ固めて、水流をおさえる堤防のこと。→方
《単語家族》
方向の方(左右にはり出す) 妨ボウ(左右に手をはり出して通さない)
妨ボウ(左右に手をはり出して通さない) 房ボウ(母屋の左右にはり出たわき屋)
房ボウ(母屋の左右にはり出たわき屋) 坊(本堂の左右に出た土べいや小室)などと同系。
《類義》
禦ギョは、×型のバリケードでふせぐこと。拒キョは、間をあけて近よせないこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
坊(本堂の左右に出た土べいや小室)などと同系。
《類義》
禦ギョは、×型のバリケードでふせぐこと。拒キョは、間をあけて近よせないこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
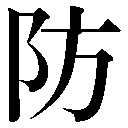 7画 阜部 [五年]
区点=4341 16進=4B49 シフトJIS=9668
《常用音訓》ボウ/ふせ…ぐ
《音読み》 ボウ(バウ)
7画 阜部 [五年]
区点=4341 16進=4B49 シフトJIS=9668
《常用音訓》ボウ/ふせ…ぐ
《音読み》 ボウ(バウ) /ホウ(ハウ)
/ホウ(ハウ) 〈f
〈f ng〉
《訓読み》 ふせぐ/ふせぎ/つつみ
《名付け》 ふせ
《意味》
ng〉
《訓読み》 ふせぐ/ふせぎ/つつみ
《名付け》 ふせ
《意味》
 {動}ふせぐ。中心から両方にはり出して、来るものをおさえふせぐ。〈類義語〉→妨・→禦ギヨ・→拒。「予防」「防之未然=コレヲ未然ニ防グ」「防其邪物=ソノ邪物ヲ防グ」〔→礼記〕
{動}ふせぐ。中心から両方にはり出して、来るものをおさえふせぐ。〈類義語〉→妨・→禦ギヨ・→拒。「予防」「防之未然=コレヲ未然ニ防グ」「防其邪物=ソノ邪物ヲ防グ」〔→礼記〕
 {名}ふせぎ。侵入や破壊をふせぐ備え。「辺防(国境の備え)」「河防策(黄河のはんらんをふせぐ策)」
{名}ふせぎ。侵入や破壊をふせぐ備え。「辺防(国境の備え)」「河防策(黄河のはんらんをふせぐ策)」
 {動・名}くらべる。ならぶ。匹敵するもの。「維此仲行、百夫之防=コレ此ノ仲行ハ、百夫ノ防」〔→詩経〕
{動・名}くらべる。ならぶ。匹敵するもの。「維此仲行、百夫之防=コレ此ノ仲行ハ、百夫ノ防」〔→詩経〕
 {名}つつみ。左右に長くはり出して、水流をおさえるつつみ。〈類義語〉→堤。「堤防」「防有鵲巣=防ニハ鵲ノ巣有リ」〔→詩経〕
{名}つつみ。左右に長くはり出して、水流をおさえるつつみ。〈類義語〉→堤。「堤防」「防有鵲巣=防ニハ鵲ノ巣有リ」〔→詩経〕
 {名}左右にはり出したついてたてや、へい。〈類義語〉→屏ヘイ。
《解字》
会意兼形声。方は、左右に柄のはり出たすきを描いた象形文字。防は「阜(積んだ土)+音符方」で、中心点から左右に土を長くつみ固めて、水流をおさえる堤防のこと。→方
《単語家族》
方向の方(左右にはり出す)
{名}左右にはり出したついてたてや、へい。〈類義語〉→屏ヘイ。
《解字》
会意兼形声。方は、左右に柄のはり出たすきを描いた象形文字。防は「阜(積んだ土)+音符方」で、中心点から左右に土を長くつみ固めて、水流をおさえる堤防のこと。→方
《単語家族》
方向の方(左右にはり出す) 妨ボウ(左右に手をはり出して通さない)
妨ボウ(左右に手をはり出して通さない) 房ボウ(母屋の左右にはり出たわき屋)
房ボウ(母屋の左右にはり出たわき屋) 坊(本堂の左右に出た土べいや小室)などと同系。
《類義》
禦ギョは、×型のバリケードでふせぐこと。拒キョは、間をあけて近よせないこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
坊(本堂の左右に出た土べいや小室)などと同系。
《類義》
禦ギョは、×型のバリケードでふせぐこと。拒キョは、間をあけて近よせないこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源 ページ 4724。