複数辞典一括検索+![]()
![]()
【陶弘景】🔗⭐🔉
【陶弘景】
トウコウケイ〈人名〉456〜536 南北朝時代、梁リョウの学者。秣陵マツリョウ(江蘇コウソ省南京ナンキン市)の人。字アザナは通明。神仙シンセン・陰陽・五行・医術などに詳しく、山中に隠棲インセイしていたが、梁の武帝に信任されて常にその諮問をうけていた。
【陶潜】🔗⭐🔉
【陶潜】
トウセン〈人名〉365?〜427 東晋トウシン末の詩人。潯陽ジンヨウ(江西省九江市)の人。曾祖父ソウソフは陶侃トウカン。字アザナは淵明エンメイ、一説では元亮ゲンリョウともいわれる。人から靖節セイセツ先生・陶靖節と呼ばれ、五柳先生とも称した。彭沢ホウタクの県知事となったが、八〇日でやめ、「帰去来辞」をつくって、帰郷した。以後は、自然と酒を愛し、田園生活をおくった。その詩風は人間味があって枯淡で、唐代の多くの詩人に大きな影響を与えた。→「漉酒巾ロクシュキン」
【陶宗儀】🔗⭐🔉
【陶宗儀】
トウソウギ〈人名〉?〜1369 明ミン代の学者。黄岩(浙江セッコウ省)の人。字アザナは九成。農耕生活をおくり、木のかげで休みながら、考えたことを木の葉にかきつけ、後にこれを集めて『輟耕テッコウ録』を著した。また、彼が編集した『説郛セップ』は、古い雑記や小説の叢書ソウショとして有名。
【陪】🔗⭐🔉
【陪】
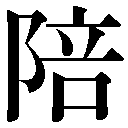 11画 阜部 [常用漢字]
区点=3970 16進=4766 シフトJIS=9486
《常用音訓》バイ
《音読み》 バイ
11画 阜部 [常用漢字]
区点=3970 16進=4766 シフトJIS=9486
《常用音訓》バイ
《音読み》 バイ /ハイ
/ハイ /ベ
/ベ 〈p
〈p i〉
《訓読み》 そう(そふ)/そえる(そふ)
《名付け》 すけ・ます
《意味》
i〉
《訓読み》 そう(そふ)/そえる(そふ)
《名付け》 すけ・ます
《意味》
 バイス{動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。根元にそえ土をする。そばに並んで供をする。つきそう。〈類義語〉→伴・→副。「陪席」「奉陪(おそばにおともする)」
バイス{動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。根元にそえ土をする。そばに並んで供をする。つきそう。〈類義語〉→伴・→副。「陪席」「奉陪(おそばにおともする)」
 {名}つきそいの人。お供。「陪弐バイジ」
{名}つきそいの人。お供。「陪弐バイジ」
 {名}正に対して副となるもの。予備のもの。〈類義語〉→副。「陪臣」
{名}正に対して副となるもの。予備のもの。〈類義語〉→副。「陪臣」
 バイス{動}ひきあてて支払う。代償とする。賠償する。〈同義語〉→賠。〈類義語〉→償。「鬻女陪男償税銭=女ヲ鬻リ男ヲ陪シテ税銭ヲ償フ」〔→袁宏道〕
《解字》
形声。右側の字が音をあらわす。
《単語家族》
倍(二つに割ってそばにそえる)
バイス{動}ひきあてて支払う。代償とする。賠償する。〈同義語〉→賠。〈類義語〉→償。「鬻女陪男償税銭=女ヲ鬻リ男ヲ陪シテ税銭ヲ償フ」〔→袁宏道〕
《解字》
形声。右側の字が音をあらわす。
《単語家族》
倍(二つに割ってそばにそえる) 培バイ(土を根にそえる)
培バイ(土を根にそえる) 伏(ぴったりとつき従う)
伏(ぴったりとつき従う) 副(そばにそえる)と同系。
《熟語》
→熟語
副(そばにそえる)と同系。
《熟語》
→熟語
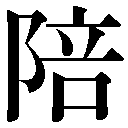 11画 阜部 [常用漢字]
区点=3970 16進=4766 シフトJIS=9486
《常用音訓》バイ
《音読み》 バイ
11画 阜部 [常用漢字]
区点=3970 16進=4766 シフトJIS=9486
《常用音訓》バイ
《音読み》 バイ /ハイ
/ハイ /ベ
/ベ 〈p
〈p i〉
《訓読み》 そう(そふ)/そえる(そふ)
《名付け》 すけ・ます
《意味》
i〉
《訓読み》 そう(そふ)/そえる(そふ)
《名付け》 すけ・ます
《意味》
 バイス{動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。根元にそえ土をする。そばに並んで供をする。つきそう。〈類義語〉→伴・→副。「陪席」「奉陪(おそばにおともする)」
バイス{動}そう(ソフ)。そえる(ソフ)。根元にそえ土をする。そばに並んで供をする。つきそう。〈類義語〉→伴・→副。「陪席」「奉陪(おそばにおともする)」
 {名}つきそいの人。お供。「陪弐バイジ」
{名}つきそいの人。お供。「陪弐バイジ」
 {名}正に対して副となるもの。予備のもの。〈類義語〉→副。「陪臣」
{名}正に対して副となるもの。予備のもの。〈類義語〉→副。「陪臣」
 バイス{動}ひきあてて支払う。代償とする。賠償する。〈同義語〉→賠。〈類義語〉→償。「鬻女陪男償税銭=女ヲ鬻リ男ヲ陪シテ税銭ヲ償フ」〔→袁宏道〕
《解字》
形声。右側の字が音をあらわす。
《単語家族》
倍(二つに割ってそばにそえる)
バイス{動}ひきあてて支払う。代償とする。賠償する。〈同義語〉→賠。〈類義語〉→償。「鬻女陪男償税銭=女ヲ鬻リ男ヲ陪シテ税銭ヲ償フ」〔→袁宏道〕
《解字》
形声。右側の字が音をあらわす。
《単語家族》
倍(二つに割ってそばにそえる) 培バイ(土を根にそえる)
培バイ(土を根にそえる) 伏(ぴったりとつき従う)
伏(ぴったりとつき従う) 副(そばにそえる)と同系。
《熟語》
→熟語
副(そばにそえる)と同系。
《熟語》
→熟語
漢字源 ページ 4763。