複数辞典一括検索+![]()
![]()
ひ🔗⭐🔉
ひ
(1)五十音図ハ行第二段の仮名。硬口蓋摩擦音の無声子音と前舌の狭母音とから成る音節。
(2)平仮名「ひ」は「比」の草体。片仮名「ヒ」は「比」の旁(ツクリ)。
〔(1)「ひ」の頭子音は,古くは両唇摩擦音の無声子音であり,さらに奈良時代以前には両唇破裂音であったかといわれる。中世末期まで両唇摩擦音であったが,近世以降現代語と同じ音になった。(2)「ひ」は,平安時代半ば以降,語中語尾では,一般に「ゐ」「い」と同じ音になった。これらは,歴史的仮名遣いでは「ひ」と書くが,現代仮名遣いではすべて「い」と書く。(3)奈良時代までは,上代特殊仮名遣いで甲乙二類の別があり,発音上区別があったとされる〕
ひ【一】🔗⭐🔉
ひ [1] 【一】
いち。ひとつ。物を数えるときに用いる。「―,ふ,み」
ひ【日】🔗⭐🔉
ひ [0] 【日】
(1)太陽。おひさま。「―が出る」「―が昇る」「―が落ちる」
(2)太陽の出ている間。朝から夕方まで。ひるま。「―が長くなる」「―が暮れる」
(3)太陽の光や熱。日光。「冬になって―が弱くなる」「―がさす」
〔(1)〜(3)は「陽」とも書く〕
(4) [1]
地球が太陽に対して一回自転する間。一日。一昼夜。「―に五時間しか眠らない」「―に三度の食事」
(5)日かず。日数(ニツスウ)。「―が経つ」
(6)定めた日時。日限(ニチゲン)。「出発の―がせまる」「約束の―までに必ず返す」
(7)毎日毎日。日日(ヒビ)。「悲しみの―を送る」
(8)天気の具合。日より。「うららかな,よい―にめぐまれる」
(9)(「…した日には」の形で)…した場合には。…した折は。多くよくない事柄についていう。「手順を間違えた―には大変なことになる」
(10)(「…ときた日には」の形で)…の場合には。「うちのおやじときた―には日曜日にはゴルフばかりしている」
(11)時代。ころ。「ありし―をしのぶ」「若かりし―のおもかげを残す」
(12)吉日・凶日などという,日がら。「―が悪い」
(13)家紋の一。日輪をかたどったもの。
(14)日の神,天照大神(アマテラスオオミカミ)の子孫である意から,皇室に関することに付けていう語。「―のみこ」
〔「…の日」などの場合,アクセントは [1]〕
ひ【火】🔗⭐🔉
ひ [1] 【火】
(1)物質が燃えるときに出す炎や熱。また,燃えたり熱せられて赤熱したもの。「紙に―をつける」「―に当たる」「食物に―を通す」「鍋を―にかける」
(2)炭火。「火鉢に―をつぐ」「―をおこす」
(3)火打ちの火。きりび。「―を打つ」
(4)火事。「―の用心」「―を出す」
(5)火のように光るもの。「蛍―」「鬼―」
(6)激しい感情。燃えさかる情熱。「胸の―が燃える」
(7)月経。
→灯(ヒ)
ひ【氷・冰】🔗⭐🔉
ひ 【氷・冰】
(1)こおり。「我が衣手に置く霜も―にさえ渡り/万葉 3281」
(2)雹(ヒヨウ)。「つぶてのやうなる―降り/宇津保(吹上・下)」
ひ【目翳】🔗⭐🔉
ひ 【目翳】
ひとみに翳(クモリ)ができて,物が見えなくなる病気。そこひ。[和名抄]
ひ【灯】🔗⭐🔉
ひ [1] 【灯】
〔「ひ(火)」と同源〕
ものを照らす光。ともしび。あかり。「町の―が見える」「―をともす」
ひ【杼・梭】🔗⭐🔉
ひ [1] 【杼・梭】
織機の部品の一。緯(ヨコ)糸を通す用具。かい。シャトル。
杼
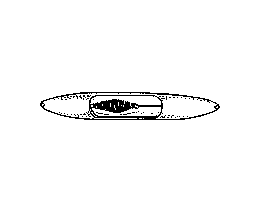 [図]
[図]
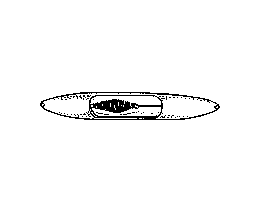 [図]
[図]
ひ【乾・干】🔗⭐🔉
ひ [1] 【乾・干】
〔動詞「ふ(干)」,または「ひる(干)」の連用形から〕
かわいていること。名詞の上に付いて複合語として用いられることが多い。「―のよい海苔(ノリ)」「―物」「―ざかな」
ひ【樋】🔗⭐🔉
ひ [1] 【樋】
(1)水を導き送る,木や竹の長い管。とい。
(2)物の表面につけた細長いみぞ。「―定規」
(3)日本刀の側面につけた細長いみぞ。血流し。
(4)せきとめた水の出口に設けた戸。開閉して水を出したりとめたりする。水門。
ひ【檜】🔗⭐🔉
ひ 【檜】
ヒノキの古名。「―のつまで/万葉 50」
ひ【 】🔗⭐🔉
】🔗⭐🔉
ひ [1] 【 】
鉱脈のこと。
】
鉱脈のこと。
 】
鉱脈のこと。
】
鉱脈のこと。
ひ【比】🔗⭐🔉
ひ [1] 【比】
(1)くらべてみて同等・同類であること。たぐい。「世界にその―を見ない」「彼の力量は私の―ではない」
(2)「詩経」の六義(リクギ)の一。漢詩の表現・修辞による分類の一。物事にたとえて意のあるところを表すもの。
(3)状態の変化に伴って量的変化が起こるとき,もとの量に対する変化後の量の割合,またはその逆数。
(4)〔数〕  ,
, を同種の量とするとき,
を同種の量とするとき, が
が  の何倍かあるいは何分のいくつかに当たるか,という関係を
の何倍かあるいは何分のいくつかに当たるか,という関係を  の
の  に対する比といい,
に対する比といい, :
:  と書く。
と書く。 /
/ をこの比の値という。
をこの比の値という。
 ,
, を同種の量とするとき,
を同種の量とするとき, が
が  の何倍かあるいは何分のいくつかに当たるか,という関係を
の何倍かあるいは何分のいくつかに当たるか,という関係を  の
の  に対する比といい,
に対する比といい, :
:  と書く。
と書く。 /
/ をこの比の値という。
をこの比の値という。
ひ【妃】🔗⭐🔉
ひ [1] 【妃】
天皇の後宮の一。皇后の次,夫人・嬪(ヒン)の上に位する。内親王を原則とする。明治以後では皇族の配偶者をいう。
ひ【非】🔗⭐🔉
ひ 【非】
■一■ [1] (名)
(1)道理に合わないこと。不正。
⇔是
「―をあばく」「―とする」
(2)不利であること。うまくゆかないこと。「形勢―なり」
(3)あやまり。欠点。「―を認める」
(4)そしること。「―を唱える」
■二■ (接頭)
漢語の名詞・形容動詞に付いて,それに当たらない,それ以外である,などの意を表す。「―能率的」「―常識」「―公式」
ひ【 】🔗⭐🔉
】🔗⭐🔉
ひ [1] 【 】
古代中国で,五刑の一。膝蓋骨(シツガイコツ)を切り去るもの。あしきりの刑。
】
古代中国で,五刑の一。膝蓋骨(シツガイコツ)を切り去るもの。あしきりの刑。
 】
古代中国で,五刑の一。膝蓋骨(シツガイコツ)を切り去るもの。あしきりの刑。
】
古代中国で,五刑の一。膝蓋骨(シツガイコツ)を切り去るもの。あしきりの刑。
ひ【秘】🔗⭐🔉
ひ [1] 【秘】
(1)隠して,人に知らせないこと。「秘中の―」「部外―」
(2)はかりしれない奥深いところ。奥義。
ひ【婢】🔗⭐🔉
ひ [1] 【婢】
(1)召し使いの女。はしため。下女。
(2)女の奴隷。
ひ【碑】🔗⭐🔉
ひ [0] 【碑】
事のいわれ,人の功績など,後世に伝えるべきことを石にきざんで,関係の深い地に建てたもの。いしぶみ。
ひ【緋】🔗⭐🔉
ひ [0] 【緋】
濃く明るい赤色。深紅色。「―の衣」
ひ🔗⭐🔉
ひ (接頭)
形容詞に付いて,いかにもそういう感じがするという意を表す。「―弱い」
ひ【曾】🔗⭐🔉
ひ 【曾】 (接頭)
血縁関係を示す語に付いて,祖父母の親または孫の子というように,三代離れた関係にあることを表す。ひい。「―じじ」「―孫」
ひ【被】🔗⭐🔉
ひ 【被】 (接頭)
行為を表す漢語に付いて,他からその行為をされる,他からその行為をこうむる,などの意を表す。「―選挙権」「―修飾語」「―支配者」
ひ【日】(和英)🔗⭐🔉
ひ【火】(和英)🔗⭐🔉
ひ【火】
(1) fire;→英和
a spark (火花);→英和
a flame (炎).→英和
(2) ⇒火事.
〜がつく catch[take]fire.〜に当たる warm oneself at the fire.〜にかける putover the fire.〜をおこす make a fire.〜を消す put out a fire.〜をつける set fire;light (点火).→英和
〜を見るより明らか as clear[plain]as day.‖火の用心precautions against fire.
ひ【比】(和英)🔗⭐🔉
ひ【非】(和英)🔗⭐🔉
ひ【緋(の)】(和英)🔗⭐🔉
ひ【緋(の)】
scarlet.→英和
ひ【灯】(和英)🔗⭐🔉
ひ【灯】
a light.→英和
〜をつける(消す) light (put out);turn[switch]on (off) a light (電灯).
大辞林に「ひ」で完全一致するの検索結果 1-33。