複数辞典一括検索+![]()
![]()
くち【口】🔗⭐🔉
くち 【口】
■一■ [0] (名)
(1)動物が飲食物をとり入れる器官。高等動物では頭部の下方にあって,唇・歯・舌があり,下あごによって開閉する。音声や鳴き声を発する器官ともなり,鳥類では嘴(クチバシ)となる。「―でくわえる」
(2)話すこと。声を出してものを言うこと。(ア)話す時に使うものとしての口。「―を開けば嫁の悪口ばかり」「―をつぐむ」(イ)話す動作。声に出すこと。また,その言葉。「―で言うほど簡単ではない」「―に出す」「―ほどでもない」(ウ)(文章などによらず)直接話すこと。口頭。「―で伝える」(エ)うわさ。評判。風説。「世間の―を気にする」(オ)話し方。話し方のよしあしや多寡(タカ)。「―が悪い」「―が達者だ」(カ)呼び出し。誘い。「―がかかる」
(3)飲食すること。(ア)飲食する時に使うものとしての口。「―をつける」(イ)飲食物を味わうものとしての口。また,味覚。「―に合う」「―あたり」(ウ)生活のために必要な量の食事をとるものとしての口。また,食事をする人数。「―が干上がる」「―を減らす」「一人―(ヒトリグチ)」(エ)飲食する動作。飲み食いすること。「酒は―にしない」
(4)通り抜けることができる空間。複合語としても用いる(この場合,多く「ぐち」となる)。(ア)穴やすき間。「傷の―」「船腹に―があく」(イ)ものを出し入れする所。また,そこをふさぐもの。「瓶の―」「―がかたくて抜けない」(ウ)人の出入りする所。戸口。「―が狭い」「登山―(トザングチ)」「非常―(ヒジヨウグチ)」
(5)〔(1)が体内への入り口であることから〕
物事の初め。最初。「序の―」「宵の―」
(6)物事を分類するときの,その一つ一つの類。種類の一。「飲める―」「そっちの―がだめなら,別の―に当たってみよう」
(7)はいっておさまる所。「嫁の―をさがす」「就職―(シユウシヨクグチ)」
(8)馬の口につける縄。「馬の―をとる」
■二■ (接尾)
助数詞。
(1)口に飲食物を入れる回数を数えるのに用いる。「一―で食べる」
(2)刀剣などを数えるのに用いる。「太刀一―」
(3)多くの人から金銭を集める時の,出してもらう単位を数えるのに用いる。「一―五千円で加入できる」
く-ち【駆馳】🔗⭐🔉
く-ち [1][2] 【駆馳】 (名)スル
(1)馬を走らせること。「老人の杖に依て歩行すると駿馬の―するとの如く/月世界旅行(勤)」
(2)人のために尽力し,奔走すること。
くち-あい【口合(い)】🔗⭐🔉
くち-あい ―アヒ [0] 【口合(い)】
(1)二人の話がよく合うこと。あいくち。「―がいい」
(2)口をきいて仲介・保証をすること。また,その人。仲人。保証人。「惣七殿には―家請も有る仁/浄瑠璃・博多小女郎(中)」
(3)〔上方語〕
語呂合わせ。江戸では「地口(ジグチ)」といった。「さまざまの―や地口を言つて/黄表紙・御存商売物」
→地口
くち-あけ【口開け・口明け】🔗⭐🔉
くち-あけ [0] 【口開け・口明け】
(1)閉じてある物の口をあけること。封を切ること。
(2)物事の初め。最初。かわきり。「興行の―の日」
(3)共有の山林や漁場の解禁。
(4)能の形式の一。狂言方の台詞で一曲を始めるもの。狂言口開け。
(5)上方の歌舞伎で,続き狂言の序幕の称。
くち-あ・し【口悪し】🔗⭐🔉
くち-あ・し 【口悪し】 (形シク)
(1)口がわるい。憎まれ口をきく。「―・しきをのこ/落窪 2」
(2)食欲がない。「或る尼の―・しとて物の食はれぬに/散木奇歌集」
くち-あそび【口遊び】🔗⭐🔉
くち-あそび 【口遊び】
(1)無意識に口ずさむこと。また,その言葉。くちずさび。「ただ仏の御ことのみを寝言にも―にもしつつ行ふ/宇津保(春日詣)」
(2)無駄口。うわさ。悪口。「かかる―は,さらにうけたまはらじ/宇津保(藤原君)」
くち-あたり【口当(た)り】🔗⭐🔉
くち-あたり [0] 【口当(た)り】
(1)食べ物や飲み物を口に入れたときの感じ。舌ざわり。「―のいいワイン」
(2)応対の折などに,人に与える感じ。人あたり。「―のいい人」
くち-あみ【口網】🔗⭐🔉
くち-あみ 【口網】
(1)籠(カゴ)などの出入り口を閉じる網。
(2)引き網の一種か。また,「朽ち網」の意とも,「くち」という魚を取る網の意ともいう。「―も諸持ちにて/土左」
くち-あらそい【口争い】🔗⭐🔉
くち-あらそい ―アラソヒ [3] 【口争い】 (名)スル
言い争うこと。口論。
くち・い🔗⭐🔉
くち・い [2][0] (形)
腹がいっぱいである。「腹が―・くなる」
くち-い・る【口入る】🔗⭐🔉
くち-い・る 【口入る】 (動ラ下二)
(1)口をさしはさむ。さしでがましい口をきく。「汝―・れずとも,わが財しあらばありなむ/宇津保(藤原君)」
(2)口をきいて世話をする。仲立ちをする。「大夫やがてはひのりて,しりにこのことに―・れたる人と,のせてやりつ/蜻蛉(下)」
くち-いれ【口入れ】🔗⭐🔉
くち-いれ [0][4] 【口入れ】 (名)スル
(1)奉公先・縁談などの周旋をすること。また,それを業とする人。
(2)口出しをすること。「いささか―を申たりけるを/十訓 1」
(3)江戸時代,金銭の斡旋をすること。また,それを業とする人。「我も人も請合,―をせりあひ/浮世草子・桜陰比事 5」
くちいれ-にん【口入れ人】🔗⭐🔉
くちいれ-にん [0] 【口入れ人】
(1)仲介をする人。
(2)雇い人などを周旋する人。また,それを業とする人。
くちいれ-や【口入れ屋】🔗⭐🔉
くちいれ-や [0] 【口入れ屋】
奉公人の周旋・仲介を業とする人。また,その家。口入れ宿。
くち-うつし【口移し・口写し】🔗⭐🔉
くち-うつし [0][3] 【口移し・口写し】
(1)飲食物を自分の口から他人の口へ移し入れること。《口移》
(2)口頭で直接に言い伝えること。口授。口伝(クデン)。《口移》「―で教え込む」
(3)話しぶりや話の内容が,ほかの人とそっくりそのままであること。《口写》「先生の説の―」
くち-うら【口占・口裏】🔗⭐🔉
くち-うら [0] 【口占・口裏】
〔(2)が原義〕
(1)言い方から察せられる本心。相手が本心を推察できるような話しぶり。《口裏》「相手の―から大体のことは察せられる」
(2)人の言葉を聞いて,それで吉凶を占うこと。《口占》「源繁昌の―あり,とぞささやきける/盛衰記 27」
くち-うるさ・い【口煩い】🔗⭐🔉
くち-うるさ・い [5] 【口煩い】 (形)[文]ク くちうるさ・し
ちょっとしたことにも細かく文句を言う。口やかましい。
くち-え【口絵】🔗⭐🔉
くち-え ― [0] 【口絵】
書籍・雑誌で,表紙の次あるいは本文の前に別丁で入れる絵や写真。
[0] 【口絵】
書籍・雑誌で,表紙の次あるいは本文の前に別丁で入れる絵や写真。
 [0] 【口絵】
書籍・雑誌で,表紙の次あるいは本文の前に別丁で入れる絵や写真。
[0] 【口絵】
書籍・雑誌で,表紙の次あるいは本文の前に別丁で入れる絵や写真。
くち-えい【口永】🔗⭐🔉
くち-えい 【口永】
口米(クチマイ)の金納化したもの。金納を建て前とする畠地で,架空の貨幣単位「永」を設定して算出した。
くち-おおい【口覆い】🔗⭐🔉
くち-おおい ―オホヒ [3] 【口覆い】
(1)茶道で,葉茶壺の口を覆う布。金襴(キンラン)などを用いる。
(2)口を覆い隠すこと。また,そのための袖や扇など。
くち-おき【口置き】🔗⭐🔉
くち-おき 【口置き】
物の縁や衣服のへりに金銀などの装飾をすること。置き口。「―など,目もあやに/栄花(根合)」
くち-おし・い【口惜しい】🔗⭐🔉
くち-おし・い ―ヲシイ [4] 【口惜しい】 (形)[文]シク くちを・し
(1)残念だ。くやしい。やや古風な言い方。「生家も人手に渡って―・い思いをした」
(2)期待はずれだ。失望を感じる。「遊びもしは見すべきことありて呼びにやりたる人の来ぬ,いと―・し/枕草子 98」
(3)取るに足りない。言うに足りない。大したことはない。「取るかたなく,―・しききはと,優なりと覚ゆばかりすぐれたるとは/源氏(帚木)」
〔語源未詳。一説に「朽ち惜し」の意とも。自分の行為を後悔する気持ちを表す「くやし」とは区別して使われていたが,室町時代頃から混同されるようになった〕
[派生] ――が・る(動ラ五[四])――げ(形動)――さ(名)
くち-おも・い【口重い】🔗⭐🔉
くち-おも・い [4][0] 【口重い】 (形)[文]ク くちおも・し
(1)口数が少ない。軽々しくものを言わない。「―・く押し黙っている」
(2)口に出すのが遠慮される。言いにくい。「明かし給はむ事は,猶,―・き心地して/源氏(手習)」
くち-がき【口書き】🔗⭐🔉
くち-がき [0] 【口書き】
(1)はしがき。序文。こうしょ。
(2)筆を口にくわえて書や絵をかくこと。また,そのかいたもの。
(3)江戸時代,裁判における供述・主張や取り調べに対する返答を記した調書。足軽以下,百姓・町人に関する調書をいい,武家のものは口上書(コウジヨウシヨ)という。
くち-がしこ・い【口賢い】🔗⭐🔉
くち-がしこ・い [5] 【口賢い】 (形)[文]ク くちがしこ・し
ものの言い方がうまい。「―・く己(オノ)れの非を蔽(オオ)ふ理窟を作る/社会百面相(魯庵)」
くち-かず【口数】🔗⭐🔉
くち-かず [0] 【口数】
(1)話をする回数。言葉かず。「すこし―が多すぎる」「―が少ない」
(2)食費のかかる人の数。「奉公に出して―を減らす」
(3)一口(ヒトクチ)単位になっている申込金・寄付金・出資金などの個数。
くち-がた・い【口堅い・口固い】🔗⭐🔉
くち-がた・い [4][0] 【口堅い・口固い】 (形)[文]ク くちがた・し
(1)やたらに人に言い散らさない。口が堅い。
(2)言うことが確かである。「―・く約束する」
(3)強く言い張る。主張をまげない。「げにあやまちてけり,とは言はで―・うあらがひたる/枕草子(一〇〇・能因本)」
くち-がため【口固め】🔗⭐🔉
くち-がため [0][3] 【口固め】 (名)スル
(1)他言をとめること。口止め。
(2)言葉で約束すること。口約束。
(3)男女の契り。
くち-がたり【口語り】🔗⭐🔉
くち-がたり [3] 【口語り】
(1)浄瑠璃一段を口(クチ)・中(ナカ)・切(キリ)に分けたとき,口を語ること。また,それを語る太夫。切り語りよりも格の低い太夫が受け持つ。端場(ハバ)語り。
→切り語り
(2)浄瑠璃などの語り物を三味線の伴奏なしで語ること。
くち-がね【口金】🔗⭐🔉
くち-がね [0] 【口金】
(1)入れ物の口もとをとめる金具。「ハンドバッグの―」
(2)電球の,ソケットにねじ込む金属の部分。
(3)槍の穂などの部分をしっかりと保持するため柄(エ)の先にはめる金具。
→鑿(ノミ)
くち-がま・し【口がまし】🔗⭐🔉
くち-がま・し 【口がまし】 (形シク)
口やかましい。口うるさい。「―・しきくるわ中の沙汰にあはば/浮世草子・禁短気」
くち-がも【口鴨】🔗⭐🔉
くち-がも [0] 【口鴨】
ハシビロガモの別名。
くち-がる【口軽】🔗⭐🔉
くち-がる [0] 【口軽】 (名・形動)
軽々しくよくしゃべり,秘密などをすぐに人にもらす・こと(さま)。
⇔口重(クチオモ)
「故(ワザ)と―に笑顔さへ粧(ツク)つて/くれの廿八日(魯庵)」
くち-がる・い【口軽い】🔗⭐🔉
くち-がる・い [4][0] 【口軽い】 (形)[文]ク くちがる・し
(1)気軽な口調である。柔らかでなめらかな口調である。「お万が客は―・く/そめちがへ(鴎外)」
(2)軽々しくものを言う。秘密などをすぐ口外する。おしゃべりだ。「かうまでも洩らし聞ゆるも,かつはいと―・けれど/源氏(宿木)」
くち-がろ・し【口軽し】🔗⭐🔉
くち-がろ・し 【口軽し】 (形ク)
「くちがるい{(2)}」に同じ。「大方―・きものに成たれば/十訓 4」
くち-がわり【口代(わ)り・口替(わ)り】🔗⭐🔉
くち-がわり ―ガハリ [3] 【口代(わ)り・口替(わ)り】
〔「口取り肴(ザカナ)」の代わりの意〕
酒の肴として数種類の料理を少しずつ一皿に盛り合わせたもの。
くち-き【口木】🔗⭐🔉
くち-き 【口木】
「枚(バイ)」に同じ。「―を銜(クク)みて城(キ)を穿(ウガ)ちて/日本書紀(天武上訓)」
くち-き【朽(ち)木】🔗⭐🔉
くち-き [0] 【朽(ち)木】
(1)枯れてくさった木。くされ木。くちた木。
(2)不遇のまま,空しく一生を終わる人の身の上のたとえ。
くちき-がき【朽(ち)木書き】🔗⭐🔉
くちき-がき [0] 【朽(ち)木書き】
消し炭や焼き筆で下絵を書くこと。また,その下絵。
くちき-がた【朽(ち)木形】🔗⭐🔉
くちき-がた [0] 【朽(ち)木形】
枯れて木目が浮き上がったような模様。几帳や壁代の文様に使われた。
朽ち木形
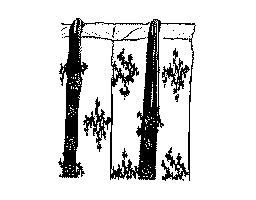 [図]
[図]
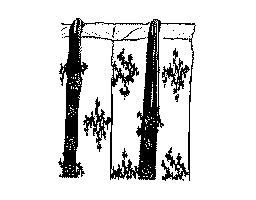 [図]
[図]
くちき-ざ【朽(ち)木座】🔗⭐🔉
くちき-ざ [0] 【朽(ち)木座】
仏像の台座の一。朽ちた木の根を用いて,岩の形に作った台座。
くちき-ざくら【朽(ち)木桜】🔗⭐🔉
くちき-ざくら [4] 【朽(ち)木桜】
枯れ朽ちた桜の木。「年古(フ)りまさる―/謡曲・熊野」
くち-きき【口利き】🔗⭐🔉
くち-きき [0][4] 【口利き】
(1)仲介・斡旋・紹介などをすること。とりもつこと。「就職の―をたのむ」
(2)談判・相談などのとりなしをすること。また,それをするのが上手な人。
(3)話し方がうまいこと。弁舌が巧みなこと。また,その人。「物なれたるうへ―なりしかば/平治(下・古活字本)」
くち-ぎたな・い【口汚い】🔗⭐🔉
くち-ぎたな・い [5][0] 【口汚い】 (形)[文]ク くちぎたな・し
(1)下品で乱暴な言葉を使うさま。聞く人が不愉快になるような言い方である。「―・くののしる」
(2)食い意地が張っている。くいしんぼうである。
[派生] ――さ(名)
くち-ぎよう【口器用】🔗⭐🔉
くち-ぎよう 【口器用】 (名・形動ナリ)
〔中世・近世語。「くちきよう」とも〕
「口上手(クチジヨウズ)」に同じ。「―にぬかすな,隠した文ここへ出せ/浄瑠璃・国性爺後日」
くち-きよ・し【口清し】🔗⭐🔉
くち-きよ・し 【口清し】 (形ク)
(1)物言いが立派である。「心の問はむにだに―・う答へむ/源氏(夕霧)」
(2)口先だけ立派である。口先が巧みである。「商人は,惣て此れ無き事也,と―・く諍(アラソ)ふ/今昔 31」
くち-きり【口切り】🔗⭐🔉
くち-きり [0] 【口切り】
(1)密封した容器の封を切ること。口あけ。
(2)物事の初め。最初。かわ切り。「講演会の―は先生にお願いしよう」
(3)茶道で,新茶を詰めた茶壺(チヤツボ)の封を切ること。[季]冬。《―や湯気たゞならぬ台所/蕪村》
(4)取引所などで,最初に成立した売買の取引。
くち-ぎれい【口綺麗】🔗⭐🔉
くち-ぎれい [3] 【口綺麗】 (形動)[文]ナリ
(1)口先だけはきれいごとを言うさま。口きよらか。「―な事はいひますとも此あたりの人に泥の中の蓮とやら/にごりえ(一葉)」
(2)食い意地が張っていないさま。
くち-ぎわ【口際】🔗⭐🔉
くち-ぎわ ―ギハ [0] 【口際】
口もと。口のまわり。
く-ちく【苦竹】🔗⭐🔉
く-ちく [0] 【苦竹】
植物マダケの異名。にがたけ。
く-ちく【駆逐】🔗⭐🔉
く-ちく [0] 【駆逐】 (名)スル
(1)敵などを追い払うこと。「敵を―する」
(2)車馬で追いかけること。「馬車相―して進み入りぬ/即興詩人(鴎外)」
くちく-かん【駆逐艦】🔗⭐🔉
くちく-かん [0] 【駆逐艦】
軍艦の艦種の一。比較的小型の高速艦。魚雷・爆雷を装備し,ミサイルを装備するものも多い。護衛・哨戒・対潜攻撃などにあたる。
くち-くさ【腐草】🔗⭐🔉
くち-くさ 【腐草】
〔草が腐ってホタルになるという俗説から〕
ホタルの異名。草の蛍。
くち-ぐすり【口薬】🔗⭐🔉
くち-ぐすり [3] 【口薬】
(1)火縄銃の火皿に盛って,起爆薬とする黒色火薬。
(2)口止めのために与える金品。口止め料。「お供の衆には,―水撒(マ)く様に飲まして置いた/浄瑠璃・菅原」
くち-ぐせ【口癖】🔗⭐🔉
くち-ぐせ [0] 【口癖】
習慣のようになっている言葉遣い。たびたび話す話やよく使う言葉。
くち-くち【口口】🔗⭐🔉
くち-くち 【口口】
接吻(セツプン)。口づけ。キス。「手付けにちよつと―とすがり付くを/浄瑠璃・神霊矢口渡」
くち-ぐち【口口】🔗⭐🔉
くち-ぐち [2] 【口口】
(1)大勢の人がそれぞれにものを言うこと。「めいめい―にわめき合う」「―に言う」
(2)あちこちの出入り口。
クチクラ (ラテン) cuticula
(ラテン) cuticula 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
クチクラ [2]  (ラテン) cuticula
(ラテン) cuticula 生物の体表の細胞(表皮細胞・上皮細胞)から分泌してできたかたい層の総称。体の保護・水分蒸散防止などに役立つ。植物では主にクチンおよび蝋(ロウ)からなる。節足動物では,硬タンパク質を主成分とし,外骨格を形成する。角皮(カクヒ)。キューティクル。
生物の体表の細胞(表皮細胞・上皮細胞)から分泌してできたかたい層の総称。体の保護・水分蒸散防止などに役立つ。植物では主にクチンおよび蝋(ロウ)からなる。節足動物では,硬タンパク質を主成分とし,外骨格を形成する。角皮(カクヒ)。キューティクル。
 (ラテン) cuticula
(ラテン) cuticula 生物の体表の細胞(表皮細胞・上皮細胞)から分泌してできたかたい層の総称。体の保護・水分蒸散防止などに役立つ。植物では主にクチンおよび蝋(ロウ)からなる。節足動物では,硬タンパク質を主成分とし,外骨格を形成する。角皮(カクヒ)。キューティクル。
生物の体表の細胞(表皮細胞・上皮細胞)から分泌してできたかたい層の総称。体の保護・水分蒸散防止などに役立つ。植物では主にクチンおよび蝋(ロウ)からなる。節足動物では,硬タンパク質を主成分とし,外骨格を形成する。角皮(カクヒ)。キューティクル。
くち-ぐるま【口車】🔗⭐🔉
くち-ぐるま [3] 【口車】
相手をおだてたりだましたりするための,巧みな話し方。
くち-げんか【口喧嘩】🔗⭐🔉
くち-げんか ―ゲンクワ [3] 【口喧嘩】 (名)スル
言い争うこと。言い合うこと。口論。
くち-こ🔗⭐🔉
くち-こ [0]
「このこ」に同じ。
くち-ごうしゃ【口巧者】🔗⭐🔉
くち-ごうしゃ ―ガウシヤ [3] 【口巧者】 (名・形動)[文]ナリ
口先のうまい・こと(さま)。そのような人のこともいう。口上手。「何をぬかす,―な/露団々(露伴)」
くち-こごと【口小言】🔗⭐🔉
くち-こごと [3] 【口小言】
不平や文句を言うこと。「下女はお上さんがあんなでは困ると,―を言ひながら/雁(鴎外)」
くち-ごたえ【口答え】🔗⭐🔉
くち-ごたえ ―ゴタヘ [3][0] 【口答え】 (名)スル
目上の人の言葉に言い返すこと。また,そのような返答。「親に―する」
くち-ことば【口言葉・口詞】🔗⭐🔉
くち-ことば [3] 【口言葉・口詞】
(1)口で言うことば。話しことば。口語。
(2)「言葉」を強めた語。「―をいれさせをつて日がくれたは/狂言・鈍根草」
くち-コミ【口―】🔗⭐🔉
くち-コミ [0] 【口―】
〔マスコミのもじり〕
口から口へ伝えられる評判。「―で伝わる」
くち-ごも・る【口籠る】🔗⭐🔉
くち-ごも・る [4] 【口籠る】 (動ラ五[四])
(1)はっきり言わない。また,言葉につまる。言いしぶる。「明日なら,と言いかけて―・った」
(2)病気などのために,声が言葉として聞きとれない状態である。「昨日辰刻より―・られ,去夜絶入す/東鑑(延応二)」
くち-ごわ【口強】🔗⭐🔉
くち-ごわ ―ゴハ 【口強】 (名・形動)[文]ナリ
〔近世語〕
(1)強く主張すること。強弁すること。また,そのさま。「此間,―に御ざるに依て,いつぞは打擲致う/狂言・髭櫓(虎寛本)」
(2)馬などの性質が荒く,御し難いさま。「坂東黒というて―なる馬に乗りて/浮世草子・風流軍配団」
くち-ごわ・し【口強し】🔗⭐🔉
くち-ごわ・し ―ゴハシ 【口強し】 (形ク)
(1)強く言いはる。負けずに言い争う。「―・くて,手触れさせず/源氏(葵)」
(2)馬などの性質が荒く,御し難い。「白葦毛なる馬の,きはめて―・きにぞ乗たりける/平家 8」
くち-さか・し【口賢し】🔗⭐🔉
くち-さか・し 【口賢し】 (形シク)
口が達者だ。言葉巧みである。「かく―・しきをしへを伝へなば/読本・雨月(白峯)」
くち-さかずき【口盃】🔗⭐🔉
くち-さかずき ―サカヅキ 【口盃】
杯をとりかわさず,口先だけで約束すること。「盃なしの―/浄瑠璃・天神記」
くち-さがな・い【口さがない】🔗⭐🔉
くち-さがな・い [5] 【口さがない】 (形)[文]ク くちさがな・し
他人のことを,あれこれ口うるさく批評するのが好きである。口うるさい。「―・い連中」
[派生] ――さ(名)
くち-さき【口先】🔗⭐🔉
くち-さき [0] 【口先】
(1)くちの端。くち。「―にくわえる」
(2)心のこもらないうわべだけの言葉や話しぶり。「―だけの約束」「―だけの親切心」
くち【口】(和英)🔗⭐🔉
くち【口】
(1) a mouth;→英和
lips (くちびる).
(2)[就職口]employment[a job].(3)[一株]a share(一口入る).→英和
(4)[種類]a kind[sort];→英和
a brand (商品).→英和
〜が肥えている have a dainty[delicate]palate.〜に合う suit one's taste.→英和
〜にする eat;→英和
taste;mention[speak](言及する).→英和
〜のうまい(悪い) honey-(foul-)tongued.〜の堅い closemouthed.〜の軽い(重い) talkative (taciturn).→英和
〜をきく speak;→英和
mediate(仲裁).→英和
〜を切る broach.→英和
〜をすべらす let slip.
〜をする(あける) (un)cork.→英和
〜を添える recommend.→英和
〜を出す put in a word;→英和
interfere[meddle](干渉).→英和
〜を慎しむ hold one's tongue.〜を割る disclose.→英和
くちあけ【口明け】(和英)🔗⭐🔉
くちあけ【口明け】
the beginning.
くちいれ【口入れ屋】(和英)🔗⭐🔉
くちいれ【口入れ屋】
an employment agency (周旋屋).
くちうつし【口移しの】(和英)🔗⭐🔉
くちうつし【口移しの】
mouth-to-mouth.
くちうら【口裏を合わせる】(和英)🔗⭐🔉
くちうら【口裏を合わせる】
rearrange a story not to contradict each other.
くちうるさい【口うるさい】(和英)🔗⭐🔉
くちうるさい【口うるさい】
nagging;faultfinding.→英和
くちえ【口絵】(和英)🔗⭐🔉
くちえ【口絵】
a frontispiece.→英和
くちかず【口数の多い(少ない)】(和英)🔗⭐🔉
くちかず【口数の多い(少ない)】
talkative (taciturn).→英和
くちがね【口金】(和英)🔗⭐🔉
くちがね【口金】
a (bottle) cap;a clasp (かばんの).→英和
くちきき【口利き】(和英)🔗⭐🔉
くちきき【口利き】
mediation;a mediator (調停者).〜で through a person's good offices.
くちぎたない【口汚ない】(和英)🔗⭐🔉
くちぎたない【口汚ない】
foulmouthed;abusive.口汚なく(ののしる) abusively (abuse).→英和
くちぐせ【口癖】(和英)🔗⭐🔉
くちぐせ【口癖】
a habit of saying (癖);one's favorite phrase.〜のように言う be in the habit of saying.
くちぐるま【口車に乗せる】(和英)🔗⭐🔉
くちぐるま【口車に乗せる】
cajoleinto;coax.→英和
くちげんか【口喧嘩】(和英)🔗⭐🔉
くちげんか【口喧嘩】
a (verbal) quarrel.
くちごたえ【口答え】(和英)🔗⭐🔉
くちごたえ【口答え】
a retort.→英和
〜する retort.
くちコミ【口コミ(で)】(和英)🔗⭐🔉
くちコミ【口コミ(で)】
(by) word of mouth.
くちさがない【口さがない】(和英)🔗⭐🔉
くちさがない【口さがない】
gossipy;→英和
scandal-loving.
くちさき【口先のうまい】(和英)🔗⭐🔉
くちさき【口先のうまい】
honey-[smooth-]tongued.〜だけの insincere.→英和
〜だけで…する pay lip service.
大辞林に「くち」で始まるの検索結果 1-97。もっと読み込む