複数辞典一括検索+![]()
![]()
ご-とく【五徳】🔗⭐🔉
ご-とく [0] 【五徳】
(1)五つの徳目。仁・義・礼・智・信。あるいは温・良・恭・倹・譲。また,五行(ゴギヨウ)(木・火・土・金・水)の徳など。
(2)〔孫子(始計)〕
武将が意を用いるべき五つの徳目。知・信・仁・勇・厳。
(3)火鉢の灰の中に据えて,鉄瓶(テツビン)や釜(カマ)などをのせる,三本脚の輪形の台。
(4)家紋の一。{(3)}の全形をかたどったもの。
→かなわ(金輪)(3)
五徳(3)
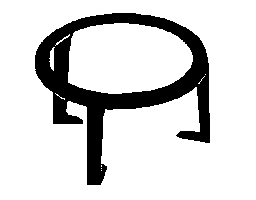 [図]
[図]
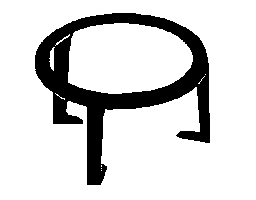 [図]
[図]
ご-とく【悟得】🔗⭐🔉
ご-とく [0] 【悟得】 (名)スル
悟りを開いて真理を会得すること。「一新理を―するものあれば/西洋聞見録(文夫)」
ごとく【如く】🔗⭐🔉
ごとく 【如く】 (助動)
〔助動詞「ごとし」の連用形から。現代語で,ややかたい文章語的な言い方として用いられる〕
活用語の連体形や体言,またそれらに助詞「の」「が」の付いたものに接続して,「…のように」「…のようで」などの意を表す。「お師匠様の円満微妙な色白の顔がにぶい明りの中に来迎仏の〈ごとく〉浮かんだ」
ごとくだいじ【後徳大寺】🔗⭐🔉
ごとくだいじ 【後徳大寺】
姓氏の一。
ごとくだいじ-さねさだ【後徳大寺実定】🔗⭐🔉
ごとくだいじ-さねさだ 【後徳大寺実定】
(1139-1191) 平安末期の歌人。藤原公能(キンヨシ)の長子。左大臣。法号,如円。詩・管弦にも優れる。家集「林下集」,日記「槐林記」
ごとく-ち【後得智】🔗⭐🔉
ごとく-ち [3] 【後得智】
〔仏〕 現象界の個々の物事の相違を認める智慧(チエ)。あらゆる物事が無差別であると知る根本智ののちに得られる。仏は衆生の差別を知って救済しようとするので,衆生を救済するのは後得智とされる。
ごとく-なり【如くなり】🔗⭐🔉
ごとく-なり 【如くなり】 (助動)(ごとくなら・ごとくなり(ごとくに)・ごとくなり・ごとくなる・ごとくなれ・ごとくなれ)
〔「ごとくにあり」の転〕
活用語の連体形や体言,またそれらに助詞「の」「が」の付いたものに接続する。
(1)似ているものに比べ,たとえる意を表す。…のようだ。…のようである。…のとおりである。「高き山も,麓のちりひぢよりなりて,あま雲たなびくまで,おひのぼれる〈ごとくに〉,この歌もかくの〈ごとくなる〉べし/古今(仮名序)」
(2)不確かな断定を表す。「まことに聞くが〈ごとくなら〉ば不便なる事也/著聞 17」
こと-くに【異国】🔗⭐🔉
こと-くに 【異国】
(1)よその国。異郷。「おのが国にはあらで―に田をつくりけるが/宇治拾遺 4」
(2)外国。異邦。とつくに。「広く―のことを知らぬ女のため/源氏(常夏)」
こ-とくにん【子徳人】🔗⭐🔉
こ-とくにん 【子徳人】
子宝を多く得た人。子福者。子沢山(コダクサン)。「徳人の中にても―にて候ふ/清元・舌出し三番叟」
ことく-らく【胡徳楽】🔗⭐🔉
ことく-らく 【胡徳楽】
舞楽の一。右方高麗楽(コマガク)。高麗壱越(イチコツ)調。襲(カサネ)装束。六人舞。酒宴の有り様を舞曲化したもので,喜劇的性格をもつ。
胡徳楽
 [図]
[図]
 [図]
[図]
こと-くわ・う【言加ふ】🔗⭐🔉
こと-くわ・う ―クハフ 【言加ふ】 (動ハ下二)
(1)横から人の話に口を出す。差し出口をする。「男(オノコ)は―・へ候ふべきにあらず/枕草子 23」
(2)唱和する。「兵部卿宮,青柳折り返しおもしろく謡ひ給ふ。あるじのおとども―・へ給ふ/源氏(胡蝶)」
ごとく【五徳】(和英)🔗⭐🔉
大辞林に「ごとく」で始まるの検索結果 1-12。