複数辞典一括検索+![]()
![]()
じゅう【住】🔗⭐🔉
じゅう ヂユウ [1] 【住】
人がすむ所・建物。すまい。すみか。「衣・食・―」
じゅう-おく【住屋】🔗⭐🔉
じゅう-おく ヂユウヲク [0] 【住屋】
すまい。住居。
じゅう-か【住家】🔗⭐🔉
じゅう-か ヂユウ― [1] 【住家】
人の住むための家。すまい。すみか。
じゅう-かんきょう【住環境】🔗⭐🔉
じゅう-かんきょう ヂユウクワンキヤウ [3] 【住環境】
居住する場をとりまく,自然・社会環境。
じゅう-きょ【住居】🔗⭐🔉
じゅう-きょ ヂユウ― [1] 【住居】 (名)スル
住まうこと。また,その家や場所。すまい。すみか。「―を移す」「古代の―」「都会に―する人民/福翁百話(諭吉)」
じゅうきょ-し【住居址】🔗⭐🔉
じゅうきょ-し ヂユウ― [3] 【住居址】
過去に人が生活を営んだ住居の跡。
じゅうきょ-しんにゅうざい【住居侵入罪】🔗⭐🔉
じゅうきょ-しんにゅうざい ヂユウ―シンニフ― [1]-[3] 【住居侵入罪】
人の住居もしくは建造物・艦船などに正当な理由なく立ち入り,また退去しない場合に成立する罪。家宅侵入罪。
じゅうきょ-ちいき【住居地域】🔗⭐🔉
じゅうきょ-ちいき ヂユウ― キ [4] 【住居地域】
用途地域のうち,主として居住環境を保全するために定める地域。
キ [4] 【住居地域】
用途地域のうち,主として居住環境を保全するために定める地域。
 キ [4] 【住居地域】
用途地域のうち,主として居住環境を保全するために定める地域。
キ [4] 【住居地域】
用途地域のうち,主として居住環境を保全するために定める地域。
じゅうきょ-の-ふかしん【住居の不可侵】🔗⭐🔉
じゅうきょ-の-ふかしん ヂユウ― 【住居の不可侵】
憲法が保障する基本的人権の一。居住者の承諾なく,住居への立ち入りや捜索は許されないという原則。
じゅうけつ-きゅうちゅう【住血吸虫】🔗⭐🔉
じゅうけつ-きゅうちゅう ヂユウケツキフチユウ [5] 【住血吸虫】
扁形動物,吸虫綱住血吸虫科の寄生虫の総称。糸状で,哺乳類・鳥類の血管内に寄生する。雌雄異体。
じゅう-こ【住戸】🔗⭐🔉
じゅう-こ ヂユウ― [1] 【住戸】
マンションなどの集合住宅で,それぞれ居住する一戸一戸をいう語。
じゅう-こう【住劫】🔗⭐🔉
じゅう-こう ヂユウコフ [0] 【住劫】
〔仏〕 四劫(シコウ)の第二。世界と生物とが安穏に続いていくという期間。
→四劫
じゅう-じ【住持】🔗⭐🔉
じゅう-じ ヂユウヂ [1] 【住持】 (名)スル
(1)寺の住職。
(2)仏法を守り保つこと。「仏法を―し,王法を祈誓し/盛衰記 18」
じゅう-しょ【住所・住処】🔗⭐🔉
じゅう-しょ ヂユウ― [1] 【住所・住処】
(1)住んでいる場所。すみか。すまい。
(2)〔法〕 生活の本拠であって,法律関係を処理する場合の基準となる場所。
→居所
じゅうしょ-ち-ほう【住所地法】🔗⭐🔉
じゅうしょ-ち-ほう ヂユウ―ハフ [0][4] 【住所地法】
〔法〕 当事者の住所がある場所(国)の法。国際私法上,準拠法として認められている。
じゅうしょ-ふてい【住所不定】🔗⭐🔉
じゅうしょ-ふてい ヂユウ― [1] 【住所不定】
一定した住所をもっていないこと。「―の男」
じゅうしょ-ろく【住所録】🔗⭐🔉
じゅうしょ-ろく ヂユウ― [3] 【住所録】
友人・知人・関係者などの住所を書きとめておく帳簿。
じゅう-しょく【住職】🔗⭐🔉
じゅう-しょく ヂユウ― [1] 【住職】 (名)スル
一寺を主管すること。また,その職分。寺の長である僧。住持。
じゅう・する【住する】🔗⭐🔉
じゅう・する ヂユウ― [3] 【住する】 (動サ変)[文]サ変 ぢゆう・す
(1)住居をかまえる。住む。「異境に―・する」「国内に―・する外国人/新聞雑誌 46」
(2)すみか・よりどころとして,とどまる。「愛に―・すれば人生に意義あり/平凡(四迷)」
(3)落ち着く。定める。「源氏合力の心に―・すべきよし,一味同心に僉議して/平家 7」
(4)拘泥する。かかずらう。「世をのがるると云は,名聞にこそ―・したれ/平治(上)」
じゅう-せい【住棲】🔗⭐🔉
じゅう-せい ヂユウ― [0] 【住棲】 (名)スル
住むこと。すみかとすること。「石館の中に―するも/明六雑誌 9」
じゅう-そう【住僧】🔗⭐🔉
じゅう-そう ヂユウ― [0][1] 【住僧】
寺院に居住している僧。
じゅう-たく【住宅】🔗⭐🔉
じゅう-たく ヂユウ― [0] 【住宅】
(1)人の住む家。すまい。すみか。「―街」「―地」
(2)居所を定めてそこに住むこと。すまいとすること。「近きこそよけれと,知らぬ松本に―して/浮世草子・新永代蔵」
じゅうたく-きんゆう-こうこ【住宅金融公庫】🔗⭐🔉
じゅうたく-きんゆう-こうこ ヂユウ― 【住宅金融公庫】
国民に低利かつ長期の住宅建設購入資金を供給することを目的とする公庫。全額政府出資の公法上の法人。1950年(昭和25)制定の住宅金融公庫法により設立。
じゅうたく-てあて【住宅手当】🔗⭐🔉
じゅうたく-てあて ヂユウ― [5] 【住宅手当】
労働者の住居費に関して支給される手当。
じゅうたく-とうけいちょうさ【住宅統計調査】🔗⭐🔉
じゅうたく-とうけいちょうさ ヂユウ―テウサ [9] 【住宅統計調査】
日本の住宅の現状と推移を明らかにし,住宅関係諸施策の基礎資料とするため総務庁統計局によって行われる統計調査。1948年(昭和23)以来五年ごとに実施。
じゅうたく-としせいび-こうだん【住宅・都市整備公団】🔗⭐🔉
じゅうたく-としせいび-こうだん ヂユウ― 【住宅・都市整備公団】
都市地域における集団住宅および宅地の大規模な供給と都市環境の改善・整備を目的として設立された特殊法人。1981年(昭和56)日本住宅公団と宅地開発公団とを統合・改組して設立。
じゅうたく-なん【住宅難】🔗⭐🔉
じゅうたく-なん ヂユウ― [4] 【住宅難】
住宅や宅地が高価で,また不足しているため,住む家を入手しがたいこと。
じゅうたく-ローン【住宅―】🔗⭐🔉
じゅうたく-ローン ヂユウ― [5] 【住宅―】
住宅・宅地の取得や新築・改築のため,住宅を抵当として銀行や住宅金融会社などが行う資金貸付。
じゅう-とう【住棟】🔗⭐🔉
じゅう-とう ヂユウ― [0] 【住棟】
集合住宅など,住居用の建物。
じゅう-にん【住人】🔗⭐🔉
じゅう-にん ヂユウ― [0] 【住人】
その土地に住む人。「武蔵国の―」
じゅう-ぼう【住房】🔗⭐🔉
じゅう-ぼう ヂユウバウ 【住房】
(僧が)日常生活しているへや。
じゅう-みん【住民】🔗⭐🔉
じゅう-みん ヂユウ― [0][3] 【住民】
その土地に住んでいる人。
じゅうみん-うんどう【住民運動】🔗⭐🔉
じゅうみん-うんどう ヂユウ― [5] 【住民運動】
同じ地域に住む人々が,職業や階層を超えて結集し,その地域で起きた問題の解決のために行う運動。
じゅうみん-かんさせいきゅう【住民監査請求】🔗⭐🔉
じゅうみん-かんさせいきゅう ヂユウ―セイキウ [8] 【住民監査請求】
地方公共団体の財産の不当な処理などがあった場合に,住民が,監査委員に対して,監査を求め,また,行為の防止や是正,地方公共団体の受けた損害の補填など必要な措置を求めること。
じゅうみん-きほんだいちょう【住民基本台帳】🔗⭐🔉
じゅうみん-きほんだいちょう ヂユウ―ダイチヤウ [8] 【住民基本台帳】
市(区)町村において,住民の居住関係の公証,選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務処理の基礎とするため,住民票を世帯ごとに編成して作成した台帳。
じゅうみん-さんか【住民参加】🔗⭐🔉
じゅうみん-さんか ヂユウ― [5] 【住民参加】
行政,特に地方行政での意思決定過程に住民が加わること。
じゅうみん-じち【住民自治】🔗⭐🔉
じゅうみん-じち ヂユウ― [5] 【住民自治】
その地方の行政が,その地方の住民の意思と責任に基づいて処理されること。団体自治とならぶ地方自治の基本。
じゅうみん-ぜい【住民税】🔗⭐🔉
じゅうみん-ぜい ヂユウ― [3] 【住民税】
地方税の一。個人と法人の所得を課税対象とするもの。道府県民税と市町村住民税とがある。
すまい【住(ま)い】🔗⭐🔉
すまい スマヒ [1] 【住(ま)い】
〔動詞「住まう」の連用形から。「住居」とも当てる〕
(1)住む家。すみか。「―を探す」
(2)住むこと。「下宿―」「かくむくつけき―するたぐひは/源氏(蓬生)」
すま・う【住まう】🔗⭐🔉
すま・う スマフ [2] 【住まう】 (動ワ五[ハ四])
〔「住む」に継続の助動詞「ふ」が付いたものから〕
(1)住み続ける。暮らし続ける。「片田舎に―・っている」「年月をあだに契りて我や―・ひし/伊勢 21」
(2)(芝居の舞台で,登場人物が)すわりこむ。座を占める。「玄関より二重へ廻り来て,両人宜しく―・ふ/歌舞伎・勧善懲悪覗機関」
[可能] すまえる
すみ-あ・し【住み悪し】🔗⭐🔉
すみ-あ・し 【住み悪し】 (形シク)
住みにくい。居心地が悪い。「他国(ヒトクニ)は―・しとそいふ/万葉 3748」
すみ-あら・す【住み荒(ら)す】🔗⭐🔉
すみ-あら・す [0][4] 【住み荒(ら)す】 (動サ五[四])
(1)家や部屋など,長い間住んで汚したり傷つけたりする。「建ててから十年になると云ふが,―・したと云ふやうな処は少しもない/青年(鴎外)」
(2)よそに行き,住んでいたところを荒れたままにしておく。「―・したる柴の庵ぞ/新古今(雑中)」
すみ-う・し【住み憂し】🔗⭐🔉
すみ-う・し 【住み憂し】 (形ク)
住みづらい。住みにくい。「京や―・かりけむ/伊勢 8」
すみ-か【住み処・栖】🔗⭐🔉
すみ-か [1] 【住み処・栖】
住む所。住まい。住居。現代では好ましくないものの住んでいる所をいうことが多い。「犯人の―を捜す」「鬼の―」
すみ-かえ【住(み)替え】🔗⭐🔉
すみ-かえ ―カヘ [0] 【住(み)替え】
(1)住居をかえること。
(2)奉公人・芸者などが主家をかえること。鞍(クラ)替え。
すみ-か・える【住(み)替える】🔗⭐🔉
すみ-か・える ―カヘル [0][4][3] 【住(み)替える】 (動ア下一)[文]ハ下二 すみか・ふ
(1)住む家・部屋をかえる。「マンションに―・える」
(2)奉公人や芸者などが,雇い主や抱え主をかえる。「江戸から―・へて来た有名な芸妓(ゲイシヤ)だつた/湯島詣(鏡花)」
すみ-かわ・る【住(み)替わる】🔗⭐🔉
すみ-かわ・る ―カハル [0][4] 【住(み)替わる】 (動ラ五[四])
家の住人がかわる。「草の戸も―・る代ぞひなの家/奥の細道」
すみ-ごこち【住み心地】🔗⭐🔉
すみ-ごこち [0] 【住み心地】
住みぐあい。「―が好い」
すみ-こみ【住(み)込み】🔗⭐🔉
すみ-こみ [0] 【住(み)込み】
住み込むこと。また,その人。
⇔通い
「―の店員」
すみ-こ・む【住(み)込む】🔗⭐🔉
すみ-こ・む [3][0] 【住(み)込む】 (動マ五[四])
使用人・弟子などが主人の家に住む。「師匠の家に―・む」
[可能] すみこめる
すみ-つ・く【住(み)着く】🔗⭐🔉
すみ-つ・く [0][3] 【住(み)着く】 (動カ五[四])
(1)長い間一か所に住む。居着く。「捨て猫が―・いてしまった」
(2)夫婦関係が定まって落ち着く。「おほきおとどのわたりに,今は―・かれにたりとな/源氏(若菜上)」
[可能] すみつける
すみ-な・す【住(み)成す】🔗⭐🔉
すみ-な・す [3][0] 【住(み)成す】 (動サ五[四])
(1)そこを住居とする。すまう。「長年―・した家」
(2)(上に修飾句を伴って)…という様子で住む。「いとのどかに心にくく―・し給へり/源氏(夕顔)」
すみ-な・れる【住み馴れる】🔗⭐🔉
すみ-な・れる [4][0] 【住み馴れる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 すみな・る
その土地や家に長年住んで,なれる。「―・れた土地」
すみのえ【墨江・住吉】🔗⭐🔉
すみのえ 【墨江・住吉】
「すみよし(住吉){(2)}」に同じ。
すみのえ-の-かみ【住吉神】🔗⭐🔉
すみのえ-の-かみ 【住吉神】
底筒男命(ソコツツノオノミコト)・中(ナカ)筒男命・表(ウワ)筒男命の総称。海上の守護神,外交の神,和歌の神とされる。住吉神社の祭神。すみよしのかみ。
すみ-はな・る【住み離る】🔗⭐🔉
すみ-はな・る 【住み離る】 (動ラ下二)
(1)住居を離れる。世間から離れる。「尼になりて同じ家の内なれど,方異(カタコト)に―・れてあり/更級」
(2)愛情が薄れて夫が妻の所へ来なくなる。「さばかり―・れたる所ある御心に/とりかへばや(上)」
すみ-み・つ【住み満つ】🔗⭐🔉
すみ-み・つ 【住み満つ】 (動タ四)
(1)大勢の人がある場所に寄り集まって住む。「勢ひことに―・ち給へれば/源氏(玉鬘)」
(2)満ち足りた気持ちで住む。「内の大い殿の姫君と―・ちておはする/栄花(根合)」
すみよし【住吉】🔗⭐🔉
すみよし 【住吉】
(1)大阪市南部の区。東部の台地は住宅地,西部は大阪湾の埋立地で,臨海工業地帯。住吉大社がある。
(2)大阪府南部の旧郡名。大阪湾に臨む一帯の地。古くは「すみのえ」と呼ばれ,平安初期以降「すみよし」として定着。難波(ナニワ)三津の一つとして栄えた。((歌枕))「―の松にたちよる白浪のかへる折にや音(ネ)は泣かるらむ/後撰(恋二)」
(3)箏曲の一。山田検校作曲。住吉神社参詣を題材とした中許し物。
すみよし-おどり【住吉踊り】🔗⭐🔉
すみよし-おどり ―ヲドリ [5] 【住吉踊り】
大阪住吉大社に伝わる踊り。音頭取りが長柄の傘を持ってその柄を扇子で打ちながら歌をうたい,菅笠(スゲガサ)をつけた僧形の四人の童子(人数不定の場合もある)が,その周りを団扇(ウチワ)を打ちながら踊りまわる。古くは住吉代参の祈祷(キトウ)のために神宮寺の社僧が各地を巡った。のち江戸に入り願人坊主によって流布されたのが「かっぽれ」である。
住吉踊り
 [図]
[図]
 [図]
[図]
すみよし-じんじゃ【住吉神社】🔗⭐🔉
すみよし-じんじゃ 【住吉神社】
大阪市住吉区にある神社。底筒男命(ソコツツノオノミコト)・中筒男命・表筒男命・神功皇后をまつる。現在では住吉大社と改称。
すみよし-づくり【住吉造り】🔗⭐🔉
すみよし-づくり [5] 【住吉造り】
神社本殿様式の一。屋根は反りのない切妻造りで,棟に千木と堅魚木(カツオギ)を置く。妻を正面とする前後に細長い建築で,内部は内陣と外陣の二室に分かれている。大阪住吉大社本殿はこの代表例。
住吉造り
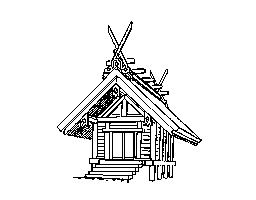 [図]
[図]
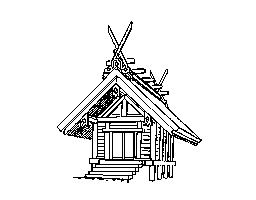 [図]
[図]
すみよし-どりい【住吉鳥居】🔗⭐🔉
すみよし-どりい ― [5] 【住吉鳥居】
住吉大社などに用いた鳥居で,中山鳥居の柱が四角となったもの。
[5] 【住吉鳥居】
住吉大社などに用いた鳥居で,中山鳥居の柱が四角となったもの。
 [5] 【住吉鳥居】
住吉大社などに用いた鳥居で,中山鳥居の柱が四角となったもの。
[5] 【住吉鳥居】
住吉大社などに用いた鳥居で,中山鳥居の柱が四角となったもの。
すみよし-にんぎょう【住吉人形】🔗⭐🔉
すみよし-にんぎょう ―ギヤウ [5] 【住吉人形】
住吉でつくった土製の人形。
すみよし-の-かみ【住吉の神】🔗⭐🔉
すみよし-の-かみ 【住吉の神】
⇒住吉神(スミノエノカミ)
すみよし【住吉】🔗⭐🔉
すみよし 【住吉】
姓氏の一。
すみよし-ぐけい【住吉具慶】🔗⭐🔉
すみよし-ぐけい 【住吉具慶】
(1631-1705) 江戸前期の大和絵画家。如慶の長男。幕府の奥絵師となり大和絵を江戸に広め,住吉派隆盛の礎を築いた。
すみよし-じょけい【住吉如慶】🔗⭐🔉
すみよし-じょけい 【住吉如慶】
(1599-1670) 江戸前期の大和絵画家。土佐光吉の弟子。後水尾天皇の勅により住吉絵所を再興,土佐派から分かれて住吉派を興した。
すみよし-は【住吉派】🔗⭐🔉
すみよし-は 【住吉派】
大和絵の一派。如慶が土佐派から分かれて一派をなしたもの。京の土佐家に対し,江戸での大和絵の中心をなし,狩野家と並んで幕末まで幕府の御用絵師を務めた。
すみよしものがたり【住吉物語】🔗⭐🔉
すみよしものがたり 【住吉物語】
物語。二巻。作者・成立年代とも未詳。平安前期の同名の物語を改作したものらしく,異本がきわめて多い。継子いじめ譚(タン)に長谷観音の利生(リシヨウ)説話を交える。
すみ-わた・る【住み渡る】🔗⭐🔉
すみ-わた・る 【住み渡る】 (動ラ四)
(1)一か所に長く住み続ける。「橘の林をうゑむほととぎす常に冬まで―・るがね/万葉 1958」
(2)女のもとに男が通い続ける。「東の方をとしごろおもひて―・りけるを/大和 11」
すみ-わ・ぶ【住み侘ぶ】🔗⭐🔉
すみ-わ・ぶ 【住み侘ぶ】 (動バ上二)
生きてゆくのがつらいと思う。「世に―・びて山にこそ入れ/源氏(早蕨)」
す・む【住む・棲む・栖む】🔗⭐🔉
す・む [1] 【住む・棲む・栖む】 (動マ五[四])
(1)所を定めて,そこで生活する。《住》「町に―・む」
(2)鳥やけだものなどが巣を作って生活する。《棲・栖》「森に―・むキツネ」
(3)(上代・中古において)男が女の家に行き,夫婦として暮らす。「いかがありけむ,そのおとこ―・まずなりにけり/伊勢 94」
[可能] すめる
住めば都(ミヤコ)🔗⭐🔉
住めば都(ミヤコ)
どんな所でも住み慣れればそこが最も住みよく思われるものだ。地獄も住み家。
じゅうしょ【住所】(和英)🔗⭐🔉
じゅうしょ【住所】
one's dwelling[residence];one's address.‖住所不定の者 a person of no fixed abode.住所録 a directory.
じゅうしょく【住職】(和英)🔗⭐🔉
じゅうしょく【住職】
a[the chief]priest of a Buddhist temple.
じゅうみん【住民】(和英)🔗⭐🔉
じゅうみん【住民】
inhabitants;residents.‖住民税 a residence tax.住民登録 resident registration.住民票 a resident card.
すまい【住い】(和英)🔗⭐🔉
すみか【住処】(和英)🔗⭐🔉
すみか【住処】
⇒住い.
すみごこち【住心地が良(悪)い】(和英)🔗⭐🔉
すみごこち【住心地が良(悪)い】
be (not) comfortable to live in.
すみこみ【住込みのお手伝い】(和英)🔗⭐🔉
すみこみ【住込みのお手伝い】
a resident maid.〜の店員 a living-in employee.
すみこむ【住み込む】(和英)🔗⭐🔉
すみこむ【住み込む】
live.→英和
すみつく【住み着く】(和英)🔗⭐🔉
すみつく【住み着く】
settle.→英和
すみなれる【住み慣れる】(和英)🔗⭐🔉
すみなれる【住み慣れる】
get used to a place.→英和
住み慣れたdear old.
すむ【住む】(和英)🔗⭐🔉
大辞林に「住」で始まるの検索結果 1-88。もっと読み込む