複数辞典一括検索+![]()
![]()
かじ-き【梶木・旗魚】🔗⭐🔉
かじ-き カヂキ [1] 【梶木・旗魚】
スズキ目マカジキ科・メカジキ科の海魚の総称。全長3メートル内外の大形魚で,上顎が槍状に伸びている。マカジキ科のマカジキ・バショウカジキ・クロカジキなどは海面近くを,メカジキ科のメカジキはやや深いところを泳ぐ。マカジキが最も美味。外洋に広く分布。カジキマグロ。カジトオシ。
梶木
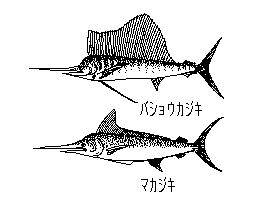 [図]
[図]
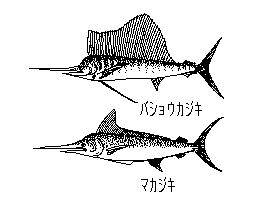 [図]
[図]
かじき-ざ【旗魚座】🔗⭐🔉
かじき-ざ カヂキ― [0] 【旗魚座】
〔(ラテン) Dorado〕
一月末頃の宵,南中する星座。日本からはその一部しか見えない。大マゼラン雲をその中に含む。
き-か【旗下】🔗⭐🔉
き-か [1][2] 【旗下】
(1)大将の旗のもと。また,大将の支配下。麾下(キカ)。「―に馳せ参ずる」
(2)特定の考え方などの影響下にあること。「実存主義の―にある」
き-かん【旗艦】🔗⭐🔉
き-かん [0][2][1] 【旗艦】
艦隊の司令官・司令長官が乗っていて,艦隊の指揮をとる軍艦。マストに司令官・司令長官の官階を示す旗を掲げる。
き-こ【旗鼓】🔗⭐🔉
き-こ [1][2] 【旗鼓】
(1)軍旗と鼓。
(2)軍隊。
きこ=の間(カン)に相見(アイマミ)ゆ🔗⭐🔉
――の間(カン)に相見(アイマミ)ゆ
戦場で敵味方になって相会する。旗鼓相当(アイア)たる。
き-ごう【旗号】🔗⭐🔉
き-ごう ―ガウ [1][0] 【旗号】
旗じるし。旗章。徽号(キゴウ)。
き-こく【旗国】🔗⭐🔉
き-こく [0][1] 【旗国】
船舶・航空機が所属するとして,登録している国。
きこく-しゅぎ【旗国主義】🔗⭐🔉
きこく-しゅぎ [4] 【旗国主義】
公海・公空にある船舶や航空機は,その旗国が管轄権を有するという原則。
き-し【旗幟】🔗⭐🔉
き-し [1][2] 【旗幟】
(1)旗とのぼり。旗じるし。
(2)表立って示す立場・態度。「―を鮮明にする」
きし-せんめい【旗幟鮮明】🔗⭐🔉
きし-せんめい [1] 【旗幟鮮明】
旗じるしのあざやかなこと。主義・主張のはっきりしていること。
き-しゅ【旗手】🔗⭐🔉
き-しゅ [1][2] 【旗手】
(1)団体のしるしとしての旗を持つ役目の人。
(2)ある運動の先頭に立って活躍する人。「新劇運動の―」
き-しょう【旗章】🔗⭐🔉
き-しょう ―シヤウ [0] 【旗章】
はたじるし。国旗・軍旗・校旗など。
き-しょく【旗色】🔗⭐🔉
き-しょく [0][1] 【旗色】
(1)戦いの形勢。はたいろ。
(2)旗じるしとするもの。立場。主張。「―鮮明」
き-じん【旗人】🔗⭐🔉
き-じん [1] 【旗人】
中国,清代の軍事組織八旗に所属した者の総称。満州族を中心にモンゴル族・漢族などを含む。各種の特権を与えられた。
き-せい【旗旌】🔗⭐🔉
き-せい [0] 【旗旌】
はたとのぼり。旗幟(キシ)。
き-ち【旗地】🔗⭐🔉
き-ち [1] 【旗地】
中国,清代に旗人の生計維持のために支給した土地。ヌルハチに始まり,瀋陽・北京付近を中心に設置。清代後期には崩壊した。
き-てい【旗亭】🔗⭐🔉
き-てい [0] 【旗亭】
〔中国で,酒旗という旗を掲げてその目印としたことから〕
酒場。酒楼。料理店。また,旅館。
き-ひょう【旗標】🔗⭐🔉
き-ひょう ―ヘウ [0] 【旗標】
はたじるし。旗章。
き-もん【旗門】🔗⭐🔉
き-もん [0] 【旗門】
スキーのアルペン競技で,コースを示すために立ててある一対の旗。
き-りゅう【旗旒】🔗⭐🔉
き-りゅう ―リウ [0] 【旗旒】
旗。特に,信号旗。
きりゅう-しんごう【旗旒信号】🔗⭐🔉
きりゅう-しんごう ―リウ―ガウ [4] 【旗旒信号】
船舶が一定の方式に従って旗を掲揚して行う信号。
はた【旗・幡・旌】🔗⭐🔉
はた [2] 【旗・幡・旌】
(1)布・紙などで作り,竿(サオ)などの先に掲げてしるしとするもの。古くは縦長で上辺を竿に結ぶ流れ旗が多く,のち,上辺と縦の一辺を乳(チ)で竿にとめる幟(ノボリ)旗が増えた。古来,朝廷で儀式・祭礼の具として用い,また,軍陣では標式として用いた。現在は,国・組織などの象徴として用いるほかに,さまざまな標識・信号として用いる。
(2)旗じるし。「独立の―をかかげる」
(3)家紋の一。{(1)}を図案化したもの。
(4)「旗売り」の略。
(5)(「幡」と書く)〔仏〕
〔梵 pat k
k 〕
仏・菩薩の威徳を示すための飾りの道具。大法要・説法などの時,寺院の境内や堂内に立てる。三角形の首部の下に細長い幡身(バンシン)をつけ,その下に数本のあしを垂れたもの。ばん。
〕
仏・菩薩の威徳を示すための飾りの道具。大法要・説法などの時,寺院の境内や堂内に立てる。三角形の首部の下に細長い幡身(バンシン)をつけ,その下に数本のあしを垂れたもの。ばん。
 k
k 〕
仏・菩薩の威徳を示すための飾りの道具。大法要・説法などの時,寺院の境内や堂内に立てる。三角形の首部の下に細長い幡身(バンシン)をつけ,その下に数本のあしを垂れたもの。ばん。
〕
仏・菩薩の威徳を示すための飾りの道具。大法要・説法などの時,寺院の境内や堂内に立てる。三角形の首部の下に細長い幡身(バンシン)をつけ,その下に数本のあしを垂れたもの。ばん。
はた=を揚(ア)・げる🔗⭐🔉
――を揚(ア)・げる
〔後漢書(袁紹伝)〕
(1)兵を集めて戦いを起こす。
(2)新しく事を起こす。旗揚げをする。
はた=を振・る🔗⭐🔉
――を振・る
政治運動などで,人々の先頭に立って指揮をとる。
はた=を巻(マ)・く🔗⭐🔉
――を巻(マ)・く
戦いに敗れて降参する。
はた-あげ【旗揚げ】🔗⭐🔉
はた-あげ [4][0] 【旗揚げ】 (名)スル
(1)兵を集めて戦いを起こすこと。
(2)芸能・演劇などで,新しく一座を組むこと。「―の公演」
(3)組織・集団などを新しく作ること。また,その名乗りをあげること。「新党が―する」
はた-いろ【旗色】🔗⭐🔉
はた-いろ [0] 【旗色】
〔戦場で軍旗のひるがえる様子から〕
(1)勝負の形勢。争い・議論などの優劣の状態。「―が悪い」
(2)〔所属を示す旗の色から〕
所属。立場。きしょく。旗幟(キシ)。「―を鮮明にする」
はたいろ=が悪・い🔗⭐🔉
――が悪・い
戦いで,形勢がよくない。
はた-うり【旗売り】🔗⭐🔉
はた-うり [0] 【旗売り】 (名)スル
取引で,空売りをすること。旗。
はた-おさめ【旗納め】🔗⭐🔉
はた-おさめ ―ヲサメ [3] 【旗納め】
労働組合などで,年末に行う懇親会。
はた-がしら【旗頭】🔗⭐🔉
はた-がしら [3] 【旗頭】
(1)ある集団の長。「一軍の―となる」
(2)旗の上方。「判官の―にひらめきて/盛衰記 43」
(3)中世,地方の同族武士団の長。「清の党の―,芳賀兵衛入道禅可/太平記 19」
(4)近世,一朝事有る際に,諸侯を率いて京都防備にあたる者の俗称。
はた-ぎょうれつ【旗行列】🔗⭐🔉
はた-ぎょうれつ ―ギヤウレツ [3] 【旗行列】
祝いなどの際に,手に小旗を持った人が行列してねり歩くこと。
はた-ぐも【旗雲】🔗⭐🔉
はた-ぐも [3][0] 【旗雲】
旗のようにたなびいた雲。
はた-ざお【旗竿】🔗⭐🔉
はた-ざお ―ザヲ [0] 【旗竿】
(1)旗をつけて掲げる竿。
(2)アブラナ科の越年草。山野・海辺に自生。茎は直立し,高さ30〜90センチメートル。葉は互生し,披針形,基部は矢じり形で茎を抱く。春,茎頂に白色の小花を総状につける。果実は細長く上を向いてつき,裂開する。
旗竿(2)
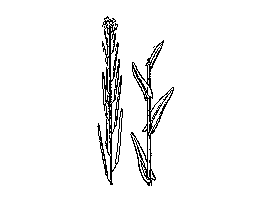 [図]
[図]
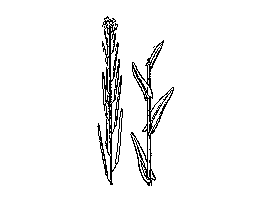 [図]
[図]
はた-さし【旗指・旗差】🔗⭐🔉
はた-さし [4] 【旗指・旗差】
(1)戦場で,大将の旗印を持つ侍。馬に乗って先頭を進む。旗手。旗持ち。
(2)「旗指物」の略。
はた-さしもの【旗指物】🔗⭐🔉
はた-さしもの [4][3] 【旗指物】
昔,鎧(ヨロイ)の背中にさして戦場で目印とした小旗。はたさし。
はた-じるし【旗印・旗標】🔗⭐🔉
はた-じるし [3] 【旗印・旗標】
(1)旗に紋や字を染め抜いて,戦場での目印とするもの。
(2)団体などが行動の目標として掲げる主義・主張。「反戦の―の下に合同する」
はた-だいしょう【旗大将】🔗⭐🔉
はた-だいしょう ―ダイシヤウ [3] 【旗大将】
(1)「旗奉行(ハタブギヨウ){(1)}」に同じ。
(2)一隊の長。旗頭。「一方の―/浄瑠璃・忠臣蔵」
はたたて-だい【旗立鯛】🔗⭐🔉
はたたて-だい ―ダヒ [4] 【旗立鯛】
スズキ目の海魚。全長約20センチメートル。体形はエンゼルフィッシュに似る。体色は白色の地に二本の太い黒色横帯が走り,背から尾にかけては黄色い。背びれの一部が長く伸び白く美しい。観賞魚とされる。相模湾以南の暖海のサンゴ礁などに分布。
はた-び【旗日】🔗⭐🔉
はた-び [2][1] 【旗日】
〔国旗を掲げることから〕
国の定めた祝日。
はた-びらき【旗開き】🔗⭐🔉
はた-びらき [3] 【旗開き】
労働組合などで,一年間の闘争を始めるにあたって年始に開く懇親会。
はた-ぶぎょう【旗奉行】🔗⭐🔉
はた-ぶぎょう ―ブギヤウ [3] 【旗奉行】
(1)武家の職名。旗を守る役。旗大将。幟(ノボリ)奉行。
(2)江戸幕府の職名。徳川家の軍旗・馬標(ウマジルシ)その他の旗を管理する役。
はた-ふり【旗振り】🔗⭐🔉
はた-ふり [4][3] 【旗振り】
(1)合図などのために旗を振ること。また,その人。
(2)ある事柄を推進すべく率先して周囲に呼びかけること。音頭取り。「後援会設立の―役」
はた-もち【旗持(ち)】🔗⭐🔉
はた-もち [4][3] 【旗持(ち)】
旗を持つ役目。はたさし。旗手。
はた-もと【旗本】🔗⭐🔉
はた-もと [0] 【旗本】
(1)軍陣で大将のいる所。本陣。本営。
(2)大将の近くにあってこれを護衛する家臣団。麾下(キカ)。
(3)江戸時代,将軍直属の家臣のうち,禄高一万石以下で御目見(オメミエ)以上の格式を有する者。御目見以下の御家人とあわせて直参(ジキサン)という。
はたもと-はちまんき【旗本八万騎】🔗⭐🔉
はたもと-はちまんき [7][0] 【旗本八万騎】
徳川将軍家の旗本の数を称したもの。旗本は,実際には五千を少し上回る程度であったが,御家人と陪臣を含めれば,約八万騎であった。
はたもと-やっこ【旗本奴】🔗⭐🔉
はたもと-やっこ [5] 【旗本奴】
江戸時代,旗本の青年武士で集団をなし,はでな服装をして,無頼を働いたもの。神祇組(ジンギグミ)・白柄組・六法組などが知られ,首領株に水野十郎左衛門がいた。
→町奴
きし【旗幟を鮮明にする】(和英)🔗⭐🔉
きし【旗幟を鮮明にする】
make clear one's position[attitude].
きしゅ【旗手】(和英)🔗⭐🔉
きしゅ【旗手】
a standard-bearer.
はた【旗】(和英)🔗⭐🔉
はたあげ【旗揚げをする】(和英)🔗⭐🔉
はたあげ【旗揚げをする】
[挙兵]raise an army;→英和
rise in arms (反乱);start a (new) business (事業を起こす).
はたいろ【旗色】(和英)🔗⭐🔉
はたざお【旗竿】(和英)🔗⭐🔉
はたじるし【旗印】(和英)🔗⭐🔉
はたじるし【旗印】
a flag mark[design];a slogan (標語).→英和
大辞林に「旗」で始まるの検索結果 1-57。