複数辞典一括検索+![]()
![]()
ます【枡・升・桝・斗】🔗⭐🔉
ます [2][0] 【枡・升・桝・斗】
(1)液状・粉状・粒状の物の一定量をはかる方形・円筒形の器具。一合枡・五合枡・一升枡などがある。
(2){(1)}ではかった分量。ますめ。「一人の僧ごとに飯(イイ)四―を受く/三宝絵詞(中)」
(3)歌舞伎劇場や相撲小屋で,土間を四角く区切った客席。現在は相撲興行と,劇場の桟敷席に見られる。仕切り枡。切り枡。枡席。
(4)銭湯などで,湯舟から湯をくむのに用いる箱形の器。
(5)家紋の一。角桝を図案化したもの。
ます=で量(ハカ)るほどある🔗⭐🔉
――で量(ハカ)るほどある
量のきわめて多いことのたとえ。
ます-あみ【枡網】🔗⭐🔉
ます-あみ [0] 【枡網】
建て網の一。魚を導く垣網と魚を取り囲む囲い網とから成り,囲い網の屈曲部に紡錘形で内部に返しが付いた袋網を付ける。遠浅泥砂の海に支柱などで固定し,タイ・カレイ・エビなどを捕らえる。
ます-あらため【枡改め】🔗⭐🔉
ます-あらため [3] 【枡改め】
江戸時代,不正枡の使用を取り締まるために行われた枡座による検査。
ます-いし【枡石】🔗⭐🔉
ます-いし [2] 【枡石】
(1)枡のような四角の石。
(2)黄鉄鉱が化学変化によって褐鉄鉱に変化した後も,黄鉄鉱の結晶をそのまま保って六面体の枡形のもの。武石(ブセキ)。
ます-うり【枡売り・升売り】🔗⭐🔉
ます-うり [0] 【枡売り・升売り】
米・酒・醤油などを,枡ではかって売ること。はかり売り。
ます-おとし【枡落(と)し・升落(と)し】🔗⭐🔉
ます-おとし [3] 【枡落(と)し・升落(と)し】
鼠(ネズミ)取りの仕掛けの一。枡を斜め下向きにして棒で支え,中に餌(エサ)をおいて,鼠がふれると枡が落ちて捕らえるようにしたわな。
ます-おり【枡織(り)】🔗⭐🔉
ます-おり [0] 【枡織(り)】
表面に枡形の凹凸を織り出した織物。木綿の敷布などに用いられる。蜂巣織り。
ます-かき【枡掻き・升掻き】🔗⭐🔉
ます-かき [4] 【枡掻き・升掻き】
(1)枡に盛った穀類などを,縁の高さにならすのに使う棒。とかき。
(2)「八十八の升掻き」の略。
ます-かけ【枡掛(け)】🔗⭐🔉
ます-かけ [4][0] 【枡掛(け)】
「枡掛け筋(スジ)」の略。
ますかけ-すじ【枡掛(け)筋】🔗⭐🔉
ますかけ-すじ ―スヂ [5][4] 【枡掛(け)筋】
掌(テノヒラ)の中央を横に貫くすじ。手相術で長寿の相とされる。枡掛け紋。ますかけ。
ます-がた【枡形・升形・斗形】🔗⭐🔉
ます-がた [0] 【枡形・升形・斗形】
(1)枡のような四角い形。
(2)「ます(斗)」に同じ。
(3)直角に設けられた二つの城門と城壁とで囲まれた四角い空き地。敵の直進をさまたげ,勢いを鈍らせる。
→枡形門
枡形(3)
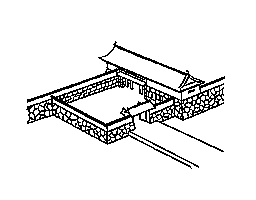 [図]
[図]
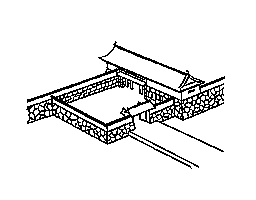 [図]
[図]
ますがた-ぼん【枡形本】🔗⭐🔉
ますがた-ぼん [0] 【枡形本】
正方形またはそれに近い形の本。鳥の子紙などの和紙を四つ折りにした四半本,六つ折りにした六半本などがある。約15センチメートル四方。
ますがた-もん【枡形門】🔗⭐🔉
ますがた-もん [4] 【枡形門】
城の入り口の形式の一。城門の内側に L 字形の城壁を設け,あいている辺に城門を構え,曲輪(クルワ)内にはいるのに二つの門を通るようにしたもの。多く外には高麗(コウライ)門,内には櫓(ヤグラ)門が設けられる。
ます-くさ【枡草】🔗⭐🔉
ます-くさ [0] 【枡草】
カヤツリグサの別名。茎を両端から裂くと四角形ができるのでいう。
ます-ぐみ【枡組(み)・斗組(み)】🔗⭐🔉
ます-ぐみ [0] 【枡組(み)・斗組(み)】
(1)障子・襖(フスマ)などの骨を四角に組むこと。また,組んだもの。
(2)「斗 (トキヨウ)」に同じ。
(トキヨウ)」に同じ。
 (トキヨウ)」に同じ。
(トキヨウ)」に同じ。
ます-ざ【枡座・升座】🔗⭐🔉
ます-ざ [0] 【枡座・升座】
江戸時代,幕府が枡の製造・販売などをさせた世襲の独占業者。江戸の樽屋氏,京の福井氏。
ます-ざけ【枡酒・升酒】🔗⭐🔉
ます-ざけ [0] 【枡酒・升酒】
(1)枡についだ酒。
(2)枡売りの酒。
ます-ずきん【枡頭巾】🔗⭐🔉
ます-ずきん ―ヅキン [3][4] 【枡頭巾】
枡のような四角い頭巾。
ます-せき【枡席・升席】🔗⭐🔉
ます-せき [0] 【枡席・升席】
「枡{(3)}」に同じ。
ます-づか【枡束・升束・斗束】🔗⭐🔉
ます-づか [0][2] 【枡束・升束・斗束】
「斗束(トヅカ)」に同じ。
ます-め【枡目・升目】🔗⭐🔉
ます-め [0][3] 【枡目・升目】
(1)枡ではかった量。「―が足りない」
(2)枡形の模様・枠・欄など。「原稿用紙の―」
ますめ【枡目】(和英)🔗⭐🔉
大辞林に「枡」で始まるの検索結果 1-24。