複数辞典一括検索+![]()
![]()
さん【算】🔗⭐🔉
さん [1] 【算】
(1)占いに用いる算木(サンギ)。また,占い。
(2)昔,中国から渡来した計算用具。長方形の小木片,二七一枚を集めたもの。
(3)計算。勘定。「たとへ―があうても/浄瑠璃・重井筒(上)」
(4)そろばん。
さん=を置・く🔗⭐🔉
――を置・く
(1)算木で計算する。
(2)算木で占う。
さん=を散ら・す🔗⭐🔉
――を散ら・す
「算を乱す」に同じ。「楯は―・したる様にさんざんに蹴ちらさる/平家 11」
さん=を乱・す🔗⭐🔉
――を乱・す
算木を乱したように散乱する。ちりぢりばらばらになる。算を散らす。
さん-おき【算置き】🔗⭐🔉
さん-おき 【算置き】
算木を使って占うこと。また,それを職とする人。易者。「安倍の外記といへる世界見通しの―が申せしは/浮世草子・一代男 4」
さん-が【算賀】🔗⭐🔉
さん-が [1] 【算賀】
長寿の祝賀。賀の祝い。四〇歳から始めて10年ごとに行う。中国伝来の慣習で,のちには六十一(還暦),七十七(喜寿),八十八(米寿)なども祝う。
さん-がく【算学】🔗⭐🔉
さん-がく [0] 【算学】
数値計算についての学問。算数。数学。「―ヲスル/ヘボン」
さん-がく【算額】🔗⭐🔉
さん-がく [0] 【算額】
和算家が自己の作った数学の問題や解答を書いて,神社・寺院などに奉納した絵馬。額面題。
さんがくけいもう【算学啓蒙】🔗⭐🔉
さんがくけいもう 【算学啓蒙】
数学書。中国,元の朱世傑(シユセイケツ)著。三巻。1299年刊。朝鮮で重刊され,文禄・慶長の役の頃,日本にも伝えられ,和算の発展に大きな影響を与えた。
さん-かん【算勘】🔗⭐🔉
さん-かん 【算勘】
(1)数量を数えること。数の勘定。計算。「知らぬ者の是程まで,―商読書の/浄瑠璃・五十年忌(中)」
(2)算木の占いによって考えること。
さんかん-じゃ【算勘者】🔗⭐🔉
さんかん-じゃ 【算勘者】
計算にたくみな人。[日葡]
さん-ぎ【算木】🔗⭐🔉
さん-ぎ [1][3] 【算木】
(1)易で占いに使う長さ約9センチメートルの正方柱体の木。六本を一組みとする。筮竹(ゼイチク)を操作して得た卦(ケ)の形に並べて判断する。
(2)和算で用いる計算用具。木製の小さな角棒。算籌(サンチユウ)。
算木(1)
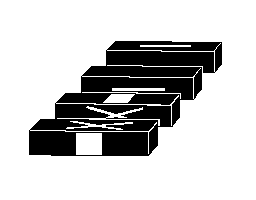 [図]
[図]
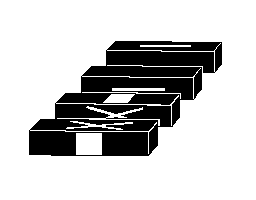 [図]
[図]
さんぎ-ぜめ【算木責め】🔗⭐🔉
さんぎ-ぜめ [0] 【算木責め】
「石抱き」に同じ。
さんぎ-づみ【算木積み】🔗⭐🔉
さんぎ-づみ [0] 【算木積み】
石垣の出角(デスミ)を積む石積み法の一。直方体に加工した石を用い,石の長辺を石垣の角の両面に交互に出すように積む。
さんぎ-もち【算木餅】🔗⭐🔉
さんぎ-もち [3] 【算木餅】
算木の形に切った餅。算餅。
さん-くずし【算崩し・三崩し】🔗⭐🔉
さん-くずし ―クヅシ [3] 【算崩し・三崩し】
縦の三筋と横の三筋を市松状に配した模様。算木崩し。
さん-けい【算計】🔗⭐🔉
さん-けい [0] 【算計】 (名)スル
(1)数量を数えはかること。勘定。計算。「斤両は百六十匁を以て―すべき事/新聞雑誌 49」
(2)起こりそうなことを予想し,考えに入れておくこと。「偶然の事を仔細(シサイ)に―する人なり/西国立志編(正直)」
さん-し【算師】🔗⭐🔉
さん-し [1] 【算師】
律令制下の下級の官人。主計寮・主税寮・大宰府に置かれて計算を担当した。
さん-しき【算式】🔗⭐🔉
さん-しき [0] 【算式】
加減乗除などの記号を用いて,計算の順序・方法を表した式。
さん-しゃ【算者】🔗⭐🔉
さん-しゃ 【算者】
計算の上手な人。「年波のせはしき世の事,―も是をつもれり/浮世草子・永代蔵 5」
さん-しゅつ【算出】🔗⭐🔉
さん-しゅつ [0] 【算出】 (名)スル
計算して数値を出すこと。「見積もり額を―する」
さん-じゅつ【算術】🔗⭐🔉
さん-じゅつ [0] 【算術】
〔arithmetic〕
(1)正の整数・小数・分数および量についての計算を中心とする初等数学。
(2)旧制の小学校における教科名。
(3)中国および近世の日本で,数学の総称。
さんじゅつ-きゅうすう【算術級数】🔗⭐🔉
さんじゅつ-きゅうすう ―キフ― [5][7] 【算術級数】
⇒等差級数(トウサキユウスウ)
さんじゅつ-へいきん【算術平均】🔗⭐🔉
さんじゅつ-へいきん [5] 【算術平均】
「相加(ソウカ)平均」に同じ。
⇔幾何平均
さん-すう【算数】🔗⭐🔉
さん-すう [3] 【算数】
(1)かぞえること。計算すること。また,損得などをはかること。「其の子肆孫店に至つては―す可からず/東京新繁昌記(撫松)」
(2)小学校の教科名。数学の初歩を教える。昭和16年,それまでの「算術」を改めたもの。
(3)「数学」に同じ。算学。
さん・する【算する】🔗⭐🔉
さん・する [3] 【算する】 (動サ変)[文]サ変 さん・す
かぞえる。かぞえて,ある数値を得る。「聴衆は一万を―・する」
さん-だん【算段】🔗⭐🔉
さん-だん [1][3] 【算段】 (名)スル
あれこれと手段・方法を考えること。特に,工夫して必要な金をそろえること。工面。やりくり。「金を―する」「くるしい―にてもとめたる袖時計/安愚楽鍋(魯文)」
さん-ちゅう【算籌】🔗⭐🔉
さん-ちゅう ―チウ [0] 【算籌】
「算木(サンギ){(2)}」に同じ。
さん-てい【算定】🔗⭐🔉
さん-てい [0] 【算定】 (名)スル
計算してはっきりと数字に表すこと。「米の価格を―する」「―基準」
さんてい-ふうたい【算定風袋】🔗⭐🔉
さんてい-ふうたい [5] 【算定風袋】
あらかじめ重量のわかっている風袋。計算風袋。見積もり風袋。
さん-とう【算当】🔗⭐🔉
さん-とう ―タウ [0] 【算当】 (名)スル
勘定すること。また,勘定をしておよその見当をつけること。「其数少なくして―に合はぬなり/学問ノススメ(諭吉)」
さん-どう【算道】🔗⭐🔉
さん-どう ―ダウ [0] 【算道】
(1)計算の方法。算術。算法。
(2)律令制における大学で教えた学科の一。算術を修める学問。
さん-にゅう【算入】🔗⭐🔉
さん-にゅう ―ニフ [0] 【算入】 (名)スル
計算に加えること。一緒にして計算すること。「給料には残業料分も―してある」
さん-にょう【算用】🔗⭐🔉
さん-にょう ―ヨウ 【算用】
「さんよう(算用)」の連声。
さん-はかせ【算博士】🔗⭐🔉
さん-はかせ [3] 【算博士】
律令制で,大学寮で算術を教授する教官。平安時代以後,三善・小槻(オヅキ)二氏の世襲。
さん-ばん【算盤】🔗⭐🔉
さん-ばん [0] 【算盤】
(1)和算の計算器具。盤上に縦横に線を引いて作った正方形の中に算木を置いて計算をする。
(2)そろばん。
さん-ぴつ【算筆】🔗⭐🔉
さん-ぴつ [0] 【算筆】
勘定と読み書き。読み書き算盤(ソロバン)。
さん-ふ【算賦】🔗⭐🔉
さん-ふ [1][0] 【算賦】
中国,秦・漢代に行われた人頭税。一五歳以上五六歳までの男女に課され,国家の重要な財源であった。
さん-ぽう【算法】🔗⭐🔉
さん-ぽう ―パフ [1][0] 【算法】
(1)計算の方法。また,計算の規則。
(2)江戸時代,数学のこと。
さん-よう【算用】🔗⭐🔉
さん-よう [0] 【算用】 (名)スル
〔古くは「さんにょう」とも〕
(1)計算すること。勘定。また,算術。「いやまづおまちやれ,―しなおいてみ申さう/狂言・賽の目」
(2)勘定を払うこと。清算すること。「これも近々には―致しまする/狂言・千鳥(虎寛本)」
(3)見積もりを立てること。予想。目算。「五十年の月日にわたるも百年の―にはあふべきをや/鶉衣」
さんよう-あい【算用合ひ】🔗⭐🔉
さんよう-あい ―アヒ 【算用合ひ】
収支決算。また,計算。帳合い。「いかに親子の中でも,たがひの―はきつとしたがよい/浮世草子・胸算用 1」
さんよう-じょう【算用状】🔗⭐🔉
さんよう-じょう ―ジヤウ [0] 【算用状】
中世,個々の荘園に関する年間の収支決算報告書。
さんよう-すうじ【算用数字】🔗⭐🔉
さんよう-すうじ [5] 【算用数字】
数字 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 ・ 9 ・ 0 のこと。本来筆算に用いる数字だったところからいう。アラビア数字。
さんよう-なし【算用無し】🔗⭐🔉
さんよう-なし 【算用無し】
見積もりも立てず,収支決算もしないこと。成り行きまかせ。また,その人。「大神宮にも―に物つかふ人うれしくは思しめさず/浮世草子・胸算用 1」
さん-れき【算暦】🔗⭐🔉
さん-れき [0] 【算暦】
算法と暦法。
そろばん【算盤・十露盤】🔗⭐🔉
そろばん [0] 【算盤・十露盤】
(1)日本・中国などで使用される簡単な計算器。横長で底の浅い長方形の枠に珠(タマ)を数個貫いた軸を縦に何本も並べたもの。軸のそれぞれが桁(ケタ)を表し,珠の上下の位置でそれぞれの桁の数値を表し,珠を指で上下させることにより四則演算が行える。日本には室町末期に中国より伝来したといわれる。
(2)損得についての計算。「この仕事は―抜きでやっています」
〔唐音「そわんぱあん」の転という〕
そろばん=が合・う🔗⭐🔉
――が合・う
計算が合う。採算が合う。
そろばん=が持て ない🔗⭐🔉
ない🔗⭐🔉
――が持て ない
損益計算をして,利益がない。そろばんが合わない。
ない
損益計算をして,利益がない。そろばんが合わない。
 ない
損益計算をして,利益がない。そろばんが合わない。
ない
損益計算をして,利益がない。そろばんが合わない。
そろばん=の玉はずれ🔗⭐🔉
――の玉はずれ
そろばんで計算した分以外の金。帳簿に記入されない余分な金。
そろばん=を置・く🔗⭐🔉
――を置・く
そろばんで計算する。損得の計算をする。
そろばん=を弾(ハジ)・く🔗⭐🔉
――を弾(ハジ)・く
(1)そろばんの玉を弾いて計算する。
(2)損得の計算をする。
そろばん=を枕(マクラ)にする🔗⭐🔉
――を枕(マクラ)にする
商人が,寝る間もそろばんを身辺から離さないで商売にうちこむさまの形容。
そろばん-うらない【算盤占い】🔗⭐🔉
そろばん-うらない ―ナヒ [5] 【算盤占い】
そろばんを使って吉凶を判断すること。算易。
そろばん-かんじょう【算盤勘定】🔗⭐🔉
そろばん-かんじょう ―ヂヤウ [5] 【算盤勘定】
そろばんで利得を計算すること。損得についての勘定。
そろばん-ぎ【算盤木】🔗⭐🔉
そろばん-ぎ [3] 【算盤木】
〔建〕 基礎杭上に架け渡した横木。
そろばん-さで【算盤桟手】🔗⭐🔉
そろばん-さで [3] 【算盤桟手】
木材運搬装置の一。小丸太を横に並べ,その両側に側木として二本の丸太をおいたもの。運搬する木材は小丸太の上をすべらせる。
そろばん-しぼり【算盤絞り】🔗⭐🔉
そろばん-しぼり [5] 【算盤絞り】
そろばんの珠をならべたような模様の絞り染め。手拭いに多く使用された。
そろばん-ずく【算盤尽く】🔗⭐🔉
そろばん-ずく ―ヅク [0] 【算盤尽く】
何でも損得を計算して,損にならないようにすること。勘定高いこと。勘定ずく。損得ずく。「―ではできない仕事だ」
そろばん-ぜめ【算盤責め】🔗⭐🔉
そろばん-ぜめ [0] 【算盤責め】
「石抱(イシダ)き」に同じ。
そろばん-だま【算盤玉】🔗⭐🔉
そろばん-だま [0] 【算盤玉】
(1)そろばんの軸に貫いてある珠。
(2)損得の計算。勘定。「
 (ドウ)いふ―でせうな,日鉄だけでも大分のものだが/社会百面相(魯庵)」
(ドウ)いふ―でせうな,日鉄だけでも大分のものだが/社会百面相(魯庵)」

 (ドウ)いふ―でせうな,日鉄だけでも大分のものだが/社会百面相(魯庵)」
(ドウ)いふ―でせうな,日鉄だけでも大分のものだが/社会百面相(魯庵)」
そろばん-だか・い【算盤高い】🔗⭐🔉
そろばん-だか・い [6] 【算盤高い】 (形)
金銭の計算に細かい。打算的だ。勘定高い。「―・い人」
[派生] ――さ(名)
さんじゅつ【算術】(和英)🔗⭐🔉
さんじゅつ【算術】
arithmetic.→英和
〜をする do sums.
さんすう【算数】(和英)🔗⭐🔉
さんようすうじ【算用数字】(和英)🔗⭐🔉
さんようすうじ【算用数字】
an Arabic figure[numeral].
そろばん【算盤】(和英)🔗⭐🔉
大辞林に「算」で始まるの検索結果 1-69。