複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (67)
さん【算】🔗⭐🔉
さん‐おき【算置】🔗⭐🔉
さん‐おき【算置】
算木でうらなうこと。また、その人。狂言、居杭「イヤ、是へ―が参る」
さん‐が【算賀】🔗⭐🔉
さん‐が【算賀】
長寿を祝う儀。賀の祝。40歳から始めて10歳長ずるごとに行う。後には還暦・古稀・喜寿・米寿などの祝も行う。
さん‐がく【算学】🔗⭐🔉
さん‐がく【算学】
算数の学。数学。
さん‐がく【算額】🔗⭐🔉
さん‐がく【算額】
和算家が自分の発見した数学の問題や解法を書いて神社などに奉納した絵馬。額面題。
さん‐かん【算勘】🔗⭐🔉
さん‐かん【算勘】
①占い考えること。東鑑36「陰陽道の輩を召さるるの上、参河守教隆―に及ぶ」
②数の勘定。計算。狂言、賽の目「何者には寄るまい、―に達した者を婿に取らう」→算。
⇒さんかん‐じゃ【算勘者】
さんかん‐じゃ【算勘者】🔗⭐🔉
さんかん‐じゃ【算勘者】
計算の達者。〈日葡辞書〉
⇒さん‐かん【算勘】
さん‐ぎ【算木】🔗⭐🔉
さん‐ぎ【算木】
①易えきで爻こうを組み合わせて卦けの形を表す具。長さ約10センチメートルの正方柱体の6個1組の木で、四面はそれぞれ図のような形をなす。
算木
 ②和算で用いる計算用具。長さ3センチメートル余の材で、盤上に並べて数を表し、配列を動かして四則・開平・開立等の計算をする。中国では算・策・籌などと呼び、日本でも奈良時代から室町時代まで計算用具として使用。また、中国で宋・元時代以降はこれを用いて高次方程式を解くことを始め、日本でも、江戸時代にはもっぱらその目的のために用いた。算籌さんちゅう。
⇒さんぎ‐もち【算木餅】
②和算で用いる計算用具。長さ3センチメートル余の材で、盤上に並べて数を表し、配列を動かして四則・開平・開立等の計算をする。中国では算・策・籌などと呼び、日本でも奈良時代から室町時代まで計算用具として使用。また、中国で宋・元時代以降はこれを用いて高次方程式を解くことを始め、日本でも、江戸時代にはもっぱらその目的のために用いた。算籌さんちゅう。
⇒さんぎ‐もち【算木餅】
 ②和算で用いる計算用具。長さ3センチメートル余の材で、盤上に並べて数を表し、配列を動かして四則・開平・開立等の計算をする。中国では算・策・籌などと呼び、日本でも奈良時代から室町時代まで計算用具として使用。また、中国で宋・元時代以降はこれを用いて高次方程式を解くことを始め、日本でも、江戸時代にはもっぱらその目的のために用いた。算籌さんちゅう。
⇒さんぎ‐もち【算木餅】
②和算で用いる計算用具。長さ3センチメートル余の材で、盤上に並べて数を表し、配列を動かして四則・開平・開立等の計算をする。中国では算・策・籌などと呼び、日本でも奈良時代から室町時代まで計算用具として使用。また、中国で宋・元時代以降はこれを用いて高次方程式を解くことを始め、日本でも、江戸時代にはもっぱらその目的のために用いた。算籌さんちゅう。
⇒さんぎ‐もち【算木餅】
さんぎ‐もち【算木餅】🔗⭐🔉
さんぎ‐もち【算木餅】
算木の形に切った長方形の餅。算餅。
⇒さん‐ぎ【算木】
さん‐くずし【算崩し】‥クヅシ🔗⭐🔉
さん‐くずし【算崩し】‥クヅシ
(算木崩しの意)三筋ずつ縦横に石畳いしだたみにした縞、または文様。あじろぐみ。日本永代蔵5「手織の―の木綿袷一つ」
さん‐けい【算計】🔗⭐🔉
さん‐けい【算計】
数量をかぞえはかること。勘定。計算。
さん‐けい【算経】🔗⭐🔉
さん‐けい【算経】
数学書のこと。中国および和算で用いる。
⇒さんけい‐じっしょ【算経十書】
さんけい‐じっしょ【算経十書】🔗⭐🔉
さんけい‐じっしょ【算経十書】
中国の唐の時代に教科書として使用した、唐およびそれ以前の数学書10種。すなわち「周髀算経」「九章算術」「海島算経」「孫子算経」「五曹算経」「夏侯陽算経」「張邱建算経」「五経算術」「綴術」「緝古算経」。
⇒さん‐けい【算経】
さん‐し【算師】🔗⭐🔉
さん‐し【算師】
律令制で、主税寮・主計寮などに置かれた役人。計算に従事する。
さん‐しき【算式】🔗⭐🔉
さん‐しき【算式】
加減乗除の符号を用いて演算の順序・方法を表した式。
さん‐じゃ【算者】🔗⭐🔉
さん‐じゃ【算者】
(サンシャとも)算術の達人。狂言、賽の目「こなたは殊の外の―で御座る」
さん‐しゅつ【算出】🔗⭐🔉
さん‐しゅつ【算出】
計算して求める数値を出すこと。「経費を―する」
さん‐じゅつ【算術】🔗⭐🔉
さん‐じゅつ【算術】
(arithmetic)記数法・四則算法・分数・比例等を取り扱う初等数学。また、もと小学校における教科名。古くは数学全般と同義。中国の「九章算術」(1世紀)以来、近世までこの意味に用いられた。→算数。
⇒さんじゅつ‐きゅうすう【算術級数】
⇒さんじゅつ‐すうれつ【算術数列】
⇒さんじゅつ‐へいきん【算術平均】
さんじゅつ‐きゅうすう【算術級数】‥キフ‥🔗⭐🔉
さんじゅつ‐きゅうすう【算術級数】‥キフ‥
(→)等差級数に同じ。
⇒さん‐じゅつ【算術】
さんじゅつ‐すうれつ【算術数列】🔗⭐🔉
さんじゅつ‐すうれつ【算術数列】
(→)等差数列のこと。
⇒さん‐じゅつ【算術】
さんじゅつ‐へいきん【算術平均】🔗⭐🔉
さんじゅつ‐へいきん【算術平均】
(→)相加平均に同じ。
⇒さん‐じゅつ【算術】
さん‐すう【算数】🔗⭐🔉
さん‐すう【算数】
①かぞえること。計算。「その数、―すべからず」
②江戸時代には数学と同義。明治時代には算術と同義。
③小学校の教科の一つ。数量や図形の基礎的知識・技能の習得や論理的思考力の育成などを目的とする。数学教育の小学校段階での名称。算術に代わり1941年から使用。
さん・する【算する】🔗⭐🔉
さん・する【算する】
〔他サ変〕[文]算す(サ変)
①かぞえる。計算する。
②ある数に達する。「応募者は2万を―・した」
さん‐だん【算段】🔗⭐🔉
さん‐だん【算段】
手段を工夫すること。特に、金銭を工面くめんすること。「―がつく」「やりくり―」「無理―」
さん‐ちゅう【算籌】‥チウ🔗⭐🔉
さん‐ちゅう【算籌】‥チウ
(→)算木さんぎに同じ。
さん‐てい【算定】🔗⭐🔉
さん‐てい【算定】
計算して数字を確定すること。「改装費を―する」「―基準」
⇒さんてい‐ふうたい【算定風袋】
さんてい‐ふうたい【算定風袋】🔗⭐🔉
さんてい‐ふうたい【算定風袋】
貨物売買の際、総重量から引き去るために、あらかじめ重量を算定してある風袋。
⇒さん‐てい【算定】
さん‐とう【算当】‥タウ🔗⭐🔉
さん‐とう【算当】‥タウ
算かぞえて見当をつけること。見積り。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「愛は献身的也などと絶叫するのも、此際の―でありませう」
⇒さんとう‐ちがい【算当違い】
さん‐どう【算道】‥ダウ🔗⭐🔉
さん‐どう【算道】‥ダウ
①平安時代の大学寮の四道の一つ。算博士が算生に算術を教授。
②数を計算する法。算法。算術。
さんとう‐ちがい【算当違い】‥タウチガヒ🔗⭐🔉
さんとう‐ちがい【算当違い】‥タウチガヒ
算当をまちがえること。誤算。
⇒さん‐とう【算当】
○算無しさんなし🔗⭐🔉
○算無しさんなし
計算しきれない。極めて多い。
⇒さん【算】
ざん‐な・し【慙なし】
〔形ク〕
①無慙である。むごい。浄瑠璃、傾城島原蛙合戦「おお―・い仏様や」
②見苦しい。だらしない。浮世草子、好色産毛「見せぬ所をわざくれと―・いなりにぞ見えにける」
さん‐なん【三難】
①三種の難儀。
②〔仏〕三悪道さんあくどうの苦難。
さん‐に【散位】‥ヰ
(サンイの連声)律令制で、位階だけあって官職についていない者。蔭位おんいにより官位があって、役職のない者、または職を辞した者などの称。散官。散事。続日本紀天平3年3月22日「―従四位下日下部宿祢老卒」。今昔物語集25「―橘遠保と云ふ者」
⇒さんに‐りょう【散位寮】
さん‐にち【散日】
〔仏〕法会ほうえの結願けちがんの日。満散。
さん‐にゅう【参入】‥ニフ
①高貴の所にまいること。入って行くこと。参上。
②加わること。参加すること。「他の業界に―する」
⇒さんにゅう‐おんじょう【参入音声】
さん‐にゅう【算入】‥ニフ
計算に加えること。数に入れること。「予算に―する」
ざん‐にゅう【竄入】‥ニフ
①にげこむこと。
②誤って入りまじること。まぎれこむこと。
さんにゅう‐いんりょう【酸乳飲料】‥レウ
(→)乳酸菌飲料に同じ。
さんにゅう‐おんじょう【参入音声】‥ニフ‥ジヤウ
(→)「まいりおんじょう」に同じ。長秋詠藻「辰日―、鏡山」
⇒さん‐にゅう【参入】
さん‐にょう【算用】‥ヨウ
サンヨウの連声。
ざん‐にょう【残尿】‥ネウ
排尿後もまだ膀胱ぼうこう内に尿が残ること。また、その尿。「―感」
さん‐にょらい【三如来】
三国伝来の三体の如来像。長野善光寺の阿弥陀如来、京都嵯峨清涼寺の釈迦如来、京都因幡堂の薬師如来。
さんに‐りょう【散位寮】‥ヰレウ
律令制で、式部省に属し、散位の文武官を総管する役所。
⇒さん‐に【散位】
さん‐にん【三人】
人の数が3であること。
⇒さんにん‐かんじょ【三人官女】
⇒さんにん‐ぐみ【三人組】
⇒さんにん‐ごし【三人輿】
⇒さんにん‐じょうご【三人上戸】
⇒さんにん‐づかい【三人遣い】
⇒さんにん‐ばり【三人張】
⇒三人旅の一人乞食
⇒三人虎を成す
⇒三人寄れば公界
⇒三人寄れば文殊の知恵
ざん‐にん【残忍】
するに忍びない無慈悲な行いを平気ですること。慈悲心の少しもないこと。「―な性質」
さんにんかたわ【三人片輪】
(サンニンガタワとも)
①狂言。座頭などを装った3人の者が富豪に召し抱えられ、その留守中酒倉をあけて大いに飲み、歌い舞う。主人が帰り3人はあわてて、各自の役を取り違える。
②歌舞伎脚本。河竹黙阿弥作の世話物「繰返開化婦見月くりかえすかいかのふみづき」の通称。
③舞踊劇。常磐津・長唄。竹柴其水作。1の劇化。
さんにん‐かんじょ【三人官女】‥クワンヂヨ
雛ひな人形で、官女の姿をした三つ一組の人形。
⇒さん‐にん【三人】
さんにんきちさ【三人吉三】
歌舞伎脚本「三人吉三廓初買くるわのはつがい」の通称。8幕。河竹黙阿弥作の世話物。1860年(安政7)初演。お坊吉三・和尚吉三・お嬢吉三の3人の間に、百両の金と庚申丸の短刀とをめぐって起こる事件を脚色。
→文献資料[三人吉三廓初買]
さんにん‐ぐみ【三人組】
三人が一組になること。トリオ。「お笑い―」
⇒さん‐にん【三人】
さんにん‐ごし【三人輿】
三人で舁かく輿。
⇒さん‐にん【三人】
さんにんしまい【三人姉妹】
チェーホフ作の戯曲。1901年モスクワ芸術座初演。地方都市に住む故旅団長の娘3人を中心に、変わらない現状と変化への憧れを静かに訴える。
さん‐にんしょう【三人称】
話し手・聞き手以外の第三者を指示する人称。「かれ」「それ」の類。他称。
さんにん‐じょうご【三人上戸】‥ジヤウ‥
怒り上戸と泣き上戸と笑い上戸。
⇒さん‐にん【三人】
さん‐にゅう【算入】‥ニフ🔗⭐🔉
さん‐にゅう【算入】‥ニフ
計算に加えること。数に入れること。「予算に―する」
さん‐にょう【算用】‥ヨウ🔗⭐🔉
さん‐にょう【算用】‥ヨウ
サンヨウの連声。
さん‐はかせ【算博士】🔗⭐🔉
さん‐はかせ【算博士】
律令制の大学寮で算術の教授にあたった教官。後世、三善・小槻おづき2氏の世職。
さん‐ばん【算盤】🔗⭐🔉
さん‐ばん【算盤】
①(→)「そろばん」1に同じ。
②算木をその上に並べ、高次方程式を解く計算をするための盤。和算で使用した。木・布・紙などで作り、盤面に縦横の碁盤目を引き、方程式の次数と係数の大きさを明示するのに役立たせる。
さん‐ぴつ【算筆】🔗⭐🔉
さん‐ぴつ【算筆】
算術と習字。計算と読み書き。
さん‐ぷ【算賦】🔗⭐🔉
さん‐ぷ【算賦】
中国、秦・漢時代の主要な税。銭納の人頭税。このほかに財産税(貲算しせん)があったという説もある。算銭。
さん‐ぶくろ【算袋】🔗⭐🔉
さん‐ぶくろ【算袋】
①算木を入れる袋。狂言、居杭「まだ―のひもをしめてそこへ手もやりは致さぬ」
②魚袋ぎょたいの別称。
さん‐ぽう【算法】‥パフ🔗⭐🔉
さん‐ぽう【算法】‥パフ
①計算の方法。算術。演算。狂言、賽の目「―を御存じないさうに御座る」
②(→)アルゴリズムに同じ。
③江戸時代、「数学」をいう語。
さんぽうとうそう【算法統宗】‥パフ‥🔗⭐🔉
さんぽうとうそう【算法統宗】‥パフ‥
明の数学者程大位の著。1593年(万暦21)頃刊。17巻。算盤による計算法を扱う。和算の実用的な面に強い影響を与えた。「塵劫記」は、これを日本の実情に合わせて平易に解説したもの。
さん‐めい【算命】🔗⭐🔉
さん‐めい【算命】
占いの一種。人の生年月日の干支などによって、運命・吉凶をうらなうもの。
さん‐よう【算用・散用】🔗⭐🔉
さん‐よう【算用・散用】
(連声でサンニョウとも)
①数を計算すること。勘定。日本永代蔵1「とかくは合はぬ―」
②支払い。清算。狂言、胸突「又例の―の事でわせたものであらう。逢うてはむつかしい」
③みつもり。目算。世間胸算用3「かねての―には十五両の心あて」
⇒さんよう‐あい【算用合い】
⇒さんよう‐じょう【算用状・散用状】
⇒さんよう‐すうじ【算用数字】
⇒さんよう‐だか・い【算用高い】
⇒さんよう‐だて【算用立て】
⇒さんよう‐ちがい【算用違い】
⇒さんよう‐なし【算用無し】
⇒さんよう‐ば【算用場】
さんよう‐あい【算用合い】‥アヒ🔗⭐🔉
さんよう‐あい【算用合い】‥アヒ
算用して数を合わせること。帳合。世間胸算用1「去りながらいかに親子の中でも、たがひの―は急度きっとしたがよい」
⇒さん‐よう【算用・散用】
さんよう‐じょう【算用状・散用状】‥ジヤウ🔗⭐🔉
さんよう‐じょう【算用状・散用状】‥ジヤウ
中世、収支計算書のこと。
⇒さん‐よう【算用・散用】
さんよう‐すうじ【算用数字】🔗⭐🔉
さんよう‐すうじ【算用数字】
筆算に使用する数字。アラビア数字。0・1・2・3・…・9の数字。
⇒さん‐よう【算用・散用】
さんよう‐だか・い【算用高い】🔗⭐🔉
さんよう‐だか・い【算用高い】
〔形〕
勘定高い。けちである。
⇒さん‐よう【算用・散用】
さんよう‐だて【算用立て】🔗⭐🔉
さんよう‐だて【算用立て】
勘定の吟味。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「―も申しにくし」
⇒さん‐よう【算用・散用】
さんよう‐ちがい【算用違い】‥チガヒ🔗⭐🔉
さんよう‐ちがい【算用違い】‥チガヒ
①計算ちがい。
②考え違い。誤った考え。
⇒さん‐よう【算用・散用】
さんよう‐なし【算用無し】🔗⭐🔉
さんよう‐なし【算用無し】
金銭に関して、向うみずなこと。日本永代蔵2「俄かに金銀を費し、―の色遊び」
⇒さん‐よう【算用・散用】
さんよう‐ば【算用場】🔗⭐🔉
さんよう‐ば【算用場】
算用する所。帳場。浄瑠璃、大経師昔暦「―には手代ども」
⇒さん‐よう【算用・散用】
さん‐れき【算暦】🔗⭐🔉
さん‐れき【算暦】
算法と暦法。
○算を置くさんをおく🔗⭐🔉
○算を置くさんをおく
①算木で計算する。
②算木でうらなう。
⇒さん【算】
○算を乱すさんをみだす🔗⭐🔉
○算を乱すさんをみだす
(人の集団が)算木を乱したように無秩序に散らばる。「算を乱して敗走する」
⇒さん【算】
そろばん【算盤・十露盤】🔗⭐🔉
そろばん【算盤・十露盤】
①計算器の一種。横長浅底の箱に横に梁を設け、これを貫いて縦に串を渡し、串に5個ないし7個の珠たまを貫く。珠は梁上に1個(もしくは2個)あって1個で5を表し、梁下に5個(現在では主に4個)あって1個で1を表す。この珠を上下して加減乗除をする。中国の発明で宋末から元代に行われ、日本へは室町末期頃伝来したらしく、文禄(1592〜1596)年間の記録と実物が現存する。
算盤(梁上二珠)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 ②勘定。計算。採算。
⇒そろばん‐うらない【算盤占い】
⇒そろばん‐かんじょう【算盤勘定】
⇒そろばん‐ぎ【算盤木】
⇒そろばん‐しぼり【十露盤絞り】
⇒そろばん‐ずく【算盤尽】
⇒そろばん‐ぜめ【算盤責め】
⇒そろばん‐だか・い【算盤高い】
⇒そろばん‐だま【算盤珠】
⇒算盤が合う
⇒算盤が持てぬ
⇒算盤の玉はずれ
⇒算盤をおく
⇒算盤をはじく
②勘定。計算。採算。
⇒そろばん‐うらない【算盤占い】
⇒そろばん‐かんじょう【算盤勘定】
⇒そろばん‐ぎ【算盤木】
⇒そろばん‐しぼり【十露盤絞り】
⇒そろばん‐ずく【算盤尽】
⇒そろばん‐ぜめ【算盤責め】
⇒そろばん‐だか・い【算盤高い】
⇒そろばん‐だま【算盤珠】
⇒算盤が合う
⇒算盤が持てぬ
⇒算盤の玉はずれ
⇒算盤をおく
⇒算盤をはじく
 ②勘定。計算。採算。
⇒そろばん‐うらない【算盤占い】
⇒そろばん‐かんじょう【算盤勘定】
⇒そろばん‐ぎ【算盤木】
⇒そろばん‐しぼり【十露盤絞り】
⇒そろばん‐ずく【算盤尽】
⇒そろばん‐ぜめ【算盤責め】
⇒そろばん‐だか・い【算盤高い】
⇒そろばん‐だま【算盤珠】
⇒算盤が合う
⇒算盤が持てぬ
⇒算盤の玉はずれ
⇒算盤をおく
⇒算盤をはじく
②勘定。計算。採算。
⇒そろばん‐うらない【算盤占い】
⇒そろばん‐かんじょう【算盤勘定】
⇒そろばん‐ぎ【算盤木】
⇒そろばん‐しぼり【十露盤絞り】
⇒そろばん‐ずく【算盤尽】
⇒そろばん‐ぜめ【算盤責め】
⇒そろばん‐だか・い【算盤高い】
⇒そろばん‐だま【算盤珠】
⇒算盤が合う
⇒算盤が持てぬ
⇒算盤の玉はずれ
⇒算盤をおく
⇒算盤をはじく
そろばん‐うらない【算盤占い】‥ウラナヒ🔗⭐🔉
そろばん‐うらない【算盤占い】‥ウラナヒ
算盤を用いて吉凶を判断する占法。算易さんえき。
⇒そろばん【算盤・十露盤】
○算盤が合うそろばんがあう
勘定が合う。収支がつぐなう。
⇒そろばん【算盤・十露盤】
○算盤が持てぬそろばんがもてぬ
収支がつぐなわない。商売にならない。
⇒そろばん【算盤・十露盤】
○算盤が合うそろばんがあう🔗⭐🔉
○算盤が合うそろばんがあう
勘定が合う。収支がつぐなう。
⇒そろばん【算盤・十露盤】
○算盤が持てぬそろばんがもてぬ🔗⭐🔉
○算盤が持てぬそろばんがもてぬ
収支がつぐなわない。商売にならない。
⇒そろばん【算盤・十露盤】
そろばん‐かんじょう【算盤勘定】‥ヂヤウ
物事を損得の面から考えること。「―は確かだ」
⇒そろばん【算盤・十露盤】
そろばん‐ぎ【算盤木】
和風建築の基礎杭上に架け渡した横木。
⇒そろばん【算盤・十露盤】
そろばん‐しぼり【十露盤絞り】
算盤の珠を並べたような文様の絞り染。多く手拭てぬぐいに用いたので、その文様の手拭をもいう。
⇒そろばん【算盤・十露盤】
そろばん‐ずく【算盤尽】‥ヅク
何事も損得から割り出すこと。勘定高いこと。もうけずく。勘定ずく。
⇒そろばん【算盤・十露盤】
そろばん‐ぜめ【算盤責め】
石抱いしだきの別称。
⇒そろばん【算盤・十露盤】
そろばん‐だか・い【算盤高い】
〔形〕
(→)「勘定高い」に同じ。
⇒そろばん【算盤・十露盤】
そろばん‐だま【算盤珠】
①算盤の串に貫いてある珠。
②勘定。計算。
⇒そろばん【算盤・十露盤】
そろばん‐かんじょう【算盤勘定】‥ヂヤウ🔗⭐🔉
そろばん‐かんじょう【算盤勘定】‥ヂヤウ
物事を損得の面から考えること。「―は確かだ」
⇒そろばん【算盤・十露盤】
そろばん‐ぎ【算盤木】🔗⭐🔉
そろばん‐ぎ【算盤木】
和風建築の基礎杭上に架け渡した横木。
⇒そろばん【算盤・十露盤】
そろばん‐ずく【算盤尽】‥ヅク🔗⭐🔉
そろばん‐ずく【算盤尽】‥ヅク
何事も損得から割り出すこと。勘定高いこと。もうけずく。勘定ずく。
⇒そろばん【算盤・十露盤】
そろばん‐ぜめ【算盤責め】🔗⭐🔉
そろばん‐ぜめ【算盤責め】
石抱いしだきの別称。
⇒そろばん【算盤・十露盤】
そろばん‐だか・い【算盤高い】🔗⭐🔉
そろばん‐だか・い【算盤高い】
〔形〕
(→)「勘定高い」に同じ。
⇒そろばん【算盤・十露盤】
そろばん‐だま【算盤珠】🔗⭐🔉
そろばん‐だま【算盤珠】
①算盤の串に貫いてある珠。
②勘定。計算。
⇒そろばん【算盤・十露盤】
○算盤の玉はずれそろばんのたまはずれ
算盤で勘定した分以外の余分。おもてむきでない余分の金。金々先生栄花夢「―を、しこため山と出かけて」
⇒そろばん【算盤・十露盤】
○算盤をおくそろばんをおく
計算をする。商売で利害を考える。日本永代蔵2「十露盤をおかず秤目はかりめ知らぬことを悔しがりぬ」
⇒そろばん【算盤・十露盤】
○算盤をはじくそろばんをはじく
損得を考える。
⇒そろばん【算盤・十露盤】
○算盤の玉はずれそろばんのたまはずれ🔗⭐🔉
○算盤の玉はずれそろばんのたまはずれ
算盤で勘定した分以外の余分。おもてむきでない余分の金。金々先生栄花夢「―を、しこため山と出かけて」
⇒そろばん【算盤・十露盤】
○算盤をおくそろばんをおく🔗⭐🔉
○算盤をおくそろばんをおく
計算をする。商売で利害を考える。日本永代蔵2「十露盤をおかず秤目はかりめ知らぬことを悔しがりぬ」
⇒そろばん【算盤・十露盤】
○算盤をはじくそろばんをはじく🔗⭐🔉
○算盤をはじくそろばんをはじく
損得を考える。
⇒そろばん【算盤・十露盤】
そろ‐べく‐そろ【そろべく候】
(中世・近世の女性の手紙によく用いられ、草体でいいかげんに書いても読めたことから)成行き次第であること。おざなり。いいかげん。浮世草子、御前義経記「日切りまでは―の揚げづめ、心任せに遊び給へ」
そろぼ‐じる【そろぼ汁】
千六本せんろっぽんと焼味噌を使ってあつものにしたもの。せろっぽ。橘庵漫筆「せろつぽの味噌焼汁と云ふもの、京師の茶席にも用ふ、是れを、―などと、いよいよ、誤れり」
そろま【曾呂間】
①元禄前期の道化人形遣いの名人曾呂間七郎兵衛のこと。
②「そろまにんぎょう」の略。
⇒そろま‐にんぎょう【曾呂間人形】
ぞろ‐まき
(働くとき、長着物を着流したままで、裾をからげない者の意)だらしのない者。しまりのない人。ぞろっぺえ。じょぼ。びとびと。
そろま‐にんぎょう【曾呂間人形】‥ギヤウ
野呂松のろま人形の一種。
⇒そろま【曾呂間】
ぞろ‐め【ぞろ目】
二つの采さいに同じ目が出ること。
ぞろ‐め・く
〔自五〕
ぞろぞろとつづく。狂言、朝比奈「ぞろりぞろりと―・くによつて」
ソロモン【Solomon】
イスラエルの3代目の王。ダヴィデの子。経済に明るく、通商によって莫大な利を得、盛んに建築工事を行なった。その奢侈は「ソロモンの栄華」とうたわれたが、民は重税に苦しみ、王の没後、ついに国家は南北両国に分裂。(在位前961頃〜前922頃)
ソロモン‐しょとう【ソロモン諸島】‥タウ
(Solomon Islands)南太平洋のメラネシアに属する島嶼群から成る国。1978年英国より独立。住民の多数はメラネシア人。面積2万9700平方キロメートル。人口44万7千(2000)。首都はガダルカナル島のホニアラ。→オセアニア(図)
そろり
①ゆっくりと静かに行われるさま。しずしず。そろそろ。「――と動く」
②なめらかにすべるさま。するり。
ぞろり
①多くのものが、一つながりに続いているさま。ぞろぞろ。「―と並ぶ」
②衣服をくずれた感じに着流したさまにいう。
そろり‐しんざえもん【曾呂利新左衛門】‥ヱ‥
豊臣秀吉の御伽衆と伝える人物。本名、杉本甚右衛門、また坂内宗拾ともいう。堺の人。鞘師を業としたが、その鞘が刀を差し入れるとき、そろりとよく合ったことからの異名という。頓知に富み、また和歌・茶事・香技にも通じたという。生没年未詳。
ソロレート【sororate】
妻が死んだ後、その夫が妻の姉妹と再婚する制度。姉妹逆縁婚。→レビレート
ソロン【Solōn】
ギリシア七賢人の一人。アテナイの立法者で詩人。前594年アルコン(執政官)になり、財産によって市民を4等級に分けて参政権・軍務を課すなど、アテナイ社会の危機を救うために貴族と市民の間に立って改革を断行。(前640頃〜前560頃)
そわ【岨】ソハ
山の切り立った斜面。がけ。きりぎし。そば。平家物語9「一の谷、生田の森、山の―、海の汀みぎわにて射られ斬られて」。日葡辞書「ソワノカケヂ」
そわか【蘇婆訶・娑婆訶】ソハカ
〔仏〕(梵語svāhā 円満・成就などと訳す)真言陀羅尼だらにの終りにつける語。功徳あれ、成就あれなどの意。「唵おん阿毘羅吽欠あびらうんけん―」
そわ‐じ【岨路】ソハヂ
けわしい山みち。そばじ。
そわ・す【添はす】ソハス
〔他下二〕
⇒そわせる(下一)
そわ・せる【添わせる】ソハセル
〔他下一〕[文]そは・す(下二)
添うようにさせる。特に、夫婦にさせる。
そわ‐そわソハソハ
気がかりなことがあって言動が落ち着かないさま。「朝から―している」
そわ‐つ・くソハ‥
〔自五〕
そわそわと落ち着かない。色道大鏡「座中―・きたらん時は」
そわ‐づたい【岨伝い】ソハヅタヒ
けわしい山路に沿って行くこと。また、断崖に沿っていること。そばづたい。日葡辞書「ソワヅタイヲスル」
そわ‐づら【岨面】ソハ‥
けわしい山の斜面。そばづら。
そわ‐みち【岨道】ソハ‥
けわしい山道。そばみち。
そわ・る【添わる】ソハル
〔自五〕
増し加わる。つけ加わる。ふえる。古今和歌集恋「秋の露さへ置き―・りつつ」
ソワレ【soirée フランス】
①夜会。また、夜会服。
②演劇・音楽会などで夜の興行。↔マチネー
そん【村】
普通地方公共団体の一つ。むら。
そん【孫】
①まご。
②後裔。
そん【巽】
八卦はっけの一つ。☴で表す。従順卑下の徳を表す形。風にかたどり、方位では東南たつみに配する。
そん【尊】
①接頭語的に用いて、敬意を表す。
②尊貴な人。また、その敬称。
③仏像・本尊を数える語。「薬師三―」
④中国古代の酒器。祭祀の礼に用いたもの。銅器のほかに陶製・木製などもある。
尊
 そん【損】
益のなくなること。利を失うこと。「株で―をする」
⇒損がいく
そん【樽】
たる。酒だる。宇津保物語貴宮「一石入る―十に酒入れ」
ソン【son】
(スペイン語で音の意)19世紀にキューバ東部で生まれたダンス音楽。1930年代にはルンバの名で世界に紹介された。
そん‐い【巽位】‥ヰ
巽たつみすなわち南東の方角。
そん‐い【尊位】‥ヰ
とうとい位。天子の位。
そん‐い【尊威】‥ヰ
とうとい威光。御威光。
そん‐い【尊意】
他人の意思または意見の尊敬語。おぼしめし。尊慮。尊旨。
そん‐い【遜位】‥ヰ
天皇が位をゆずること。譲位。
ぞん‐い【存意】
心持のあるところ。かんがえ。存念。
そん‐いっせん【孫逸仙】
⇒そんぶん(孫文)
そん‐えい【村営】
村が経営すること。
そん‐えい【尊詠】
他人の詩歌の尊敬語。貴詠。
そん‐えい【尊影】
他人の写真または肖像などの尊敬語。
そん‐えき【損益】
①損失と利益。損得。
②へらすこととますこと。減ることと加わること。
③簿記で、損益勘定の略。
⇒そんえき‐かんじょう【損益勘定】
⇒そんえき‐けいさん‐しょ【損益計算書】
⇒そんえき‐ぶんきてん【損益分岐点】
⇒そんえき‐ほう【損益法】
そんえき‐かんじょう【損益勘定】‥ヂヤウ
簿記で、当期の純損益を計算するために、決算期末に元帳に設けられる集合勘定。借方には費用に関する諸勘定の残高が、貸方には収益に関する諸勘定の残高が集合される。貸方合計が借方合計を超過すればその差額が純利益、これと反対の場合には純損失となる。
⇒そん‐えき【損益】
そんえき‐けいさん‐しょ【損益計算書】
一会計期間における企業の経営成績を明らかにするために、その期間に属する総収益と総費用とを対応させ、当期純損益を表示した書類。損益表。利益計算書。
⇒そん‐えき【損益】
そんえき‐ぶんきてん【損益分岐点】
損益発生の分れ目となる売上高。一期間の売上高がこの額を超えて初めて、売上高に比例した利益が発生する。利益管理や原価管理に利用される。
⇒そん‐えき【損益】
そんえき‐ほう【損益法】‥ハフ
簿記で、一会計期間に属する総収益と総費用の差額を純損益とする計算方法。今日の企業会計実務はこの方法に依拠している。↔財産法
⇒そん‐えき【損益】
そんえん‐にゅうどうしんのう【尊円入道親王】‥ヱンニフダウ‥ワウ
伏見天皇の皇子。名は守彦。青蓮院しょうれんいん門主・天台座主となる。和歌に秀で、また書を世尊寺行房・行尹ゆきただに学び、小野道風・藤原行成の書法を参酌して青蓮院流(後の御家流)を開いた。著「入木抄じゅぼくしょう」。(1298〜1356)
そんえん‐りゅう【尊円流】‥ヱンリウ
書道の一派。(→)青蓮院しょうれんいん流に同じ。
そん‐おう【村翁】‥ヲウ
いなかのじいさん。村の老人。
そん‐おう【村媼】‥アウ
いなかのばあさん。村の老女。
そん‐おう【尊翁】‥ヲウ
老人の尊敬語。
そん‐か【村家】
村にある家。いなかや。
そん‐か【孫科】‥クワ
(Sun Ke)中国の政治家。孫文の先夫人の嫡子。国民政府行政院長などを歴任。(1895〜1973)
そん‐か【尊下】
書状の宛名の脇付けに用いる語。貴下。
そん‐か【尊家】
他人の家の尊敬語。おたく。貴家。多く手紙文に用いる。
そん‐かい【村会】‥クワイ
①旧制で、村の議決機関。→村議会。
②村議会の非公式の称。「―議員」
そん‐かい【損壊】‥クワイ
そこないこわすこと。また、そこないこわれること。「―家屋」
そん‐がい【損害】
そこない傷つけること。不利益をうけること。損失。「敵の―」「1億円の―」「―をこうむる」
⇒そんがい‐たんぽ‐けいやく【損害担保契約】
⇒そんがい‐ばいしょう【損害賠償】
⇒そんがい‐ほけん【損害保険】
ソンガイ【Songhai】
西アフリカのイスラム教徒ソンガイ人が建てたアフリカ最大の古王国。サハラ越え交易で栄える。16世紀末モロッコ軍の南下により滅亡。(1335〜1594)
ぞん‐がい【存外】‥グワイ
①思いがけないこと。予想と食い違うこと。意外。案外。正法眼蔵随聞記2「―の次第なり」。「―むずかしいものだ」
②もってのほかであること。無礼。ぶしつけ。懐硯ふところすずり「娘ばかりの内証に入て―せしゆへなし」
そん【損】
益のなくなること。利を失うこと。「株で―をする」
⇒損がいく
そん【樽】
たる。酒だる。宇津保物語貴宮「一石入る―十に酒入れ」
ソン【son】
(スペイン語で音の意)19世紀にキューバ東部で生まれたダンス音楽。1930年代にはルンバの名で世界に紹介された。
そん‐い【巽位】‥ヰ
巽たつみすなわち南東の方角。
そん‐い【尊位】‥ヰ
とうとい位。天子の位。
そん‐い【尊威】‥ヰ
とうとい威光。御威光。
そん‐い【尊意】
他人の意思または意見の尊敬語。おぼしめし。尊慮。尊旨。
そん‐い【遜位】‥ヰ
天皇が位をゆずること。譲位。
ぞん‐い【存意】
心持のあるところ。かんがえ。存念。
そん‐いっせん【孫逸仙】
⇒そんぶん(孫文)
そん‐えい【村営】
村が経営すること。
そん‐えい【尊詠】
他人の詩歌の尊敬語。貴詠。
そん‐えい【尊影】
他人の写真または肖像などの尊敬語。
そん‐えき【損益】
①損失と利益。損得。
②へらすこととますこと。減ることと加わること。
③簿記で、損益勘定の略。
⇒そんえき‐かんじょう【損益勘定】
⇒そんえき‐けいさん‐しょ【損益計算書】
⇒そんえき‐ぶんきてん【損益分岐点】
⇒そんえき‐ほう【損益法】
そんえき‐かんじょう【損益勘定】‥ヂヤウ
簿記で、当期の純損益を計算するために、決算期末に元帳に設けられる集合勘定。借方には費用に関する諸勘定の残高が、貸方には収益に関する諸勘定の残高が集合される。貸方合計が借方合計を超過すればその差額が純利益、これと反対の場合には純損失となる。
⇒そん‐えき【損益】
そんえき‐けいさん‐しょ【損益計算書】
一会計期間における企業の経営成績を明らかにするために、その期間に属する総収益と総費用とを対応させ、当期純損益を表示した書類。損益表。利益計算書。
⇒そん‐えき【損益】
そんえき‐ぶんきてん【損益分岐点】
損益発生の分れ目となる売上高。一期間の売上高がこの額を超えて初めて、売上高に比例した利益が発生する。利益管理や原価管理に利用される。
⇒そん‐えき【損益】
そんえき‐ほう【損益法】‥ハフ
簿記で、一会計期間に属する総収益と総費用の差額を純損益とする計算方法。今日の企業会計実務はこの方法に依拠している。↔財産法
⇒そん‐えき【損益】
そんえん‐にゅうどうしんのう【尊円入道親王】‥ヱンニフダウ‥ワウ
伏見天皇の皇子。名は守彦。青蓮院しょうれんいん門主・天台座主となる。和歌に秀で、また書を世尊寺行房・行尹ゆきただに学び、小野道風・藤原行成の書法を参酌して青蓮院流(後の御家流)を開いた。著「入木抄じゅぼくしょう」。(1298〜1356)
そんえん‐りゅう【尊円流】‥ヱンリウ
書道の一派。(→)青蓮院しょうれんいん流に同じ。
そん‐おう【村翁】‥ヲウ
いなかのじいさん。村の老人。
そん‐おう【村媼】‥アウ
いなかのばあさん。村の老女。
そん‐おう【尊翁】‥ヲウ
老人の尊敬語。
そん‐か【村家】
村にある家。いなかや。
そん‐か【孫科】‥クワ
(Sun Ke)中国の政治家。孫文の先夫人の嫡子。国民政府行政院長などを歴任。(1895〜1973)
そん‐か【尊下】
書状の宛名の脇付けに用いる語。貴下。
そん‐か【尊家】
他人の家の尊敬語。おたく。貴家。多く手紙文に用いる。
そん‐かい【村会】‥クワイ
①旧制で、村の議決機関。→村議会。
②村議会の非公式の称。「―議員」
そん‐かい【損壊】‥クワイ
そこないこわすこと。また、そこないこわれること。「―家屋」
そん‐がい【損害】
そこない傷つけること。不利益をうけること。損失。「敵の―」「1億円の―」「―をこうむる」
⇒そんがい‐たんぽ‐けいやく【損害担保契約】
⇒そんがい‐ばいしょう【損害賠償】
⇒そんがい‐ほけん【損害保険】
ソンガイ【Songhai】
西アフリカのイスラム教徒ソンガイ人が建てたアフリカ最大の古王国。サハラ越え交易で栄える。16世紀末モロッコ軍の南下により滅亡。(1335〜1594)
ぞん‐がい【存外】‥グワイ
①思いがけないこと。予想と食い違うこと。意外。案外。正法眼蔵随聞記2「―の次第なり」。「―むずかしいものだ」
②もってのほかであること。無礼。ぶしつけ。懐硯ふところすずり「娘ばかりの内証に入て―せしゆへなし」
 そん【損】
益のなくなること。利を失うこと。「株で―をする」
⇒損がいく
そん【樽】
たる。酒だる。宇津保物語貴宮「一石入る―十に酒入れ」
ソン【son】
(スペイン語で音の意)19世紀にキューバ東部で生まれたダンス音楽。1930年代にはルンバの名で世界に紹介された。
そん‐い【巽位】‥ヰ
巽たつみすなわち南東の方角。
そん‐い【尊位】‥ヰ
とうとい位。天子の位。
そん‐い【尊威】‥ヰ
とうとい威光。御威光。
そん‐い【尊意】
他人の意思または意見の尊敬語。おぼしめし。尊慮。尊旨。
そん‐い【遜位】‥ヰ
天皇が位をゆずること。譲位。
ぞん‐い【存意】
心持のあるところ。かんがえ。存念。
そん‐いっせん【孫逸仙】
⇒そんぶん(孫文)
そん‐えい【村営】
村が経営すること。
そん‐えい【尊詠】
他人の詩歌の尊敬語。貴詠。
そん‐えい【尊影】
他人の写真または肖像などの尊敬語。
そん‐えき【損益】
①損失と利益。損得。
②へらすこととますこと。減ることと加わること。
③簿記で、損益勘定の略。
⇒そんえき‐かんじょう【損益勘定】
⇒そんえき‐けいさん‐しょ【損益計算書】
⇒そんえき‐ぶんきてん【損益分岐点】
⇒そんえき‐ほう【損益法】
そんえき‐かんじょう【損益勘定】‥ヂヤウ
簿記で、当期の純損益を計算するために、決算期末に元帳に設けられる集合勘定。借方には費用に関する諸勘定の残高が、貸方には収益に関する諸勘定の残高が集合される。貸方合計が借方合計を超過すればその差額が純利益、これと反対の場合には純損失となる。
⇒そん‐えき【損益】
そんえき‐けいさん‐しょ【損益計算書】
一会計期間における企業の経営成績を明らかにするために、その期間に属する総収益と総費用とを対応させ、当期純損益を表示した書類。損益表。利益計算書。
⇒そん‐えき【損益】
そんえき‐ぶんきてん【損益分岐点】
損益発生の分れ目となる売上高。一期間の売上高がこの額を超えて初めて、売上高に比例した利益が発生する。利益管理や原価管理に利用される。
⇒そん‐えき【損益】
そんえき‐ほう【損益法】‥ハフ
簿記で、一会計期間に属する総収益と総費用の差額を純損益とする計算方法。今日の企業会計実務はこの方法に依拠している。↔財産法
⇒そん‐えき【損益】
そんえん‐にゅうどうしんのう【尊円入道親王】‥ヱンニフダウ‥ワウ
伏見天皇の皇子。名は守彦。青蓮院しょうれんいん門主・天台座主となる。和歌に秀で、また書を世尊寺行房・行尹ゆきただに学び、小野道風・藤原行成の書法を参酌して青蓮院流(後の御家流)を開いた。著「入木抄じゅぼくしょう」。(1298〜1356)
そんえん‐りゅう【尊円流】‥ヱンリウ
書道の一派。(→)青蓮院しょうれんいん流に同じ。
そん‐おう【村翁】‥ヲウ
いなかのじいさん。村の老人。
そん‐おう【村媼】‥アウ
いなかのばあさん。村の老女。
そん‐おう【尊翁】‥ヲウ
老人の尊敬語。
そん‐か【村家】
村にある家。いなかや。
そん‐か【孫科】‥クワ
(Sun Ke)中国の政治家。孫文の先夫人の嫡子。国民政府行政院長などを歴任。(1895〜1973)
そん‐か【尊下】
書状の宛名の脇付けに用いる語。貴下。
そん‐か【尊家】
他人の家の尊敬語。おたく。貴家。多く手紙文に用いる。
そん‐かい【村会】‥クワイ
①旧制で、村の議決機関。→村議会。
②村議会の非公式の称。「―議員」
そん‐かい【損壊】‥クワイ
そこないこわすこと。また、そこないこわれること。「―家屋」
そん‐がい【損害】
そこない傷つけること。不利益をうけること。損失。「敵の―」「1億円の―」「―をこうむる」
⇒そんがい‐たんぽ‐けいやく【損害担保契約】
⇒そんがい‐ばいしょう【損害賠償】
⇒そんがい‐ほけん【損害保険】
ソンガイ【Songhai】
西アフリカのイスラム教徒ソンガイ人が建てたアフリカ最大の古王国。サハラ越え交易で栄える。16世紀末モロッコ軍の南下により滅亡。(1335〜1594)
ぞん‐がい【存外】‥グワイ
①思いがけないこと。予想と食い違うこと。意外。案外。正法眼蔵随聞記2「―の次第なり」。「―むずかしいものだ」
②もってのほかであること。無礼。ぶしつけ。懐硯ふところすずり「娘ばかりの内証に入て―せしゆへなし」
そん【損】
益のなくなること。利を失うこと。「株で―をする」
⇒損がいく
そん【樽】
たる。酒だる。宇津保物語貴宮「一石入る―十に酒入れ」
ソン【son】
(スペイン語で音の意)19世紀にキューバ東部で生まれたダンス音楽。1930年代にはルンバの名で世界に紹介された。
そん‐い【巽位】‥ヰ
巽たつみすなわち南東の方角。
そん‐い【尊位】‥ヰ
とうとい位。天子の位。
そん‐い【尊威】‥ヰ
とうとい威光。御威光。
そん‐い【尊意】
他人の意思または意見の尊敬語。おぼしめし。尊慮。尊旨。
そん‐い【遜位】‥ヰ
天皇が位をゆずること。譲位。
ぞん‐い【存意】
心持のあるところ。かんがえ。存念。
そん‐いっせん【孫逸仙】
⇒そんぶん(孫文)
そん‐えい【村営】
村が経営すること。
そん‐えい【尊詠】
他人の詩歌の尊敬語。貴詠。
そん‐えい【尊影】
他人の写真または肖像などの尊敬語。
そん‐えき【損益】
①損失と利益。損得。
②へらすこととますこと。減ることと加わること。
③簿記で、損益勘定の略。
⇒そんえき‐かんじょう【損益勘定】
⇒そんえき‐けいさん‐しょ【損益計算書】
⇒そんえき‐ぶんきてん【損益分岐点】
⇒そんえき‐ほう【損益法】
そんえき‐かんじょう【損益勘定】‥ヂヤウ
簿記で、当期の純損益を計算するために、決算期末に元帳に設けられる集合勘定。借方には費用に関する諸勘定の残高が、貸方には収益に関する諸勘定の残高が集合される。貸方合計が借方合計を超過すればその差額が純利益、これと反対の場合には純損失となる。
⇒そん‐えき【損益】
そんえき‐けいさん‐しょ【損益計算書】
一会計期間における企業の経営成績を明らかにするために、その期間に属する総収益と総費用とを対応させ、当期純損益を表示した書類。損益表。利益計算書。
⇒そん‐えき【損益】
そんえき‐ぶんきてん【損益分岐点】
損益発生の分れ目となる売上高。一期間の売上高がこの額を超えて初めて、売上高に比例した利益が発生する。利益管理や原価管理に利用される。
⇒そん‐えき【損益】
そんえき‐ほう【損益法】‥ハフ
簿記で、一会計期間に属する総収益と総費用の差額を純損益とする計算方法。今日の企業会計実務はこの方法に依拠している。↔財産法
⇒そん‐えき【損益】
そんえん‐にゅうどうしんのう【尊円入道親王】‥ヱンニフダウ‥ワウ
伏見天皇の皇子。名は守彦。青蓮院しょうれんいん門主・天台座主となる。和歌に秀で、また書を世尊寺行房・行尹ゆきただに学び、小野道風・藤原行成の書法を参酌して青蓮院流(後の御家流)を開いた。著「入木抄じゅぼくしょう」。(1298〜1356)
そんえん‐りゅう【尊円流】‥ヱンリウ
書道の一派。(→)青蓮院しょうれんいん流に同じ。
そん‐おう【村翁】‥ヲウ
いなかのじいさん。村の老人。
そん‐おう【村媼】‥アウ
いなかのばあさん。村の老女。
そん‐おう【尊翁】‥ヲウ
老人の尊敬語。
そん‐か【村家】
村にある家。いなかや。
そん‐か【孫科】‥クワ
(Sun Ke)中国の政治家。孫文の先夫人の嫡子。国民政府行政院長などを歴任。(1895〜1973)
そん‐か【尊下】
書状の宛名の脇付けに用いる語。貴下。
そん‐か【尊家】
他人の家の尊敬語。おたく。貴家。多く手紙文に用いる。
そん‐かい【村会】‥クワイ
①旧制で、村の議決機関。→村議会。
②村議会の非公式の称。「―議員」
そん‐かい【損壊】‥クワイ
そこないこわすこと。また、そこないこわれること。「―家屋」
そん‐がい【損害】
そこない傷つけること。不利益をうけること。損失。「敵の―」「1億円の―」「―をこうむる」
⇒そんがい‐たんぽ‐けいやく【損害担保契約】
⇒そんがい‐ばいしょう【損害賠償】
⇒そんがい‐ほけん【損害保険】
ソンガイ【Songhai】
西アフリカのイスラム教徒ソンガイ人が建てたアフリカ最大の古王国。サハラ越え交易で栄える。16世紀末モロッコ軍の南下により滅亡。(1335〜1594)
ぞん‐がい【存外】‥グワイ
①思いがけないこと。予想と食い違うこと。意外。案外。正法眼蔵随聞記2「―の次第なり」。「―むずかしいものだ」
②もってのほかであること。無礼。ぶしつけ。懐硯ふところすずり「娘ばかりの内証に入て―せしゆへなし」
[漢]算🔗⭐🔉
算 字形
 筆順
筆順
 〔竹部8画/14画/教育/2727・3B3B〕
〔音〕サン(呉)(漢)
〔訓〕かぞえる
[意味]
①数をかぞえる。「敵兵二千を算する」「算出・算術・計算・暗算・採算・珠算」
②思いはかる。見つもる。見込み。「算段・心算・成算・勝算」
③年齢。「宝算・算賀」
④「算木さんぎ」の略。「算を置く」「算を乱す」(算木を散らしたように散乱する)
[解字]
会意。「竹」+「具」(=そろえる)。数とりの竹をそろえてかぞえる意。[
〔竹部8画/14画/教育/2727・3B3B〕
〔音〕サン(呉)(漢)
〔訓〕かぞえる
[意味]
①数をかぞえる。「敵兵二千を算する」「算出・算術・計算・暗算・採算・珠算」
②思いはかる。見つもる。見込み。「算段・心算・成算・勝算」
③年齢。「宝算・算賀」
④「算木さんぎ」の略。「算を置く」「算を乱す」(算木を散らしたように散乱する)
[解字]
会意。「竹」+「具」(=そろえる)。数とりの竹をそろえてかぞえる意。[ ]は異体字。
[下ツキ
暗算・違算・運算・演算・概算・加算・合算・換算・起算・逆算・計算・決算・検算・験算・減算・公算・誤算・御破算・採算・試算・珠算・勝算・乗算・心算・神算・推算・成算・清算・精算・積算・速算・打算・通算・筆算・宝算・目算・洋算・予算・累算・和算
]は異体字。
[下ツキ
暗算・違算・運算・演算・概算・加算・合算・換算・起算・逆算・計算・決算・検算・験算・減算・公算・誤算・御破算・採算・試算・珠算・勝算・乗算・心算・神算・推算・成算・清算・精算・積算・速算・打算・通算・筆算・宝算・目算・洋算・予算・累算・和算
 筆順
筆順
 〔竹部8画/14画/教育/2727・3B3B〕
〔音〕サン(呉)(漢)
〔訓〕かぞえる
[意味]
①数をかぞえる。「敵兵二千を算する」「算出・算術・計算・暗算・採算・珠算」
②思いはかる。見つもる。見込み。「算段・心算・成算・勝算」
③年齢。「宝算・算賀」
④「算木さんぎ」の略。「算を置く」「算を乱す」(算木を散らしたように散乱する)
[解字]
会意。「竹」+「具」(=そろえる)。数とりの竹をそろえてかぞえる意。[
〔竹部8画/14画/教育/2727・3B3B〕
〔音〕サン(呉)(漢)
〔訓〕かぞえる
[意味]
①数をかぞえる。「敵兵二千を算する」「算出・算術・計算・暗算・採算・珠算」
②思いはかる。見つもる。見込み。「算段・心算・成算・勝算」
③年齢。「宝算・算賀」
④「算木さんぎ」の略。「算を置く」「算を乱す」(算木を散らしたように散乱する)
[解字]
会意。「竹」+「具」(=そろえる)。数とりの竹をそろえてかぞえる意。[ ]は異体字。
[下ツキ
暗算・違算・運算・演算・概算・加算・合算・換算・起算・逆算・計算・決算・検算・験算・減算・公算・誤算・御破算・採算・試算・珠算・勝算・乗算・心算・神算・推算・成算・清算・精算・積算・速算・打算・通算・筆算・宝算・目算・洋算・予算・累算・和算
]は異体字。
[下ツキ
暗算・違算・運算・演算・概算・加算・合算・換算・起算・逆算・計算・決算・検算・験算・減算・公算・誤算・御破算・採算・試算・珠算・勝算・乗算・心算・神算・推算・成算・清算・精算・積算・速算・打算・通算・筆算・宝算・目算・洋算・予算・累算・和算
大辞林の検索結果 (69)
さん【算】🔗⭐🔉
さん [1] 【算】
(1)占いに用いる算木(サンギ)。また,占い。
(2)昔,中国から渡来した計算用具。長方形の小木片,二七一枚を集めたもの。
(3)計算。勘定。「たとへ―があうても/浄瑠璃・重井筒(上)」
(4)そろばん。
さん=を置・く🔗⭐🔉
――を置・く
(1)算木で計算する。
(2)算木で占う。
さん=を散ら・す🔗⭐🔉
――を散ら・す
「算を乱す」に同じ。「楯は―・したる様にさんざんに蹴ちらさる/平家 11」
さん=を乱・す🔗⭐🔉
――を乱・す
算木を乱したように散乱する。ちりぢりばらばらになる。算を散らす。
さん-おき【算置き】🔗⭐🔉
さん-おき 【算置き】
算木を使って占うこと。また,それを職とする人。易者。「安倍の外記といへる世界見通しの―が申せしは/浮世草子・一代男 4」
さん-が【算賀】🔗⭐🔉
さん-が [1] 【算賀】
長寿の祝賀。賀の祝い。四〇歳から始めて10年ごとに行う。中国伝来の慣習で,のちには六十一(還暦),七十七(喜寿),八十八(米寿)なども祝う。
さん-がく【算学】🔗⭐🔉
さん-がく [0] 【算学】
数値計算についての学問。算数。数学。「―ヲスル/ヘボン」
さん-がく【算額】🔗⭐🔉
さん-がく [0] 【算額】
和算家が自己の作った数学の問題や解答を書いて,神社・寺院などに奉納した絵馬。額面題。
さんがくけいもう【算学啓蒙】🔗⭐🔉
さんがくけいもう 【算学啓蒙】
数学書。中国,元の朱世傑(シユセイケツ)著。三巻。1299年刊。朝鮮で重刊され,文禄・慶長の役の頃,日本にも伝えられ,和算の発展に大きな影響を与えた。
さん-かん【算勘】🔗⭐🔉
さん-かん 【算勘】
(1)数量を数えること。数の勘定。計算。「知らぬ者の是程まで,―商読書の/浄瑠璃・五十年忌(中)」
(2)算木の占いによって考えること。
さんかん-じゃ【算勘者】🔗⭐🔉
さんかん-じゃ 【算勘者】
計算にたくみな人。[日葡]
さん-ぎ【算木】🔗⭐🔉
さん-ぎ [1][3] 【算木】
(1)易で占いに使う長さ約9センチメートルの正方柱体の木。六本を一組みとする。筮竹(ゼイチク)を操作して得た卦(ケ)の形に並べて判断する。
(2)和算で用いる計算用具。木製の小さな角棒。算籌(サンチユウ)。
算木(1)
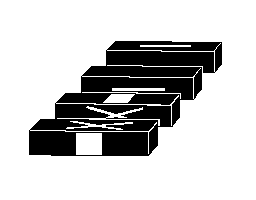 [図]
[図]
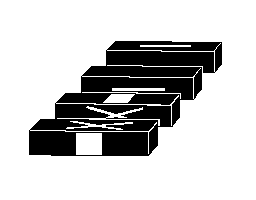 [図]
[図]
さんぎ-ぜめ【算木責め】🔗⭐🔉
さんぎ-ぜめ [0] 【算木責め】
「石抱き」に同じ。
さんぎ-づみ【算木積み】🔗⭐🔉
さんぎ-づみ [0] 【算木積み】
石垣の出角(デスミ)を積む石積み法の一。直方体に加工した石を用い,石の長辺を石垣の角の両面に交互に出すように積む。
さんぎ-もち【算木餅】🔗⭐🔉
さんぎ-もち [3] 【算木餅】
算木の形に切った餅。算餅。
さん-くずし【算崩し・三崩し】🔗⭐🔉
さん-くずし ―クヅシ [3] 【算崩し・三崩し】
縦の三筋と横の三筋を市松状に配した模様。算木崩し。
さん-けい【算計】🔗⭐🔉
さん-けい [0] 【算計】 (名)スル
(1)数量を数えはかること。勘定。計算。「斤両は百六十匁を以て―すべき事/新聞雑誌 49」
(2)起こりそうなことを予想し,考えに入れておくこと。「偶然の事を仔細(シサイ)に―する人なり/西国立志編(正直)」
さん-し【算師】🔗⭐🔉
さん-し [1] 【算師】
律令制下の下級の官人。主計寮・主税寮・大宰府に置かれて計算を担当した。
さん-しき【算式】🔗⭐🔉
さん-しき [0] 【算式】
加減乗除などの記号を用いて,計算の順序・方法を表した式。
さん-しゃ【算者】🔗⭐🔉
さん-しゃ 【算者】
計算の上手な人。「年波のせはしき世の事,―も是をつもれり/浮世草子・永代蔵 5」
さん-しゅつ【算出】🔗⭐🔉
さん-しゅつ [0] 【算出】 (名)スル
計算して数値を出すこと。「見積もり額を―する」
さん-じゅつ【算術】🔗⭐🔉
さん-じゅつ [0] 【算術】
〔arithmetic〕
(1)正の整数・小数・分数および量についての計算を中心とする初等数学。
(2)旧制の小学校における教科名。
(3)中国および近世の日本で,数学の総称。
さんじゅつ-きゅうすう【算術級数】🔗⭐🔉
さんじゅつ-きゅうすう ―キフ― [5][7] 【算術級数】
⇒等差級数(トウサキユウスウ)
さんじゅつ-へいきん【算術平均】🔗⭐🔉
さんじゅつ-へいきん [5] 【算術平均】
「相加(ソウカ)平均」に同じ。
⇔幾何平均
さん-すう【算数】🔗⭐🔉
さん-すう [3] 【算数】
(1)かぞえること。計算すること。また,損得などをはかること。「其の子肆孫店に至つては―す可からず/東京新繁昌記(撫松)」
(2)小学校の教科名。数学の初歩を教える。昭和16年,それまでの「算術」を改めたもの。
(3)「数学」に同じ。算学。
さん・する【算する】🔗⭐🔉
さん・する [3] 【算する】 (動サ変)[文]サ変 さん・す
かぞえる。かぞえて,ある数値を得る。「聴衆は一万を―・する」
さん-だん【算段】🔗⭐🔉
さん-だん [1][3] 【算段】 (名)スル
あれこれと手段・方法を考えること。特に,工夫して必要な金をそろえること。工面。やりくり。「金を―する」「くるしい―にてもとめたる袖時計/安愚楽鍋(魯文)」
さん-ちゅう【算籌】🔗⭐🔉
さん-ちゅう ―チウ [0] 【算籌】
「算木(サンギ){(2)}」に同じ。
さん-てい【算定】🔗⭐🔉
さん-てい [0] 【算定】 (名)スル
計算してはっきりと数字に表すこと。「米の価格を―する」「―基準」
さんてい-ふうたい【算定風袋】🔗⭐🔉
さんてい-ふうたい [5] 【算定風袋】
あらかじめ重量のわかっている風袋。計算風袋。見積もり風袋。
さん-とう【算当】🔗⭐🔉
さん-とう ―タウ [0] 【算当】 (名)スル
勘定すること。また,勘定をしておよその見当をつけること。「其数少なくして―に合はぬなり/学問ノススメ(諭吉)」
さん-どう【算道】🔗⭐🔉
さん-どう ―ダウ [0] 【算道】
(1)計算の方法。算術。算法。
(2)律令制における大学で教えた学科の一。算術を修める学問。
さん-にゅう【算入】🔗⭐🔉
さん-にゅう ―ニフ [0] 【算入】 (名)スル
計算に加えること。一緒にして計算すること。「給料には残業料分も―してある」
さん-にょう【算用】🔗⭐🔉
さん-にょう ―ヨウ 【算用】
「さんよう(算用)」の連声。
さん-はかせ【算博士】🔗⭐🔉
さん-はかせ [3] 【算博士】
律令制で,大学寮で算術を教授する教官。平安時代以後,三善・小槻(オヅキ)二氏の世襲。
さん-ばん【算盤】🔗⭐🔉
さん-ばん [0] 【算盤】
(1)和算の計算器具。盤上に縦横に線を引いて作った正方形の中に算木を置いて計算をする。
(2)そろばん。
さん-ぴつ【算筆】🔗⭐🔉
さん-ぴつ [0] 【算筆】
勘定と読み書き。読み書き算盤(ソロバン)。
さん-ふ【算賦】🔗⭐🔉
さん-ふ [1][0] 【算賦】
中国,秦・漢代に行われた人頭税。一五歳以上五六歳までの男女に課され,国家の重要な財源であった。
さん-ぽう【算法】🔗⭐🔉
さん-ぽう ―パフ [1][0] 【算法】
(1)計算の方法。また,計算の規則。
(2)江戸時代,数学のこと。
さん-よう【算用】🔗⭐🔉
さん-よう [0] 【算用】 (名)スル
〔古くは「さんにょう」とも〕
(1)計算すること。勘定。また,算術。「いやまづおまちやれ,―しなおいてみ申さう/狂言・賽の目」
(2)勘定を払うこと。清算すること。「これも近々には―致しまする/狂言・千鳥(虎寛本)」
(3)見積もりを立てること。予想。目算。「五十年の月日にわたるも百年の―にはあふべきをや/鶉衣」
さんよう-あい【算用合ひ】🔗⭐🔉
さんよう-あい ―アヒ 【算用合ひ】
収支決算。また,計算。帳合い。「いかに親子の中でも,たがひの―はきつとしたがよい/浮世草子・胸算用 1」
さんよう-じょう【算用状】🔗⭐🔉
さんよう-じょう ―ジヤウ [0] 【算用状】
中世,個々の荘園に関する年間の収支決算報告書。
さんよう-すうじ【算用数字】🔗⭐🔉
さんよう-すうじ [5] 【算用数字】
数字 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 ・ 9 ・ 0 のこと。本来筆算に用いる数字だったところからいう。アラビア数字。
さんよう-なし【算用無し】🔗⭐🔉
さんよう-なし 【算用無し】
見積もりも立てず,収支決算もしないこと。成り行きまかせ。また,その人。「大神宮にも―に物つかふ人うれしくは思しめさず/浮世草子・胸算用 1」
さん-れき【算暦】🔗⭐🔉
さん-れき [0] 【算暦】
算法と暦法。
そろばん【算盤・十露盤】🔗⭐🔉
そろばん [0] 【算盤・十露盤】
(1)日本・中国などで使用される簡単な計算器。横長で底の浅い長方形の枠に珠(タマ)を数個貫いた軸を縦に何本も並べたもの。軸のそれぞれが桁(ケタ)を表し,珠の上下の位置でそれぞれの桁の数値を表し,珠を指で上下させることにより四則演算が行える。日本には室町末期に中国より伝来したといわれる。
(2)損得についての計算。「この仕事は―抜きでやっています」
〔唐音「そわんぱあん」の転という〕
そろばん=が合・う🔗⭐🔉
――が合・う
計算が合う。採算が合う。
そろばん=が持て ない🔗⭐🔉
ない🔗⭐🔉
――が持て ない
損益計算をして,利益がない。そろばんが合わない。
ない
損益計算をして,利益がない。そろばんが合わない。
 ない
損益計算をして,利益がない。そろばんが合わない。
ない
損益計算をして,利益がない。そろばんが合わない。
そろばん=の玉はずれ🔗⭐🔉
――の玉はずれ
そろばんで計算した分以外の金。帳簿に記入されない余分な金。
そろばん=を置・く🔗⭐🔉
――を置・く
そろばんで計算する。損得の計算をする。
そろばん=を弾(ハジ)・く🔗⭐🔉
――を弾(ハジ)・く
(1)そろばんの玉を弾いて計算する。
(2)損得の計算をする。
そろばん=を枕(マクラ)にする🔗⭐🔉
――を枕(マクラ)にする
商人が,寝る間もそろばんを身辺から離さないで商売にうちこむさまの形容。
そろばん-うらない【算盤占い】🔗⭐🔉
そろばん-うらない ―ナヒ [5] 【算盤占い】
そろばんを使って吉凶を判断すること。算易。
そろばん-かんじょう【算盤勘定】🔗⭐🔉
そろばん-かんじょう ―ヂヤウ [5] 【算盤勘定】
そろばんで利得を計算すること。損得についての勘定。
そろばん-ぎ【算盤木】🔗⭐🔉
そろばん-ぎ [3] 【算盤木】
〔建〕 基礎杭上に架け渡した横木。
そろばん-さで【算盤桟手】🔗⭐🔉
そろばん-さで [3] 【算盤桟手】
木材運搬装置の一。小丸太を横に並べ,その両側に側木として二本の丸太をおいたもの。運搬する木材は小丸太の上をすべらせる。
そろばん-しぼり【算盤絞り】🔗⭐🔉
そろばん-しぼり [5] 【算盤絞り】
そろばんの珠をならべたような模様の絞り染め。手拭いに多く使用された。
そろばん-ずく【算盤尽く】🔗⭐🔉
そろばん-ずく ―ヅク [0] 【算盤尽く】
何でも損得を計算して,損にならないようにすること。勘定高いこと。勘定ずく。損得ずく。「―ではできない仕事だ」
そろばん-ぜめ【算盤責め】🔗⭐🔉
そろばん-ぜめ [0] 【算盤責め】
「石抱(イシダ)き」に同じ。
そろばん-だま【算盤玉】🔗⭐🔉
そろばん-だま [0] 【算盤玉】
(1)そろばんの軸に貫いてある珠。
(2)損得の計算。勘定。「
 (ドウ)いふ―でせうな,日鉄だけでも大分のものだが/社会百面相(魯庵)」
(ドウ)いふ―でせうな,日鉄だけでも大分のものだが/社会百面相(魯庵)」

 (ドウ)いふ―でせうな,日鉄だけでも大分のものだが/社会百面相(魯庵)」
(ドウ)いふ―でせうな,日鉄だけでも大分のものだが/社会百面相(魯庵)」
そろばん-だか・い【算盤高い】🔗⭐🔉
そろばん-だか・い [6] 【算盤高い】 (形)
金銭の計算に細かい。打算的だ。勘定高い。「―・い人」
[派生] ――さ(名)
さんじゅつ【算術】(和英)🔗⭐🔉
さんじゅつ【算術】
arithmetic.→英和
〜をする do sums.
さんすう【算数】(和英)🔗⭐🔉
さんようすうじ【算用数字】(和英)🔗⭐🔉
さんようすうじ【算用数字】
an Arabic figure[numeral].
そろばん【算盤】(和英)🔗⭐🔉
広辞苑+大辞林に「算」で始まるの検索結果。