複数辞典一括検索+![]()
![]()
おう-きゃく【鴨脚】🔗⭐🔉
おう-きゃく アフ― [0] 【鴨脚】
イチョウの漢名。鴨脚子。
おうりょく-こう【鴨緑江】🔗⭐🔉
おうりょく-こう アフリヨクカウ 【鴨緑江】
朝鮮民主主義人民共和国と中国との国境をなす河川。白頭山に源を発し,南西流して黄海に注ぐ。長さ790キロメートル。アムノック-カン。ヤーリュイ-チアン。
おうりょくこう-ぶし【鴨緑江節】🔗⭐🔉
おうりょくこう-ぶし アフリヨクカウ― 【鴨緑江節】
大正中期頃から流行したはやり唄。鴨緑江沿岸の恵山鎮近辺の酒席の唄を,出稼ぎの日本人筏師(イカダシ)たちが伝えたもの。
かも【鴨・鳧】🔗⭐🔉
かも [1] 【鴨・鳧】
(1)カモ目カモ科のうち,ハクチョウ類・ガン類・アイサ類を除いたものの総称。中形の水鳥。雄は派手な色合い,雌は地味な茶褐色のものが多い。マガモ・コガモ・オナガガモ・ハシビロガモなど。日本ではカルガモを除き,多くは冬鳥。[季]冬。《海くれて―のこゑほのかに白し/芭蕉》
(2)勝負事などで,くみしやすい相手。また,だましやすい相手。「―にする」「いい―だ」
かも=が葱(ネギ)をしょって来る🔗⭐🔉
――が葱(ネギ)をしょって来る
〔鴨鍋の材料がそろうことから〕
願ってもないこと,大変好都合であることにいう。鴨葱。
かも=の浮き寝🔗⭐🔉
――の浮き寝
〔鴨が水に浮きながら寝るさまが,不安に思われることから〕
安らかでないことのたとえ。「沖に住む―の安けくもなき/万葉 2806」
かも=の脛(ハギ)🔗⭐🔉
――の脛(ハギ)
鴨の脚。短いもののたとえとする。
かも=の水掻(カ)き🔗⭐🔉
――の水掻(カ)き
鴨は気楽そうに水に浮かんでいるが,その水掻きは水中で絶えず動いているという意。人知れぬ苦労の絶えないことのたとえ。
かも【賀茂・鴨】🔗⭐🔉
かも 【賀茂・鴨】
京都市鴨川流域の上賀茂・下鴨の総称。((歌枕))「かれにける葵のみこそ悲しけれあはれとみずや―の瑞垣(ミズガキ)/新古今(恋四)」
〔多く「葵(アオイ)」とともに詠まれた〕
かも【鴨】🔗⭐🔉
かも 【鴨】
姓氏の一。
かも-の-ちょうめい【鴨長明】🔗⭐🔉
かも-の-ちょうめい ―チヤウメイ 【鴨長明】
(1155頃-1216) 鎌倉初期の歌人・随筆作者。下鴨神社の禰宜(ネギ)長継の次男。俗名,長明(ナガアキラ)。法名,蓮胤。和歌を俊恵に学び,和歌所寄人となる。父祖の務めた河合社(カワイシヤ)の神官を望んでかなわず,五〇歳頃出家。著「方丈記」「無名抄」「発心集」など。
かもい-かくし【鴨居隠し】🔗⭐🔉
かもい-かくし ― ― [4] 【鴨居隠し】
〔鴨居を隠す高さなのでいう〕
丈(タケ)が六尺(約182センチメートル)の屏風(ビヨウブ)。
― [4] 【鴨居隠し】
〔鴨居を隠す高さなのでいう〕
丈(タケ)が六尺(約182センチメートル)の屏風(ビヨウブ)。
 ― [4] 【鴨居隠し】
〔鴨居を隠す高さなのでいう〕
丈(タケ)が六尺(約182センチメートル)の屏風(ビヨウブ)。
― [4] 【鴨居隠し】
〔鴨居を隠す高さなのでいう〕
丈(タケ)が六尺(約182センチメートル)の屏風(ビヨウブ)。
かもい-した【鴨居下】🔗⭐🔉
かもい-した ― ― [0] 【鴨居下】
〔鴨居まで届かない高さなのでいう〕
丈が五尺六寸五分(約171センチメートル)の屏風(ビヨウブ)。
― [0] 【鴨居下】
〔鴨居まで届かない高さなのでいう〕
丈が五尺六寸五分(約171センチメートル)の屏風(ビヨウブ)。
 ― [0] 【鴨居下】
〔鴨居まで届かない高さなのでいう〕
丈が五尺六寸五分(約171センチメートル)の屏風(ビヨウブ)。
― [0] 【鴨居下】
〔鴨居まで届かない高さなのでいう〕
丈が五尺六寸五分(約171センチメートル)の屏風(ビヨウブ)。
かもい【鴨居】🔗⭐🔉
かもい カモ 【鴨居】
姓氏の一。
【鴨居】
姓氏の一。
 【鴨居】
姓氏の一。
【鴨居】
姓氏の一。
かもい-ようこ【鴨居羊子】🔗⭐🔉
かもい-ようこ カモ ヤウコ 【鴨居羊子】
(1925-1991) 下着デザイナー・随筆家。大阪府生まれ。本名,洋子。全国各地で下着ショーを開催,下着を偏見から解放するとともに女性解放運動の一翼を担った。
ヤウコ 【鴨居羊子】
(1925-1991) 下着デザイナー・随筆家。大阪府生まれ。本名,洋子。全国各地で下着ショーを開催,下着を偏見から解放するとともに女性解放運動の一翼を担った。
 ヤウコ 【鴨居羊子】
(1925-1991) 下着デザイナー・随筆家。大阪府生まれ。本名,洋子。全国各地で下着ショーを開催,下着を偏見から解放するとともに女性解放運動の一翼を担った。
ヤウコ 【鴨居羊子】
(1925-1991) 下着デザイナー・随筆家。大阪府生まれ。本名,洋子。全国各地で下着ショーを開催,下着を偏見から解放するとともに女性解放運動の一翼を担った。
かも-いけ【鴨池】🔗⭐🔉
かも-いけ [2] 【鴨池】
(1)鴨のいる池。
(2)野生の鴨を誘いよせ猟をするために設けた池。
かもがた【鴨方】🔗⭐🔉
かもがた 【鴨方】
岡山県南西部,浅口郡の町。近世には岡山藩の支藩鴨方藩の陣屋があった。そうめん・麦藁細工(麦かん真田)などを産する。備中杜氏(トウジ)の出身地。
かも-がや【鴨茅】🔗⭐🔉
かも-がや [2] 【鴨茅】
イネ科の多年草。ヨーロッパ原産。飼料作物として世界で広く栽培する。日本には江戸末期に渡来。茎は高さ約80センチメートル。葉は線形で根生して大株を作る。初夏,茎頂に緑色の穂をつける。小穂はカモの足状。オーチャード-グラス。
かもがわ【鴨川】🔗⭐🔉
かもがわ カモガハ 【鴨川】
千葉県南部の市。太平洋に臨み漁業・花卉(カキ)栽培が盛ん。観光地。海水浴場として知られる。
かも-がわ【鴨川・賀茂川・加茂川】🔗⭐🔉
かも-がわ ―ガハ 【鴨川・賀茂川・加茂川】
京都市街東部を貫流し,桂川に注ぐ川。北山城山塊の桟敷ヶ岳(サジキガダケ)に源を発する。長さ31キロメートル。高野川との合流点から上流を賀茂川,下流を鴨川と書く。友禅染めの水洗いに利用。「加茂の七石」といわれる水石を産する。((歌枕))「―の水底(ミナゾコ)澄みて照る月をゆきて見むとや夏祓へする/後撰(夏)」
かもがわ-おどり【鴨川をどり】🔗⭐🔉
かもがわ-おどり ―ガハヲドリ 【鴨川をどり】
五月一日から二四日まで,京都の先斗町(ポントチヨウ)の舞妓(マイコ)・芸妓(ゲイコ)が,鴨川沿いの先斗町歌舞練場で興行する歌舞の会。1872年(明治5)に始まる。[季]夏。
〔秋は一〇月一五日から一一月七日まで行われる〕
かもがわ-ぞめ【鴨川染】🔗⭐🔉
かもがわ-ぞめ ―ガハ― [0] 【鴨川染】
(1)京都の鴨川で染色した友禅染め。
(2)模様の大きな友禅染め。
(3)京染め。
かもがわ-にんぎょう【鴨川人形】🔗⭐🔉
かもがわ-にんぎょう ―ガハ―ギヤウ [5] 【鴨川人形】
元文(1736-1741)頃,賀茂中社の雑掌高橋忠重が鴨川堤の柳の木を用いて作った木目込み人形。賀茂人形。
かも-ぐつ【鴨沓】🔗⭐🔉
かも-ぐつ 【鴨沓】
蹴鞠(ケマリ)用のつま先の丸い革製の長靴。[日葡]
鴨沓
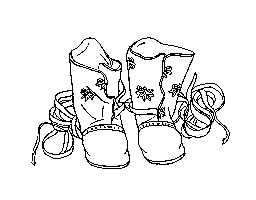 [図]
[図]
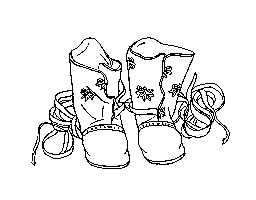 [図]
[図]
かもじま【鴨島】🔗⭐🔉
かもじま 【鴨島】
徳島県北西部,麻植(オエ)郡の町。近世は藍栽培の中心,明治以降は製糸業が発達した。
かも-なんばん【鴨南蛮】🔗⭐🔉
かも-なんばん [3] 【鴨南蛮】
鴨の肉と細切りのネギを入れたかけのうどん・そば。鴨南。
かも-の-いれくび【鴨の入れ首】🔗⭐🔉
かも-の-いれくび [1] 【鴨の入れ首】
相撲で,互いに首を相手の脇(ワキ)の下にさし入れて四つに組んだ際,思い切って体を反らして相手を倒す技。
かものさわだち【鴨の騒立】🔗⭐🔉
かものさわだち 【鴨の騒立】
1836年9月,三河国加茂郡で起きた百姓一揆の記録書。一冊。同国幡豆(ハズ)郡寺津村(愛知県西尾市)の神官渡辺政香著。
かも-の-はし【鴨嘴】🔗⭐🔉
かも-の-はし [3][1] 【鴨嘴】
(1)単孔目の原始的な哺乳類。頭胴長37センチメートル,尾13センチメートルほど。四肢は短く水掻きがあり,カモに似たくちばしをもち,尾はビーバーに似て長く扁平。体は灰褐色。卵を産み,孵化(フカ)した子は乳を飲んで育つ。夜行性。オーストラリア東部・タスマニア島に分布。
(2)イネ科の多年草。海岸の湿地などに自生。高さ50センチメートル内外。葉は線形。枝頂に長さ5センチメートル内外の紫赤色の花穂を密接して二個立てる。二個の花穂をカモのくちばしに見立てこの名がある。
鴨嘴(2)
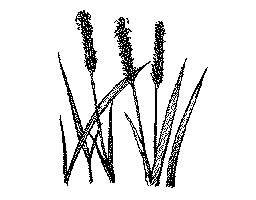 [図]
[図]
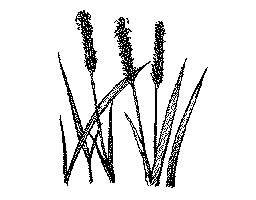 [図]
[図]
かも-ば【鴨場】🔗⭐🔉
かも-ば [0] 【鴨場】
鴨猟を行う場所。
かも-りょう【鴨猟】🔗⭐🔉
かも-りょう ―レフ [2] 【鴨猟】
(1)鴨を狩猟すること。
(2)宮内省(現在,宮内庁)で,一〇月初中旬から翌年4月初中旬にかけて随時行う鴨を狩る行事。囮(オトリ)の鴨を使って御猟場の堀に誘い入れた鴨を,手に持った網ですくいとる。
かも・る【鴨る】🔗⭐🔉
かも・る 【鴨る】 (動ラ五)
〔「かも(鴨)(2)」を動詞化したもの〕
勝負事などで,相手を食い物にする。また,詐欺にかけて金品を奪う。鴨にする。「麻雀で―・られた」
[可能] かもれる
こう-とう【香頭・鴨頭】🔗⭐🔉
こう-とう カウ― 【香頭・鴨頭】
〔「鴨」は当て字〕
薬味。こうと。「柚(ユウ)の葉の―に貝杓子まで取りそへ/狂言・鱸庖丁(虎寛本)」
かもい【鴨居】(和英)🔗⭐🔉
かもい【鴨居】
a lintel.→英和
かもりょう【鴨猟】(和英)🔗⭐🔉
かもりょう【鴨猟】
wild-duck hunting.
大辞林に「鴨」で始まるの検索結果 1-38。