複数辞典一括検索+![]()
![]()
○契りを籠むちぎりをこむ🔗⭐🔉
○契りを籠むちぎりをこむ
深い約束をする。夫婦の交わりをする。
⇒ちぎり【契り】
ちぎ・る【契る】
〔他五〕
①固く言いかわして約束する。古今和歌集秋「―・りけん心ぞつらき織女たなばたの年にひとたび逢ふは逢ふかは」
②夫婦の約束をする。源氏物語桐壺「いときなき初もとゆひに長き世を―・る心は結びこめつや」
③夫婦の交わりをする。
ち‐ぎ・る
(「千切る」とも書く)
[一]〔他五〕
①手先で細かく切りとる。蜻蛉日記上「海松みるのひきほしの、短く―・りたるを」。「紙を―・る」
②無理にもぎとる。ねじきる。「ボタンを―・られる」
③動詞の連用形に付いて、その動作を強くする意を表す語。宇治拾遺物語3「歯をくひあはせて、念珠をもみ―・る」。「ほめ―・る」
[二]〔自下二〕
⇒ちぎれる(下一)
ち‐ぎれ
ちぎれた切れはし。
⇒ちぎれ‐ぐも【断雲・千切れ雲】
⇒ちぎれ‐ちぎれ
ちぎれ‐ぐも【断雲・千切れ雲】
ちぎれ離れた雲。切れ離れた雲。
断雲・千切れ雲
撮影:高橋健司
 ⇒ち‐ぎれ
ちぎれ‐ちぎれ
幾つにもちぎれたさま。きれぎれ。「―の布」
⇒ち‐ぎれ
ち‐ぎ・れる
(「千切れる」とも書く)〔自下一〕[文]ちぎ・る(下二)
切れて離れる。ねじられて切れる。きれぎれになる。徒然草「頸も―・るばかり引きたるに」。「袖が―・れる」
チキン【chicken】
①鶏の雛ひな。また、その肉。転じて、鶏肉。「フライド‐―」
②臆病者。
⇒チキン‐カツレツ【chicken cutlet】
⇒チキン‐ライス
ち‐ぎん【地銀】
地方銀行の略。
チキン‐カツレツ【chicken cutlet】
鶏肉に小麦粉・溶き卵・パン粉をつけて油で揚げた料理。
⇒チキン【chicken】
チキン‐ライス
(和製語chicken rice)鶏肉・玉葱たまねぎなどと共に飯を炒め、トマト‐ケチャップなどで調味した料理。
⇒チキン【chicken】
ちく
(関東方言)うそ。物類称呼「うそといふを…常陸下野辺にて―とも又ちくらくともいふ」
ちく【竹】
中国の楽器の分類、八音はちおんの一つ。管楽器の類。転じて、笛の総称。
ちく【筑】
①中国の古代楽器。箏に似て小さい。頸が細く肩は円い。左手で柱ちゅうを押さえ、右手に竹の細棒を持って弦を打って鳴らす。周末より漢初にかけて燕えんの地方を中心に行われた。
②筑紫国つくしのくにの略。「―豊炭田」
ちく【築】
きずくこと。たてること。「―3年」
ち‐く【地区】
①地面の区域。一区画の土地。
②法令の施行地域を限るため、または特定の行政目的のためなどに特に指定された地域。「風致―」
ち‐く【知工】
近世、廻船の船員のうち、船内会計事務を受け持った役職。船頭に次ぐ地位。賄役。〈日葡辞書〉
ち‐く【馳駆】
①馬を走らせること。
②走りまわること。また、いろいろと世話をやくこと。奔走。
ち‐ぐ【知愚・智愚】
かしこいことと愚かなこと。知者と愚者。
ち‐ぐ【値遇】
(チグウとも)
①出合うこと。めぐりあうこと。太平記20「大慈大悲の薩埵に―し奉らば」
②親しくすること。
③「値遇の縁」の略。
⇒値遇の縁
ち‐ぐ【痴愚】
①おろか。ばか。
②医学で、精神薄弱のうち白痴と軽愚(魯鈍)との中間の段階をいった語。
ちくあん【竹庵】
藪医者の通称。→藪井竹庵やぶいちくあん
ちく‐い【竹葦】‥ヰ
竹とあし。物が多く密集するさまをいう。「稲麻とうま―」
ちく・い
〔形〕
小さい。ちっぽけである。滑稽本、続膝栗毛「こりや―・いのでござらア。でかいのは八畳敷もあらず」
ちく‐いち【逐一】
〔名・副〕
(チクイツとも)一つ一つ順を追うこと。いちいち詳細に。「―報告する」
ちく‐いつ【逐一】
〔名・副〕
⇒ちくいち。日葡辞書「チクイッニフンベッ(分別)シタ」
ちく‐いん【竹印】
竹材を彫った印判。
ちく‐いん【竹院】‥ヰン
竹を植えめぐらした屋敷。
ちく‐いん【竹陰】
竹のしげったかげ。
ち‐ぐう【知遇】
人格や識見を認めた上での厚い待遇。「―を得る」
ち‐ぐう【値遇】
⇒ちぐ。天草本平家物語「ただ平家に―したことをひるがへいて、源氏に合力せうずると」
ちく‐えん【竹園】‥ヱン
(→)「たけのその」に同じ。
ちく‐えん【竹縁】
竹で造ったえん。たけえん。
ちくおん‐き【蓄音機・蓄音器】
(phonograph)音波を記録したレコード盤から音を再生させる装置。レコード盤上には、音に対応する横ぶれを有する溝を刻み、溝に当たる針の振動を機械的に増幅して振動板に伝え音とする。1877年エジソンが発明。のち、針の振動を電気信号に変換し増幅する方式となる。尾崎紅葉、三人妻「聞かせたき人あり、こゝに―の無きこそ恨なれ」。夏目漱石、野分「無駄口を叩く学者や、―の代理をする教師が」
ちく‐かん【竹竿】
①直立した竹の幹。
②たけざお。
ちく‐かん【竹簡】
中国の戦国時代に、竹の豊富な楚の国などで、竹の小札に文字を書きしるしたもの。湖南省の長沙などで出土。→木簡
ちく‐きん【竹琴】
①竹製の胴を持つ弦楽器。
㋐太い竹筒を半分に割り、切断面に桐板を張って胴とし、その上に3弦を張った琴きん。1886年(明治19)沼津の田村与三郎(竹琴)が発明。
㋑葛原勾当の二弦琴の初名。→八雲琴やくもごと。
②木琴状に竹を並べた打楽器の総称。
ちくけい【竹渓】
中国山東省泰安の徂徠山下にある名勝。
⇒ちくけい‐の‐りくいつ【竹渓の六逸】
ちく‐けいかく【地区計画】‥クワク
市街地の建物形式・構造などを一体的に規制し、街区の整備を図る計画。
ちくけい‐の‐りくいつ【竹渓の六逸】
唐代、竹渓で詩酒の交わりをした6人の隠士、すなわち李白・孔巣父・韓準・裴政・張叔明・陶沔とうべんの称。
⇒ちくけい【竹渓】
ちくご【筑後】
①旧国名。今の福岡県の南部。
②福岡県南西部、筑紫平野南東部の市。花むしろ・ござ・和紙などを産。人口4万8千。
⇒ちくご‐がわ【筑後川】
⇒ちくご‐ぶし【筑後節】
ちく‐こう【竹工】
竹を加工して工芸品を製作する細工。また、その職人。
ちくご‐がわ【筑後川】‥ガハ
熊本・大分・福岡・佐賀の4県を流れる九州第一の川。熊本県阿蘇山北側に発源する大山川と、大分県九重山に発する玖珠くす川とを水源とし、日田盆地を経て筑紫平野を流れて有明海に注ぐ。長さ143キロメートル。筑紫次郎。
筑後川
撮影:山梨勝弘
⇒ち‐ぎれ
ちぎれ‐ちぎれ
幾つにもちぎれたさま。きれぎれ。「―の布」
⇒ち‐ぎれ
ち‐ぎ・れる
(「千切れる」とも書く)〔自下一〕[文]ちぎ・る(下二)
切れて離れる。ねじられて切れる。きれぎれになる。徒然草「頸も―・るばかり引きたるに」。「袖が―・れる」
チキン【chicken】
①鶏の雛ひな。また、その肉。転じて、鶏肉。「フライド‐―」
②臆病者。
⇒チキン‐カツレツ【chicken cutlet】
⇒チキン‐ライス
ち‐ぎん【地銀】
地方銀行の略。
チキン‐カツレツ【chicken cutlet】
鶏肉に小麦粉・溶き卵・パン粉をつけて油で揚げた料理。
⇒チキン【chicken】
チキン‐ライス
(和製語chicken rice)鶏肉・玉葱たまねぎなどと共に飯を炒め、トマト‐ケチャップなどで調味した料理。
⇒チキン【chicken】
ちく
(関東方言)うそ。物類称呼「うそといふを…常陸下野辺にて―とも又ちくらくともいふ」
ちく【竹】
中国の楽器の分類、八音はちおんの一つ。管楽器の類。転じて、笛の総称。
ちく【筑】
①中国の古代楽器。箏に似て小さい。頸が細く肩は円い。左手で柱ちゅうを押さえ、右手に竹の細棒を持って弦を打って鳴らす。周末より漢初にかけて燕えんの地方を中心に行われた。
②筑紫国つくしのくにの略。「―豊炭田」
ちく【築】
きずくこと。たてること。「―3年」
ち‐く【地区】
①地面の区域。一区画の土地。
②法令の施行地域を限るため、または特定の行政目的のためなどに特に指定された地域。「風致―」
ち‐く【知工】
近世、廻船の船員のうち、船内会計事務を受け持った役職。船頭に次ぐ地位。賄役。〈日葡辞書〉
ち‐く【馳駆】
①馬を走らせること。
②走りまわること。また、いろいろと世話をやくこと。奔走。
ち‐ぐ【知愚・智愚】
かしこいことと愚かなこと。知者と愚者。
ち‐ぐ【値遇】
(チグウとも)
①出合うこと。めぐりあうこと。太平記20「大慈大悲の薩埵に―し奉らば」
②親しくすること。
③「値遇の縁」の略。
⇒値遇の縁
ち‐ぐ【痴愚】
①おろか。ばか。
②医学で、精神薄弱のうち白痴と軽愚(魯鈍)との中間の段階をいった語。
ちくあん【竹庵】
藪医者の通称。→藪井竹庵やぶいちくあん
ちく‐い【竹葦】‥ヰ
竹とあし。物が多く密集するさまをいう。「稲麻とうま―」
ちく・い
〔形〕
小さい。ちっぽけである。滑稽本、続膝栗毛「こりや―・いのでござらア。でかいのは八畳敷もあらず」
ちく‐いち【逐一】
〔名・副〕
(チクイツとも)一つ一つ順を追うこと。いちいち詳細に。「―報告する」
ちく‐いつ【逐一】
〔名・副〕
⇒ちくいち。日葡辞書「チクイッニフンベッ(分別)シタ」
ちく‐いん【竹印】
竹材を彫った印判。
ちく‐いん【竹院】‥ヰン
竹を植えめぐらした屋敷。
ちく‐いん【竹陰】
竹のしげったかげ。
ち‐ぐう【知遇】
人格や識見を認めた上での厚い待遇。「―を得る」
ち‐ぐう【値遇】
⇒ちぐ。天草本平家物語「ただ平家に―したことをひるがへいて、源氏に合力せうずると」
ちく‐えん【竹園】‥ヱン
(→)「たけのその」に同じ。
ちく‐えん【竹縁】
竹で造ったえん。たけえん。
ちくおん‐き【蓄音機・蓄音器】
(phonograph)音波を記録したレコード盤から音を再生させる装置。レコード盤上には、音に対応する横ぶれを有する溝を刻み、溝に当たる針の振動を機械的に増幅して振動板に伝え音とする。1877年エジソンが発明。のち、針の振動を電気信号に変換し増幅する方式となる。尾崎紅葉、三人妻「聞かせたき人あり、こゝに―の無きこそ恨なれ」。夏目漱石、野分「無駄口を叩く学者や、―の代理をする教師が」
ちく‐かん【竹竿】
①直立した竹の幹。
②たけざお。
ちく‐かん【竹簡】
中国の戦国時代に、竹の豊富な楚の国などで、竹の小札に文字を書きしるしたもの。湖南省の長沙などで出土。→木簡
ちく‐きん【竹琴】
①竹製の胴を持つ弦楽器。
㋐太い竹筒を半分に割り、切断面に桐板を張って胴とし、その上に3弦を張った琴きん。1886年(明治19)沼津の田村与三郎(竹琴)が発明。
㋑葛原勾当の二弦琴の初名。→八雲琴やくもごと。
②木琴状に竹を並べた打楽器の総称。
ちくけい【竹渓】
中国山東省泰安の徂徠山下にある名勝。
⇒ちくけい‐の‐りくいつ【竹渓の六逸】
ちく‐けいかく【地区計画】‥クワク
市街地の建物形式・構造などを一体的に規制し、街区の整備を図る計画。
ちくけい‐の‐りくいつ【竹渓の六逸】
唐代、竹渓で詩酒の交わりをした6人の隠士、すなわち李白・孔巣父・韓準・裴政・張叔明・陶沔とうべんの称。
⇒ちくけい【竹渓】
ちくご【筑後】
①旧国名。今の福岡県の南部。
②福岡県南西部、筑紫平野南東部の市。花むしろ・ござ・和紙などを産。人口4万8千。
⇒ちくご‐がわ【筑後川】
⇒ちくご‐ぶし【筑後節】
ちく‐こう【竹工】
竹を加工して工芸品を製作する細工。また、その職人。
ちくご‐がわ【筑後川】‥ガハ
熊本・大分・福岡・佐賀の4県を流れる九州第一の川。熊本県阿蘇山北側に発源する大山川と、大分県九重山に発する玖珠くす川とを水源とし、日田盆地を経て筑紫平野を流れて有明海に注ぐ。長さ143キロメートル。筑紫次郎。
筑後川
撮影:山梨勝弘
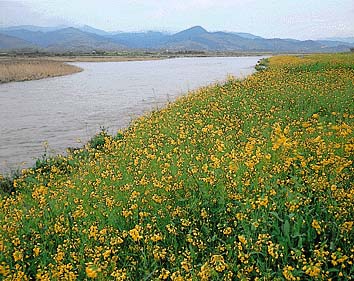 ⇒ちくご【筑後】
ちくご‐ぶし【筑後節】
義太夫節の異称。竹本義太夫が筑後掾ちくごのじょうを名乗ったことに由来。
⇒ちくご【筑後】
ちくご‐やく【逐語訳】
原文の一語一語に即して、忠実に翻訳・解釈すること。直訳。逐字訳。↔意訳
ちくさ【千種】
(チグサとも)姓氏の一つ。
⇒ちくさ‐ありこと【千種有功】
⇒ちくさ‐ただあき【千種忠顕】
ち‐ぐさ【千草】
(古くはチクサ)
①いろいろの草。古今和歌集春「咲く花は―ながらにあだなれど」。「庭の―」
②千草色の略。日本永代蔵5「浅黄の上を―に色揚げて」
⇒ちぐさ‐いろ【千草色】
ち‐ぐさ【千種】
(チクサとも)種類の多いこと。種々様々。いろいろ。くさぐさ。古今和歌集恋「秋の野に乱れて咲ける花の色の―に物を思ふころかな」
⇒ちぐさ‐がい【千種貝】
⇒ちぐさ‐の‐ほそぞめ【千種の細染】
ち‐ぐさ【乳草】
つる・茎などを切ると白い汁を出す植物の俗称。ガガイモ・ノウルシ・ノゲシ・タビラコなどを指す。ちちくさ。
ちくさ‐ありこと【千種有功】
江戸末期の歌人。号は千千廼舎ちぢのや。左近衛権中将。香川景樹と交わり、二条派の歌風を脱し一種の風格を持った。歌集「千千廼舎集」「日枝の百枝」など。(1797〜1854)
⇒ちくさ【千種】
ちくさい【竹斎】
仮名草子。2巻2冊。富山道冶とみやまどうや作。元和(1615〜1624)末頃刊行。山城の藪医者の竹斎が神社仏閣・名所旧跡をたずね江戸へ下る道中の滑稽・失敗の物語。後世への影響が大きい。竹斎物語。
ち‐くさ・い【血臭い】
〔形〕[文]ちくさ・し(ク)
血のにおいがする。ちなまぐさい。
ち‐くさ・い【乳臭い】
〔形〕[文]ちくさ・し(ク)
(→)「ちちくさい」に同じ。
ちく‐ざい【蓄財】
財産をたくわえること。また、その財産。「―にはげむ」「不正―」
ちぐさ‐いろ【千草色】
もえぎ色。そら色。ちぐさ。
Munsell color system: 10G7/2.5
⇒ち‐ぐさ【千草】
ちぐさ‐がい【千種貝】‥ガヒ
ニシキウズガイ科の巻貝。円錐形で小形、殻高約1.5センチメートル。赤・黄・樺などの美しい色彩を持つ。北海道南部以南の海藻の上に多い。
⇒ち‐ぐさ【千種】
ちく‐さく【竹冊】
文字を記した竹のふだ。竹簡。
ちく‐さく【竹柵】
竹のしがらみ。竹矢来。
ちくさ‐ただあき【千種忠顕】
南北朝時代の公家。後醍醐天皇に従い隠岐に渡る。建武政権では蔵人頭・近衛中将となり権勢を振るい、三木一草さんぼくいっそうの一人に数えられた。足利直義軍と戦い敗死。( 〜1336)
⇒ちくさ【千種】
ちく‐さつ【畜殺】
家畜類を殺すこと。屠畜とちく。
ちぐさ‐の‐ほそぞめ【千種の細染】
種々の色に染めたこまかい手のこんだ文様。
⇒ち‐ぐさ【千種】
ちく‐さん【畜産】
家畜を飼育・増殖し、人間生活に利用するものを得る産業。
⇒ちくさん‐がく【畜産学】
⇒ちくさん‐しけんじょう【畜産試験場】
⇒ちくさん‐だんち【畜産団地】
ちくさん‐がく【畜産学】
畜産を研究し、その改良・発達に役立てる学問。広義の農学の一分科。
⇒ちく‐さん【畜産】
ちくさん‐しけんじょう【畜産試験場】‥ヂヤウ
①農林水産省の一機関。畜産にかかわる改良・開発のための試験研究・調査・指導などを業務とした。2001年農業技術研究機構(現、農業‐食品産業技術総合研究機構)に改組・統合。
②1と同じ目的で設置された、各地方自治体所属の機関。
⇒ちく‐さん【畜産】
ちくさん‐だんち【畜産団地】
畜産の経営を大規模化し、生産・流通を大型化・合理化するために作られた営農集団。
⇒ちく‐さん【畜産】
ちく‐し【竹枝】
①竹の枝。
②楽府がふの一体。その土地の風俗、男女の情愛を民謡風に詠じたもの。唐の劉禹錫りゅううしゃくの創始。竹枝詞。
ちく‐し【竹紙】
①若竹の繊維を材料として製した中国産の紙。江戸中期以後、文人画家や書家が好んで用いた。
②江戸中期から越前で産した薄い鳥の子紙。
ちくし【筑紫】
⇒つくし
ちく‐じ【逐次】
〔副〕
(古くはチクシ)順を追って次々に。順次。
⇒ちくじ‐かんこうぶつ【逐次刊行物】
⇒ちくじ‐たんさく【逐次探索】
⇒ちくじ‐つうやく【逐次通訳】
⇒ちくじ‐はんのう【逐次反応】
ちくじ‐かんこうぶつ【逐次刊行物】‥カウ‥
雑誌・年報など、同一タイトルで継続して刊行する出版物。
⇒ちく‐じ【逐次】
ちくじ‐たんさく【逐次探索】
コンピューターで、格納されたデータを先頭から順に調べていく探索法。→二分探索。
⇒ちく‐じ【逐次】
ちく‐じつ【逐日】
〔副〕
日がたつに従って。日ましに。一日一日。
ちくじ‐つうやく【逐次通訳】
話者があるまとまりを話し終えてから、通訳者が翻訳する方式。→同時通訳。
⇒ちく‐じ【逐次】
ちくしの【筑紫野】
福岡市の南東にある市。中心地区二日市は古くから市場町・宿場町。福岡市の衛星都市。人口9万8千。
ちくじ‐はんのう【逐次反応】‥オウ
〔化〕(consecutive reaction)いくつかの素反応が相次いで起こる反応。
⇒ちく‐じ【逐次】
ちく‐しゃ【畜舎】
家畜を飼育し、畜産物を生産するための建物。家畜小屋。
ちくじ‐やく【逐字訳】
(→)逐語訳に同じ。
ちく‐しゅう【筑州】‥シウ
筑前ちくぜん国または筑後ちくご国の別称。
ちく‐しょう【畜生】‥シヤウ
①(人に畜やしなわれて生きているものの意)禽獣・虫魚の総称。今昔物語集15「慈悲深くして人を導き―を哀ぶことかぎりなし」
②〔仏〕畜生道に生まれた者。
③人をののしっていう語。また、憎しみうらやんでいう語。「こん―め」
⇒ちくしょう‐ざんがい【畜生残害】
⇒ちくしょう‐づか【畜生塚】
⇒ちくしょう‐づら【畜生面】
⇒ちくしょう‐どう【畜生道】
⇒ちくしょう‐ばら【畜生腹】
⇒ちくしょう‐ばらみ【畜生孕み】
ちく‐しょう【蓄妾】‥セフ
めかけを囲っておくこと。
ちく‐じょう【竹杖】‥ヂヤウ
竹のつえ。
⇒ちくじょう‐げどう【竹杖外道】
ちく‐じょう【逐条】‥デウ
箇条を追うこと。箇条を追って順々にすること。「―審議」
ちく‐じょう【築城】‥ジヤウ
城をきずくこと。また、陣地を作ること。「要害の地に―する」
ちくじょう‐げどう【竹杖外道】‥ヂヤウ‥ダウ
手に人頭に似た杖を持った外道の行者。釈尊の弟子目犍連もくけんれんを撃殺したという。竹林外道。執杖外道。
⇒ちく‐じょう【竹杖】
ちくしょう‐ざんがい【畜生残害】‥シヤウ‥
畜生が互いに噛み合って害すること。徒然草「生ける物を殺し、痛め、闘はしめて遊びたのしまん人は、―の類なり」
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐づか【畜生塚】‥シヤウ‥
1595年(文禄4)豊臣秀吉が養子秀次を自殺させ、妻妾子女30人余を斬に処し、その死骸を埋めた京都三条河原にあった塚。今、中京区瑞泉寺の境内にある。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐づら【畜生面】‥シヤウ‥
畜生のような顔つき。義理や人情を知らない人の顔つきをののしっていう語。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐どう【畜生道】‥シヤウダウ
①〔仏〕三悪趣さんあくしゅ・六道・十界の一つ。生前に悪業をなした者が趣おもむく世界。地獄道・餓鬼道より上だが、禽獣の姿に生まれて苦しむ。
②人倫上許しがたい間柄での色情。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐ばら【畜生腹】‥シヤウ‥
①女が1回に2子以上を産むこと。また、多産をののしっていう語。
②男女の双生児。前世で心中した者の生れ変りとしていう。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐ばらみ【畜生孕み】‥シヤウ‥
(→)畜生腹に同じ。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょきねん【竹書紀年】
夏・殷・周より戦国時代の魏に至る編年史。279年晋の汲郡(河南省)の人が戦国の魏の襄王の墓を発掘して得た竹簡。荀勗・和嶠が錯簡を正し、13巻とした。唐代以後また散逸(元・明代の2巻本は偽書)。清代、王国維らが逸文を集成。
ちくすい‐じつ【竹酔日】
陰暦5月13日の称。中国の俗説で、この日に竹を植えれば、よく繁茂するという。竹迷日。竜生りょうせいじつ日。竹植うる日。ちくすいにち。
ちく‐せい【竹声】
竹管を吹奏して発する音色。また、竹のそよぎ。
ちくせい【筑西】
茨城県西部の市。旧城下町下館を中心に、鬼怒川・小貝川などが南北に貫流し、田園地帯を形成。人口11万3千。
ちく‐せき【竹席】
薄く削りとった竹で編んだむしろ。たかむしろ。竹簟ちくてん。
ちく‐せき【逐斥】
追いしりぞけること。斥逐。
ちく‐せき【蓄積】
①たくわえためること。たくわえてたまったもの。「疲労が―する」「知識の―」
②資本家が利潤(剰余価値)の一部分のみを個人的消費につかい、残余を資本に転化して拡大再生産をはかること。
⇒ちくせき‐かん【蓄積管】
ちくせき‐かん【蓄積管】‥クワン
信号を記録・蓄積し、必要に応じて再生できる電子管。
⇒ちく‐せき【蓄積】
ちく‐せん【蓄銭】
金銭を貯蓄すること。また、たくわえた金銭。
ちくぜん【筑前】
旧国名。今の福岡県の北西部。
⇒ちくぜん‐に【筑前煮】
⇒ちくぜん‐びわ【筑前琵琶】
ちくぜん‐に【筑前煮】
鶏肉・根菜類・蒟蒻こんにゃくなどを油でいため、醤油と砂糖で煮た料理。福岡、筑前地方の郷土料理。筑前炊き。がめ煮。
⇒ちくぜん【筑前】
ちくぜん‐びわ【筑前琵琶】‥ビハ
琵琶の一種。また、その歌曲。楽琵琶や薩摩琵琶より小さく、桐胴。当初は4弦5柱、のちに5弦5柱のものが主流。撥ばちで弾奏。博多の橘智定(のち上京して初世旭翁1848〜1919)らが、明治20年代に筑前盲僧琵琶に薩摩琵琶と三味線音楽とを融合して創始。女性の演奏家が多く、優美な芸風が特色。旭会・橘会2派が代表的。代表曲は「湖水渡」「壇の浦」など。筑紫琵琶。
⇒ちくぜん【筑前】
ち‐くそ【血屎】
赤痢せきりの古称。
ちく‐そ【竹素】
(「素」は絹の意)(→)竹帛ちくはくに同じ。
ちく‐そう【竹窓】‥サウ
①竹の格子のついた窓。
②前に竹を植えてある窓。
ちく‐そう【竹槍】‥サウ
たけやり。
⇒ちくそう‐せっき【竹槍蓆旗】
ちく‐そう【竹叢】
たけやぶ。たかむら。
ちく‐ぞう【蓄蔵】‥ザウ
たくわえしまっておくこと。
⇒ちくぞう‐かへい【蓄蔵貨幣】
ちく‐ぞう【築造】‥ザウ
きずきつくること。
ちくぞう‐かへい【蓄蔵貨幣】‥ザウクワ‥
流通部面から引き上げられて蓄蔵された貨幣。商品の販売に引き続いて購買が行われないとき、貨幣は蓄蔵貨幣となる。退蔵貨幣。
⇒ちく‐ぞう【蓄蔵】
ちくそう‐せっき【竹槍蓆旗】‥サウセキ‥
たけやりとむしろばた。転じて、百姓一揆。
⇒ちく‐そう【竹槍】
ちく‐だい【竹台】
清涼殿の東庭に竹を植えた壇。石灰壇いしばいのだんの前のものを「河竹の台うてな」、仁寿殿じじゅうでんの西向の北方のものを「呉竹くれたけの台」という。たけのうてな。→清涼殿(図)
チクタク【ticktack】
時計の動く音を表す語。チックタック。
ち‐ぐち【乳口】
乳房の、乳の出る口。
ちく‐ちく
①こまごましたさま。こまぎれになっているさま。正徹物語「―として候へば鼠の足形のやうにありしなり」
②少しずつするさま。徐々に。仁勢物語「―と木末に春もなりぬれば」
③針やとげなど先のとがった物で小刻みに何度も浅く刺すさま。また、そのように責めるさま。「蚊に―と刺される」「―いやみを言う」
④繰り返し刺されるような痛みを肌や心などに感ずるさま。夏目漱石、こゝろ「私の良心は其度に―刺されるやうに痛みました」。「背中が―する」
ちく‐ちく【矗矗】
まっすぐ伸びるさま。そびえ立つさま。
ちく‐ちつ【竹帙】
細い竹で編んだ帙。帙簀ちす。たけちつ。
ち‐ぐ・つ【乳朽つ】
〔自上二〕
子供の歯が乳のために黒ずむ。日葡辞書「ハ(歯)ガチグチテ、また、チグチタ」
ちく‐てい【竹亭】
庭に竹を植えた亭。
ちく‐てい【築庭】
樹木や石を配置し、または泉水を設けるなどして、庭園を築造すること。造園。
ちく‐てい【築堤】
つつみを築くこと。また、築いた堤。
ちく‐でき【搐搦】
〔医〕(→)クローヌスに同じ。
ちく‐てん【逐電】
(チクデンとも。稲妻を追いかける意)
①きわめて早く行動するさま。急いでその場を立ち去ること。帥記「参内の後―退出了んぬ」。〈伊呂波字類抄〉
②ゆくえをくらまして逃げること。逃亡。出奔。失踪。平家物語5「かの夢見たる青侍せいしやがて―してんげり」
ちくでん【竹田】
⇒たのむらちくでん(田能村竹田)
ちく‐でん【蓄電】
電気をためること。充電。
⇒ちくでん‐き【蓄電器】
⇒ちくでん‐ち【蓄電池】
ちくでん‐き【蓄電器】
(→)コンデンサー1に同じ。
⇒ちく‐でん【蓄電】
ちくでん‐ち【蓄電池】
外部電源から得た電気的エネルギーを化学的エネルギーの形に変化して蓄え、必要に応じて、再び起電力として取り出す装置。普通に用いるのは、鉛蓄電池およびアルカリ蓄電池の2種。二次電池。バッテリー。
⇒ちく‐でん【蓄電】
ちく‐と
〔副〕
①すこし。ちょっと。ちと。東海道中膝栗毛2「よい酒があらば―出しなさろ」
②針などで刺すさま。ちくっと。
ちく‐とう【竹刀】‥タウ
①竹で作った刀。
②しない。
ちくとう‐ぼくせつ【竹頭木屑】
[晋書陶侃伝](船を造る時に出た竹の切れ端や木の切りくずをとっておき、後日それぞれに役立てた故事から)一見無用の物、また、瑣末な事も、おろそかにしないたとえ。
ちくどの【筑登之】
琉球王国で、里主さとぬし2に次ぐ官位。
ちく‐にく【畜肉】
家畜の肉。牛肉・豚肉・羊肉など。
ちぐぬ・く
〔自五〕
(茨城県で)うそをつく。
ちく‐ねつ【蓄熱】
熱を蓄えること。余剰となったエネルギーを蓄えておくこと。
ちく‐ねん【逐年】
年を追うこと。年々。
ちく‐ねん【蓄念】
かねてから心に思っている念願。宿念。
ちくのう‐しょう【蓄膿症】‥シヤウ
肋膜腔・副鼻腔・関節・脳腔などの体腔内に膿うみのたまる疾患。普通には、慢性の副鼻腔炎の場合をいい、頬部緊張、重圧感、頭痛、悪臭ある膿性の鼻汁分泌、嗅覚障害などを伴う。
⇒ちくご【筑後】
ちくご‐ぶし【筑後節】
義太夫節の異称。竹本義太夫が筑後掾ちくごのじょうを名乗ったことに由来。
⇒ちくご【筑後】
ちくご‐やく【逐語訳】
原文の一語一語に即して、忠実に翻訳・解釈すること。直訳。逐字訳。↔意訳
ちくさ【千種】
(チグサとも)姓氏の一つ。
⇒ちくさ‐ありこと【千種有功】
⇒ちくさ‐ただあき【千種忠顕】
ち‐ぐさ【千草】
(古くはチクサ)
①いろいろの草。古今和歌集春「咲く花は―ながらにあだなれど」。「庭の―」
②千草色の略。日本永代蔵5「浅黄の上を―に色揚げて」
⇒ちぐさ‐いろ【千草色】
ち‐ぐさ【千種】
(チクサとも)種類の多いこと。種々様々。いろいろ。くさぐさ。古今和歌集恋「秋の野に乱れて咲ける花の色の―に物を思ふころかな」
⇒ちぐさ‐がい【千種貝】
⇒ちぐさ‐の‐ほそぞめ【千種の細染】
ち‐ぐさ【乳草】
つる・茎などを切ると白い汁を出す植物の俗称。ガガイモ・ノウルシ・ノゲシ・タビラコなどを指す。ちちくさ。
ちくさ‐ありこと【千種有功】
江戸末期の歌人。号は千千廼舎ちぢのや。左近衛権中将。香川景樹と交わり、二条派の歌風を脱し一種の風格を持った。歌集「千千廼舎集」「日枝の百枝」など。(1797〜1854)
⇒ちくさ【千種】
ちくさい【竹斎】
仮名草子。2巻2冊。富山道冶とみやまどうや作。元和(1615〜1624)末頃刊行。山城の藪医者の竹斎が神社仏閣・名所旧跡をたずね江戸へ下る道中の滑稽・失敗の物語。後世への影響が大きい。竹斎物語。
ち‐くさ・い【血臭い】
〔形〕[文]ちくさ・し(ク)
血のにおいがする。ちなまぐさい。
ち‐くさ・い【乳臭い】
〔形〕[文]ちくさ・し(ク)
(→)「ちちくさい」に同じ。
ちく‐ざい【蓄財】
財産をたくわえること。また、その財産。「―にはげむ」「不正―」
ちぐさ‐いろ【千草色】
もえぎ色。そら色。ちぐさ。
Munsell color system: 10G7/2.5
⇒ち‐ぐさ【千草】
ちぐさ‐がい【千種貝】‥ガヒ
ニシキウズガイ科の巻貝。円錐形で小形、殻高約1.5センチメートル。赤・黄・樺などの美しい色彩を持つ。北海道南部以南の海藻の上に多い。
⇒ち‐ぐさ【千種】
ちく‐さく【竹冊】
文字を記した竹のふだ。竹簡。
ちく‐さく【竹柵】
竹のしがらみ。竹矢来。
ちくさ‐ただあき【千種忠顕】
南北朝時代の公家。後醍醐天皇に従い隠岐に渡る。建武政権では蔵人頭・近衛中将となり権勢を振るい、三木一草さんぼくいっそうの一人に数えられた。足利直義軍と戦い敗死。( 〜1336)
⇒ちくさ【千種】
ちく‐さつ【畜殺】
家畜類を殺すこと。屠畜とちく。
ちぐさ‐の‐ほそぞめ【千種の細染】
種々の色に染めたこまかい手のこんだ文様。
⇒ち‐ぐさ【千種】
ちく‐さん【畜産】
家畜を飼育・増殖し、人間生活に利用するものを得る産業。
⇒ちくさん‐がく【畜産学】
⇒ちくさん‐しけんじょう【畜産試験場】
⇒ちくさん‐だんち【畜産団地】
ちくさん‐がく【畜産学】
畜産を研究し、その改良・発達に役立てる学問。広義の農学の一分科。
⇒ちく‐さん【畜産】
ちくさん‐しけんじょう【畜産試験場】‥ヂヤウ
①農林水産省の一機関。畜産にかかわる改良・開発のための試験研究・調査・指導などを業務とした。2001年農業技術研究機構(現、農業‐食品産業技術総合研究機構)に改組・統合。
②1と同じ目的で設置された、各地方自治体所属の機関。
⇒ちく‐さん【畜産】
ちくさん‐だんち【畜産団地】
畜産の経営を大規模化し、生産・流通を大型化・合理化するために作られた営農集団。
⇒ちく‐さん【畜産】
ちく‐し【竹枝】
①竹の枝。
②楽府がふの一体。その土地の風俗、男女の情愛を民謡風に詠じたもの。唐の劉禹錫りゅううしゃくの創始。竹枝詞。
ちく‐し【竹紙】
①若竹の繊維を材料として製した中国産の紙。江戸中期以後、文人画家や書家が好んで用いた。
②江戸中期から越前で産した薄い鳥の子紙。
ちくし【筑紫】
⇒つくし
ちく‐じ【逐次】
〔副〕
(古くはチクシ)順を追って次々に。順次。
⇒ちくじ‐かんこうぶつ【逐次刊行物】
⇒ちくじ‐たんさく【逐次探索】
⇒ちくじ‐つうやく【逐次通訳】
⇒ちくじ‐はんのう【逐次反応】
ちくじ‐かんこうぶつ【逐次刊行物】‥カウ‥
雑誌・年報など、同一タイトルで継続して刊行する出版物。
⇒ちく‐じ【逐次】
ちくじ‐たんさく【逐次探索】
コンピューターで、格納されたデータを先頭から順に調べていく探索法。→二分探索。
⇒ちく‐じ【逐次】
ちく‐じつ【逐日】
〔副〕
日がたつに従って。日ましに。一日一日。
ちくじ‐つうやく【逐次通訳】
話者があるまとまりを話し終えてから、通訳者が翻訳する方式。→同時通訳。
⇒ちく‐じ【逐次】
ちくしの【筑紫野】
福岡市の南東にある市。中心地区二日市は古くから市場町・宿場町。福岡市の衛星都市。人口9万8千。
ちくじ‐はんのう【逐次反応】‥オウ
〔化〕(consecutive reaction)いくつかの素反応が相次いで起こる反応。
⇒ちく‐じ【逐次】
ちく‐しゃ【畜舎】
家畜を飼育し、畜産物を生産するための建物。家畜小屋。
ちくじ‐やく【逐字訳】
(→)逐語訳に同じ。
ちく‐しゅう【筑州】‥シウ
筑前ちくぜん国または筑後ちくご国の別称。
ちく‐しょう【畜生】‥シヤウ
①(人に畜やしなわれて生きているものの意)禽獣・虫魚の総称。今昔物語集15「慈悲深くして人を導き―を哀ぶことかぎりなし」
②〔仏〕畜生道に生まれた者。
③人をののしっていう語。また、憎しみうらやんでいう語。「こん―め」
⇒ちくしょう‐ざんがい【畜生残害】
⇒ちくしょう‐づか【畜生塚】
⇒ちくしょう‐づら【畜生面】
⇒ちくしょう‐どう【畜生道】
⇒ちくしょう‐ばら【畜生腹】
⇒ちくしょう‐ばらみ【畜生孕み】
ちく‐しょう【蓄妾】‥セフ
めかけを囲っておくこと。
ちく‐じょう【竹杖】‥ヂヤウ
竹のつえ。
⇒ちくじょう‐げどう【竹杖外道】
ちく‐じょう【逐条】‥デウ
箇条を追うこと。箇条を追って順々にすること。「―審議」
ちく‐じょう【築城】‥ジヤウ
城をきずくこと。また、陣地を作ること。「要害の地に―する」
ちくじょう‐げどう【竹杖外道】‥ヂヤウ‥ダウ
手に人頭に似た杖を持った外道の行者。釈尊の弟子目犍連もくけんれんを撃殺したという。竹林外道。執杖外道。
⇒ちく‐じょう【竹杖】
ちくしょう‐ざんがい【畜生残害】‥シヤウ‥
畜生が互いに噛み合って害すること。徒然草「生ける物を殺し、痛め、闘はしめて遊びたのしまん人は、―の類なり」
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐づか【畜生塚】‥シヤウ‥
1595年(文禄4)豊臣秀吉が養子秀次を自殺させ、妻妾子女30人余を斬に処し、その死骸を埋めた京都三条河原にあった塚。今、中京区瑞泉寺の境内にある。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐づら【畜生面】‥シヤウ‥
畜生のような顔つき。義理や人情を知らない人の顔つきをののしっていう語。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐どう【畜生道】‥シヤウダウ
①〔仏〕三悪趣さんあくしゅ・六道・十界の一つ。生前に悪業をなした者が趣おもむく世界。地獄道・餓鬼道より上だが、禽獣の姿に生まれて苦しむ。
②人倫上許しがたい間柄での色情。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐ばら【畜生腹】‥シヤウ‥
①女が1回に2子以上を産むこと。また、多産をののしっていう語。
②男女の双生児。前世で心中した者の生れ変りとしていう。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐ばらみ【畜生孕み】‥シヤウ‥
(→)畜生腹に同じ。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょきねん【竹書紀年】
夏・殷・周より戦国時代の魏に至る編年史。279年晋の汲郡(河南省)の人が戦国の魏の襄王の墓を発掘して得た竹簡。荀勗・和嶠が錯簡を正し、13巻とした。唐代以後また散逸(元・明代の2巻本は偽書)。清代、王国維らが逸文を集成。
ちくすい‐じつ【竹酔日】
陰暦5月13日の称。中国の俗説で、この日に竹を植えれば、よく繁茂するという。竹迷日。竜生りょうせいじつ日。竹植うる日。ちくすいにち。
ちく‐せい【竹声】
竹管を吹奏して発する音色。また、竹のそよぎ。
ちくせい【筑西】
茨城県西部の市。旧城下町下館を中心に、鬼怒川・小貝川などが南北に貫流し、田園地帯を形成。人口11万3千。
ちく‐せき【竹席】
薄く削りとった竹で編んだむしろ。たかむしろ。竹簟ちくてん。
ちく‐せき【逐斥】
追いしりぞけること。斥逐。
ちく‐せき【蓄積】
①たくわえためること。たくわえてたまったもの。「疲労が―する」「知識の―」
②資本家が利潤(剰余価値)の一部分のみを個人的消費につかい、残余を資本に転化して拡大再生産をはかること。
⇒ちくせき‐かん【蓄積管】
ちくせき‐かん【蓄積管】‥クワン
信号を記録・蓄積し、必要に応じて再生できる電子管。
⇒ちく‐せき【蓄積】
ちく‐せん【蓄銭】
金銭を貯蓄すること。また、たくわえた金銭。
ちくぜん【筑前】
旧国名。今の福岡県の北西部。
⇒ちくぜん‐に【筑前煮】
⇒ちくぜん‐びわ【筑前琵琶】
ちくぜん‐に【筑前煮】
鶏肉・根菜類・蒟蒻こんにゃくなどを油でいため、醤油と砂糖で煮た料理。福岡、筑前地方の郷土料理。筑前炊き。がめ煮。
⇒ちくぜん【筑前】
ちくぜん‐びわ【筑前琵琶】‥ビハ
琵琶の一種。また、その歌曲。楽琵琶や薩摩琵琶より小さく、桐胴。当初は4弦5柱、のちに5弦5柱のものが主流。撥ばちで弾奏。博多の橘智定(のち上京して初世旭翁1848〜1919)らが、明治20年代に筑前盲僧琵琶に薩摩琵琶と三味線音楽とを融合して創始。女性の演奏家が多く、優美な芸風が特色。旭会・橘会2派が代表的。代表曲は「湖水渡」「壇の浦」など。筑紫琵琶。
⇒ちくぜん【筑前】
ち‐くそ【血屎】
赤痢せきりの古称。
ちく‐そ【竹素】
(「素」は絹の意)(→)竹帛ちくはくに同じ。
ちく‐そう【竹窓】‥サウ
①竹の格子のついた窓。
②前に竹を植えてある窓。
ちく‐そう【竹槍】‥サウ
たけやり。
⇒ちくそう‐せっき【竹槍蓆旗】
ちく‐そう【竹叢】
たけやぶ。たかむら。
ちく‐ぞう【蓄蔵】‥ザウ
たくわえしまっておくこと。
⇒ちくぞう‐かへい【蓄蔵貨幣】
ちく‐ぞう【築造】‥ザウ
きずきつくること。
ちくぞう‐かへい【蓄蔵貨幣】‥ザウクワ‥
流通部面から引き上げられて蓄蔵された貨幣。商品の販売に引き続いて購買が行われないとき、貨幣は蓄蔵貨幣となる。退蔵貨幣。
⇒ちく‐ぞう【蓄蔵】
ちくそう‐せっき【竹槍蓆旗】‥サウセキ‥
たけやりとむしろばた。転じて、百姓一揆。
⇒ちく‐そう【竹槍】
ちく‐だい【竹台】
清涼殿の東庭に竹を植えた壇。石灰壇いしばいのだんの前のものを「河竹の台うてな」、仁寿殿じじゅうでんの西向の北方のものを「呉竹くれたけの台」という。たけのうてな。→清涼殿(図)
チクタク【ticktack】
時計の動く音を表す語。チックタック。
ち‐ぐち【乳口】
乳房の、乳の出る口。
ちく‐ちく
①こまごましたさま。こまぎれになっているさま。正徹物語「―として候へば鼠の足形のやうにありしなり」
②少しずつするさま。徐々に。仁勢物語「―と木末に春もなりぬれば」
③針やとげなど先のとがった物で小刻みに何度も浅く刺すさま。また、そのように責めるさま。「蚊に―と刺される」「―いやみを言う」
④繰り返し刺されるような痛みを肌や心などに感ずるさま。夏目漱石、こゝろ「私の良心は其度に―刺されるやうに痛みました」。「背中が―する」
ちく‐ちく【矗矗】
まっすぐ伸びるさま。そびえ立つさま。
ちく‐ちつ【竹帙】
細い竹で編んだ帙。帙簀ちす。たけちつ。
ち‐ぐ・つ【乳朽つ】
〔自上二〕
子供の歯が乳のために黒ずむ。日葡辞書「ハ(歯)ガチグチテ、また、チグチタ」
ちく‐てい【竹亭】
庭に竹を植えた亭。
ちく‐てい【築庭】
樹木や石を配置し、または泉水を設けるなどして、庭園を築造すること。造園。
ちく‐てい【築堤】
つつみを築くこと。また、築いた堤。
ちく‐でき【搐搦】
〔医〕(→)クローヌスに同じ。
ちく‐てん【逐電】
(チクデンとも。稲妻を追いかける意)
①きわめて早く行動するさま。急いでその場を立ち去ること。帥記「参内の後―退出了んぬ」。〈伊呂波字類抄〉
②ゆくえをくらまして逃げること。逃亡。出奔。失踪。平家物語5「かの夢見たる青侍せいしやがて―してんげり」
ちくでん【竹田】
⇒たのむらちくでん(田能村竹田)
ちく‐でん【蓄電】
電気をためること。充電。
⇒ちくでん‐き【蓄電器】
⇒ちくでん‐ち【蓄電池】
ちくでん‐き【蓄電器】
(→)コンデンサー1に同じ。
⇒ちく‐でん【蓄電】
ちくでん‐ち【蓄電池】
外部電源から得た電気的エネルギーを化学的エネルギーの形に変化して蓄え、必要に応じて、再び起電力として取り出す装置。普通に用いるのは、鉛蓄電池およびアルカリ蓄電池の2種。二次電池。バッテリー。
⇒ちく‐でん【蓄電】
ちく‐と
〔副〕
①すこし。ちょっと。ちと。東海道中膝栗毛2「よい酒があらば―出しなさろ」
②針などで刺すさま。ちくっと。
ちく‐とう【竹刀】‥タウ
①竹で作った刀。
②しない。
ちくとう‐ぼくせつ【竹頭木屑】
[晋書陶侃伝](船を造る時に出た竹の切れ端や木の切りくずをとっておき、後日それぞれに役立てた故事から)一見無用の物、また、瑣末な事も、おろそかにしないたとえ。
ちくどの【筑登之】
琉球王国で、里主さとぬし2に次ぐ官位。
ちく‐にく【畜肉】
家畜の肉。牛肉・豚肉・羊肉など。
ちぐぬ・く
〔自五〕
(茨城県で)うそをつく。
ちく‐ねつ【蓄熱】
熱を蓄えること。余剰となったエネルギーを蓄えておくこと。
ちく‐ねん【逐年】
年を追うこと。年々。
ちく‐ねん【蓄念】
かねてから心に思っている念願。宿念。
ちくのう‐しょう【蓄膿症】‥シヤウ
肋膜腔・副鼻腔・関節・脳腔などの体腔内に膿うみのたまる疾患。普通には、慢性の副鼻腔炎の場合をいい、頬部緊張、重圧感、頭痛、悪臭ある膿性の鼻汁分泌、嗅覚障害などを伴う。
 ⇒ち‐ぎれ
ちぎれ‐ちぎれ
幾つにもちぎれたさま。きれぎれ。「―の布」
⇒ち‐ぎれ
ち‐ぎ・れる
(「千切れる」とも書く)〔自下一〕[文]ちぎ・る(下二)
切れて離れる。ねじられて切れる。きれぎれになる。徒然草「頸も―・るばかり引きたるに」。「袖が―・れる」
チキン【chicken】
①鶏の雛ひな。また、その肉。転じて、鶏肉。「フライド‐―」
②臆病者。
⇒チキン‐カツレツ【chicken cutlet】
⇒チキン‐ライス
ち‐ぎん【地銀】
地方銀行の略。
チキン‐カツレツ【chicken cutlet】
鶏肉に小麦粉・溶き卵・パン粉をつけて油で揚げた料理。
⇒チキン【chicken】
チキン‐ライス
(和製語chicken rice)鶏肉・玉葱たまねぎなどと共に飯を炒め、トマト‐ケチャップなどで調味した料理。
⇒チキン【chicken】
ちく
(関東方言)うそ。物類称呼「うそといふを…常陸下野辺にて―とも又ちくらくともいふ」
ちく【竹】
中国の楽器の分類、八音はちおんの一つ。管楽器の類。転じて、笛の総称。
ちく【筑】
①中国の古代楽器。箏に似て小さい。頸が細く肩は円い。左手で柱ちゅうを押さえ、右手に竹の細棒を持って弦を打って鳴らす。周末より漢初にかけて燕えんの地方を中心に行われた。
②筑紫国つくしのくにの略。「―豊炭田」
ちく【築】
きずくこと。たてること。「―3年」
ち‐く【地区】
①地面の区域。一区画の土地。
②法令の施行地域を限るため、または特定の行政目的のためなどに特に指定された地域。「風致―」
ち‐く【知工】
近世、廻船の船員のうち、船内会計事務を受け持った役職。船頭に次ぐ地位。賄役。〈日葡辞書〉
ち‐く【馳駆】
①馬を走らせること。
②走りまわること。また、いろいろと世話をやくこと。奔走。
ち‐ぐ【知愚・智愚】
かしこいことと愚かなこと。知者と愚者。
ち‐ぐ【値遇】
(チグウとも)
①出合うこと。めぐりあうこと。太平記20「大慈大悲の薩埵に―し奉らば」
②親しくすること。
③「値遇の縁」の略。
⇒値遇の縁
ち‐ぐ【痴愚】
①おろか。ばか。
②医学で、精神薄弱のうち白痴と軽愚(魯鈍)との中間の段階をいった語。
ちくあん【竹庵】
藪医者の通称。→藪井竹庵やぶいちくあん
ちく‐い【竹葦】‥ヰ
竹とあし。物が多く密集するさまをいう。「稲麻とうま―」
ちく・い
〔形〕
小さい。ちっぽけである。滑稽本、続膝栗毛「こりや―・いのでござらア。でかいのは八畳敷もあらず」
ちく‐いち【逐一】
〔名・副〕
(チクイツとも)一つ一つ順を追うこと。いちいち詳細に。「―報告する」
ちく‐いつ【逐一】
〔名・副〕
⇒ちくいち。日葡辞書「チクイッニフンベッ(分別)シタ」
ちく‐いん【竹印】
竹材を彫った印判。
ちく‐いん【竹院】‥ヰン
竹を植えめぐらした屋敷。
ちく‐いん【竹陰】
竹のしげったかげ。
ち‐ぐう【知遇】
人格や識見を認めた上での厚い待遇。「―を得る」
ち‐ぐう【値遇】
⇒ちぐ。天草本平家物語「ただ平家に―したことをひるがへいて、源氏に合力せうずると」
ちく‐えん【竹園】‥ヱン
(→)「たけのその」に同じ。
ちく‐えん【竹縁】
竹で造ったえん。たけえん。
ちくおん‐き【蓄音機・蓄音器】
(phonograph)音波を記録したレコード盤から音を再生させる装置。レコード盤上には、音に対応する横ぶれを有する溝を刻み、溝に当たる針の振動を機械的に増幅して振動板に伝え音とする。1877年エジソンが発明。のち、針の振動を電気信号に変換し増幅する方式となる。尾崎紅葉、三人妻「聞かせたき人あり、こゝに―の無きこそ恨なれ」。夏目漱石、野分「無駄口を叩く学者や、―の代理をする教師が」
ちく‐かん【竹竿】
①直立した竹の幹。
②たけざお。
ちく‐かん【竹簡】
中国の戦国時代に、竹の豊富な楚の国などで、竹の小札に文字を書きしるしたもの。湖南省の長沙などで出土。→木簡
ちく‐きん【竹琴】
①竹製の胴を持つ弦楽器。
㋐太い竹筒を半分に割り、切断面に桐板を張って胴とし、その上に3弦を張った琴きん。1886年(明治19)沼津の田村与三郎(竹琴)が発明。
㋑葛原勾当の二弦琴の初名。→八雲琴やくもごと。
②木琴状に竹を並べた打楽器の総称。
ちくけい【竹渓】
中国山東省泰安の徂徠山下にある名勝。
⇒ちくけい‐の‐りくいつ【竹渓の六逸】
ちく‐けいかく【地区計画】‥クワク
市街地の建物形式・構造などを一体的に規制し、街区の整備を図る計画。
ちくけい‐の‐りくいつ【竹渓の六逸】
唐代、竹渓で詩酒の交わりをした6人の隠士、すなわち李白・孔巣父・韓準・裴政・張叔明・陶沔とうべんの称。
⇒ちくけい【竹渓】
ちくご【筑後】
①旧国名。今の福岡県の南部。
②福岡県南西部、筑紫平野南東部の市。花むしろ・ござ・和紙などを産。人口4万8千。
⇒ちくご‐がわ【筑後川】
⇒ちくご‐ぶし【筑後節】
ちく‐こう【竹工】
竹を加工して工芸品を製作する細工。また、その職人。
ちくご‐がわ【筑後川】‥ガハ
熊本・大分・福岡・佐賀の4県を流れる九州第一の川。熊本県阿蘇山北側に発源する大山川と、大分県九重山に発する玖珠くす川とを水源とし、日田盆地を経て筑紫平野を流れて有明海に注ぐ。長さ143キロメートル。筑紫次郎。
筑後川
撮影:山梨勝弘
⇒ち‐ぎれ
ちぎれ‐ちぎれ
幾つにもちぎれたさま。きれぎれ。「―の布」
⇒ち‐ぎれ
ち‐ぎ・れる
(「千切れる」とも書く)〔自下一〕[文]ちぎ・る(下二)
切れて離れる。ねじられて切れる。きれぎれになる。徒然草「頸も―・るばかり引きたるに」。「袖が―・れる」
チキン【chicken】
①鶏の雛ひな。また、その肉。転じて、鶏肉。「フライド‐―」
②臆病者。
⇒チキン‐カツレツ【chicken cutlet】
⇒チキン‐ライス
ち‐ぎん【地銀】
地方銀行の略。
チキン‐カツレツ【chicken cutlet】
鶏肉に小麦粉・溶き卵・パン粉をつけて油で揚げた料理。
⇒チキン【chicken】
チキン‐ライス
(和製語chicken rice)鶏肉・玉葱たまねぎなどと共に飯を炒め、トマト‐ケチャップなどで調味した料理。
⇒チキン【chicken】
ちく
(関東方言)うそ。物類称呼「うそといふを…常陸下野辺にて―とも又ちくらくともいふ」
ちく【竹】
中国の楽器の分類、八音はちおんの一つ。管楽器の類。転じて、笛の総称。
ちく【筑】
①中国の古代楽器。箏に似て小さい。頸が細く肩は円い。左手で柱ちゅうを押さえ、右手に竹の細棒を持って弦を打って鳴らす。周末より漢初にかけて燕えんの地方を中心に行われた。
②筑紫国つくしのくにの略。「―豊炭田」
ちく【築】
きずくこと。たてること。「―3年」
ち‐く【地区】
①地面の区域。一区画の土地。
②法令の施行地域を限るため、または特定の行政目的のためなどに特に指定された地域。「風致―」
ち‐く【知工】
近世、廻船の船員のうち、船内会計事務を受け持った役職。船頭に次ぐ地位。賄役。〈日葡辞書〉
ち‐く【馳駆】
①馬を走らせること。
②走りまわること。また、いろいろと世話をやくこと。奔走。
ち‐ぐ【知愚・智愚】
かしこいことと愚かなこと。知者と愚者。
ち‐ぐ【値遇】
(チグウとも)
①出合うこと。めぐりあうこと。太平記20「大慈大悲の薩埵に―し奉らば」
②親しくすること。
③「値遇の縁」の略。
⇒値遇の縁
ち‐ぐ【痴愚】
①おろか。ばか。
②医学で、精神薄弱のうち白痴と軽愚(魯鈍)との中間の段階をいった語。
ちくあん【竹庵】
藪医者の通称。→藪井竹庵やぶいちくあん
ちく‐い【竹葦】‥ヰ
竹とあし。物が多く密集するさまをいう。「稲麻とうま―」
ちく・い
〔形〕
小さい。ちっぽけである。滑稽本、続膝栗毛「こりや―・いのでござらア。でかいのは八畳敷もあらず」
ちく‐いち【逐一】
〔名・副〕
(チクイツとも)一つ一つ順を追うこと。いちいち詳細に。「―報告する」
ちく‐いつ【逐一】
〔名・副〕
⇒ちくいち。日葡辞書「チクイッニフンベッ(分別)シタ」
ちく‐いん【竹印】
竹材を彫った印判。
ちく‐いん【竹院】‥ヰン
竹を植えめぐらした屋敷。
ちく‐いん【竹陰】
竹のしげったかげ。
ち‐ぐう【知遇】
人格や識見を認めた上での厚い待遇。「―を得る」
ち‐ぐう【値遇】
⇒ちぐ。天草本平家物語「ただ平家に―したことをひるがへいて、源氏に合力せうずると」
ちく‐えん【竹園】‥ヱン
(→)「たけのその」に同じ。
ちく‐えん【竹縁】
竹で造ったえん。たけえん。
ちくおん‐き【蓄音機・蓄音器】
(phonograph)音波を記録したレコード盤から音を再生させる装置。レコード盤上には、音に対応する横ぶれを有する溝を刻み、溝に当たる針の振動を機械的に増幅して振動板に伝え音とする。1877年エジソンが発明。のち、針の振動を電気信号に変換し増幅する方式となる。尾崎紅葉、三人妻「聞かせたき人あり、こゝに―の無きこそ恨なれ」。夏目漱石、野分「無駄口を叩く学者や、―の代理をする教師が」
ちく‐かん【竹竿】
①直立した竹の幹。
②たけざお。
ちく‐かん【竹簡】
中国の戦国時代に、竹の豊富な楚の国などで、竹の小札に文字を書きしるしたもの。湖南省の長沙などで出土。→木簡
ちく‐きん【竹琴】
①竹製の胴を持つ弦楽器。
㋐太い竹筒を半分に割り、切断面に桐板を張って胴とし、その上に3弦を張った琴きん。1886年(明治19)沼津の田村与三郎(竹琴)が発明。
㋑葛原勾当の二弦琴の初名。→八雲琴やくもごと。
②木琴状に竹を並べた打楽器の総称。
ちくけい【竹渓】
中国山東省泰安の徂徠山下にある名勝。
⇒ちくけい‐の‐りくいつ【竹渓の六逸】
ちく‐けいかく【地区計画】‥クワク
市街地の建物形式・構造などを一体的に規制し、街区の整備を図る計画。
ちくけい‐の‐りくいつ【竹渓の六逸】
唐代、竹渓で詩酒の交わりをした6人の隠士、すなわち李白・孔巣父・韓準・裴政・張叔明・陶沔とうべんの称。
⇒ちくけい【竹渓】
ちくご【筑後】
①旧国名。今の福岡県の南部。
②福岡県南西部、筑紫平野南東部の市。花むしろ・ござ・和紙などを産。人口4万8千。
⇒ちくご‐がわ【筑後川】
⇒ちくご‐ぶし【筑後節】
ちく‐こう【竹工】
竹を加工して工芸品を製作する細工。また、その職人。
ちくご‐がわ【筑後川】‥ガハ
熊本・大分・福岡・佐賀の4県を流れる九州第一の川。熊本県阿蘇山北側に発源する大山川と、大分県九重山に発する玖珠くす川とを水源とし、日田盆地を経て筑紫平野を流れて有明海に注ぐ。長さ143キロメートル。筑紫次郎。
筑後川
撮影:山梨勝弘
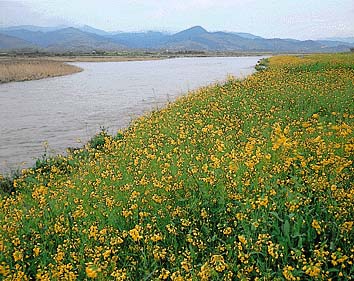 ⇒ちくご【筑後】
ちくご‐ぶし【筑後節】
義太夫節の異称。竹本義太夫が筑後掾ちくごのじょうを名乗ったことに由来。
⇒ちくご【筑後】
ちくご‐やく【逐語訳】
原文の一語一語に即して、忠実に翻訳・解釈すること。直訳。逐字訳。↔意訳
ちくさ【千種】
(チグサとも)姓氏の一つ。
⇒ちくさ‐ありこと【千種有功】
⇒ちくさ‐ただあき【千種忠顕】
ち‐ぐさ【千草】
(古くはチクサ)
①いろいろの草。古今和歌集春「咲く花は―ながらにあだなれど」。「庭の―」
②千草色の略。日本永代蔵5「浅黄の上を―に色揚げて」
⇒ちぐさ‐いろ【千草色】
ち‐ぐさ【千種】
(チクサとも)種類の多いこと。種々様々。いろいろ。くさぐさ。古今和歌集恋「秋の野に乱れて咲ける花の色の―に物を思ふころかな」
⇒ちぐさ‐がい【千種貝】
⇒ちぐさ‐の‐ほそぞめ【千種の細染】
ち‐ぐさ【乳草】
つる・茎などを切ると白い汁を出す植物の俗称。ガガイモ・ノウルシ・ノゲシ・タビラコなどを指す。ちちくさ。
ちくさ‐ありこと【千種有功】
江戸末期の歌人。号は千千廼舎ちぢのや。左近衛権中将。香川景樹と交わり、二条派の歌風を脱し一種の風格を持った。歌集「千千廼舎集」「日枝の百枝」など。(1797〜1854)
⇒ちくさ【千種】
ちくさい【竹斎】
仮名草子。2巻2冊。富山道冶とみやまどうや作。元和(1615〜1624)末頃刊行。山城の藪医者の竹斎が神社仏閣・名所旧跡をたずね江戸へ下る道中の滑稽・失敗の物語。後世への影響が大きい。竹斎物語。
ち‐くさ・い【血臭い】
〔形〕[文]ちくさ・し(ク)
血のにおいがする。ちなまぐさい。
ち‐くさ・い【乳臭い】
〔形〕[文]ちくさ・し(ク)
(→)「ちちくさい」に同じ。
ちく‐ざい【蓄財】
財産をたくわえること。また、その財産。「―にはげむ」「不正―」
ちぐさ‐いろ【千草色】
もえぎ色。そら色。ちぐさ。
Munsell color system: 10G7/2.5
⇒ち‐ぐさ【千草】
ちぐさ‐がい【千種貝】‥ガヒ
ニシキウズガイ科の巻貝。円錐形で小形、殻高約1.5センチメートル。赤・黄・樺などの美しい色彩を持つ。北海道南部以南の海藻の上に多い。
⇒ち‐ぐさ【千種】
ちく‐さく【竹冊】
文字を記した竹のふだ。竹簡。
ちく‐さく【竹柵】
竹のしがらみ。竹矢来。
ちくさ‐ただあき【千種忠顕】
南北朝時代の公家。後醍醐天皇に従い隠岐に渡る。建武政権では蔵人頭・近衛中将となり権勢を振るい、三木一草さんぼくいっそうの一人に数えられた。足利直義軍と戦い敗死。( 〜1336)
⇒ちくさ【千種】
ちく‐さつ【畜殺】
家畜類を殺すこと。屠畜とちく。
ちぐさ‐の‐ほそぞめ【千種の細染】
種々の色に染めたこまかい手のこんだ文様。
⇒ち‐ぐさ【千種】
ちく‐さん【畜産】
家畜を飼育・増殖し、人間生活に利用するものを得る産業。
⇒ちくさん‐がく【畜産学】
⇒ちくさん‐しけんじょう【畜産試験場】
⇒ちくさん‐だんち【畜産団地】
ちくさん‐がく【畜産学】
畜産を研究し、その改良・発達に役立てる学問。広義の農学の一分科。
⇒ちく‐さん【畜産】
ちくさん‐しけんじょう【畜産試験場】‥ヂヤウ
①農林水産省の一機関。畜産にかかわる改良・開発のための試験研究・調査・指導などを業務とした。2001年農業技術研究機構(現、農業‐食品産業技術総合研究機構)に改組・統合。
②1と同じ目的で設置された、各地方自治体所属の機関。
⇒ちく‐さん【畜産】
ちくさん‐だんち【畜産団地】
畜産の経営を大規模化し、生産・流通を大型化・合理化するために作られた営農集団。
⇒ちく‐さん【畜産】
ちく‐し【竹枝】
①竹の枝。
②楽府がふの一体。その土地の風俗、男女の情愛を民謡風に詠じたもの。唐の劉禹錫りゅううしゃくの創始。竹枝詞。
ちく‐し【竹紙】
①若竹の繊維を材料として製した中国産の紙。江戸中期以後、文人画家や書家が好んで用いた。
②江戸中期から越前で産した薄い鳥の子紙。
ちくし【筑紫】
⇒つくし
ちく‐じ【逐次】
〔副〕
(古くはチクシ)順を追って次々に。順次。
⇒ちくじ‐かんこうぶつ【逐次刊行物】
⇒ちくじ‐たんさく【逐次探索】
⇒ちくじ‐つうやく【逐次通訳】
⇒ちくじ‐はんのう【逐次反応】
ちくじ‐かんこうぶつ【逐次刊行物】‥カウ‥
雑誌・年報など、同一タイトルで継続して刊行する出版物。
⇒ちく‐じ【逐次】
ちくじ‐たんさく【逐次探索】
コンピューターで、格納されたデータを先頭から順に調べていく探索法。→二分探索。
⇒ちく‐じ【逐次】
ちく‐じつ【逐日】
〔副〕
日がたつに従って。日ましに。一日一日。
ちくじ‐つうやく【逐次通訳】
話者があるまとまりを話し終えてから、通訳者が翻訳する方式。→同時通訳。
⇒ちく‐じ【逐次】
ちくしの【筑紫野】
福岡市の南東にある市。中心地区二日市は古くから市場町・宿場町。福岡市の衛星都市。人口9万8千。
ちくじ‐はんのう【逐次反応】‥オウ
〔化〕(consecutive reaction)いくつかの素反応が相次いで起こる反応。
⇒ちく‐じ【逐次】
ちく‐しゃ【畜舎】
家畜を飼育し、畜産物を生産するための建物。家畜小屋。
ちくじ‐やく【逐字訳】
(→)逐語訳に同じ。
ちく‐しゅう【筑州】‥シウ
筑前ちくぜん国または筑後ちくご国の別称。
ちく‐しょう【畜生】‥シヤウ
①(人に畜やしなわれて生きているものの意)禽獣・虫魚の総称。今昔物語集15「慈悲深くして人を導き―を哀ぶことかぎりなし」
②〔仏〕畜生道に生まれた者。
③人をののしっていう語。また、憎しみうらやんでいう語。「こん―め」
⇒ちくしょう‐ざんがい【畜生残害】
⇒ちくしょう‐づか【畜生塚】
⇒ちくしょう‐づら【畜生面】
⇒ちくしょう‐どう【畜生道】
⇒ちくしょう‐ばら【畜生腹】
⇒ちくしょう‐ばらみ【畜生孕み】
ちく‐しょう【蓄妾】‥セフ
めかけを囲っておくこと。
ちく‐じょう【竹杖】‥ヂヤウ
竹のつえ。
⇒ちくじょう‐げどう【竹杖外道】
ちく‐じょう【逐条】‥デウ
箇条を追うこと。箇条を追って順々にすること。「―審議」
ちく‐じょう【築城】‥ジヤウ
城をきずくこと。また、陣地を作ること。「要害の地に―する」
ちくじょう‐げどう【竹杖外道】‥ヂヤウ‥ダウ
手に人頭に似た杖を持った外道の行者。釈尊の弟子目犍連もくけんれんを撃殺したという。竹林外道。執杖外道。
⇒ちく‐じょう【竹杖】
ちくしょう‐ざんがい【畜生残害】‥シヤウ‥
畜生が互いに噛み合って害すること。徒然草「生ける物を殺し、痛め、闘はしめて遊びたのしまん人は、―の類なり」
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐づか【畜生塚】‥シヤウ‥
1595年(文禄4)豊臣秀吉が養子秀次を自殺させ、妻妾子女30人余を斬に処し、その死骸を埋めた京都三条河原にあった塚。今、中京区瑞泉寺の境内にある。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐づら【畜生面】‥シヤウ‥
畜生のような顔つき。義理や人情を知らない人の顔つきをののしっていう語。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐どう【畜生道】‥シヤウダウ
①〔仏〕三悪趣さんあくしゅ・六道・十界の一つ。生前に悪業をなした者が趣おもむく世界。地獄道・餓鬼道より上だが、禽獣の姿に生まれて苦しむ。
②人倫上許しがたい間柄での色情。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐ばら【畜生腹】‥シヤウ‥
①女が1回に2子以上を産むこと。また、多産をののしっていう語。
②男女の双生児。前世で心中した者の生れ変りとしていう。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐ばらみ【畜生孕み】‥シヤウ‥
(→)畜生腹に同じ。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょきねん【竹書紀年】
夏・殷・周より戦国時代の魏に至る編年史。279年晋の汲郡(河南省)の人が戦国の魏の襄王の墓を発掘して得た竹簡。荀勗・和嶠が錯簡を正し、13巻とした。唐代以後また散逸(元・明代の2巻本は偽書)。清代、王国維らが逸文を集成。
ちくすい‐じつ【竹酔日】
陰暦5月13日の称。中国の俗説で、この日に竹を植えれば、よく繁茂するという。竹迷日。竜生りょうせいじつ日。竹植うる日。ちくすいにち。
ちく‐せい【竹声】
竹管を吹奏して発する音色。また、竹のそよぎ。
ちくせい【筑西】
茨城県西部の市。旧城下町下館を中心に、鬼怒川・小貝川などが南北に貫流し、田園地帯を形成。人口11万3千。
ちく‐せき【竹席】
薄く削りとった竹で編んだむしろ。たかむしろ。竹簟ちくてん。
ちく‐せき【逐斥】
追いしりぞけること。斥逐。
ちく‐せき【蓄積】
①たくわえためること。たくわえてたまったもの。「疲労が―する」「知識の―」
②資本家が利潤(剰余価値)の一部分のみを個人的消費につかい、残余を資本に転化して拡大再生産をはかること。
⇒ちくせき‐かん【蓄積管】
ちくせき‐かん【蓄積管】‥クワン
信号を記録・蓄積し、必要に応じて再生できる電子管。
⇒ちく‐せき【蓄積】
ちく‐せん【蓄銭】
金銭を貯蓄すること。また、たくわえた金銭。
ちくぜん【筑前】
旧国名。今の福岡県の北西部。
⇒ちくぜん‐に【筑前煮】
⇒ちくぜん‐びわ【筑前琵琶】
ちくぜん‐に【筑前煮】
鶏肉・根菜類・蒟蒻こんにゃくなどを油でいため、醤油と砂糖で煮た料理。福岡、筑前地方の郷土料理。筑前炊き。がめ煮。
⇒ちくぜん【筑前】
ちくぜん‐びわ【筑前琵琶】‥ビハ
琵琶の一種。また、その歌曲。楽琵琶や薩摩琵琶より小さく、桐胴。当初は4弦5柱、のちに5弦5柱のものが主流。撥ばちで弾奏。博多の橘智定(のち上京して初世旭翁1848〜1919)らが、明治20年代に筑前盲僧琵琶に薩摩琵琶と三味線音楽とを融合して創始。女性の演奏家が多く、優美な芸風が特色。旭会・橘会2派が代表的。代表曲は「湖水渡」「壇の浦」など。筑紫琵琶。
⇒ちくぜん【筑前】
ち‐くそ【血屎】
赤痢せきりの古称。
ちく‐そ【竹素】
(「素」は絹の意)(→)竹帛ちくはくに同じ。
ちく‐そう【竹窓】‥サウ
①竹の格子のついた窓。
②前に竹を植えてある窓。
ちく‐そう【竹槍】‥サウ
たけやり。
⇒ちくそう‐せっき【竹槍蓆旗】
ちく‐そう【竹叢】
たけやぶ。たかむら。
ちく‐ぞう【蓄蔵】‥ザウ
たくわえしまっておくこと。
⇒ちくぞう‐かへい【蓄蔵貨幣】
ちく‐ぞう【築造】‥ザウ
きずきつくること。
ちくぞう‐かへい【蓄蔵貨幣】‥ザウクワ‥
流通部面から引き上げられて蓄蔵された貨幣。商品の販売に引き続いて購買が行われないとき、貨幣は蓄蔵貨幣となる。退蔵貨幣。
⇒ちく‐ぞう【蓄蔵】
ちくそう‐せっき【竹槍蓆旗】‥サウセキ‥
たけやりとむしろばた。転じて、百姓一揆。
⇒ちく‐そう【竹槍】
ちく‐だい【竹台】
清涼殿の東庭に竹を植えた壇。石灰壇いしばいのだんの前のものを「河竹の台うてな」、仁寿殿じじゅうでんの西向の北方のものを「呉竹くれたけの台」という。たけのうてな。→清涼殿(図)
チクタク【ticktack】
時計の動く音を表す語。チックタック。
ち‐ぐち【乳口】
乳房の、乳の出る口。
ちく‐ちく
①こまごましたさま。こまぎれになっているさま。正徹物語「―として候へば鼠の足形のやうにありしなり」
②少しずつするさま。徐々に。仁勢物語「―と木末に春もなりぬれば」
③針やとげなど先のとがった物で小刻みに何度も浅く刺すさま。また、そのように責めるさま。「蚊に―と刺される」「―いやみを言う」
④繰り返し刺されるような痛みを肌や心などに感ずるさま。夏目漱石、こゝろ「私の良心は其度に―刺されるやうに痛みました」。「背中が―する」
ちく‐ちく【矗矗】
まっすぐ伸びるさま。そびえ立つさま。
ちく‐ちつ【竹帙】
細い竹で編んだ帙。帙簀ちす。たけちつ。
ち‐ぐ・つ【乳朽つ】
〔自上二〕
子供の歯が乳のために黒ずむ。日葡辞書「ハ(歯)ガチグチテ、また、チグチタ」
ちく‐てい【竹亭】
庭に竹を植えた亭。
ちく‐てい【築庭】
樹木や石を配置し、または泉水を設けるなどして、庭園を築造すること。造園。
ちく‐てい【築堤】
つつみを築くこと。また、築いた堤。
ちく‐でき【搐搦】
〔医〕(→)クローヌスに同じ。
ちく‐てん【逐電】
(チクデンとも。稲妻を追いかける意)
①きわめて早く行動するさま。急いでその場を立ち去ること。帥記「参内の後―退出了んぬ」。〈伊呂波字類抄〉
②ゆくえをくらまして逃げること。逃亡。出奔。失踪。平家物語5「かの夢見たる青侍せいしやがて―してんげり」
ちくでん【竹田】
⇒たのむらちくでん(田能村竹田)
ちく‐でん【蓄電】
電気をためること。充電。
⇒ちくでん‐き【蓄電器】
⇒ちくでん‐ち【蓄電池】
ちくでん‐き【蓄電器】
(→)コンデンサー1に同じ。
⇒ちく‐でん【蓄電】
ちくでん‐ち【蓄電池】
外部電源から得た電気的エネルギーを化学的エネルギーの形に変化して蓄え、必要に応じて、再び起電力として取り出す装置。普通に用いるのは、鉛蓄電池およびアルカリ蓄電池の2種。二次電池。バッテリー。
⇒ちく‐でん【蓄電】
ちく‐と
〔副〕
①すこし。ちょっと。ちと。東海道中膝栗毛2「よい酒があらば―出しなさろ」
②針などで刺すさま。ちくっと。
ちく‐とう【竹刀】‥タウ
①竹で作った刀。
②しない。
ちくとう‐ぼくせつ【竹頭木屑】
[晋書陶侃伝](船を造る時に出た竹の切れ端や木の切りくずをとっておき、後日それぞれに役立てた故事から)一見無用の物、また、瑣末な事も、おろそかにしないたとえ。
ちくどの【筑登之】
琉球王国で、里主さとぬし2に次ぐ官位。
ちく‐にく【畜肉】
家畜の肉。牛肉・豚肉・羊肉など。
ちぐぬ・く
〔自五〕
(茨城県で)うそをつく。
ちく‐ねつ【蓄熱】
熱を蓄えること。余剰となったエネルギーを蓄えておくこと。
ちく‐ねん【逐年】
年を追うこと。年々。
ちく‐ねん【蓄念】
かねてから心に思っている念願。宿念。
ちくのう‐しょう【蓄膿症】‥シヤウ
肋膜腔・副鼻腔・関節・脳腔などの体腔内に膿うみのたまる疾患。普通には、慢性の副鼻腔炎の場合をいい、頬部緊張、重圧感、頭痛、悪臭ある膿性の鼻汁分泌、嗅覚障害などを伴う。
⇒ちくご【筑後】
ちくご‐ぶし【筑後節】
義太夫節の異称。竹本義太夫が筑後掾ちくごのじょうを名乗ったことに由来。
⇒ちくご【筑後】
ちくご‐やく【逐語訳】
原文の一語一語に即して、忠実に翻訳・解釈すること。直訳。逐字訳。↔意訳
ちくさ【千種】
(チグサとも)姓氏の一つ。
⇒ちくさ‐ありこと【千種有功】
⇒ちくさ‐ただあき【千種忠顕】
ち‐ぐさ【千草】
(古くはチクサ)
①いろいろの草。古今和歌集春「咲く花は―ながらにあだなれど」。「庭の―」
②千草色の略。日本永代蔵5「浅黄の上を―に色揚げて」
⇒ちぐさ‐いろ【千草色】
ち‐ぐさ【千種】
(チクサとも)種類の多いこと。種々様々。いろいろ。くさぐさ。古今和歌集恋「秋の野に乱れて咲ける花の色の―に物を思ふころかな」
⇒ちぐさ‐がい【千種貝】
⇒ちぐさ‐の‐ほそぞめ【千種の細染】
ち‐ぐさ【乳草】
つる・茎などを切ると白い汁を出す植物の俗称。ガガイモ・ノウルシ・ノゲシ・タビラコなどを指す。ちちくさ。
ちくさ‐ありこと【千種有功】
江戸末期の歌人。号は千千廼舎ちぢのや。左近衛権中将。香川景樹と交わり、二条派の歌風を脱し一種の風格を持った。歌集「千千廼舎集」「日枝の百枝」など。(1797〜1854)
⇒ちくさ【千種】
ちくさい【竹斎】
仮名草子。2巻2冊。富山道冶とみやまどうや作。元和(1615〜1624)末頃刊行。山城の藪医者の竹斎が神社仏閣・名所旧跡をたずね江戸へ下る道中の滑稽・失敗の物語。後世への影響が大きい。竹斎物語。
ち‐くさ・い【血臭い】
〔形〕[文]ちくさ・し(ク)
血のにおいがする。ちなまぐさい。
ち‐くさ・い【乳臭い】
〔形〕[文]ちくさ・し(ク)
(→)「ちちくさい」に同じ。
ちく‐ざい【蓄財】
財産をたくわえること。また、その財産。「―にはげむ」「不正―」
ちぐさ‐いろ【千草色】
もえぎ色。そら色。ちぐさ。
Munsell color system: 10G7/2.5
⇒ち‐ぐさ【千草】
ちぐさ‐がい【千種貝】‥ガヒ
ニシキウズガイ科の巻貝。円錐形で小形、殻高約1.5センチメートル。赤・黄・樺などの美しい色彩を持つ。北海道南部以南の海藻の上に多い。
⇒ち‐ぐさ【千種】
ちく‐さく【竹冊】
文字を記した竹のふだ。竹簡。
ちく‐さく【竹柵】
竹のしがらみ。竹矢来。
ちくさ‐ただあき【千種忠顕】
南北朝時代の公家。後醍醐天皇に従い隠岐に渡る。建武政権では蔵人頭・近衛中将となり権勢を振るい、三木一草さんぼくいっそうの一人に数えられた。足利直義軍と戦い敗死。( 〜1336)
⇒ちくさ【千種】
ちく‐さつ【畜殺】
家畜類を殺すこと。屠畜とちく。
ちぐさ‐の‐ほそぞめ【千種の細染】
種々の色に染めたこまかい手のこんだ文様。
⇒ち‐ぐさ【千種】
ちく‐さん【畜産】
家畜を飼育・増殖し、人間生活に利用するものを得る産業。
⇒ちくさん‐がく【畜産学】
⇒ちくさん‐しけんじょう【畜産試験場】
⇒ちくさん‐だんち【畜産団地】
ちくさん‐がく【畜産学】
畜産を研究し、その改良・発達に役立てる学問。広義の農学の一分科。
⇒ちく‐さん【畜産】
ちくさん‐しけんじょう【畜産試験場】‥ヂヤウ
①農林水産省の一機関。畜産にかかわる改良・開発のための試験研究・調査・指導などを業務とした。2001年農業技術研究機構(現、農業‐食品産業技術総合研究機構)に改組・統合。
②1と同じ目的で設置された、各地方自治体所属の機関。
⇒ちく‐さん【畜産】
ちくさん‐だんち【畜産団地】
畜産の経営を大規模化し、生産・流通を大型化・合理化するために作られた営農集団。
⇒ちく‐さん【畜産】
ちく‐し【竹枝】
①竹の枝。
②楽府がふの一体。その土地の風俗、男女の情愛を民謡風に詠じたもの。唐の劉禹錫りゅううしゃくの創始。竹枝詞。
ちく‐し【竹紙】
①若竹の繊維を材料として製した中国産の紙。江戸中期以後、文人画家や書家が好んで用いた。
②江戸中期から越前で産した薄い鳥の子紙。
ちくし【筑紫】
⇒つくし
ちく‐じ【逐次】
〔副〕
(古くはチクシ)順を追って次々に。順次。
⇒ちくじ‐かんこうぶつ【逐次刊行物】
⇒ちくじ‐たんさく【逐次探索】
⇒ちくじ‐つうやく【逐次通訳】
⇒ちくじ‐はんのう【逐次反応】
ちくじ‐かんこうぶつ【逐次刊行物】‥カウ‥
雑誌・年報など、同一タイトルで継続して刊行する出版物。
⇒ちく‐じ【逐次】
ちくじ‐たんさく【逐次探索】
コンピューターで、格納されたデータを先頭から順に調べていく探索法。→二分探索。
⇒ちく‐じ【逐次】
ちく‐じつ【逐日】
〔副〕
日がたつに従って。日ましに。一日一日。
ちくじ‐つうやく【逐次通訳】
話者があるまとまりを話し終えてから、通訳者が翻訳する方式。→同時通訳。
⇒ちく‐じ【逐次】
ちくしの【筑紫野】
福岡市の南東にある市。中心地区二日市は古くから市場町・宿場町。福岡市の衛星都市。人口9万8千。
ちくじ‐はんのう【逐次反応】‥オウ
〔化〕(consecutive reaction)いくつかの素反応が相次いで起こる反応。
⇒ちく‐じ【逐次】
ちく‐しゃ【畜舎】
家畜を飼育し、畜産物を生産するための建物。家畜小屋。
ちくじ‐やく【逐字訳】
(→)逐語訳に同じ。
ちく‐しゅう【筑州】‥シウ
筑前ちくぜん国または筑後ちくご国の別称。
ちく‐しょう【畜生】‥シヤウ
①(人に畜やしなわれて生きているものの意)禽獣・虫魚の総称。今昔物語集15「慈悲深くして人を導き―を哀ぶことかぎりなし」
②〔仏〕畜生道に生まれた者。
③人をののしっていう語。また、憎しみうらやんでいう語。「こん―め」
⇒ちくしょう‐ざんがい【畜生残害】
⇒ちくしょう‐づか【畜生塚】
⇒ちくしょう‐づら【畜生面】
⇒ちくしょう‐どう【畜生道】
⇒ちくしょう‐ばら【畜生腹】
⇒ちくしょう‐ばらみ【畜生孕み】
ちく‐しょう【蓄妾】‥セフ
めかけを囲っておくこと。
ちく‐じょう【竹杖】‥ヂヤウ
竹のつえ。
⇒ちくじょう‐げどう【竹杖外道】
ちく‐じょう【逐条】‥デウ
箇条を追うこと。箇条を追って順々にすること。「―審議」
ちく‐じょう【築城】‥ジヤウ
城をきずくこと。また、陣地を作ること。「要害の地に―する」
ちくじょう‐げどう【竹杖外道】‥ヂヤウ‥ダウ
手に人頭に似た杖を持った外道の行者。釈尊の弟子目犍連もくけんれんを撃殺したという。竹林外道。執杖外道。
⇒ちく‐じょう【竹杖】
ちくしょう‐ざんがい【畜生残害】‥シヤウ‥
畜生が互いに噛み合って害すること。徒然草「生ける物を殺し、痛め、闘はしめて遊びたのしまん人は、―の類なり」
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐づか【畜生塚】‥シヤウ‥
1595年(文禄4)豊臣秀吉が養子秀次を自殺させ、妻妾子女30人余を斬に処し、その死骸を埋めた京都三条河原にあった塚。今、中京区瑞泉寺の境内にある。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐づら【畜生面】‥シヤウ‥
畜生のような顔つき。義理や人情を知らない人の顔つきをののしっていう語。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐どう【畜生道】‥シヤウダウ
①〔仏〕三悪趣さんあくしゅ・六道・十界の一つ。生前に悪業をなした者が趣おもむく世界。地獄道・餓鬼道より上だが、禽獣の姿に生まれて苦しむ。
②人倫上許しがたい間柄での色情。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐ばら【畜生腹】‥シヤウ‥
①女が1回に2子以上を産むこと。また、多産をののしっていう語。
②男女の双生児。前世で心中した者の生れ変りとしていう。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょう‐ばらみ【畜生孕み】‥シヤウ‥
(→)畜生腹に同じ。
⇒ちく‐しょう【畜生】
ちくしょきねん【竹書紀年】
夏・殷・周より戦国時代の魏に至る編年史。279年晋の汲郡(河南省)の人が戦国の魏の襄王の墓を発掘して得た竹簡。荀勗・和嶠が錯簡を正し、13巻とした。唐代以後また散逸(元・明代の2巻本は偽書)。清代、王国維らが逸文を集成。
ちくすい‐じつ【竹酔日】
陰暦5月13日の称。中国の俗説で、この日に竹を植えれば、よく繁茂するという。竹迷日。竜生りょうせいじつ日。竹植うる日。ちくすいにち。
ちく‐せい【竹声】
竹管を吹奏して発する音色。また、竹のそよぎ。
ちくせい【筑西】
茨城県西部の市。旧城下町下館を中心に、鬼怒川・小貝川などが南北に貫流し、田園地帯を形成。人口11万3千。
ちく‐せき【竹席】
薄く削りとった竹で編んだむしろ。たかむしろ。竹簟ちくてん。
ちく‐せき【逐斥】
追いしりぞけること。斥逐。
ちく‐せき【蓄積】
①たくわえためること。たくわえてたまったもの。「疲労が―する」「知識の―」
②資本家が利潤(剰余価値)の一部分のみを個人的消費につかい、残余を資本に転化して拡大再生産をはかること。
⇒ちくせき‐かん【蓄積管】
ちくせき‐かん【蓄積管】‥クワン
信号を記録・蓄積し、必要に応じて再生できる電子管。
⇒ちく‐せき【蓄積】
ちく‐せん【蓄銭】
金銭を貯蓄すること。また、たくわえた金銭。
ちくぜん【筑前】
旧国名。今の福岡県の北西部。
⇒ちくぜん‐に【筑前煮】
⇒ちくぜん‐びわ【筑前琵琶】
ちくぜん‐に【筑前煮】
鶏肉・根菜類・蒟蒻こんにゃくなどを油でいため、醤油と砂糖で煮た料理。福岡、筑前地方の郷土料理。筑前炊き。がめ煮。
⇒ちくぜん【筑前】
ちくぜん‐びわ【筑前琵琶】‥ビハ
琵琶の一種。また、その歌曲。楽琵琶や薩摩琵琶より小さく、桐胴。当初は4弦5柱、のちに5弦5柱のものが主流。撥ばちで弾奏。博多の橘智定(のち上京して初世旭翁1848〜1919)らが、明治20年代に筑前盲僧琵琶に薩摩琵琶と三味線音楽とを融合して創始。女性の演奏家が多く、優美な芸風が特色。旭会・橘会2派が代表的。代表曲は「湖水渡」「壇の浦」など。筑紫琵琶。
⇒ちくぜん【筑前】
ち‐くそ【血屎】
赤痢せきりの古称。
ちく‐そ【竹素】
(「素」は絹の意)(→)竹帛ちくはくに同じ。
ちく‐そう【竹窓】‥サウ
①竹の格子のついた窓。
②前に竹を植えてある窓。
ちく‐そう【竹槍】‥サウ
たけやり。
⇒ちくそう‐せっき【竹槍蓆旗】
ちく‐そう【竹叢】
たけやぶ。たかむら。
ちく‐ぞう【蓄蔵】‥ザウ
たくわえしまっておくこと。
⇒ちくぞう‐かへい【蓄蔵貨幣】
ちく‐ぞう【築造】‥ザウ
きずきつくること。
ちくぞう‐かへい【蓄蔵貨幣】‥ザウクワ‥
流通部面から引き上げられて蓄蔵された貨幣。商品の販売に引き続いて購買が行われないとき、貨幣は蓄蔵貨幣となる。退蔵貨幣。
⇒ちく‐ぞう【蓄蔵】
ちくそう‐せっき【竹槍蓆旗】‥サウセキ‥
たけやりとむしろばた。転じて、百姓一揆。
⇒ちく‐そう【竹槍】
ちく‐だい【竹台】
清涼殿の東庭に竹を植えた壇。石灰壇いしばいのだんの前のものを「河竹の台うてな」、仁寿殿じじゅうでんの西向の北方のものを「呉竹くれたけの台」という。たけのうてな。→清涼殿(図)
チクタク【ticktack】
時計の動く音を表す語。チックタック。
ち‐ぐち【乳口】
乳房の、乳の出る口。
ちく‐ちく
①こまごましたさま。こまぎれになっているさま。正徹物語「―として候へば鼠の足形のやうにありしなり」
②少しずつするさま。徐々に。仁勢物語「―と木末に春もなりぬれば」
③針やとげなど先のとがった物で小刻みに何度も浅く刺すさま。また、そのように責めるさま。「蚊に―と刺される」「―いやみを言う」
④繰り返し刺されるような痛みを肌や心などに感ずるさま。夏目漱石、こゝろ「私の良心は其度に―刺されるやうに痛みました」。「背中が―する」
ちく‐ちく【矗矗】
まっすぐ伸びるさま。そびえ立つさま。
ちく‐ちつ【竹帙】
細い竹で編んだ帙。帙簀ちす。たけちつ。
ち‐ぐ・つ【乳朽つ】
〔自上二〕
子供の歯が乳のために黒ずむ。日葡辞書「ハ(歯)ガチグチテ、また、チグチタ」
ちく‐てい【竹亭】
庭に竹を植えた亭。
ちく‐てい【築庭】
樹木や石を配置し、または泉水を設けるなどして、庭園を築造すること。造園。
ちく‐てい【築堤】
つつみを築くこと。また、築いた堤。
ちく‐でき【搐搦】
〔医〕(→)クローヌスに同じ。
ちく‐てん【逐電】
(チクデンとも。稲妻を追いかける意)
①きわめて早く行動するさま。急いでその場を立ち去ること。帥記「参内の後―退出了んぬ」。〈伊呂波字類抄〉
②ゆくえをくらまして逃げること。逃亡。出奔。失踪。平家物語5「かの夢見たる青侍せいしやがて―してんげり」
ちくでん【竹田】
⇒たのむらちくでん(田能村竹田)
ちく‐でん【蓄電】
電気をためること。充電。
⇒ちくでん‐き【蓄電器】
⇒ちくでん‐ち【蓄電池】
ちくでん‐き【蓄電器】
(→)コンデンサー1に同じ。
⇒ちく‐でん【蓄電】
ちくでん‐ち【蓄電池】
外部電源から得た電気的エネルギーを化学的エネルギーの形に変化して蓄え、必要に応じて、再び起電力として取り出す装置。普通に用いるのは、鉛蓄電池およびアルカリ蓄電池の2種。二次電池。バッテリー。
⇒ちく‐でん【蓄電】
ちく‐と
〔副〕
①すこし。ちょっと。ちと。東海道中膝栗毛2「よい酒があらば―出しなさろ」
②針などで刺すさま。ちくっと。
ちく‐とう【竹刀】‥タウ
①竹で作った刀。
②しない。
ちくとう‐ぼくせつ【竹頭木屑】
[晋書陶侃伝](船を造る時に出た竹の切れ端や木の切りくずをとっておき、後日それぞれに役立てた故事から)一見無用の物、また、瑣末な事も、おろそかにしないたとえ。
ちくどの【筑登之】
琉球王国で、里主さとぬし2に次ぐ官位。
ちく‐にく【畜肉】
家畜の肉。牛肉・豚肉・羊肉など。
ちぐぬ・く
〔自五〕
(茨城県で)うそをつく。
ちく‐ねつ【蓄熱】
熱を蓄えること。余剰となったエネルギーを蓄えておくこと。
ちく‐ねん【逐年】
年を追うこと。年々。
ちく‐ねん【蓄念】
かねてから心に思っている念願。宿念。
ちくのう‐しょう【蓄膿症】‥シヤウ
肋膜腔・副鼻腔・関節・脳腔などの体腔内に膿うみのたまる疾患。普通には、慢性の副鼻腔炎の場合をいい、頬部緊張、重圧感、頭痛、悪臭ある膿性の鼻汁分泌、嗅覚障害などを伴う。
広辞苑 ページ 12588 での【○契りを籠む】単語。