複数辞典一括検索+![]()
![]()
○旋毛を曲げるつむじをまげる🔗⭐🔉
○旋毛を曲げるつむじをまげる
気分をそこね、意地わるく反対して従わない。わざとひねくれる。
⇒つむじ【旋毛】
つむら‐べついん【津村別院】‥ヰン
大阪市中央区にある浄土真宗本願寺派の別院。大谷派の難波別院(南御堂)に対し北御堂と称する。1591年(天正19)石山本願寺が京都に移った後、大坂の門徒が准如じゅんにょを請じて創立。
つむり【頭】
あたま。つぶり。
⇒つむり‐かけ【頭掛】
⇒つむり‐の‐もの【頭の物】
つむり‐かけ【頭掛】
(→)「袖被り」に同じ。
⇒つむり【頭】
つむり‐の‐ひかる【頭光】
江戸後期の狂歌師。本名、岸識之。別号、桑楊庵・2世巴人亭。江戸日本橋亀井町の町代ちょうだいで、狂歌四天王の一人。その社中を伯楽連と称した。つぶりのひかる。(1754〜1796)
つむり‐の‐もの【頭の物】
女の頭髪を飾るもの。櫛くし・笄こうがい・簪かんざしなどの総称。
⇒つむり【頭】
つむ・る【瞑る】
〔他五〕
(→)「つぶる」に同じ。
つむれ【培塿】
小高くなった土地。〈倭名類聚鈔1〉
つめ
文楽人形の首かしらの一つ。男女の雑多な端役に用いるもの。
つめ【爪】
①指または趾あしゆびの先端に生じる角質の突起。表皮の堅くなったもの。人の爪は扁爪ひらづめといい、他の動物には鉤爪かぎづめと蹄ひづめがある。また、昆虫では跗節ふせつの末端の小節をいう。万葉集18「馬の―い尽す極み」
②琴爪ことづめ。また、鞍爪くらづめ。
③物をひっかけるために装置した物、すなわち、こはぜ・鉤かぎの類。
④花弁の基部の細まった部分。
⇒爪食う
⇒爪で拾って箕で零す
⇒爪に爪なく瓜に爪あり
⇒爪に火をともす
⇒爪を隠す
⇒爪を銜える
⇒爪を研ぐ
つめ【詰め】
①物をつめること。
②隙間につめこむもの。日葡辞書「ツメヲカ(支)ウ」
③物の端。きわ。特に、橋のたもと。万葉集9「大橋の―に家あらば」
④かぎり。結末。三道「その所の名歌・名句の言葉を取ること、能の破三段の中の―と覚しからん在所に書くべし」
⑤勝負・決着をつけるべき最後の追込み・手順。また、物事の最後の段取り。「―が甘い」
⑥城の最も高い所。日葡辞書「シロノツメ」
⑦(振袖に対する脇つめの衣の意から)年増としまの女。わきつめ。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「枕の御伽が御用ならば振袖なりと―なりと」
⑧(→)「おつめ」に同じ。
⑨蹴鞠けまりで、詰め寄せること。狂言、八幡の前「お若い衆の遊ばすに依て―を致いてござる」
⑩牢ろう内の便所。大便。
⑪(「づめ」の形で)
㋐詰めること。また、詰めてあるもの。「瓶―」「氷―」
㋑一定の場所に控えて勤務すること。その場所、また、その人。「警視庁―の記者」
㋒もっぱらそれで通すこと。「理―」「規則―」
㋓(動詞の連用形に付けて)その状態が続くこと。「笑い―」「働き―」
づめ【詰め】
⇒つめ11
つめ‐あい【詰め合い】‥アヒ
①共に同じ所につめていること。同じ所に勤めていること。また、その人。
②論じあうこと。
つめ‐あ・う【詰め合ふ】‥アフ
〔自四〕
①同じ所に出仕する。同じ所に勤める。
②論じあって互いにつめよる。歌舞伎、傾城壬生大念仏「後に若林と―・ひ、実めきて面白し」
つめ‐あと【爪痕】
①物についている爪のかた。
②爪でかいたきずあと。比喩的に、事件・災害が残した被害や影響。「台風の―」
つめ‐あわせ【詰合せ】‥アハセ
一つの容器にいろいろの品物を詰めること。また、その詰めたもの。「果物の―」
つめ‐あわ・せる【詰め合わせる】‥アハセル
〔他下一〕[文]つめあは・す(下二)
いろいろの品物を一つの容器に一緒に詰める。
つめ‐いくさ【詰め軍】
敵を追いつめて戦ういくさ。義経記4「壇の浦の―までもつひに弱げを見せ給はず」
つめ‐いし【詰め石】
積み上げた石。積石。また、いしずえ。栄華物語音楽「大象の―、紫金銀の棟」
つめ‐いん【爪印】
(ソウインとも)爪先に墨・印肉をつけ、印鑑の代りに押して証とするもの。墨などをつけないで、紙面に爪痕だけをつける場合もある。奈良時代に中国から伝わり江戸時代に盛行。爪判そうはん。つめばん。
つめ‐うた【詰歌】
狂歌の一種。故意に名詞・助詞などを省略、要約したもの。天明(1781〜1789)ごろ江戸で流行。
つめ‐えり【詰襟】
洋服の襟の立っているもの。また、その洋服。軍服や学生服に多い。
つめ‐かえ【詰め替え】‥カヘ
つめかえること。また、つめかえたもの。
つめ‐か・える【詰め替える】‥カヘル
〔他下一〕[文]つめか・ふ(下二)
改めてつめる。つめなおす。「パイプの煙草を―・える」「大瓶から小瓶に―・える」
つめ‐がえる【爪蛙】‥ガヘル
カエルの一種。体長約10センチメートル。後肢のみずかきはよく発達し、内側の3本の指先に黒色の爪がある。ほとんど水中生活。舌がないので、前肢を使って餌をとる。オタマジャクシは透きとおっていて、口角にひげがある。アフリカ中部・南部に分布。医学などの実験動物として広く飼育。ペットとしても人気がある。アフリカツメガエル。
つめがえる
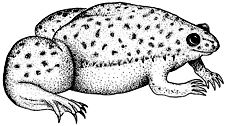 ツメガエル
提供:東京動物園協会
ツメガエル
提供:東京動物園協会
 つめ‐か・ける【詰め掛ける】
〔自下一〕[文]つめか・く(下二)
①大勢の人がひと所に押しよせる。「新聞記者が―・ける」
②間近く迫り寄る。色道大鏡「立たんとするをもすかさず―・けてのますれば」
つめ‐がた【爪形】
①つめのあと。つめのかた。
②爪印つめいん。
つめ‐かみ【爪髪】
馬のひづめとたてがみ。狂言、富士松「是は―はつたと致いて、たくましいよいお馬ではござれども」
つめ‐かんむり【爪冠】
漢字の冠かんむりの一つ。「爰」「爵」などの冠の「爫」の称。
つめ‐きり【爪切り】
①刃先が爪形に曲がっている、爪を切る具。
②爪切り鋏の略。
⇒つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】
つめ‐きり【詰め切り】
たえずそこにいること。つめっきり。「―で看病する」
つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】
手足の爪を切りとるのに使う小さい鋏。つめとりばさみ。
⇒つめ‐きり【爪切り】
つめ‐き・る【詰め切る】
[一]〔自五〕
その場を離れずに、ずっとそこにいて勤務や待機をする。
[二]〔他五〕
つめこみおわる。いっぱいに詰め込む。
つめ‐か・ける【詰め掛ける】
〔自下一〕[文]つめか・く(下二)
①大勢の人がひと所に押しよせる。「新聞記者が―・ける」
②間近く迫り寄る。色道大鏡「立たんとするをもすかさず―・けてのますれば」
つめ‐がた【爪形】
①つめのあと。つめのかた。
②爪印つめいん。
つめ‐かみ【爪髪】
馬のひづめとたてがみ。狂言、富士松「是は―はつたと致いて、たくましいよいお馬ではござれども」
つめ‐かんむり【爪冠】
漢字の冠かんむりの一つ。「爰」「爵」などの冠の「爫」の称。
つめ‐きり【爪切り】
①刃先が爪形に曲がっている、爪を切る具。
②爪切り鋏の略。
⇒つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】
つめ‐きり【詰め切り】
たえずそこにいること。つめっきり。「―で看病する」
つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】
手足の爪を切りとるのに使う小さい鋏。つめとりばさみ。
⇒つめ‐きり【爪切り】
つめ‐き・る【詰め切る】
[一]〔自五〕
その場を離れずに、ずっとそこにいて勤務や待機をする。
[二]〔他五〕
つめこみおわる。いっぱいに詰め込む。
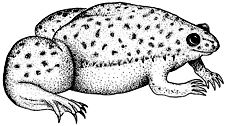 ツメガエル
提供:東京動物園協会
ツメガエル
提供:東京動物園協会
 つめ‐か・ける【詰め掛ける】
〔自下一〕[文]つめか・く(下二)
①大勢の人がひと所に押しよせる。「新聞記者が―・ける」
②間近く迫り寄る。色道大鏡「立たんとするをもすかさず―・けてのますれば」
つめ‐がた【爪形】
①つめのあと。つめのかた。
②爪印つめいん。
つめ‐かみ【爪髪】
馬のひづめとたてがみ。狂言、富士松「是は―はつたと致いて、たくましいよいお馬ではござれども」
つめ‐かんむり【爪冠】
漢字の冠かんむりの一つ。「爰」「爵」などの冠の「爫」の称。
つめ‐きり【爪切り】
①刃先が爪形に曲がっている、爪を切る具。
②爪切り鋏の略。
⇒つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】
つめ‐きり【詰め切り】
たえずそこにいること。つめっきり。「―で看病する」
つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】
手足の爪を切りとるのに使う小さい鋏。つめとりばさみ。
⇒つめ‐きり【爪切り】
つめ‐き・る【詰め切る】
[一]〔自五〕
その場を離れずに、ずっとそこにいて勤務や待機をする。
[二]〔他五〕
つめこみおわる。いっぱいに詰め込む。
つめ‐か・ける【詰め掛ける】
〔自下一〕[文]つめか・く(下二)
①大勢の人がひと所に押しよせる。「新聞記者が―・ける」
②間近く迫り寄る。色道大鏡「立たんとするをもすかさず―・けてのますれば」
つめ‐がた【爪形】
①つめのあと。つめのかた。
②爪印つめいん。
つめ‐かみ【爪髪】
馬のひづめとたてがみ。狂言、富士松「是は―はつたと致いて、たくましいよいお馬ではござれども」
つめ‐かんむり【爪冠】
漢字の冠かんむりの一つ。「爰」「爵」などの冠の「爫」の称。
つめ‐きり【爪切り】
①刃先が爪形に曲がっている、爪を切る具。
②爪切り鋏の略。
⇒つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】
つめ‐きり【詰め切り】
たえずそこにいること。つめっきり。「―で看病する」
つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】
手足の爪を切りとるのに使う小さい鋏。つめとりばさみ。
⇒つめ‐きり【爪切り】
つめ‐き・る【詰め切る】
[一]〔自五〕
その場を離れずに、ずっとそこにいて勤務や待機をする。
[二]〔他五〕
つめこみおわる。いっぱいに詰め込む。
広辞苑 ページ 13255 での【○旋毛を曲げる】単語。