複数辞典一括検索+![]()
![]()
○螺子を巻くねじをまく🔗⭐🔉
○螺子を巻くねじをまく
だらけた態度・行動などを、叱り励ましてきちんとさせる。
⇒ねじ【螺子・捻子・捩子・螺旋】
ね・す【寝す】
〔他下二〕
⇒ねせる(下一)
ね・す【熱す】
〔自サ変〕
(ネッスのツの表記されない形)熱が出る。発熱する。栄華物語鳥辺野「女院もの(はれもの)―・せさせ給ひて悩ましうおぼしめしたり」
ねず【鼠】
①「ねずみ」の略。「―鳴き」
②「ねずみ色」の略。「銀―」
ねず【杜松】
ヒノキ科の常緑針葉樹。東アジア北部に分布し、西日本に自生。庭木、特に生垣に栽植。高さ1〜10メートル。樹皮は赤みを帯びる。葉は3個ずつ輪生。春、雌雄の花を異株に生じ、紫黒色の肉質の球果を結ぶ。これを杜松子としょうしと称して利尿薬・灯用とする。ヨーロッパ産の実はジンの香り付けに用いる。材は建築・器具用。ネズミサシ。古名、むろ。
ねず
 ね‐ず【不寝】
(何かをするために)終夜寝ないでいること。「―の番」
ね‐ず【寝唾】‥ヅ
⇒ねつ。日葡辞書「ネヅヲタルル」
ね・ず【捩づ・捻づ】ネヅ
[一]〔他上二〕
ひねりまげる。宇治拾遺物語1「鬼、よりて、さはとるぞとて、(瘤を)―・ぢて引くに、大方痛きことなし」
[二]〔自上二〕
くねりまがる。ねじれる。日葡辞書「ハシラガネヂタ」
ねず‐お【根助緒】‥ヲ
①鷹に鈴をむすびつける緒。
②指貫さしぬきのくくり。
ねず‐が‐せき【念珠ヶ関・鼠ヶ関】
古代の奥羽三関の一つ。遺称地は山形県鶴岡市鼠ヶ関。越後と出羽との境、日本海に面する。
ね‐すがた【寝姿】
寝ている姿。
ね‐す・ぎる【寝過ぎる】
〔自上一〕
①程度をこえて長い時間寝る。超過して寝る。「―・ぎて頭がぼんやりする」
②(→)「ねすごす」に同じ。
ね‐すぐ・す【寝過す】
〔自五〕
(→)「ねすごす」に同じ。源氏物語夕顔「つとめて、少し―・し給ひて」
ネス‐こ【ネス湖】
(Loch Ness)イギリス、スコットランド北部にある狭長な湖。氷食を受けた地溝湖で、面積1800平方キロメートル。怪獣ネッシーの伝説で有名。
ねずこ
〔植〕(→)クロベの別称。
ね‐すご・す【寝過ごす】
〔自五〕
起きるべき時間を過ぎても目がさめず、定刻に間に合わなくなる。「1時間―・す」
ねずっぽ【鼠坊】
ネズッポ科の硬骨魚の総称。海産で、温帯から熱帯に分布。日本に37種。頭部は扁平で体は細長く鱗がない。ヌメリゴチ・ヨメゴチなど。また特に、その一種のネズミゴチの別称。
ネストリオス【Nestorios ギリシア】
コンスタンチノープルの司教。イエス=キリストの神性に対し人性を強調し、マリアの「神の母」の称号を否認したために431年司教の座を追われ、異端の宣告を受けた。エジプトに客死。ネストリウス。( 〜451頃)
⇒ネストリオス‐は【ネストリオス派】
ネストリオス‐は【ネストリオス派】
ネストリオスの起こしたキリスト教分派。その教義は東方ペルシアに勢力を得、インド・中国に入り、中国では景教という。→景教
⇒ネストリオス【Nestorios ギリシア】
ネストル【Nestor】
①ホメロスの叙事詩「イリアス」「オデュッセイア」の中で活躍するピュロスの王。温和で常識的でかつ饒舌な老人。転じて、賢い助言者、また長老の意。
②ロシアの学僧。最古のロシア年代記の編者。
⇒ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】
ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】
ネストル2の編述したロシア最初の年代記。ノアの洪水からスラヴ諸族の勃興を述べ、11世紀中頃に終わる。原初年代記。
⇒ネストル【Nestor】
ねず‐なき【鼠鳴き】
①ねずみが鳴くこと。また、その声。
②ねずみに似た鳴き声。また、そのような声を出すこと。枕草子151「雀の子の―するにをどりくる」
③特に、男女の逢引の合図。遊女などが客を呼び入れようとするときに出す声。ねずみなき。今昔物語集29「半蔀の有りけるより―をして手を指し出でて招きければ」
ねず‐な・く【鼠鳴く】
〔自四〕
ねずみが鳴く。また、ねずみの鳴き声に似た声を出す。林葉和歌集「―・けど見もかへらねば」
ねず‐の‐ばん【不寝の番】
①一晩中寝ないで番をすること。また、その人。ふしんばん。ねずばん。狂言、鞍馬参「今夜は通夜をする、汝はそれへ寄て―をせい」
②遊女屋で、夜起きていて油をさすなど、火の世話をしながら火の用心をする者。ねずの男。ねずばん。
ねず‐ばしり【鼠走】
(→)「とかみ(
ね‐ず【不寝】
(何かをするために)終夜寝ないでいること。「―の番」
ね‐ず【寝唾】‥ヅ
⇒ねつ。日葡辞書「ネヅヲタルル」
ね・ず【捩づ・捻づ】ネヅ
[一]〔他上二〕
ひねりまげる。宇治拾遺物語1「鬼、よりて、さはとるぞとて、(瘤を)―・ぢて引くに、大方痛きことなし」
[二]〔自上二〕
くねりまがる。ねじれる。日葡辞書「ハシラガネヂタ」
ねず‐お【根助緒】‥ヲ
①鷹に鈴をむすびつける緒。
②指貫さしぬきのくくり。
ねず‐が‐せき【念珠ヶ関・鼠ヶ関】
古代の奥羽三関の一つ。遺称地は山形県鶴岡市鼠ヶ関。越後と出羽との境、日本海に面する。
ね‐すがた【寝姿】
寝ている姿。
ね‐す・ぎる【寝過ぎる】
〔自上一〕
①程度をこえて長い時間寝る。超過して寝る。「―・ぎて頭がぼんやりする」
②(→)「ねすごす」に同じ。
ね‐すぐ・す【寝過す】
〔自五〕
(→)「ねすごす」に同じ。源氏物語夕顔「つとめて、少し―・し給ひて」
ネス‐こ【ネス湖】
(Loch Ness)イギリス、スコットランド北部にある狭長な湖。氷食を受けた地溝湖で、面積1800平方キロメートル。怪獣ネッシーの伝説で有名。
ねずこ
〔植〕(→)クロベの別称。
ね‐すご・す【寝過ごす】
〔自五〕
起きるべき時間を過ぎても目がさめず、定刻に間に合わなくなる。「1時間―・す」
ねずっぽ【鼠坊】
ネズッポ科の硬骨魚の総称。海産で、温帯から熱帯に分布。日本に37種。頭部は扁平で体は細長く鱗がない。ヌメリゴチ・ヨメゴチなど。また特に、その一種のネズミゴチの別称。
ネストリオス【Nestorios ギリシア】
コンスタンチノープルの司教。イエス=キリストの神性に対し人性を強調し、マリアの「神の母」の称号を否認したために431年司教の座を追われ、異端の宣告を受けた。エジプトに客死。ネストリウス。( 〜451頃)
⇒ネストリオス‐は【ネストリオス派】
ネストリオス‐は【ネストリオス派】
ネストリオスの起こしたキリスト教分派。その教義は東方ペルシアに勢力を得、インド・中国に入り、中国では景教という。→景教
⇒ネストリオス【Nestorios ギリシア】
ネストル【Nestor】
①ホメロスの叙事詩「イリアス」「オデュッセイア」の中で活躍するピュロスの王。温和で常識的でかつ饒舌な老人。転じて、賢い助言者、また長老の意。
②ロシアの学僧。最古のロシア年代記の編者。
⇒ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】
ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】
ネストル2の編述したロシア最初の年代記。ノアの洪水からスラヴ諸族の勃興を述べ、11世紀中頃に終わる。原初年代記。
⇒ネストル【Nestor】
ねず‐なき【鼠鳴き】
①ねずみが鳴くこと。また、その声。
②ねずみに似た鳴き声。また、そのような声を出すこと。枕草子151「雀の子の―するにをどりくる」
③特に、男女の逢引の合図。遊女などが客を呼び入れようとするときに出す声。ねずみなき。今昔物語集29「半蔀の有りけるより―をして手を指し出でて招きければ」
ねず‐な・く【鼠鳴く】
〔自四〕
ねずみが鳴く。また、ねずみの鳴き声に似た声を出す。林葉和歌集「―・けど見もかへらねば」
ねず‐の‐ばん【不寝の番】
①一晩中寝ないで番をすること。また、その人。ふしんばん。ねずばん。狂言、鞍馬参「今夜は通夜をする、汝はそれへ寄て―をせい」
②遊女屋で、夜起きていて油をさすなど、火の世話をしながら火の用心をする者。ねずの男。ねずばん。
ねず‐ばしり【鼠走】
(→)「とかみ( )」の異称。〈倭名類聚鈔10〉
ねず‐ばん【不寝番】
(→)「ねずのばん」に同じ。梅暦「下働きやら―やら」
ね‐ずまい【寝住い】‥ズマヒ
寝ている時の姿。ねざま。ねぞう。
ねず‐まい【鼠舞】‥マヒ
(ねずみが穴から出ようとしては引っこみ引っこみするさまの意)ためらうこと。まごまごすること。ねずみまい。首鼠しゅそ。狐疑こぎ。
ねずみ【鼠】
①広くはネズミ目(齧歯げっし類)のネズミ亜目、またリス亜目のホリネズミ、さらにモグラ目のトガリネズミを含む小形哺乳類の総称。200以上の属、約1800種を含み、種数としては哺乳類の約3分の1。そのうちネズミ亜目ネズミ科はカヤネズミ・クマネズミ・アカネズミ・ハツカネズミなどの属を含む。普通はドブネズミ・クマネズミなどのイエネズミをいう。〈倭名類聚鈔18〉
②鼠色ねずみいろの略。
③ひそかに害をなす者のたとえ。
⇒ねずみ‐あな【鼠穴】
⇒ねずみ‐いらず【鼠入らず】
⇒ねずみ‐いろ【鼠色】
⇒ねずみ‐おい【鼠生】
⇒ねずみ‐おとし【鼠落し】
⇒ねずみ‐がえし【鼠返し】
⇒ねずみ‐かべ【鼠壁】
⇒ねずみ‐がみ【鼠紙】
⇒ねずみ‐きど【鼠木戸】
⇒ねずみ‐くい【鼠食い】
⇒ねずみ‐ぐら【鼠倉】
⇒ねずみ‐げ【鼠毛】
⇒ねずみ‐こう【鼠講】
⇒ねずみ‐ごち【鼠鯒】
⇒ねずみ‐ごっこ【鼠ごっこ】
⇒ねずみ‐ごめ【鼠米】
⇒ねずみ‐こもん【鼠小紋】
⇒ねずみ‐ころし【鼠殺し】
⇒ねずみ‐ごろも【鼠衣】
⇒ねずみ‐こんじょう【鼠根性】
⇒ねずみ‐さし【鼠刺】
⇒ねずみ‐ざめ【鼠鮫】
⇒ねずみ‐ざん【鼠算】
⇒ねずみ‐せん【鼠銑】
⇒ねずみ‐たけ【鼠茸】
⇒ねずみ‐ちゃ【鼠茶】
⇒ねずみ‐つき【鼠突き】
⇒ねずみ‐ど【鼠戸】
⇒ねずみど‐ぜに【鼠戸銭】
⇒ねずみ‐とり【鼠取り・鼠捕り】
⇒ねずみ‐なき【鼠鳴き】
⇒ねずみ‐の‐お【鼠の尾】
⇒ねずみのこ‐さんよう【鼠の子算用】
⇒ねずみ‐のみ【鼠蚤】
⇒ねずみ‐の‐よめいり【鼠の嫁入り】
⇒ねずみば‐ぎり【鼠歯錐】
⇒ねずみ‐ばしり【鼠走】
⇒ねずみ‐はなび【鼠花火】
⇒ねずみ‐はんきり【鼠半切】
⇒ねずみ‐ばんし【鼠半紙】
⇒ねずみ‐ぶか【鼠鱶】
⇒ねずみ‐まい【鼠舞】
⇒ねずみ‐もち【鼠黐】
⇒鼠が塩を引く
⇒鼠に引かれそう
ねずみ‐あな【鼠穴】
鼠のかじってあけた穴。
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐いらず【鼠入らず】
鼠が侵入しないように作った食器棚。小杉天外、初すがた「蠅帳になツてる食厨ねずみいらず、其れと並んで桐の茶棚がある」
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐いろ【鼠色】
①鼠の毛のような、青ばんだ淡い黒色。灰色。ねずいろ。
Munsell color system: N5.5
②(白黒がはっきりしないところから)所属・主張・態度の曖昧あいまいなこと。
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐おい【鼠生】‥オヒ
鼠の子のようにおさなく弱いこと。蜻蛉日記下「世にいふなる―の程にだにあらぬを」
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐おとし【鼠落し】
鼠を陥れて捕らえる器具。ねずみとり。
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐がえし【鼠返し】‥ガヘシ
鼠の入るのを防ぐために設けた装置。高床の倉の柱の床下部に付けた鍔つば状の大きい板、土蔵の入口に外側に向けて斜めに立て渡した板、床下の換気口や排水口にはめた金網または格子、船舶の係留索や錨鎖びょうさに設けた円板の類。
鼠返し
)」の異称。〈倭名類聚鈔10〉
ねず‐ばん【不寝番】
(→)「ねずのばん」に同じ。梅暦「下働きやら―やら」
ね‐ずまい【寝住い】‥ズマヒ
寝ている時の姿。ねざま。ねぞう。
ねず‐まい【鼠舞】‥マヒ
(ねずみが穴から出ようとしては引っこみ引っこみするさまの意)ためらうこと。まごまごすること。ねずみまい。首鼠しゅそ。狐疑こぎ。
ねずみ【鼠】
①広くはネズミ目(齧歯げっし類)のネズミ亜目、またリス亜目のホリネズミ、さらにモグラ目のトガリネズミを含む小形哺乳類の総称。200以上の属、約1800種を含み、種数としては哺乳類の約3分の1。そのうちネズミ亜目ネズミ科はカヤネズミ・クマネズミ・アカネズミ・ハツカネズミなどの属を含む。普通はドブネズミ・クマネズミなどのイエネズミをいう。〈倭名類聚鈔18〉
②鼠色ねずみいろの略。
③ひそかに害をなす者のたとえ。
⇒ねずみ‐あな【鼠穴】
⇒ねずみ‐いらず【鼠入らず】
⇒ねずみ‐いろ【鼠色】
⇒ねずみ‐おい【鼠生】
⇒ねずみ‐おとし【鼠落し】
⇒ねずみ‐がえし【鼠返し】
⇒ねずみ‐かべ【鼠壁】
⇒ねずみ‐がみ【鼠紙】
⇒ねずみ‐きど【鼠木戸】
⇒ねずみ‐くい【鼠食い】
⇒ねずみ‐ぐら【鼠倉】
⇒ねずみ‐げ【鼠毛】
⇒ねずみ‐こう【鼠講】
⇒ねずみ‐ごち【鼠鯒】
⇒ねずみ‐ごっこ【鼠ごっこ】
⇒ねずみ‐ごめ【鼠米】
⇒ねずみ‐こもん【鼠小紋】
⇒ねずみ‐ころし【鼠殺し】
⇒ねずみ‐ごろも【鼠衣】
⇒ねずみ‐こんじょう【鼠根性】
⇒ねずみ‐さし【鼠刺】
⇒ねずみ‐ざめ【鼠鮫】
⇒ねずみ‐ざん【鼠算】
⇒ねずみ‐せん【鼠銑】
⇒ねずみ‐たけ【鼠茸】
⇒ねずみ‐ちゃ【鼠茶】
⇒ねずみ‐つき【鼠突き】
⇒ねずみ‐ど【鼠戸】
⇒ねずみど‐ぜに【鼠戸銭】
⇒ねずみ‐とり【鼠取り・鼠捕り】
⇒ねずみ‐なき【鼠鳴き】
⇒ねずみ‐の‐お【鼠の尾】
⇒ねずみのこ‐さんよう【鼠の子算用】
⇒ねずみ‐のみ【鼠蚤】
⇒ねずみ‐の‐よめいり【鼠の嫁入り】
⇒ねずみば‐ぎり【鼠歯錐】
⇒ねずみ‐ばしり【鼠走】
⇒ねずみ‐はなび【鼠花火】
⇒ねずみ‐はんきり【鼠半切】
⇒ねずみ‐ばんし【鼠半紙】
⇒ねずみ‐ぶか【鼠鱶】
⇒ねずみ‐まい【鼠舞】
⇒ねずみ‐もち【鼠黐】
⇒鼠が塩を引く
⇒鼠に引かれそう
ねずみ‐あな【鼠穴】
鼠のかじってあけた穴。
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐いらず【鼠入らず】
鼠が侵入しないように作った食器棚。小杉天外、初すがた「蠅帳になツてる食厨ねずみいらず、其れと並んで桐の茶棚がある」
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐いろ【鼠色】
①鼠の毛のような、青ばんだ淡い黒色。灰色。ねずいろ。
Munsell color system: N5.5
②(白黒がはっきりしないところから)所属・主張・態度の曖昧あいまいなこと。
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐おい【鼠生】‥オヒ
鼠の子のようにおさなく弱いこと。蜻蛉日記下「世にいふなる―の程にだにあらぬを」
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐おとし【鼠落し】
鼠を陥れて捕らえる器具。ねずみとり。
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐がえし【鼠返し】‥ガヘシ
鼠の入るのを防ぐために設けた装置。高床の倉の柱の床下部に付けた鍔つば状の大きい板、土蔵の入口に外側に向けて斜めに立て渡した板、床下の換気口や排水口にはめた金網または格子、船舶の係留索や錨鎖びょうさに設けた円板の類。
鼠返し
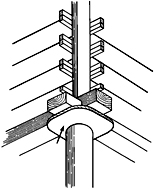 ⇒ねずみ【鼠】
⇒ねずみ【鼠】
 ね‐ず【不寝】
(何かをするために)終夜寝ないでいること。「―の番」
ね‐ず【寝唾】‥ヅ
⇒ねつ。日葡辞書「ネヅヲタルル」
ね・ず【捩づ・捻づ】ネヅ
[一]〔他上二〕
ひねりまげる。宇治拾遺物語1「鬼、よりて、さはとるぞとて、(瘤を)―・ぢて引くに、大方痛きことなし」
[二]〔自上二〕
くねりまがる。ねじれる。日葡辞書「ハシラガネヂタ」
ねず‐お【根助緒】‥ヲ
①鷹に鈴をむすびつける緒。
②指貫さしぬきのくくり。
ねず‐が‐せき【念珠ヶ関・鼠ヶ関】
古代の奥羽三関の一つ。遺称地は山形県鶴岡市鼠ヶ関。越後と出羽との境、日本海に面する。
ね‐すがた【寝姿】
寝ている姿。
ね‐す・ぎる【寝過ぎる】
〔自上一〕
①程度をこえて長い時間寝る。超過して寝る。「―・ぎて頭がぼんやりする」
②(→)「ねすごす」に同じ。
ね‐すぐ・す【寝過す】
〔自五〕
(→)「ねすごす」に同じ。源氏物語夕顔「つとめて、少し―・し給ひて」
ネス‐こ【ネス湖】
(Loch Ness)イギリス、スコットランド北部にある狭長な湖。氷食を受けた地溝湖で、面積1800平方キロメートル。怪獣ネッシーの伝説で有名。
ねずこ
〔植〕(→)クロベの別称。
ね‐すご・す【寝過ごす】
〔自五〕
起きるべき時間を過ぎても目がさめず、定刻に間に合わなくなる。「1時間―・す」
ねずっぽ【鼠坊】
ネズッポ科の硬骨魚の総称。海産で、温帯から熱帯に分布。日本に37種。頭部は扁平で体は細長く鱗がない。ヌメリゴチ・ヨメゴチなど。また特に、その一種のネズミゴチの別称。
ネストリオス【Nestorios ギリシア】
コンスタンチノープルの司教。イエス=キリストの神性に対し人性を強調し、マリアの「神の母」の称号を否認したために431年司教の座を追われ、異端の宣告を受けた。エジプトに客死。ネストリウス。( 〜451頃)
⇒ネストリオス‐は【ネストリオス派】
ネストリオス‐は【ネストリオス派】
ネストリオスの起こしたキリスト教分派。その教義は東方ペルシアに勢力を得、インド・中国に入り、中国では景教という。→景教
⇒ネストリオス【Nestorios ギリシア】
ネストル【Nestor】
①ホメロスの叙事詩「イリアス」「オデュッセイア」の中で活躍するピュロスの王。温和で常識的でかつ饒舌な老人。転じて、賢い助言者、また長老の意。
②ロシアの学僧。最古のロシア年代記の編者。
⇒ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】
ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】
ネストル2の編述したロシア最初の年代記。ノアの洪水からスラヴ諸族の勃興を述べ、11世紀中頃に終わる。原初年代記。
⇒ネストル【Nestor】
ねず‐なき【鼠鳴き】
①ねずみが鳴くこと。また、その声。
②ねずみに似た鳴き声。また、そのような声を出すこと。枕草子151「雀の子の―するにをどりくる」
③特に、男女の逢引の合図。遊女などが客を呼び入れようとするときに出す声。ねずみなき。今昔物語集29「半蔀の有りけるより―をして手を指し出でて招きければ」
ねず‐な・く【鼠鳴く】
〔自四〕
ねずみが鳴く。また、ねずみの鳴き声に似た声を出す。林葉和歌集「―・けど見もかへらねば」
ねず‐の‐ばん【不寝の番】
①一晩中寝ないで番をすること。また、その人。ふしんばん。ねずばん。狂言、鞍馬参「今夜は通夜をする、汝はそれへ寄て―をせい」
②遊女屋で、夜起きていて油をさすなど、火の世話をしながら火の用心をする者。ねずの男。ねずばん。
ねず‐ばしり【鼠走】
(→)「とかみ(
ね‐ず【不寝】
(何かをするために)終夜寝ないでいること。「―の番」
ね‐ず【寝唾】‥ヅ
⇒ねつ。日葡辞書「ネヅヲタルル」
ね・ず【捩づ・捻づ】ネヅ
[一]〔他上二〕
ひねりまげる。宇治拾遺物語1「鬼、よりて、さはとるぞとて、(瘤を)―・ぢて引くに、大方痛きことなし」
[二]〔自上二〕
くねりまがる。ねじれる。日葡辞書「ハシラガネヂタ」
ねず‐お【根助緒】‥ヲ
①鷹に鈴をむすびつける緒。
②指貫さしぬきのくくり。
ねず‐が‐せき【念珠ヶ関・鼠ヶ関】
古代の奥羽三関の一つ。遺称地は山形県鶴岡市鼠ヶ関。越後と出羽との境、日本海に面する。
ね‐すがた【寝姿】
寝ている姿。
ね‐す・ぎる【寝過ぎる】
〔自上一〕
①程度をこえて長い時間寝る。超過して寝る。「―・ぎて頭がぼんやりする」
②(→)「ねすごす」に同じ。
ね‐すぐ・す【寝過す】
〔自五〕
(→)「ねすごす」に同じ。源氏物語夕顔「つとめて、少し―・し給ひて」
ネス‐こ【ネス湖】
(Loch Ness)イギリス、スコットランド北部にある狭長な湖。氷食を受けた地溝湖で、面積1800平方キロメートル。怪獣ネッシーの伝説で有名。
ねずこ
〔植〕(→)クロベの別称。
ね‐すご・す【寝過ごす】
〔自五〕
起きるべき時間を過ぎても目がさめず、定刻に間に合わなくなる。「1時間―・す」
ねずっぽ【鼠坊】
ネズッポ科の硬骨魚の総称。海産で、温帯から熱帯に分布。日本に37種。頭部は扁平で体は細長く鱗がない。ヌメリゴチ・ヨメゴチなど。また特に、その一種のネズミゴチの別称。
ネストリオス【Nestorios ギリシア】
コンスタンチノープルの司教。イエス=キリストの神性に対し人性を強調し、マリアの「神の母」の称号を否認したために431年司教の座を追われ、異端の宣告を受けた。エジプトに客死。ネストリウス。( 〜451頃)
⇒ネストリオス‐は【ネストリオス派】
ネストリオス‐は【ネストリオス派】
ネストリオスの起こしたキリスト教分派。その教義は東方ペルシアに勢力を得、インド・中国に入り、中国では景教という。→景教
⇒ネストリオス【Nestorios ギリシア】
ネストル【Nestor】
①ホメロスの叙事詩「イリアス」「オデュッセイア」の中で活躍するピュロスの王。温和で常識的でかつ饒舌な老人。転じて、賢い助言者、また長老の意。
②ロシアの学僧。最古のロシア年代記の編者。
⇒ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】
ネストル‐ねんだいき【ネストル年代記】
ネストル2の編述したロシア最初の年代記。ノアの洪水からスラヴ諸族の勃興を述べ、11世紀中頃に終わる。原初年代記。
⇒ネストル【Nestor】
ねず‐なき【鼠鳴き】
①ねずみが鳴くこと。また、その声。
②ねずみに似た鳴き声。また、そのような声を出すこと。枕草子151「雀の子の―するにをどりくる」
③特に、男女の逢引の合図。遊女などが客を呼び入れようとするときに出す声。ねずみなき。今昔物語集29「半蔀の有りけるより―をして手を指し出でて招きければ」
ねず‐な・く【鼠鳴く】
〔自四〕
ねずみが鳴く。また、ねずみの鳴き声に似た声を出す。林葉和歌集「―・けど見もかへらねば」
ねず‐の‐ばん【不寝の番】
①一晩中寝ないで番をすること。また、その人。ふしんばん。ねずばん。狂言、鞍馬参「今夜は通夜をする、汝はそれへ寄て―をせい」
②遊女屋で、夜起きていて油をさすなど、火の世話をしながら火の用心をする者。ねずの男。ねずばん。
ねず‐ばしり【鼠走】
(→)「とかみ( )」の異称。〈倭名類聚鈔10〉
ねず‐ばん【不寝番】
(→)「ねずのばん」に同じ。梅暦「下働きやら―やら」
ね‐ずまい【寝住い】‥ズマヒ
寝ている時の姿。ねざま。ねぞう。
ねず‐まい【鼠舞】‥マヒ
(ねずみが穴から出ようとしては引っこみ引っこみするさまの意)ためらうこと。まごまごすること。ねずみまい。首鼠しゅそ。狐疑こぎ。
ねずみ【鼠】
①広くはネズミ目(齧歯げっし類)のネズミ亜目、またリス亜目のホリネズミ、さらにモグラ目のトガリネズミを含む小形哺乳類の総称。200以上の属、約1800種を含み、種数としては哺乳類の約3分の1。そのうちネズミ亜目ネズミ科はカヤネズミ・クマネズミ・アカネズミ・ハツカネズミなどの属を含む。普通はドブネズミ・クマネズミなどのイエネズミをいう。〈倭名類聚鈔18〉
②鼠色ねずみいろの略。
③ひそかに害をなす者のたとえ。
⇒ねずみ‐あな【鼠穴】
⇒ねずみ‐いらず【鼠入らず】
⇒ねずみ‐いろ【鼠色】
⇒ねずみ‐おい【鼠生】
⇒ねずみ‐おとし【鼠落し】
⇒ねずみ‐がえし【鼠返し】
⇒ねずみ‐かべ【鼠壁】
⇒ねずみ‐がみ【鼠紙】
⇒ねずみ‐きど【鼠木戸】
⇒ねずみ‐くい【鼠食い】
⇒ねずみ‐ぐら【鼠倉】
⇒ねずみ‐げ【鼠毛】
⇒ねずみ‐こう【鼠講】
⇒ねずみ‐ごち【鼠鯒】
⇒ねずみ‐ごっこ【鼠ごっこ】
⇒ねずみ‐ごめ【鼠米】
⇒ねずみ‐こもん【鼠小紋】
⇒ねずみ‐ころし【鼠殺し】
⇒ねずみ‐ごろも【鼠衣】
⇒ねずみ‐こんじょう【鼠根性】
⇒ねずみ‐さし【鼠刺】
⇒ねずみ‐ざめ【鼠鮫】
⇒ねずみ‐ざん【鼠算】
⇒ねずみ‐せん【鼠銑】
⇒ねずみ‐たけ【鼠茸】
⇒ねずみ‐ちゃ【鼠茶】
⇒ねずみ‐つき【鼠突き】
⇒ねずみ‐ど【鼠戸】
⇒ねずみど‐ぜに【鼠戸銭】
⇒ねずみ‐とり【鼠取り・鼠捕り】
⇒ねずみ‐なき【鼠鳴き】
⇒ねずみ‐の‐お【鼠の尾】
⇒ねずみのこ‐さんよう【鼠の子算用】
⇒ねずみ‐のみ【鼠蚤】
⇒ねずみ‐の‐よめいり【鼠の嫁入り】
⇒ねずみば‐ぎり【鼠歯錐】
⇒ねずみ‐ばしり【鼠走】
⇒ねずみ‐はなび【鼠花火】
⇒ねずみ‐はんきり【鼠半切】
⇒ねずみ‐ばんし【鼠半紙】
⇒ねずみ‐ぶか【鼠鱶】
⇒ねずみ‐まい【鼠舞】
⇒ねずみ‐もち【鼠黐】
⇒鼠が塩を引く
⇒鼠に引かれそう
ねずみ‐あな【鼠穴】
鼠のかじってあけた穴。
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐いらず【鼠入らず】
鼠が侵入しないように作った食器棚。小杉天外、初すがた「蠅帳になツてる食厨ねずみいらず、其れと並んで桐の茶棚がある」
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐いろ【鼠色】
①鼠の毛のような、青ばんだ淡い黒色。灰色。ねずいろ。
Munsell color system: N5.5
②(白黒がはっきりしないところから)所属・主張・態度の曖昧あいまいなこと。
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐おい【鼠生】‥オヒ
鼠の子のようにおさなく弱いこと。蜻蛉日記下「世にいふなる―の程にだにあらぬを」
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐おとし【鼠落し】
鼠を陥れて捕らえる器具。ねずみとり。
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐がえし【鼠返し】‥ガヘシ
鼠の入るのを防ぐために設けた装置。高床の倉の柱の床下部に付けた鍔つば状の大きい板、土蔵の入口に外側に向けて斜めに立て渡した板、床下の換気口や排水口にはめた金網または格子、船舶の係留索や錨鎖びょうさに設けた円板の類。
鼠返し
)」の異称。〈倭名類聚鈔10〉
ねず‐ばん【不寝番】
(→)「ねずのばん」に同じ。梅暦「下働きやら―やら」
ね‐ずまい【寝住い】‥ズマヒ
寝ている時の姿。ねざま。ねぞう。
ねず‐まい【鼠舞】‥マヒ
(ねずみが穴から出ようとしては引っこみ引っこみするさまの意)ためらうこと。まごまごすること。ねずみまい。首鼠しゅそ。狐疑こぎ。
ねずみ【鼠】
①広くはネズミ目(齧歯げっし類)のネズミ亜目、またリス亜目のホリネズミ、さらにモグラ目のトガリネズミを含む小形哺乳類の総称。200以上の属、約1800種を含み、種数としては哺乳類の約3分の1。そのうちネズミ亜目ネズミ科はカヤネズミ・クマネズミ・アカネズミ・ハツカネズミなどの属を含む。普通はドブネズミ・クマネズミなどのイエネズミをいう。〈倭名類聚鈔18〉
②鼠色ねずみいろの略。
③ひそかに害をなす者のたとえ。
⇒ねずみ‐あな【鼠穴】
⇒ねずみ‐いらず【鼠入らず】
⇒ねずみ‐いろ【鼠色】
⇒ねずみ‐おい【鼠生】
⇒ねずみ‐おとし【鼠落し】
⇒ねずみ‐がえし【鼠返し】
⇒ねずみ‐かべ【鼠壁】
⇒ねずみ‐がみ【鼠紙】
⇒ねずみ‐きど【鼠木戸】
⇒ねずみ‐くい【鼠食い】
⇒ねずみ‐ぐら【鼠倉】
⇒ねずみ‐げ【鼠毛】
⇒ねずみ‐こう【鼠講】
⇒ねずみ‐ごち【鼠鯒】
⇒ねずみ‐ごっこ【鼠ごっこ】
⇒ねずみ‐ごめ【鼠米】
⇒ねずみ‐こもん【鼠小紋】
⇒ねずみ‐ころし【鼠殺し】
⇒ねずみ‐ごろも【鼠衣】
⇒ねずみ‐こんじょう【鼠根性】
⇒ねずみ‐さし【鼠刺】
⇒ねずみ‐ざめ【鼠鮫】
⇒ねずみ‐ざん【鼠算】
⇒ねずみ‐せん【鼠銑】
⇒ねずみ‐たけ【鼠茸】
⇒ねずみ‐ちゃ【鼠茶】
⇒ねずみ‐つき【鼠突き】
⇒ねずみ‐ど【鼠戸】
⇒ねずみど‐ぜに【鼠戸銭】
⇒ねずみ‐とり【鼠取り・鼠捕り】
⇒ねずみ‐なき【鼠鳴き】
⇒ねずみ‐の‐お【鼠の尾】
⇒ねずみのこ‐さんよう【鼠の子算用】
⇒ねずみ‐のみ【鼠蚤】
⇒ねずみ‐の‐よめいり【鼠の嫁入り】
⇒ねずみば‐ぎり【鼠歯錐】
⇒ねずみ‐ばしり【鼠走】
⇒ねずみ‐はなび【鼠花火】
⇒ねずみ‐はんきり【鼠半切】
⇒ねずみ‐ばんし【鼠半紙】
⇒ねずみ‐ぶか【鼠鱶】
⇒ねずみ‐まい【鼠舞】
⇒ねずみ‐もち【鼠黐】
⇒鼠が塩を引く
⇒鼠に引かれそう
ねずみ‐あな【鼠穴】
鼠のかじってあけた穴。
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐いらず【鼠入らず】
鼠が侵入しないように作った食器棚。小杉天外、初すがた「蠅帳になツてる食厨ねずみいらず、其れと並んで桐の茶棚がある」
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐いろ【鼠色】
①鼠の毛のような、青ばんだ淡い黒色。灰色。ねずいろ。
Munsell color system: N5.5
②(白黒がはっきりしないところから)所属・主張・態度の曖昧あいまいなこと。
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐おい【鼠生】‥オヒ
鼠の子のようにおさなく弱いこと。蜻蛉日記下「世にいふなる―の程にだにあらぬを」
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐おとし【鼠落し】
鼠を陥れて捕らえる器具。ねずみとり。
⇒ねずみ【鼠】
ねずみ‐がえし【鼠返し】‥ガヘシ
鼠の入るのを防ぐために設けた装置。高床の倉の柱の床下部に付けた鍔つば状の大きい板、土蔵の入口に外側に向けて斜めに立て渡した板、床下の換気口や排水口にはめた金網または格子、船舶の係留索や錨鎖びょうさに設けた円板の類。
鼠返し
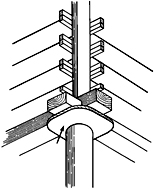 ⇒ねずみ【鼠】
⇒ねずみ【鼠】
広辞苑 ページ 15228 での【○螺子を巻く】単語。