複数辞典一括検索+![]()
![]()
○針刺すばかりはりさすばかり🔗⭐🔉
○針刺すばかりはりさすばかり
針をやっと刺せるほど狭いこと。宇治拾遺物語15「その子孫、世に―の所をしらず」
⇒はり【針】
ばり‐ざんぼう【罵詈讒謗】‥バウ
悪口をあびせ、口ぎたなく相手をののしること。「―を浴びせる」
はり‐し【針師】
針を製造する人。
はり‐し【張師】
ばくちをうつ人。歌舞伎、韓人漢文手管始「―と見へる」
はり‐し【鍼師】
(→)鍼医はりいに同じ。
パリジェンヌ【Parisienne フランス】
パリ生れの女性。
はり‐しごと【針仕事】
裁縫。縫い物。「夜なべの―」
はり‐した【針下】
(針は馬の血を取る道具)獣医の担当区域。
ハリジャン【harijan ヒンディー】
「不可触民」参照。
パリジャン【Parisien フランス】
パリ生れの男性。パリ市民。パリっ子。
はり‐しょうが【針生姜】‥シヤウ‥
ショウガを針のように細くきざんだもの。和え物などの天盛り、汁物の吸口などに用いる。
パリ‐じょうやく【パリ条約】‥デウ‥
①1763年、七年戦争の終結に際してイギリスとフランス・スペインとの間に成立した講和条約。イギリスはカナダ・フロリダなどを取得。
②1783年、アメリカ独立戦争を終結させた条約。イギリスはアメリカ合衆国の独立を承認。
③ナポレオンがライプチヒで敗れた後、1814年、フランスと対仏大同盟諸国との間に締結された条約。第1回パリ講和条約。
④ナポレオンの百日天下後、1815年に締結された条約。フランスの国境を画定。第2回パリ講和条約。
⑤1856年、クリミア戦争を終結させた対露講和条約。ドナウ川の自由航行、オスマン帝国の領土保全などを承認。
⑥1883年、工業所有権を国際的に保護するために締結された条約。万国工業所有権保護同盟条約。
⑦1898年、米西戦争を終結させた講和条約。キューバの独立、フィリピンのアメリカへの割譲などを決定。
はり‐す【鉤素】
釣具の一種。錘おもりの下から釣鉤までの間に使用する糸。なるべく魚の目につかない細いナイロン・天蚕糸てぐす・馬尾毛ばすなどを用いる。
はり‐す【玻璃珠】
水晶の玉。ガラスのたま。
ハリス【Townsend Harris】
アメリカの外交官。1856年(安政3)最初の駐日総領事、のち公使。幕府との間に日米修好通商条約・貿易章程を締結。著「日本滞在記」。(1804〜1878)
パリス【Paris】
ギリシア神話で、トロイアの王子。プリアモスの子。アテナ・ヘラ・アフロディテ3女神の美貌争いの審判をした。スパルタ王妃ヘレネを奪って妻としたので、トロイア戦争が起こったという。
パリス【Gaston Paris】
フランスの中世学者。ドイツ文献学を採り入れて19世紀実証主義文献学の基礎を定めた。著「シャルルマーニュ詩史」など。(1839〜1903)
はりすい‐いし【針吸石】‥スヒ‥
磁石の異称。〈書言字考節用集〉
バリスカン‐ぞうざん‐うんどう【バリスカン造山運動】‥ザウ‥
(ドイツの古代民族Varisci ラテンの名に因む)古生代の終り頃に北大西洋岸で起こった造山運動。これにより、ヨーロッパではイギリス南端からフランス・ドイツにかけて褶曲しゅうきょく山脈ができた。
はり‐すじ【針筋】‥スヂ
①針で縫う筋目。
②磁石の針の指す方。
バリスター【varistor】
電圧が増すと急速に抵抗が減少する半導体抵抗素子。
ハリストス【Khristos ロシア】
(→)キリストのこと。
⇒ハリストス‐せいきょうかい【ハリストス正教会】
ハリストス‐せいきょうかい【ハリストス正教会】‥ケウクワイ
東方正教会系教会の日本での呼称。→東方正教会→日本ハリストス正教会
⇒ハリストス【Khristos ロシア】
はり‐すり【針磨り】
針の製造を業とする人。針師。〈日葡辞書〉
はり‐すり【榛摺】
榛はりの樹皮で布を染めること。また、その布。榛木染はりのきぞめ。天武紀下「―の御衣三具」
はり‐せんぼん【針千本】
①ハリセンボン科の海産の硬骨魚。全長約30センチメートルで、体は卵形。体表は鋭く長いとげでおおわれ、濃褐色の斑紋が散在。熱帯・温帯に分布。ふぐ提灯ちょうちんや飾りものにする。沖縄ではアバサーと称し食用。ハリフグ。スズメフグ。
はりせんぼん
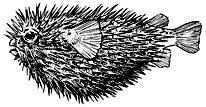 ハリセンボン
提供:東京動物園協会
ハリセンボン
提供:東京動物園協会
 ②クモガニ科のカニ。甲は細長い洋梨形で、左右の額角がっかくが中央部で合わさる。甲、歩脚一面が細い刺とげで覆われる。本州中部以南の浅海砂泥底にすむ。
③(山陰・北陸地方で)12月8日のこと。冬の北西季節風による海荒れの際、1が海浜に波で打ち上げられるのでいう。この日針供養をする。
はり‐そ【張訴・貼訴】
江戸時代、老中邸または役所の門前などに訴状をひそかに貼っておいたこと。
ばり‐ぞうごん【罵詈雑言】‥ザフ‥
口ぎたない、ののしりの言葉。「―を浴びせる」
はり‐た【墾田】
新たに開墾した田。孝徳紀「―の頃畝」
パリ‐だいがく【パリ大学】
(Université de Paris フランス)パリにあるフランス最古の国立大学。起源は12世紀にさかのぼり、ヨーロッパ中世大学の典型。神学寮に発祥。19世紀以後総合大学として発展。1968年大学改革により13の大学に分割・再編。→パリ(図)→ソルボンヌ
はり‐だいこ【張太鼓】
革を張った太鼓。狂言、張蛸「張蛸ではない、―でおりやる」→締しめ太鼓
はり‐たお・す【張り倒す・撲り倒す】‥タフス
〔他五〕
平手で打って倒す。なぐりたおす。
パリ‐ダカール‐ラリー
(Le rallye Dakar フランス)主にサハラ砂漠を走行する、自動車とオートバイのラリー。総走行距離は1万数千キロメートル。1979年開始。当初はフランスのパリから出発し、セネガルのダカールがゴールであったが、近年はほぼ毎年コースが変わる。パリ‐ダカ。
はり‐だくみ【張工】
(→)経師屋きょうじやのこと。
はり‐だこ【張蛸】
張りひろげて乾燥させた蛸。狂言、張蛸「何を―ぢやと云うて売つてやらう物がない」
はり‐だし【張出し】
①外側へ出っぱらせること。また、そのもの。特に建築でいう。
②広く示すための張り紙。張り札。貼出し。
③相撲で、三役以上の同じ地位に三人以上の力士が並ぶとき、三人目以下を番付の欄外に記すこと。また、その記された力士。「―大関」
④江戸時代、女の結髪に両鬢びんを張り出すのに用いた鯨鬚くじらひげ製の具。
⇒はりだし‐まど【張出し窓】
はりだし‐まど【張出し窓】
建物の外壁面から突き出るように造った窓。出窓。
⇒はり‐だし【張出し】
はり‐だ・す【張り出す】
〔自他五〕
①外側へ出っぱる。また、出っぱらせる。「道路に―・した枝」
②広く示すために、紙や札に記してかかげる。貼り出す。
はり‐たて【針立て・鍼立て】
①はりさし。はりやま。
②(→)鍼医はりいに同じ。昨日は今日の物語「或る人の女房、腹を再々痛がりければ、常々―を呼びてたてさせける」
⇒はりたて‐いかずち【針立雷】
はりたて‐いかずち【針立雷】‥イカヅチ
狂言。(→)「雷かみなり」に同じ。
⇒はり‐たて【針立て・鍼立て】
はり‐だましい【張魂】‥ダマシヒ
意地をはって一徹な気質。まけじだましい。
はり‐ちょうせき【玻璃長石】‥チヤウ‥
カリウムを主成分とする長石の一種。単斜晶系。ガラス光沢をもち、珪長質火山岩中に産する。
はりつ【破笠】
⇒おがわはりつ(小川破笠)。
⇒はりつ‐ざいく【破笠細工】
はり‐つ・く【張り付く・貼り付く】
[一]〔自五〕
①はりつけた状態になる。はりつけたようにくっつく。
②「張付け」2をする。
[二]〔他下二〕
⇒はりつける(下一)
ばり‐つ・く
〔自四〕
威勢よくふるまう。幅をきかす。浮世風呂3「あの人の若い時分―・いた本書ほんかきに」
はり‐つけ【磔】
(「張り付け」の意)昔の刑罰の一つ。初めは身体を板または地上に張りひろげ、釘で打ち付けて殺したが、江戸時代の頃にははりつけ柱に縛りつけ、左右の脇腹から槍で突き殺した。西洋では古代ローマのものが知られるが、のち廃止。はっつけ。磔刑たっけい。
はり‐つけ【張付け・貼付け】
①ものをはりつけること。また、はりつけるもの。
②(比喩的に)監視や取材などのため、そのもののそばから離れずにいること。
⇒はりつけ‐が【貼付画】
⇒はりつけ‐かべ【張付壁】
はりつけ‐が【貼付画】‥グワ
絹や紙に描いて、室内の板や壁に貼りつけた障壁画。
⇒はり‐つけ【張付け・貼付け】
はりつけ‐かべ【張付壁】
襖ふすまを嵌殺はめごろしにしたような構造の壁。また、板に紙を貼った壁。
⇒はり‐つけ【張付け・貼付け】
はりつけ‐もざえもん【磔茂左衛門】‥ヱ‥
江戸前期の農民・義民。上野国の人。姓は杉木。沼田領主真田氏の悪政を将軍に直訴。真田氏は改易・配流され、茂左衛門は磔にされたという。生没年未詳。
はり‐つ・ける【張り付ける・貼り付ける】
〔他下一〕[文]はりつ・く(下二)
①ひろげて他の物につける。
②糊などでくっつける。
③「張付け」2をさせる。「現場に記者を―・ける」
④磔はりつけにする。
はりつ‐ざいく【破笠細工】
貝・陶片・角・牙・木片・板金などを蒔絵と併用して模様を表した漆器。江戸中期の漆工小川破笠が得意とした。
⇒はりつ【破笠】
はり‐づつ【鍼筒】
鍼術しんじゅつ用の鍼を入れておく筒。
はりつつみ‐いす【張包椅子】
座・背・肱ひじの全部を布地で張り包んだ椅子。
ばりっ‐と
〔副〕
①押出しがよく立派なさま。「―した人」
②固い物を強い力で打ち割る音の形容。
ぱりっ‐と
〔副〕
①衣服などが新しく見ばえのするさま。「―した服装」
②ぴんと張りをもっているさま。「糊のり付けで―させたシャツ」
③薄く固い物が割れたりはがれたりする音の形容。
はり‐づな【張綱】
①馬の口につけて左右へ引っ張る綱。
②張り渡した綱。
はり‐つ・める【張り詰める】
〔自他下一〕[文]はりつ・む(下二)
①一面に残す所なく張る。「氷が―・める」
②気持を十分に張る。緊張する。二葉亭四迷、平凡「―・めて破裂はちきれさうになつてゐた気がサツと退ひいて」
はり‐て【張手】
①物事をはりこんでする人。物事をはでにする人。
②相撲のわざの一つ。相手の横面を平手で打つこと。
はり‐で【針手】
(ハリテとも)裁縫の技量。また、裁縫に巧みな人。傾城禁短気「―の利かぬ槌の子は」
パリティー【parity】
①同等。等価。
②量子力学で空間反転を表現する物理量。その値はプラス1かマイナス1。一般に反応の前後でパリティーは変わらない。偶奇性。
⇒パリティー‐けいさん【パリティー計算】
⇒パリティー‐チェック【parity check】
⇒パリティー‐ビット【parity bit】
パリティー‐けいさん【パリティー計算】
(parity account)一定の基準年度の価格に、当該年度の価格指数(パリティー指数)を乗じて価格を算出する方法。第二次大戦後、食糧管理制度下で農産物の生産者価格の算定に用いられた。
⇒パリティー【parity】
パリティー‐チェック【parity check】
コンピューターやデータ通信で、データの誤りを検出する手法の一つ。データの各ビットの総和が偶数(あるいは奇数)を示す1ビットを付加する。
⇒パリティー【parity】
パリティー‐ビット【parity bit】
パリティー‐チェックのために余分に付け加えるビット。
⇒パリティー【parity】
バリ‐とう【バリ島】‥タウ
(Bali)ジャワ島の東に隣接する小火山島。イスラム文化圏にあるインドネシア共和国の中でヒンドゥー教を信仰する唯一の島。古典舞踊やガムラン音楽で有名。観光地。
バリ島の舞踊(1)
撮影:小松義夫
②クモガニ科のカニ。甲は細長い洋梨形で、左右の額角がっかくが中央部で合わさる。甲、歩脚一面が細い刺とげで覆われる。本州中部以南の浅海砂泥底にすむ。
③(山陰・北陸地方で)12月8日のこと。冬の北西季節風による海荒れの際、1が海浜に波で打ち上げられるのでいう。この日針供養をする。
はり‐そ【張訴・貼訴】
江戸時代、老中邸または役所の門前などに訴状をひそかに貼っておいたこと。
ばり‐ぞうごん【罵詈雑言】‥ザフ‥
口ぎたない、ののしりの言葉。「―を浴びせる」
はり‐た【墾田】
新たに開墾した田。孝徳紀「―の頃畝」
パリ‐だいがく【パリ大学】
(Université de Paris フランス)パリにあるフランス最古の国立大学。起源は12世紀にさかのぼり、ヨーロッパ中世大学の典型。神学寮に発祥。19世紀以後総合大学として発展。1968年大学改革により13の大学に分割・再編。→パリ(図)→ソルボンヌ
はり‐だいこ【張太鼓】
革を張った太鼓。狂言、張蛸「張蛸ではない、―でおりやる」→締しめ太鼓
はり‐たお・す【張り倒す・撲り倒す】‥タフス
〔他五〕
平手で打って倒す。なぐりたおす。
パリ‐ダカール‐ラリー
(Le rallye Dakar フランス)主にサハラ砂漠を走行する、自動車とオートバイのラリー。総走行距離は1万数千キロメートル。1979年開始。当初はフランスのパリから出発し、セネガルのダカールがゴールであったが、近年はほぼ毎年コースが変わる。パリ‐ダカ。
はり‐だくみ【張工】
(→)経師屋きょうじやのこと。
はり‐だこ【張蛸】
張りひろげて乾燥させた蛸。狂言、張蛸「何を―ぢやと云うて売つてやらう物がない」
はり‐だし【張出し】
①外側へ出っぱらせること。また、そのもの。特に建築でいう。
②広く示すための張り紙。張り札。貼出し。
③相撲で、三役以上の同じ地位に三人以上の力士が並ぶとき、三人目以下を番付の欄外に記すこと。また、その記された力士。「―大関」
④江戸時代、女の結髪に両鬢びんを張り出すのに用いた鯨鬚くじらひげ製の具。
⇒はりだし‐まど【張出し窓】
はりだし‐まど【張出し窓】
建物の外壁面から突き出るように造った窓。出窓。
⇒はり‐だし【張出し】
はり‐だ・す【張り出す】
〔自他五〕
①外側へ出っぱる。また、出っぱらせる。「道路に―・した枝」
②広く示すために、紙や札に記してかかげる。貼り出す。
はり‐たて【針立て・鍼立て】
①はりさし。はりやま。
②(→)鍼医はりいに同じ。昨日は今日の物語「或る人の女房、腹を再々痛がりければ、常々―を呼びてたてさせける」
⇒はりたて‐いかずち【針立雷】
はりたて‐いかずち【針立雷】‥イカヅチ
狂言。(→)「雷かみなり」に同じ。
⇒はり‐たて【針立て・鍼立て】
はり‐だましい【張魂】‥ダマシヒ
意地をはって一徹な気質。まけじだましい。
はり‐ちょうせき【玻璃長石】‥チヤウ‥
カリウムを主成分とする長石の一種。単斜晶系。ガラス光沢をもち、珪長質火山岩中に産する。
はりつ【破笠】
⇒おがわはりつ(小川破笠)。
⇒はりつ‐ざいく【破笠細工】
はり‐つ・く【張り付く・貼り付く】
[一]〔自五〕
①はりつけた状態になる。はりつけたようにくっつく。
②「張付け」2をする。
[二]〔他下二〕
⇒はりつける(下一)
ばり‐つ・く
〔自四〕
威勢よくふるまう。幅をきかす。浮世風呂3「あの人の若い時分―・いた本書ほんかきに」
はり‐つけ【磔】
(「張り付け」の意)昔の刑罰の一つ。初めは身体を板または地上に張りひろげ、釘で打ち付けて殺したが、江戸時代の頃にははりつけ柱に縛りつけ、左右の脇腹から槍で突き殺した。西洋では古代ローマのものが知られるが、のち廃止。はっつけ。磔刑たっけい。
はり‐つけ【張付け・貼付け】
①ものをはりつけること。また、はりつけるもの。
②(比喩的に)監視や取材などのため、そのもののそばから離れずにいること。
⇒はりつけ‐が【貼付画】
⇒はりつけ‐かべ【張付壁】
はりつけ‐が【貼付画】‥グワ
絹や紙に描いて、室内の板や壁に貼りつけた障壁画。
⇒はり‐つけ【張付け・貼付け】
はりつけ‐かべ【張付壁】
襖ふすまを嵌殺はめごろしにしたような構造の壁。また、板に紙を貼った壁。
⇒はり‐つけ【張付け・貼付け】
はりつけ‐もざえもん【磔茂左衛門】‥ヱ‥
江戸前期の農民・義民。上野国の人。姓は杉木。沼田領主真田氏の悪政を将軍に直訴。真田氏は改易・配流され、茂左衛門は磔にされたという。生没年未詳。
はり‐つ・ける【張り付ける・貼り付ける】
〔他下一〕[文]はりつ・く(下二)
①ひろげて他の物につける。
②糊などでくっつける。
③「張付け」2をさせる。「現場に記者を―・ける」
④磔はりつけにする。
はりつ‐ざいく【破笠細工】
貝・陶片・角・牙・木片・板金などを蒔絵と併用して模様を表した漆器。江戸中期の漆工小川破笠が得意とした。
⇒はりつ【破笠】
はり‐づつ【鍼筒】
鍼術しんじゅつ用の鍼を入れておく筒。
はりつつみ‐いす【張包椅子】
座・背・肱ひじの全部を布地で張り包んだ椅子。
ばりっ‐と
〔副〕
①押出しがよく立派なさま。「―した人」
②固い物を強い力で打ち割る音の形容。
ぱりっ‐と
〔副〕
①衣服などが新しく見ばえのするさま。「―した服装」
②ぴんと張りをもっているさま。「糊のり付けで―させたシャツ」
③薄く固い物が割れたりはがれたりする音の形容。
はり‐づな【張綱】
①馬の口につけて左右へ引っ張る綱。
②張り渡した綱。
はり‐つ・める【張り詰める】
〔自他下一〕[文]はりつ・む(下二)
①一面に残す所なく張る。「氷が―・める」
②気持を十分に張る。緊張する。二葉亭四迷、平凡「―・めて破裂はちきれさうになつてゐた気がサツと退ひいて」
はり‐て【張手】
①物事をはりこんでする人。物事をはでにする人。
②相撲のわざの一つ。相手の横面を平手で打つこと。
はり‐で【針手】
(ハリテとも)裁縫の技量。また、裁縫に巧みな人。傾城禁短気「―の利かぬ槌の子は」
パリティー【parity】
①同等。等価。
②量子力学で空間反転を表現する物理量。その値はプラス1かマイナス1。一般に反応の前後でパリティーは変わらない。偶奇性。
⇒パリティー‐けいさん【パリティー計算】
⇒パリティー‐チェック【parity check】
⇒パリティー‐ビット【parity bit】
パリティー‐けいさん【パリティー計算】
(parity account)一定の基準年度の価格に、当該年度の価格指数(パリティー指数)を乗じて価格を算出する方法。第二次大戦後、食糧管理制度下で農産物の生産者価格の算定に用いられた。
⇒パリティー【parity】
パリティー‐チェック【parity check】
コンピューターやデータ通信で、データの誤りを検出する手法の一つ。データの各ビットの総和が偶数(あるいは奇数)を示す1ビットを付加する。
⇒パリティー【parity】
パリティー‐ビット【parity bit】
パリティー‐チェックのために余分に付け加えるビット。
⇒パリティー【parity】
バリ‐とう【バリ島】‥タウ
(Bali)ジャワ島の東に隣接する小火山島。イスラム文化圏にあるインドネシア共和国の中でヒンドゥー教を信仰する唯一の島。古典舞踊やガムラン音楽で有名。観光地。
バリ島の舞踊(1)
撮影:小松義夫
 バリ島の舞踊(2)
撮影:小松義夫
バリ島の舞踊(2)
撮影:小松義夫
 はり‐とがめ【針咎め】
針で指先を傷つけること。誹風柳多留初「じれつたく師走を遊ぶ―」
はり‐どの【張殿】
着物を打ち、また板引いたびきなどをする家。三十二番職人歌合「―、きぬ共を春の日しめしおきもあへず、花見の出立ち急がるる比」
はり‐とば・す【張り飛ばす・撲り飛ばす】
〔他五〕
平手でなぐりとばす。二葉亭四迷、其面影「乱暴にも其人を―・し、後で謝罪書を取られるなど」
バリトン【barytone】
①テノールとバスとの中間の男声音域。次低音。また、その音域の歌手。
②次低音の音域をもつ楽器(弦楽器、チューバ系の金管楽器)の名称。また他の楽器名に付加して次低音音域の楽器であることを示す。
バリニャーノ【A. Valignano】
⇒ヴァリニャーノ
はり‐ぬき【張抜き】
(→)張子はりこ1に同じ。
⇒はりぬき‐づつ【張抜き筒】
はりぬき‐づつ【張抜き筒】
張抜きで円く長く造った筒。
⇒はり‐ぬき【張抜き】
はり‐ぬ・く【張り抜く】
〔他四〕
張抜きに作る。鹿の子餅「美しいきれで―・いた上り兜」
はり‐ねずみ【針鼠】
モグラ目ハリネズミ科の哺乳類の総称。8属17種。その1種ヨーロッパハリネズミ(ナミハリネズミ)は、頭胴長25センチメートル前後。尾・足は短い。毛色は茶褐色。頭頂部と背には針状の毛があり、危険に遭えば体を丸め身を守る。薄暗い時間に活動し、昆虫やミミズなどを食べる。ヨーロッパから中国・朝鮮に分布するが、アジアのものを別種とすることもある。猬。蝟。
はりねずみ
はり‐とがめ【針咎め】
針で指先を傷つけること。誹風柳多留初「じれつたく師走を遊ぶ―」
はり‐どの【張殿】
着物を打ち、また板引いたびきなどをする家。三十二番職人歌合「―、きぬ共を春の日しめしおきもあへず、花見の出立ち急がるる比」
はり‐とば・す【張り飛ばす・撲り飛ばす】
〔他五〕
平手でなぐりとばす。二葉亭四迷、其面影「乱暴にも其人を―・し、後で謝罪書を取られるなど」
バリトン【barytone】
①テノールとバスとの中間の男声音域。次低音。また、その音域の歌手。
②次低音の音域をもつ楽器(弦楽器、チューバ系の金管楽器)の名称。また他の楽器名に付加して次低音音域の楽器であることを示す。
バリニャーノ【A. Valignano】
⇒ヴァリニャーノ
はり‐ぬき【張抜き】
(→)張子はりこ1に同じ。
⇒はりぬき‐づつ【張抜き筒】
はりぬき‐づつ【張抜き筒】
張抜きで円く長く造った筒。
⇒はり‐ぬき【張抜き】
はり‐ぬ・く【張り抜く】
〔他四〕
張抜きに作る。鹿の子餅「美しいきれで―・いた上り兜」
はり‐ねずみ【針鼠】
モグラ目ハリネズミ科の哺乳類の総称。8属17種。その1種ヨーロッパハリネズミ(ナミハリネズミ)は、頭胴長25センチメートル前後。尾・足は短い。毛色は茶褐色。頭頂部と背には針状の毛があり、危険に遭えば体を丸め身を守る。薄暗い時間に活動し、昆虫やミミズなどを食べる。ヨーロッパから中国・朝鮮に分布するが、アジアのものを別種とすることもある。猬。蝟。
はりねずみ
 ハリネズミ
提供:東京動物園協会
ハリネズミ
提供:東京動物園協会
 ハリネズミ
提供:東京動物園協会
ハリネズミ
提供:東京動物園協会
 はり‐の‐あな【針の孔・針の穴】
縫針の頭部にある糸を通す孔。めど。針の耳。
⇒針の孔から天のぞく
はり‐の‐あな【針の孔・針の穴】
縫針の頭部にある糸を通す孔。めど。針の耳。
⇒針の孔から天のぞく
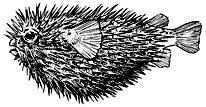 ハリセンボン
提供:東京動物園協会
ハリセンボン
提供:東京動物園協会
 ②クモガニ科のカニ。甲は細長い洋梨形で、左右の額角がっかくが中央部で合わさる。甲、歩脚一面が細い刺とげで覆われる。本州中部以南の浅海砂泥底にすむ。
③(山陰・北陸地方で)12月8日のこと。冬の北西季節風による海荒れの際、1が海浜に波で打ち上げられるのでいう。この日針供養をする。
はり‐そ【張訴・貼訴】
江戸時代、老中邸または役所の門前などに訴状をひそかに貼っておいたこと。
ばり‐ぞうごん【罵詈雑言】‥ザフ‥
口ぎたない、ののしりの言葉。「―を浴びせる」
はり‐た【墾田】
新たに開墾した田。孝徳紀「―の頃畝」
パリ‐だいがく【パリ大学】
(Université de Paris フランス)パリにあるフランス最古の国立大学。起源は12世紀にさかのぼり、ヨーロッパ中世大学の典型。神学寮に発祥。19世紀以後総合大学として発展。1968年大学改革により13の大学に分割・再編。→パリ(図)→ソルボンヌ
はり‐だいこ【張太鼓】
革を張った太鼓。狂言、張蛸「張蛸ではない、―でおりやる」→締しめ太鼓
はり‐たお・す【張り倒す・撲り倒す】‥タフス
〔他五〕
平手で打って倒す。なぐりたおす。
パリ‐ダカール‐ラリー
(Le rallye Dakar フランス)主にサハラ砂漠を走行する、自動車とオートバイのラリー。総走行距離は1万数千キロメートル。1979年開始。当初はフランスのパリから出発し、セネガルのダカールがゴールであったが、近年はほぼ毎年コースが変わる。パリ‐ダカ。
はり‐だくみ【張工】
(→)経師屋きょうじやのこと。
はり‐だこ【張蛸】
張りひろげて乾燥させた蛸。狂言、張蛸「何を―ぢやと云うて売つてやらう物がない」
はり‐だし【張出し】
①外側へ出っぱらせること。また、そのもの。特に建築でいう。
②広く示すための張り紙。張り札。貼出し。
③相撲で、三役以上の同じ地位に三人以上の力士が並ぶとき、三人目以下を番付の欄外に記すこと。また、その記された力士。「―大関」
④江戸時代、女の結髪に両鬢びんを張り出すのに用いた鯨鬚くじらひげ製の具。
⇒はりだし‐まど【張出し窓】
はりだし‐まど【張出し窓】
建物の外壁面から突き出るように造った窓。出窓。
⇒はり‐だし【張出し】
はり‐だ・す【張り出す】
〔自他五〕
①外側へ出っぱる。また、出っぱらせる。「道路に―・した枝」
②広く示すために、紙や札に記してかかげる。貼り出す。
はり‐たて【針立て・鍼立て】
①はりさし。はりやま。
②(→)鍼医はりいに同じ。昨日は今日の物語「或る人の女房、腹を再々痛がりければ、常々―を呼びてたてさせける」
⇒はりたて‐いかずち【針立雷】
はりたて‐いかずち【針立雷】‥イカヅチ
狂言。(→)「雷かみなり」に同じ。
⇒はり‐たて【針立て・鍼立て】
はり‐だましい【張魂】‥ダマシヒ
意地をはって一徹な気質。まけじだましい。
はり‐ちょうせき【玻璃長石】‥チヤウ‥
カリウムを主成分とする長石の一種。単斜晶系。ガラス光沢をもち、珪長質火山岩中に産する。
はりつ【破笠】
⇒おがわはりつ(小川破笠)。
⇒はりつ‐ざいく【破笠細工】
はり‐つ・く【張り付く・貼り付く】
[一]〔自五〕
①はりつけた状態になる。はりつけたようにくっつく。
②「張付け」2をする。
[二]〔他下二〕
⇒はりつける(下一)
ばり‐つ・く
〔自四〕
威勢よくふるまう。幅をきかす。浮世風呂3「あの人の若い時分―・いた本書ほんかきに」
はり‐つけ【磔】
(「張り付け」の意)昔の刑罰の一つ。初めは身体を板または地上に張りひろげ、釘で打ち付けて殺したが、江戸時代の頃にははりつけ柱に縛りつけ、左右の脇腹から槍で突き殺した。西洋では古代ローマのものが知られるが、のち廃止。はっつけ。磔刑たっけい。
はり‐つけ【張付け・貼付け】
①ものをはりつけること。また、はりつけるもの。
②(比喩的に)監視や取材などのため、そのもののそばから離れずにいること。
⇒はりつけ‐が【貼付画】
⇒はりつけ‐かべ【張付壁】
はりつけ‐が【貼付画】‥グワ
絹や紙に描いて、室内の板や壁に貼りつけた障壁画。
⇒はり‐つけ【張付け・貼付け】
はりつけ‐かべ【張付壁】
襖ふすまを嵌殺はめごろしにしたような構造の壁。また、板に紙を貼った壁。
⇒はり‐つけ【張付け・貼付け】
はりつけ‐もざえもん【磔茂左衛門】‥ヱ‥
江戸前期の農民・義民。上野国の人。姓は杉木。沼田領主真田氏の悪政を将軍に直訴。真田氏は改易・配流され、茂左衛門は磔にされたという。生没年未詳。
はり‐つ・ける【張り付ける・貼り付ける】
〔他下一〕[文]はりつ・く(下二)
①ひろげて他の物につける。
②糊などでくっつける。
③「張付け」2をさせる。「現場に記者を―・ける」
④磔はりつけにする。
はりつ‐ざいく【破笠細工】
貝・陶片・角・牙・木片・板金などを蒔絵と併用して模様を表した漆器。江戸中期の漆工小川破笠が得意とした。
⇒はりつ【破笠】
はり‐づつ【鍼筒】
鍼術しんじゅつ用の鍼を入れておく筒。
はりつつみ‐いす【張包椅子】
座・背・肱ひじの全部を布地で張り包んだ椅子。
ばりっ‐と
〔副〕
①押出しがよく立派なさま。「―した人」
②固い物を強い力で打ち割る音の形容。
ぱりっ‐と
〔副〕
①衣服などが新しく見ばえのするさま。「―した服装」
②ぴんと張りをもっているさま。「糊のり付けで―させたシャツ」
③薄く固い物が割れたりはがれたりする音の形容。
はり‐づな【張綱】
①馬の口につけて左右へ引っ張る綱。
②張り渡した綱。
はり‐つ・める【張り詰める】
〔自他下一〕[文]はりつ・む(下二)
①一面に残す所なく張る。「氷が―・める」
②気持を十分に張る。緊張する。二葉亭四迷、平凡「―・めて破裂はちきれさうになつてゐた気がサツと退ひいて」
はり‐て【張手】
①物事をはりこんでする人。物事をはでにする人。
②相撲のわざの一つ。相手の横面を平手で打つこと。
はり‐で【針手】
(ハリテとも)裁縫の技量。また、裁縫に巧みな人。傾城禁短気「―の利かぬ槌の子は」
パリティー【parity】
①同等。等価。
②量子力学で空間反転を表現する物理量。その値はプラス1かマイナス1。一般に反応の前後でパリティーは変わらない。偶奇性。
⇒パリティー‐けいさん【パリティー計算】
⇒パリティー‐チェック【parity check】
⇒パリティー‐ビット【parity bit】
パリティー‐けいさん【パリティー計算】
(parity account)一定の基準年度の価格に、当該年度の価格指数(パリティー指数)を乗じて価格を算出する方法。第二次大戦後、食糧管理制度下で農産物の生産者価格の算定に用いられた。
⇒パリティー【parity】
パリティー‐チェック【parity check】
コンピューターやデータ通信で、データの誤りを検出する手法の一つ。データの各ビットの総和が偶数(あるいは奇数)を示す1ビットを付加する。
⇒パリティー【parity】
パリティー‐ビット【parity bit】
パリティー‐チェックのために余分に付け加えるビット。
⇒パリティー【parity】
バリ‐とう【バリ島】‥タウ
(Bali)ジャワ島の東に隣接する小火山島。イスラム文化圏にあるインドネシア共和国の中でヒンドゥー教を信仰する唯一の島。古典舞踊やガムラン音楽で有名。観光地。
バリ島の舞踊(1)
撮影:小松義夫
②クモガニ科のカニ。甲は細長い洋梨形で、左右の額角がっかくが中央部で合わさる。甲、歩脚一面が細い刺とげで覆われる。本州中部以南の浅海砂泥底にすむ。
③(山陰・北陸地方で)12月8日のこと。冬の北西季節風による海荒れの際、1が海浜に波で打ち上げられるのでいう。この日針供養をする。
はり‐そ【張訴・貼訴】
江戸時代、老中邸または役所の門前などに訴状をひそかに貼っておいたこと。
ばり‐ぞうごん【罵詈雑言】‥ザフ‥
口ぎたない、ののしりの言葉。「―を浴びせる」
はり‐た【墾田】
新たに開墾した田。孝徳紀「―の頃畝」
パリ‐だいがく【パリ大学】
(Université de Paris フランス)パリにあるフランス最古の国立大学。起源は12世紀にさかのぼり、ヨーロッパ中世大学の典型。神学寮に発祥。19世紀以後総合大学として発展。1968年大学改革により13の大学に分割・再編。→パリ(図)→ソルボンヌ
はり‐だいこ【張太鼓】
革を張った太鼓。狂言、張蛸「張蛸ではない、―でおりやる」→締しめ太鼓
はり‐たお・す【張り倒す・撲り倒す】‥タフス
〔他五〕
平手で打って倒す。なぐりたおす。
パリ‐ダカール‐ラリー
(Le rallye Dakar フランス)主にサハラ砂漠を走行する、自動車とオートバイのラリー。総走行距離は1万数千キロメートル。1979年開始。当初はフランスのパリから出発し、セネガルのダカールがゴールであったが、近年はほぼ毎年コースが変わる。パリ‐ダカ。
はり‐だくみ【張工】
(→)経師屋きょうじやのこと。
はり‐だこ【張蛸】
張りひろげて乾燥させた蛸。狂言、張蛸「何を―ぢやと云うて売つてやらう物がない」
はり‐だし【張出し】
①外側へ出っぱらせること。また、そのもの。特に建築でいう。
②広く示すための張り紙。張り札。貼出し。
③相撲で、三役以上の同じ地位に三人以上の力士が並ぶとき、三人目以下を番付の欄外に記すこと。また、その記された力士。「―大関」
④江戸時代、女の結髪に両鬢びんを張り出すのに用いた鯨鬚くじらひげ製の具。
⇒はりだし‐まど【張出し窓】
はりだし‐まど【張出し窓】
建物の外壁面から突き出るように造った窓。出窓。
⇒はり‐だし【張出し】
はり‐だ・す【張り出す】
〔自他五〕
①外側へ出っぱる。また、出っぱらせる。「道路に―・した枝」
②広く示すために、紙や札に記してかかげる。貼り出す。
はり‐たて【針立て・鍼立て】
①はりさし。はりやま。
②(→)鍼医はりいに同じ。昨日は今日の物語「或る人の女房、腹を再々痛がりければ、常々―を呼びてたてさせける」
⇒はりたて‐いかずち【針立雷】
はりたて‐いかずち【針立雷】‥イカヅチ
狂言。(→)「雷かみなり」に同じ。
⇒はり‐たて【針立て・鍼立て】
はり‐だましい【張魂】‥ダマシヒ
意地をはって一徹な気質。まけじだましい。
はり‐ちょうせき【玻璃長石】‥チヤウ‥
カリウムを主成分とする長石の一種。単斜晶系。ガラス光沢をもち、珪長質火山岩中に産する。
はりつ【破笠】
⇒おがわはりつ(小川破笠)。
⇒はりつ‐ざいく【破笠細工】
はり‐つ・く【張り付く・貼り付く】
[一]〔自五〕
①はりつけた状態になる。はりつけたようにくっつく。
②「張付け」2をする。
[二]〔他下二〕
⇒はりつける(下一)
ばり‐つ・く
〔自四〕
威勢よくふるまう。幅をきかす。浮世風呂3「あの人の若い時分―・いた本書ほんかきに」
はり‐つけ【磔】
(「張り付け」の意)昔の刑罰の一つ。初めは身体を板または地上に張りひろげ、釘で打ち付けて殺したが、江戸時代の頃にははりつけ柱に縛りつけ、左右の脇腹から槍で突き殺した。西洋では古代ローマのものが知られるが、のち廃止。はっつけ。磔刑たっけい。
はり‐つけ【張付け・貼付け】
①ものをはりつけること。また、はりつけるもの。
②(比喩的に)監視や取材などのため、そのもののそばから離れずにいること。
⇒はりつけ‐が【貼付画】
⇒はりつけ‐かべ【張付壁】
はりつけ‐が【貼付画】‥グワ
絹や紙に描いて、室内の板や壁に貼りつけた障壁画。
⇒はり‐つけ【張付け・貼付け】
はりつけ‐かべ【張付壁】
襖ふすまを嵌殺はめごろしにしたような構造の壁。また、板に紙を貼った壁。
⇒はり‐つけ【張付け・貼付け】
はりつけ‐もざえもん【磔茂左衛門】‥ヱ‥
江戸前期の農民・義民。上野国の人。姓は杉木。沼田領主真田氏の悪政を将軍に直訴。真田氏は改易・配流され、茂左衛門は磔にされたという。生没年未詳。
はり‐つ・ける【張り付ける・貼り付ける】
〔他下一〕[文]はりつ・く(下二)
①ひろげて他の物につける。
②糊などでくっつける。
③「張付け」2をさせる。「現場に記者を―・ける」
④磔はりつけにする。
はりつ‐ざいく【破笠細工】
貝・陶片・角・牙・木片・板金などを蒔絵と併用して模様を表した漆器。江戸中期の漆工小川破笠が得意とした。
⇒はりつ【破笠】
はり‐づつ【鍼筒】
鍼術しんじゅつ用の鍼を入れておく筒。
はりつつみ‐いす【張包椅子】
座・背・肱ひじの全部を布地で張り包んだ椅子。
ばりっ‐と
〔副〕
①押出しがよく立派なさま。「―した人」
②固い物を強い力で打ち割る音の形容。
ぱりっ‐と
〔副〕
①衣服などが新しく見ばえのするさま。「―した服装」
②ぴんと張りをもっているさま。「糊のり付けで―させたシャツ」
③薄く固い物が割れたりはがれたりする音の形容。
はり‐づな【張綱】
①馬の口につけて左右へ引っ張る綱。
②張り渡した綱。
はり‐つ・める【張り詰める】
〔自他下一〕[文]はりつ・む(下二)
①一面に残す所なく張る。「氷が―・める」
②気持を十分に張る。緊張する。二葉亭四迷、平凡「―・めて破裂はちきれさうになつてゐた気がサツと退ひいて」
はり‐て【張手】
①物事をはりこんでする人。物事をはでにする人。
②相撲のわざの一つ。相手の横面を平手で打つこと。
はり‐で【針手】
(ハリテとも)裁縫の技量。また、裁縫に巧みな人。傾城禁短気「―の利かぬ槌の子は」
パリティー【parity】
①同等。等価。
②量子力学で空間反転を表現する物理量。その値はプラス1かマイナス1。一般に反応の前後でパリティーは変わらない。偶奇性。
⇒パリティー‐けいさん【パリティー計算】
⇒パリティー‐チェック【parity check】
⇒パリティー‐ビット【parity bit】
パリティー‐けいさん【パリティー計算】
(parity account)一定の基準年度の価格に、当該年度の価格指数(パリティー指数)を乗じて価格を算出する方法。第二次大戦後、食糧管理制度下で農産物の生産者価格の算定に用いられた。
⇒パリティー【parity】
パリティー‐チェック【parity check】
コンピューターやデータ通信で、データの誤りを検出する手法の一つ。データの各ビットの総和が偶数(あるいは奇数)を示す1ビットを付加する。
⇒パリティー【parity】
パリティー‐ビット【parity bit】
パリティー‐チェックのために余分に付け加えるビット。
⇒パリティー【parity】
バリ‐とう【バリ島】‥タウ
(Bali)ジャワ島の東に隣接する小火山島。イスラム文化圏にあるインドネシア共和国の中でヒンドゥー教を信仰する唯一の島。古典舞踊やガムラン音楽で有名。観光地。
バリ島の舞踊(1)
撮影:小松義夫
 バリ島の舞踊(2)
撮影:小松義夫
バリ島の舞踊(2)
撮影:小松義夫
 はり‐とがめ【針咎め】
針で指先を傷つけること。誹風柳多留初「じれつたく師走を遊ぶ―」
はり‐どの【張殿】
着物を打ち、また板引いたびきなどをする家。三十二番職人歌合「―、きぬ共を春の日しめしおきもあへず、花見の出立ち急がるる比」
はり‐とば・す【張り飛ばす・撲り飛ばす】
〔他五〕
平手でなぐりとばす。二葉亭四迷、其面影「乱暴にも其人を―・し、後で謝罪書を取られるなど」
バリトン【barytone】
①テノールとバスとの中間の男声音域。次低音。また、その音域の歌手。
②次低音の音域をもつ楽器(弦楽器、チューバ系の金管楽器)の名称。また他の楽器名に付加して次低音音域の楽器であることを示す。
バリニャーノ【A. Valignano】
⇒ヴァリニャーノ
はり‐ぬき【張抜き】
(→)張子はりこ1に同じ。
⇒はりぬき‐づつ【張抜き筒】
はりぬき‐づつ【張抜き筒】
張抜きで円く長く造った筒。
⇒はり‐ぬき【張抜き】
はり‐ぬ・く【張り抜く】
〔他四〕
張抜きに作る。鹿の子餅「美しいきれで―・いた上り兜」
はり‐ねずみ【針鼠】
モグラ目ハリネズミ科の哺乳類の総称。8属17種。その1種ヨーロッパハリネズミ(ナミハリネズミ)は、頭胴長25センチメートル前後。尾・足は短い。毛色は茶褐色。頭頂部と背には針状の毛があり、危険に遭えば体を丸め身を守る。薄暗い時間に活動し、昆虫やミミズなどを食べる。ヨーロッパから中国・朝鮮に分布するが、アジアのものを別種とすることもある。猬。蝟。
はりねずみ
はり‐とがめ【針咎め】
針で指先を傷つけること。誹風柳多留初「じれつたく師走を遊ぶ―」
はり‐どの【張殿】
着物を打ち、また板引いたびきなどをする家。三十二番職人歌合「―、きぬ共を春の日しめしおきもあへず、花見の出立ち急がるる比」
はり‐とば・す【張り飛ばす・撲り飛ばす】
〔他五〕
平手でなぐりとばす。二葉亭四迷、其面影「乱暴にも其人を―・し、後で謝罪書を取られるなど」
バリトン【barytone】
①テノールとバスとの中間の男声音域。次低音。また、その音域の歌手。
②次低音の音域をもつ楽器(弦楽器、チューバ系の金管楽器)の名称。また他の楽器名に付加して次低音音域の楽器であることを示す。
バリニャーノ【A. Valignano】
⇒ヴァリニャーノ
はり‐ぬき【張抜き】
(→)張子はりこ1に同じ。
⇒はりぬき‐づつ【張抜き筒】
はりぬき‐づつ【張抜き筒】
張抜きで円く長く造った筒。
⇒はり‐ぬき【張抜き】
はり‐ぬ・く【張り抜く】
〔他四〕
張抜きに作る。鹿の子餅「美しいきれで―・いた上り兜」
はり‐ねずみ【針鼠】
モグラ目ハリネズミ科の哺乳類の総称。8属17種。その1種ヨーロッパハリネズミ(ナミハリネズミ)は、頭胴長25センチメートル前後。尾・足は短い。毛色は茶褐色。頭頂部と背には針状の毛があり、危険に遭えば体を丸め身を守る。薄暗い時間に活動し、昆虫やミミズなどを食べる。ヨーロッパから中国・朝鮮に分布するが、アジアのものを別種とすることもある。猬。蝟。
はりねずみ
 ハリネズミ
提供:東京動物園協会
ハリネズミ
提供:東京動物園協会
 ハリネズミ
提供:東京動物園協会
ハリネズミ
提供:東京動物園協会
 はり‐の‐あな【針の孔・針の穴】
縫針の頭部にある糸を通す孔。めど。針の耳。
⇒針の孔から天のぞく
はり‐の‐あな【針の孔・針の穴】
縫針の頭部にある糸を通す孔。めど。針の耳。
⇒針の孔から天のぞく
広辞苑 ページ 16135 での【○針刺すばかり】単語。