複数辞典一括検索+![]()
![]()
○株が上がるかぶがあがる🔗⭐🔉
○株が上がるかぶがあがる
その人に対する評価が高くなる。「会長としての―」
⇒かぶ【株】
かぶか‐しすう【株価指数】
個々の株式の価格を総合して、その変動を示す統計的指数。→東証株価指数→日経平均株価。
⇒かぶ‐か【株価】
かぶかしすう‐さきものとりひき【株価指数先物取引】
株価指数の動きを対象とした先物取引。→株式先物取引。
⇒かぶ‐か【株価】
かぶか‐しゅうえき‐りつ【株価収益率】‥シウ‥
(price-earnings ratio; PER)株価指標の一つ。1株当り予想利益に対する株価の倍率。倍率が高い場合を割高、低い場合を割安という。株価を配当とではなく、利益と直結させて考えるもの。→株価純資産倍率。
⇒かぶ‐か【株価】
かぶか‐じゅんしさん‐ばいりつ【株価純資産倍率】
(price book-value ratio; PBR)株価指標の一つ。株価をその会社の1株当り純資産で割った倍率。企業の資産価値を判断する指標となる。
⇒かぶ‐か【株価】
カフカス【Kavkaz ロシア】
①黒海とカスピ海の間を北西から南東に走る山脈。長さ約1100キロメートル。ギリシア神話のプロメテウスが縛りつけられたと伝えられる所。約2000の氷河がある。最高峰はエリブルス山(5642メートル)。コーカサス。
②ヨーロッパ‐ロシアの南部、カフカス山脈の南北にわたる地方。黒海とカスピ海の間に位置し、ロシア連邦に属する北カフカスと、アルメニア・アゼルバイジャン・グルジア3共和国に分属するザカフカスとに分かれる。コーカシア。コーカサス。
⇒カフカス‐ご【カフカス語】
カフカス‐ご【カフカス語】
(→)コーカサス語に同じ。
⇒カフカス【Kavkaz ロシア】
がぶ‐がぶ
液体を勢いよく大量に続けて飲む音。また、そのさま。日葡辞書「ガブガブトノム」
かぶき【歌舞伎・歌舞妓】
(天正1573〜1592頃に流行した俗語カブクの連用形から)
①異常な放埒ほうらつをすること。ふざけた振舞い。異様な風俗。
②歌舞伎踊の略。
③歌舞伎劇の略。
⇒かぶき‐うた【歌舞伎唄】
⇒かぶき‐おどり【歌舞伎踊】
⇒かぶき‐おんがく【歌舞伎音楽】
⇒かぶき‐きょうげん【歌舞伎狂言】
⇒かぶき‐げき【歌舞伎劇】
⇒かぶき‐こ【歌舞伎子】
⇒かぶき‐ざ【歌舞伎座】
⇒かぶき‐しばい【歌舞伎芝居】
⇒かぶき‐じゅうはちばん【歌舞伎十八番】
⇒かぶき‐じょうるり【歌舞伎浄瑠璃】
⇒かぶき‐そうし【歌舞伎草子】
⇒かぶき‐ねんだいき【歌舞伎年代記】
⇒かぶき‐もの【歌舞伎者】
⇒かぶき‐やくしゃ【歌舞伎役者】
⇒かぶき‐わかしゅ【歌舞伎若衆】
かぶ‐き【冠木】
①門柱の上部を貫く横木。柱の頂上より少し下にある点で笠木と異なる。
②冠木門の略。
⇒かぶき‐もん【冠木門】
かぶ‐き【歌舞伎】
歌舞を演奏すること。日本後紀「伊勢斎宮新嘗会を停む。但し―を以て九月祭に供す」
かぶき‐うた【歌舞伎唄】
歌舞伎劇に用いられる唄。初期は地唄・小唄を主とし、後には長唄が代表的となり、所作事しょさごと唄と下座げざ唄とに分かれる。
⇒かぶき【歌舞伎・歌舞妓】
かぶき‐おどり【歌舞伎踊】‥ヲドリ
歌舞伎初期の女歌舞伎または若衆歌舞伎の踊。流行唄にあわせて踊ったもの。
⇒かぶき【歌舞伎・歌舞妓】
かぶき‐おんがく【歌舞伎音楽】
歌舞伎劇に伴う音楽。所作事しょさごとの伴奏に当たる所作音楽と、舞台の音楽効果のための下座げざ音楽とがある。
⇒かぶき【歌舞伎・歌舞妓】
かぶき‐きょうげん【歌舞伎狂言】‥キヤウ‥
(能狂言・操あやつり狂言に対して)歌舞伎劇。また、その脚本。
⇒かぶき【歌舞伎・歌舞妓】
かぶき‐げき【歌舞伎劇】
阿国おくに歌舞伎に発源し、江戸時代に興隆、独自の発達を遂げた日本特有の演劇。史実・伝説や社会事象を、俳優が主として江戸時代およびそれ以前の人物に扮し、音楽・舞台装置の補助によって演ずる技芸で、舞踊の要素をも含む。歌舞伎芝居。旧劇。
⇒かぶき【歌舞伎・歌舞妓】
かぶき‐こ【歌舞伎子】
江戸時代、歌舞伎劇に出る少年俳優。かげで男色を売った。舞台子。歌舞伎若衆。
⇒かぶき【歌舞伎・歌舞妓】
かぶき‐ざ【歌舞伎座】
①歌舞伎劇を演ずる一座および劇場。
②東京都中央区銀座(もと木挽町)にある劇場。主として歌舞伎劇を上演。1889年(明治22)開場。
⇒かぶき【歌舞伎・歌舞妓】
かぶき‐しばい【歌舞伎芝居】‥ヰ
①江戸時代、櫓やぐらをあげる(一座を組んで興行する)ことを許された芝居。
②(操芝居・人形芝居に対していう)歌舞伎劇。
⇒かぶき【歌舞伎・歌舞妓】
かぶき‐じゅうはちばん【歌舞伎十八番】‥ジフ‥
市川家で代々勤めてきた当り狂言十八番、すなわち助六・矢の根・関羽・不動・象引・毛抜・外郎売ういろううり・暫しばらく・七つ面・解脱・嫐うわなり・蛇柳じゃやなぎ・鳴神・鎌髭・景清・不破・押戻おしもどし・勧進帳をいう。7代団十郎が制定。
⇒かぶき【歌舞伎・歌舞妓】
かぶき‐じょうるり【歌舞伎浄瑠璃】‥ジヤウ‥
歌舞伎で用いられる各種の浄瑠璃。普通は人形劇に用いられる義太夫節を除いて一中節・河東節・豊後節・常磐津節・清元節などを指して言う。
⇒かぶき【歌舞伎・歌舞妓】
かぶき‐そうし【歌舞伎草子】‥サウ‥
創始期の阿国おくに歌舞伎・女歌舞伎を素材に絵と詞によって仕立てた草子・絵巻の総称。「国女くにじょ歌舞妓絵詞」など。
⇒かぶき【歌舞伎・歌舞妓】
かぶき‐ちょう【歌舞伎町】‥チヤウ
東京都新宿区南部、JR新宿駅の東にある町。飲食店・映画館・劇場などが集中する歓楽街。
かぶき‐どう【衡胴】
鎧よろい・腹巻・具足の類の立挙たてあげと草摺くさずりとの間の胴を取り巻く部分。長側ながかわ。→大鎧(図)
かぶき‐ねんだいき【歌舞伎年代記】
江戸歌舞伎の興行年表の総称。狭義には烏亭焉馬うていえんば編のもの(寛永元年〜文化元年)を指す。広義には石塚豊芥子ほうかいし編(〜安政6年7月)・田村成義編(〜明治36年)・利倉幸一編(〜明治45年7月)のものを含む。のち伊原敏郎「歌舞伎年表」(永禄2年〜明治40年)8巻が出た。
⇒かぶき【歌舞伎・歌舞妓】
かぶき‐もの【歌舞伎者】
異様な風体をして大道を横行する者。軽佻浮薄な遊侠の徒や伊達者。好色一代男5「博多小女郎と申して―ありける」
⇒かぶき【歌舞伎・歌舞妓】
かぶき‐もん【冠木門】
冠木を2柱の上方に渡した屋根のない門。衡門こうもん。
冠木門
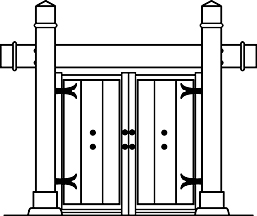 ⇒かぶ‐き【冠木】
かぶき‐やくしゃ【歌舞伎役者】
歌舞伎劇に出演する俳優。歌舞伎俳優。
⇒かぶき【歌舞伎・歌舞妓】
か‐ふきゅう【過不及】クワ‥キフ
程度を過ぎたり、程度に達しなかったりすること。多すぎたり足りなかったりすること。過不足。日葡辞書「ヨロヅニクヮフギュウハワルイ」
⇒過不及無し
⇒かぶ‐き【冠木】
かぶき‐やくしゃ【歌舞伎役者】
歌舞伎劇に出演する俳優。歌舞伎俳優。
⇒かぶき【歌舞伎・歌舞妓】
か‐ふきゅう【過不及】クワ‥キフ
程度を過ぎたり、程度に達しなかったりすること。多すぎたり足りなかったりすること。過不足。日葡辞書「ヨロヅニクヮフギュウハワルイ」
⇒過不及無し
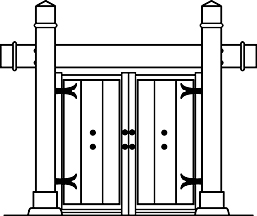 ⇒かぶ‐き【冠木】
かぶき‐やくしゃ【歌舞伎役者】
歌舞伎劇に出演する俳優。歌舞伎俳優。
⇒かぶき【歌舞伎・歌舞妓】
か‐ふきゅう【過不及】クワ‥キフ
程度を過ぎたり、程度に達しなかったりすること。多すぎたり足りなかったりすること。過不足。日葡辞書「ヨロヅニクヮフギュウハワルイ」
⇒過不及無し
⇒かぶ‐き【冠木】
かぶき‐やくしゃ【歌舞伎役者】
歌舞伎劇に出演する俳優。歌舞伎俳優。
⇒かぶき【歌舞伎・歌舞妓】
か‐ふきゅう【過不及】クワ‥キフ
程度を過ぎたり、程度に達しなかったりすること。多すぎたり足りなかったりすること。過不足。日葡辞書「ヨロヅニクヮフギュウハワルイ」
⇒過不及無し
広辞苑 ページ 4037 での【○株が上がる】単語。