複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (25)
はえ🔗⭐🔉
はえ
海中の暗礁。そね。くり。はえね。
はえ【生え】🔗⭐🔉
はえ【生え】
生えること。万葉集14「柳こそ切れば―すれ」
はえ【映え・栄え】🔗⭐🔉
はえ【映え・栄え】
①はえること。はえるさま。目にうつる感じのよいこと。枕草子83「つゆの―も見えぬに」
②光栄。ほまれ。「―ある伝統」
◇2は、「栄え」と書くことが多い。
はえ【掽】ハヘ🔗⭐🔉
はえ【掽】ハヘ
原木や米俵などを積み重ねたもの。また、それを数えるのにいう。浄瑠璃、心中宵庚申「幾―か庭に五つのたなつ物」
はえ【蠅】ハヘ🔗⭐🔉
はえ【蠅】ハヘ
ハエ目短角亜目に属する昆虫の総称。狭義にはイエバエ科およびその近縁の科のものを指す。触角が太く短い。幼虫はいわゆる「うじ」。伝染病を媒介するものもある。はい。〈[季]夏〉。〈倭名類聚鈔19〉
はえ【南風】🔗⭐🔉
はえ【南風】
(主に中国・四国・九州地方で)みなみかぜ。おだやかな順風。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉
は‐え【破壊】‥ヱ🔗⭐🔉
は‐え【破壊】‥ヱ
やぶれこわれること。やぶりこわすこと。はかい。日本霊異記下「僧の過を説く時は、多くの人の信を―し」
はえ‐い・ず【生え出づ】‥イヅ🔗⭐🔉
はえ‐い・ず【生え出づ】‥イヅ
〔自下二〕
生い出る。出生する。生え出る。発芽する。
はえ‐いろ【映え色】🔗⭐🔉
はえ‐いろ【映え色】
はえた色。つやのある色。新撰六帖6「岩がねはみどりもあけも―の」
はえ‐うち【蠅打ち】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえ‐うち【蠅打ち】ハヘ‥
(→)「はえたたき」に同じ。
はえ‐がしら【蠅頭】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえ‐がしら【蠅頭】ハヘ‥
①矢羽やばねの名。黒みを残して用いたもの。
②(→)疣結いぼゆいに同じ。
③擬餌鉤ぎじばりの一種。釣針の端に蠅の形に模した物を付けたもの。蚊鉤。
⇒はえがしら‐ほぞ【蠅頭枘】
はえがしら‐ほぞ【蠅頭枘】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえがしら‐ほぞ【蠅頭枘】ハヘ‥
〔建〕枘ほぞの根元の周り(胴付どうつき)が材と直角でなく、斜めに切ってあるもの。
⇒はえ‐がしら【蠅頭】
はえ‐かび【蠅黴】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえ‐かび【蠅黴】ハヘ‥
接合菌類のカビで、イエバエなどに寄生して殺す。夏から秋、死んだイエバエの周囲には白色の分生子の輪ができる。
はえ‐かわ・る【生え変わる】‥カハル🔗⭐🔉
はえ‐かわ・る【生え変わる】‥カハル
〔自五〕
前に生えていたものがなくなったあとに、その代りにあたらしく生える。「歯が―・る」
はえ‐き【榱】ハヘキ🔗⭐🔉
はえ‐き【榱】ハヘキ
(→)「たるき(垂木)」に同じ。法華経玄賛平安中期点「梠の音は力挙反、桷ハヘキの端の木ぞ」
はえ‐ぎわ【生え際】‥ギハ🔗⭐🔉
はえ‐ぎわ【生え際】‥ギハ
額・襟首えりくびなどの髪の生えるきわ。
はえ‐ざ【蠅座】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえ‐ざ【蠅座】ハヘ‥
(Musca ラテン)南天の星座。南十字座の南隣。天の川の内にある。
はえ‐さがり【生え下り】🔗⭐🔉
はえ‐さがり【生え下り】
襟足えりあしや揉上もみあげなどの髪が生えさがること。また、その髪。おいさがり。
はえ‐ざむらい【蠅侍】ハヘザムラヒ🔗⭐🔉
はえ‐ざむらい【蠅侍】ハヘザムラヒ
蠅のように取るに足りない武士。蠅武者。
はえ‐じごく【蠅地獄】ハヘヂ‥🔗⭐🔉
はえ‐じごく【蠅地獄】ハヘヂ‥
〔植〕(→)ハエトリグサの別称。
はえ‐すべり【蠅滑り】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえ‐すべり【蠅滑り】ハヘ‥
(蠅がとまろうとしても、すべりおちるという意)はげ頭をあざわらっていう語。慶長見聞集「頭に毛のなきをば、年寄のきんかつぶり、―などとあだ名をいうて、若き人たち笑ふ」
はえ‐たたき【蠅叩き】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえ‐たたき【蠅叩き】ハヘ‥
蠅を打ち殺すのに用いる道具。はえうち。はえとり。〈[季]夏〉
はえ‐ちょう【蠅帳】ハヘチヤウ🔗⭐🔉
はえ‐ちょう【蠅帳】ハヘチヤウ
⇒はいちょう
はえ‐つ・く【蝕え尽く】🔗⭐🔉
はえ‐つ・く【蝕え尽く】
〔自上二〕
日食・月食が皆既となる。推古紀「日―・きたること有り」
大辞林の検索結果 (43)
はえ【岩礁】🔗⭐🔉
はえ [2][0] 【岩礁】
海中の暗礁。陸から海中に突き出している岩礁。
はえ【映え・栄え】🔗⭐🔉
はえ [2] 【映え・栄え】
〔動詞「はえる(映)」の連用形から〕
(1)ほまれ。名誉。「―ある栄冠をかちとる」
(2)はえること。はえるさま。見た目によく見えること。「見ばえ」「出来ばえ」などのように他の名詞の下に付いて「ばえ」と濁り,複合語を作る。
(3)引き立つこと。見ばえがすること。「その君をぞこの女御,大方のよろづのものの―にものし給ふ/栄花(見はてぬ夢)」
はえ【鮠】🔗⭐🔉
はえ [1] 【鮠】
「はや(鮠)」に同じ。
はえ【蠅】🔗⭐🔉
はえ ハヘ [0] 【蠅】
(1)双翅目短角亜目ハエ群に属する昆虫の総称。体は黒または褐色で太く,二枚の透明なはねを有し,触角は短い。幼虫は「うじ」と呼ばれる。イエバエ・クロバエ・ニクバエ・サシバエ・ツェツェバエなど種類が多く,伝染病を媒介したりして人畜に害を与えるものもある。はい。[季]夏。《やれうつな―が手をする足をする/一茶》
(2)とるに足らない者,つまらない者をののしっていう語。「―侍」
は-え【破壊】🔗⭐🔉
は-え ― 【破壊】
〔「え」は呉音〕
こわすこと。こわれること。破壊(ハカイ)。「塔婆を―せんと云ふ悪念をおこし/正統記(武烈)」
【破壊】
〔「え」は呉音〕
こわすこと。こわれること。破壊(ハカイ)。「塔婆を―せんと云ふ悪念をおこし/正統記(武烈)」
 【破壊】
〔「え」は呉音〕
こわすこと。こわれること。破壊(ハカイ)。「塔婆を―せんと云ふ悪念をおこし/正統記(武烈)」
【破壊】
〔「え」は呉音〕
こわすこと。こわれること。破壊(ハカイ)。「塔婆を―せんと云ふ悪念をおこし/正統記(武烈)」
はえ-うち【蠅打ち】🔗⭐🔉
はえ-うち ハヘ― [0][4] 【蠅打ち】
「蠅叩(ハエタタ)き」に同じ。[季]夏。
はえ-かび【蠅黴】🔗⭐🔉
はえ-かび ハヘ― [2] 【蠅黴】
接合菌類ハエカビ科に属するかび。生きているハエ類に寄生し,寄主を殺して体外に菌糸を伸ばして子実層をつくる。ほかの昆虫類につく近似種も多い。
はえ-かわ・る【生え変(わ)る】🔗⭐🔉
はえ-かわ・る ―カハル [4][0] 【生え変(わ)る】 (動ラ五[四])
前にあったものがなくなったあとに,新しいものが生える。「歯が―・る」
はえ-ぎわ【生え際】🔗⭐🔉
はえ-ぎわ ―ギハ [0] 【生え際】
額(ヒタイ)などの髪の生え始めている部分。「―の美しい人」
はえ-ざ【蠅座】🔗⭐🔉
はえ-ざ ハヘ― [0] 【蠅座】
〔(ラテン) Musca〕
南天の星座。日本からは見えない。南十字星の南にあり,天の川の一部を含む。
はえ-じごく【蠅地獄】🔗⭐🔉
はえ-じごく ハヘヂゴク [3] 【蠅地獄】
モウセンゴケ科の多年生食虫植物。北アメリカ東南部原産。葉は根生し円形で縁に長い毛がある。葉面に三対の感覚毛があって,虫などが触れると二つに閉じて捕らえ,消化液を出す。五月頃,白色の五弁花をつける。蠅取草(ハエトリソウ)。
蝿地獄
 [図]
[図]
 [図]
[図]
はえ-たたき【蠅叩き】🔗⭐🔉
はえ-たたき ハヘ― [3] 【蠅叩き】
蠅を打ち殺すための,長い柄のついた道具。はいたたき。はえうち。[季]夏。《―とり彼一打我一打/虚子》
はえ-ちょう【蠅帳】🔗⭐🔉
はえ-ちょう ハヘチヤウ [0] 【蠅帳】
風通しをよくし,また蠅などが入らないように金網あるいは紗(シヤ)を張った,食品を入れておく小さな戸棚。蠅入らず。蠅よけ。はいちょう。[季]夏。
はえ-つ・く【蝕え尽く】🔗⭐🔉
はえ-つ・く 【蝕え尽く】 (動カ上二)
日食・月食で,皆既食となる。「日,―・きたること有り/日本書紀(推古訓)」
はえ-づみ【 積み】🔗⭐🔉
積み】🔗⭐🔉
はえ-づみ ハヘ― [0] 【 積み】
木材を土場(ドバ)や貯木場に積み上げる方式の一。一段目を並列に並べほぼ正方形とし,その上に直角方向に次の段を並べ,それを繰り返して積み上げる。交差積み。はい積み。
→巻立て
積み】
木材を土場(ドバ)や貯木場に積み上げる方式の一。一段目を並列に並べほぼ正方形とし,その上に直角方向に次の段を並べ,それを繰り返して積み上げる。交差積み。はい積み。
→巻立て
 積み】
木材を土場(ドバ)や貯木場に積み上げる方式の一。一段目を並列に並べほぼ正方形とし,その上に直角方向に次の段を並べ,それを繰り返して積み上げる。交差積み。はい積み。
→巻立て
積み】
木材を土場(ドバ)や貯木場に積み上げる方式の一。一段目を並列に並べほぼ正方形とし,その上に直角方向に次の段を並べ,それを繰り返して積み上げる。交差積み。はい積み。
→巻立て
はえ・でる【生え出る】🔗⭐🔉
はえ・でる [0][3] 【生え出る】 (動ダ下一)
はえて出る。発芽する。「土筆(ツクシ)が―・でる」
はえ-どくそう【蠅毒草】🔗⭐🔉
はえ-どくそう ハヘドクサウ [0] 【蠅毒草】
ハエドクソウ科の多年草。高さ約7センチメートル。原野の林内に自生。葉は三角卵形。夏,細長い穂を立て淡紅色の小花をまばらにつける。根を蠅を殺すのに用いた。
はえ-とり【蠅取り】🔗⭐🔉
はえ-とり ハヘ― [0][4][3] 【蠅取り】
(1)ハエをとるための道具。蠅取り器や蠅取り紙,蠅たたきなど。はいとり。
(2)「蠅取蜘蛛(グモ)」の略。
はえとり-がみ【蠅取り紙】🔗⭐🔉
はえとり-がみ ハヘ― [4] 【蠅取り紙】
ハエを取るために,ねばる薬液を塗った紙。天井からつるすテープ状にしたものは蠅取りリボンという。はえとりし。[季]夏。
はえとり-ぐも【蠅取蜘蛛・蠅虎】🔗⭐🔉
はえとり-ぐも ハヘ― [5] 【蠅取蜘蛛・蠅虎】
真正クモ目ハエトリグモ科のクモの総称。小形のクモ類で体は扁平。目は三列に並び,前列中央の一対は巨大。網を張らず,壁面などを歩行し,跳躍力が強く,巧みにハエなどの小昆虫を捕らえる。日本では約八〇種が知られる。[季]夏。
はえとり-そう【蠅取草】🔗⭐🔉
はえとり-そう ハヘ―サウ [0] 【蠅取草】
ハエジゴクの別名。
はえとり-だけ【蠅取茸】🔗⭐🔉
はえとり-だけ ハヘ― [4] 【蠅取茸】
テングタケ・ベニテングタケなどの俗称。その毒液がハエを殺すので,この名がある。
はえとり-なでしこ【蠅取撫子】🔗⭐🔉
はえとり-なでしこ ハヘ― [6] 【蠅取撫子】
ムシトリナデシコの別名。
はえ-なわ【延縄】🔗⭐🔉
はえ-なわ ハヘナハ [0] 【延縄】
釣り漁具の一。一本の長い幹縄に適当な間隔で,浮きを結ぶ浮縄と釣り針のついた多数の枝縄をつけたもの。それぞれの釣り針に餌(エサ)をつけ,海面下に浮かせあるいは海底に沈めて張る,浮き延縄と底延縄がある。のべなわ。ながなわ。「―漁業」
延縄
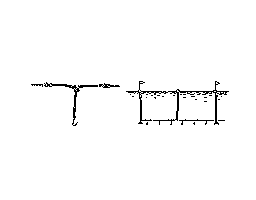 [図]
[図]
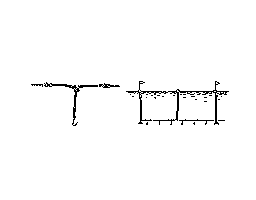 [図]
[図]
はえ-ぬき【生え抜き】🔗⭐🔉
はえ-ぬき [0] 【生え抜き】
(1)その土地に生まれ,その土地で育つこと。生粋(キツスイ)。「―の江戸っ子」
(2)団体・組織などにはじめから所属して現在に至っていること。「―の社員」
はえ-ぬ・く【生え抜く】🔗⭐🔉
はえ-ぬ・く 【生え抜く】 (動カ四)
(1)その土地で生まれそこで成長する。「吉原で―・いたやうに口を利くから/洒落本・南江駅話」
(2)はえて上に突き抜ける。「二王立ちに立たるは,金輪際より忽ちに―・いたるがごとく也/浄瑠璃・嫗山姥」
はえ-の-こ【蠅の子】🔗⭐🔉
はえ-の-こ ハヘ― [0] 【蠅の子】
ハエの幼虫。うじ。
はえばえ・し【映え映えし・栄え栄えし】🔗⭐🔉
はえばえ・し 【映え映えし・栄え栄えし】 (形シク)
(1)非常にはえて見える。はなやかで見ばえがする。「内わたりにも墨染にて,―・しき事もなし/栄花(松の下枝)」
(2)光栄である。面目が立つ。「講師も―・しく覚ゆるなるべし/枕草子 33」
はえばる【南風原】🔗⭐🔉
はえばる 【南風原】
沖縄県島尻郡,沖縄島南部の町。サトウキビのほか琉球絣(リユウキユウガスリ)を特産。
ハエマンサス (ラテン) Haemanthus
(ラテン) Haemanthus 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ハエマンサス [3]  (ラテン) Haemanthus
(ラテン) Haemanthus ヒガンバナ科ハエマンサス属の球根植物。南アフリカから熱帯アフリカにかけて約五〇種が分布。葉はオモトに似る。日本では長い白色のおしべが密集して化粧用の刷毛(ハケ)のような観を呈するマユハケオモト,おしべの長い赤色六弁花を散形につけるセンコウハナビなどが栽培される。
ヒガンバナ科ハエマンサス属の球根植物。南アフリカから熱帯アフリカにかけて約五〇種が分布。葉はオモトに似る。日本では長い白色のおしべが密集して化粧用の刷毛(ハケ)のような観を呈するマユハケオモト,おしべの長い赤色六弁花を散形につけるセンコウハナビなどが栽培される。
 (ラテン) Haemanthus
(ラテン) Haemanthus ヒガンバナ科ハエマンサス属の球根植物。南アフリカから熱帯アフリカにかけて約五〇種が分布。葉はオモトに似る。日本では長い白色のおしべが密集して化粧用の刷毛(ハケ)のような観を呈するマユハケオモト,おしべの長い赤色六弁花を散形につけるセンコウハナビなどが栽培される。
ヒガンバナ科ハエマンサス属の球根植物。南アフリカから熱帯アフリカにかけて約五〇種が分布。葉はオモトに似る。日本では長い白色のおしべが密集して化粧用の刷毛(ハケ)のような観を呈するマユハケオモト,おしべの長い赤色六弁花を散形につけるセンコウハナビなどが栽培される。
はえ-よけ【蠅除け】🔗⭐🔉
はえ-よけ ハヘ― [0][4] 【蠅除け】
ハエをよけたり追い払ったりすること。またそれに用いる道具。はいよけ。[季]夏。
は・える【生える】🔗⭐🔉
は・える [2] 【生える】 (動ア下一)[文]ヤ下二 は・ゆ
(1)草木の芽・枝などが(わずかに)出る。生ずる。「雑草が―・える」「青かびが―・える」「生ひををれる川藻もぞ枯るれば―・ゆる/万葉 196」
(2)動物の体から毛・歯・角などが生じる。「赤ちゃんに歯が―・える」「ひげが―・える」
[慣用] 根が―/羽が生えたよう
は・える【映える・栄える】🔗⭐🔉
は・える [2] 【映える・栄える】 (動ア下一)[文]ヤ下二 は・ゆ
(1)明るい光に照らされて輝く。あざやかに見える。《映》「朝日に―・える富士山」
(2)周囲のものとの対比によって一段と美しさが目立つ。引き立って見える。《映》「紺碧の海に白い船体が―・える」
は・える【 へる】🔗⭐🔉
へる】🔗⭐🔉
は・える ハヘル 【 へる】 (動ハ下一)
〔近世語〕
俵や木材などをきれいに形よく積み上げる。「杉なりの俵物広庭に幾所か―・へて/浮世草子・商人軍配団」
〔下二段動詞「はう(延)」の下一段化したものからか〕
へる】 (動ハ下一)
〔近世語〕
俵や木材などをきれいに形よく積み上げる。「杉なりの俵物広庭に幾所か―・へて/浮世草子・商人軍配団」
〔下二段動詞「はう(延)」の下一段化したものからか〕
 へる】 (動ハ下一)
〔近世語〕
俵や木材などをきれいに形よく積み上げる。「杉なりの俵物広庭に幾所か―・へて/浮世草子・商人軍配団」
〔下二段動詞「はう(延)」の下一段化したものからか〕
へる】 (動ハ下一)
〔近世語〕
俵や木材などをきれいに形よく積み上げる。「杉なりの俵物広庭に幾所か―・へて/浮世草子・商人軍配団」
〔下二段動詞「はう(延)」の下一段化したものからか〕
は-えん【巴猿】🔗⭐🔉
は-えん ― ン 【巴猿】
〔中国湖北省巴東県地方の巴峡には猿が多くいたことから〕
峡谷に鳴く猿。また,その哀愁を帯びた鳴き声。「―三叫,暁行人の裳を霑ほす/和漢朗詠(雑)」
ン 【巴猿】
〔中国湖北省巴東県地方の巴峡には猿が多くいたことから〕
峡谷に鳴く猿。また,その哀愁を帯びた鳴き声。「―三叫,暁行人の裳を霑ほす/和漢朗詠(雑)」
 ン 【巴猿】
〔中国湖北省巴東県地方の巴峡には猿が多くいたことから〕
峡谷に鳴く猿。また,その哀愁を帯びた鳴き声。「―三叫,暁行人の裳を霑ほす/和漢朗詠(雑)」
ン 【巴猿】
〔中国湖北省巴東県地方の巴峡には猿が多くいたことから〕
峡谷に鳴く猿。また,その哀愁を帯びた鳴き声。「―三叫,暁行人の裳を霑ほす/和漢朗詠(雑)」
はえ【栄えある】(和英)🔗⭐🔉
はえなわ【延縄】(和英)🔗⭐🔉
はえなわ【延縄】
a longline.延縄漁業 a longline fishing.延縄漁船 a longliner.
はえる【生える】(和英)🔗⭐🔉
はえる【映える】(和英)🔗⭐🔉
はえる【映える】
[かがやく]shine;→英和
be bright;[引き立つ]look attractive;be set off.
広辞苑+大辞林に「ハエ」で始まるの検索結果。もっと読み込む