複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (50)
はえ🔗⭐🔉
はえ
海中の暗礁。そね。くり。はえね。
はえ【生え】🔗⭐🔉
はえ【生え】
生えること。万葉集14「柳こそ切れば―すれ」
はえ【映え・栄え】🔗⭐🔉
はえ【映え・栄え】
①はえること。はえるさま。目にうつる感じのよいこと。枕草子83「つゆの―も見えぬに」
②光栄。ほまれ。「―ある伝統」
◇2は、「栄え」と書くことが多い。
はえ【掽】ハヘ🔗⭐🔉
はえ【掽】ハヘ
原木や米俵などを積み重ねたもの。また、それを数えるのにいう。浄瑠璃、心中宵庚申「幾―か庭に五つのたなつ物」
はえ【蠅】ハヘ🔗⭐🔉
はえ【蠅】ハヘ
ハエ目短角亜目に属する昆虫の総称。狭義にはイエバエ科およびその近縁の科のものを指す。触角が太く短い。幼虫はいわゆる「うじ」。伝染病を媒介するものもある。はい。〈[季]夏〉。〈倭名類聚鈔19〉
はえ【南風】🔗⭐🔉
はえ【南風】
(主に中国・四国・九州地方で)みなみかぜ。おだやかな順風。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉
は‐え【破壊】‥ヱ🔗⭐🔉
は‐え【破壊】‥ヱ
やぶれこわれること。やぶりこわすこと。はかい。日本霊異記下「僧の過を説く時は、多くの人の信を―し」
はえ‐い・ず【生え出づ】‥イヅ🔗⭐🔉
はえ‐い・ず【生え出づ】‥イヅ
〔自下二〕
生い出る。出生する。生え出る。発芽する。
はえ‐いろ【映え色】🔗⭐🔉
はえ‐いろ【映え色】
はえた色。つやのある色。新撰六帖6「岩がねはみどりもあけも―の」
はえ‐うち【蠅打ち】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえ‐うち【蠅打ち】ハヘ‥
(→)「はえたたき」に同じ。
はえ‐がしら【蠅頭】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえ‐がしら【蠅頭】ハヘ‥
①矢羽やばねの名。黒みを残して用いたもの。
②(→)疣結いぼゆいに同じ。
③擬餌鉤ぎじばりの一種。釣針の端に蠅の形に模した物を付けたもの。蚊鉤。
⇒はえがしら‐ほぞ【蠅頭枘】
はえがしら‐ほぞ【蠅頭枘】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえがしら‐ほぞ【蠅頭枘】ハヘ‥
〔建〕枘ほぞの根元の周り(胴付どうつき)が材と直角でなく、斜めに切ってあるもの。
⇒はえ‐がしら【蠅頭】
はえ‐かび【蠅黴】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえ‐かび【蠅黴】ハヘ‥
接合菌類のカビで、イエバエなどに寄生して殺す。夏から秋、死んだイエバエの周囲には白色の分生子の輪ができる。
はえ‐かわ・る【生え変わる】‥カハル🔗⭐🔉
はえ‐かわ・る【生え変わる】‥カハル
〔自五〕
前に生えていたものがなくなったあとに、その代りにあたらしく生える。「歯が―・る」
はえ‐き【榱】ハヘキ🔗⭐🔉
はえ‐き【榱】ハヘキ
(→)「たるき(垂木)」に同じ。法華経玄賛平安中期点「梠の音は力挙反、桷ハヘキの端の木ぞ」
はえ‐ぎわ【生え際】‥ギハ🔗⭐🔉
はえ‐ぎわ【生え際】‥ギハ
額・襟首えりくびなどの髪の生えるきわ。
はえ‐ざ【蠅座】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえ‐ざ【蠅座】ハヘ‥
(Musca ラテン)南天の星座。南十字座の南隣。天の川の内にある。
はえ‐さがり【生え下り】🔗⭐🔉
はえ‐さがり【生え下り】
襟足えりあしや揉上もみあげなどの髪が生えさがること。また、その髪。おいさがり。
はえ‐ざむらい【蠅侍】ハヘザムラヒ🔗⭐🔉
はえ‐ざむらい【蠅侍】ハヘザムラヒ
蠅のように取るに足りない武士。蠅武者。
はえ‐じごく【蠅地獄】ハヘヂ‥🔗⭐🔉
はえ‐じごく【蠅地獄】ハヘヂ‥
〔植〕(→)ハエトリグサの別称。
はえ‐すべり【蠅滑り】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえ‐すべり【蠅滑り】ハヘ‥
(蠅がとまろうとしても、すべりおちるという意)はげ頭をあざわらっていう語。慶長見聞集「頭に毛のなきをば、年寄のきんかつぶり、―などとあだ名をいうて、若き人たち笑ふ」
はえ‐たたき【蠅叩き】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえ‐たたき【蠅叩き】ハヘ‥
蠅を打ち殺すのに用いる道具。はえうち。はえとり。〈[季]夏〉
はえ‐ちょう【蠅帳】ハヘチヤウ🔗⭐🔉
はえ‐ちょう【蠅帳】ハヘチヤウ
⇒はいちょう
はえ‐つ・く【蝕え尽く】🔗⭐🔉
はえ‐つ・く【蝕え尽く】
〔自上二〕
日食・月食が皆既となる。推古紀「日―・きたること有り」
はえ・でる【生え出る】🔗⭐🔉
はえ・でる【生え出る】
〔自下一〕
生えて出る。発芽する。
はえ‐どくそう【蠅毒草】ハヘ‥サウ🔗⭐🔉
はえ‐どくそう【蠅毒草】ハヘ‥サウ
ハエドクソウ科の多年草。林縁などに自生。高さ数十センチメートル。葉は卵状楕円形。夏、淡紫色の小唇形花を穂状に配列。根の煎汁は蠅取紙にしませて蠅を殺すのに有効。
はえ‐どまり【生え止り】🔗⭐🔉
はえ‐どまり【生え止り】
自然に生えたままでそれ以上は生えないこと。手入れをしなくとも、それよりは生えないこと。好色一代女1「額はわざとならず、自然じねんの―」
はえ‐とり【蠅取】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえ‐とり【蠅取】ハヘ‥
①蠅を取ること。また、それに使う道具。〈[季]夏〉
②「はえとりぐも」の略。
⇒はえとり‐がみ【蠅取紙】
⇒はえとり‐ぐさ【蠅取草】
⇒はえとり‐ぐも【蠅捕蜘蛛】
⇒はえとり‐たけ【蠅取茸】
⇒はえとり‐なでしこ【蠅取撫子】
⇒はえとり‐むし【蠅取虫】
はえとり‐がみ【蠅取紙】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえとり‐がみ【蠅取紙】ハヘ‥
とまった蠅がはりつくように、粘着性のある薬品を塗った紙。天井から釣り下げたりテーブルの上に広げたりして用いる。
⇒はえ‐とり【蠅取】
はえとり‐ぐさ【蠅取草】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえとり‐ぐさ【蠅取草】ハヘ‥
モウセンゴケ科の多年生食虫植物。北米カロライナ地方などの原産。葉は軍扇状の葉身と扁平な葉柄とから成る。葉の上面に敏感な3本の糸状突起があり、小虫がこの毛に触れると、葉身の両側がたたまれてその小虫を捕らえ消化吸収する。初夏、純白色の花を開く。観賞用に栽培。ハエジゴク。〈[季]夏〉
はえとりぐさ
 ハエトリグサ
提供:OPO
ハエトリグサ
提供:OPO
 ⇒はえ‐とり【蠅取】
⇒はえ‐とり【蠅取】
 ハエトリグサ
提供:OPO
ハエトリグサ
提供:OPO
 ⇒はえ‐とり【蠅取】
⇒はえ‐とり【蠅取】
はえとり‐ぐも【蠅捕蜘蛛】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえとり‐ぐも【蠅捕蜘蛛】ハヘ‥
ハエトリグモ科のクモの総称。体長2〜20ミリメートル。灰色・緑色・黄褐色などで腹部にさまざまな模様がある。前方中央の二つの眼は大きく発達。網を張らず、巧みに跳び、ハエなどを捕食。日本に100種以上生息する。
はえとりぐも
 ⇒はえ‐とり【蠅取】
⇒はえ‐とり【蠅取】
 ⇒はえ‐とり【蠅取】
⇒はえ‐とり【蠅取】
はえとり‐たけ【蠅取茸】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえとり‐たけ【蠅取茸】ハヘ‥
〔植〕(その液汁が蠅を殺すからいう)(→)テングタケの別称。
⇒はえ‐とり【蠅取】
はえとり‐なでしこ【蠅取撫子】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえとり‐なでしこ【蠅取撫子】ハヘ‥
(→)ムシトリナデシコの別称。〈[季]夏〉
⇒はえ‐とり【蠅取】
はえとり‐むし【蠅取虫】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえとり‐むし【蠅取虫】ハヘ‥
(→)カマキリの別称。
⇒はえ‐とり【蠅取】
はえ‐なわ【延縄】ハヘナハ🔗⭐🔉
はえ‐なわ【延縄】ハヘナハ
釣漁具の一種。1条の長い幹縄に、適当な間隔を置いて多くの釣糸を取り付け、それぞれに鉤はりをつけたもの。なわづり。のべなわ。「―漁業」→浮延縄うきはえなわ
延縄


はえ‐ぬき【生え抜き】🔗⭐🔉
はえ‐ぬき【生え抜き】
その土地に生まれて、ずっとそこで成長したこと。また、生まれてからずっとそうであること、はじめから続けてその会社・部署に勤務していることなどにいう。きっすい。ねぬき。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―の念者ぢや」。「―の江戸っ子」「―の社員」
はえ‐の‐こ【蠅の子】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえ‐の‐こ【蠅の子】ハヘ‥
ハエの幼虫。うじ。
はえ‐ばえ・し【映映し】🔗⭐🔉
はえ‐ばえ・し【映映し】
〔形シク〕
非常に映えている。はなやかに見ばえがする。栄華物語松下枝「墨染にて―・しきこともなし」
○這えば立て立てば歩めの親心はえばたてたてばあゆめのおやごころ
幼児の成長を待ちに待つ親心をいう。
⇒は・う【這う・延う】
○這えば立て立てば歩めの親心はえばたてたてばあゆめのおやごころ🔗⭐🔉
○這えば立て立てば歩めの親心はえばたてたてばあゆめのおやごころ
幼児の成長を待ちに待つ親心をいう。
⇒は・う【這う・延う】
はえ‐はらい【蠅払い】ハヘハラヒ
蠅を追い払うのに用いるもの。払子ほっす。また、武具の一つ。
はえ‐まいり【蠅参り】ハヘマヰリ
蠅が馬の尾に付いて行くように、道者の後に付いて伊勢参りをすること。また、その人。
はえ‐むし【蠅虫】ハヘ‥
①蠅と虫。また、蠅。
②人を卑しめていう語。取るに足りない人。うじむし。「ほととぎす―めらもよつく聞け」(一茶)
はえ‐もく【蠅目】ハヘ‥
昆虫綱の一目。体は総じて小形。4枚の翅のうち後翅2枚は縮小して平均棍となっている。複眼は一般に大きい。口器は吸い型またはなめ型。完全変態し、幼虫は「うじ」や「ぼうふら」。世界に約25万種と推定される。双翅類。
はえ‐もの【生え物】
地上に生えたもの。草木などの類。
はえ‐やま【生え山】
草木の生えた山。↔禿山はげやま
パエリア【paella スペイン】
⇒パエーリャ
は・える【生える】
〔自下一〕[文]は・ゆ(下二)
植物や毛などが、内部から外面に出て育つ。芽が出る。生じる。万葉集2「打橋に生ひををれる川藻もぞ枯るれば―・ゆる」。「かびが―・える」「歯が―・える」
は・える【映える・栄える】
〔自下一〕[文]は・ゆ(下二)
(「生える」と同源)
①光を映して美しく輝く。反映する。源氏物語槿「をかしげなる姿、頭つきども月に―・えて」。「夕日に―・える山」
②(他の事物のために)目に立つようになる。勢いを得る。盛んになる。源氏物語常夏「まことや、暮れにも参りこむと思う給へ立つは、厭ふに―・ゆるにや」。「話が―・えない」
③周囲のものとの映り具合がよい。引き立つ。「このネクタイがよく―・える」
④立派に見える。目立つ。「―・えない男」
◇「栄」は、4で使うことが多い。
はえ‐わた・る【映え渡る】
〔自四〕
すみずみまではえる。ことごとくはえる。栄華物語殿上花見「―・りをかしう見ゆ」
は‐えん【巴猿】‥ヱン
(中国湖北省巴東県地方の渓流、巴峡の付近に猿が多いのでいう)巴峡の猿。山の峡谷に鳴く猿。
ば‐えん【馬煙】
⇒うまけむり。日葡辞書「バエンヲタテテタタカウ」
ば‐えん【馬遠】‥ヱン
南宋中期の画家。号は遥父、字は欽山。光宗・寧宗に仕え、画院の待詔となる。夏珪かけいと共に南宋の院体山水画の代表作家として、室町時代の画家に大きな影響を与えた。
はお【這ほ】ハホ
(上代東国方言)動詞「這ふ(連体形)」の訛。万葉集20「足柄の峰―雲を見とと偲はね」
ハオ【好】
(中国語)「好い」「よろしい」の意。
パオ【包】
(中国語)(→)ゲルに同じ。
は‐おう【覇王】‥ワウ
①覇者と王者。覇道と王道。王覇。
②諸侯を統御し天下を治める者。覇者の長。
は‐おく【破屋】‥ヲク
こわれた家。あばらや。廃屋。
ば‐おじ【姥爺】‥オヂ
(ウバオヂの転。山陰地方で)老夫婦。うばぐじ。
パオズ【包子】
(中国語)肉や餡などを入れた饅頭まんじゅう。中華饅頭。
バオ‐ダイ【Bao Dai・保大】
ベトナムのグエン(阮)朝第13代皇帝。1925年即位、第二次大戦直後退位。ベトナム民主共和国独立に対抗し、49年ベトナム国元首、55年の国民投票に敗れて亡命。(1913〜1997)
は‐おち【端落・羽落】
茶釜の腰を回る煙返し(端)を打ち欠いたようにしたものの称。端落釜。
はおち‐づき【葉落月】
陰暦8月の異称。
は‐おと【刃音】
斬り合う刀剣の刃の音。
は‐おと【羽音】
①鳥の両翼を打つ音。虫の飛ぶ音。万葉集12「葦辺ゆく鴨の―」。「―を立てる」
②風を切って飛ぶ矢羽やばねの音。
は‐おと【葉音】
葉が触れ合って発する音。
パオトウ【包頭】
(Baotou; Paot‘ou)中国内モンゴル自治区中部、黄河中流北岸の河港都市。三つの鉄道幹線の交点に当たり、中国北西部の物産の主要集散地、また鉄工業を中心とした工業都市。人口167万1千(2000)。ほうとう。
バオバブ【baobab】
パンヤ科の巨木。アフリカ内陸部とマダガスカル島、オーストラリアのサバンナに生ずる。幹が肥大して徳利とっくり状になるので有名。高さ十数メートル、幹の太い部分は直径10メートルになる。密に分枝して乾季に落葉、老樹の幹は空洞化する。
バオバブ
 ハオユー【蠔油】
(中国語)(→)オイスター‐ソースに同じ。
は‐おり【羽織】
①長着の上におおい着る、襟を折った短い衣。
②「はおりおとし」の略。
⇒はおり‐おとし【羽織落し】
⇒はおり‐げいしゃ【羽織芸者】
⇒はおり‐ごろ【羽織ごろ】
⇒はおり‐はかま【羽織袴】
⇒はおり‐ひも【羽織紐】
⇒はおり‐むし【羽織虫】
⇒はおり‐りょうし【羽織漁師】
はおり‐おとし【羽織落し】
歌舞伎演出用語。着ている羽織が知らずしらず脱げ落ちるしぐさ。魂の抜けた町人の有様を表現する。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐げいしゃ【羽織芸者】
(羽織を着て宴席に出たのでいう)(→)辰巳芸者のこと。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐ごろ【羽織ごろ】
立派な服装をしていながら、ごろつきのように恐喝を行う者。内田魯庵、社会百面相「実業家といふと聞えが好いが近頃の奴は―の方に近い」
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐はかま【羽織袴】
①羽織と袴。
②羽織と袴とを身につけること。転じて、あらたまった服装。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐ひも【羽織紐】
羽織の胸元が開かないように結ぶ紐。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐むし【羽織虫】
有鬚ゆうしゅ動物門ハオリムシ綱に属する長虫。直径1〜数センチメートルで、殻蓋部、羽織部(前体)、栄養体部(胴部)、分節する後体からなり、長さ0.5〜数メートルのキチン質の管の中に棲む。硫化物を栄養に変える化学合成細菌と共生する。ガラパゴス沖深海の熱水鉱床ではじめて採集された。世界各地の浅海から深海まで、熱水あるいは冷水湧出域で15種ほどが知られている。管虫。チューブ‐ワーム。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐りょうし【羽織漁師】‥レフ‥
自らは漁船に乗らない漁業経営者をいう。網元・網主など。
⇒は‐おり【羽織】
は‐お・る【羽織る】
〔他五〕
(「羽織」を動詞化した語)着物の上にうちかけて着る。森鴎外、雁「細帯一つでねんねこ半纏を―・つて」
はおん‐きごう【ハ音記号】‥ガウ
〔音〕(C-clef)五線譜で使われる音部記号の一つで、主として中音域の記譜に用いられる。Cの字を装飾化したもの。記号の中心でハ音(C)の位置を示し、第1線に置いた場合はソプラノ記号、第3線に置いた場合はアルト記号、第4線に置いた場合はテノール記号として用いる。→音部記号
ハ音記号
ハオユー【蠔油】
(中国語)(→)オイスター‐ソースに同じ。
は‐おり【羽織】
①長着の上におおい着る、襟を折った短い衣。
②「はおりおとし」の略。
⇒はおり‐おとし【羽織落し】
⇒はおり‐げいしゃ【羽織芸者】
⇒はおり‐ごろ【羽織ごろ】
⇒はおり‐はかま【羽織袴】
⇒はおり‐ひも【羽織紐】
⇒はおり‐むし【羽織虫】
⇒はおり‐りょうし【羽織漁師】
はおり‐おとし【羽織落し】
歌舞伎演出用語。着ている羽織が知らずしらず脱げ落ちるしぐさ。魂の抜けた町人の有様を表現する。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐げいしゃ【羽織芸者】
(羽織を着て宴席に出たのでいう)(→)辰巳芸者のこと。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐ごろ【羽織ごろ】
立派な服装をしていながら、ごろつきのように恐喝を行う者。内田魯庵、社会百面相「実業家といふと聞えが好いが近頃の奴は―の方に近い」
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐はかま【羽織袴】
①羽織と袴。
②羽織と袴とを身につけること。転じて、あらたまった服装。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐ひも【羽織紐】
羽織の胸元が開かないように結ぶ紐。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐むし【羽織虫】
有鬚ゆうしゅ動物門ハオリムシ綱に属する長虫。直径1〜数センチメートルで、殻蓋部、羽織部(前体)、栄養体部(胴部)、分節する後体からなり、長さ0.5〜数メートルのキチン質の管の中に棲む。硫化物を栄養に変える化学合成細菌と共生する。ガラパゴス沖深海の熱水鉱床ではじめて採集された。世界各地の浅海から深海まで、熱水あるいは冷水湧出域で15種ほどが知られている。管虫。チューブ‐ワーム。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐りょうし【羽織漁師】‥レフ‥
自らは漁船に乗らない漁業経営者をいう。網元・網主など。
⇒は‐おり【羽織】
は‐お・る【羽織る】
〔他五〕
(「羽織」を動詞化した語)着物の上にうちかけて着る。森鴎外、雁「細帯一つでねんねこ半纏を―・つて」
はおん‐きごう【ハ音記号】‥ガウ
〔音〕(C-clef)五線譜で使われる音部記号の一つで、主として中音域の記譜に用いられる。Cの字を装飾化したもの。記号の中心でハ音(C)の位置を示し、第1線に置いた場合はソプラノ記号、第3線に置いた場合はアルト記号、第4線に置いた場合はテノール記号として用いる。→音部記号
ハ音記号
 はか【計・量】
①稲を植えたり刈ったり、また茅を刈る時などの範囲や量。また、稲を植えた列と列との間をいう。万葉集10「秋の田の吾が苅りばかの過ぎぬれば」
②めあて。あてど。はかり。後撰和歌集恋「いづこを―と君がとはまし」
③(「捗」とも書く)仕事の進み具合。やり終えた量。
⇒計が行く
はか【墓】
①死者の遺骸や遺骨を葬った所。つか。おくつき。墳墓。仁徳紀「田道が―を掘る」。「―に参る」
②墓碑ぼひ。墓石。「―を建てる」
は‐か【破瓜】‥クワ
①(「瓜」の字を二分すると、二つの「八」の字の形となるからいう)
㋐女性の16歳の称。思春期の年ごろ。「―期」
㋑(8の8倍は64であるからいう)男性の64歳の称。
②女性の処女膜の破れること。
は‐か【薄荷】
⇒はっか。〈倭名類聚鈔16〉
はか
〔助詞〕
(「ほか(外)」の転。下に打消の語を伴う)…よりほか。…ほか。…しか。浄瑠璃、長町女腹切「私をお袋と―云ひませぬ」
はが【
はか【計・量】
①稲を植えたり刈ったり、また茅を刈る時などの範囲や量。また、稲を植えた列と列との間をいう。万葉集10「秋の田の吾が苅りばかの過ぎぬれば」
②めあて。あてど。はかり。後撰和歌集恋「いづこを―と君がとはまし」
③(「捗」とも書く)仕事の進み具合。やり終えた量。
⇒計が行く
はか【墓】
①死者の遺骸や遺骨を葬った所。つか。おくつき。墳墓。仁徳紀「田道が―を掘る」。「―に参る」
②墓碑ぼひ。墓石。「―を建てる」
は‐か【破瓜】‥クワ
①(「瓜」の字を二分すると、二つの「八」の字の形となるからいう)
㋐女性の16歳の称。思春期の年ごろ。「―期」
㋑(8の8倍は64であるからいう)男性の64歳の称。
②女性の処女膜の破れること。
は‐か【薄荷】
⇒はっか。〈倭名類聚鈔16〉
はか
〔助詞〕
(「ほか(外)」の転。下に打消の語を伴う)…よりほか。…ほか。…しか。浄瑠璃、長町女腹切「私をお袋と―云ひませぬ」
はが【 ・黐
・黐 】
竹串や木の枝・藁などに黐もちをぬり囮おとりを用いて鳥などを捕るもの。はご。〈倭名類聚鈔15〉
はが【芳賀】
姓氏の一つ。
⇒はが‐やいち【芳賀矢一】
ばか【馬鹿・莫迦】
(梵語moha(慕何)、すなわち無知の意からか。古くは僧侶の隠語。「馬鹿」は当て字)
①おろかなこと。社会的常識に欠けていること。また、その人。愚。愚人。あほう。〈文明本節用集〉。「専門―」
②取るに足りないつまらないこと。無益なこと。また、とんでもないこと。「―を言うな」「―なことをしたものだ」
③役に立たないこと。「蝶番ちょうつがいが―で戸が締まらない」
④馬鹿貝の略。夏目漱石、草枕「貝の殻は牡蠣かきか、―か、馬刀貝まてがいか」
⑤(接頭語的に)度はずれて、の意。「―ていねい」「―さわぎ」「―陽気」
→馬鹿に
⇒馬鹿と鋏は使いよう
⇒馬鹿にする
⇒馬鹿に付ける薬は無い
⇒馬鹿にならない
⇒馬鹿になる
⇒馬鹿の一つ覚え
⇒馬鹿は死ななきゃ直らない
⇒馬鹿も休み休み言え
⇒馬鹿を見る
ハガード【Henry Rider Haggard】
イギリスの冒険小説家。移民・農業政策の著作もある。作「ソロモン王の洞窟」「洞窟の女王」など。(1856〜1925)
はか‐あな【墓穴】
屍体や遺骨を葬る穴。つかあな。
ばか‐あな【馬鹿穴】
ボルトを通す穴で、直径をボルトより多少大きくしたもの。
は‐かい【破戒】
戒を破ること。受戒した者が戒法に違うこと。「―僧」↔持戒。
⇒はかい‐むざん【破戒無慙】
⇒破戒の出家は牛に生るる
はかい【破戒】
長編小説。島崎藤村作。1906年(明治39)刊。被差別部落出身の小学校教師瀬川丑松うしまつが、父の戒めを破って自分の素姓を告白し、周囲の因襲と戦う苦悩を描く。日本自然主義文学の先駆。
→文献資料[破戒]
は‐かい【破潰】‥クワイ
破れついえること。破りくずすこと。
は‐かい【破壊】‥クワイ
うちこわすこと。うちこわされること。こわれること。「建物を―する」
⇒はかい‐おうりょく【破壊応力】
⇒はかいかつどう‐ぼうし‐ほう【破壊活動防止法】
⇒はかい‐しけん【破壊試験】
⇒はかい‐てき【破壊的】
⇒はかい‐りょく【破壊力】
は‐がい【羽交】‥ガヒ
①鳥の左右の翼のうちちがうところ。万葉集1「葦辺行く鴨の―に霜零ふりて」
②鳥のはね。つばさ。〈日葡辞書〉
⇒はがい‐がさね【羽交重ね】
⇒はがい‐じめ【羽交締め】
は‐がい・い【歯痒い】
〔形〕
ハガユイの転。
はかい‐おうりょく【破壊応力】‥クワイ‥
物体が破壊せずにもちこたえられる最大の応力。破壊強さ。極限強さ。
⇒は‐かい【破壊】
はがい‐がさね【羽交重ね】‥ガヒ‥
鳥が羽をかさねること。また、鳥が羽をかさね合うように、あちこちから集まりかさなること。
⇒は‐がい【羽交】
はかいかつどう‐ぼうし‐ほう【破壊活動防止法】‥クワイクワツ‥バウ‥ハフ
暴力主義的破壊活動を行なった団体に対する規制措置を定めるとともに、その種の活動に関する団体等規正令の刑罰規定を補整した法律。治安立法の一種で、1952年公布・施行。破防法。→団体等規正令。
⇒は‐かい【破壊】
はか‐いし【墓石】
墓じるしの石。ぼせき。
はかい‐しけん【破壊試験】‥クワイ‥
①材料試験の一種。材料から採取した試験片または材料そのものに破壊するまで荷重を加え、材料の靱性・強度その他の機械的諸性質を検査するもの。
②機械などを、それが破壊するような厳しい条件で試験すること。
⇒は‐かい【破壊】
はがい‐じめ【羽交締め】‥ガヒ‥
①相手の後ろから両手を腋の下へ通し、襟首の所で組み合わせて、相手が動けないようにすること。
②両腕を背後に交差させてしばること。
⇒は‐がい【羽交】
はかい‐てき【破壊的】‥クワイ‥
物事をこわしてしまうほどに、強力で荒っぽいさま。「―言動」↔建設的。
⇒は‐かい【破壊】
】
竹串や木の枝・藁などに黐もちをぬり囮おとりを用いて鳥などを捕るもの。はご。〈倭名類聚鈔15〉
はが【芳賀】
姓氏の一つ。
⇒はが‐やいち【芳賀矢一】
ばか【馬鹿・莫迦】
(梵語moha(慕何)、すなわち無知の意からか。古くは僧侶の隠語。「馬鹿」は当て字)
①おろかなこと。社会的常識に欠けていること。また、その人。愚。愚人。あほう。〈文明本節用集〉。「専門―」
②取るに足りないつまらないこと。無益なこと。また、とんでもないこと。「―を言うな」「―なことをしたものだ」
③役に立たないこと。「蝶番ちょうつがいが―で戸が締まらない」
④馬鹿貝の略。夏目漱石、草枕「貝の殻は牡蠣かきか、―か、馬刀貝まてがいか」
⑤(接頭語的に)度はずれて、の意。「―ていねい」「―さわぎ」「―陽気」
→馬鹿に
⇒馬鹿と鋏は使いよう
⇒馬鹿にする
⇒馬鹿に付ける薬は無い
⇒馬鹿にならない
⇒馬鹿になる
⇒馬鹿の一つ覚え
⇒馬鹿は死ななきゃ直らない
⇒馬鹿も休み休み言え
⇒馬鹿を見る
ハガード【Henry Rider Haggard】
イギリスの冒険小説家。移民・農業政策の著作もある。作「ソロモン王の洞窟」「洞窟の女王」など。(1856〜1925)
はか‐あな【墓穴】
屍体や遺骨を葬る穴。つかあな。
ばか‐あな【馬鹿穴】
ボルトを通す穴で、直径をボルトより多少大きくしたもの。
は‐かい【破戒】
戒を破ること。受戒した者が戒法に違うこと。「―僧」↔持戒。
⇒はかい‐むざん【破戒無慙】
⇒破戒の出家は牛に生るる
はかい【破戒】
長編小説。島崎藤村作。1906年(明治39)刊。被差別部落出身の小学校教師瀬川丑松うしまつが、父の戒めを破って自分の素姓を告白し、周囲の因襲と戦う苦悩を描く。日本自然主義文学の先駆。
→文献資料[破戒]
は‐かい【破潰】‥クワイ
破れついえること。破りくずすこと。
は‐かい【破壊】‥クワイ
うちこわすこと。うちこわされること。こわれること。「建物を―する」
⇒はかい‐おうりょく【破壊応力】
⇒はかいかつどう‐ぼうし‐ほう【破壊活動防止法】
⇒はかい‐しけん【破壊試験】
⇒はかい‐てき【破壊的】
⇒はかい‐りょく【破壊力】
は‐がい【羽交】‥ガヒ
①鳥の左右の翼のうちちがうところ。万葉集1「葦辺行く鴨の―に霜零ふりて」
②鳥のはね。つばさ。〈日葡辞書〉
⇒はがい‐がさね【羽交重ね】
⇒はがい‐じめ【羽交締め】
は‐がい・い【歯痒い】
〔形〕
ハガユイの転。
はかい‐おうりょく【破壊応力】‥クワイ‥
物体が破壊せずにもちこたえられる最大の応力。破壊強さ。極限強さ。
⇒は‐かい【破壊】
はがい‐がさね【羽交重ね】‥ガヒ‥
鳥が羽をかさねること。また、鳥が羽をかさね合うように、あちこちから集まりかさなること。
⇒は‐がい【羽交】
はかいかつどう‐ぼうし‐ほう【破壊活動防止法】‥クワイクワツ‥バウ‥ハフ
暴力主義的破壊活動を行なった団体に対する規制措置を定めるとともに、その種の活動に関する団体等規正令の刑罰規定を補整した法律。治安立法の一種で、1952年公布・施行。破防法。→団体等規正令。
⇒は‐かい【破壊】
はか‐いし【墓石】
墓じるしの石。ぼせき。
はかい‐しけん【破壊試験】‥クワイ‥
①材料試験の一種。材料から採取した試験片または材料そのものに破壊するまで荷重を加え、材料の靱性・強度その他の機械的諸性質を検査するもの。
②機械などを、それが破壊するような厳しい条件で試験すること。
⇒は‐かい【破壊】
はがい‐じめ【羽交締め】‥ガヒ‥
①相手の後ろから両手を腋の下へ通し、襟首の所で組み合わせて、相手が動けないようにすること。
②両腕を背後に交差させてしばること。
⇒は‐がい【羽交】
はかい‐てき【破壊的】‥クワイ‥
物事をこわしてしまうほどに、強力で荒っぽいさま。「―言動」↔建設的。
⇒は‐かい【破壊】
 ハオユー【蠔油】
(中国語)(→)オイスター‐ソースに同じ。
は‐おり【羽織】
①長着の上におおい着る、襟を折った短い衣。
②「はおりおとし」の略。
⇒はおり‐おとし【羽織落し】
⇒はおり‐げいしゃ【羽織芸者】
⇒はおり‐ごろ【羽織ごろ】
⇒はおり‐はかま【羽織袴】
⇒はおり‐ひも【羽織紐】
⇒はおり‐むし【羽織虫】
⇒はおり‐りょうし【羽織漁師】
はおり‐おとし【羽織落し】
歌舞伎演出用語。着ている羽織が知らずしらず脱げ落ちるしぐさ。魂の抜けた町人の有様を表現する。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐げいしゃ【羽織芸者】
(羽織を着て宴席に出たのでいう)(→)辰巳芸者のこと。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐ごろ【羽織ごろ】
立派な服装をしていながら、ごろつきのように恐喝を行う者。内田魯庵、社会百面相「実業家といふと聞えが好いが近頃の奴は―の方に近い」
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐はかま【羽織袴】
①羽織と袴。
②羽織と袴とを身につけること。転じて、あらたまった服装。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐ひも【羽織紐】
羽織の胸元が開かないように結ぶ紐。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐むし【羽織虫】
有鬚ゆうしゅ動物門ハオリムシ綱に属する長虫。直径1〜数センチメートルで、殻蓋部、羽織部(前体)、栄養体部(胴部)、分節する後体からなり、長さ0.5〜数メートルのキチン質の管の中に棲む。硫化物を栄養に変える化学合成細菌と共生する。ガラパゴス沖深海の熱水鉱床ではじめて採集された。世界各地の浅海から深海まで、熱水あるいは冷水湧出域で15種ほどが知られている。管虫。チューブ‐ワーム。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐りょうし【羽織漁師】‥レフ‥
自らは漁船に乗らない漁業経営者をいう。網元・網主など。
⇒は‐おり【羽織】
は‐お・る【羽織る】
〔他五〕
(「羽織」を動詞化した語)着物の上にうちかけて着る。森鴎外、雁「細帯一つでねんねこ半纏を―・つて」
はおん‐きごう【ハ音記号】‥ガウ
〔音〕(C-clef)五線譜で使われる音部記号の一つで、主として中音域の記譜に用いられる。Cの字を装飾化したもの。記号の中心でハ音(C)の位置を示し、第1線に置いた場合はソプラノ記号、第3線に置いた場合はアルト記号、第4線に置いた場合はテノール記号として用いる。→音部記号
ハ音記号
ハオユー【蠔油】
(中国語)(→)オイスター‐ソースに同じ。
は‐おり【羽織】
①長着の上におおい着る、襟を折った短い衣。
②「はおりおとし」の略。
⇒はおり‐おとし【羽織落し】
⇒はおり‐げいしゃ【羽織芸者】
⇒はおり‐ごろ【羽織ごろ】
⇒はおり‐はかま【羽織袴】
⇒はおり‐ひも【羽織紐】
⇒はおり‐むし【羽織虫】
⇒はおり‐りょうし【羽織漁師】
はおり‐おとし【羽織落し】
歌舞伎演出用語。着ている羽織が知らずしらず脱げ落ちるしぐさ。魂の抜けた町人の有様を表現する。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐げいしゃ【羽織芸者】
(羽織を着て宴席に出たのでいう)(→)辰巳芸者のこと。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐ごろ【羽織ごろ】
立派な服装をしていながら、ごろつきのように恐喝を行う者。内田魯庵、社会百面相「実業家といふと聞えが好いが近頃の奴は―の方に近い」
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐はかま【羽織袴】
①羽織と袴。
②羽織と袴とを身につけること。転じて、あらたまった服装。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐ひも【羽織紐】
羽織の胸元が開かないように結ぶ紐。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐むし【羽織虫】
有鬚ゆうしゅ動物門ハオリムシ綱に属する長虫。直径1〜数センチメートルで、殻蓋部、羽織部(前体)、栄養体部(胴部)、分節する後体からなり、長さ0.5〜数メートルのキチン質の管の中に棲む。硫化物を栄養に変える化学合成細菌と共生する。ガラパゴス沖深海の熱水鉱床ではじめて採集された。世界各地の浅海から深海まで、熱水あるいは冷水湧出域で15種ほどが知られている。管虫。チューブ‐ワーム。
⇒は‐おり【羽織】
はおり‐りょうし【羽織漁師】‥レフ‥
自らは漁船に乗らない漁業経営者をいう。網元・網主など。
⇒は‐おり【羽織】
は‐お・る【羽織る】
〔他五〕
(「羽織」を動詞化した語)着物の上にうちかけて着る。森鴎外、雁「細帯一つでねんねこ半纏を―・つて」
はおん‐きごう【ハ音記号】‥ガウ
〔音〕(C-clef)五線譜で使われる音部記号の一つで、主として中音域の記譜に用いられる。Cの字を装飾化したもの。記号の中心でハ音(C)の位置を示し、第1線に置いた場合はソプラノ記号、第3線に置いた場合はアルト記号、第4線に置いた場合はテノール記号として用いる。→音部記号
ハ音記号
 はか【計・量】
①稲を植えたり刈ったり、また茅を刈る時などの範囲や量。また、稲を植えた列と列との間をいう。万葉集10「秋の田の吾が苅りばかの過ぎぬれば」
②めあて。あてど。はかり。後撰和歌集恋「いづこを―と君がとはまし」
③(「捗」とも書く)仕事の進み具合。やり終えた量。
⇒計が行く
はか【墓】
①死者の遺骸や遺骨を葬った所。つか。おくつき。墳墓。仁徳紀「田道が―を掘る」。「―に参る」
②墓碑ぼひ。墓石。「―を建てる」
は‐か【破瓜】‥クワ
①(「瓜」の字を二分すると、二つの「八」の字の形となるからいう)
㋐女性の16歳の称。思春期の年ごろ。「―期」
㋑(8の8倍は64であるからいう)男性の64歳の称。
②女性の処女膜の破れること。
は‐か【薄荷】
⇒はっか。〈倭名類聚鈔16〉
はか
〔助詞〕
(「ほか(外)」の転。下に打消の語を伴う)…よりほか。…ほか。…しか。浄瑠璃、長町女腹切「私をお袋と―云ひませぬ」
はが【
はか【計・量】
①稲を植えたり刈ったり、また茅を刈る時などの範囲や量。また、稲を植えた列と列との間をいう。万葉集10「秋の田の吾が苅りばかの過ぎぬれば」
②めあて。あてど。はかり。後撰和歌集恋「いづこを―と君がとはまし」
③(「捗」とも書く)仕事の進み具合。やり終えた量。
⇒計が行く
はか【墓】
①死者の遺骸や遺骨を葬った所。つか。おくつき。墳墓。仁徳紀「田道が―を掘る」。「―に参る」
②墓碑ぼひ。墓石。「―を建てる」
は‐か【破瓜】‥クワ
①(「瓜」の字を二分すると、二つの「八」の字の形となるからいう)
㋐女性の16歳の称。思春期の年ごろ。「―期」
㋑(8の8倍は64であるからいう)男性の64歳の称。
②女性の処女膜の破れること。
は‐か【薄荷】
⇒はっか。〈倭名類聚鈔16〉
はか
〔助詞〕
(「ほか(外)」の転。下に打消の語を伴う)…よりほか。…ほか。…しか。浄瑠璃、長町女腹切「私をお袋と―云ひませぬ」
はが【 ・黐
・黐 】
竹串や木の枝・藁などに黐もちをぬり囮おとりを用いて鳥などを捕るもの。はご。〈倭名類聚鈔15〉
はが【芳賀】
姓氏の一つ。
⇒はが‐やいち【芳賀矢一】
ばか【馬鹿・莫迦】
(梵語moha(慕何)、すなわち無知の意からか。古くは僧侶の隠語。「馬鹿」は当て字)
①おろかなこと。社会的常識に欠けていること。また、その人。愚。愚人。あほう。〈文明本節用集〉。「専門―」
②取るに足りないつまらないこと。無益なこと。また、とんでもないこと。「―を言うな」「―なことをしたものだ」
③役に立たないこと。「蝶番ちょうつがいが―で戸が締まらない」
④馬鹿貝の略。夏目漱石、草枕「貝の殻は牡蠣かきか、―か、馬刀貝まてがいか」
⑤(接頭語的に)度はずれて、の意。「―ていねい」「―さわぎ」「―陽気」
→馬鹿に
⇒馬鹿と鋏は使いよう
⇒馬鹿にする
⇒馬鹿に付ける薬は無い
⇒馬鹿にならない
⇒馬鹿になる
⇒馬鹿の一つ覚え
⇒馬鹿は死ななきゃ直らない
⇒馬鹿も休み休み言え
⇒馬鹿を見る
ハガード【Henry Rider Haggard】
イギリスの冒険小説家。移民・農業政策の著作もある。作「ソロモン王の洞窟」「洞窟の女王」など。(1856〜1925)
はか‐あな【墓穴】
屍体や遺骨を葬る穴。つかあな。
ばか‐あな【馬鹿穴】
ボルトを通す穴で、直径をボルトより多少大きくしたもの。
は‐かい【破戒】
戒を破ること。受戒した者が戒法に違うこと。「―僧」↔持戒。
⇒はかい‐むざん【破戒無慙】
⇒破戒の出家は牛に生るる
はかい【破戒】
長編小説。島崎藤村作。1906年(明治39)刊。被差別部落出身の小学校教師瀬川丑松うしまつが、父の戒めを破って自分の素姓を告白し、周囲の因襲と戦う苦悩を描く。日本自然主義文学の先駆。
→文献資料[破戒]
は‐かい【破潰】‥クワイ
破れついえること。破りくずすこと。
は‐かい【破壊】‥クワイ
うちこわすこと。うちこわされること。こわれること。「建物を―する」
⇒はかい‐おうりょく【破壊応力】
⇒はかいかつどう‐ぼうし‐ほう【破壊活動防止法】
⇒はかい‐しけん【破壊試験】
⇒はかい‐てき【破壊的】
⇒はかい‐りょく【破壊力】
は‐がい【羽交】‥ガヒ
①鳥の左右の翼のうちちがうところ。万葉集1「葦辺行く鴨の―に霜零ふりて」
②鳥のはね。つばさ。〈日葡辞書〉
⇒はがい‐がさね【羽交重ね】
⇒はがい‐じめ【羽交締め】
は‐がい・い【歯痒い】
〔形〕
ハガユイの転。
はかい‐おうりょく【破壊応力】‥クワイ‥
物体が破壊せずにもちこたえられる最大の応力。破壊強さ。極限強さ。
⇒は‐かい【破壊】
はがい‐がさね【羽交重ね】‥ガヒ‥
鳥が羽をかさねること。また、鳥が羽をかさね合うように、あちこちから集まりかさなること。
⇒は‐がい【羽交】
はかいかつどう‐ぼうし‐ほう【破壊活動防止法】‥クワイクワツ‥バウ‥ハフ
暴力主義的破壊活動を行なった団体に対する規制措置を定めるとともに、その種の活動に関する団体等規正令の刑罰規定を補整した法律。治安立法の一種で、1952年公布・施行。破防法。→団体等規正令。
⇒は‐かい【破壊】
はか‐いし【墓石】
墓じるしの石。ぼせき。
はかい‐しけん【破壊試験】‥クワイ‥
①材料試験の一種。材料から採取した試験片または材料そのものに破壊するまで荷重を加え、材料の靱性・強度その他の機械的諸性質を検査するもの。
②機械などを、それが破壊するような厳しい条件で試験すること。
⇒は‐かい【破壊】
はがい‐じめ【羽交締め】‥ガヒ‥
①相手の後ろから両手を腋の下へ通し、襟首の所で組み合わせて、相手が動けないようにすること。
②両腕を背後に交差させてしばること。
⇒は‐がい【羽交】
はかい‐てき【破壊的】‥クワイ‥
物事をこわしてしまうほどに、強力で荒っぽいさま。「―言動」↔建設的。
⇒は‐かい【破壊】
】
竹串や木の枝・藁などに黐もちをぬり囮おとりを用いて鳥などを捕るもの。はご。〈倭名類聚鈔15〉
はが【芳賀】
姓氏の一つ。
⇒はが‐やいち【芳賀矢一】
ばか【馬鹿・莫迦】
(梵語moha(慕何)、すなわち無知の意からか。古くは僧侶の隠語。「馬鹿」は当て字)
①おろかなこと。社会的常識に欠けていること。また、その人。愚。愚人。あほう。〈文明本節用集〉。「専門―」
②取るに足りないつまらないこと。無益なこと。また、とんでもないこと。「―を言うな」「―なことをしたものだ」
③役に立たないこと。「蝶番ちょうつがいが―で戸が締まらない」
④馬鹿貝の略。夏目漱石、草枕「貝の殻は牡蠣かきか、―か、馬刀貝まてがいか」
⑤(接頭語的に)度はずれて、の意。「―ていねい」「―さわぎ」「―陽気」
→馬鹿に
⇒馬鹿と鋏は使いよう
⇒馬鹿にする
⇒馬鹿に付ける薬は無い
⇒馬鹿にならない
⇒馬鹿になる
⇒馬鹿の一つ覚え
⇒馬鹿は死ななきゃ直らない
⇒馬鹿も休み休み言え
⇒馬鹿を見る
ハガード【Henry Rider Haggard】
イギリスの冒険小説家。移民・農業政策の著作もある。作「ソロモン王の洞窟」「洞窟の女王」など。(1856〜1925)
はか‐あな【墓穴】
屍体や遺骨を葬る穴。つかあな。
ばか‐あな【馬鹿穴】
ボルトを通す穴で、直径をボルトより多少大きくしたもの。
は‐かい【破戒】
戒を破ること。受戒した者が戒法に違うこと。「―僧」↔持戒。
⇒はかい‐むざん【破戒無慙】
⇒破戒の出家は牛に生るる
はかい【破戒】
長編小説。島崎藤村作。1906年(明治39)刊。被差別部落出身の小学校教師瀬川丑松うしまつが、父の戒めを破って自分の素姓を告白し、周囲の因襲と戦う苦悩を描く。日本自然主義文学の先駆。
→文献資料[破戒]
は‐かい【破潰】‥クワイ
破れついえること。破りくずすこと。
は‐かい【破壊】‥クワイ
うちこわすこと。うちこわされること。こわれること。「建物を―する」
⇒はかい‐おうりょく【破壊応力】
⇒はかいかつどう‐ぼうし‐ほう【破壊活動防止法】
⇒はかい‐しけん【破壊試験】
⇒はかい‐てき【破壊的】
⇒はかい‐りょく【破壊力】
は‐がい【羽交】‥ガヒ
①鳥の左右の翼のうちちがうところ。万葉集1「葦辺行く鴨の―に霜零ふりて」
②鳥のはね。つばさ。〈日葡辞書〉
⇒はがい‐がさね【羽交重ね】
⇒はがい‐じめ【羽交締め】
は‐がい・い【歯痒い】
〔形〕
ハガユイの転。
はかい‐おうりょく【破壊応力】‥クワイ‥
物体が破壊せずにもちこたえられる最大の応力。破壊強さ。極限強さ。
⇒は‐かい【破壊】
はがい‐がさね【羽交重ね】‥ガヒ‥
鳥が羽をかさねること。また、鳥が羽をかさね合うように、あちこちから集まりかさなること。
⇒は‐がい【羽交】
はかいかつどう‐ぼうし‐ほう【破壊活動防止法】‥クワイクワツ‥バウ‥ハフ
暴力主義的破壊活動を行なった団体に対する規制措置を定めるとともに、その種の活動に関する団体等規正令の刑罰規定を補整した法律。治安立法の一種で、1952年公布・施行。破防法。→団体等規正令。
⇒は‐かい【破壊】
はか‐いし【墓石】
墓じるしの石。ぼせき。
はかい‐しけん【破壊試験】‥クワイ‥
①材料試験の一種。材料から採取した試験片または材料そのものに破壊するまで荷重を加え、材料の靱性・強度その他の機械的諸性質を検査するもの。
②機械などを、それが破壊するような厳しい条件で試験すること。
⇒は‐かい【破壊】
はがい‐じめ【羽交締め】‥ガヒ‥
①相手の後ろから両手を腋の下へ通し、襟首の所で組み合わせて、相手が動けないようにすること。
②両腕を背後に交差させてしばること。
⇒は‐がい【羽交】
はかい‐てき【破壊的】‥クワイ‥
物事をこわしてしまうほどに、強力で荒っぽいさま。「―言動」↔建設的。
⇒は‐かい【破壊】
はえ‐はらい【蠅払い】ハヘハラヒ🔗⭐🔉
はえ‐はらい【蠅払い】ハヘハラヒ
蠅を追い払うのに用いるもの。払子ほっす。また、武具の一つ。
はえ‐まいり【蠅参り】ハヘマヰリ🔗⭐🔉
はえ‐まいり【蠅参り】ハヘマヰリ
蠅が馬の尾に付いて行くように、道者の後に付いて伊勢参りをすること。また、その人。
はえ‐むし【蠅虫】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえ‐むし【蠅虫】ハヘ‥
①蠅と虫。また、蠅。
②人を卑しめていう語。取るに足りない人。うじむし。「ほととぎす―めらもよつく聞け」(一茶)
はえ‐もく【蠅目】ハヘ‥🔗⭐🔉
はえ‐もく【蠅目】ハヘ‥
昆虫綱の一目。体は総じて小形。4枚の翅のうち後翅2枚は縮小して平均棍となっている。複眼は一般に大きい。口器は吸い型またはなめ型。完全変態し、幼虫は「うじ」や「ぼうふら」。世界に約25万種と推定される。双翅類。
はえ‐もの【生え物】🔗⭐🔉
はえ‐もの【生え物】
地上に生えたもの。草木などの類。
はえ‐やま【生え山】🔗⭐🔉
はえ‐やま【生え山】
草木の生えた山。↔禿山はげやま
は・える【生える】🔗⭐🔉
は・える【生える】
〔自下一〕[文]は・ゆ(下二)
植物や毛などが、内部から外面に出て育つ。芽が出る。生じる。万葉集2「打橋に生ひををれる川藻もぞ枯るれば―・ゆる」。「かびが―・える」「歯が―・える」
は・える【映える・栄える】🔗⭐🔉
は・える【映える・栄える】
〔自下一〕[文]は・ゆ(下二)
(「生える」と同源)
①光を映して美しく輝く。反映する。源氏物語槿「をかしげなる姿、頭つきども月に―・えて」。「夕日に―・える山」
②(他の事物のために)目に立つようになる。勢いを得る。盛んになる。源氏物語常夏「まことや、暮れにも参りこむと思う給へ立つは、厭ふに―・ゆるにや」。「話が―・えない」
③周囲のものとの映り具合がよい。引き立つ。「このネクタイがよく―・える」
④立派に見える。目立つ。「―・えない男」
◇「栄」は、4で使うことが多い。
はえ‐わた・る【映え渡る】🔗⭐🔉
はえ‐わた・る【映え渡る】
〔自四〕
すみずみまではえる。ことごとくはえる。栄華物語殿上花見「―・りをかしう見ゆ」
は‐えん【巴猿】‥ヱン🔗⭐🔉
は‐えん【巴猿】‥ヱン
(中国湖北省巴東県地方の渓流、巴峡の付近に猿が多いのでいう)巴峡の猿。山の峡谷に鳴く猿。
大辞林の検索結果 (43)
はえ【岩礁】🔗⭐🔉
はえ [2][0] 【岩礁】
海中の暗礁。陸から海中に突き出している岩礁。
はえ【映え・栄え】🔗⭐🔉
はえ [2] 【映え・栄え】
〔動詞「はえる(映)」の連用形から〕
(1)ほまれ。名誉。「―ある栄冠をかちとる」
(2)はえること。はえるさま。見た目によく見えること。「見ばえ」「出来ばえ」などのように他の名詞の下に付いて「ばえ」と濁り,複合語を作る。
(3)引き立つこと。見ばえがすること。「その君をぞこの女御,大方のよろづのものの―にものし給ふ/栄花(見はてぬ夢)」
はえ【鮠】🔗⭐🔉
はえ [1] 【鮠】
「はや(鮠)」に同じ。
はえ【蠅】🔗⭐🔉
はえ ハヘ [0] 【蠅】
(1)双翅目短角亜目ハエ群に属する昆虫の総称。体は黒または褐色で太く,二枚の透明なはねを有し,触角は短い。幼虫は「うじ」と呼ばれる。イエバエ・クロバエ・ニクバエ・サシバエ・ツェツェバエなど種類が多く,伝染病を媒介したりして人畜に害を与えるものもある。はい。[季]夏。《やれうつな―が手をする足をする/一茶》
(2)とるに足らない者,つまらない者をののしっていう語。「―侍」
は-え【破壊】🔗⭐🔉
は-え ― 【破壊】
〔「え」は呉音〕
こわすこと。こわれること。破壊(ハカイ)。「塔婆を―せんと云ふ悪念をおこし/正統記(武烈)」
【破壊】
〔「え」は呉音〕
こわすこと。こわれること。破壊(ハカイ)。「塔婆を―せんと云ふ悪念をおこし/正統記(武烈)」
 【破壊】
〔「え」は呉音〕
こわすこと。こわれること。破壊(ハカイ)。「塔婆を―せんと云ふ悪念をおこし/正統記(武烈)」
【破壊】
〔「え」は呉音〕
こわすこと。こわれること。破壊(ハカイ)。「塔婆を―せんと云ふ悪念をおこし/正統記(武烈)」
はえ-うち【蠅打ち】🔗⭐🔉
はえ-うち ハヘ― [0][4] 【蠅打ち】
「蠅叩(ハエタタ)き」に同じ。[季]夏。
はえ-かび【蠅黴】🔗⭐🔉
はえ-かび ハヘ― [2] 【蠅黴】
接合菌類ハエカビ科に属するかび。生きているハエ類に寄生し,寄主を殺して体外に菌糸を伸ばして子実層をつくる。ほかの昆虫類につく近似種も多い。
はえ-かわ・る【生え変(わ)る】🔗⭐🔉
はえ-かわ・る ―カハル [4][0] 【生え変(わ)る】 (動ラ五[四])
前にあったものがなくなったあとに,新しいものが生える。「歯が―・る」
はえ-ぎわ【生え際】🔗⭐🔉
はえ-ぎわ ―ギハ [0] 【生え際】
額(ヒタイ)などの髪の生え始めている部分。「―の美しい人」
はえ-ざ【蠅座】🔗⭐🔉
はえ-ざ ハヘ― [0] 【蠅座】
〔(ラテン) Musca〕
南天の星座。日本からは見えない。南十字星の南にあり,天の川の一部を含む。
はえ-じごく【蠅地獄】🔗⭐🔉
はえ-じごく ハヘヂゴク [3] 【蠅地獄】
モウセンゴケ科の多年生食虫植物。北アメリカ東南部原産。葉は根生し円形で縁に長い毛がある。葉面に三対の感覚毛があって,虫などが触れると二つに閉じて捕らえ,消化液を出す。五月頃,白色の五弁花をつける。蠅取草(ハエトリソウ)。
蝿地獄
 [図]
[図]
 [図]
[図]
はえ-たたき【蠅叩き】🔗⭐🔉
はえ-たたき ハヘ― [3] 【蠅叩き】
蠅を打ち殺すための,長い柄のついた道具。はいたたき。はえうち。[季]夏。《―とり彼一打我一打/虚子》
はえ-ちょう【蠅帳】🔗⭐🔉
はえ-ちょう ハヘチヤウ [0] 【蠅帳】
風通しをよくし,また蠅などが入らないように金網あるいは紗(シヤ)を張った,食品を入れておく小さな戸棚。蠅入らず。蠅よけ。はいちょう。[季]夏。
はえ-つ・く【蝕え尽く】🔗⭐🔉
はえ-つ・く 【蝕え尽く】 (動カ上二)
日食・月食で,皆既食となる。「日,―・きたること有り/日本書紀(推古訓)」
はえ-づみ【 積み】🔗⭐🔉
積み】🔗⭐🔉
はえ-づみ ハヘ― [0] 【 積み】
木材を土場(ドバ)や貯木場に積み上げる方式の一。一段目を並列に並べほぼ正方形とし,その上に直角方向に次の段を並べ,それを繰り返して積み上げる。交差積み。はい積み。
→巻立て
積み】
木材を土場(ドバ)や貯木場に積み上げる方式の一。一段目を並列に並べほぼ正方形とし,その上に直角方向に次の段を並べ,それを繰り返して積み上げる。交差積み。はい積み。
→巻立て
 積み】
木材を土場(ドバ)や貯木場に積み上げる方式の一。一段目を並列に並べほぼ正方形とし,その上に直角方向に次の段を並べ,それを繰り返して積み上げる。交差積み。はい積み。
→巻立て
積み】
木材を土場(ドバ)や貯木場に積み上げる方式の一。一段目を並列に並べほぼ正方形とし,その上に直角方向に次の段を並べ,それを繰り返して積み上げる。交差積み。はい積み。
→巻立て
はえ・でる【生え出る】🔗⭐🔉
はえ・でる [0][3] 【生え出る】 (動ダ下一)
はえて出る。発芽する。「土筆(ツクシ)が―・でる」
はえ-どくそう【蠅毒草】🔗⭐🔉
はえ-どくそう ハヘドクサウ [0] 【蠅毒草】
ハエドクソウ科の多年草。高さ約7センチメートル。原野の林内に自生。葉は三角卵形。夏,細長い穂を立て淡紅色の小花をまばらにつける。根を蠅を殺すのに用いた。
はえ-とり【蠅取り】🔗⭐🔉
はえ-とり ハヘ― [0][4][3] 【蠅取り】
(1)ハエをとるための道具。蠅取り器や蠅取り紙,蠅たたきなど。はいとり。
(2)「蠅取蜘蛛(グモ)」の略。
はえとり-がみ【蠅取り紙】🔗⭐🔉
はえとり-がみ ハヘ― [4] 【蠅取り紙】
ハエを取るために,ねばる薬液を塗った紙。天井からつるすテープ状にしたものは蠅取りリボンという。はえとりし。[季]夏。
はえとり-ぐも【蠅取蜘蛛・蠅虎】🔗⭐🔉
はえとり-ぐも ハヘ― [5] 【蠅取蜘蛛・蠅虎】
真正クモ目ハエトリグモ科のクモの総称。小形のクモ類で体は扁平。目は三列に並び,前列中央の一対は巨大。網を張らず,壁面などを歩行し,跳躍力が強く,巧みにハエなどの小昆虫を捕らえる。日本では約八〇種が知られる。[季]夏。
はえとり-そう【蠅取草】🔗⭐🔉
はえとり-そう ハヘ―サウ [0] 【蠅取草】
ハエジゴクの別名。
はえとり-だけ【蠅取茸】🔗⭐🔉
はえとり-だけ ハヘ― [4] 【蠅取茸】
テングタケ・ベニテングタケなどの俗称。その毒液がハエを殺すので,この名がある。
はえとり-なでしこ【蠅取撫子】🔗⭐🔉
はえとり-なでしこ ハヘ― [6] 【蠅取撫子】
ムシトリナデシコの別名。
はえ-なわ【延縄】🔗⭐🔉
はえ-なわ ハヘナハ [0] 【延縄】
釣り漁具の一。一本の長い幹縄に適当な間隔で,浮きを結ぶ浮縄と釣り針のついた多数の枝縄をつけたもの。それぞれの釣り針に餌(エサ)をつけ,海面下に浮かせあるいは海底に沈めて張る,浮き延縄と底延縄がある。のべなわ。ながなわ。「―漁業」
延縄
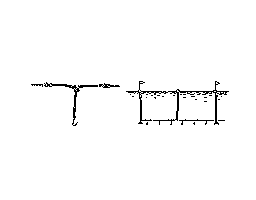 [図]
[図]
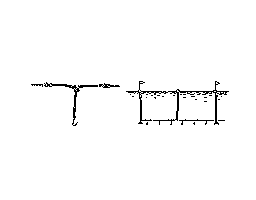 [図]
[図]
はえ-ぬき【生え抜き】🔗⭐🔉
はえ-ぬき [0] 【生え抜き】
(1)その土地に生まれ,その土地で育つこと。生粋(キツスイ)。「―の江戸っ子」
(2)団体・組織などにはじめから所属して現在に至っていること。「―の社員」
はえ-ぬ・く【生え抜く】🔗⭐🔉
はえ-ぬ・く 【生え抜く】 (動カ四)
(1)その土地で生まれそこで成長する。「吉原で―・いたやうに口を利くから/洒落本・南江駅話」
(2)はえて上に突き抜ける。「二王立ちに立たるは,金輪際より忽ちに―・いたるがごとく也/浄瑠璃・嫗山姥」
はえ-の-こ【蠅の子】🔗⭐🔉
はえ-の-こ ハヘ― [0] 【蠅の子】
ハエの幼虫。うじ。
はえばえ・し【映え映えし・栄え栄えし】🔗⭐🔉
はえばえ・し 【映え映えし・栄え栄えし】 (形シク)
(1)非常にはえて見える。はなやかで見ばえがする。「内わたりにも墨染にて,―・しき事もなし/栄花(松の下枝)」
(2)光栄である。面目が立つ。「講師も―・しく覚ゆるなるべし/枕草子 33」
はえばる【南風原】🔗⭐🔉
はえばる 【南風原】
沖縄県島尻郡,沖縄島南部の町。サトウキビのほか琉球絣(リユウキユウガスリ)を特産。
ハエマンサス (ラテン) Haemanthus
(ラテン) Haemanthus 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ハエマンサス [3]  (ラテン) Haemanthus
(ラテン) Haemanthus ヒガンバナ科ハエマンサス属の球根植物。南アフリカから熱帯アフリカにかけて約五〇種が分布。葉はオモトに似る。日本では長い白色のおしべが密集して化粧用の刷毛(ハケ)のような観を呈するマユハケオモト,おしべの長い赤色六弁花を散形につけるセンコウハナビなどが栽培される。
ヒガンバナ科ハエマンサス属の球根植物。南アフリカから熱帯アフリカにかけて約五〇種が分布。葉はオモトに似る。日本では長い白色のおしべが密集して化粧用の刷毛(ハケ)のような観を呈するマユハケオモト,おしべの長い赤色六弁花を散形につけるセンコウハナビなどが栽培される。
 (ラテン) Haemanthus
(ラテン) Haemanthus ヒガンバナ科ハエマンサス属の球根植物。南アフリカから熱帯アフリカにかけて約五〇種が分布。葉はオモトに似る。日本では長い白色のおしべが密集して化粧用の刷毛(ハケ)のような観を呈するマユハケオモト,おしべの長い赤色六弁花を散形につけるセンコウハナビなどが栽培される。
ヒガンバナ科ハエマンサス属の球根植物。南アフリカから熱帯アフリカにかけて約五〇種が分布。葉はオモトに似る。日本では長い白色のおしべが密集して化粧用の刷毛(ハケ)のような観を呈するマユハケオモト,おしべの長い赤色六弁花を散形につけるセンコウハナビなどが栽培される。
はえ-よけ【蠅除け】🔗⭐🔉
はえ-よけ ハヘ― [0][4] 【蠅除け】
ハエをよけたり追い払ったりすること。またそれに用いる道具。はいよけ。[季]夏。
は・える【生える】🔗⭐🔉
は・える [2] 【生える】 (動ア下一)[文]ヤ下二 は・ゆ
(1)草木の芽・枝などが(わずかに)出る。生ずる。「雑草が―・える」「青かびが―・える」「生ひををれる川藻もぞ枯るれば―・ゆる/万葉 196」
(2)動物の体から毛・歯・角などが生じる。「赤ちゃんに歯が―・える」「ひげが―・える」
[慣用] 根が―/羽が生えたよう
は・える【映える・栄える】🔗⭐🔉
は・える [2] 【映える・栄える】 (動ア下一)[文]ヤ下二 は・ゆ
(1)明るい光に照らされて輝く。あざやかに見える。《映》「朝日に―・える富士山」
(2)周囲のものとの対比によって一段と美しさが目立つ。引き立って見える。《映》「紺碧の海に白い船体が―・える」
は・える【 へる】🔗⭐🔉
へる】🔗⭐🔉
は・える ハヘル 【 へる】 (動ハ下一)
〔近世語〕
俵や木材などをきれいに形よく積み上げる。「杉なりの俵物広庭に幾所か―・へて/浮世草子・商人軍配団」
〔下二段動詞「はう(延)」の下一段化したものからか〕
へる】 (動ハ下一)
〔近世語〕
俵や木材などをきれいに形よく積み上げる。「杉なりの俵物広庭に幾所か―・へて/浮世草子・商人軍配団」
〔下二段動詞「はう(延)」の下一段化したものからか〕
 へる】 (動ハ下一)
〔近世語〕
俵や木材などをきれいに形よく積み上げる。「杉なりの俵物広庭に幾所か―・へて/浮世草子・商人軍配団」
〔下二段動詞「はう(延)」の下一段化したものからか〕
へる】 (動ハ下一)
〔近世語〕
俵や木材などをきれいに形よく積み上げる。「杉なりの俵物広庭に幾所か―・へて/浮世草子・商人軍配団」
〔下二段動詞「はう(延)」の下一段化したものからか〕
は-えん【巴猿】🔗⭐🔉
は-えん ― ン 【巴猿】
〔中国湖北省巴東県地方の巴峡には猿が多くいたことから〕
峡谷に鳴く猿。また,その哀愁を帯びた鳴き声。「―三叫,暁行人の裳を霑ほす/和漢朗詠(雑)」
ン 【巴猿】
〔中国湖北省巴東県地方の巴峡には猿が多くいたことから〕
峡谷に鳴く猿。また,その哀愁を帯びた鳴き声。「―三叫,暁行人の裳を霑ほす/和漢朗詠(雑)」
 ン 【巴猿】
〔中国湖北省巴東県地方の巴峡には猿が多くいたことから〕
峡谷に鳴く猿。また,その哀愁を帯びた鳴き声。「―三叫,暁行人の裳を霑ほす/和漢朗詠(雑)」
ン 【巴猿】
〔中国湖北省巴東県地方の巴峡には猿が多くいたことから〕
峡谷に鳴く猿。また,その哀愁を帯びた鳴き声。「―三叫,暁行人の裳を霑ほす/和漢朗詠(雑)」
はえ【栄えある】(和英)🔗⭐🔉
はえなわ【延縄】(和英)🔗⭐🔉
はえなわ【延縄】
a longline.延縄漁業 a longline fishing.延縄漁船 a longliner.
はえる【生える】(和英)🔗⭐🔉
はえる【映える】(和英)🔗⭐🔉
はえる【映える】
[かがやく]shine;→英和
be bright;[引き立つ]look attractive;be set off.
広辞苑+大辞林に「ハエ」で始まるの検索結果。もっと読み込む