複数辞典一括検索+![]()
![]()
匁 め🔗⭐🔉
【匁】
 4画 勹部 [常用漢字] 〔国〕
区点=4472 16進=4C68 シフトJIS=96E6
《常用音訓》もんめ
《訓読み》 もんめ/め
《意味》
4画 勹部 [常用漢字] 〔国〕
区点=4472 16進=4C68 シフトJIS=96E6
《常用音訓》もんめ
《訓読み》 もんめ/め
《意味》
 もんめ。め。重さの単位。一匁は、一貫の千分の一で、約三・七五グラム。
もんめ。め。重さの単位。一匁は、一貫の千分の一で、約三・七五グラム。 もんめ。江戸時代の通貨の単位。一匁は、一両の六十分の一。
《解字》
通貨・重さの単位である「もんめ」を「文メ」と続けて書いたために生じた、日本製の漢字。
もんめ。江戸時代の通貨の単位。一匁は、一両の六十分の一。
《解字》
通貨・重さの単位である「もんめ」を「文メ」と続けて書いたために生じた、日本製の漢字。
 4画 勹部 [常用漢字] 〔国〕
区点=4472 16進=4C68 シフトJIS=96E6
《常用音訓》もんめ
《訓読み》 もんめ/め
《意味》
4画 勹部 [常用漢字] 〔国〕
区点=4472 16進=4C68 シフトJIS=96E6
《常用音訓》もんめ
《訓読み》 もんめ/め
《意味》
 もんめ。め。重さの単位。一匁は、一貫の千分の一で、約三・七五グラム。
もんめ。め。重さの単位。一匁は、一貫の千分の一で、約三・七五グラム。 もんめ。江戸時代の通貨の単位。一匁は、一両の六十分の一。
《解字》
通貨・重さの単位である「もんめ」を「文メ」と続けて書いたために生じた、日本製の漢字。
もんめ。江戸時代の通貨の単位。一匁は、一両の六十分の一。
《解字》
通貨・重さの単位である「もんめ」を「文メ」と続けて書いたために生じた、日本製の漢字。
女 め🔗⭐🔉
【女】
 3画 女部 [一年]
区点=2987 16進=3D77 シフトJIS=8F97
《常用音訓》ジョ/ニョ/ニョウ/おんな/め
《音読み》 ジョ(ヂョ)
3画 女部 [一年]
区点=2987 16進=3D77 シフトJIS=8F97
《常用音訓》ジョ/ニョ/ニョウ/おんな/め
《音読み》 ジョ(ヂョ) /ニョ
/ニョ /ニョウ
/ニョウ 〈n
〈n 〉
《訓読み》 おんな(をんな)/め/むすめ/なんじ(なんぢ)/めあわす(めあはす)
《名付け》 こ・たか・め・よし
《意味》
〉
《訓読み》 おんな(をんな)/め/むすめ/なんじ(なんぢ)/めあわす(めあはす)
《名付け》 こ・たか・め・よし
《意味》
 {名}おんな(ヲンナ)。め。〈対語〉→男。
{名}おんな(ヲンナ)。め。〈対語〉→男。
 {名}むすめ。ある人のおんなの子。「楊家有女初長成=楊家ニ女有リ初メテ長成ス」〔→白居易〕
{名}むすめ。ある人のおんなの子。「楊家有女初長成=楊家ニ女有リ初メテ長成ス」〔→白居易〕
 {名}娘や嫁が親に対して自分をさしていうことば。「女行無偏斜=女ノ行ヒニ偏斜無シ」〔古楽府〕
{名}娘や嫁が親に対して自分をさしていうことば。「女行無偏斜=女ノ行ヒニ偏斜無シ」〔古楽府〕
 {代}なんじ(ナンヂ)。おまえ。第二人称。〈同義語〉→汝。〈類義語〉→爾。「予及女偕亡=予ト女ト偕ニ亡ビン」〔→孟子〕
{代}なんじ(ナンヂ)。おまえ。第二人称。〈同義語〉→汝。〈類義語〉→爾。「予及女偕亡=予ト女ト偕ニ亡ビン」〔→孟子〕
 {名}二十八宿の一つ。規準星は今のみずがめ座に含まれる。うるき。
{名}二十八宿の一つ。規準星は今のみずがめ座に含まれる。うるき。
 {動}めあわす(メアハス)。嫁にやる。とつがせる。▽去声に読む。〈類義語〉→妻。「女以驪姫=女スニ驪姫ヲモッテス」〔→左伝〕
《解字》
{動}めあわす(メアハス)。嫁にやる。とつがせる。▽去声に読む。〈類義語〉→妻。「女以驪姫=女スニ驪姫ヲモッテス」〔→左伝〕
《解字》
 象形。なよなよとしたからだつきの女性を描いたもの。
《単語家族》
弱ジャク・ニャク
象形。なよなよとしたからだつきの女性を描いたもの。
《単語家族》
弱ジャク・ニャク 若ジャク・ニャク(柔らかい)
若ジャク・ニャク(柔らかい) 娘ジョウ・ニョウと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
娘ジョウ・ニョウと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
 3画 女部 [一年]
区点=2987 16進=3D77 シフトJIS=8F97
《常用音訓》ジョ/ニョ/ニョウ/おんな/め
《音読み》 ジョ(ヂョ)
3画 女部 [一年]
区点=2987 16進=3D77 シフトJIS=8F97
《常用音訓》ジョ/ニョ/ニョウ/おんな/め
《音読み》 ジョ(ヂョ) /ニョ
/ニョ /ニョウ
/ニョウ 〈n
〈n 〉
《訓読み》 おんな(をんな)/め/むすめ/なんじ(なんぢ)/めあわす(めあはす)
《名付け》 こ・たか・め・よし
《意味》
〉
《訓読み》 おんな(をんな)/め/むすめ/なんじ(なんぢ)/めあわす(めあはす)
《名付け》 こ・たか・め・よし
《意味》
 {名}おんな(ヲンナ)。め。〈対語〉→男。
{名}おんな(ヲンナ)。め。〈対語〉→男。
 {名}むすめ。ある人のおんなの子。「楊家有女初長成=楊家ニ女有リ初メテ長成ス」〔→白居易〕
{名}むすめ。ある人のおんなの子。「楊家有女初長成=楊家ニ女有リ初メテ長成ス」〔→白居易〕
 {名}娘や嫁が親に対して自分をさしていうことば。「女行無偏斜=女ノ行ヒニ偏斜無シ」〔古楽府〕
{名}娘や嫁が親に対して自分をさしていうことば。「女行無偏斜=女ノ行ヒニ偏斜無シ」〔古楽府〕
 {代}なんじ(ナンヂ)。おまえ。第二人称。〈同義語〉→汝。〈類義語〉→爾。「予及女偕亡=予ト女ト偕ニ亡ビン」〔→孟子〕
{代}なんじ(ナンヂ)。おまえ。第二人称。〈同義語〉→汝。〈類義語〉→爾。「予及女偕亡=予ト女ト偕ニ亡ビン」〔→孟子〕
 {名}二十八宿の一つ。規準星は今のみずがめ座に含まれる。うるき。
{名}二十八宿の一つ。規準星は今のみずがめ座に含まれる。うるき。
 {動}めあわす(メアハス)。嫁にやる。とつがせる。▽去声に読む。〈類義語〉→妻。「女以驪姫=女スニ驪姫ヲモッテス」〔→左伝〕
《解字》
{動}めあわす(メアハス)。嫁にやる。とつがせる。▽去声に読む。〈類義語〉→妻。「女以驪姫=女スニ驪姫ヲモッテス」〔→左伝〕
《解字》
 象形。なよなよとしたからだつきの女性を描いたもの。
《単語家族》
弱ジャク・ニャク
象形。なよなよとしたからだつきの女性を描いたもの。
《単語家族》
弱ジャク・ニャク 若ジャク・ニャク(柔らかい)
若ジャク・ニャク(柔らかい) 娘ジョウ・ニョウと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
娘ジョウ・ニョウと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
奴 め🔗⭐🔉
【奴】
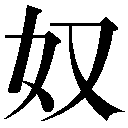 5画 女部 [常用漢字]
区点=3759 16進=455B シフトJIS=937A
《常用音訓》ド
《音読み》 ド
5画 女部 [常用漢字]
区点=3759 16進=455B シフトJIS=937A
《常用音訓》ド
《音読み》 ド /ヌ
/ヌ 〈n
〈n 〉
《訓読み》 やっこ/やつ/め
《名付け》 ぬい
《意味》
〉
《訓読み》 やっこ/やつ/め
《名付け》 ぬい
《意味》
 {名}召使。のち、金で買われた住みこみの使用人のこと。〈類義語〉→傭ヨウ(賃金で雇われる人)・→婢ヒ(女の召使)。「奴隷」「箕子為之奴=箕子コレガ奴ト為ル」〔→論語〕
{名}召使。のち、金で買われた住みこみの使用人のこと。〈類義語〉→傭ヨウ(賃金で雇われる人)・→婢ヒ(女の召使)。「奴隷」「箕子為之奴=箕子コレガ奴ト為ル」〔→論語〕
 {形}どれいのように地位が低いさま。また、能力の劣ったさま。
{形}どれいのように地位が低いさま。また、能力の劣ったさま。
 {名}〔俗〕女性が自分をへりくだっていうことば。やつがれ。〈対語〉→僕。
〔国〕
{名}〔俗〕女性が自分をへりくだっていうことば。やつがれ。〈対語〉→僕。
〔国〕 やっこ。武家の下男。仲間チュウゲンやぞうりとりなど。▽「家ヤつ子」の意。「供奴トモヤッコ」
やっこ。武家の下男。仲間チュウゲンやぞうりとりなど。▽「家ヤつ子」の意。「供奴トモヤッコ」 やつ。人を卑しめていうことば。「こ奴」
やつ。人を卑しめていうことば。「こ奴」 め。人や動物を卑しめていったり、低いものと見ていったりすることば。「こいつ奴」「私奴」
《解字》
め。人や動物を卑しめていったり、低いものと見ていったりすることば。「こいつ奴」「私奴」
《解字》
 会意兼形声。「又(て)+音符女」。手で労働する女のどれい。努と同じで、激しい力仕事をする意から、ねばり強い意を含む。
《単語家族》
怒(じわじわとおこる)
会意兼形声。「又(て)+音符女」。手で労働する女のどれい。努と同じで、激しい力仕事をする意から、ねばり強い意を含む。
《単語家族》
怒(じわじわとおこる) 弩ド(ねばりづよい大弓)などと同系。
《類義》
→童
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
弩ド(ねばりづよい大弓)などと同系。
《類義》
→童
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
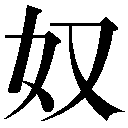 5画 女部 [常用漢字]
区点=3759 16進=455B シフトJIS=937A
《常用音訓》ド
《音読み》 ド
5画 女部 [常用漢字]
区点=3759 16進=455B シフトJIS=937A
《常用音訓》ド
《音読み》 ド /ヌ
/ヌ 〈n
〈n 〉
《訓読み》 やっこ/やつ/め
《名付け》 ぬい
《意味》
〉
《訓読み》 やっこ/やつ/め
《名付け》 ぬい
《意味》
 {名}召使。のち、金で買われた住みこみの使用人のこと。〈類義語〉→傭ヨウ(賃金で雇われる人)・→婢ヒ(女の召使)。「奴隷」「箕子為之奴=箕子コレガ奴ト為ル」〔→論語〕
{名}召使。のち、金で買われた住みこみの使用人のこと。〈類義語〉→傭ヨウ(賃金で雇われる人)・→婢ヒ(女の召使)。「奴隷」「箕子為之奴=箕子コレガ奴ト為ル」〔→論語〕
 {形}どれいのように地位が低いさま。また、能力の劣ったさま。
{形}どれいのように地位が低いさま。また、能力の劣ったさま。
 {名}〔俗〕女性が自分をへりくだっていうことば。やつがれ。〈対語〉→僕。
〔国〕
{名}〔俗〕女性が自分をへりくだっていうことば。やつがれ。〈対語〉→僕。
〔国〕 やっこ。武家の下男。仲間チュウゲンやぞうりとりなど。▽「家ヤつ子」の意。「供奴トモヤッコ」
やっこ。武家の下男。仲間チュウゲンやぞうりとりなど。▽「家ヤつ子」の意。「供奴トモヤッコ」 やつ。人を卑しめていうことば。「こ奴」
やつ。人を卑しめていうことば。「こ奴」 め。人や動物を卑しめていったり、低いものと見ていったりすることば。「こいつ奴」「私奴」
《解字》
め。人や動物を卑しめていったり、低いものと見ていったりすることば。「こいつ奴」「私奴」
《解字》
 会意兼形声。「又(て)+音符女」。手で労働する女のどれい。努と同じで、激しい力仕事をする意から、ねばり強い意を含む。
《単語家族》
怒(じわじわとおこる)
会意兼形声。「又(て)+音符女」。手で労働する女のどれい。努と同じで、激しい力仕事をする意から、ねばり強い意を含む。
《単語家族》
怒(じわじわとおこる) 弩ド(ねばりづよい大弓)などと同系。
《類義》
→童
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
弩ド(ねばりづよい大弓)などと同系。
《類義》
→童
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
目 め🔗⭐🔉
【目】
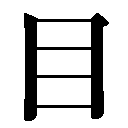 5画 目部 [一年]
区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA
《常用音訓》ボク/モク/ま/め
《音読み》 モク
5画 目部 [一年]
区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA
《常用音訓》ボク/モク/ま/め
《音読み》 モク /ボク
/ボク 〈m
〈m 〉
《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)
《名付け》 ま・み・め・より
《意味》
〉
《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)
《名付け》 ま・み・め・より
《意味》
 {名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕
{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕
 {名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」
{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」
 モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕
モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕
 {名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕
{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕
 {名}め。網や、格子のめ。
{名}め。網や、格子のめ。
 {単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」
{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」
 {名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」
{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」
 {名}人の主となる者。かしら。「頭目」
〔国〕
{名}人の主となる者。かしら。「頭目」
〔国〕 さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。
さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。 め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」
め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」 め。ものを見とおす力。「目がきく」
め。ものを見とおす力。「目がきく」 碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」
碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」 め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」
《解字》
め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」
《解字》
 象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。
《単語家族》
モクとは木(葉をかぶった立ちき)
象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。
《単語家族》
モクとは木(葉をかぶった立ちき) 沐モク(水をかぶる)
沐モク(水をかぶる) 冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。
《類義》
眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。
《類義》
眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
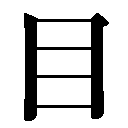 5画 目部 [一年]
区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA
《常用音訓》ボク/モク/ま/め
《音読み》 モク
5画 目部 [一年]
区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA
《常用音訓》ボク/モク/ま/め
《音読み》 モク /ボク
/ボク 〈m
〈m 〉
《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)
《名付け》 ま・み・め・より
《意味》
〉
《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)
《名付け》 ま・み・め・より
《意味》
 {名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕
{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕
 {名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」
{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」
 モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕
モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕
 {名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕
{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕
 {名}め。網や、格子のめ。
{名}め。網や、格子のめ。
 {単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」
{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」
 {名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」
{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」
 {名}人の主となる者。かしら。「頭目」
〔国〕
{名}人の主となる者。かしら。「頭目」
〔国〕 さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。
さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。 め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」
め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」 め。ものを見とおす力。「目がきく」
め。ものを見とおす力。「目がきく」 碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」
碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」 め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」
《解字》
め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」
《解字》
 象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。
《単語家族》
モクとは木(葉をかぶった立ちき)
象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。
《単語家族》
モクとは木(葉をかぶった立ちき) 沐モク(水をかぶる)
沐モク(水をかぶる) 冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。
《類義》
眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。
《類義》
眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
眼 め🔗⭐🔉
【眼】
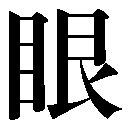 11画 目部 [五年]
区点=2067 16進=3463 シフトJIS=8AE1
《常用音訓》ガン/ゲン/まなこ
《音読み》 ガン
11画 目部 [五年]
区点=2067 16進=3463 シフトJIS=8AE1
《常用音訓》ガン/ゲン/まなこ
《音読み》 ガン /ゲン
/ゲン 〈y
〈y n〉
《訓読み》 まなこ/め
《名付け》 まくはし・め
《意味》
n〉
《訓読み》 まなこ/め
《名付け》 まくはし・め
《意味》
 {名}まなこ。め。頭骨の穴にはまっているめ。また、めつき。「眼科」「冷眼」
{名}まなこ。め。頭骨の穴にはまっているめ。また、めつき。「眼科」「冷眼」
 {名}め。あな。「井眼(井戸の穴)」「針眼」
{名}め。あな。「井眼(井戸の穴)」「針眼」
 {名・形}かなめ。要点。めだつさま。「眼目」「字眼(重要な字)」
《解字》
会意兼形声。艮コンは「目+匕首ヒシュの匕(小刀)」の会意文字で、小刀でくまどっため。または、小刀で彫ったような穴にはまっているめ。一定の座にはまって動かないの意を含む。眼は「目+音符艮」で、艮の原義をあらわす。
《単語家族》
痕(穴のあいた傷あと)
{名・形}かなめ。要点。めだつさま。「眼目」「字眼(重要な字)」
《解字》
会意兼形声。艮コンは「目+匕首ヒシュの匕(小刀)」の会意文字で、小刀でくまどっため。または、小刀で彫ったような穴にはまっているめ。一定の座にはまって動かないの意を含む。眼は「目+音符艮」で、艮の原義をあらわす。
《単語家族》
痕(穴のあいた傷あと) 根(穴をあけてはまりこんだ木のね)と同系。
《類義》
目は、冒モウ・ボウ(かぶる)と同系で、まぶたのかぶさっため。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
根(穴をあけてはまりこんだ木のね)と同系。
《類義》
目は、冒モウ・ボウ(かぶる)と同系で、まぶたのかぶさっため。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
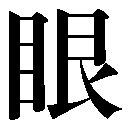 11画 目部 [五年]
区点=2067 16進=3463 シフトJIS=8AE1
《常用音訓》ガン/ゲン/まなこ
《音読み》 ガン
11画 目部 [五年]
区点=2067 16進=3463 シフトJIS=8AE1
《常用音訓》ガン/ゲン/まなこ
《音読み》 ガン /ゲン
/ゲン 〈y
〈y n〉
《訓読み》 まなこ/め
《名付け》 まくはし・め
《意味》
n〉
《訓読み》 まなこ/め
《名付け》 まくはし・め
《意味》
 {名}まなこ。め。頭骨の穴にはまっているめ。また、めつき。「眼科」「冷眼」
{名}まなこ。め。頭骨の穴にはまっているめ。また、めつき。「眼科」「冷眼」
 {名}め。あな。「井眼(井戸の穴)」「針眼」
{名}め。あな。「井眼(井戸の穴)」「針眼」
 {名・形}かなめ。要点。めだつさま。「眼目」「字眼(重要な字)」
《解字》
会意兼形声。艮コンは「目+匕首ヒシュの匕(小刀)」の会意文字で、小刀でくまどっため。または、小刀で彫ったような穴にはまっているめ。一定の座にはまって動かないの意を含む。眼は「目+音符艮」で、艮の原義をあらわす。
《単語家族》
痕(穴のあいた傷あと)
{名・形}かなめ。要点。めだつさま。「眼目」「字眼(重要な字)」
《解字》
会意兼形声。艮コンは「目+匕首ヒシュの匕(小刀)」の会意文字で、小刀でくまどっため。または、小刀で彫ったような穴にはまっているめ。一定の座にはまって動かないの意を含む。眼は「目+音符艮」で、艮の原義をあらわす。
《単語家族》
痕(穴のあいた傷あと) 根(穴をあけてはまりこんだ木のね)と同系。
《類義》
目は、冒モウ・ボウ(かぶる)と同系で、まぶたのかぶさっため。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
根(穴をあけてはまりこんだ木のね)と同系。
《類義》
目は、冒モウ・ボウ(かぶる)と同系で、まぶたのかぶさっため。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
芽 め🔗⭐🔉
雌 め🔗⭐🔉
【雌】
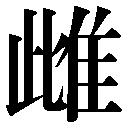 13画 隹部 [常用漢字]
区点=2783 16進=3B73 シフトJIS=8E93
《常用音訓》シ/め/めす
《音読み》 シ
13画 隹部 [常用漢字]
区点=2783 16進=3B73 シフトJIS=8E93
《常用音訓》シ/め/めす
《音読み》 シ
 〈c
〈c ・c
・c 〉
《訓読み》 め/めす
《意味》
〉
《訓読み》 め/めす
《意味》
 {名}め。めす。鳥のめす。転じて、獣のめす。また、弱々しいものや小形のもののたとえ。〈対語〉→雄。「決雌雄=雌雄ヲ決ス」〔→史記〕
{名}め。めす。鳥のめす。転じて、獣のめす。また、弱々しいものや小形のもののたとえ。〈対語〉→雄。「決雌雄=雌雄ヲ決ス」〔→史記〕
 {形}めめしい。弱々しい。ひかえめな。「雌伏」「雌声」
《解字》
会意兼形声。此シは、足がちぐはぐに並んださまをあらわす会意文字。雌は「隹(とり)+音符此」で、左右の羽をちぐはぐに交差させて、尻シリをかくすめすの鳥。
《単語家族》
疵シ(ぎざぎざしたきず)
{形}めめしい。弱々しい。ひかえめな。「雌伏」「雌声」
《解字》
会意兼形声。此シは、足がちぐはぐに並んださまをあらわす会意文字。雌は「隹(とり)+音符此」で、左右の羽をちぐはぐに交差させて、尻シリをかくすめすの鳥。
《単語家族》
疵シ(ぎざぎざしたきず) 眥シ(上下のまぶたの交わるめじり)
眥シ(上下のまぶたの交わるめじり) 柴サイ(ふぞろいに束ねたたきぎ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
柴サイ(ふぞろいに束ねたたきぎ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
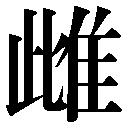 13画 隹部 [常用漢字]
区点=2783 16進=3B73 シフトJIS=8E93
《常用音訓》シ/め/めす
《音読み》 シ
13画 隹部 [常用漢字]
区点=2783 16進=3B73 シフトJIS=8E93
《常用音訓》シ/め/めす
《音読み》 シ
 〈c
〈c ・c
・c 〉
《訓読み》 め/めす
《意味》
〉
《訓読み》 め/めす
《意味》
 {名}め。めす。鳥のめす。転じて、獣のめす。また、弱々しいものや小形のもののたとえ。〈対語〉→雄。「決雌雄=雌雄ヲ決ス」〔→史記〕
{名}め。めす。鳥のめす。転じて、獣のめす。また、弱々しいものや小形のもののたとえ。〈対語〉→雄。「決雌雄=雌雄ヲ決ス」〔→史記〕
 {形}めめしい。弱々しい。ひかえめな。「雌伏」「雌声」
《解字》
会意兼形声。此シは、足がちぐはぐに並んださまをあらわす会意文字。雌は「隹(とり)+音符此」で、左右の羽をちぐはぐに交差させて、尻シリをかくすめすの鳥。
《単語家族》
疵シ(ぎざぎざしたきず)
{形}めめしい。弱々しい。ひかえめな。「雌伏」「雌声」
《解字》
会意兼形声。此シは、足がちぐはぐに並んださまをあらわす会意文字。雌は「隹(とり)+音符此」で、左右の羽をちぐはぐに交差させて、尻シリをかくすめすの鳥。
《単語家族》
疵シ(ぎざぎざしたきず) 眥シ(上下のまぶたの交わるめじり)
眥シ(上下のまぶたの交わるめじり) 柴サイ(ふぞろいに束ねたたきぎ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
柴サイ(ふぞろいに束ねたたきぎ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
漢字源に「め」で完全一致するの検索結果 1-7。
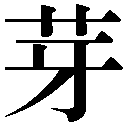 8画 艸部 [四年]
区点=1874 16進=326A シフトJIS=89E8
《常用音訓》ガ/め
《音読み》 ガ
8画 艸部 [四年]
区点=1874 16進=326A シフトJIS=89E8
《常用音訓》ガ/め
《音読み》 ガ 〉
《訓読み》 め/きざし/めぐむ/きざす
《名付け》 め・めい
《意味》
〉
《訓読み》 め/きざし/めぐむ/きざす
《名付け》 め・めい
《意味》