複数辞典一括検索+![]()
![]()
【折敷】🔗⭐🔉
【折敷】
オシキ〔国〕へぎ板を折り曲げて四方をかこんだ四角い盆。
【折衝】🔗⭐🔉
【折衝】
セツショウ  相手の出かた・攻撃・主張などをくじくこと。敵の攻撃に対抗して負けないこと。
相手の出かた・攻撃・主張などをくじくこと。敵の攻撃に対抗して負けないこと。 相手とのかけひき。
相手とのかけひき。
 相手の出かた・攻撃・主張などをくじくこと。敵の攻撃に対抗して負けないこと。
相手の出かた・攻撃・主張などをくじくこと。敵の攻撃に対抗して負けないこと。 相手とのかけひき。
相手とのかけひき。
【折簡】🔗⭐🔉
【折簡】
セツカン  紙を二つ切りにして手紙を書く。
紙を二つ切りにして手紙を書く。 転じて短い手紙のこと。
転じて短い手紙のこと。
 紙を二つ切りにして手紙を書く。
紙を二つ切りにして手紙を書く。 転じて短い手紙のこと。
転じて短い手紙のこと。
【折檻】🔗⭐🔉
【折檻】
セッカン  〈故事〉強くいさめること。▽漢の成帝が、朱雲のいさめに怒って、朝廷から引き出そうとしたとき、朱雲が御殿の檻(てすり)につかまっていたため、檻が折れた故事から。〔→漢書〕
〈故事〉強くいさめること。▽漢の成帝が、朱雲のいさめに怒って、朝廷から引き出そうとしたとき、朱雲が御殿の檻(てすり)につかまっていたため、檻が折れた故事から。〔→漢書〕 〔国〕きびしく責めしかること。多く、打ったりけったりしてしかることをいう。
〔国〕きびしく責めしかること。多く、打ったりけったりしてしかることをいう。
 〈故事〉強くいさめること。▽漢の成帝が、朱雲のいさめに怒って、朝廷から引き出そうとしたとき、朱雲が御殿の檻(てすり)につかまっていたため、檻が折れた故事から。〔→漢書〕
〈故事〉強くいさめること。▽漢の成帝が、朱雲のいさめに怒って、朝廷から引き出そうとしたとき、朱雲が御殿の檻(てすり)につかまっていたため、檻が折れた故事から。〔→漢書〕 〔国〕きびしく責めしかること。多く、打ったりけったりしてしかることをいう。
〔国〕きびしく責めしかること。多く、打ったりけったりしてしかることをいう。
【抓】🔗⭐🔉
【抓】
 7画
7画  部
区点=5720 16進=5934 シフトJIS=9D53
《音読み》 ソウ(サウ)
部
区点=5720 16進=5934 シフトJIS=9D53
《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(セウ)
/ショウ(セウ) 〈zhu
〈zhu 〉
《訓読み》 つまむ/つかむ/つねる
《意味》
〉
《訓読み》 つまむ/つかむ/つねる
《意味》
 {動}つまむ。つかむ。指先でつかむ。
{動}つまむ。つかむ。指先でつかむ。
 {動}かく。つめの先でひっかくこと。▽掻ソウ(かく)に当てた用法。
〔国〕つねる。指先でつねる。
《解字》
会意兼形声。爪ソウは、指先でつかむさま。抓は「手+音符爪」で、爪の動詞としての意味をあらわす。
《類義》
→摘
{動}かく。つめの先でひっかくこと。▽掻ソウ(かく)に当てた用法。
〔国〕つねる。指先でつねる。
《解字》
会意兼形声。爪ソウは、指先でつかむさま。抓は「手+音符爪」で、爪の動詞としての意味をあらわす。
《類義》
→摘
 7画
7画  部
区点=5720 16進=5934 シフトJIS=9D53
《音読み》 ソウ(サウ)
部
区点=5720 16進=5934 シフトJIS=9D53
《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(セウ)
/ショウ(セウ) 〈zhu
〈zhu 〉
《訓読み》 つまむ/つかむ/つねる
《意味》
〉
《訓読み》 つまむ/つかむ/つねる
《意味》
 {動}つまむ。つかむ。指先でつかむ。
{動}つまむ。つかむ。指先でつかむ。
 {動}かく。つめの先でひっかくこと。▽掻ソウ(かく)に当てた用法。
〔国〕つねる。指先でつねる。
《解字》
会意兼形声。爪ソウは、指先でつかむさま。抓は「手+音符爪」で、爪の動詞としての意味をあらわす。
《類義》
→摘
{動}かく。つめの先でひっかくこと。▽掻ソウ(かく)に当てた用法。
〔国〕つねる。指先でつねる。
《解字》
会意兼形声。爪ソウは、指先でつかむさま。抓は「手+音符爪」で、爪の動詞としての意味をあらわす。
《類義》
→摘
【択】🔗⭐🔉
【択】
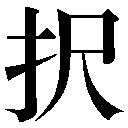 7画
7画  部 [常用漢字]
区点=3482 16進=4272 シフトJIS=91F0
【擇】旧字旧字
部 [常用漢字]
区点=3482 16進=4272 シフトJIS=91F0
【擇】旧字旧字
 16画
16画  部
区点=5804 16進=5A24 シフトJIS=9DA2
《常用音訓》タク
《音読み》 タク
部
区点=5804 16進=5A24 シフトJIS=9DA2
《常用音訓》タク
《音読み》 タク /ジャク(ヂャク)
/ジャク(ヂャク) 〈zh
〈zh i・z
i・z 〉
《訓読み》 えらぶ
《名付け》 えらむ
《意味》
〉
《訓読み》 えらぶ
《名付け》 えらむ
《意味》
 {動}えらぶ。一列に並べ、また順次に引き出して、適したものをえらび出す。〈類義語〉→選。「選択」「君子居必択郷=君子ハ居ルニ必ズ郷ヲ択ブ」〔→荀子〕
{動}えらぶ。一列に並べ、また順次に引き出して、適したものをえらび出す。〈類義語〉→選。「選択」「君子居必択郷=君子ハ居ルニ必ズ郷ヲ択ブ」〔→荀子〕
 {動}えらぶ。区別する。よしあしをわける。「牛羊何択焉=牛羊何ゾ択バン」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。擇の右側(音エキ)は「目+幸(てかせ)」の会意文字で、手かせをはめた容疑者を次々と並べて、犯人をえらび出す面通メンドオしのさまを示す。擇はそれを音符とし、手をそえた字で、次々と並べた中からえらび出すこと。
《単語家族》
驛(=駅。次々と並んだ宿場)
{動}えらぶ。区別する。よしあしをわける。「牛羊何択焉=牛羊何ゾ択バン」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。擇の右側(音エキ)は「目+幸(てかせ)」の会意文字で、手かせをはめた容疑者を次々と並べて、犯人をえらび出す面通メンドオしのさまを示す。擇はそれを音符とし、手をそえた字で、次々と並べた中からえらび出すこと。
《単語家族》
驛(=駅。次々と並んだ宿場) 澤(=沢。次々と水沼の並んださわ)と同系。
《類義》
→選
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
澤(=沢。次々と水沼の並んださわ)と同系。
《類義》
→選
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
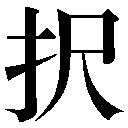 7画
7画  部 [常用漢字]
区点=3482 16進=4272 シフトJIS=91F0
【擇】旧字旧字
部 [常用漢字]
区点=3482 16進=4272 シフトJIS=91F0
【擇】旧字旧字
 16画
16画  部
区点=5804 16進=5A24 シフトJIS=9DA2
《常用音訓》タク
《音読み》 タク
部
区点=5804 16進=5A24 シフトJIS=9DA2
《常用音訓》タク
《音読み》 タク /ジャク(ヂャク)
/ジャク(ヂャク) 〈zh
〈zh i・z
i・z 〉
《訓読み》 えらぶ
《名付け》 えらむ
《意味》
〉
《訓読み》 えらぶ
《名付け》 えらむ
《意味》
 {動}えらぶ。一列に並べ、また順次に引き出して、適したものをえらび出す。〈類義語〉→選。「選択」「君子居必択郷=君子ハ居ルニ必ズ郷ヲ択ブ」〔→荀子〕
{動}えらぶ。一列に並べ、また順次に引き出して、適したものをえらび出す。〈類義語〉→選。「選択」「君子居必択郷=君子ハ居ルニ必ズ郷ヲ択ブ」〔→荀子〕
 {動}えらぶ。区別する。よしあしをわける。「牛羊何択焉=牛羊何ゾ択バン」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。擇の右側(音エキ)は「目+幸(てかせ)」の会意文字で、手かせをはめた容疑者を次々と並べて、犯人をえらび出す面通メンドオしのさまを示す。擇はそれを音符とし、手をそえた字で、次々と並べた中からえらび出すこと。
《単語家族》
驛(=駅。次々と並んだ宿場)
{動}えらぶ。区別する。よしあしをわける。「牛羊何択焉=牛羊何ゾ択バン」〔→孟子〕
《解字》
会意兼形声。擇の右側(音エキ)は「目+幸(てかせ)」の会意文字で、手かせをはめた容疑者を次々と並べて、犯人をえらび出す面通メンドオしのさまを示す。擇はそれを音符とし、手をそえた字で、次々と並べた中からえらび出すこと。
《単語家族》
驛(=駅。次々と並んだ宿場) 澤(=沢。次々と水沼の並んださわ)と同系。
《類義》
→選
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
澤(=沢。次々と水沼の並んださわ)と同系。
《類義》
→選
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源 ページ 1798。