複数辞典一括検索+![]()
![]()
【鄭樵】🔗⭐🔉
【鄭樵】
テイショウ〈人名〉1104〜62 南宋ナンソウの学者。字アザナは漁仲。著に『通志』がある。
【鄭燮】🔗⭐🔉
【鄭燮】
テイショウ〈人名〉1693〜1765 清シンの文人。江蘇コウソ省興化県の人。字アザナは克柔、号は板橋ハンキョウ。詩・書画に巧みであった。『板橋集』がある。
【鄭成功】🔗⭐🔉
【鄭成功】
テイセイコウ〈人名〉1624〜62 明ミン末の忠臣。日本の平戸で生まれた。鄭芝竜シリュウの子。明朝の復興のために清シンと戦い、南京ナンキンの攻略失敗後は台湾によって清に抵抗した。明朝の国姓の朱氏を賜ったので国姓爺コクセンヤともいわれる。
【酉】🔗⭐🔉
【酉】
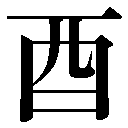 7画 酉部 [人名漢字]
区点=3851 16進=4653 シフトJIS=93D1
《音読み》 ユウ(イウ)
7画 酉部 [人名漢字]
区点=3851 16進=4653 シフトJIS=93D1
《音読み》 ユウ(イウ) /ユ
/ユ 〈y
〈y u〉
《訓読み》 とり
《名付け》 とり・なが・みのる
《意味》
{名}とり。十二支の十番め。▽時刻では午後六時、およびその前後の二時間、方角では西、動物では鶏に当てる。作物をおさめ酒を抽出する十月。のち、十二支の十番め(とり)に当てる。「酉時ユウジ(酉トリの刻)」「乙酉イツユウ」
《解字》
u〉
《訓読み》 とり
《名付け》 とり・なが・みのる
《意味》
{名}とり。十二支の十番め。▽時刻では午後六時、およびその前後の二時間、方角では西、動物では鶏に当てる。作物をおさめ酒を抽出する十月。のち、十二支の十番め(とり)に当てる。「酉時ユウジ(酉トリの刻)」「乙酉イツユウ」
《解字》
 象形。口の細い酒つぼを描いたもの。のち、酒に関する字の意符として用いる。
《単語家族》
由ユウ(口の細いつぼ)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
象形。口の細い酒つぼを描いたもの。のち、酒に関する字の意符として用いる。
《単語家族》
由ユウ(口の細いつぼ)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
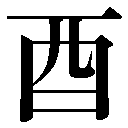 7画 酉部 [人名漢字]
区点=3851 16進=4653 シフトJIS=93D1
《音読み》 ユウ(イウ)
7画 酉部 [人名漢字]
区点=3851 16進=4653 シフトJIS=93D1
《音読み》 ユウ(イウ) /ユ
/ユ 〈y
〈y u〉
《訓読み》 とり
《名付け》 とり・なが・みのる
《意味》
{名}とり。十二支の十番め。▽時刻では午後六時、およびその前後の二時間、方角では西、動物では鶏に当てる。作物をおさめ酒を抽出する十月。のち、十二支の十番め(とり)に当てる。「酉時ユウジ(酉トリの刻)」「乙酉イツユウ」
《解字》
u〉
《訓読み》 とり
《名付け》 とり・なが・みのる
《意味》
{名}とり。十二支の十番め。▽時刻では午後六時、およびその前後の二時間、方角では西、動物では鶏に当てる。作物をおさめ酒を抽出する十月。のち、十二支の十番め(とり)に当てる。「酉時ユウジ(酉トリの刻)」「乙酉イツユウ」
《解字》
 象形。口の細い酒つぼを描いたもの。のち、酒に関する字の意符として用いる。
《単語家族》
由ユウ(口の細いつぼ)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
象形。口の細い酒つぼを描いたもの。のち、酒に関する字の意符として用いる。
《単語家族》
由ユウ(口の細いつぼ)と同系。
《熟語》
→下付・中付語
【酋】🔗⭐🔉
【酋】
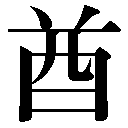 9画 酉部
区点=2922 16進=3D36 シフトJIS=8F55
《音読み》 シュウ
9画 酉部
区点=2922 16進=3D36 シフトJIS=8F55
《音読み》 シュウ /ジュ
/ジュ 〈qi
〈qi 〉
《意味》
〉
《意味》
 {名}酒をかもしてしぼる職人のかしら。とうじ。みきのかみ。「大酋タイシュウ(酒づくりの職人の長)」
{名}酒をかもしてしぼる職人のかしら。とうじ。みきのかみ。「大酋タイシュウ(酒づくりの職人の長)」
 {名}仲間や一族をひきしめるかしら。「巨酋キョシュウ(大親分)」「酋長シュウチョウ」
{名}仲間や一族をひきしめるかしら。「巨酋キョシュウ(大親分)」「酋長シュウチョウ」
 {動・名}発酵したもろみを袋に入れてしぼる。また、よくなじんでしぼれるようになった酒。▽「説文解字」に「酋繹酒也=酋トハ繹酒ナリ」とある。
{動・名}発酵したもろみを袋に入れてしぼる。また、よくなじんでしぼれるようになった酒。▽「説文解字」に「酋繹酒也=酋トハ繹酒ナリ」とある。
 シュウス{動}物事をしめくくる。しあげる。〈同義語〉→就。「似先公酋矣=先公ノゴトクニ酋セン」〔→詩経〕
《解字》
シュウス{動}物事をしめくくる。しあげる。〈同義語〉→就。「似先公酋矣=先公ノゴトクニ酋セン」〔→詩経〕
《解字》
 象形。つぼの中に酒がかもされて、外へ香気がもれ出るさまを描いたもの。シュウということばは、愁シュウ(心が小さくちぢむ)
象形。つぼの中に酒がかもされて、外へ香気がもれ出るさまを描いたもの。シュウということばは、愁シュウ(心が小さくちぢむ) 就(ひきしめる)などと同系で、もと、酒をしぼる、しぼり酒の意であったが、のち、それを酒の字で書きあらわし、酋はおもに、一族を引きしめるかしらの意に用いるようになった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
就(ひきしめる)などと同系で、もと、酒をしぼる、しぼり酒の意であったが、のち、それを酒の字で書きあらわし、酋はおもに、一族を引きしめるかしらの意に用いるようになった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
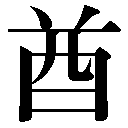 9画 酉部
区点=2922 16進=3D36 シフトJIS=8F55
《音読み》 シュウ
9画 酉部
区点=2922 16進=3D36 シフトJIS=8F55
《音読み》 シュウ /ジュ
/ジュ 〈qi
〈qi 〉
《意味》
〉
《意味》
 {名}酒をかもしてしぼる職人のかしら。とうじ。みきのかみ。「大酋タイシュウ(酒づくりの職人の長)」
{名}酒をかもしてしぼる職人のかしら。とうじ。みきのかみ。「大酋タイシュウ(酒づくりの職人の長)」
 {名}仲間や一族をひきしめるかしら。「巨酋キョシュウ(大親分)」「酋長シュウチョウ」
{名}仲間や一族をひきしめるかしら。「巨酋キョシュウ(大親分)」「酋長シュウチョウ」
 {動・名}発酵したもろみを袋に入れてしぼる。また、よくなじんでしぼれるようになった酒。▽「説文解字」に「酋繹酒也=酋トハ繹酒ナリ」とある。
{動・名}発酵したもろみを袋に入れてしぼる。また、よくなじんでしぼれるようになった酒。▽「説文解字」に「酋繹酒也=酋トハ繹酒ナリ」とある。
 シュウス{動}物事をしめくくる。しあげる。〈同義語〉→就。「似先公酋矣=先公ノゴトクニ酋セン」〔→詩経〕
《解字》
シュウス{動}物事をしめくくる。しあげる。〈同義語〉→就。「似先公酋矣=先公ノゴトクニ酋セン」〔→詩経〕
《解字》
 象形。つぼの中に酒がかもされて、外へ香気がもれ出るさまを描いたもの。シュウということばは、愁シュウ(心が小さくちぢむ)
象形。つぼの中に酒がかもされて、外へ香気がもれ出るさまを描いたもの。シュウということばは、愁シュウ(心が小さくちぢむ) 就(ひきしめる)などと同系で、もと、酒をしぼる、しぼり酒の意であったが、のち、それを酒の字で書きあらわし、酋はおもに、一族を引きしめるかしらの意に用いるようになった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
就(ひきしめる)などと同系で、もと、酒をしぼる、しぼり酒の意であったが、のち、それを酒の字で書きあらわし、酋はおもに、一族を引きしめるかしらの意に用いるようになった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源 ページ 4536。