複数辞典一括検索+![]()
![]()
乖異 カイイ🔗⭐🔉
【乖異】
カイイ 意見・態度などが互いに食い違う。気があわない。『乖違カイイ』
介 かい🔗⭐🔉
【介】
 4画 人部 [常用漢字]
区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE
《常用音訓》カイ
《音読み》 カイ
4画 人部 [常用漢字]
区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE
《常用音訓》カイ
《音読み》 カイ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)
《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし
《意味》
〉
《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)
《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし
《意味》

 カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕
カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕
 カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕
カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕
 {動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕
{動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕
 {名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」
{名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」
 {形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」
{形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」
 {形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」
{形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」
 {名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」
〔国〕すけ。
{名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」
〔国〕すけ。 四等官で、国司の第二位。
四等官で、国司の第二位。 かい(カヒ)。貝の当て字。
《解字》
かい(カヒ)。貝の当て字。
《解字》
 会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。
《単語家族》
界
会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。
《単語家族》
界 堺(わけめをつける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
堺(わけめをつける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 4画 人部 [常用漢字]
区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE
《常用音訓》カイ
《音読み》 カイ
4画 人部 [常用漢字]
区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE
《常用音訓》カイ
《音読み》 カイ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji 〉
《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)
《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし
《意味》
〉
《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)
《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし
《意味》

 カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕
カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕
 カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕
カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕
 {動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕
{動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕
 {名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」
{名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」
 {形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」
{形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」
 {形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」
{形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」
 {名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」
〔国〕すけ。
{名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」
〔国〕すけ。 四等官で、国司の第二位。
四等官で、国司の第二位。 かい(カヒ)。貝の当て字。
《解字》
かい(カヒ)。貝の当て字。
《解字》
 会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。
《単語家族》
界
会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。
《単語家族》
界 堺(わけめをつける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
堺(わけめをつける)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
介意 カイイ🔗⭐🔉
【介意】
カイイ・イニカイス 気にすること。『介心カイシン・介懐カイカイ』
会意 カイイ🔗⭐🔉
【会心】
カイシン・ココロニカイス  心の中ではっきりさとる。
心の中ではっきりさとる。 自分でした物事が気に入る。『会意カイイ』
自分でした物事が気に入る。『会意カイイ』
 心の中ではっきりさとる。
心の中ではっきりさとる。 自分でした物事が気に入る。『会意カイイ』
自分でした物事が気に入る。『会意カイイ』
会意 カイイ🔗⭐🔉
【会意】
カイイ  六書リクショの一つ。
六書リクショの一つ。 イニカイス「会心
イニカイス「会心 」と同じ。
」と同じ。
 六書リクショの一つ。
六書リクショの一つ。 イニカイス「会心
イニカイス「会心 」と同じ。
」と同じ。
効 かい🔗⭐🔉
【効】
 8画 力部 [五年]
区点=2490 16進=387A シフトJIS=8CF8
【效】旧字旧字
8画 力部 [五年]
区点=2490 16進=387A シフトJIS=8CF8
【效】旧字旧字
 10画 攴部
区点=5835 16進=5A43 シフトJIS=9DC1
《常用音訓》コウ/き…く
《音読み》 コウ(カウ)
10画 攴部
区点=5835 16進=5A43 シフトJIS=9DC1
《常用音訓》コウ/き…く
《音読み》 コウ(カウ) /ギョウ(ゲウ)
/ギョウ(ゲウ) 〈xi
〈xi o〉
《訓読み》 しるし/かい(かひ)/きく/いたす/ならう(ならふ)
《名付け》 いたる・かず・かた・すすむ・なり・のり
《意味》
o〉
《訓読み》 しるし/かい(かひ)/きく/いたす/ならう(ならふ)
《名付け》 いたる・かず・かた・すすむ・なり・のり
《意味》
 {名}しるし。かい(カヒ)。ききめ。「効果」「効験」
{名}しるし。かい(カヒ)。ききめ。「効果」「効験」
 コウアリ{動・形}きく。効果がある。ききめがある。また、そのさま。「不効、則治臣之罪=効アラズンバ、スナハチ臣ノ罪ヲ治ケ」〔→諸葛亮〕
コウアリ{動・形}きく。効果がある。ききめがある。また、そのさま。「不効、則治臣之罪=効アラズンバ、スナハチ臣ノ罪ヲ治ケ」〔→諸葛亮〕
 {動}いたす。力を出し尽くす。効果をあげる。「自効=ミヅカラ効ス」「効死而民弗去=死ヲ効スモ民去ラズ」〔→孟子〕
{動}いたす。力を出し尽くす。効果をあげる。「自効=ミヅカラ効ス」「効死而民弗去=死ヲ効スモ民去ラズ」〔→孟子〕
 {動}ならう(ナラフ)。まねる。▽本来は效と書くべきだが、効で代用した。〈同義語〉→傚コウ。「倣効」「尤而効之罪又甚焉=尤アリテコレニ効フハ罪又甚ダシ」〔→左伝〕
《解字》
会意兼形声。交は、人が足を交差させた姿。平行線をたどれば、どこまでも結果が出ない。交差してしめあげたところに結果が出る。効は「力+音符交」。実際の結果を出すよう努力すること。效は「攴(動詞記号)+音符交」で、二つのものを交差させて、てらしあわすこと。もとは別字。
《単語家族》
絞(しぼる、しぼり出す)や、校正の校(てらしあわせる。しめあげる)と同系。
《類義》
→習
《異字同訓》
きく。 効く「薬が効く。宣伝が効く。効き目がある」利く「左手が利く。目が利く。機転が利く」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{動}ならう(ナラフ)。まねる。▽本来は效と書くべきだが、効で代用した。〈同義語〉→傚コウ。「倣効」「尤而効之罪又甚焉=尤アリテコレニ効フハ罪又甚ダシ」〔→左伝〕
《解字》
会意兼形声。交は、人が足を交差させた姿。平行線をたどれば、どこまでも結果が出ない。交差してしめあげたところに結果が出る。効は「力+音符交」。実際の結果を出すよう努力すること。效は「攴(動詞記号)+音符交」で、二つのものを交差させて、てらしあわすこと。もとは別字。
《単語家族》
絞(しぼる、しぼり出す)や、校正の校(てらしあわせる。しめあげる)と同系。
《類義》
→習
《異字同訓》
きく。 効く「薬が効く。宣伝が効く。効き目がある」利く「左手が利く。目が利く。機転が利く」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 8画 力部 [五年]
区点=2490 16進=387A シフトJIS=8CF8
【效】旧字旧字
8画 力部 [五年]
区点=2490 16進=387A シフトJIS=8CF8
【效】旧字旧字
 10画 攴部
区点=5835 16進=5A43 シフトJIS=9DC1
《常用音訓》コウ/き…く
《音読み》 コウ(カウ)
10画 攴部
区点=5835 16進=5A43 シフトJIS=9DC1
《常用音訓》コウ/き…く
《音読み》 コウ(カウ) /ギョウ(ゲウ)
/ギョウ(ゲウ) 〈xi
〈xi o〉
《訓読み》 しるし/かい(かひ)/きく/いたす/ならう(ならふ)
《名付け》 いたる・かず・かた・すすむ・なり・のり
《意味》
o〉
《訓読み》 しるし/かい(かひ)/きく/いたす/ならう(ならふ)
《名付け》 いたる・かず・かた・すすむ・なり・のり
《意味》
 {名}しるし。かい(カヒ)。ききめ。「効果」「効験」
{名}しるし。かい(カヒ)。ききめ。「効果」「効験」
 コウアリ{動・形}きく。効果がある。ききめがある。また、そのさま。「不効、則治臣之罪=効アラズンバ、スナハチ臣ノ罪ヲ治ケ」〔→諸葛亮〕
コウアリ{動・形}きく。効果がある。ききめがある。また、そのさま。「不効、則治臣之罪=効アラズンバ、スナハチ臣ノ罪ヲ治ケ」〔→諸葛亮〕
 {動}いたす。力を出し尽くす。効果をあげる。「自効=ミヅカラ効ス」「効死而民弗去=死ヲ効スモ民去ラズ」〔→孟子〕
{動}いたす。力を出し尽くす。効果をあげる。「自効=ミヅカラ効ス」「効死而民弗去=死ヲ効スモ民去ラズ」〔→孟子〕
 {動}ならう(ナラフ)。まねる。▽本来は效と書くべきだが、効で代用した。〈同義語〉→傚コウ。「倣効」「尤而効之罪又甚焉=尤アリテコレニ効フハ罪又甚ダシ」〔→左伝〕
《解字》
会意兼形声。交は、人が足を交差させた姿。平行線をたどれば、どこまでも結果が出ない。交差してしめあげたところに結果が出る。効は「力+音符交」。実際の結果を出すよう努力すること。效は「攴(動詞記号)+音符交」で、二つのものを交差させて、てらしあわすこと。もとは別字。
《単語家族》
絞(しぼる、しぼり出す)や、校正の校(てらしあわせる。しめあげる)と同系。
《類義》
→習
《異字同訓》
きく。 効く「薬が効く。宣伝が効く。効き目がある」利く「左手が利く。目が利く。機転が利く」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{動}ならう(ナラフ)。まねる。▽本来は效と書くべきだが、効で代用した。〈同義語〉→傚コウ。「倣効」「尤而効之罪又甚焉=尤アリテコレニ効フハ罪又甚ダシ」〔→左伝〕
《解字》
会意兼形声。交は、人が足を交差させた姿。平行線をたどれば、どこまでも結果が出ない。交差してしめあげたところに結果が出る。効は「力+音符交」。実際の結果を出すよう努力すること。效は「攴(動詞記号)+音符交」で、二つのものを交差させて、てらしあわすこと。もとは別字。
《単語家族》
絞(しぼる、しぼり出す)や、校正の校(てらしあわせる。しめあげる)と同系。
《類義》
→習
《異字同訓》
きく。 効く「薬が効く。宣伝が効く。効き目がある」利く「左手が利く。目が利く。機転が利く」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
回易 カイエキ🔗⭐🔉
【回易】
カイエキ =廻易。宋ソウ代の慣例の一つで、外国へ使節を送るとき、自国の産物を持って行き、先方の物産と交換して帰国したこと。
回憶 カイオク🔗⭐🔉
【回想】
カイソウ・オモイヲメグラス 過ぎ去ったことを思いおこすこと。『回顧カイコ・回憶カイオク』
回隠 カイイン🔗⭐🔉
【回隠】
カイイン 不都合なことがあって、避け隠れること。
嵬峨 カイガ🔗⭐🔉
【嵬峨】
カイガ  たかくそびえたつさま。『嵬嵬カイカイ』
たかくそびえたつさま。『嵬嵬カイカイ』 酔って足もとのあぶないさま。
酔って足もとのあぶないさま。
 たかくそびえたつさま。『嵬嵬カイカイ』
たかくそびえたつさま。『嵬嵬カイカイ』 酔って足もとのあぶないさま。
酔って足もとのあぶないさま。
快意 カイイ🔗⭐🔉
【快心】
カイシン  さっぱりする。よい気持ちになる。『快意カイイ』
さっぱりする。よい気持ちになる。『快意カイイ』 〔国〕うまくいってじゅうぶんに満足する。
〔国〕うまくいってじゅうぶんに満足する。
 さっぱりする。よい気持ちになる。『快意カイイ』
さっぱりする。よい気持ちになる。『快意カイイ』 〔国〕うまくいってじゅうぶんに満足する。
〔国〕うまくいってじゅうぶんに満足する。
怪異 カイイ🔗⭐🔉
【怪異】
 カイイ
カイイ  見なれない。奇異なこと。不思議なこと。
見なれない。奇異なこと。不思議なこと。 化け物。
化け物。 ケイ〔国〕不思議なこと。
ケイ〔国〕不思議なこと。
 カイイ
カイイ  見なれない。奇異なこと。不思議なこと。
見なれない。奇異なこと。不思議なこと。 化け物。
化け物。 ケイ〔国〕不思議なこと。
ケイ〔国〕不思議なこと。
怪訝 カイガ🔗⭐🔉
【怪訝】
 カイガ あやしむ。
カイガ あやしむ。 ケゲン〔国〕不思議で、なっとくがいかないさま。
ケゲン〔国〕不思議で、なっとくがいかないさま。
 カイガ あやしむ。
カイガ あやしむ。 ケゲン〔国〕不思議で、なっとくがいかないさま。
ケゲン〔国〕不思議で、なっとくがいかないさま。
怪偉 カイイ🔗⭐🔉
【怪偉】
カイイ 並はずれていて雄大であること。
怪迂 カイウ🔗⭐🔉
【怪譎】
カイケツ ひねくれて、ふにおちない。不合理であやしい。『怪迂カイウ』
恢偉 カイイ🔗⭐🔉
【恢偉】
カイイ 大きくて、目だつさま。〈同義語〉魁偉。
懐王 カイオウ🔗⭐🔉
【懐王】
カイオウ(楚)〈人名〉戦国時代、楚ソの王。在位前328〜前298。威王の子。名は熊槐ユウカイ、懐は諡オクリナ。屈原の忠告をきかず秦シンの計略にのって斉セイとの同盟をやめ、斉が滅ぼされてから、秦王に会いにゆき殺された。→「巫山之夢フザンノユメ」
懐王 カイオウ🔗⭐🔉
【懐王】
カイオウ(秦)〈人名〉?〜前206?戦国時代の楚ソの懐王槐カイの孫で、項梁コウリョウにかつがれて楚の王になった。名は心。項羽が天下をとると義帝とされたが、すぐ暗殺された。
改意 カイイ🔗⭐🔉
【改心】
カイシン・ココロヲアラタム 心を入れ替える。悪い心をあらため直すこと。『改意カイイ』
改易 カイエキ🔗⭐🔉
【改易】
カイエキ  あらためる。かえる。『改変カイヘン』
あらためる。かえる。『改変カイヘン』 〔国〕江戸時代、武家に科した刑罰の一つ。家禄カロクを没収して、武士の身分を奪った。
〔国〕江戸時代、武家に科した刑罰の一つ。家禄カロクを没収して、武士の身分を奪った。
 あらためる。かえる。『改変カイヘン』
あらためる。かえる。『改変カイヘン』 〔国〕江戸時代、武家に科した刑罰の一つ。家禄カロクを没収して、武士の身分を奪った。
〔国〕江戸時代、武家に科した刑罰の一つ。家禄カロクを没収して、武士の身分を奪った。
改悪 カイアク🔗⭐🔉
【改悪】
カイアク  悪いことをあらためる。
悪いことをあらためる。 〔国〕あらためて悪くすること。▽改正することを、批判的な立場からいったことば。
〔国〕あらためて悪くすること。▽改正することを、批判的な立場からいったことば。
 悪いことをあらためる。
悪いことをあらためる。 〔国〕あらためて悪くすること。▽改正することを、批判的な立場からいったことば。
〔国〕あらためて悪くすること。▽改正することを、批判的な立場からいったことば。
晦菴 カイアン🔗⭐🔉
【晦菴】
カイアン 南宋ナンソウの儒学者の朱熹シュキが門弟に講義したへやの名。また、そのへやの名にちなんで、門弟たちが朱熹を呼んだ名。「晦庵」とも。
槐安夢 カイアンノユメ🔗⭐🔉
【槐安夢】
カイアンノユメ〈故事〉→「南柯夢ナンカノユメ」
槐位 カイイ🔗⭐🔉
【槐位】
カイイ 三公の位。『槐座カイザ・槐庭カイテイ・槐鉉カイゲン・槐鼎カイテイ』▽朝廷の庭に三本の槐エンジュを植え、三公がそれに向かってすわった故事や、鼎カナエの三本足や、鉉ゲン(鼎の耳の金具)を三公にたとえたことから。
櫂 かい🔗⭐🔉
海阿 カイア🔗⭐🔉
【海曲】
カイキョク  海が陸地にいりこんだところ。『海隅カイグウ・海阿カイア』
海が陸地にいりこんだところ。『海隅カイグウ・海阿カイア』 島。
島。
 海が陸地にいりこんだところ。『海隅カイグウ・海阿カイア』
海が陸地にいりこんだところ。『海隅カイグウ・海阿カイア』 島。
島。
海淵 カイエン🔗⭐🔉
【海淵】
カイエン 大洋の底の比較的せまい範囲が特に深くなっている部分。ふつう海溝カイコウの中にある。
魁偉 カイイ🔗⭐🔉
【瑰偉】
カイイ =魁偉。 すぐれていて珍しい。
すぐれていて珍しい。 人がらがひときわ目だってすぐれている。
人がらがひときわ目だってすぐれている。
 すぐれていて珍しい。
すぐれていて珍しい。 人がらがひときわ目だってすぐれている。
人がらがひときわ目だってすぐれている。
界域 カイイキ🔗⭐🔉
【界域】
カイイキ  さかい。境界。
さかい。境界。 区域。
区域。
 さかい。境界。
さかい。境界。 区域。
区域。
華夷 カイ🔗⭐🔉
【華夷】
カイ 中国と外国(=夷)。中国と、中国から遠くはなれた未開の民族が住んでいる所。〈類義語〉華裔カエイ。
解印 カイイン🔗⭐🔉
【解綬】
カイジュ・ジュヲトク 印綬インジュをとく。役人をやめること。『解印カイイン・解紐カイチュウ・解組カイソ・解亀カイキ』
解頤 カイイ🔗⭐🔉
【解頤】
カイイ・イヲトク〈故事〉下あごを外す。大笑いすること。また、非常に感心すること。▽「漢書」匡衡伝の「匡説詩解人頤=匡詩ヲ説キテ人ノ頤ヲ解ク」から。
貝 かい🔗⭐🔉
【貝】
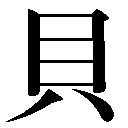 7画 貝部 [一年]
区点=1913 16進=332D シフトJIS=8A4C
《常用音訓》かい
《音読み》 バイ
7画 貝部 [一年]
区点=1913 16進=332D シフトJIS=8A4C
《常用音訓》かい
《音読み》 バイ /ハイ
/ハイ
 〈b
〈b i〉
《訓読み》 かい(かひ)
《名付け》 かい
《意味》
i〉
《訓読み》 かい(かひ)
《名付け》 かい
《意味》
 {名}かい(カヒ)。二枚貝や、まん中にわれめのある子安貝コヤスガイなど、二つにわれるかい。のち転じて、かいの総称。
{名}かい(カヒ)。二枚貝や、まん中にわれめのある子安貝コヤスガイなど、二つにわれるかい。のち転じて、かいの総称。
 {名}宝のこと。▽古代にはきれいな貝を装飾や賞品、貨幣のかわりに用いたことから。「宝貝」
{名}宝のこと。▽古代にはきれいな貝を装飾や賞品、貨幣のかわりに用いたことから。「宝貝」
 {名}貝多羅樹バイタラジュの略。多羅樹。▽インドの仏教徒はこの木の葉に経文を写したので、仏書を「貝葉バイヨウ」「貝葉経」という。
《解字》
{名}貝多羅樹バイタラジュの略。多羅樹。▽インドの仏教徒はこの木の葉に経文を写したので、仏書を「貝葉バイヨウ」「貝葉経」という。
《解字》
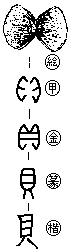 象形。われめのある子安貝、または二枚貝を描いたもの。▽古代には貝を交易の貨幣に用いたので、貨・財・費などの字に貝印を含む。
《単語家族》
敗ハイ(二つにやぶれる)
象形。われめのある子安貝、または二枚貝を描いたもの。▽古代には貝を交易の貨幣に用いたので、貨・財・費などの字に貝印を含む。
《単語家族》
敗ハイ(二つにやぶれる) 廃(われてだめになる)
廃(われてだめになる) 肺ハイ(左右二つにわれたはい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
肺ハイ(左右二つにわれたはい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
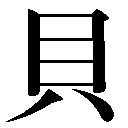 7画 貝部 [一年]
区点=1913 16進=332D シフトJIS=8A4C
《常用音訓》かい
《音読み》 バイ
7画 貝部 [一年]
区点=1913 16進=332D シフトJIS=8A4C
《常用音訓》かい
《音読み》 バイ /ハイ
/ハイ
 〈b
〈b i〉
《訓読み》 かい(かひ)
《名付け》 かい
《意味》
i〉
《訓読み》 かい(かひ)
《名付け》 かい
《意味》
 {名}かい(カヒ)。二枚貝や、まん中にわれめのある子安貝コヤスガイなど、二つにわれるかい。のち転じて、かいの総称。
{名}かい(カヒ)。二枚貝や、まん中にわれめのある子安貝コヤスガイなど、二つにわれるかい。のち転じて、かいの総称。
 {名}宝のこと。▽古代にはきれいな貝を装飾や賞品、貨幣のかわりに用いたことから。「宝貝」
{名}宝のこと。▽古代にはきれいな貝を装飾や賞品、貨幣のかわりに用いたことから。「宝貝」
 {名}貝多羅樹バイタラジュの略。多羅樹。▽インドの仏教徒はこの木の葉に経文を写したので、仏書を「貝葉バイヨウ」「貝葉経」という。
《解字》
{名}貝多羅樹バイタラジュの略。多羅樹。▽インドの仏教徒はこの木の葉に経文を写したので、仏書を「貝葉バイヨウ」「貝葉経」という。
《解字》
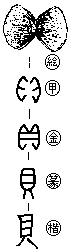 象形。われめのある子安貝、または二枚貝を描いたもの。▽古代には貝を交易の貨幣に用いたので、貨・財・費などの字に貝印を含む。
《単語家族》
敗ハイ(二つにやぶれる)
象形。われめのある子安貝、または二枚貝を描いたもの。▽古代には貝を交易の貨幣に用いたので、貨・財・費などの字に貝印を含む。
《単語家族》
敗ハイ(二つにやぶれる) 廃(われてだめになる)
廃(われてだめになる) 肺ハイ(左右二つにわれたはい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
肺ハイ(左右二つにわれたはい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
遐異 カイ🔗⭐🔉
【遐異】
カイ 世俗とかけ離れて異なっていること。
開化 カイカ🔗⭐🔉
【開化】
カイカ  人知が進歩して世が開けること。「文明開化」
人知が進歩して世が開けること。「文明開化」 カヲヒラク教化して世の中を進歩させる。
カヲヒラク教化して世の中を進歩させる。
 人知が進歩して世が開けること。「文明開化」
人知が進歩して世が開けること。「文明開化」 カヲヒラク教化して世の中を進歩させる。
カヲヒラク教化して世の中を進歩させる。
開可 カイカ🔗⭐🔉
【開可】
カイカ 許可する。
開運 カイウン🔗⭐🔉
【開運】
カイウン  ウンヲヒラク運をよいほうに向ける。
ウンヲヒラク運をよいほうに向ける。 運がよいほうに向かうこと。
運がよいほうに向かうこと。
 ウンヲヒラク運をよいほうに向ける。
ウンヲヒラク運をよいほうに向ける。 運がよいほうに向かうこと。
運がよいほうに向かうこと。
漢字源に「かい」で始まるの検索結果 1-47。もっと読み込む
 塾を開いて子弟を教える。「白首下帷復何益=白首帷ヲ下スモ復タ何ノ益カアラン」〔
塾を開いて子弟を教える。「白首下帷復何益=白首帷ヲ下スモ復タ何ノ益カアラン」〔 18画 木部
区点=6105 16進=5D25 シフトJIS=9F44
《音読み》
18画 木部
区点=6105 16進=5D25 シフトJIS=9F44
《音読み》