複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (12)
がさ🔗⭐🔉
がさ
(警察の隠語。サガス(捜)のサガの倒語)家宅捜索などのため警官が踏みこむこと。がさいれ。
が‐さ【画叉】グワ‥🔗⭐🔉
が‐さ【画叉】グワ‥
掛物掛け。
が‐さい【画才】グワ‥🔗⭐🔉
が‐さい【画才】グワ‥
絵をかく才能。
がさ‐いれ【がさ入れ】🔗⭐🔉
がさ‐いれ【がさ入れ】
家宅捜索をいう隠語。→がさ
がさ‐がさ🔗⭐🔉
がさ‐がさ
①薄くて乾いたものが触れ合って発するやや濁った音。「―と笹をかき分けて行く」
②表面が荒れているさま。うるおいがないさま。「手が―になる」
③性格や言動が粗野でがさつなさま。「―した物言い」
がさくさ‐りゅう【がさくさ流】‥リウ🔗⭐🔉
がさくさ‐りゅう【がさくさ流】‥リウ
我流で文字をまずく、また粗雑に書くこと。また、その書いた筆跡。
がさ‐ごそ🔗⭐🔉
がさ‐ごそ
乾いたものが触れ合って発するやや大きな音。また、人や動物がそのような音を立てて動き回るさま。「押入れを―と探す」
がさつ🔗⭐🔉
がさつ
言動が粗暴で、ぞんざいなさま。「彼のやりかたは―だ」「―な男」
がさ‐つ・く🔗⭐🔉
がさ‐つ・く
〔自五〕
①がさがさと音がする。
②おちつかない態度・挙動をする。
が‐さん【画賛・画讃】グワ‥🔗⭐🔉
が‐さん【画賛・画讃】グワ‥
画に因んで、その余白に書き添えた詩句など。讃。
が‐さん【臥蚕】グワ‥🔗⭐🔉
が‐さん【臥蚕】グワ‥
眠みんの時期にある蚕。
⇒がさん‐び【臥蚕眉】
がさん‐び【臥蚕眉】グワ‥🔗⭐🔉
がさん‐び【臥蚕眉】グワ‥
湾曲した臥蚕状の太くたくましい眉。若くして立身する相という。
⇒が‐さん【臥蚕】
大辞林の検索結果 (55)
かさ-の-いらつめ【笠女郎】🔗⭐🔉
かさ-の-いらつめ 【笠女郎】
女流万葉歌人。万葉集に大伴家持との相聞歌二九首が見える。軽妙機知に富んだ歌が多い。生没年未詳。
かさ-の-かなむら【笠金村】🔗⭐🔉
かさ-の-かなむら 【笠金村】
万葉歌人。従駕の歌が多く,聖武朝の宮廷歌人と思われる。万葉集に「笠朝臣金村歌集」の名が見えるが伝わらない。生没年未詳。
がさ🔗⭐🔉
がさ [0]
〔てきやなどの隠語。「さがす」の「さが」の倒語〕
家宅捜索。「―を入れる」「―入れ」
が-さ【画叉】🔗⭐🔉
が-さ グワ― [1] 【画叉】
「掛け竿(ザオ){(2)}」に同じ。
かさ-あて【笠当て】🔗⭐🔉
かさ-あて [2] 【笠当て】
かぶり笠の内側の,頭にあたる所につける小さい布団のようなもの。
かさい-かんちき【火災感知器】🔗⭐🔉
かさい-かんちき クワ― [6] 【火災感知器】
熱・煙などを感知し,火災の発生を自動的に発見して警報を鳴らす装置。火災報知機。
かさい-ほうちき【火災報知機】🔗⭐🔉
かさい-ほうちき クワ― [6] 【火災報知機】
(1)火災の発生とその場所を消防署などに知らせる装置。
(2)「火災感知器」の通称。
かさい-ほけん【火災保険】🔗⭐🔉
かさい-ほけん クワ― [4] 【火災保険】
火災によって生ずる財産上の損害を填補(テンポ)するための損害保険。建物・家具・商品・貴金属などが対象となる。
かさい-のり【葛西海苔】🔗⭐🔉
かさい-のり [2] 【葛西海苔】
葛西辺から産出した海苔。浅草海苔。
かさい-りんかい-こうえん【葛西臨海公園】🔗⭐🔉
かさい-りんかい-こうえん ―コウ ン 【葛西臨海公園】
東京都江戸川区,荒川・旧江戸川の河口の間にある都立公園。1989年(平成1)開園。水族園・野鳥園などがある。
ン 【葛西臨海公園】
東京都江戸川区,荒川・旧江戸川の河口の間にある都立公園。1989年(平成1)開園。水族園・野鳥園などがある。
 ン 【葛西臨海公園】
東京都江戸川区,荒川・旧江戸川の河口の間にある都立公園。1989年(平成1)開園。水族園・野鳥園などがある。
ン 【葛西臨海公園】
東京都江戸川区,荒川・旧江戸川の河口の間にある都立公園。1989年(平成1)開園。水族園・野鳥園などがある。
が-さい【画才】🔗⭐🔉
が-さい グワ― [0] 【画才】
絵をかく才能。
かさ-いし【笠石】🔗⭐🔉
かさ-いし [2] 【笠石】
(1)石灯籠の火袋の上にかぶせる笠状の石。笠。
(2)石や煉瓦などの塀や手すりの上にかぶせ,壁体の頂上を保護する石。冠石(カムリイシ)。
かさ-いた【笠板】🔗⭐🔉
かさ-いた [0][2] 【笠板】
戸袋などの上部にかぶせる板。
かさおか【笠岡】🔗⭐🔉
かさおか カサヲカ 【笠岡】
岡山県南西端,瀬戸内海に臨む市。鉄鋼・化学肥料・食品加工・家具製造などの工業が盛ん。カブトガニ繁殖地で有名。
かさ-おし【嵩押し】🔗⭐🔉
かさ-おし 【嵩押し】 (名・形動ナリ)
人を見下して偉そうにすること。無理押しすること。また,そのさま。「そのやうに―な事は言はぬものでござる/狂言・靭猿(鷺流)」
かさ-かき【瘡掻き】🔗⭐🔉
かさ-かき 【瘡掻き】
皮膚病にかかっている人。特に,梅毒にかかっている人。かさっかき。
がさ-がさ🔗⭐🔉
がさ-がさ
■一■ [1] (副)スル
(1)(多く「と」を伴って)乾いたものなどが触れ合って発する音を表す語。「かさかさ」よりやや重く騒がしい感じの音。「やぶを―と分けて進む」
(2)潤いがなくて荒れているさま。「―したてのひら」
(3)性質・態度が粗野なさま。「―した人」
■二■ [0] (形動)
{■一■(2)}に同じ。「かかとが―になる」
がさ-ごそ🔗⭐🔉
がさ-ごそ [1] (副)
枯れ葉・紙などが触れ合ったり,人や動物がそれらに触れた時に出る,やや濁った音を表す語。「―(と)音がしてリスが出て来た」
かさ-さつ【傘札】🔗⭐🔉
かさ-さつ [0] 【傘札】
1859年美濃国加納藩が,幕府の許可を得て発行した藩札。銀貨と兌換(ダカン)され,額面に傘の数量が記されている。
かさ-たて【傘立て】🔗⭐🔉
かさ-たて [2] 【傘立て】
玄関や建物の入り口に置いて,傘を入れる器具。傘入れ。
がさつ🔗⭐🔉
がさつ [0] (形動)[文]ナリ
細かいところに神経が行き届かず,雑で荒っぽいさま。「―な態度」「―者」
[派生] ――さ(名)
がさ-つ・く🔗⭐🔉
がさ-つ・く [0] (動カ五[四])
(1)がさがさ音がする。「紙袋を―・かせて菓子を取り出す」
(2)言動が粗野である。落ち着かない。「―・いた人」
かさとり-やま【笠取山】🔗⭐🔉
かさとり-やま 【笠取山】
京都府宇治市北東部にある山。海抜371メートル。((歌枕))「雨ふれど露ももらじを笠取の山はいかでかもみぢそめけむ/古今(秋下)」
かさなり【重なり】🔗⭐🔉
かさなり [0] 【重なり】
物が重なっていること。また,重なっている状態。
かさ-ぬい【笠縫い】🔗⭐🔉
かさ-ぬい ―ヌヒ [2] 【笠縫い】
菅笠(スゲガサ)などを糸で縫って作ること。また,その人。
かさね-うちき【重袿】🔗⭐🔉
かさね-うちき [4] 【重袿】
〔「かさねうちぎ」とも〕
平安時代,貴族の女性や女官が上衣(ウワギ)の下に何枚も重ねて着た袿。
→五つ衣(ギヌ)
かさね-おち【重ね落ち】🔗⭐🔉
かさね-おち [0] 【重ね落ち】
庭園の滝で,二重三重に段を設けてあるもの。
かさね-おりもの【重ね織物】🔗⭐🔉
かさね-おりもの [4][5] 【重ね織物】
たて糸・よこ糸あるいはその一方が二重以上に重なっている織物。布面には平織り・斜文織り・繻子(シユス)織りなどの組織が表れる。重ね織。
かさね-かわらけ【重ね土器】🔗⭐🔉
かさね-かわらけ ―カハラ― [4] 【重ね土器】
(1)いく枚も重ねた土器。
(2)三献(サンコン)・五献など定まった数の杯が終わって,さらに重ねる杯。
(3)旅立ちの時,前途の無事を祝って飲む酒。「たつ程の―なかりせば/永久百首」
かさね-く【重ね句】🔗⭐🔉
かさね-く [3] 【重ね句】
和歌で,一音以上の同じ音,または同じ句を重ねて用いること。また,その和歌。
かさね-ぬい【重ね縫い】🔗⭐🔉
かさね-ぬい ―ヌヒ [0] 【重ね縫い】
二枚の布の端を少し重ねて,その中央または両端を縫って接(ハ)ぐこと。重ね接ぎ。
かさね-の-いろめ【襲の色目】🔗⭐🔉
かさね-の-いろめ [7] 【襲の色目】
襲{(3)}の色の組み合わせ。それぞれの組み合わせに,山吹・葵・枯野などの名があり,季節・年齢などで使い分けた。
〔細部は各家,伝書などにより必ずしも一定ではない〕
かさね-もち【重ね餅】🔗⭐🔉
かさね-もち [3] 【重ね餅】
(1)鏡餅を二つ重ねたもの。
(2)相撲などで,組み合ったままで折り重なった状態になること。
かさね-もよう【重ね模様】🔗⭐🔉
かさね-もよう ―ヤウ [4] 【重ね模様】
地紋の上にさらに模様を重ねたもの。
かさね-やき【重ね焼き】🔗⭐🔉
かさね-やき [0] 【重ね焼き】
合成写真法の一種。二枚のネガ-フィルムを重ね合わせて印画紙やポジ-フィルムに焼き付けること。
かさのした【笠の下】🔗⭐🔉
かさのした 【笠の下】
狂言「地蔵舞(ジゾウマイ)」の別名。
かさ-の-ゆき【笠の雪】🔗⭐🔉
かさ-の-ゆき [1] 【笠の雪】
笠の上に降り積もった雪。重いもののたとえにもいう。
かさ-のり【傘海苔】🔗⭐🔉
かさ-のり [2] 【傘海苔】
緑藻類カサノリ目の小形の海藻。南西諸島の浅海や潮だまりに群生。体は単細胞で,傘・柄・仮根に分化。傘は径約1センチメートルで,鮮緑色。遺伝の研究材料などに使われる。
傘海苔
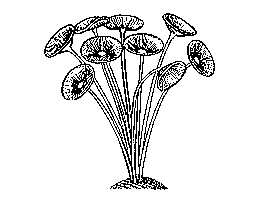 [図]
[図]
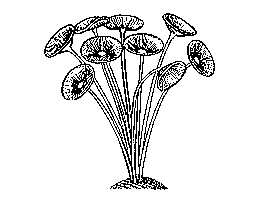 [図]
[図]
かさ-はり【傘張(り)】🔗⭐🔉
かさ-はり [2] 【傘張(り)】
から傘を張ること。また,その職人。
かさ-ほこ【傘鉾】🔗⭐🔉
かさ-ほこ [0] 【傘鉾】
祭礼の飾り物の一。大きな唐傘(カラカサ)の上に鉾・造花・鷺などを飾りつけたもの。京都の祇園会,東京の山王祭・神田祭のものが有名。かさぼこ。
かさ-もち【傘持(ち)】🔗⭐🔉
かさ-もち [2][0] 【傘持(ち)】
貴人の外出・行列などで,長柄の傘を持つ供人。
かさもり-おせん【笠森お仙】🔗⭐🔉
かさもり-おせん 【笠森お仙】
(1)江戸谷中,笠森稲荷地内の茶屋の娘。明和(1764-1772)頃の錦絵に描かれた柳腰で知られた美人。
(2)歌舞伎「怪談月笠森」の通称。世話物。河竹黙阿弥作。1865年江戸守田座初演。{(1)}をモデルとし,殺された姉の仇(アダ)を討つ筋に脚色。
が-さん【画賛・画讃】🔗⭐🔉
が-さん グワ― [0] 【画賛・画讃】
絵の余白などに書き添えられた文章・詩句。讃。
が-さん【臥蚕】🔗⭐🔉
が-さん グワ― [0] 【臥蚕】
脱皮のため眠期にある蚕(カイコ)。
がさん-び【臥蚕眉】🔗⭐🔉
がさん-び グワ― [2] 【臥蚕眉】
眠期にある蚕のような形をした太い眉。
がさん【峨山】🔗⭐🔉
がさん 【峨山】
(1275-1365) 鎌倉後期の曹洞宗の僧。総持寺第二世。名は韶碩(ジヨウセキ)。能登の人。比叡山で天台宗を学んだが,のち瑩山紹瑾(ケイザンジヨウキン)の弟子となり,曹洞宗に転じた。多くの門弟を育て,曹洞宗の発展に寄与。
かさんか-すいそ【過酸化水素】🔗⭐🔉
かさんか-すいそ クワサンクワ― [5] 【過酸化水素】
水素と酸素の化合物の一。化学式 H O
O 強い酸化性を示す。金属酸化物の触媒や酵素により分解されて酸素を放出する。純粋のものは粘性のある無色透明の爆発性液体でロケット燃料として重要。水溶液は漂白剤・消毒殺菌剤として用いる。
強い酸化性を示す。金属酸化物の触媒や酵素により分解されて酸素を放出する。純粋のものは粘性のある無色透明の爆発性液体でロケット燃料として重要。水溶液は漂白剤・消毒殺菌剤として用いる。
 O
O 強い酸化性を示す。金属酸化物の触媒や酵素により分解されて酸素を放出する。純粋のものは粘性のある無色透明の爆発性液体でロケット燃料として重要。水溶液は漂白剤・消毒殺菌剤として用いる。
強い酸化性を示す。金属酸化物の触媒や酵素により分解されて酸素を放出する。純粋のものは粘性のある無色透明の爆発性液体でロケット燃料として重要。水溶液は漂白剤・消毒殺菌剤として用いる。
かさんか-すいそ-すい【過酸化水素水】🔗⭐🔉
かさんか-すいそ-すい クワサンクワ― [7] 【過酸化水素水】
過酸化水素を含む水溶液。3パーセント水溶液は消毒薬,30パーセント水溶液は化学薬品として用いられる。
→オキシドール
かさんか-なまり【過酸化鉛】🔗⭐🔉
かさんか-なまり クワサンクワ― [5] 【過酸化鉛】
二酸化鉛のこと。化学式 PbO 酸素‐酸素の結合がないので過酸化物ではない。
酸素‐酸素の結合がないので過酸化物ではない。
 酸素‐酸素の結合がないので過酸化物ではない。
酸素‐酸素の結合がないので過酸化物ではない。
が-さんすい【画山水】🔗⭐🔉
が-さんすい グワ― [2] 【画山水】
山水の画。また,画中の山水。
かさん-めいし【可算名詞】🔗⭐🔉
かさん-めいし [4] 【可算名詞】
〔countable noun〕
英語の名詞を数の観点から分類した一。一定の形状や限界をもち,一つ,二つと数えられるものを指す名詞。単数と複数の対立があるもの。「机」「犬」「本」など。
⇔不可算名詞
がさい【画才】(和英)🔗⭐🔉
がさい【画才】
artistic talent.
広辞苑+大辞林に「がさ」で始まるの検索結果。