複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (9)
いちじゅう‐ぎり【一重切】‥ヂユウ‥🔗⭐🔉
いちじゅう‐ぎり【一重切】‥ヂユウ‥
竹の花入れの一種で、花を挿す窓が一つのもの。↔二重切
ひたえ【一重】ヒタヘ🔗⭐🔉
ひたえ【一重】ヒタヘ
一重ひとえの転。一説に、「ひたたへ(直 )」の約で、不純物のない白
)」の約で、不純物のない白 しろたえ。万葉集14「我が衣きぬに着きよらしもよ―と思へば」
しろたえ。万葉集14「我が衣きぬに着きよらしもよ―と思へば」
 )」の約で、不純物のない白
)」の約で、不純物のない白 しろたえ。万葉集14「我が衣きぬに着きよらしもよ―と思へば」
しろたえ。万葉集14「我が衣きぬに着きよらしもよ―と思へば」
ひと‐え【一重・単】‥ヘ🔗⭐🔉
ひと‐え【一重・単】‥ヘ
①そのものだけで、重ならないこと。
②花弁が重なっていないこと。また、その花弁。単弁。
③単衣ひとえぎぬ・単物ひとえものの略。〈[季]夏〉
⇒ひとえ‐うめ【一重梅】
⇒ひとえ‐おび【単帯・一重帯】
⇒ひとえ‐がさね【単襲】
⇒ひとえ‐ぎぬ【単衣】
⇒ひとえ‐ぐさ【一重草】
⇒ひとえ‐ざくら【一重桜】
⇒ひとえ‐つかい【単使】
⇒ひとえ‐ばおり【単羽織】
⇒ひとえ‐ばかま【単袴】
⇒ひとえ‐まぶた【一重瞼】
⇒ひとえ‐むすび【一重結び】
⇒ひとえ‐もの【単物】
ひとえ‐うめ【一重梅】‥ヘ‥🔗⭐🔉
ひとえ‐うめ【一重梅】‥ヘ‥
①単弁の梅。
②襲かさねの色目。表は白、裏は紅。
⇒ひと‐え【一重・単】
ひとえ‐おび【単帯・一重帯】‥ヘ‥🔗⭐🔉
ひとえ‐おび【単帯・一重帯】‥ヘ‥
裏地をつけない帯。普通には女性が夏季に用いるものをいい、太糸で地厚に織り上げた綴織つづれおり・博多織など。〈[季]夏〉
⇒ひと‐え【一重・単】
ひとえ‐ぐさ【一重草】‥ヘ‥🔗⭐🔉
ひとえ‐ぐさ【一重草】‥ヘ‥
海産の緑藻(アオサ藻綱)。日本の太平洋岸の暖海の潮間帯上部に生え、体は膜状で1層の細胞から成り、緑色。長さ5〜10センチメートル、扇形で丸く拡がる。アオノリとともに食用にする。
⇒ひと‐え【一重・単】
ひとえ‐ざくら【一重桜】‥ヘ‥🔗⭐🔉
ひとえ‐ざくら【一重桜】‥ヘ‥
単弁の桜。
⇒ひと‐え【一重・単】
ひとえ‐まぶた【一重瞼】‥ヘ‥🔗⭐🔉
ひとえ‐まぶた【一重瞼】‥ヘ‥
瞼に横襞よこひだがなく一重であるもの。ひとかわめ。
⇒ひと‐え【一重・単】
ひとえ‐むすび【一重結び】‥ヘ‥🔗⭐🔉
ひとえ‐むすび【一重結び】‥ヘ‥
紐の結び方の一つ。最も基本的な結び方で、引き締めると「結び留め」になる。
一重結び
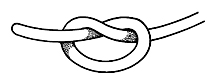 ⇒ひと‐え【一重・単】
⇒ひと‐え【一重・単】
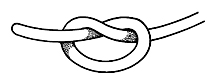 ⇒ひと‐え【一重・単】
⇒ひと‐え【一重・単】
大辞林の検索結果 (10)
いち-じゅう【一重】🔗⭐🔉
いち-じゅう ―ヂユウ [0] 【一重】
(1)ひとかさね。ひとえ。
(2)ひときわ程度がはなはだしいこと。「城へ切て入らんずる事は,又―の大事ぞ/太平記 34」
いちじゅう-ぎり【一重切り】🔗⭐🔉
いちじゅう-ぎり ―ヂユウ― [0] 【一重切り】
竹筒の花入れで,花を生ける窓が一つのもの。
ひと-え【一重・単】🔗⭐🔉
ひと-え ―ヘ [2] 【一重・単】
(1)重なっていないこと。そのものだけであること。「壁―をへだてるのみだ」
(2)花びらが重なっていないこと。また,その花。単弁。
(3)裏をつけないで仕立てた衣類,特に長着。ひとえもの。《単》 [季]夏。
→袷(アワセ)
(4)装束の下に着た肌着。平安末期,小袖肌着ができてからは,その上に重ねる中着となった。男は袴に着込め,女は袴の上からはおる。ひとえぎぬ。
ひとえ-うめ【一重梅】🔗⭐🔉
ひとえ-うめ ―ヘ― [3] 【一重梅】
(1)単弁の梅。
(2)襲(カサネ)の色目の名。表は白,裏は紅。一一月から二月に着用。雪の下の紅梅。
(3)梅紋の一。{(1)}を図案化したもの。
ひとえ-おび【単帯・一重帯】🔗⭐🔉
ひとえ-おび ―ヘ― [4] 【単帯・一重帯】
厚地の,かたい織物を用いて裏や芯(シン)をつけない帯。主に女帯で夏に用いる。[季]夏。
ひとえ-ぐさ【一重草】🔗⭐🔉
ひとえ-ぐさ ―ヘ― [3] 【一重草】
(1)キキョウの異名。
(2)緑藻類ヒビミドロ目の海藻。関東地方以西の太平洋沿岸の潮間帯上部に生育。葉状体は一層の細胞からなり,扇形ないし円形の薄い膜質で,黄緑色を呈する。食用として養殖し,青のり・佃煮とする。
ひとえ-ざくら【一重桜】🔗⭐🔉
ひとえ-ざくら ―ヘ― [4] 【一重桜】
単弁の桜。
ひとえ-まぶた【一重瞼】🔗⭐🔉
ひとえ-まぶた ―ヘ― [4] 【一重瞼】
横ひだのない,ひとえの瞼。ひとかわめ。
ひとえ-むすび【一重結び】🔗⭐🔉
ひとえ-むすび ―ヘ― [4] 【一重結び】
紐(ヒモ)の結び方の一。輪を作り,端を通して締めるもの。
ひとえ【一重の】(和英)🔗⭐🔉
ひとえ【一重の】
single.→英和
一重まぶた a single-edged eyelid.
広辞苑+大辞林に「一重」で始まるの検索結果。