複数辞典一括検索+![]()
![]()
い-だ【委蛇・逶 】🔗⭐🔉
】🔗⭐🔉
い-だ  ― [1] 【委蛇・逶
― [1] 【委蛇・逶 】 (ト|タル)[文]形動タリ
「いい(委蛇)」に同じ。「―たる細径は荊榛(ケイシン)の間に通ぜり/即興詩人(鴎外)」
】 (ト|タル)[文]形動タリ
「いい(委蛇)」に同じ。「―たる細径は荊榛(ケイシン)の間に通ぜり/即興詩人(鴎外)」
 ― [1] 【委蛇・逶
― [1] 【委蛇・逶 】 (ト|タル)[文]形動タリ
「いい(委蛇)」に同じ。「―たる細径は荊榛(ケイシン)の間に通ぜり/即興詩人(鴎外)」
】 (ト|タル)[文]形動タリ
「いい(委蛇)」に同じ。「―たる細径は荊榛(ケイシン)の間に通ぜり/即興詩人(鴎外)」
い-だい【医大】🔗⭐🔉
い-だい [0] 【医大】
「医科大学」の略。
い-だい【遺題】🔗⭐🔉
い-だい  ― [0] 【遺題】
江戸時代,和算家が数学書の中に解答をつけず問題だけを提出して,後世の人にその解答を求めた問題。「―承継」
― [0] 【遺題】
江戸時代,和算家が数学書の中に解答をつけず問題だけを提出して,後世の人にその解答を求めた問題。「―承継」
 ― [0] 【遺題】
江戸時代,和算家が数学書の中に解答をつけず問題だけを提出して,後世の人にその解答を求めた問題。「―承継」
― [0] 【遺題】
江戸時代,和算家が数学書の中に解答をつけず問題だけを提出して,後世の人にその解答を求めた問題。「―承継」
い-だい【偉大】🔗⭐🔉
い-だい  ― [0] 【偉大】 (形動)[文]ナリ
優れて立派なさま。優れて大きいさま。「―な人物」「―な業績」
[派生] ――さ(名)
― [0] 【偉大】 (形動)[文]ナリ
優れて立派なさま。優れて大きいさま。「―な人物」「―な業績」
[派生] ――さ(名)
 ― [0] 【偉大】 (形動)[文]ナリ
優れて立派なさま。優れて大きいさま。「―な人物」「―な業績」
[派生] ――さ(名)
― [0] 【偉大】 (形動)[文]ナリ
優れて立派なさま。優れて大きいさま。「―な人物」「―な業績」
[派生] ――さ(名)
いだいけ【韋提希】🔗⭐🔉
いだいけ  ダイケ 【韋提希】
〔梵 Vaideh
ダイケ 【韋提希】
〔梵 Vaideh 〕
インド,マガダ国の頻婆娑羅(ビンバシヤラ)王の后。釈尊と同時代の人。息子の阿闍世(アジヤセ)によって牢に幽閉された時,釈尊の説法を願った。釈尊は,彼女のために「観無量寿経」を説いたという。
〕
インド,マガダ国の頻婆娑羅(ビンバシヤラ)王の后。釈尊と同時代の人。息子の阿闍世(アジヤセ)によって牢に幽閉された時,釈尊の説法を願った。釈尊は,彼女のために「観無量寿経」を説いたという。
 ダイケ 【韋提希】
〔梵 Vaideh
ダイケ 【韋提希】
〔梵 Vaideh 〕
インド,マガダ国の頻婆娑羅(ビンバシヤラ)王の后。釈尊と同時代の人。息子の阿闍世(アジヤセ)によって牢に幽閉された時,釈尊の説法を願った。釈尊は,彼女のために「観無量寿経」を説いたという。
〕
インド,マガダ国の頻婆娑羅(ビンバシヤラ)王の后。釈尊と同時代の人。息子の阿闍世(アジヤセ)によって牢に幽閉された時,釈尊の説法を願った。釈尊は,彼女のために「観無量寿経」を説いたという。
いたいけ・す【幼気す】🔗⭐🔉
いたいけ・す 【幼気す】 (動サ変)
かわいく見える。「―・したる小女房/平家 6」
いたいけ-な・い【幼気ない】🔗⭐🔉
いたいけ-な・い [5] 【幼気ない】 (形)
〔形容動詞「いたいけ」の形容詞化。「ない」は接尾語〕
いたいけである。「まだ―・い子供だ」
いたいけ-ら・し【幼気らし】🔗⭐🔉
いたいけ-ら・し 【幼気らし】 (形シク)
いかにもかわいげである。「孫を持つたも名ばかりで,―・しい顔も見ず/浄瑠璃・賀古教信」
いた-え【板絵】🔗⭐🔉
いた-え ― [2][0] 【板絵】
木板・銅板・カンバスなどに描かれた絵画作品の総称。狭義には,中世ヨーロッパで祭壇画として発達した,板に描いた絵をいう。
[2][0] 【板絵】
木板・銅板・カンバスなどに描かれた絵画作品の総称。狭義には,中世ヨーロッパで祭壇画として発達した,板に描いた絵をいう。
 [2][0] 【板絵】
木板・銅板・カンバスなどに描かれた絵画作品の総称。狭義には,中世ヨーロッパで祭壇画として発達した,板に描いた絵をいう。
[2][0] 【板絵】
木板・銅板・カンバスなどに描かれた絵画作品の総称。狭義には,中世ヨーロッパで祭壇画として発達した,板に描いた絵をいう。
いた-えん【板縁】🔗⭐🔉
いた-えん [2] 【板縁】
板張りの縁側。
いた-おい【板笈】🔗⭐🔉
いた-おい ―オヒ [2] 【板笈】
笈の一種。普通の笈のように箱形でなく,薄板の左右両端に太い縁をつけ,旅行用具などを結びつけて背に負う。修験者(シユゲンジヤ)が用いる。
いた-おこし【板起(こ)し】🔗⭐🔉
いた-おこし [3] 【板起(こ)し】
ろくろで形を整えた器を取り離す時に,糸切りを用いず,竹べらなどではがすこと。
い-たお・す【射倒す】🔗⭐🔉
い-たお・す ―タフス [3][0] 【射倒す】 (動サ五[四])
矢を射あてて相手を倒す。「敵の大将を―・す」
いた-おもり【板錘】🔗⭐🔉
いた-おもり [3] 【板錘】
釣りの錘の一。鉛を薄い板状にしたもので,必要量だけ切って使う。板鉛。
いだか・う【抱かふ】🔗⭐🔉
いだか・う イダカフ 【抱かふ】 (動ハ下二)
だきかかえる。「女,塗籠(ヌリゴメ)の内に,かぐや姫を―・へてをり/竹取」
いた-かましき【板釜敷】🔗⭐🔉
いた-かましき [3] 【板釜敷】
茶道で,水屋で使う釜敷。五寸(=約15センチメートル)四方の桐(キリ)や朴(ホオ)の板のかどを切り,中央に丸い穴をあけたもの。炉で炭をつぐ時,釜をのせる。
いた-きれ【板切れ】🔗⭐🔉
いた-きれ [0] 【板切れ】
板の断片。木材のきれはし。
いたく-せい【依託生】🔗⭐🔉
いたく-せい [2] 【依託生】
「依託学生」に同じ。
いたく-かこう【委託加工】🔗⭐🔉
いたく-かこう  ― [4] 【委託加工】
原料を提供して,加工を委託すること。
― [4] 【委託加工】
原料を提供して,加工を委託すること。
 ― [4] 【委託加工】
原料を提供して,加工を委託すること。
― [4] 【委託加工】
原料を提供して,加工を委託すること。
い-だく【唯諾】🔗⭐🔉
い-だく  ― [0] 【唯諾】 (名)スル
承諾の返事をすること。「何の目的もなく,在来の倫理に―し/文学史骨(透谷)」
― [0] 【唯諾】 (名)スル
承諾の返事をすること。「何の目的もなく,在来の倫理に―し/文学史骨(透谷)」
 ― [0] 【唯諾】 (名)スル
承諾の返事をすること。「何の目的もなく,在来の倫理に―し/文学史骨(透谷)」
― [0] 【唯諾】 (名)スル
承諾の返事をすること。「何の目的もなく,在来の倫理に―し/文学史骨(透谷)」
いだ・く【抱く・懐く】🔗⭐🔉
いだ・く [2] 【抱く・懐く】 (動カ五[四])
(1)「だく{(1)}」の文語的な言い方。「二つの半島に―・かれた静かな湾」「大自然の懐に―・かれて暮らす」「子を―・きつつおりのりす/土左」
(2)ある考え・気持ちを心の中にもつ。「理想を―・く」「不安を―・く」「相手に不信感を―・かせる」
[可能] いだける
い-たけ【居丈】🔗⭐🔉
い-たけ  ― 【居丈】
〔「いだけ」とも〕
座っている時の背の高さ。「御髪は―にて,いとけ高う清らなり/宇津保(国譲下)」
― 【居丈】
〔「いだけ」とも〕
座っている時の背の高さ。「御髪は―にて,いとけ高う清らなり/宇津保(国譲下)」
 ― 【居丈】
〔「いだけ」とも〕
座っている時の背の高さ。「御髪は―にて,いとけ高う清らなり/宇津保(国譲下)」
― 【居丈】
〔「いだけ」とも〕
座っている時の背の高さ。「御髪は―にて,いとけ高う清らなり/宇津保(国譲下)」
いたける-の-みこと【五十猛命】🔗⭐🔉
いたける-の-みこと 【五十猛命】
日本書紀の神話の神。素戔嗚尊(スサノオノミコト)の子。新羅(シラギ)から樹種を持ち帰り,大八洲(オオヤシマ)国全土に植えた。
いだし【出】🔗⭐🔉
いだし 【出】
(動詞「出だす」の連用形)
いだし-あこめ【出衵】🔗⭐🔉
いだし-あこめ 【出衵】
「いだしぎぬ{(1)}」に同じ。「直衣(ノウシ)のながやかにめでたき裾より,青き打たる―して/宇治拾遺 11」
いだし-うた【出歌】🔗⭐🔉
いだし-うた 【出歌】
五節(ゴセチ)の舞のときに歌う歌。
いだし-うちき【出袿】🔗⭐🔉
いだし-うちき [4] 【出袿】
「いだしぎぬ{(1)}」に同じ。「桜の直衣(ノウシ)に―して/枕草子 4」
いだし-ぎぬ【出衣】🔗⭐🔉
いだし-ぎぬ 【出衣】
(1)下着の衵(アコメ)や袿(ウチキ)の裾をのぞかせて着ること。古くは指貫(サシヌキ)の裾から,のちには直衣(ノウシ)や狩衣の前裾からのぞかせた。出褄(イダシヅマ)。出衵(イダシアコメ)。出袿(イダシウチキ)。
(2)牛車(ギツシヤ)の下簾(シタスダレ)や御簾(ミス)の下から女房装束の袖口や裳(モ)の裾などを出すこと。また,その衣。うちいでのきぬ。おしいだしぎぬ。「下簾より―をいだして女房車の体に見せ/太平記 2」
出衣(1)
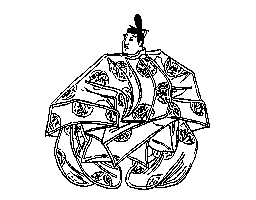 [図]
[図]
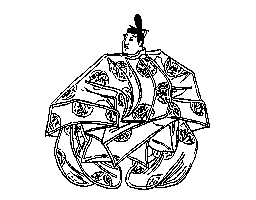 [図]
[図]
いだし-ぐるま【出車】🔗⭐🔉
いだし-ぐるま 【出車】
女房たちが出衣(イダシギヌ)をして乗っている牛車(ギツシヤ)。「むかへの―十二,本所の人々乗せてなむありける/源氏(宿木)」
いだし-づま【出褄】🔗⭐🔉
いだし-づま 【出褄】
「いだしぎぬ{(1)}」に同じ。「上達部の―の姿ども目とまりてぞ見ゆる/弁内侍日記」
いだし-ふづくえ【出文机】🔗⭐🔉
いだし-ふづくえ 【出文机】
中世,僧侶・貴族などの住宅に壁から張り出して設けられた,作りつけの机。また,付け書院の古称。
いだし-ふみだな【出文棚】🔗⭐🔉
いだし-ふみだな 【出文棚】
「出文机(イダシフヅクエ)」に同じ。
いたし-かた【致し方】🔗⭐🔉
いたし-かた [0] 【致し方】
する方法。しかた。「―ございません」
い-だ・す【鋳出す】🔗⭐🔉
い-だ・す [2] 【鋳出す】 (動サ五[四])
溶かした金属を鋳型に流して器物を作り出す。「仏像を―・す」
いだ・す【出だす】🔗⭐🔉
いだ・す 【出だす】 (動サ四)
(1)人や物を中から外へ移動させる。「帳の内よりも―・さずいつき養ふ/竹取」
(2)かげに隠れていたものを,表面に現れるようにする。目に見えるようにする。「杯(サカズキ)の皿に歌を書きて―・したり/伊勢 69」「世の人聞きにこの事―・さじ,とせちにこめ給へど/源氏(行幸)」
(3)それまでなかったものを,出現・発生させる。「きのふ事―・したりし童(ワラワベ)捕ふべし/大鏡(伊尹)」
(4)声に出す。吟じる。「高砂を,―・して謡ふ/源氏(賢木)」
(5)動詞の連用形の下に付いて,複合動詞を作る。(ア)中から外に向かって動作を行う意を表す。「言い―・す」「見―・す」(イ)ある動作を開始するという意を表す。…し始める。「走り―・す」
〔自動詞「出(イ)ず」に対する他動詞。口語では「だす」となる〕
いたたまら ない【居た堪らない】🔗⭐🔉
ない【居た堪らない】🔗⭐🔉
いたたまら ない
ない  タタマラ― 【居た堪らない】 (連語)
「いたたまれない」に同じ。「―
タタマラ― 【居た堪らない】 (連語)
「いたたまれない」に同じ。「― ない思い」
ない思い」
 ない
ない  タタマラ― 【居た堪らない】 (連語)
「いたたまれない」に同じ。「―
タタマラ― 【居た堪らない】 (連語)
「いたたまれない」に同じ。「― ない思い」
ない思い」
いたち-うお【鼬魚】🔗⭐🔉
いたち-うお ―ウヲ [3] 【鼬魚】
スズキ目の海魚。全長約60センチメートル。体は太くて後半は側扁し,背びれ・尾びれ・尻びれが連続している。体色は茶褐色でイタチの毛色に似ており,吻(フン)と下顎(カガク)に一二本のひげがある。食用。南日本に分布。オキナマズ。ウミナマズ。
いた-ちん【板賃】🔗⭐🔉
いた-ちん [2] 【板賃】
(1)版木の彫刻代金。「黄楊(ツゲ)はかへつて―桜に五割増ぢや/浮世草子・元禄太平記」
(2)版木の使用料。
い-だつ【遺脱】🔗⭐🔉
い-だつ  ― [0] 【遺脱】 (名)スル
漏れ落ちること。遺漏(イロウ)。
― [0] 【遺脱】 (名)スル
漏れ落ちること。遺漏(イロウ)。
 ― [0] 【遺脱】 (名)スル
漏れ落ちること。遺漏(イロウ)。
― [0] 【遺脱】 (名)スル
漏れ落ちること。遺漏(イロウ)。
いたつ・く【労く】🔗⭐🔉
いたつ・く 【労く】 (動カ四)
〔「いたづく」とも〕
(1)苦労して物事に当たる。努める。「とかうものすることなど―・く人多くて/蜻蛉(上)」
(2)世話をする。いたわる。「かくてねむごろに―・きけり/伊勢 69」
(3)病気になる。疲れる。「イタヅキ参ラセソロ/日葡」
い-た・てる【射立てる】🔗⭐🔉
い-た・てる [3][0] 【射立てる】 (動タ下一)[文]タ下二 いた・つ
(1)相手に向けて盛んに矢を射る。「敵に―・てられて敗走する」
(2)体に矢を突き立たせる。「矢七つ八つ―・てられて,立ち死ににこそ死にけれ/平家 7」
いだてん【韋駄天】🔗⭐🔉
いだてん  ダ― [0] 【韋駄天】
〔梵 Skanda 塞建陀と音訳〕
(1)バラモン教の神。シバ神の子。仏教に入って仏法,特に僧や寺院の守護神。捷疾鬼(シヨウシツキ)が仏舎利を持って逃げ去ったとき,これを追って取り戻したことからよく走る神として知られる。増長天八将軍の一。四天王三十二将の長。
(2)足の速い人。
ダ― [0] 【韋駄天】
〔梵 Skanda 塞建陀と音訳〕
(1)バラモン教の神。シバ神の子。仏教に入って仏法,特に僧や寺院の守護神。捷疾鬼(シヨウシツキ)が仏舎利を持って逃げ去ったとき,これを追って取り戻したことからよく走る神として知られる。増長天八将軍の一。四天王三十二将の長。
(2)足の速い人。
 ダ― [0] 【韋駄天】
〔梵 Skanda 塞建陀と音訳〕
(1)バラモン教の神。シバ神の子。仏教に入って仏法,特に僧や寺院の守護神。捷疾鬼(シヨウシツキ)が仏舎利を持って逃げ去ったとき,これを追って取り戻したことからよく走る神として知られる。増長天八将軍の一。四天王三十二将の長。
(2)足の速い人。
ダ― [0] 【韋駄天】
〔梵 Skanda 塞建陀と音訳〕
(1)バラモン教の神。シバ神の子。仏教に入って仏法,特に僧や寺院の守護神。捷疾鬼(シヨウシツキ)が仏舎利を持って逃げ去ったとき,これを追って取り戻したことからよく走る神として知られる。増長天八将軍の一。四天王三十二将の長。
(2)足の速い人。
いだてん-ばしり【韋駄天走り】🔗⭐🔉
いだてん-ばしり  ダ― [5] 【韋駄天走り】
(韋駄天のように)非常に速く走ること。
ダ― [5] 【韋駄天走り】
(韋駄天のように)非常に速く走ること。
 ダ― [5] 【韋駄天走り】
(韋駄天のように)非常に速く走ること。
ダ― [5] 【韋駄天走り】
(韋駄天のように)非常に速く走ること。
いた-ふね【板舟】🔗⭐🔉
いた-ふね [3][0] 【板舟】
(1)泥深い田で,苗や稲をのせて運ぶ,薄板で作った小舟。いたぶね。
(2)江戸時代から昭和初期,東京日本橋の魚市場で,販売する魚をのせた板。初めは縁の浅い舟形であった。
いた-ま【板間】🔗⭐🔉
いた-ま [0][2] 【板間】
(1)板敷の部屋。板の間。
(2)板葺(ブ)きの屋根の,板と板とのすき間。「ふるき軒の―よりもる月影ぞくまもなき/平家 3」
いた-まさ【板柾】🔗⭐🔉
いた-まさ [0] 【板柾】
木目の通った板。柾目(マサメ)の板。
いたみ-もの【痛み物】🔗⭐🔉
いたみ-もの [4][0] 【痛み物】
(1)壊れたもの。腐ったもの。
(2)壊れやすいもの。腐りやすいもの。
いたみ-わけ【傷み分け・痛み分け】🔗⭐🔉
いたみ-わけ [0] 【傷み分け・痛み分け】
相撲で,取組中に一方または両方の力士が負傷して引き分けとなること。
いたみ-ふう【伊丹風】🔗⭐🔉
いたみ-ふう 【伊丹風】
摂津伊丹に栄えた俳諧の一派。池田宗旦を祖とし,口語を使った奇抜な作風。上島鬼貫(オニツラ)を中心に森本蟻道・上島才人・鹿島後村・森本百丸らが集まったが,鬼貫の没後衰えた。
いたみ-もろはく【伊丹諸白】🔗⭐🔉
いたみ-もろはく 【伊丹諸白】
「伊丹酒」に同じ。
いたみ-まんさく【伊丹万作】🔗⭐🔉
いたみ-まんさく 【伊丹万作】
(1900-1946) 映画監督。愛媛県生まれ。本名,池内義豊。「国士無双」「赤西蠣太(カキタ)」などの演出,「無法松の一生」などの脚本,病床の映画随筆などで,感性と知性を評価される。
いため-もくはん【板目木版】🔗⭐🔉
いため-もくはん [4] 【板目木版】
板目彫りによる木版。浮世絵版画はその代表例。
⇔木口(コグチ)木版
いため-に【炒め煮】🔗⭐🔉
いため-に [0] 【炒め煮】
材料を油で炒めてから汁を入れ,味つけをして煮込む調理法。
いため-もの【炒め物】🔗⭐🔉
いため-もの [0][5] 【炒め物】
油で炒めた料理の総称。
いた-も【甚も】🔗⭐🔉
いた-も 【甚も】
〔「いた」は形容詞「いたし」の語幹。「も」は係助詞〕
はなはだしくも。「吾(ア)が思(モ)ふ心―すべなし/万葉 3785」
いた-もと【板元】🔗⭐🔉
いた-もと [0] 【板元】
(1)〔「板」は俎板(マナイタ)の意〕
料理屋などの調理場。また,料理人。板前。板場。
(2)「板頭(イタガシラ)」に同じ。
いた-もの【板物】🔗⭐🔉
いた-もの [0][2] 【板物】
(1)板を芯(シン)にして平たく畳んだ織物。いたのもの。
⇔巻物
(2)重箱・膳(ゼン)・広蓋(ヒロブタ)など,板を組み合わせて作った漆器の総称。
いた-やかた【板屋形】🔗⭐🔉
いた-やかた [3] 【板屋形】
牛車(ギツシヤ)の屋形の一。屋根を板で作った粗末なもの。
いた-やき【板焼(き)】🔗⭐🔉
いた-やき [0] 【板焼(き)】
ガン・カモなどの肉を薄切りにして,醤油・味醂(ミリン)などで下味をつけ,杉板にのせて焼いた料理。片木(ヘギ)焼き。
いた-やね【板屋根】🔗⭐🔉
いた-やね [3][0] 【板屋根】
板で葺(フ)いた屋根。板葺きの屋根。
いた-よせ【板寄せ】🔗⭐🔉
いた-よせ [0] 【板寄せ】
取引所における,一般銘柄の値段の決定方法の一。取引開始前に売買注文を紙上(板という)に記載させ,売りと買いの数量が一致するまで値段を上下させ,一致したところで単一の値段を決定する。
いたら ぬ【至らぬ】🔗⭐🔉
ぬ【至らぬ】🔗⭐🔉
いたら ぬ 【至らぬ】 (連語)
「いたらない」に同じ。「―
ぬ 【至らぬ】 (連語)
「いたらない」に同じ。「― ぬ点があるかと思いますが」「―
ぬ点があるかと思いますが」「― ぬ者ですが」
ぬ者ですが」
 ぬ 【至らぬ】 (連語)
「いたらない」に同じ。「―
ぬ 【至らぬ】 (連語)
「いたらない」に同じ。「― ぬ点があるかと思いますが」「―
ぬ点があるかと思いますが」「― ぬ者ですが」
ぬ者ですが」
いたり-せんさく【至り穿鑿】🔗⭐🔉
いたり-せんさく 【至り穿鑿】
(1)うるさく知りたがること。
(2)ぜいたくの限りを尽くした物好み。「次第に―の世なり/浮世草子・一代女 4」
いたり-かしこ・し【至り賢し】🔗⭐🔉
いたり-かしこ・し 【至り賢し】 (形ク)
思慮深い。「この中将も若けれど,いと聞えあり,―・くして/枕草子 244」
いたり-て【至りて】🔗⭐🔉
いたり-て 【至りて】 (副)
きわめて。非常に。大層。いたって。「―浄く仏の御法を継ぎ隆(ヒロ)めむと念行(オモホシ)まし/続紀(天平宝字八宣命)」
〔多く漢文訓読語として用いられた〕
イダルゴ Hidalgo y Costilla
Hidalgo y Costilla 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
イダルゴ  Hidalgo y Costilla
Hidalgo y Costilla (1753-1811) メキシコの司祭。1810年よりスペインに対する反乱を指導,敗れて処刑されたが,独立闘争の契機をつくる。独立の父と呼ばれ,武装蜂起の日(九月一六日)は独立記念日となる。
(1753-1811) メキシコの司祭。1810年よりスペインに対する反乱を指導,敗れて処刑されたが,独立闘争の契機をつくる。独立の父と呼ばれ,武装蜂起の日(九月一六日)は独立記念日となる。
 Hidalgo y Costilla
Hidalgo y Costilla (1753-1811) メキシコの司祭。1810年よりスペインに対する反乱を指導,敗れて処刑されたが,独立闘争の契機をつくる。独立の父と呼ばれ,武装蜂起の日(九月一六日)は独立記念日となる。
(1753-1811) メキシコの司祭。1810年よりスペインに対する反乱を指導,敗れて処刑されたが,独立闘争の契機をつくる。独立の父と呼ばれ,武装蜂起の日(九月一六日)は独立記念日となる。
いた-わさ【板山葵】🔗⭐🔉
いた-わさ [0] 【板山葵】
〔「板」は板付きかまぼこ,「わさ」は「わさび」の略〕
板付きかまぼこを切り,おろしわさびを添えた料理。
いたん-しんもん【異端審問】🔗⭐🔉
いたん-しんもん [4] 【異端審問】
カトリック教会で,異端者を追及・処罰するためなされた裁判。一三世紀以降南ヨーロッパを中心に広く行われた。審問官は教皇が任命。その尋問録は当時の民衆の世界を知る貴重な史料。
い-だん【い段・イ段】🔗⭐🔉
い-だん [1] 【い段・イ段】
五十音図の第二段。母音にイをもつ音の総称。い・き・し・ち・に・ひ・み・い・り・ゐ。イ列。
→五十音図
いだい【偉大な】(和英)🔗⭐🔉
いだく【抱く】(和英)🔗⭐🔉
いたさ【痛さ】(和英)🔗⭐🔉
いたれりつくせり【至れり尽せり】(和英)🔗⭐🔉
いたれりつくせり【至れり尽せり】
leave nothing to be desired;be perfect.
大辞林に「いだ」で始まるの検索結果 1-76。