複数辞典一括検索+![]()
![]()
ぢ🔗⭐🔉
ぢ [1]
「ち」の濁音の仮名。現代共通語では「じ」と発音上の区別はなく,硬口蓋破擦音(または硬口蓋摩擦音)の有声子音と前舌の狭母音とから成る音節。現代仮名遣いでは,この音節の仮名として,一般には「じ」が用いられるが,二語の連合による連濁(「はなぢ(鼻血)」「みぢか(身近)」など)と一語中の同音の連呼(「ちぢみ(縮)」「ちぢれる(縮れる)」など)の場合には「ぢ」を用いる。
〔「ぢ」は,清音「ち」に対する濁音の仮名として,中世末期までは「じ」とは別々の音を表していたが,江戸時代に入り,両者の発音上の区別は失われた。もっとも,方言には,現在でも「じ」「ぢ」を区別する地方がある〕
ち-あい【血合(い)】🔗⭐🔉
ち-あい ―アヒ [0] 【血合(い)】
魚の肉で,黒ずんだ赤みを帯びた部分。カツオ・マグロなどは体側および背骨の周辺に多い。
ちあえ-の-まつり【道饗祭】🔗⭐🔉
ちあえ-の-まつり チアヘ― 【道饗祭】
⇒みちあえのまつり(道饗祭)
ち-あつ【地圧】🔗⭐🔉
ち-あつ [0][1] 【地圧】
地殻を構成する物体が,その内部またはこれに接する物体に及ぼす力。トンネルの壁面に加わる圧力や造山運動の際の圧力など。
ち-あゆ【稚鮎】🔗⭐🔉
ち-あゆ [0] 【稚鮎】
孵化(フカ)してまもないアユ。アユの稚魚。
ち-あれ【血荒れ】🔗⭐🔉
ち-あれ 【血荒れ】
流産の古い言い方。[ヘボン(三版)]
ち-あわせ【血合(わ)せ】🔗⭐🔉
ち-あわせ ―アハセ [2] 【血合(わ)せ】
血縁関係の有無を調べる古い風習の一。水の中にそれぞれの血をたらし,そのまじり方によって判定した。
ちあん-けいさつ-ほう【治安警察法】🔗⭐🔉
ちあん-けいさつ-ほう ―ハフ 【治安警察法】
集会・結社および労働運動や大衆運動の取り締まりについて規定した法律。1900年(明治33)制定。のち,治安維持法で補完。45年(昭和20)廃止。
ち-いお【千五百】🔗⭐🔉
ち-いお ―イホ 【千五百】
数のきわめて多いこと。無数。ちいほ。「―の黄泉軍(ヨモツイクサ)を副へて追はしめき/古事記(上訓)」
ちいき-かいはつ【地域開発】🔗⭐🔉
ちいき-かいはつ ― キ― [4] 【地域開発】
特定地域の社会生活の向上を目的として,政府や地方公共団体が実施する総合的な開発。
キ― [4] 【地域開発】
特定地域の社会生活の向上を目的として,政府や地方公共団体が実施する総合的な開発。
 キ― [4] 【地域開発】
特定地域の社会生活の向上を目的として,政府や地方公共団体が実施する総合的な開発。
キ― [4] 【地域開発】
特定地域の社会生活の向上を目的として,政府や地方公共団体が実施する総合的な開発。
ちいき-かくさ【地域格差】🔗⭐🔉
ちいき-かくさ ― キ― [4] 【地域格差】
一国を構成する諸地域の間に存在する,一人当たりの所得額や住宅面積,上下水道の普及率,個人貯蓄額などの経済・福祉に関する差異。
キ― [4] 【地域格差】
一国を構成する諸地域の間に存在する,一人当たりの所得額や住宅面積,上下水道の普及率,個人貯蓄額などの経済・福祉に関する差異。
 キ― [4] 【地域格差】
一国を構成する諸地域の間に存在する,一人当たりの所得額や住宅面積,上下水道の普及率,個人貯蓄額などの経済・福祉に関する差異。
キ― [4] 【地域格差】
一国を構成する諸地域の間に存在する,一人当たりの所得額や住宅面積,上下水道の普及率,個人貯蓄額などの経済・福祉に関する差異。
ちいき-てあて【地域手当】🔗⭐🔉
ちいき-てあて ― キ― [4] 【地域手当】
地域によって生ずる生活費の差を調整するために支給される手当。寒冷地手当など。地域給。
キ― [4] 【地域手当】
地域によって生ずる生活費の差を調整するために支給される手当。寒冷地手当など。地域給。
 キ― [4] 【地域手当】
地域によって生ずる生活費の差を調整するために支給される手当。寒冷地手当など。地域給。
キ― [4] 【地域手当】
地域によって生ずる生活費の差を調整するために支給される手当。寒冷地手当など。地域給。
ちいき-とうそう【地域闘争】🔗⭐🔉
ちいき-とうそう ― キ―サウ [4] 【地域闘争】
地域に共通の要求のために,その地域の労働者・市民などが結束して行う闘争。労働運動の一形態。
キ―サウ [4] 【地域闘争】
地域に共通の要求のために,その地域の労働者・市民などが結束して行う闘争。労働運動の一形態。
 キ―サウ [4] 【地域闘争】
地域に共通の要求のために,その地域の労働者・市民などが結束して行う闘争。労働運動の一形態。
キ―サウ [4] 【地域闘争】
地域に共通の要求のために,その地域の労働者・市民などが結束して行う闘争。労働運動の一形態。
ちいき-ふんそう【地域紛争】🔗⭐🔉
ちいき-ふんそう ― キ―サウ [4] 【地域紛争】
比較的せまい地域内の複数国で起こる紛争。局地紛争。
キ―サウ [4] 【地域紛争】
比較的せまい地域内の複数国で起こる紛争。局地紛争。
 キ―サウ [4] 【地域紛争】
比較的せまい地域内の複数国で起こる紛争。局地紛争。
キ―サウ [4] 【地域紛争】
比較的せまい地域内の複数国で起こる紛争。局地紛争。
ちいさ【小さ】🔗⭐🔉
ちいさ チヒサ [1] 【小さ】
〔形容詞「小さい」の語幹から〕
■一■ (名)
幼児。「どれ
 ―よ,小さ刀伯父におこせ/浄瑠璃・いろは蔵三組盃」
■二■ (形動ナリ)
小さいさま。「につこりと笑ひ―なる声にて…といひながら/人情本・恵の花」
―よ,小さ刀伯父におこせ/浄瑠璃・いろは蔵三組盃」
■二■ (形動ナリ)
小さいさま。「につこりと笑ひ―なる声にて…といひながら/人情本・恵の花」

 ―よ,小さ刀伯父におこせ/浄瑠璃・いろは蔵三組盃」
■二■ (形動ナリ)
小さいさま。「につこりと笑ひ―なる声にて…といひながら/人情本・恵の花」
―よ,小さ刀伯父におこせ/浄瑠璃・いろは蔵三組盃」
■二■ (形動ナリ)
小さいさま。「につこりと笑ひ―なる声にて…といひながら/人情本・恵の花」
ちいさ-わらわ【小童】🔗⭐🔉
ちいさ-わらわ チヒサワラハ 【小童】
(1)小さい子供。
(2)平安時代,宮中で走り使いの用を足した子供。内豎(ナイジユ)。
ちいさ・し【小さし】🔗⭐🔉
ちいさ・し チヒサシ 【小さし】 (形ク)
⇒ちいさい
ちいさ-な【小さな】🔗⭐🔉
ちいさ-な チヒサ― [1] 【小さな】 (形動)
〔形容動詞「ちひさなり」の連体形から〕
現代語では,連体形「ちいさな」の形だけが用いられる。小さいさま。
⇔大きな
「―箱」「規模の―会社」
〔「ちいさな」を連体詞とする説もあるが,この語は「手の小さな人」などのように,述語としてのはたらきをもっている点が,一般の連体詞とは異なっている〕
ちいさ-め【小さめ】🔗⭐🔉
ちいさ-め チヒサ― [0] 【小さめ】 (名・形動)
物がいくぶん小さいこと。また,小さいと思われるさま。
⇔大きめ
ちいさ-やか【小さやか】🔗⭐🔉
ちいさ-やか チヒサ― 【小さやか】 (形動ナリ)
いかにも小さいさま。「いと―なれば,かき抱きて/源氏(帚木)」
ちい-たい【地衣帯】🔗⭐🔉
ちい-たい [0][2] 【地衣帯】
垂直分布による植物帯の一。高山帯の上部に位置し,主に地衣植物が生育する。
ちい-ちい🔗⭐🔉
ちい-ちい
〔幼児語〕
虫。特に,虱(シラミ)や蚤(ノミ)をいう。「ひとつ身の着物をひろげ,―をひろつて/滑稽本・浮世風呂 2」
ちい-と🔗⭐🔉
ちい-と [0][1] (副)
〔「ちと」の転〕
少し。ちょっと。「―相談がある」
ち-いみ【血忌み】🔗⭐🔉
ち-いみ [0] 【血忌み】
(1)出産の忌み。
(2)「血忌み日」の略。
ちい-るい【地衣類】🔗⭐🔉
ちい-るい [2] 【地衣類】
⇒地衣植物(チイシヨクブツ)
ち-うみ【血膿】🔗⭐🔉
ち-うみ [0] 【血膿】
血のまじったうみ。
ちうん【智蘊】🔗⭐🔉
ちうん 【智蘊】
(?-1448) 室町中期の武将・連歌作者。本名,蜷川新右衛門親当(チカマサ)。和歌を正徹に学ぶ。連歌七賢の一人。句集「親当句集」
ちえい【智永】🔗⭐🔉
ちえい 【智永】
六世紀の中国の僧・書家。王羲之(オウギシ)の七世の孫といわれる。羲之風の書をよくし,「真草千字文」が伝わる。生没年未詳。
ちえ-おくれ【知恵遅れ】🔗⭐🔉
ちえ-おくれ チ ― [3] 【知恵遅れ】
知能の発育がおくれていること。知的障害があること。
― [3] 【知恵遅れ】
知能の発育がおくれていること。知的障害があること。
 ― [3] 【知恵遅れ】
知能の発育がおくれていること。知的障害があること。
― [3] 【知恵遅れ】
知能の発育がおくれていること。知的障害があること。
ち-えき【地役】🔗⭐🔉
ち-えき [0] 【地役】
(1)他人の土地を自分の土地の便益に供すること。
(2)「地役権」の略。
ちえき-けん【地役権】🔗⭐🔉
ちえき-けん [3][2] 【地役権】
他人の土地を自分の土地の便益のために利用する権利。物権の一つで,契約により設定。他人の土地を通行する権利など。地役。
ちえ-こう【智慧光】🔗⭐🔉
ちえ-こう チ クワウ [2] 【智慧光】
〔仏〕 阿弥陀仏の十二光の一。衆生(シユジヨウ)の迷いの闇を照らし導く光明。
クワウ [2] 【智慧光】
〔仏〕 阿弥陀仏の十二光の一。衆生(シユジヨウ)の迷いの闇を照らし導く光明。
 クワウ [2] 【智慧光】
〔仏〕 阿弥陀仏の十二光の一。衆生(シユジヨウ)の迷いの闇を照らし導く光明。
クワウ [2] 【智慧光】
〔仏〕 阿弥陀仏の十二光の一。衆生(シユジヨウ)の迷いの闇を照らし導く光明。
ちえ-なみ【千重波】🔗⭐🔉
ちえ-なみ チヘ― 【千重波】
幾重にも重なり合って寄せる波。「朝なぎに―寄せ夕なぎに五百重(イオエ)波寄す/万葉 931」
ちえなみ-しきに【千重波頻に】🔗⭐🔉
ちえなみ-しきに チヘ― 【千重波頻に】 (副)
波が次々に寄せるようにしきりに。「一日(ヒトヒ)には―思へども/万葉 409」
ちえ-ねつ【知恵熱】🔗⭐🔉
ちえ-ねつ チ ― [2] 【知恵熱】
生後六,七か月頃から満一歳前後の乳児にみられる発熱。ちょうど歯の生える頃にあたるが,原因は明らかでない。ちえぼとり。
― [2] 【知恵熱】
生後六,七か月頃から満一歳前後の乳児にみられる発熱。ちょうど歯の生える頃にあたるが,原因は明らかでない。ちえぼとり。
 ― [2] 【知恵熱】
生後六,七か月頃から満一歳前後の乳児にみられる発熱。ちょうど歯の生える頃にあたるが,原因は明らかでない。ちえぼとり。
― [2] 【知恵熱】
生後六,七か月頃から満一歳前後の乳児にみられる発熱。ちょうど歯の生える頃にあたるが,原因は明らかでない。ちえぼとり。
ちえ-の-いた【知恵の板】🔗⭐🔉
ちえ-の-いた チ ― [3] 【知恵の板】
江戸時代の玩具の一。種々の形の小さな板を組み合わせ,並べて遊ぶもの。
― [3] 【知恵の板】
江戸時代の玩具の一。種々の形の小さな板を組み合わせ,並べて遊ぶもの。
 ― [3] 【知恵の板】
江戸時代の玩具の一。種々の形の小さな板を組み合わせ,並べて遊ぶもの。
― [3] 【知恵の板】
江戸時代の玩具の一。種々の形の小さな板を組み合わせ,並べて遊ぶもの。
ちえ-の-うみ【智慧の海】🔗⭐🔉
ちえ-の-うみ チ ― 【智慧の海】
智慧の深く広いことを海にたとえていう語。
― 【智慧の海】
智慧の深く広いことを海にたとえていう語。
 ― 【智慧の海】
智慧の深く広いことを海にたとえていう語。
― 【智慧の海】
智慧の深く広いことを海にたとえていう語。
ちえ-の-けん【智慧の剣】🔗⭐🔉
ちえ-の-けん チ ― 【智慧の剣】
智慧の力が煩悩(ボンノウ)を断ち切ることを剣にたとえていう語。智慧の利剣。
― 【智慧の剣】
智慧の力が煩悩(ボンノウ)を断ち切ることを剣にたとえていう語。智慧の利剣。
 ― 【智慧の剣】
智慧の力が煩悩(ボンノウ)を断ち切ることを剣にたとえていう語。智慧の利剣。
― 【智慧の剣】
智慧の力が煩悩(ボンノウ)を断ち切ることを剣にたとえていう語。智慧の利剣。
ちえ-の-こま【知恵の駒】🔗⭐🔉
ちえ-の-こま チ ― [0][4] 【知恵の駒】
玩具の一種。縦横四列に駒の入る浅い正方形の箱枠の中に番号を打った一五個の駒を順不同に置き,空いた一駒分の所に駒を順に移動させ,番号順に並べ替えて遊ぶもの。
― [0][4] 【知恵の駒】
玩具の一種。縦横四列に駒の入る浅い正方形の箱枠の中に番号を打った一五個の駒を順不同に置き,空いた一駒分の所に駒を順に移動させ,番号順に並べ替えて遊ぶもの。
 ― [0][4] 【知恵の駒】
玩具の一種。縦横四列に駒の入る浅い正方形の箱枠の中に番号を打った一五個の駒を順不同に置き,空いた一駒分の所に駒を順に移動させ,番号順に並べ替えて遊ぶもの。
― [0][4] 【知恵の駒】
玩具の一種。縦横四列に駒の入る浅い正方形の箱枠の中に番号を打った一五個の駒を順不同に置き,空いた一駒分の所に駒を順に移動させ,番号順に並べ替えて遊ぶもの。
ちえ-の-わ【知恵の輪】🔗⭐🔉
ちえ-の-わ チ ― [4][0] 【知恵の輪】
(1)種々の形をした金属製の輪をつなぎ合わせたり,はずしたりして遊ぶ玩具。九連環。
(2)家紋の一。枠に輪がからんだもの。
(3)文殊菩薩(モンジユボサツ)をまつる寺院にある石の輪。これをくぐると知恵が授かるといわれる。
― [4][0] 【知恵の輪】
(1)種々の形をした金属製の輪をつなぎ合わせたり,はずしたりして遊ぶ玩具。九連環。
(2)家紋の一。枠に輪がからんだもの。
(3)文殊菩薩(モンジユボサツ)をまつる寺院にある石の輪。これをくぐると知恵が授かるといわれる。
 ― [4][0] 【知恵の輪】
(1)種々の形をした金属製の輪をつなぎ合わせたり,はずしたりして遊ぶ玩具。九連環。
(2)家紋の一。枠に輪がからんだもの。
(3)文殊菩薩(モンジユボサツ)をまつる寺院にある石の輪。これをくぐると知恵が授かるといわれる。
― [4][0] 【知恵の輪】
(1)種々の形をした金属製の輪をつなぎ合わせたり,はずしたりして遊ぶ玩具。九連環。
(2)家紋の一。枠に輪がからんだもの。
(3)文殊菩薩(モンジユボサツ)をまつる寺院にある石の輪。これをくぐると知恵が授かるといわれる。
ちえ-まけ【知恵負け】🔗⭐🔉
ちえ-まけ チ ― [0] 【知恵負け】
知恵があるため考えをめぐらしすぎて,かえって失敗すること。
― [0] 【知恵負け】
知恵があるため考えをめぐらしすぎて,かえって失敗すること。
 ― [0] 【知恵負け】
知恵があるため考えをめぐらしすぎて,かえって失敗すること。
― [0] 【知恵負け】
知恵があるため考えをめぐらしすぎて,かえって失敗すること。
ちえん-りそく【遅延利息】🔗⭐🔉
ちえん-りそく [4] 【遅延利息】
金銭債務の返済を期日までに履行しなかった場合,損害賠償として支払われるべき金銭。金額は債務額に対する法定利率を原則とする。延滞利息。
ち-おも【乳母】🔗⭐🔉
ち-おも 【乳母】
うば。めのと。ちも。「婦人(オミナ)を取りて,―・湯母・及び飯嚼(イイガミ),湯坐(ユエビト)としたまふ/日本書紀(神代下訓)」
ち-おや【乳親】🔗⭐🔉
ち-おや [0] 【乳親】
(1)母親の代わりに赤子に乳を飲ませて育てる女。うば。めのと。
(2)生まれた子供に,実母より先に儀礼的に乳を与える女性。乳付け親。乳飲み親。乳代(チシロ)。
ち-おろし【血下ろし】🔗⭐🔉
ち-おろし 【血下ろし】
胎児をおろすこと。堕胎。「さては昔―をせし親なし子かと悲し/浮世草子・一代女 6」
ち-おん【地温】🔗⭐🔉
ち-おん ―ヲン [0] 【地温】
地表または地中の温度。
ちおん-いん【知恩院】🔗⭐🔉
ちおん-いん ― ン 【知恩院】
京都市東山区林下町にある浄土宗総本山。正しくは華頂山智恩教院大谷寺。比叡山を下った法然が専修念仏を唱えて庵を結んだのに始まる。その死後,弟子の源智が堂宇を建立。徳川家康が生母の菩提のため,壮大な伽藍(ガラン)を建立。「法然上人絵伝」などを所蔵。
ン 【知恩院】
京都市東山区林下町にある浄土宗総本山。正しくは華頂山智恩教院大谷寺。比叡山を下った法然が専修念仏を唱えて庵を結んだのに始まる。その死後,弟子の源智が堂宇を建立。徳川家康が生母の菩提のため,壮大な伽藍(ガラン)を建立。「法然上人絵伝」などを所蔵。
 ン 【知恩院】
京都市東山区林下町にある浄土宗総本山。正しくは華頂山智恩教院大谷寺。比叡山を下った法然が専修念仏を唱えて庵を結んだのに始まる。その死後,弟子の源智が堂宇を建立。徳川家康が生母の菩提のため,壮大な伽藍(ガラン)を建立。「法然上人絵伝」などを所蔵。
ン 【知恩院】
京都市東山区林下町にある浄土宗総本山。正しくは華頂山智恩教院大谷寺。比叡山を下った法然が専修念仏を唱えて庵を結んだのに始まる。その死後,弟子の源智が堂宇を建立。徳川家康が生母の菩提のため,壮大な伽藍(ガラン)を建立。「法然上人絵伝」などを所蔵。
ちかい-の-あみ【誓いの網】🔗⭐🔉
ちかい-の-あみ チカヒ― 【誓いの網】
衆生を救おうとする仏の誓願を,網にたとえていう語。弘誓(グゼイ)の網。
ちかい-の-うみ【誓いの海】🔗⭐🔉
ちかい-の-うみ チカヒ― 【誓いの海】
衆生を救おうとする仏の誓願の広大なことを,海にたとえていう語。弘誓の海。
ちかい-の-ふね【誓いの船】🔗⭐🔉
ちかい-の-ふね チカヒ― 【誓いの船】
衆生を彼岸へ渡そうという仏の誓願を,舟にたとえていう語。弘誓(グゼイ)の船。
ちか-いえか【地下家蚊】🔗⭐🔉
ちか-いえか ―イヘカ [3] 【地下家蚊】
カの一種。体長約5.5ミリメートル。赤褐色。都会の汚水漕などから発生する。アカイエカに似るが,冬でも人から吸血する。
ちか-おとり【近劣り】🔗⭐🔉
ちか-おとり 【近劣り】
近寄って見ると,遠くで見るより,悪く見えること。
⇔近優(マサ)り
「人しれず―しては,思はずやあらむと,たのもしくうれしくて/源氏(総角)」
ちかき-まもり【近衛】🔗⭐🔉
ちかき-まもり 【近衛】
「このえ(近衛)」に同じ。「かういときびしき―こそむつかしけれ/源氏(真木柱)」
ちかきまもり-の-つかさ【近衛府】🔗⭐🔉
ちかきまもり-の-つかさ 【近衛府】
⇒このえふ(近衛府)
ちかく-きんこう-せつ【地殻均衡説】🔗⭐🔉
ちかく-きんこう-せつ ―キンカウ― [6] 【地殻均衡説】
⇒アイソスタシー
ちかく-しんけい【知覚神経】🔗⭐🔉
ちかく-しんけい [4] 【知覚神経】
⇒感覚神経(カンカクシンケイ)
ちかく-まひ【知覚麻痺】🔗⭐🔉
ちかく-まひ [4] 【知覚麻痺】
神経系の障害のために,一部またはすべての感覚がなくなること。感覚麻痺。
ちか-けい【地下茎】🔗⭐🔉
ちか-けい [2] 【地下茎】
地中にある茎。その形によって根茎・塊茎・球茎・鱗茎(リンケイ)などに区別される。
→地上茎
地下茎
 [図]
[図]
 [図]
[図]
ちか-けん【地下権】🔗⭐🔉
ちか-こうさく【地下工作】🔗⭐🔉
ちか-こうさく [3] 【地下工作】
(1)非合法の組織活動を秘密に行うこと。
(2)裏面での運動や活動。裏面工作。
ちかしき-こう【地下式壙】🔗⭐🔉
ちかしき-こう ―クワウ [4] 【地下式壙】
古墳時代後期の墓の一形態。地面に竪穴(タテアナ)を掘り,さらにそこから横穴を作って玄室としたもの。南九州に多く分布する。地下式横穴。
ちか-しつ【地下室】🔗⭐🔉
ちか-しつ [2] 【地下室】
地盤面よりも下に作られた部屋。地階の部屋。
ちか-すい【地下水】🔗⭐🔉
ちか-すい [2] 【地下水】
地下の岩石の割れ目や,地層中の間隙を満たしている水。雨水が地中に浸透して蓄えられたもの。飲用・灌漑・工業用水などに利用される。
⇔地表水
ちか-せいふ【地下政府】🔗⭐🔉
ちか-せいふ [3] 【地下政府】
非合法の組織・団体が,自分たちだけで作った政府。
ちか-そしき【地下組織】🔗⭐🔉
ちか-そしき [3] 【地下組織】
地下運動を行う非公然の組織。
ち-かた【血方】🔗⭐🔉
ち-かた 【血方】
血筋を引く者。血縁の者。
ちかつおうみ【近つ淡海・近江】🔗⭐🔉
ちかつおうみ チカツアフミ 【近つ淡海・近江】
〔浜名湖を「遠淡海(トオツオウミ)」というのに対して,都から近い湖の意〕
琵琶湖。また,近江国(オウミノクニ)。
ちか-つ-よ【近つ代】🔗⭐🔉
ちか-つ-よ 【近つ代】
いまの代。近代。
ちか-てつ【地下鉄】🔗⭐🔉
ちか-てつ [0] 【地下鉄】
〔「地下鉄道」の略〕
主として都市の市街部の地下に構築されたトンネル内を走る鉄道。メトロ。サブウエー。
ち-かなもの【乳金物】🔗⭐🔉
ち-かなもの [2] 【乳金物】
扉などの釘隠しのために打ちつける,乳房状の金物。饅頭(マンジユウ)金物。ちちかなもの。
乳金物
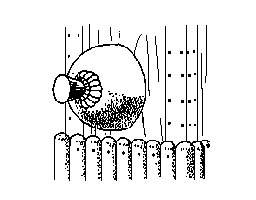 [図]
[図]
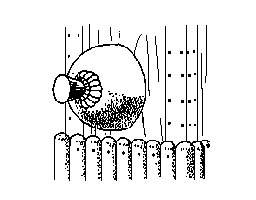 [図]
[図]
ちか-の-しま【値嘉島】🔗⭐🔉
ちか-の-しま 【値嘉島】
長崎県五島列島と平戸島の総称。((歌枕))「名をたのみ―へとこぎくれば今日もふなぢにくれぬべきかな/重之集」
ちか-ま【近間】🔗⭐🔉
ちか-ま [2] 【近間】
近い所。近く。「―の店で間に合わせる」
ちか-まさり【近優り】🔗⭐🔉
ちか-まさり 【近優り】 (名)スル
近づいて見ると,遠くで見るより,すぐれて見えること。
⇔近劣り
「御心ざしの,―するなるべし/源氏(明石)」
ちかまつ【近松】🔗⭐🔉
ちかまつ 【近松】
姓氏の一。
ちかまつ-き【近松忌】🔗⭐🔉
ちかまつ-き [4] 【近松忌】
近松門左衛門の忌日。一一月二二日。巣林子忌(ソウリンシキ)。巣林忌。[季]冬。
ちかま・る【近まる】🔗⭐🔉
ちかま・る [3] 【近まる】 (動ラ五)
近づいてくる。近づく。近くなる。「国会の開設も―・ったれば/思出の記(蘆花)」
ちか-まわり【近回り】🔗⭐🔉
ちか-まわり ―マハリ [3] 【近回り】 (名)スル
(1)近道をとること。
⇔遠回り
(2)近所。ちかま。
ちかみち-はんのう【近道反応】🔗⭐🔉
ちかみち-はんのう ―オウ [5] 【近道反応】
〔心〕 目標に向かって,回り道せずに,直接的・衝動的に行動すること。近道行動。短絡反応。
ちかめ-きんとき【近眼金時】🔗⭐🔉
ちかめ-きんとき [4] 【近眼金時】
スズキ目キントキダイ科の海魚。体長40センチメートル程度。体は卵円形で側扁する。眼は大きい。腹びれが著しく大きい。体は朱紅色。食用。南日本,全世界の熱帯・亜熱帯域に分布。
ちか-やか【近やか】🔗⭐🔉
ちか-やか 【近やか】 (形動ナリ)
(1)いかにも近いさま。「―に臥し給へば/源氏(胡蝶)」
(2)親しいさま。「―なる御有様も,もてなし聞え給はざりけり/源氏(初音)」
ちから-あし【力足】🔗⭐🔉
ちから-あし [3] 【力足】
(1)力を入れた足。足に力を込めること。「―を踏んでつい立ちあがり/平家 9」
(2)相撲で,四股(シコ)のこと。「―を踏む」
ちから-あわせ【力合(わ)せ】🔗⭐🔉
ちから-あわせ ―アハセ 【力合(わ)せ】
〔互いの力の強さを競い合う意から〕
相撲。「ながつきの―に勝ちにけり/山家(百首)」
ちから-いし【力石】🔗⭐🔉
ちから-いし [3] 【力石】
力くらべに持ち上げる石。神社や村の辻に置いたりした。
ちから-おとし【力落(と)し】🔗⭐🔉
ちから-おとし [4] 【力落(と)し】
落胆して元気がなくなること。がっかりすること。「御主人を亡くされて,さぞお―のことでしょう」
ちから-おとり【力劣り】🔗⭐🔉
ちから-おとり [4] 【力劣り】
人よりも力が弱いこと。実力が劣ること。また,その人。
ちから-しろ【力代・庸】🔗⭐🔉
ちから-しろ 【力代・庸】
律令制で,一年に一〇日間の力役の代わりに納める代納物。
→庸(ヨウ)
ちから-ぬけ【力抜け】🔗⭐🔉
ちから-ぬけ [0] 【力抜け】 (名)スル
張りつめていた心がゆるんで力が抜けること。「安心したら―がした」
ちから-の-へいこうしへんけい【力の平行四辺形】🔗⭐🔉
ちから-の-へいこうしへんけい ―ヘイカウシヘンケイ 【力の平行四辺形】
二つの力の合力を求める際に描かれる平行四辺形。力を表す二つのベクトルを隣り合う二辺とする平行四辺形の対角線が合力のベクトルとなる。
ちから-まさり【力優り】🔗⭐🔉
ちから-まさり [4] 【力優り】
力が他にすぐれて強いこと。また,その人。
ちから-の-かみ【主税頭】🔗⭐🔉
ちから-の-かみ 【主税頭】
主税寮の長官。
ちから-の-つかさ【主税寮】🔗⭐🔉
ちから-の-つかさ 【主税寮】
⇒しゅぜいりょう(主税寮)
ちから-な・い【力無い】🔗⭐🔉
ちから-な・い [4] 【力無い】 (形)[文]ク ちからな・し
(1)元気がない。気力が抜けている。「―・い足取りで歩く」「―・く笑う」
(2)仕方がない。どうにもならない。「さらんには―・し/平家 4」
[派生] ――げ(形動)――さ(名)
ちかり-ちかり🔗⭐🔉
ちかり-ちかり (副)
〔「ちがりちがり」とも〕
片足を引きずって歩くさま。「腰の骨が違うたやら,方屋(カタヤ)へ―としてお退きやつた/狂言・飛越」
ちき-なん【知己難】🔗⭐🔉
ちき-なん [2] 【知己難】
知己にはなかなかめぐり会いがたいことをいう語。
ちくあん【竹庵】🔗⭐🔉
ちくあん [2] 【竹庵】
⇒藪井竹庵(ヤブイチクアン)
ちくかん-もん【竹管文】🔗⭐🔉
ちくかん-もん チククワン― [3][0] 【竹管文】
⇒ちっかんもん(竹管文)
ちくけい【竹渓】🔗⭐🔉
ちくけい 【竹渓】
中国,山東省泰安県の東南,徂来山下の地名。
大辞林に「ぢ」で始まるの検索結果 1-100。もっと読み込む