複数辞典一括検索+![]()
![]()
えだ-ね【支根】🔗⭐🔉
えだ-ね [0] 【支根】
主根から分かれ出た根。しこん。側根。
か・う【支う】🔗⭐🔉
か・う カフ [1] 【支う】 (動ワ五[ハ四])
〔「交(カ)う」と同源〕
(1)棒などをあてがってささえとする。「つっかい棒を―・う」
(2)鍵(カギ)や閂(カンヌキ)などをかけて扉が開かないようにする。「鍵を―・う」
[可能] かえる
さえ-にん【支人】🔗⭐🔉
さえ-にん サヘ― 【支人】
けんかや口論などの仲裁人。さえびと。「―踏んだは堪忍せぬ/浄瑠璃・生玉心中(上)」
ささい-こさい【支いこさい】🔗⭐🔉
ささい-こさい 【支いこさい】
「ささえこさえ」の転。「傍に付添ふ侫人原(ネイジンバラ)めが,―言廻し/浄瑠璃・先代萩」
ささえ【支え】🔗⭐🔉
ささえ ササヘ [3][0] 【支え】
(1)ささえること。また,そのもの。「塀に―をする」「一家の―となって働く」「心の―」
(2)「ささえぐち」の略。「物ごとに―を言はず暮らされける故(ユエ)/浮世草子・姑気質」
ささえ-ぐち【支へ口】🔗⭐🔉
ささえ-ぐち ササヘ― 【支へ口】
人を中傷する言葉。かげぐち。ささえごと。「かげごと・中言・―/浄瑠璃・卯月の紅葉(上)」
ささえ-こさえ【支え小支え】🔗⭐🔉
ささえ-こさえ ササヘコサヘ 【支え小支え】
〔同音・類音の語を重ねた語〕
じゃまだてすること。中傷すること。ささいこさい。「『牛島殿,待たしやんせ』『こりゃ何故あって私らを,―をしなさんすのぢや』/歌舞伎・加賀見山再岩藤」
ささえ-じょう【支え状】🔗⭐🔉
ささえ-じょう ササヘジヤウ 【支え状】
鎌倉・室町時代の訴訟沙汰で,訴人の提出した訴状に対して,被告である論人が弁明のため提出する陳情。しじょう。
ささえ-ばしら【支え柱】🔗⭐🔉
ささえ-ばしら ササヘ― [4] 【支え柱】
支柱(シチユウ)。
ささ・える【支える】🔗⭐🔉
ささ・える ササヘル [0][3] 【支える】 (動ア下一)[文]ハ下二 ささ・ふ
(1)力を加えて,物が倒れたり落ちたりしないように押さえたりつっぱったりする。「はしごが倒れないように―・えていてください」「全重量を一点で―・える」「人に―・えられてやっと立っている」
(2)社会・集団を維持する。ある状態をもちこたえる。「会社を―・えているのは一人一人の社員の力だ」「家計を―・える」
(3)援助する。支援する。「仲間に―・えられてここまで来ました」
(4)攻撃などを防ぎ止める。「しばし―・へて防ぎけれども敵は大勢なり/平家 7」
(5)人や物が通ろうとするのを妨げる。さえぎる。「木の芽峠の大雪に―・へられ,只今もつて罷り上る/狂言・餅酒」「日の光は―・えられて,眸に至らぬなるべし/浴泉記(喜美子)」
(6)中傷する。「ヒトヲ―・ユル/日葡」
ささ・ゆ【支ゆ】🔗⭐🔉
ささ・ゆ 【支ゆ】 (動ヤ下二)
〔ハ行下二段動詞「ささふ」をヤ行に活用させたもの。中世後期以降の語〕
「ささえる」に同じ。「道ヲ―・ユル/日葡」
し-いん【子院・支院・枝院】🔗⭐🔉
し-いん ― ン [1][0] 【子院・支院・枝院】
(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。
(2)本寺に属する寺院。末寺。
ン [1][0] 【子院・支院・枝院】
(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。
(2)本寺に属する寺院。末寺。
 ン [1][0] 【子院・支院・枝院】
(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。
(2)本寺に属する寺院。末寺。
ン [1][0] 【子院・支院・枝院】
(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。
(2)本寺に属する寺院。末寺。
し-えん【支援】🔗⭐🔉
し-えん ― ン [0] 【支援】 (名)スル
他人を支えたすけること。援助。後援。「友人の事業を―する」「―の手をさしのべる」
ン [0] 【支援】 (名)スル
他人を支えたすけること。援助。後援。「友人の事業を―する」「―の手をさしのべる」
 ン [0] 【支援】 (名)スル
他人を支えたすけること。援助。後援。「友人の事業を―する」「―の手をさしのべる」
ン [0] 【支援】 (名)スル
他人を支えたすけること。援助。後援。「友人の事業を―する」「―の手をさしのべる」
し-かん【支干】🔗⭐🔉
し-かん [0] 【支干】
十二支と十干(ジツカン)。干支(カンシ)。
し-かん【支間】🔗⭐🔉
し-かん [0] 【支間】
橋脚と橋台,また橋脚と橋脚の距離。スパン。
し-かん【支管】🔗⭐🔉
し-かん ―クワン [0] 【支管】
ガス管・水道管などの,本管から分かれた細い管。
し-きゃく【支脚】🔗⭐🔉
し-きゃく [0] 【支脚】
人体立像で,体重がかかる方の脚。
し-きゅう【支給】🔗⭐🔉
し-きゅう ―キフ [0] 【支給】 (名)スル
金銭・物品などを払い渡すこと。「ボーナスを―する」
し-きょく【支局】🔗⭐🔉
し-きょく [2][0] 【支局】
新聞社・放送局などの地方出先機関。本社・本局の管理のもと,その地域の業務を扱う。
し-けい【支系】🔗⭐🔉
し-けい [0] 【支系】
直系から分かれた系統。傍系。
しこう【支考】🔗⭐🔉
しこう シカウ 【支考】
⇒各務(カガミ)支考
し-さく【支索】🔗⭐🔉
し-さく [0] 【支索】
ものをささえるために張ってある鋼索。
し-し【支子】🔗⭐🔉
し-し [1] 【支子】
嫡子以外の子。
し-じ【支持】🔗⭐🔉
し-じ ―ヂ [1] 【支持】 (名)スル
(1)支えること。「梁(ハリ)を―する柱」「瀦水(タマリミズ)暴漲(ボウチヨウ)堤防之を―するを得ず/新聞雑誌 23」
(2)他の人の思想・意見・態度などに賛成して援助すること。また,その援助。「―する政党」「―を取り付ける」
しじ-かかく【支持価格】🔗⭐🔉
しじ-かかく シヂ― [3] 【支持価格】
価格を安定させる必要性から,政府が定めた価格。主として農産物が対象となる。
し-じく【支軸】🔗⭐🔉
し-じく ―ヂク [0] 【支軸】
梃子(テコ)などの支点にある支えの軸。
しじ-ぐい【支持杭】🔗⭐🔉
しじ-ぐい シヂグヒ [2] 【支持杭】
軟弱地盤を貫通し,先端が硬い層に達して支持される杭。
→摩擦杭
ししゅつ-こくみんしょとく【支出国民所得】🔗⭐🔉
ししゅつ-こくみんしょとく [8] 【支出国民所得】
国民所得をその付加価値に対する支出の側面からとらえたもの。一定期間(通常一年)の民間の消費と投資,政府の支出,輸出から輸入を引いた差額を合計したもの。
ししゅつ-ぜい【支出税】🔗⭐🔉
ししゅつ-ぜい [3] 【支出税】
ある期間の個人の消費支出総額に対して累進的に課す税。通常の消費税と異なり直接税。現在は,この税を実施している国はない。総合消費税。
し-しょ【支所】🔗⭐🔉
し-しょ [1] 【支所】
会社・役所などの出先の事務所。
し-しょ【支庶】🔗⭐🔉
し-しょ [1] 【支庶】
(1)本家から分かれた血筋。支族。
(2)めかけばらの子。妾腹(シヨウフク)。支子。
し-しょ【支署】🔗⭐🔉
し-しょ [1] 【支署】
警察・税務署などの,本署から離れた地に設置され,その地域の業務を担当する役所。
し-しょう【支障】🔗⭐🔉
し-しょう ―シヤウ [0] 【支障】
事をなす妨げとなる物事。さしつかえ。さしさわり。「―を来す」
し-じょう【支状】🔗⭐🔉
し-じょう ―ジヤウ [0] 【支状】
⇒初陳状(シヨチンジヨウ)
し-じょう【支城】🔗⭐🔉
し-じょう ―ジヤウ [0] 【支城】
本城を補助するために配された城。
しせき-ぼ【支石墓】🔗⭐🔉
しせき-ぼ [3] 【支石墓】
新石器時代末から金石併用時代にかけての巨大な石を用いた墳墓。中国の山東半島・東北部,朝鮮半島,日本の北九州に分布。
→ドルメン
し-せん【支線】🔗⭐🔉
し-せん [0] 【支線】
(1)本線・幹線から分岐した鉄道線路や道路。
(2)本線から分岐した短距離の送電線。
(3)電柱を支持するため,上部から斜めに地上に張る線。
し-ぞく【支族・枝族】🔗⭐🔉
し-ぞく [1] 【支族・枝族】
分かれ出た血族。分家。別家。
し-たく【支度・仕度】🔗⭐🔉
し-たく [0] 【支度・仕度】 (名)スル
(1)準備すること。用意すること。「食事の―をする」
(2)外出などのために服装を整えること。身支度。「旅―」
(3)食事をすること。「これから精養軒で―をしようと/うづまき(敏)」
(4)あらかじめ見積もること。計算すること。「石つくりの御子は心の―ある人にて/竹取」
したく-きん【支度金】🔗⭐🔉
したく-きん [0] 【支度金】
準備や用意に必要な金。就職や嫁入りなどの準備に要する金。支度料。
し-ちゅう【支柱】🔗⭐🔉
し-ちゅう [0] 【支柱】
(1)物が倒れないようにささえている柱。つっかえ棒。
(2)中心になっている人。「一家の―を失う」
しちゅう-こん【支柱根】🔗⭐🔉
しちゅう-こん [2] 【支柱根】
気根の一種。茎の地上部から伸びて地中に入り,茎を支持する根。トウモロコシ・タコノキ・ヒルギなどにみられる。支柱気根。柱根。
支柱根
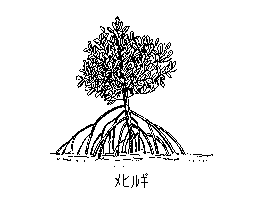 [図]
[図]
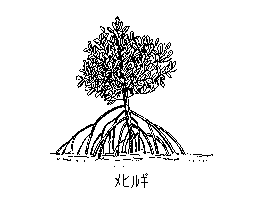 [図]
[図]
し-ちょう【支庁】🔗⭐🔉
し-ちょう ―チヤウ [2][1] 【支庁】
本庁の下にあって,本庁と分離して,所在地方の事務を取り扱う官庁。「網走―」「―管内」
し-て【支手】🔗⭐🔉
し-て [0] 【支手】
「支払手形」の略。
し-と【使途・支途】🔗⭐🔉
し-と [1][2] 【使途・支途】
金銭などのつかいみち。「―が明確でない」「―不明の金」
しな【支那】🔗⭐🔉
しな 【支那】
外国人が中国を呼んだ称。「秦(シン)」の転という。中国で仏典を漢訳する際,インドでの呼称を音訳したもの。日本では江戸中期以後,第二次大戦末まで称した。
しな-かばん【支那鞄】🔗⭐🔉
しな-かばん [3] 【支那鞄】
〔もと中国から伝来したのでいう〕
木製で,外側を革または紙で貼った櫃形(ヒツガタ)の鞄。
しな-こうじ【支那麹】🔗⭐🔉
しな-こうじ ―カウジ [3] 【支那麹】
⇒酒薬(シユヤク)
しな-じへん【支那事変】🔗⭐🔉
しな-じへん 【支那事変】
⇒日中戦争(ニツチユウセンソウ)
しな-そば【支那蕎麦】🔗⭐🔉
しな-そば [0] 【支那蕎麦】
中華蕎麦(チユウカソバ)。ラーメン。
しな-ちく【支那竹】🔗⭐🔉
しな-ちく [2][0] 【支那竹】
⇒メンマ
しなチベット-しょご【支那―諸語】🔗⭐🔉
しなチベット-しょご [7] 【支那―諸語】
〔Sino-Tibetan〕
東南アジアから中央アジアにかけて広域に分布する諸言語。カム-タイ(タイ諸語など),チベット-ビルマ(カチン,チベット,カナウリ,ロロ-ビルマ諸語など),中国(粤(エツ),呉,客家(ハツカ), (ビン),北方語),ミャオ-ヤオの四語群を数える。
(ビン),北方語),ミャオ-ヤオの四語群を数える。
 (ビン),北方語),ミャオ-ヤオの四語群を数える。
(ビン),北方語),ミャオ-ヤオの四語群を数える。
しな-ちりめん【支那縮緬】🔗⭐🔉
しな-ちりめん [3] 【支那縮緬】
中国,浙江省湖州府産の縮緬の旧称。しなちり。
しな-ろうにん【支那浪人】🔗⭐🔉
しな-ろうにん ―ラウニン [3] 【支那浪人】
⇒大陸浪人(タイリクロウニン)
し-は【支派】🔗⭐🔉
し-は [1] 【支派】
本派から分かれた一派。分派。
し-はい【支配】🔗⭐🔉
し-はい [1] 【支配】 (名)スル
□一□
(1)ある地域・組織を自分の勢力下に置き,治めること。「近隣諸国を―した」「系列会社を―する」「―者」
(2)あるものの意志・命令・運動などが,他の人間や物事を規定し束縛すること。「運命を―する」「感情に―される」「機械に―される」
□二□仕事の配分をしたり,部下を監督し,指図して仕事をさせること。「宇治のおとど,成佐が弟子どもに―して,一日に三尺地蔵菩薩の像を図絵し/著聞 13」
〔□二□が原義〕
しはい-か【支配下】🔗⭐🔉
しはい-か [2] 【支配下】
ある者の意志・命令に従う状態にあること。「隣国の―にある」
しはい-かいきゅう【支配階級】🔗⭐🔉
しはい-かいきゅう ―キフ [4] 【支配階級】
政治的・社会的・経済的地位において,他よりも優越して国家または社会を支配している階級。
しはい-かぶ【支配株】🔗⭐🔉
しはい-かぶ [2] 【支配株】
⇒貯蔵株(チヨゾウカブ)
しはい-かぶぬし【支配株主】🔗⭐🔉
しはい-かぶぬし [5] 【支配株主】
株主総会の意思決定を支配し,取締役の選任・解任をすることができる大株主。
しはい-かんじょう【支配勘定】🔗⭐🔉
しはい-かんじょう ―ヂヤウ [4] 【支配勘定】
江戸幕府の職名。勘定奉行に所属し,幕府の財政・領地の調査をつかさどった。
しはい-ぎょく【支配玉】🔗⭐🔉
しはい-ぎょく [2] 【支配玉】
証券会社が販売のために手持ちしている債券。
しはい-けん【支配権】🔗⭐🔉
しはい-じょ【支配所】🔗⭐🔉
しはい-じょ [0] 【支配所】
江戸時代,遠国奉行や代官を派遣して治めさせた幕府の領地。
しはい-てき【支配的】🔗⭐🔉
しはい-てき [0] 【支配的】 (形動)
ある傾向や勢力が全体を左右するさま。「悲観的観測が―になる」
しはい-にん【支配人】🔗⭐🔉
しはい-にん [2] 【支配人】
(1)使用人のうち,営業主に代わって店舗の営業を取り仕切る責任者。マネージャー。
(2)法律上,営業主によって選任され,特定の営業所の営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする,代理権をもつ商業使用人。
→商業使用人
し-はん【支藩】🔗⭐🔉
し-はん [0][1] 【支藩】
本家から分かれた者が藩主である藩。
つか・う【支ふ・閊ふ】🔗⭐🔉
つか・う ツカフ 【支ふ・閊ふ】 (動ハ下二)
⇒つかえる
つかえ【支え・閊え】🔗⭐🔉
つかえ ツカヘ [3][2] 【支え・閊え】
(1)さしつかえ。さしさわり。滞り。「―の出来た日は差繰るとして/杏の落ちる音(虚子)」
(2)(「痞え」と書く)病気や精神的な悩みのために,胸が苦しいこと。「胸の―が下りる」
(3)ささえ。支柱。「―ヲスル/日葡」
つかえ-ばしら【支え柱】🔗⭐🔉
つかえ-ばしら ツカヘ― [4] 【支え柱】
支柱(シチユウ)。ささえばしら。
つか・える【支える・閊える】🔗⭐🔉
つか・える ツカヘル [3] 【支える・閊える】 (動ア下一)[文]ハ下二 つか・ふ
(1)物に妨げられて,先へ進めない状態になる。「天井に頭が―・える」「机が入り口で―・えて部屋に入らない」
(2)途中がつまって流れがとまる。「排水管が―・えて汚水があふれる」「もちがのどに―・える」
(3)言葉がスムーズに発せられないで途中で何度かとまる。「―・え―・え読む」
(4)処理されるべきものが残っていて,先へ進めない。「仕事が―・えている」
(5)(「痞える」と書く)胸・のどなどがふさがった感じになる。「胸が―・える」
(6)(「手をつかえる」の形で)礼をするために両手をつく。「手を―・へつゝ面(カオ)さしいだす/当世書生気質(逍遥)」
(7)肩などがこる。「肩が―・へて灸をすゑに来たのさ/歌舞伎・四谷怪談」
つっか・える【支える】🔗⭐🔉
つっか・える ツツカヘル [4][3] 【支える】 (動ア下一)
〔「つかえる」の転〕
「つかえる」に同じ。「のどに食べ物が―・える」「―・えながら読む」
はせくら【支倉】🔗⭐🔉
はせくら 【支倉】
姓氏の一。
はせくら-つねなが【支倉常長】🔗⭐🔉
はせくら-つねなが 【支倉常長】
(1571-1622) 江戸初期の仙台藩士。伊達政宗の命で1613年渡欧し,ローマで法王パウロ五世に謁見し,市民権を得た。奥州司教区の創設,通商の交渉は成功せず,20年帰国。
ささえ【支え】(和英)🔗⭐🔉
しえん【支援】(和英)🔗⭐🔉
しきゅう【支給】(和英)🔗⭐🔉
しきょく【支局】(和英)🔗⭐🔉
しきょく【支局】
a branch (office).→英和
しじ【支持】(和英)🔗⭐🔉
ししゃ【支社】(和英)🔗⭐🔉
ししゃ【支社】
a branch (office).→英和
ししゅつ【支出】(和英)🔗⭐🔉
ししょ【支署[所]】(和英)🔗⭐🔉
ししょ【支署[所]】
a branch (office).→英和
ししょう【支障】(和英)🔗⭐🔉
ししょう【支障】
⇒差支え.
しせん【支線】(和英)🔗⭐🔉
しせん【支線】
a branch line (鉄道).
したく【支度】(和英)🔗⭐🔉
しちゅう【支柱】(和英)🔗⭐🔉
しちょう【支庁】(和英)🔗⭐🔉
しちょう【支庁】
a branch administrative office.
してん【支店】(和英)🔗⭐🔉
してん【支店】
a branch (office,shop).→英和
〜を設ける open a branch.‖支店長 a branch manager.
してん【支点】(和英)🔗⭐🔉
してん【支点】
《理》a fulcrum.→英和
しはい【支配】(和英)🔗⭐🔉
大辞林に「支」で始まるの検索結果 1-100。もっと読み込む