複数辞典一括検索+![]()
![]()
あら-ぞめ【荒染・退紅・桃花染】🔗⭐🔉
あら-ぞめ 【荒染・退紅・桃花染】
(1)紅花で染めた薄い紅色。洗い染。
(2)薄い紅色の布狩衣(ヌノカリギヌ)の短いもの。仕丁が着用した。
とう-か【桃花】🔗⭐🔉
とう-か タウクワ [1] 【桃花】
桃の花。
とうか-げん【桃花源】🔗⭐🔉
とうか-げん タウクワ― [3] 【桃花源】
「桃源(トウゲン)」に同じ。
とうか-じゅく【桃花粥】🔗⭐🔉
とうか-じゅく タウクワ― [3] 【桃花粥】
もと中国で,寒食(カンシヨク)の日に食べたかゆ。
とうか-すい【桃花水】🔗⭐🔉
とうか-すい タウクワ― [3] 【桃花水】
春,雪解けのために増す川の水。
とうか-の-せつ【桃花の節】🔗⭐🔉
とうか-の-せつ タウクワ― 【桃花の節】
桃の節句。上巳(ジヨウシ)。
とうかげんき【桃花源記】🔗⭐🔉
とうかげんき タウクワゲンキ 【桃花源記】
中国の伝奇的散文。東晋の陶淵明(トウエンメイ)の作。道に迷った武陵の漁夫が,桃林の奥に秦の乱を避けた者の子孫が世の変遷も知らずに平和に暮らしている仙境を見いだしたという話。老子の小国寡民(カミン)のユートピア思想を描く。
とうかずいよう【桃華蘂葉】🔗⭐🔉
とうかずいよう タウクワズイエフ 【桃華蘂葉】
〔「桃華」は一条家の別名〕
有職故実書。一巻。一条兼良著。1480年成立。兼良が死の前年に,その子冬良に一条家の故実を伝えるために記した書。
とうかせん【桃花扇】🔗⭐🔉
とうかせん タウクワセン 【桃花扇】
中国,清代の戯曲。四〇幕。孔尚任(コウシヨウジン)作。1699年完成。明朝滅亡を背景に,文人侯方域(コウホウイキ)と名妓(メイギ)李香君(リコウクン)の悲恋物語を描いたもの。「長生殿」と並ぶ清代の代表的戯曲。桃花扇伝奇。
とう-げん【桃源】🔗⭐🔉
とう-げん タウ― [0] 【桃源】
〔陶淵明の「桃花源記」に描かれた理想郷から〕
俗世間を離れた平和な世界。仙境。桃源郷。ユートピア。
とうげん-きょう【桃源郷】🔗⭐🔉
とうげん-きょう タウ―キヤウ [0] 【桃源郷】
「桃源」に同じ。
とうげん-ずいせん【桃源瑞仙】🔗⭐🔉
とうげん-ずいせん タウゲン― 【桃源瑞仙】
(1433-1489) 京都相国寺の禅僧。近江の人。五山文学者。「史記抄」「三体詩抄」「百衲襖(周易の抄)」などの抄物を著した。
とうせい-き【桃青忌】🔗⭐🔉
とうせい-き タウセイ― [3] 【桃青忌】
〔生前の号から〕
松尾芭蕉(マツオバシヨウ)の忌日。陰暦一〇月一二日。[季]冬。
→翁忌(オキナキ)
とうちゅうけん-くもえもん【桃中軒雲右衛門】🔗⭐🔉
とうちゅうけん-くもえもん タウチユウケンクモ モン 【桃中軒雲右衛門】
(1873-1916) 浪曲師。本名,山本幸蔵。群馬県生まれ。1907年(明治40)東京本郷座で「義士銘々伝」を口演。迫力ある節調で人気を得る。武士道鼓吹を旗印に浪曲の内容を高め,その地位向上に尽くした。
モン 【桃中軒雲右衛門】
(1873-1916) 浪曲師。本名,山本幸蔵。群馬県生まれ。1907年(明治40)東京本郷座で「義士銘々伝」を口演。迫力ある節調で人気を得る。武士道鼓吹を旗印に浪曲の内容を高め,その地位向上に尽くした。
 モン 【桃中軒雲右衛門】
(1873-1916) 浪曲師。本名,山本幸蔵。群馬県生まれ。1907年(明治40)東京本郷座で「義士銘々伝」を口演。迫力ある節調で人気を得る。武士道鼓吹を旗印に浪曲の内容を高め,その地位向上に尽くした。
モン 【桃中軒雲右衛門】
(1873-1916) 浪曲師。本名,山本幸蔵。群馬県生まれ。1907年(明治40)東京本郷座で「義士銘々伝」を口演。迫力ある節調で人気を得る。武士道鼓吹を旗印に浪曲の内容を高め,その地位向上に尽くした。
とう-にん【桃仁】🔗⭐🔉
とう-にん タウ― [0] 【桃仁】
桃の種子の核を干したもの。消炎・通経薬として漢方で用いる。
とうにん-しゅ【桃仁酒】🔗⭐🔉
とうにん-しゅ タウ― [3][0] 【桃仁酒】
桃仁を焼酎に浸し,砂糖を加えて作った酒。
とう-ふ【桃符】🔗⭐🔉
とう-ふ タウ― [1][0] 【桃符】
中国で,元旦などに門の脇に張る桃の木で作った魔よけの札。神の像や吉祥の文字を記す。
とう-よう【桃夭】🔗⭐🔉
とう-よう タウエウ [0] 【桃夭】
〔「詩経(周南,桃夭)」による。「夭」は若くしなやかなさま。若々しい娘をみずみずしい桃にたとえる〕
嫁ぐのにふさわしい年頃。嫁入りどき。婚期。
とうよう-とう【桃葉湯】🔗⭐🔉
とうよう-とう タウエフタウ [0] 【桃葉湯】
桃の葉を入れた風呂。暑気払いに入るもの。[季]夏。
とう-り【桃李】🔗⭐🔉
とう-り タウ― [1] 【桃李】
(1)桃と李(スモモ)。
(2)〔劉禹錫の寄 王侍郎放榜
王侍郎放榜 詩「一日声名
詩「一日声名
 天下
天下 ,満城桃李属
,満城桃李属 春官
春官 」による〕
試験官が採用した優れた門下生。自分がとりたてた人材。
」による〕
試験官が採用した優れた門下生。自分がとりたてた人材。
 王侍郎放榜
王侍郎放榜 詩「一日声名
詩「一日声名
 天下
天下 ,満城桃李属
,満城桃李属 春官
春官 」による〕
試験官が採用した優れた門下生。自分がとりたてた人材。
」による〕
試験官が採用した優れた門下生。自分がとりたてた人材。
とうり=もの言わざれども下(シタ)自(オノズカ)ら蹊(ミチ)を成す🔗⭐🔉
――もの言わざれども下(シタ)自(オノズカ)ら蹊(ミチ)を成す
〔史記(李将軍伝賛)〕
桃や李(スモモ)は何も言わないが,美しい花にひかれて人が集まり,その下には自然に道ができる。徳のある者は弁舌を用いなくても,人はその徳を慕って集まり帰服する。
とうり=門に満つ🔗⭐🔉
――門に満つ
〔資治通鑑(唐則天后久視元年)〕
門下に俊秀の士がたくさんいることにいう。
とう-りん【桃林】🔗⭐🔉
とう-りん タウ― [0] 【桃林】
(1)モモの林。
(2)〔書経(武成篇)「放 牛于桃林之野
牛于桃林之野 」〕
牛の異名。
」〕
牛の異名。
 牛于桃林之野
牛于桃林之野 」〕
牛の異名。
」〕
牛の異名。
とき【鴇・朱鷺・桃花鳥】🔗⭐🔉
とき [1] 【鴇・朱鷺・桃花鳥】
コウノトリ目トキ科の鳥。学名ニッポニア-ニッポン。全長約75センチメートル。全身が白色の羽毛に覆われ,後頭部に長い冠羽がある。翼や尾羽は淡紅色(鴇色)を呈し,顔の裸出部と脚は赤色。繁殖期には羽色が灰色となる。黒く長いくちばしは下方に湾曲する。日本では1981年(昭和56)に野生種は絶滅し,現在,中国陝西(センセイ)省で繁殖が確認されているのみ。特別天然記念物および国際保護鳥。朱鷺(シユロ)。
鴇
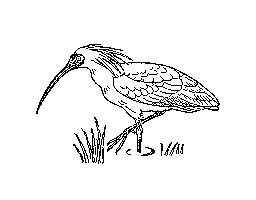 [図]
[図]
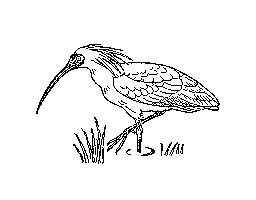 [図]
[図]
もも【桃】🔗⭐🔉
もも [0] 【桃】
(1)バラ科の落葉小高木。中国北部原産。果樹および花木として栽培。葉は披針形で互生する。春,淡紅・濃紅・白などの五弁または重弁花を開く。核果は球形で大きく,ビロード状の毛がある。果肉は柔らかく多汁で甘い。つぼみや種子を漢方で薬用とし,葉は浴湯料に,樹皮は染色に用いられる。[季]秋。
〔「桃の花」は [季]春〕
(2)「桃の節句」の略。
(3)「桃割れ」の略。
もも=栗((モモクリ))三年柿(カキ)八年🔗⭐🔉
――栗((モモクリ))三年柿(カキ)八年
芽を出してから桃と栗は三年で,柿は八年で実を結ぶ。
もも-いろ【桃色】🔗⭐🔉
もも-いろ [0] 【桃色】
(1)桃の花の色に似たうす赤色。淡紅色。ピンク。
(2)男女の色情に関すること。「―遊戯」「―事件」
もも-かわ【楊梅皮・桃皮】🔗⭐🔉
もも-かわ ―カハ [0] 【楊梅皮・桃皮】
ヤマモモの樹皮を乾燥したもの。煎汁を薬用または染料とする。渋木(シブキ)。
もも-じり【桃尻】🔗⭐🔉
もも-じり [0] 【桃尻】
(1)〔桃の実が,すわりが悪いことから〕
馬に乗るのがへたで,鞍(クラ)の上に尻がうまくすわらないこと。「―にて落ちなんは,心憂かるべし/徒然 188」
(2)尻をもじもじさせて落ち着かないこと。「ものさへいへば粋かと思ひ―してゐる人に/浮世草子・好色敗毒散」
もも-ぞの【桃園】🔗⭐🔉
もも-ぞの [0] 【桃園】
桃の木を多く植えた庭園。
ももぞの-てんのう【桃園天皇】🔗⭐🔉
ももぞの-てんのう ―テンワウ 【桃園天皇】
(1741-1762) 第一一六代天皇(在位 1747-1762)。桜町天皇の第一皇子。名は遐仁(トオヒト)。治政下,宝暦事件が起こった。
もも-ぞめ【桃染め】🔗⭐🔉
もも-ぞめ [0] 【桃染め】
桃色に染めること。また,その色。退紅(アラゾメ)。つきそめ。
ももたろう【桃太郎】🔗⭐🔉
ももたろう モモタラウ 【桃太郎】
昔話。異常誕生譚の一。桃から生まれた桃太郎が大きくなって黍(キビ)だんごを持ち,犬・猿・雉(キジ)を家来にして鬼退治に行くというもの。臼(ウス)・蜂(ハチ)・牛糞などの助けで鬼退治をするという話もある。
ももたろうのたんじょう【桃太郎の誕生】🔗⭐🔉
ももたろうのたんじょう モモタラウノタンジヤウ 【桃太郎の誕生】
昔話の研究書。柳田国男著。1933年(昭和8)刊。小さ子譚の問題を中心として,九編の論考が収録されている。
もものい【桃井】🔗⭐🔉
もものい モモノ 【桃井】
姓氏の一。
【桃井】
姓氏の一。
 【桃井】
姓氏の一。
【桃井】
姓氏の一。
もものい-こうわかまる【桃井幸若丸】🔗⭐🔉
もものい-こうわかまる モモノ カウワカマル 【桃井幸若丸】
南北朝後期の幸若舞の始祖といわれる人。越前の人。武将桃井直常の孫といわれる。幸若丸は幼名,長じて直詮(ナオアキ)。比叡山の稚児であったとき,軍記・草子に節付けをして幸若舞を創始したと伝えられる。生没年未詳。
カウワカマル 【桃井幸若丸】
南北朝後期の幸若舞の始祖といわれる人。越前の人。武将桃井直常の孫といわれる。幸若丸は幼名,長じて直詮(ナオアキ)。比叡山の稚児であったとき,軍記・草子に節付けをして幸若舞を創始したと伝えられる。生没年未詳。
 カウワカマル 【桃井幸若丸】
南北朝後期の幸若舞の始祖といわれる人。越前の人。武将桃井直常の孫といわれる。幸若丸は幼名,長じて直詮(ナオアキ)。比叡山の稚児であったとき,軍記・草子に節付けをして幸若舞を創始したと伝えられる。生没年未詳。
カウワカマル 【桃井幸若丸】
南北朝後期の幸若舞の始祖といわれる人。越前の人。武将桃井直常の孫といわれる。幸若丸は幼名,長じて直詮(ナオアキ)。比叡山の稚児であったとき,軍記・草子に節付けをして幸若舞を創始したと伝えられる。生没年未詳。
もものう-さく【桃生柵】🔗⭐🔉
もものう-さく モモノフ― 【桃生柵】
古代,陸奥(ムツ)国に設けられた城柵。律令政府が蝦夷支配のために759年に築造。宮城県桃生郡河北町にある。桃生城。
もも-の-さけ【桃の酒】🔗⭐🔉
もも-の-さけ [0] 【桃の酒】
桃の花を浸した酒。三月三日の節句に供え,これを飲めば万病を払うという。[季]春。
もも-の-せっく【桃の節句】🔗⭐🔉
もも-の-せっく [0] 【桃の節句】
三月三日の節句。上巳(ジヨウシ)の節句。ひなまつり。[季]春。
もも-の-ゆみ【桃の弓】🔗⭐🔉
もも-の-ゆみ 【桃の弓】
追儺(ツイナ)に用いる桃の木で作った弓。悪鬼を追い払う呪力を持つと信じられた。
もも-まゆ【桃眉】🔗⭐🔉
もも-まゆ 【桃眉】
「茫眉(ボウマユ)」に同じ。
もも-やま【桃山】🔗⭐🔉
もも-やま [0] 【桃山】
和菓子の名。白餡(アン)に砂糖・みじん粉・卵黄を加え,模様をつけて焼いたもの。現在はこれを皮として餡を包んだものもある。
ももやま【桃山】🔗⭐🔉
ももやま 【桃山】
京都市伏見区の地名。豊臣秀吉が伏見城を築いた地で,江戸初期廃城後,桃を植えて桃林としたことに由来する名称という。桓武・明治天皇の陵がある。
ももやま-じだい【桃山時代】🔗⭐🔉
ももやま-じだい [5] 【桃山時代】
一六世紀後半の豊臣秀吉が政権を握っていた時代。秀吉が築いた伏見城の地をのちに桃山と呼んだことに由来する。
→安土桃山時代
ももやま-ぶんか【桃山文化】🔗⭐🔉
ももやま-ぶんか ―クワ [5] 【桃山文化】
桃山時代の文化。美術史上では安土時代を含めていう。新興大名の成長と都市の豪商たちの財力を背景として生み出された自由清新な文化で,大坂城・聚楽第(ジユラクダイ)・伏見城などの城郭が建築され,絵画では豪華雄大な障壁画が発達した。芸能では千利休によって茶の湯が大成され,能楽が盛んとなり,浄瑠璃や阿国(オクニ)歌舞伎などが発達した。また,南蛮文化の影響も見逃せない。
ももやまがくいん-だいがく【桃山学院大学】🔗⭐🔉
ももやまがくいん-だいがく モモヤマガク ン― 【桃山学院大学】
私立大学の一。1884年(明治17)聖公会宣教師が開いた男子塾を源とし,1959年(昭和34)設立。本部は堺市。
ン― 【桃山学院大学】
私立大学の一。1884年(明治17)聖公会宣教師が開いた男子塾を源とし,1959年(昭和34)設立。本部は堺市。
 ン― 【桃山学院大学】
私立大学の一。1884年(明治17)聖公会宣教師が開いた男子塾を源とし,1959年(昭和34)設立。本部は堺市。
ン― 【桃山学院大学】
私立大学の一。1884年(明治17)聖公会宣教師が開いた男子塾を源とし,1959年(昭和34)設立。本部は堺市。
もも-ゆ【桃湯】🔗⭐🔉
もも-ゆ [0] 【桃湯】
夏の土用に桃の葉を入れてわかした風呂。また,それに入浴すること。あせもにきくという。
もも-われ【桃割れ】🔗⭐🔉
もも-われ [0] 【桃割れ】
日本髪の髪形の一。髷(マゲ)を二つに分け,割った桃のように丸く輪に結ったもの。明治・大正期に一六,七歳の少女が結った。
桃割れ
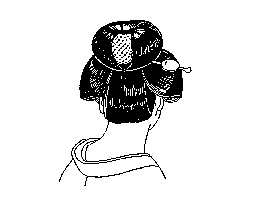 [図]
[図]
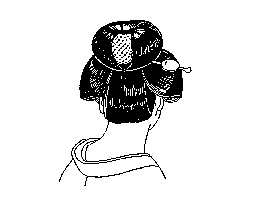 [図]
[図]
とうげんきょう【桃源境】(和英)🔗⭐🔉
とうげんきょう【桃源境】
Arcadia;→英和
Shangri-la.
大辞林に「桃」で始まるの検索結果 1-51。