複数辞典一括検索+![]()
![]()
かば【蒲】🔗⭐🔉
かば [1] 【蒲】
(1)植物ガマの異名。
(2)「蒲色(カバイロ)」の略。
かば-いろ【蒲色・樺色】🔗⭐🔉
かば-いろ [0] 【蒲色・樺色】
赤みの強い茶黄色。かば。
かば-やき【蒲焼(き)】🔗⭐🔉
かば-やき [0] 【蒲焼(き)】
〔もと,ウナギを丸のまま縦に串刺しにして焼いたのが,蒲(ガマ)の穂に似ていたからとも,形・色が樺(カバ)皮に似るからともいう〕
ウナギ・ハモ・アナゴ・ドジョウなどを開いて骨をとり,適当な長さに切って串に刺し,たれをつけて焼く料理法。また,その料理。
がま【蒲・香蒲】🔗⭐🔉
がま [1][0] 【蒲・香蒲】
〔古くは「かま」〕
ガマ科の多年草。池や沼などに生える。高さ1〜2メートル。葉は厚く線形で根生する。夏,茎頂に花穂をつけ,上半に雄花,下半に雌花がつき,雌花部はのちに赤褐色の円柱形となる。漢方で花粉を蒲黄(ホオウ)といい,傷薬にする。みすくさ。[季]夏。
蒲
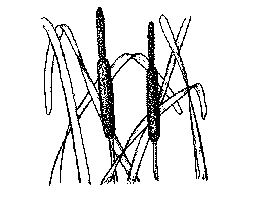 [図]
[図]
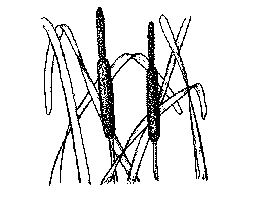 [図]
[図]
がま=の穂綿🔗⭐🔉
――の穂綿
蒲の雌花から成る果穂。蒲団綿(フトンワタ)や火口(ホクチ)に用いた。
がまごおり【蒲郡】🔗⭐🔉
がまごおり ガマゴホリ 【蒲郡】
愛知県,渥美(アツミ)湾北岸にある市。繊維工業が盛ん。三河湾国定公園観光の中心地。
かまた【蒲田】🔗⭐🔉
かまた 【蒲田】
東京都大田区南部の商工業地区。旧区名。東端に東京国際空港がある。
がま-の-かんじゃ【蒲の冠者】🔗⭐🔉
がま-の-かんじゃ ―クワンジヤ 【蒲の冠者】
源範頼(ミナモトノノリヨリ)の異名。遠江国蒲御厨(ガマノミクリヤ)で生まれたのでいう。
かま-ぼこ【蒲鉾】🔗⭐🔉
かま-ぼこ [0] 【蒲鉾】
(1)タイ・ハモ・サメ・エソなど白身の魚肉をすりつぶして味をつけ,練りあげたあと長方形の小板に半月形に塗ったり,簀(ス)巻きにしたりして蒸し上げた食品。昔は,竹に筒形に長く塗った形が蒲(ガマ)の穂に似ていたのでこの名があるが,現在ではこの作り方のものを竹輪(チクワ),板につけたものを板つき蒲鉾という。
(2)宝石をはめ込まない中高の指輪。
(3)蒲の穂。鉾の形に似るところからいう。[本草綱目啓蒙]
かまぼこ-いた【蒲鉾板】🔗⭐🔉
かまぼこ-いた [5] 【蒲鉾板】
板蒲鉾に付いている長方形の小板。
かまぼこ-がた【蒲鉾形】🔗⭐🔉
かまぼこ-がた [0] 【蒲鉾形】
円筒を縦に切ったような形。中高で弓なりになっている形。かまぼこなり。「―兵舎」
かまぼこ-ごや【蒲鉾小屋】🔗⭐🔉
かまぼこ-ごや [0] 【蒲鉾小屋】
竹を骨とし,まわりを筵(ムシロ)などで覆って蒲鉾形に作った粗末な小屋。
かまぼこ-たが【蒲鉾箍】🔗⭐🔉
かまぼこ-たが [4] 【蒲鉾箍】
真鍮(シンチユウ)・銅などのたがで,中央が高く,縁が薄い蒲鉾形のもの。
かまぼこ-なり【蒲鉾形】🔗⭐🔉
かまぼこ-なり [0] 【蒲鉾形】
⇒かまぼこがた(蒲鉾形)
かまぼこ-やね【蒲鉾屋根】🔗⭐🔉
かまぼこ-やね [5] 【蒲鉾屋根】
蒲鉾形の屋根。体育館などにみられる。
かまぼこ-ゆみ【蒲鉾弓】🔗⭐🔉
かまぼこ-ゆみ [4] 【蒲鉾弓】
伏竹(フセダケ)の異名。
がま-むしろ【蒲蓆】🔗⭐🔉
がま-むしろ [3] 【蒲蓆】
蒲の茎で編んだ蓆。夏の敷物とする。[季]夏。《―一枚敷いてあるばかり/高浜年尾》
がもう【蒲生】🔗⭐🔉
がもう ガマフ 【蒲生】
滋賀県南東部の町。日野川流域の丘陵に位置し,米作が中心。百済(クダラ)の様式を模した三重石塔のある石塔寺がある。
がもう【蒲生】🔗⭐🔉
がもう ガマフ 【蒲生】
姓氏の一。
がもう-うじさと【蒲生氏郷】🔗⭐🔉
がもう-うじさと ガマフウヂサト 【蒲生氏郷】
(1556-1595) 安土桃山時代の武将。初名,賦秀(ヤスヒデ)。蒲生賢秀の子。織田信長・豊臣秀吉に仕え,小田原・奥州出兵に活躍。会津九一万石余を領す。キリスト教に入信。
がもう-かたひで【蒲生賢秀】🔗⭐🔉
がもう-かたひで ガマフ― 【蒲生賢秀】
(1534-1584) 安土桃山時代の武将。六角義賢,織田信長に仕える。本能寺の変に際し,信長の家族を日野城に移して守った。
がもう-くんぺい【蒲生君平】🔗⭐🔉
がもう-くんぺい ガマフ― 【蒲生君平】
(1768-1813) 江戸後期の尊王論者。名は秀実。宇都宮の人。藤田幽谷と交わり,水戸学の影響を受けた。著書「山陵志」は幕末尊王論の先駆。林子平・高山彦九郎と並んで寛政の三奇人とされる。
かんばら【蒲原】🔗⭐🔉
かんばら 【蒲原】
静岡県中部,富士川河口西岸にある町。東海道の宿場町から発達。アルミ工場が立地。
かんばら【蒲原】🔗⭐🔉
かんばら 【蒲原】
姓氏の一。
かんばら-ありあけ【蒲原有明】🔗⭐🔉
かんばら-ありあけ 【蒲原有明】
(1876-1952) 詩人。東京生まれ。本名,隼雄。「春鳥集」「有明集」などで日本近代象徴詩の理念と実作を示した。
たんぽぽ【蒲公英】🔗⭐🔉
たんぽぽ [1] 【蒲公英】
キク科タンポポ属の多年草の総称。日当たりのよい草地に生える。葉はロゼット状に叢生し,倒披針形で切れ込みがある。春,中空の花茎を出し,舌状花のみから成る黄色または白色の頭花をつける。柄のある白色の冠毛がついた小さい実が,風に乗って飛び散る。若い葉は食用。カントウタンポポ・エゾタンポポ・セイヨウタンポポなど。[季]春。《―や長江にごるとこしなへ/山口青邨》
→蒲公英(ホコウエイ)
蒲公英
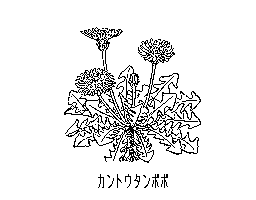 [図]
[図]
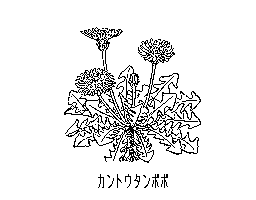 [図]
[図]
たんぽぽ-いろ【蒲公英色】🔗⭐🔉
たんぽぽ-いろ [0] 【蒲公英色】
タンポポの花のような鮮やかな黄色。
び-ろう【檳榔・蒲葵】🔗⭐🔉
び-ろう ―ラウ [0][1] 【檳榔・蒲葵】
ヤシ科の常緑高木。暖地の海岸付近に生え,シュロに似る。高さ10メートル近くになる。葉は大きな扇状で柄が長く,幹の頂に多数集まってつく。花は黄色で小さく,果実は楕円形で青色。古名,あじまさ。
檳榔
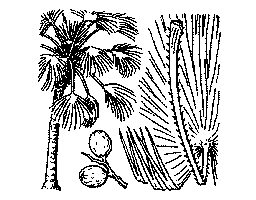 [図]
[図]
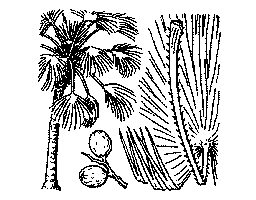 [図]
[図]
ふと-もも【蒲桃】🔗⭐🔉
ふと-もも [0] 【蒲桃】
フトモモ科の常緑小高木。東南アジア原産。葉は披針形で質が厚い。花は白色の四弁花で,雄しべは長く数が多い。液果は径2.5〜5センチメートルの球形で,食用になる。花は観賞用。ローズ-アップル。ホトウ。
ふ-とん【布団・蒲団】🔗⭐🔉
ふ-とん [0] 【布団・蒲団】
〔「蒲団」の唐音,「布」は当て字〕
(1)袋に縫った布の中に綿・鳥の羽毛・わらなどを入れたもの。寝具や防寒・保温用にする。[季]冬。《―着て寝たる姿や東山/嵐雪》
(2)僧や修行者が座禅などに用いる丸い敷物。本来は蒲(ガマ)の葉で編んだ。ほたん。
ふとん【蒲団】🔗⭐🔉
ふとん 【蒲団】
小説。田山花袋作。1907年(明治40)発表。中年の作家が自己の内面の醜悪さを大胆に告白暴露する。日本自然主義文学の方向を決めたとされる作。
ほ-き【蒲葵】🔗⭐🔉
ほ-き [1] 【蒲葵】
植物ビロウの漢名。
ほこうえい【蒲公英】🔗⭐🔉
ほこうえい [2] 【蒲公英】
タンポポの漢名。また,タンポポの葉を乾燥させた生薬。解熱・健胃薬とする。
ほ-じゅこう【蒲寿庚】🔗⭐🔉
ほ-じゅこう ―ジユカウ 【蒲寿庚】
中国,南宋末・元初の南海貿易家。イスラム教徒でアラビア人ともペルシャ人ともいう。泉州の提挙市舶司となる。のちに元に降り,その南海政策に協力。生没年未詳。
ほ-しょうれい【蒲松齢】🔗⭐🔉
ほ-しょうれい 【蒲松齢】
(1640-1715) 中国,清代の文人。字(アザナ)は留仙・剣臣,号は柳泉居士。著に怪異小説集「聊斎志異」,農業・医薬の通俗読物「農桑経」など。
ほ-とう【蒲桃】🔗⭐🔉
ほ-とう ―タウ [0] 【蒲桃】
(1)植物ブドウの異名。
(2)植物フトモモの漢名。
ほ-べん【蒲鞭】🔗⭐🔉
ほ-べん [0] 【蒲鞭】
〔蒲(ガマ)の穂の鞭(ムチ)の意〕
はずかしめるだけで苦痛を加えない寛大な刑罰。また,寛大な政治。
ほ-りゅう【蒲柳】🔗⭐🔉
ほ-りゅう ―リウ [0] 【蒲柳】
〔「蒲柳」はカワヤナギの意。カワヤナギの葉は早く落ちるところから〕
ひよわなこと。虚弱。
ほりゅう-の-しつ【蒲柳の質】🔗⭐🔉
ほりゅう-の-しつ ―リウ― [0][6] 【蒲柳の質】
体がほっそりしていて病気になりやすい弱々しい体質。
かばやき【蒲焼】(和英)🔗⭐🔉
かばやき【蒲焼】
an eel split and broiled.〜にする spitchcock.→英和
かまぼこ【蒲鉾】(和英)🔗⭐🔉
かまぼこ【蒲鉾】
boiled fish paste.蒲鉾形の semicylindrical.
たんぽぽ【蒲公英】(和英)🔗⭐🔉
たんぽぽ【蒲公英】
a dandelion.→英和
大辞林に「蒲」で始まるの検索結果 1-43。