複数辞典一括検索+![]()
![]()
○男を磨くおとこをみがく🔗⭐🔉
○男を磨くおとこをみがく
男達おとこだての修業をする。
⇒おとこ【男】
おと‐さた【音沙汰】
たより。消息。「近ごろ―がない」
▷多く打消の語を伴う。
おとし【落し】
①おとすこと。おとしたもの。「つるべ―」
②入れるはずのものをうっかり忘れること。紫式部日記「え読み侍らぬところどころ、文字―ぞ侍らむ」
③馬などを、急な坂道をくだらせること。平家物語9「究竟の荒馬のり、悪所―」
④鳥獣などを捕らえるしかけ。また、おとし穴。日葡辞書「ヲトシニイルル」→おし(圧)[一]9。
⑤話の結末。話のおち。「―話」
⑥木製火鉢の内部の、灰を入れる部分。銅などでつくる。おとしがけ。「銅あかの―」
⑦戸の桟さんにつけて敷居の穴におとし入れる戸締り用の木片。くるる。
⑧㋐鉱脈中の品位のよい鉱石を含む部分で、下方に長くつづく形のもの。
㋑鉱石や廃石を重力で流し落とす通路。
⑨謡曲で下行する節の一つ。数種の型がある。おち。
⑩近世邦楽で、終止のための定型的な旋律。種目により種々の型がある。例えば義太夫節の大落し・上総かずさ落し、常磐津・清元の豊後落しなど。
⑪ウサギの糞。〈日葡辞書〉
⑫裁ち落し。余りぎれ。
⑬「落し巾着ぎんちゃく」の略。
⇒おとし‐あな【落し穴】
⇒おとし‐あみ【落し網】
⇒おとし‐いも【落し薯】
⇒おとし‐え【落し餌】
⇒おとし‐えん【落し縁】
⇒おとし‐がけ【落し懸け・落し掛け】
⇒おとし‐がみ【落し紙】
⇒おとし‐ぎんちゃく【落し巾着】
⇒おとし‐ご【落し子】
⇒おとし‐ざし【落し差し】
⇒おとし‐だて【落し閉て】
⇒おとし‐だな【落し棚】
⇒おとし‐だね【落し胤】
⇒おとし‐たまご【落し玉子】
⇒おとし‐ちがいだな【落し違い棚】
⇒おとし‐づの【落角】
⇒おとし‐てんじょう【落し天井】
⇒おとし‐どころ【落し所】
⇒おとし‐ぬし【落し主】
⇒おとし‐の‐おや【落しの親】
⇒おとし‐ばなし【落し噺・落し咄】
⇒おとし‐ばらげ【落し散毛】
⇒おとし‐ぶた【落し蓋】
⇒おとし‐ぶみ【落し文・落書】
⇒おとし‐ぼり【落し堀】
⇒おとし‐まえ【落し前】
⇒おとし‐まく【落し幕】
⇒おとし‐みず【落し水】
⇒おとし‐みそ【落し味噌】
⇒おとし‐もの【落し物】
⇒おとし‐もの【落し者】
⇒おとし‐や【落し矢】
⇒おとし‐やき【落し焼】
お‐とじ【大刀自】
⇒おおとじ
おどし【威し・脅し】
①おどすこと。恐れさせること。恐喝。「―に屈しない」「―をかける」「―文句」
②田畑を荒らす鳥獣をおどすために作ったもの。案山子かかしなど。おどせ。おどろかし。
③⇒おどし(縅)。
⇒おどし‐ぐさ【威し種】
⇒おどし‐てっぽう【威し鉄砲】
⇒おどし‐もんく【威し文句・脅し文句】
おどし【縅】ヲドシ
(「緒通し」の意。「縅」は国字、もと「威」と当てた)鎧よろいの札さねを糸または細い革でつづること。また、そのもの。
⇒おどし‐げ【縅毛】
おとし‐あな【落し穴】
①人や鳥獣をだまして落とすために地面に仕掛けた穴。
②人をおとしいれる謀略。「―にはまる」
③大きな失敗や不幸につながることでありながら、うっかり見逃している点。「高度成長の―」
⇒おとし【落し】
おとし‐あみ【落し網】
定置網の一種。魚が逃げないよう昇り勾配のある網をつけ、袋網に誘導する仕掛けをもったもの。大謀網だいぼうあみから発展した。
落し網
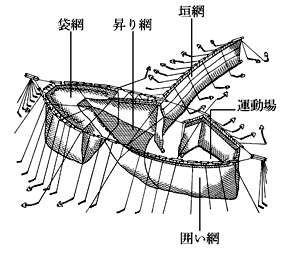 ⇒おとし【落し】
おとし‐いも【落し薯】
吸物にすりいもを落とし入れた料理。
⇒おとし【落し】
おとし‐い・れる【陥れる・落とし入れる】
〔他下一〕[文]おとしい・る(下二)
①中に落ちこませる。おちいらせる。
②だまして苦しい立場にはめこむ。「無実の人を罪に―・れる」
③城や敵陣などを攻めとる。
おとし‐え【落し餌】‥ヱ
鷹が雛に樹上から落として与える餌。
⇒おとし【落し】
おとし‐えん【落し縁】
(→)落縁おちえんに同じ。
⇒おとし【落し】
おとし‐がけ【落し懸け・落し掛け】
①急な坂。源氏物語東屋「―の高き所に」
②仏龕ぶつがんなどの欄間らんまの下につける雲形などのほりもの。
③床の間や書院窓の上に架けわたす横木。
④元禄頃に流行した元結もとゆいのかけ方。根元に近くかけるもの。
⑤火鉢のおとし。
⇒おとし【落し】
おとし‐がみ【落し紙】
便所で使う紙。清紙きよめがみ。
⇒おとし【落し】
おとし‐ぎんちゃく【落し巾着】
ひもをつけて首や襟えりにかけるようにした巾着。おとし。
⇒おとし【落し】
おどし‐ぐさ【威し種】
人をおどす材料。源氏物語紅葉賀「たださるべき折の―にせんとぞ思ひける」
⇒おどし【威し・脅し】
おどし‐げ【縅毛】ヲドシ‥
鎧よろいのおどしの革・組み糸・畳み綾の緒の類。並べた状態が毛を伏せたさまに似るのでいう。太平記17「―こそよくも候はねども」
⇒おどし【縅】
おとし‐ご【落し子】
貴人が、妻以外の女に生ませた子。おとしだね。比喩的に、ある事柄に付随して、意図されないで生ずる事柄。「受験地獄の―」
⇒おとし【落し】
おとし‐ざし【落し差し】
刀をきちんとささずに、こじりを下げてさすこと。
⇒おとし【落し】
おとし‐だて【落し閉て】
戸を上から落として閉めるようにしたもの。
⇒おとし【落し】
おとし‐だな【落し棚】
床脇の棚の一形式。落違棚おとしちがいだな。
落し棚
⇒おとし【落し】
おとし‐いも【落し薯】
吸物にすりいもを落とし入れた料理。
⇒おとし【落し】
おとし‐い・れる【陥れる・落とし入れる】
〔他下一〕[文]おとしい・る(下二)
①中に落ちこませる。おちいらせる。
②だまして苦しい立場にはめこむ。「無実の人を罪に―・れる」
③城や敵陣などを攻めとる。
おとし‐え【落し餌】‥ヱ
鷹が雛に樹上から落として与える餌。
⇒おとし【落し】
おとし‐えん【落し縁】
(→)落縁おちえんに同じ。
⇒おとし【落し】
おとし‐がけ【落し懸け・落し掛け】
①急な坂。源氏物語東屋「―の高き所に」
②仏龕ぶつがんなどの欄間らんまの下につける雲形などのほりもの。
③床の間や書院窓の上に架けわたす横木。
④元禄頃に流行した元結もとゆいのかけ方。根元に近くかけるもの。
⑤火鉢のおとし。
⇒おとし【落し】
おとし‐がみ【落し紙】
便所で使う紙。清紙きよめがみ。
⇒おとし【落し】
おとし‐ぎんちゃく【落し巾着】
ひもをつけて首や襟えりにかけるようにした巾着。おとし。
⇒おとし【落し】
おどし‐ぐさ【威し種】
人をおどす材料。源氏物語紅葉賀「たださるべき折の―にせんとぞ思ひける」
⇒おどし【威し・脅し】
おどし‐げ【縅毛】ヲドシ‥
鎧よろいのおどしの革・組み糸・畳み綾の緒の類。並べた状態が毛を伏せたさまに似るのでいう。太平記17「―こそよくも候はねども」
⇒おどし【縅】
おとし‐ご【落し子】
貴人が、妻以外の女に生ませた子。おとしだね。比喩的に、ある事柄に付随して、意図されないで生ずる事柄。「受験地獄の―」
⇒おとし【落し】
おとし‐ざし【落し差し】
刀をきちんとささずに、こじりを下げてさすこと。
⇒おとし【落し】
おとし‐だて【落し閉て】
戸を上から落として閉めるようにしたもの。
⇒おとし【落し】
おとし‐だな【落し棚】
床脇の棚の一形式。落違棚おとしちがいだな。
落し棚
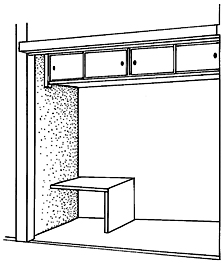 ⇒おとし【落し】
おとし‐だね【落し胤】
貴人が、妻以外の女に生ませた子。落し子。らくいん。
⇒おとし【落し】
お‐としだま【御年玉】
新年のお祝いの贈物。現在では主に子供や使用人などに贈る金品をいう。〈[季]新年〉
おとし‐たまご【落し玉子】
吸物の汁の中へ生卵を割って落とした料理。
⇒おとし【落し】
おとし‐ちがいだな【落し違い棚】‥チガヒ‥
(→)「落し棚」に同じ。
⇒おとし【落し】
おとし‐つ・く【落し着く】
〔他下二〕
①気持をおちつかせる。なだめる。日葡辞書「シアン(思案)ヲヲトシツクル」
②おちつきはらう。どっしりと構える。好色一代女1「万事―・けて居たる客」
③考えを定める。きめこむ。浮世草子、沖津白波「必定一休の正筆に―・け」
おどし‐つ・ける【威し付ける・脅し付ける】
〔他下一〕
ひどくおどす。
おとし‐づの【落角】
晩春から初夏にかけて抜け落ちる牡鹿の角。〈[季]春〉
⇒おとし【落し】
おどし‐てっぽう【威し鉄砲】‥パウ
鳥獣などをおどして追い払うためにうつ空砲。
⇒おどし【威し・脅し】
おとし‐てんじょう【落し天井】‥ジヤウ
他の部分より一段低く作った天井。主として茶室で使われる。おち天井。
⇒おとし【落し】
おとし‐どころ【落し所】
結着を付けるのに最適な場面。「―をさぐる」「―を心得た人」
⇒おとし【落し】
おどし‐と・る【脅し取る】
〔他五〕
脅迫して金品を奪い取る。
おとし‐ぬし【落し主】
その金品を落としたり置き忘れたりした人。「財布の―が現れる」
⇒おとし【落し】
おとし‐の‐おや【落しの親】
仮の親に対して、生みの親のこと。
⇒おとし【落し】
おとし‐ばなし【落し噺・落し咄】
話の最後を語呂合せや洒落しゃれで落ちをつける小話。烏亭焉馬うていえんばらにより話芸として発展、のち落語らくごと呼ばれる。→落語。
⇒おとし【落し】
おとし‐ばらげ【落し散毛】
女の髪の結い方。鬢差びんさしを用いず、鬢を耳の脇に垂れ下がった形に結うもの。江戸後期、文化頃からの髪風。おとしばら。
⇒おとし【落し】
おとし‐ぶた【落し蓋】
①なべなどの、直接材料にかぶせるため、すっぽり中に落ち込むように作った蓋。さしぶた。
②箱の側面を口にし、縦にみぞに沿って上げ下げして開閉するように作った蓋。
⇒おとし【落し】
おとし‐ぶみ【落し文・落書】
①公然と言えないことを記して、わざと通路などに落としておく文書。らくしょ。愚管抄5「かゝる歌よみて、おほく―に書きなどしけるとぞ」
②オトシブミ科の甲虫の総称。また、ナミオトシブミの通称。体長は3〜10ミリメートル。頭部が細長い。夏、広葉樹の葉を丸めた中に産卵して地上に落とす。これを「ほととぎすの落文」「落文の揺籃ようらん」という。中の幼虫は、内面を食べて育つ。〈[季]夏〉
おとしぶみ
⇒おとし【落し】
おとし‐だね【落し胤】
貴人が、妻以外の女に生ませた子。落し子。らくいん。
⇒おとし【落し】
お‐としだま【御年玉】
新年のお祝いの贈物。現在では主に子供や使用人などに贈る金品をいう。〈[季]新年〉
おとし‐たまご【落し玉子】
吸物の汁の中へ生卵を割って落とした料理。
⇒おとし【落し】
おとし‐ちがいだな【落し違い棚】‥チガヒ‥
(→)「落し棚」に同じ。
⇒おとし【落し】
おとし‐つ・く【落し着く】
〔他下二〕
①気持をおちつかせる。なだめる。日葡辞書「シアン(思案)ヲヲトシツクル」
②おちつきはらう。どっしりと構える。好色一代女1「万事―・けて居たる客」
③考えを定める。きめこむ。浮世草子、沖津白波「必定一休の正筆に―・け」
おどし‐つ・ける【威し付ける・脅し付ける】
〔他下一〕
ひどくおどす。
おとし‐づの【落角】
晩春から初夏にかけて抜け落ちる牡鹿の角。〈[季]春〉
⇒おとし【落し】
おどし‐てっぽう【威し鉄砲】‥パウ
鳥獣などをおどして追い払うためにうつ空砲。
⇒おどし【威し・脅し】
おとし‐てんじょう【落し天井】‥ジヤウ
他の部分より一段低く作った天井。主として茶室で使われる。おち天井。
⇒おとし【落し】
おとし‐どころ【落し所】
結着を付けるのに最適な場面。「―をさぐる」「―を心得た人」
⇒おとし【落し】
おどし‐と・る【脅し取る】
〔他五〕
脅迫して金品を奪い取る。
おとし‐ぬし【落し主】
その金品を落としたり置き忘れたりした人。「財布の―が現れる」
⇒おとし【落し】
おとし‐の‐おや【落しの親】
仮の親に対して、生みの親のこと。
⇒おとし【落し】
おとし‐ばなし【落し噺・落し咄】
話の最後を語呂合せや洒落しゃれで落ちをつける小話。烏亭焉馬うていえんばらにより話芸として発展、のち落語らくごと呼ばれる。→落語。
⇒おとし【落し】
おとし‐ばらげ【落し散毛】
女の髪の結い方。鬢差びんさしを用いず、鬢を耳の脇に垂れ下がった形に結うもの。江戸後期、文化頃からの髪風。おとしばら。
⇒おとし【落し】
おとし‐ぶた【落し蓋】
①なべなどの、直接材料にかぶせるため、すっぽり中に落ち込むように作った蓋。さしぶた。
②箱の側面を口にし、縦にみぞに沿って上げ下げして開閉するように作った蓋。
⇒おとし【落し】
おとし‐ぶみ【落し文・落書】
①公然と言えないことを記して、わざと通路などに落としておく文書。らくしょ。愚管抄5「かゝる歌よみて、おほく―に書きなどしけるとぞ」
②オトシブミ科の甲虫の総称。また、ナミオトシブミの通称。体長は3〜10ミリメートル。頭部が細長い。夏、広葉樹の葉を丸めた中に産卵して地上に落とす。これを「ほととぎすの落文」「落文の揺籃ようらん」という。中の幼虫は、内面を食べて育つ。〈[季]夏〉
おとしぶみ
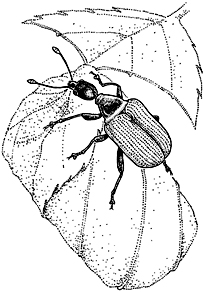 ナミオトシブミ
提供:ネイチャー・プロダクション
ナミオトシブミ
提供:ネイチャー・プロダクション
 ⇒おとし【落し】
おとし‐ぼり【落し堀】
用水の残りを落とすために設けた堀。
⇒おとし【落し】
おとし‐まえ【落し前】‥マヘ
(もと的屋などの隠語)もめごとの仲に立って話をつけること。失敗や無礼をはたらいた時などのあとしまつ。「―をつける」
⇒おとし【落し】
おとし‐まく【落し幕】
劇場で、綱を引くと落ちるように装置した幕。振り落し幕。
⇒おとし【落し】
おとし‐みず【落し水】‥ミヅ
稲を刈る前に、田の水を流し去ること。また、その水。〈[季]秋〉
⇒おとし【落し】
おとし‐みそ【落し味噌】
味噌をすらないままで汁をつくること。また、その汁。
⇒おとし【落し】
おとし・む【貶む】
〔他下二〕
⇒おとしめる(下一)
おとしめ‐ごと【貶め言】
おとしめていう言葉。悪口。源氏物語若菜下「あいなき御―になむと…腹だつを」
おとしめ‐ざま【貶め方】
おとしめるようなこと。侮辱めいたこと。源氏物語蛍「人の上を難つけ、―のこといふ人をば」
おとし・める【貶める】
〔他下一〕[文]おとし・む(下二)
劣ったものとして扱う。みさげる。さげすむ。源氏物語桐壺「―・め、きずをもとめ給ふ人は多く」。「人を―・めた物言い」
おとし‐もの【落し物】
うっかり気づかずに落としたもの。遺失物。
⇒おとし【落し】
おとし‐もの【落し者】
他国または寺院に逃してやる罪人。
⇒おとし【落し】
おどし‐もんく【威し文句・脅し文句】
人を恐れさせる言葉。
⇒おどし【威し・脅し】
おとし‐や【落し矢】
①上差うわざしの矢。
②低い方へ射おろす矢。おろし矢。
⇒おとし【落し】
お‐どしゃ【御土砂】
土砂加持どしゃかじに用いる砂。死体にかけると、硬直がなおるという。
⇒御土砂を掛ける
おとし‐やき【落し焼】
熱したフライパンや鉄板などに材料をスプーンなどで流し落として焼く調理法。また、その料理や菓子。
⇒おとし【落し】
⇒おとし【落し】
おとし‐ぼり【落し堀】
用水の残りを落とすために設けた堀。
⇒おとし【落し】
おとし‐まえ【落し前】‥マヘ
(もと的屋などの隠語)もめごとの仲に立って話をつけること。失敗や無礼をはたらいた時などのあとしまつ。「―をつける」
⇒おとし【落し】
おとし‐まく【落し幕】
劇場で、綱を引くと落ちるように装置した幕。振り落し幕。
⇒おとし【落し】
おとし‐みず【落し水】‥ミヅ
稲を刈る前に、田の水を流し去ること。また、その水。〈[季]秋〉
⇒おとし【落し】
おとし‐みそ【落し味噌】
味噌をすらないままで汁をつくること。また、その汁。
⇒おとし【落し】
おとし・む【貶む】
〔他下二〕
⇒おとしめる(下一)
おとしめ‐ごと【貶め言】
おとしめていう言葉。悪口。源氏物語若菜下「あいなき御―になむと…腹だつを」
おとしめ‐ざま【貶め方】
おとしめるようなこと。侮辱めいたこと。源氏物語蛍「人の上を難つけ、―のこといふ人をば」
おとし・める【貶める】
〔他下一〕[文]おとし・む(下二)
劣ったものとして扱う。みさげる。さげすむ。源氏物語桐壺「―・め、きずをもとめ給ふ人は多く」。「人を―・めた物言い」
おとし‐もの【落し物】
うっかり気づかずに落としたもの。遺失物。
⇒おとし【落し】
おとし‐もの【落し者】
他国または寺院に逃してやる罪人。
⇒おとし【落し】
おどし‐もんく【威し文句・脅し文句】
人を恐れさせる言葉。
⇒おどし【威し・脅し】
おとし‐や【落し矢】
①上差うわざしの矢。
②低い方へ射おろす矢。おろし矢。
⇒おとし【落し】
お‐どしゃ【御土砂】
土砂加持どしゃかじに用いる砂。死体にかけると、硬直がなおるという。
⇒御土砂を掛ける
おとし‐やき【落し焼】
熱したフライパンや鉄板などに材料をスプーンなどで流し落として焼く調理法。また、その料理や菓子。
⇒おとし【落し】
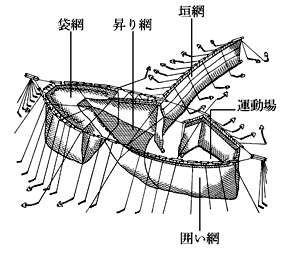 ⇒おとし【落し】
おとし‐いも【落し薯】
吸物にすりいもを落とし入れた料理。
⇒おとし【落し】
おとし‐い・れる【陥れる・落とし入れる】
〔他下一〕[文]おとしい・る(下二)
①中に落ちこませる。おちいらせる。
②だまして苦しい立場にはめこむ。「無実の人を罪に―・れる」
③城や敵陣などを攻めとる。
おとし‐え【落し餌】‥ヱ
鷹が雛に樹上から落として与える餌。
⇒おとし【落し】
おとし‐えん【落し縁】
(→)落縁おちえんに同じ。
⇒おとし【落し】
おとし‐がけ【落し懸け・落し掛け】
①急な坂。源氏物語東屋「―の高き所に」
②仏龕ぶつがんなどの欄間らんまの下につける雲形などのほりもの。
③床の間や書院窓の上に架けわたす横木。
④元禄頃に流行した元結もとゆいのかけ方。根元に近くかけるもの。
⑤火鉢のおとし。
⇒おとし【落し】
おとし‐がみ【落し紙】
便所で使う紙。清紙きよめがみ。
⇒おとし【落し】
おとし‐ぎんちゃく【落し巾着】
ひもをつけて首や襟えりにかけるようにした巾着。おとし。
⇒おとし【落し】
おどし‐ぐさ【威し種】
人をおどす材料。源氏物語紅葉賀「たださるべき折の―にせんとぞ思ひける」
⇒おどし【威し・脅し】
おどし‐げ【縅毛】ヲドシ‥
鎧よろいのおどしの革・組み糸・畳み綾の緒の類。並べた状態が毛を伏せたさまに似るのでいう。太平記17「―こそよくも候はねども」
⇒おどし【縅】
おとし‐ご【落し子】
貴人が、妻以外の女に生ませた子。おとしだね。比喩的に、ある事柄に付随して、意図されないで生ずる事柄。「受験地獄の―」
⇒おとし【落し】
おとし‐ざし【落し差し】
刀をきちんとささずに、こじりを下げてさすこと。
⇒おとし【落し】
おとし‐だて【落し閉て】
戸を上から落として閉めるようにしたもの。
⇒おとし【落し】
おとし‐だな【落し棚】
床脇の棚の一形式。落違棚おとしちがいだな。
落し棚
⇒おとし【落し】
おとし‐いも【落し薯】
吸物にすりいもを落とし入れた料理。
⇒おとし【落し】
おとし‐い・れる【陥れる・落とし入れる】
〔他下一〕[文]おとしい・る(下二)
①中に落ちこませる。おちいらせる。
②だまして苦しい立場にはめこむ。「無実の人を罪に―・れる」
③城や敵陣などを攻めとる。
おとし‐え【落し餌】‥ヱ
鷹が雛に樹上から落として与える餌。
⇒おとし【落し】
おとし‐えん【落し縁】
(→)落縁おちえんに同じ。
⇒おとし【落し】
おとし‐がけ【落し懸け・落し掛け】
①急な坂。源氏物語東屋「―の高き所に」
②仏龕ぶつがんなどの欄間らんまの下につける雲形などのほりもの。
③床の間や書院窓の上に架けわたす横木。
④元禄頃に流行した元結もとゆいのかけ方。根元に近くかけるもの。
⑤火鉢のおとし。
⇒おとし【落し】
おとし‐がみ【落し紙】
便所で使う紙。清紙きよめがみ。
⇒おとし【落し】
おとし‐ぎんちゃく【落し巾着】
ひもをつけて首や襟えりにかけるようにした巾着。おとし。
⇒おとし【落し】
おどし‐ぐさ【威し種】
人をおどす材料。源氏物語紅葉賀「たださるべき折の―にせんとぞ思ひける」
⇒おどし【威し・脅し】
おどし‐げ【縅毛】ヲドシ‥
鎧よろいのおどしの革・組み糸・畳み綾の緒の類。並べた状態が毛を伏せたさまに似るのでいう。太平記17「―こそよくも候はねども」
⇒おどし【縅】
おとし‐ご【落し子】
貴人が、妻以外の女に生ませた子。おとしだね。比喩的に、ある事柄に付随して、意図されないで生ずる事柄。「受験地獄の―」
⇒おとし【落し】
おとし‐ざし【落し差し】
刀をきちんとささずに、こじりを下げてさすこと。
⇒おとし【落し】
おとし‐だて【落し閉て】
戸を上から落として閉めるようにしたもの。
⇒おとし【落し】
おとし‐だな【落し棚】
床脇の棚の一形式。落違棚おとしちがいだな。
落し棚
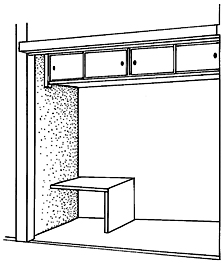 ⇒おとし【落し】
おとし‐だね【落し胤】
貴人が、妻以外の女に生ませた子。落し子。らくいん。
⇒おとし【落し】
お‐としだま【御年玉】
新年のお祝いの贈物。現在では主に子供や使用人などに贈る金品をいう。〈[季]新年〉
おとし‐たまご【落し玉子】
吸物の汁の中へ生卵を割って落とした料理。
⇒おとし【落し】
おとし‐ちがいだな【落し違い棚】‥チガヒ‥
(→)「落し棚」に同じ。
⇒おとし【落し】
おとし‐つ・く【落し着く】
〔他下二〕
①気持をおちつかせる。なだめる。日葡辞書「シアン(思案)ヲヲトシツクル」
②おちつきはらう。どっしりと構える。好色一代女1「万事―・けて居たる客」
③考えを定める。きめこむ。浮世草子、沖津白波「必定一休の正筆に―・け」
おどし‐つ・ける【威し付ける・脅し付ける】
〔他下一〕
ひどくおどす。
おとし‐づの【落角】
晩春から初夏にかけて抜け落ちる牡鹿の角。〈[季]春〉
⇒おとし【落し】
おどし‐てっぽう【威し鉄砲】‥パウ
鳥獣などをおどして追い払うためにうつ空砲。
⇒おどし【威し・脅し】
おとし‐てんじょう【落し天井】‥ジヤウ
他の部分より一段低く作った天井。主として茶室で使われる。おち天井。
⇒おとし【落し】
おとし‐どころ【落し所】
結着を付けるのに最適な場面。「―をさぐる」「―を心得た人」
⇒おとし【落し】
おどし‐と・る【脅し取る】
〔他五〕
脅迫して金品を奪い取る。
おとし‐ぬし【落し主】
その金品を落としたり置き忘れたりした人。「財布の―が現れる」
⇒おとし【落し】
おとし‐の‐おや【落しの親】
仮の親に対して、生みの親のこと。
⇒おとし【落し】
おとし‐ばなし【落し噺・落し咄】
話の最後を語呂合せや洒落しゃれで落ちをつける小話。烏亭焉馬うていえんばらにより話芸として発展、のち落語らくごと呼ばれる。→落語。
⇒おとし【落し】
おとし‐ばらげ【落し散毛】
女の髪の結い方。鬢差びんさしを用いず、鬢を耳の脇に垂れ下がった形に結うもの。江戸後期、文化頃からの髪風。おとしばら。
⇒おとし【落し】
おとし‐ぶた【落し蓋】
①なべなどの、直接材料にかぶせるため、すっぽり中に落ち込むように作った蓋。さしぶた。
②箱の側面を口にし、縦にみぞに沿って上げ下げして開閉するように作った蓋。
⇒おとし【落し】
おとし‐ぶみ【落し文・落書】
①公然と言えないことを記して、わざと通路などに落としておく文書。らくしょ。愚管抄5「かゝる歌よみて、おほく―に書きなどしけるとぞ」
②オトシブミ科の甲虫の総称。また、ナミオトシブミの通称。体長は3〜10ミリメートル。頭部が細長い。夏、広葉樹の葉を丸めた中に産卵して地上に落とす。これを「ほととぎすの落文」「落文の揺籃ようらん」という。中の幼虫は、内面を食べて育つ。〈[季]夏〉
おとしぶみ
⇒おとし【落し】
おとし‐だね【落し胤】
貴人が、妻以外の女に生ませた子。落し子。らくいん。
⇒おとし【落し】
お‐としだま【御年玉】
新年のお祝いの贈物。現在では主に子供や使用人などに贈る金品をいう。〈[季]新年〉
おとし‐たまご【落し玉子】
吸物の汁の中へ生卵を割って落とした料理。
⇒おとし【落し】
おとし‐ちがいだな【落し違い棚】‥チガヒ‥
(→)「落し棚」に同じ。
⇒おとし【落し】
おとし‐つ・く【落し着く】
〔他下二〕
①気持をおちつかせる。なだめる。日葡辞書「シアン(思案)ヲヲトシツクル」
②おちつきはらう。どっしりと構える。好色一代女1「万事―・けて居たる客」
③考えを定める。きめこむ。浮世草子、沖津白波「必定一休の正筆に―・け」
おどし‐つ・ける【威し付ける・脅し付ける】
〔他下一〕
ひどくおどす。
おとし‐づの【落角】
晩春から初夏にかけて抜け落ちる牡鹿の角。〈[季]春〉
⇒おとし【落し】
おどし‐てっぽう【威し鉄砲】‥パウ
鳥獣などをおどして追い払うためにうつ空砲。
⇒おどし【威し・脅し】
おとし‐てんじょう【落し天井】‥ジヤウ
他の部分より一段低く作った天井。主として茶室で使われる。おち天井。
⇒おとし【落し】
おとし‐どころ【落し所】
結着を付けるのに最適な場面。「―をさぐる」「―を心得た人」
⇒おとし【落し】
おどし‐と・る【脅し取る】
〔他五〕
脅迫して金品を奪い取る。
おとし‐ぬし【落し主】
その金品を落としたり置き忘れたりした人。「財布の―が現れる」
⇒おとし【落し】
おとし‐の‐おや【落しの親】
仮の親に対して、生みの親のこと。
⇒おとし【落し】
おとし‐ばなし【落し噺・落し咄】
話の最後を語呂合せや洒落しゃれで落ちをつける小話。烏亭焉馬うていえんばらにより話芸として発展、のち落語らくごと呼ばれる。→落語。
⇒おとし【落し】
おとし‐ばらげ【落し散毛】
女の髪の結い方。鬢差びんさしを用いず、鬢を耳の脇に垂れ下がった形に結うもの。江戸後期、文化頃からの髪風。おとしばら。
⇒おとし【落し】
おとし‐ぶた【落し蓋】
①なべなどの、直接材料にかぶせるため、すっぽり中に落ち込むように作った蓋。さしぶた。
②箱の側面を口にし、縦にみぞに沿って上げ下げして開閉するように作った蓋。
⇒おとし【落し】
おとし‐ぶみ【落し文・落書】
①公然と言えないことを記して、わざと通路などに落としておく文書。らくしょ。愚管抄5「かゝる歌よみて、おほく―に書きなどしけるとぞ」
②オトシブミ科の甲虫の総称。また、ナミオトシブミの通称。体長は3〜10ミリメートル。頭部が細長い。夏、広葉樹の葉を丸めた中に産卵して地上に落とす。これを「ほととぎすの落文」「落文の揺籃ようらん」という。中の幼虫は、内面を食べて育つ。〈[季]夏〉
おとしぶみ
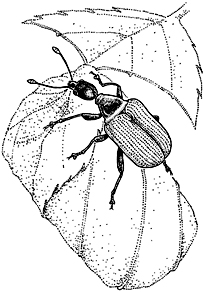 ナミオトシブミ
提供:ネイチャー・プロダクション
ナミオトシブミ
提供:ネイチャー・プロダクション
 ⇒おとし【落し】
おとし‐ぼり【落し堀】
用水の残りを落とすために設けた堀。
⇒おとし【落し】
おとし‐まえ【落し前】‥マヘ
(もと的屋などの隠語)もめごとの仲に立って話をつけること。失敗や無礼をはたらいた時などのあとしまつ。「―をつける」
⇒おとし【落し】
おとし‐まく【落し幕】
劇場で、綱を引くと落ちるように装置した幕。振り落し幕。
⇒おとし【落し】
おとし‐みず【落し水】‥ミヅ
稲を刈る前に、田の水を流し去ること。また、その水。〈[季]秋〉
⇒おとし【落し】
おとし‐みそ【落し味噌】
味噌をすらないままで汁をつくること。また、その汁。
⇒おとし【落し】
おとし・む【貶む】
〔他下二〕
⇒おとしめる(下一)
おとしめ‐ごと【貶め言】
おとしめていう言葉。悪口。源氏物語若菜下「あいなき御―になむと…腹だつを」
おとしめ‐ざま【貶め方】
おとしめるようなこと。侮辱めいたこと。源氏物語蛍「人の上を難つけ、―のこといふ人をば」
おとし・める【貶める】
〔他下一〕[文]おとし・む(下二)
劣ったものとして扱う。みさげる。さげすむ。源氏物語桐壺「―・め、きずをもとめ給ふ人は多く」。「人を―・めた物言い」
おとし‐もの【落し物】
うっかり気づかずに落としたもの。遺失物。
⇒おとし【落し】
おとし‐もの【落し者】
他国または寺院に逃してやる罪人。
⇒おとし【落し】
おどし‐もんく【威し文句・脅し文句】
人を恐れさせる言葉。
⇒おどし【威し・脅し】
おとし‐や【落し矢】
①上差うわざしの矢。
②低い方へ射おろす矢。おろし矢。
⇒おとし【落し】
お‐どしゃ【御土砂】
土砂加持どしゃかじに用いる砂。死体にかけると、硬直がなおるという。
⇒御土砂を掛ける
おとし‐やき【落し焼】
熱したフライパンや鉄板などに材料をスプーンなどで流し落として焼く調理法。また、その料理や菓子。
⇒おとし【落し】
⇒おとし【落し】
おとし‐ぼり【落し堀】
用水の残りを落とすために設けた堀。
⇒おとし【落し】
おとし‐まえ【落し前】‥マヘ
(もと的屋などの隠語)もめごとの仲に立って話をつけること。失敗や無礼をはたらいた時などのあとしまつ。「―をつける」
⇒おとし【落し】
おとし‐まく【落し幕】
劇場で、綱を引くと落ちるように装置した幕。振り落し幕。
⇒おとし【落し】
おとし‐みず【落し水】‥ミヅ
稲を刈る前に、田の水を流し去ること。また、その水。〈[季]秋〉
⇒おとし【落し】
おとし‐みそ【落し味噌】
味噌をすらないままで汁をつくること。また、その汁。
⇒おとし【落し】
おとし・む【貶む】
〔他下二〕
⇒おとしめる(下一)
おとしめ‐ごと【貶め言】
おとしめていう言葉。悪口。源氏物語若菜下「あいなき御―になむと…腹だつを」
おとしめ‐ざま【貶め方】
おとしめるようなこと。侮辱めいたこと。源氏物語蛍「人の上を難つけ、―のこといふ人をば」
おとし・める【貶める】
〔他下一〕[文]おとし・む(下二)
劣ったものとして扱う。みさげる。さげすむ。源氏物語桐壺「―・め、きずをもとめ給ふ人は多く」。「人を―・めた物言い」
おとし‐もの【落し物】
うっかり気づかずに落としたもの。遺失物。
⇒おとし【落し】
おとし‐もの【落し者】
他国または寺院に逃してやる罪人。
⇒おとし【落し】
おどし‐もんく【威し文句・脅し文句】
人を恐れさせる言葉。
⇒おどし【威し・脅し】
おとし‐や【落し矢】
①上差うわざしの矢。
②低い方へ射おろす矢。おろし矢。
⇒おとし【落し】
お‐どしゃ【御土砂】
土砂加持どしゃかじに用いる砂。死体にかけると、硬直がなおるという。
⇒御土砂を掛ける
おとし‐やき【落し焼】
熱したフライパンや鉄板などに材料をスプーンなどで流し落として焼く調理法。また、その料理や菓子。
⇒おとし【落し】
広辞苑 ページ 2879 での【○男を磨く】単語。