複数辞典一括検索+![]()
![]()
○毛を以て馬を相すけをもってうまをそうす🔗⭐🔉
○毛を以て馬を相すけをもってうまをそうす
[塩鉄論利議]毛色によって、馬のよしあしを判断する意で、外見だけで事物の価値を判断する。皮相の観察をする。
⇒け【毛】
けん
料理のつけあわせ。刺身などのつま。浄瑠璃、傾城酒呑童子「―に置いたるめうがの程ぞ恐しき」
けん【件】
ひとくだりのこと。事柄。また、事柄を数えるのに用いる語。「先日の―」
けん【見】
①目のつけかた。見かた。考え。狂言、布施無経ふせないきょう「有ると思へば有の―、無いと思へば無の―」
②素見すけん。ひやかし。浮世草子、世間娘容気「遊女の―して帰るなど」
けん【券】
①荘園・田地などの所有を証明する手形。また、割符わりふ・切手・信用証書・印紙・証文の類。落窪物語3「家といふ物は―持たる人よりほかにしる人なき」
②切符きっぷ。
けん【妍】
美しいこと。なまめかしく、あでやかなこと。「―をきそう」
けん【県】
①中国の行政区画の一つ。春秋時代、国を滅ぼして県とすることが一般化。戦国時代以後郡の下に県が置かれ、後代、州または府で県を統べ、民国初めには道の下に県を置く。現在は省(および自治区・直轄市)の下に県がある。「―城」
②日本の地方行政区画の一つ。1871年(明治4)廃藩置県により藩に代えて設置。現在は普通地方公共団体およびその区域の一つ。→都道府県
けん【倹】
費用を節約すること。つつましいこと。「―につとめる」
けん【兼】
かねること。あわせもつこと。「首相―外相」
けん【剣】
①諸刃もろはの太刀。つるぎ。刃物。
②剣を使う技。剣術。撃剣。「―の達人」
⇒剣は一人の敵、学ぶに足らず
⇒剣を売り牛を買わしむ
⇒剣を落として舟を刻む
けん【拳】
(呉音はゲン)
①こぶし。にぎりこぶし。
②二人以上相対して、手の開閉または指の屈伸などによって勝負を争う遊戯。近世、中国から伝来。本拳・虫拳・狐拳など種々ある。じゃんけんも拳の一種。冥途の飛脚「―の上手」。「―を打つ」
けん【軒】
①前の高い車。古代中国で大夫以上の貴人が乗った。
②家を数える語。また、雅号または屋号に添えて用いる。「桃中―」
けん【乾】
八卦はっけの一つ。☰で表す。陽の卦で、その徳は健、天にかたどる。方位では北西いぬいに配する。↔坤こん
⇒乾を旋らし坤を転ず
けん【健】
はなはだしいこと。盛んに行うこと。
けん【険】
①(「嶮」に通用)山がけわしいこと。けわしい所。「天下の―」
②顔つきにけわしさのあること。「―のある目つき」
けん【圏】
限られた区域。範囲。「当選―外」
けん【堅】
①かたいこと。
②よろいかぶと。甲冑。
⇒堅を被り鋭を執る
けん【検】
検察庁の略。
けん【間】
(呉音)
①日本建築で、柱と柱とのあいだ。ま。
②長さの単位。主に土地・建物などに用いる。普通1間は6尺(約1.818メートル)。
③家を数える語。棟。宇。正倉院文書「板屋一―」
④将棋盤・碁盤の面に引いた線のなす目め。浮世風呂前「もう一―角かくをつつこめ」。「一―飛びに悪手なし」
→かん(間)→ま(間)
けん【腱】
骨格筋を骨に結びつける組織。帯白色で膠原こうげん線維が集まって束になったもの。きわめて強靱。「アキレス―」
けん【権】
①支配する力。物事を処置する威力。「生殺与奪の―」
②法・定めによって付与された力、資格。「シード―」
③高慢であること。見高けんだか。傲岸ごうがん。誹風柳多留10「たださへも―な娘に金を付け」
→ごん(権)
⇒権に借る
⇒権に募る
⇒権を取る
けん【嶮】
山が高くけわしいこと。けわしい所。「天下の―」
けん【憲】
憲法の略。「護―」
けん【賢】
①かしこいこと。学才・徳行のすぐれた人。
②(「聖」が清酒を意味するのに対していう)にごり酒。
③相手に対して敬意をあらわす語。「諸―」
けん【黔】
中国貴州省の別称。
けん【塤・壎】
中国の古代楽器。陶製または土製でほぼ壺形の笛。上部に歌口があり、指孔は5〜8個。同種の楽器が日本でも縄文時代から使用された。土笛つちぶえ。
塤
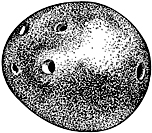 けん【鍵】
オルガン・ピアノ・タイプライターなどの指で押さえるところ。キー。また、それを数える語。
けん【顕】
顕教。↔密
けん【験】
(慣用音)
⇒げん(験)
ケン【羹】
(中国語)中国料理で、濃厚な汁物。あつもの。→かん(羹)
けん
〔助動〕
⇒けむ
けん
〔助詞〕
(中国・四国・九州地方で)から。故に。けに。きに。
げん【元】
(呉音はガン)
①もと。みなもと。
②王朝の始まり。年号の第1年。
③〔数〕
㋐方程式の未知数。「2―1次方程式」
㋑(element)集合の要素。
④中国の貨幣の単位。1元は10角。
げん【元】
中国の王朝の一つ。モンゴル帝国第5代の世祖フビライが建てた国。南宋を滅ぼし、高麗・吐蕃とばんを降し、安南・ビルマ・タイなどを服属させ、東アジアの大帝国を建設。都は大都(北京)。11代で明の朱元璋に滅ぼされた。大元。(1271〜1368)
げん【玄】
①黒色。くろ。
②微妙で深遠な理。老荘の道徳における微妙な道。「―の又た―」
③(名に「玄」の字の付くことが多かったから)江戸吉原で、医者・僧などの異称。玄さま。
げん【見】
見参げんざんの略。→けん(見)
げん【言】
(呉音はゴン)
①こと。ことば。語句。文句。
②ものをいうこと。「―を待つ」
⇒言近くして意遠し
⇒言を左右にする
⇒言を俟たない
げん【弦】
①弓のつる。つる。ゆづる。
②弦楽器に張りわたす線条。絹糸・鋼線・ガット・化学繊維などで作る。また、その楽器。→絃げん。
③枡ますの上部に対角線上に張りわたす鉄線。
④月相が半円形に見えるもの。弦月。月齢7〜8日頃のを上弦、22〜23日頃のを下弦という。
⑤〔数〕円または曲線の弧の両端を結ぶ線分。また、直角三角形の斜辺。→勾股弦こうこげん
げん【限】
①かぎること。さかいめ。くぎり。「時―立法」
②授業の時間割を数える語。「3―は体育」
げん【原】
①中国の古文の文体の一つ。本源をたずねて推論するもの。
②原子・原子力の略。
げん【現】
①〔仏〕現世または現在の略。「―当」
②今この世にあること。まのあたりにあること。実際にあること。狂言、墨塗「―のしようこを只今見せう」。「―に存在している」
③(名詞の上に付けて)現在の。
げん【絃】
(「弦」に通用)琴・三味線・バイオリン・ギターなどに張り渡す糸。絹糸・鋼線・ガット・ナイロンなどで作る。また、その楽器。「―が切れる」
げん【舷】
船の側面。ふなべり。ふなばた。
げん【減】
①へること。へらすこと。↔増。
②ひきざん。「加―乗除」
③古代、特定の身分ある者に対し、律が規定した刑法上の特典。議ぎや請しょうに次ぐ資格。七位以上の官人などに適用される。
げん【源】
みなもと氏の称。「―平藤橘」
げん【監】
①8世紀初め、畿内に置かれた特殊行政区。芳野よしの・和泉の2監があり、いずれも離宮所在地。740年(天平12)廃止。
②大宰府の第三等の官。大少がある。源氏物語玉鬘「大夫の―とて肥後の国に族ぞう広く」
げん【厳】
(呉音はゴン)
①きびしいこと。「―に言い渡す」
②父に対する尊称。
げん【験】
①仏道修行を積んだしるし。加持祈祷のききめ。枕草子157「―だにいちはやからばよかるべきを」
②ききめ。しるし。功能。効験。好色五人女1「はや揚屋には―を見せて手たたきても返事せず」
③縁起。前兆。「―がよい」
げん【甗】
中国の先史時代・古代に用いられた蒸し器の一種。甑そうと鬲れきとを結合した形で、土製または青銅製。
甗
けん【鍵】
オルガン・ピアノ・タイプライターなどの指で押さえるところ。キー。また、それを数える語。
けん【顕】
顕教。↔密
けん【験】
(慣用音)
⇒げん(験)
ケン【羹】
(中国語)中国料理で、濃厚な汁物。あつもの。→かん(羹)
けん
〔助動〕
⇒けむ
けん
〔助詞〕
(中国・四国・九州地方で)から。故に。けに。きに。
げん【元】
(呉音はガン)
①もと。みなもと。
②王朝の始まり。年号の第1年。
③〔数〕
㋐方程式の未知数。「2―1次方程式」
㋑(element)集合の要素。
④中国の貨幣の単位。1元は10角。
げん【元】
中国の王朝の一つ。モンゴル帝国第5代の世祖フビライが建てた国。南宋を滅ぼし、高麗・吐蕃とばんを降し、安南・ビルマ・タイなどを服属させ、東アジアの大帝国を建設。都は大都(北京)。11代で明の朱元璋に滅ぼされた。大元。(1271〜1368)
げん【玄】
①黒色。くろ。
②微妙で深遠な理。老荘の道徳における微妙な道。「―の又た―」
③(名に「玄」の字の付くことが多かったから)江戸吉原で、医者・僧などの異称。玄さま。
げん【見】
見参げんざんの略。→けん(見)
げん【言】
(呉音はゴン)
①こと。ことば。語句。文句。
②ものをいうこと。「―を待つ」
⇒言近くして意遠し
⇒言を左右にする
⇒言を俟たない
げん【弦】
①弓のつる。つる。ゆづる。
②弦楽器に張りわたす線条。絹糸・鋼線・ガット・化学繊維などで作る。また、その楽器。→絃げん。
③枡ますの上部に対角線上に張りわたす鉄線。
④月相が半円形に見えるもの。弦月。月齢7〜8日頃のを上弦、22〜23日頃のを下弦という。
⑤〔数〕円または曲線の弧の両端を結ぶ線分。また、直角三角形の斜辺。→勾股弦こうこげん
げん【限】
①かぎること。さかいめ。くぎり。「時―立法」
②授業の時間割を数える語。「3―は体育」
げん【原】
①中国の古文の文体の一つ。本源をたずねて推論するもの。
②原子・原子力の略。
げん【現】
①〔仏〕現世または現在の略。「―当」
②今この世にあること。まのあたりにあること。実際にあること。狂言、墨塗「―のしようこを只今見せう」。「―に存在している」
③(名詞の上に付けて)現在の。
げん【絃】
(「弦」に通用)琴・三味線・バイオリン・ギターなどに張り渡す糸。絹糸・鋼線・ガット・ナイロンなどで作る。また、その楽器。「―が切れる」
げん【舷】
船の側面。ふなべり。ふなばた。
げん【減】
①へること。へらすこと。↔増。
②ひきざん。「加―乗除」
③古代、特定の身分ある者に対し、律が規定した刑法上の特典。議ぎや請しょうに次ぐ資格。七位以上の官人などに適用される。
げん【源】
みなもと氏の称。「―平藤橘」
げん【監】
①8世紀初め、畿内に置かれた特殊行政区。芳野よしの・和泉の2監があり、いずれも離宮所在地。740年(天平12)廃止。
②大宰府の第三等の官。大少がある。源氏物語玉鬘「大夫の―とて肥後の国に族ぞう広く」
げん【厳】
(呉音はゴン)
①きびしいこと。「―に言い渡す」
②父に対する尊称。
げん【験】
①仏道修行を積んだしるし。加持祈祷のききめ。枕草子157「―だにいちはやからばよかるべきを」
②ききめ。しるし。功能。効験。好色五人女1「はや揚屋には―を見せて手たたきても返事せず」
③縁起。前兆。「―がよい」
げん【甗】
中国の先史時代・古代に用いられた蒸し器の一種。甑そうと鬲れきとを結合した形で、土製または青銅製。
甗
 ゲン【Gen ドイツ】
〔生〕(→)遺伝子。
けん‐あい【兼愛】
自他・親疎の差別なく平等に人を愛すること。墨子ぼくしの倫理説。「―説」
けん‐あい【涓埃】
しずくとちり。極めてわずかなことにたとえる。
けん‐あい【眷愛】
なさけをかけること。目をかけかわいがること。
けん‐あい【険隘】
けわしくせまいこと。また、その所。
けん‐あく【険悪】
道路・天候・人心などがけわしくわるいこと。「―な空模様」「―な戦況」「―な目で見る」
げん‐あく【元悪】
わるもののかしら。元凶。大悪人。
げん‐あつ【減圧】
圧力を減ずること。圧力がへること。
⇒げんあつ‐しょう【減圧症】
⇒げんあつ‐じょうりゅう【減圧蒸留】
⇒げんあつ‐べん【減圧弁】
けんあつ‐き【検圧器】
圧力・気圧などをはかる計器。
げんあつ‐しょう【減圧症】‥シヤウ
気圧の減少によって起こる症状。→ケーソン病。
⇒げん‐あつ【減圧】
げんあつ‐じょうりゅう【減圧蒸留】‥リウ
装置内部の圧力を1気圧以下に保って行う蒸留法。沸点が下がるため、熱的に不安定な物質の分解を防止できる。真空蒸留。
⇒げん‐あつ【減圧】
げんあつ‐べん【減圧弁】
①ボイラーからくる高圧蒸気を一定の圧力まで減じて使用する場合に用いる弁。
②一般に、高圧の流体の圧力を低下させるために用いる弁。
⇒げん‐あつ【減圧】
けんあん【建安】
後漢末の献帝朝の年号。(196〜220)
⇒けんあん‐しちし【建安七子】
⇒けんあん‐たい【建安体】
けん‐あん【検案】
①形跡・状況などを調べ考えること。
②〔法〕死体について死亡の事実を医学的に確認すること。
⇒けんあん‐しょ【検案書】
けん‐あん【懸案】
解決を迫られながら解決されずにある問題。「―の事項」
げん‐あん【原案】
もとの案。多く、修正案に対していう。「―通り可決する」
けんあん‐しちし【建安七子】
建安年中に輩出した7人の詩文家、すなわち孔融・陳琳・王粲おうさん・徐幹・阮瑀げんう・応瑒おうとう・劉楨りゅうてい。魏の都鄴ぎょうにいたので、鄴中の七子ともいう。
⇒けんあん【建安】
けんあん‐しょ【検案書】
医師の治療を受けずに死亡した者について、その死亡を確認する医師の証明書。
⇒けん‐あん【検案】
けんあん‐たい【建安体】
魏の曹操・曹丕そうひ・曹植父子および建安七子の詩風。民間の歌謡であった五言詩を作者個人の心情をうたうものとし、清新で気骨に富み、高い風格を備える。
⇒けんあん【建安】
けんあん‐ふ【建安府】
もと皇居内にあった戦役記念御府の一つ。日露戦争戦没将兵の名簿・写真・武器・戦利品などを天皇の御物として収めた。第二次大戦後廃止。
けん‐い【険夷】
①土地のけわしい所と、たいらな所。
②むずかしいことと、たやすいこと。険易。
けん‐い【険易】
①けわしいことと、たいらなこと。
②むずかしいことと、たやすいこと。険夷。
けん‐い【権威】‥ヰ
(authority)
①他人を強制し服従させる威力。人に承認と服従の義務を要求する精神的・道徳的・社会的または法的威力。「―が失墜する」
②その道で第一人者と認められていること。また、そのような人。大家。「数学の―」
⇒けんい‐しゅぎ【権威主義】
⇒けんい‐しゅぎ‐たいせい【権威主義体制】
⇒けんい‐すじ【権威筋】
⇒けんいてき‐せいかく【権威的性格】
⇒けんい‐どうとく【権威道徳】
けん‐い【顕位】‥ヰ
人目に立つ高い地位。
げん‐い【言意】
①ことばの意味。
②ことばと心。
げん‐い【原委・源委】‥ヰ
(「委」は流れのあつまるところの意)もととすえ。本末。首尾。
げん‐い【原意】
本来の意味。原義。
げん‐い【厳威】‥ヰ
おごそかで威光のあること。おごそかな威儀。
けん‐いき【圏域】‥ヰキ
あるまとまりとしてとらえた広い地域。
けんい‐ざい【健胃剤】‥ヰ‥
胃の機能を助け、胃液の分泌を促し、消化・吸収作用を盛んにさせる薬剤。橙皮とうひ・竜胆りんどう・当薬の類。
けん‐いし【剣石】
(→)要石かなめいし2に同じ。
けんい‐しゅぎ【権威主義】‥ヰ‥
もっぱら権威に価値を認める主義。権威に対する自己卑下や盲目的服従、また、権威をもって他を圧迫する態度や行動としてあらわれる。
⇒けん‐い【権威】
けんい‐しゅぎ‐たいせい【権威主義体制】‥ヰ‥
(authoritarian regime)非民主主義的な政治体制の一種。強権的な支配を行うが、指導者の権力行使範囲の限定性、明確な統治イデオロギーの欠如、一定の多元性・言論の自由の容認、民衆の政治的無関心への依拠などの点で全体主義と区別される。
⇒けん‐い【権威】
けんい‐すじ【権威筋】‥ヰスヂ
信頼するに足る方面。消息筋。報道で、公表できないが信頼できる情報源をいうのに用いる。
⇒けん‐い【権威】
けん‐いち【見一】
旧式珠算における2桁以上の割算。「見一の割」ともいい、「見一無頭作九一さくきゅうのいち」などの割声を用いたところからいう。見一無頭作九一より見九無頭作九九にいたる。
⇒けんいち‐むとう【見一無頭】
けんいち‐むとう【見一無頭】
見一無頭作九一の略。2桁以上の割算で、首位が同じで、しかも被除数が除数より小さいとき、まず商として9を立てる、その割声。
⇒けん‐いち【見一】
けんいてき‐せいかく【権威的性格】‥ヰ‥
権威や強者に服従する一方、弱者には自分の力を誇示する性格。
⇒けん‐い【権威】
けんい‐どうとく【権威道徳】‥ヰダウ‥
個人の意志の外にある国家や教会や政党のような権威による価値秩序への服従を道徳とする説。権威説ともいう。
⇒けん‐い【権威】
けん‐いん【見印】
「見留印みとめいん」(認印)の「留」を略して音読した語。
けん‐いん【牽引】
ひくこと。ひきよせること。
⇒けんいん‐じどうしゃ【牽引自動車】
⇒けんいん‐しゃ【牽引車】
⇒けんいん‐りょうほう【牽引療法】
けん‐いん【険韻】‥ヰン
漢詩を作るのに使用困難な韻字。
けん‐いん【検印】
①検査済みの証明としておす印いん。
②書籍の奥付に、著者が発行部数を確認するためにおす印。
けんいん【玁狁・獫允】
中国周代の異民族。西周滅亡の原因となったとされる犬戎けんじゅうは戦国時代にこれを言い換えたもの。のちの匈奴きょうどと同一視する説もある。
げん‐いん【原因】
(cause)
①ある物事を引き起こすもと。また、その働き。「火事の―」「―をつきとめる」
②事物の変化を引き起こすもの。アリストテレスは形相因・質料因・動力因(作用因)・目的因の4種を区別した。現在の科学でいう原因は動力因にあたる。↔結果。
⇒げんいん‐に‐おいて‐じゆうな‐こうい【原因において自由な行為】
げん‐いん【現員】‥ヰン
現在の人員。現在員。
げん‐いん【減員】‥ヰン
人員を減らすこと。人員が減ること。「経理部門を―する」↔増員
けんいん‐じどうしゃ【牽引自動車】
被牽引車に重量物を積載し、これを牽引運搬する自動車。トラクター。
⇒けん‐いん【牽引】
けんいん‐しゃ【牽引車】
①荷物などを積載した車両を牽引する機関車などの動力車。また、牽引自動車。
②比喩的に、先頭に立って推進する人。
⇒けん‐いん【牽引】
げんいん‐に‐おいて‐じゆうな‐こうい【原因において自由な行為】‥イウ‥カウヰ
〔法〕自らを責任能力のない状態におとしいれて犯罪結果を発生させること。泥酔状態を利用して他人を傷害する類。
⇒げん‐いん【原因】
けんいん‐りょうほう【牽引療法】‥レウハフ
躯幹くかんや四肢を牽引する治療法。骨折に対する持続牽引、頸部神経根由来の痛みに対する頸椎牽引、脊椎由来の腰痛に対する骨盤牽引など。
⇒けん‐いん【牽引】
げん‐う【幻有】
〔仏〕一切の存在は因縁の和合により、幻まぼろしのように仮の存在であるということ。仮有けう。
けん‐うん【巻雲】
十種雲級の一つ。上層雲に属し、繊維状にかかる白雲。中緯度帯では5〜13キロメートルの高さに現れる。極めて小さい氷の結晶から成る。すじ雲。まきぐも。記号Ci →雲級(表)
巻雲
撮影:高橋健司
ゲン【Gen ドイツ】
〔生〕(→)遺伝子。
けん‐あい【兼愛】
自他・親疎の差別なく平等に人を愛すること。墨子ぼくしの倫理説。「―説」
けん‐あい【涓埃】
しずくとちり。極めてわずかなことにたとえる。
けん‐あい【眷愛】
なさけをかけること。目をかけかわいがること。
けん‐あい【険隘】
けわしくせまいこと。また、その所。
けん‐あく【険悪】
道路・天候・人心などがけわしくわるいこと。「―な空模様」「―な戦況」「―な目で見る」
げん‐あく【元悪】
わるもののかしら。元凶。大悪人。
げん‐あつ【減圧】
圧力を減ずること。圧力がへること。
⇒げんあつ‐しょう【減圧症】
⇒げんあつ‐じょうりゅう【減圧蒸留】
⇒げんあつ‐べん【減圧弁】
けんあつ‐き【検圧器】
圧力・気圧などをはかる計器。
げんあつ‐しょう【減圧症】‥シヤウ
気圧の減少によって起こる症状。→ケーソン病。
⇒げん‐あつ【減圧】
げんあつ‐じょうりゅう【減圧蒸留】‥リウ
装置内部の圧力を1気圧以下に保って行う蒸留法。沸点が下がるため、熱的に不安定な物質の分解を防止できる。真空蒸留。
⇒げん‐あつ【減圧】
げんあつ‐べん【減圧弁】
①ボイラーからくる高圧蒸気を一定の圧力まで減じて使用する場合に用いる弁。
②一般に、高圧の流体の圧力を低下させるために用いる弁。
⇒げん‐あつ【減圧】
けんあん【建安】
後漢末の献帝朝の年号。(196〜220)
⇒けんあん‐しちし【建安七子】
⇒けんあん‐たい【建安体】
けん‐あん【検案】
①形跡・状況などを調べ考えること。
②〔法〕死体について死亡の事実を医学的に確認すること。
⇒けんあん‐しょ【検案書】
けん‐あん【懸案】
解決を迫られながら解決されずにある問題。「―の事項」
げん‐あん【原案】
もとの案。多く、修正案に対していう。「―通り可決する」
けんあん‐しちし【建安七子】
建安年中に輩出した7人の詩文家、すなわち孔融・陳琳・王粲おうさん・徐幹・阮瑀げんう・応瑒おうとう・劉楨りゅうてい。魏の都鄴ぎょうにいたので、鄴中の七子ともいう。
⇒けんあん【建安】
けんあん‐しょ【検案書】
医師の治療を受けずに死亡した者について、その死亡を確認する医師の証明書。
⇒けん‐あん【検案】
けんあん‐たい【建安体】
魏の曹操・曹丕そうひ・曹植父子および建安七子の詩風。民間の歌謡であった五言詩を作者個人の心情をうたうものとし、清新で気骨に富み、高い風格を備える。
⇒けんあん【建安】
けんあん‐ふ【建安府】
もと皇居内にあった戦役記念御府の一つ。日露戦争戦没将兵の名簿・写真・武器・戦利品などを天皇の御物として収めた。第二次大戦後廃止。
けん‐い【険夷】
①土地のけわしい所と、たいらな所。
②むずかしいことと、たやすいこと。険易。
けん‐い【険易】
①けわしいことと、たいらなこと。
②むずかしいことと、たやすいこと。険夷。
けん‐い【権威】‥ヰ
(authority)
①他人を強制し服従させる威力。人に承認と服従の義務を要求する精神的・道徳的・社会的または法的威力。「―が失墜する」
②その道で第一人者と認められていること。また、そのような人。大家。「数学の―」
⇒けんい‐しゅぎ【権威主義】
⇒けんい‐しゅぎ‐たいせい【権威主義体制】
⇒けんい‐すじ【権威筋】
⇒けんいてき‐せいかく【権威的性格】
⇒けんい‐どうとく【権威道徳】
けん‐い【顕位】‥ヰ
人目に立つ高い地位。
げん‐い【言意】
①ことばの意味。
②ことばと心。
げん‐い【原委・源委】‥ヰ
(「委」は流れのあつまるところの意)もととすえ。本末。首尾。
げん‐い【原意】
本来の意味。原義。
げん‐い【厳威】‥ヰ
おごそかで威光のあること。おごそかな威儀。
けん‐いき【圏域】‥ヰキ
あるまとまりとしてとらえた広い地域。
けんい‐ざい【健胃剤】‥ヰ‥
胃の機能を助け、胃液の分泌を促し、消化・吸収作用を盛んにさせる薬剤。橙皮とうひ・竜胆りんどう・当薬の類。
けん‐いし【剣石】
(→)要石かなめいし2に同じ。
けんい‐しゅぎ【権威主義】‥ヰ‥
もっぱら権威に価値を認める主義。権威に対する自己卑下や盲目的服従、また、権威をもって他を圧迫する態度や行動としてあらわれる。
⇒けん‐い【権威】
けんい‐しゅぎ‐たいせい【権威主義体制】‥ヰ‥
(authoritarian regime)非民主主義的な政治体制の一種。強権的な支配を行うが、指導者の権力行使範囲の限定性、明確な統治イデオロギーの欠如、一定の多元性・言論の自由の容認、民衆の政治的無関心への依拠などの点で全体主義と区別される。
⇒けん‐い【権威】
けんい‐すじ【権威筋】‥ヰスヂ
信頼するに足る方面。消息筋。報道で、公表できないが信頼できる情報源をいうのに用いる。
⇒けん‐い【権威】
けん‐いち【見一】
旧式珠算における2桁以上の割算。「見一の割」ともいい、「見一無頭作九一さくきゅうのいち」などの割声を用いたところからいう。見一無頭作九一より見九無頭作九九にいたる。
⇒けんいち‐むとう【見一無頭】
けんいち‐むとう【見一無頭】
見一無頭作九一の略。2桁以上の割算で、首位が同じで、しかも被除数が除数より小さいとき、まず商として9を立てる、その割声。
⇒けん‐いち【見一】
けんいてき‐せいかく【権威的性格】‥ヰ‥
権威や強者に服従する一方、弱者には自分の力を誇示する性格。
⇒けん‐い【権威】
けんい‐どうとく【権威道徳】‥ヰダウ‥
個人の意志の外にある国家や教会や政党のような権威による価値秩序への服従を道徳とする説。権威説ともいう。
⇒けん‐い【権威】
けん‐いん【見印】
「見留印みとめいん」(認印)の「留」を略して音読した語。
けん‐いん【牽引】
ひくこと。ひきよせること。
⇒けんいん‐じどうしゃ【牽引自動車】
⇒けんいん‐しゃ【牽引車】
⇒けんいん‐りょうほう【牽引療法】
けん‐いん【険韻】‥ヰン
漢詩を作るのに使用困難な韻字。
けん‐いん【検印】
①検査済みの証明としておす印いん。
②書籍の奥付に、著者が発行部数を確認するためにおす印。
けんいん【玁狁・獫允】
中国周代の異民族。西周滅亡の原因となったとされる犬戎けんじゅうは戦国時代にこれを言い換えたもの。のちの匈奴きょうどと同一視する説もある。
げん‐いん【原因】
(cause)
①ある物事を引き起こすもと。また、その働き。「火事の―」「―をつきとめる」
②事物の変化を引き起こすもの。アリストテレスは形相因・質料因・動力因(作用因)・目的因の4種を区別した。現在の科学でいう原因は動力因にあたる。↔結果。
⇒げんいん‐に‐おいて‐じゆうな‐こうい【原因において自由な行為】
げん‐いん【現員】‥ヰン
現在の人員。現在員。
げん‐いん【減員】‥ヰン
人員を減らすこと。人員が減ること。「経理部門を―する」↔増員
けんいん‐じどうしゃ【牽引自動車】
被牽引車に重量物を積載し、これを牽引運搬する自動車。トラクター。
⇒けん‐いん【牽引】
けんいん‐しゃ【牽引車】
①荷物などを積載した車両を牽引する機関車などの動力車。また、牽引自動車。
②比喩的に、先頭に立って推進する人。
⇒けん‐いん【牽引】
げんいん‐に‐おいて‐じゆうな‐こうい【原因において自由な行為】‥イウ‥カウヰ
〔法〕自らを責任能力のない状態におとしいれて犯罪結果を発生させること。泥酔状態を利用して他人を傷害する類。
⇒げん‐いん【原因】
けんいん‐りょうほう【牽引療法】‥レウハフ
躯幹くかんや四肢を牽引する治療法。骨折に対する持続牽引、頸部神経根由来の痛みに対する頸椎牽引、脊椎由来の腰痛に対する骨盤牽引など。
⇒けん‐いん【牽引】
げん‐う【幻有】
〔仏〕一切の存在は因縁の和合により、幻まぼろしのように仮の存在であるということ。仮有けう。
けん‐うん【巻雲】
十種雲級の一つ。上層雲に属し、繊維状にかかる白雲。中緯度帯では5〜13キロメートルの高さに現れる。極めて小さい氷の結晶から成る。すじ雲。まきぐも。記号Ci →雲級(表)
巻雲
撮影:高橋健司
 げん‐うん【玄雲】
黒い雲。くろくも。
げん‐うん【眩暈】
目がくらんで頭のふらふらする感じ。めまい。
げんえ【玄慧・玄恵】‥ヱ
(ゲンネとも)鎌倉後期・南北朝時代の学僧。京都の人。一説に虎関師錬こかんしれんの弟。天台・禅・宋学を究め、足利尊氏・直義に用いられ、建武式目の制定に参与。「太平記」「庭訓往来」の著者に擬せられる。(1279〜1350)
けん‐えい【巻纓】
纓を巻き、黒塗りまたは白木の夾木はさみぎでとめたもの。武官用。まきえい。→冠(図)→纓(図)
けんえい【建永】
(ケンヨウとも)[文選]鎌倉前期、土御門天皇朝の年号。元久3年4月27日(1206年6月5日)改元、建永2年10月25日(1207年11月16日)承元に改元。
けん‐えい【県営】
県が経営または設置・管理すること。
けん‐えい【兼営】
本業のほかに別の営業を兼ねて行うこと。
⇒けんえい‐ぎんこう【兼営銀行】
けん‐えい【牽曳】
ひくこと。ひっぱること。牽引。
けん‐えい【献詠】
詩歌を詠んで宮中・神社などにたてまつること。また、その詩歌。
けん‐えい【顕栄】
名があらわれ、身の栄えること。位高く立身すること。
げんえい【元永】
平安後期、鳥羽天皇朝の年号。永久6年4月3日(1118年4月25日)改元、元永3年4月10日(1120年5月9日)保安に改元。
げん‐えい【幻影】
そこにいない人間や霊魂の幻覚。本当は存在しないのに、あるように見えるもの。まぼろし。「―におびえる」
⇒げんえい‐し【幻影肢】
けんえい‐ぎんこう【兼営銀行】‥カウ
短期資金と長期資金とをあわせて取り扱う銀行。特に、銀行業務と証券業務とをあわせ行う銀行。ドイツの銀行がその典型。
⇒けん‐えい【兼営】
げんえい‐し【幻影肢】
失った腕や脚がまだ存在するかのように、痛み・かゆみや運動感覚を感ずる現象。幻肢。
⇒げん‐えい【幻影】
げんえい‐じん【玄英神】
冬をつかさどる神。浄瑠璃、天神記「冬の神は北方の天に立ち給ひ、―と申すとかや」
けん‐えき【検疫】
伝染病を予防するため、病原体の有無につき人・貨物・家畜などを診断・検案し、必要な場合には隔離・消毒などの措置をとること。
⇒けんえき‐かんせんしょう【検疫感染症】
⇒けんえき‐こう【検疫港】
⇒けんえき‐せん【検疫船】
けん‐えき【権益】
権利と利益。特に、ある国が他国の領土内で得た権利と利益。「―を守る」
げん‐えき【原液】
製造・加工のもとになる液体。
げん‐えき【現役】
①常備兵役の一つ。常時軍務に服し、戦時部隊の骨幹とされる役種。
②現にある職務に従事して活躍している人。「―投手」
③浪人4に対して、在校中の受験生。「―で合格する」
げん‐えき【減益】
利益が減ること。↔増益
けんえき‐かんせんしょう【検疫感染症】‥シヤウ
検疫の対象となる感染症。日本では検疫法により、感染症法の1類感染症(エボラ出血熱・ラッサ熱・クリミア‐コンゴ出血熱・SARSサーズ・マールブルグ病・ペスト・痘瘡)とコレラ・黄熱・H5N1型インフルエンザ・マラリア・デング熱と定められている。
⇒けん‐えき【検疫】
けんえき‐こう【検疫港】‥カウ
外航船の乗客・船員・貨物の検疫・消毒を行い、検疫済の証明書を交付できる港。
⇒けん‐えき【検疫】
けんえき‐せん【検疫船】
検疫を行う検疫官を沖合の船に送り迎えする小型船。
⇒けん‐えき【検疫】
けん‐えつ【検閲】
①調べあらためること。特に、出版物・映画などの内容を公権力が審査し、不適当と認めるときはその発表などを禁止する行為をいい、日本国憲法はこれを禁止。
→参照条文:日本国憲法第21条
②〔心〕自我、とくに超自我の機能の一つ。快楽原則に従って無意識の欲求を解放しようとするイドがそのままの形では出現しないように、超自我による社会的規範と自我の防衛機制とを通じて、抑圧したり、変形して放出させたりすること。精神分析の用語。
けん‐えん【犬猿】‥ヱン
犬と猿。互いに仲の悪いことをたとえていう。
⇒けんえん‐の‐なか【犬猿の仲】
⇒犬猿もただならず
けん‐えん【妍艶】
あでやかで美しいこと。
けん‐えん【倦厭】
あきていやになること。
けん‐えん【嫌煙】
(「禁煙」をもじって)近くで他人が喫煙するのをきらって拒否すること。「―権」
けん‐えん【慊焉】
(「慊」には満足と不満足との両意がある)
①あきたらず思うさま。慊如けんじょ。「―たるものがある」
②(多く打消の語を伴う)満足に思うさま。慊然。「―とせぬ顔」
けんえん【蘐園】‥ヱン
荻生徂徠おぎゅうそらいの書斎と塾の名称。江戸日本橋茅場町にあり、「茅」と同義の「蘐」をもって命名。
⇒けんえん‐がくは【蘐園学派】
げん‐えん【玄猿】‥ヱン
(顔が黒いからいう)手長猿てながざる。
げん‐えん【減塩】
①循環器疾患などの治療や予防のために、食塩の摂取量をひかえること。
②醤油・味噌などの食塩の含有量を少なめにすること。「―醤油」
⇒げんえん‐しょく【減塩食】
げんえん【諺苑】‥ヱン
辞書。太田全斎著。7巻。1797年(寛政9)成る。俗語・俚諺をいろは順に編集。これを増修したのが「俚言集覧」。
けんえん‐がくは【蘐園学派】‥ヱン‥
荻生徂徠の門流。徂徠学派・古文辞派ともいう。
⇒けんえん【蘐園】
けんえん‐き【検塩器】
比重計の一種で、水中の塩分の含量を測る器具。
げんえん‐しょく【減塩食】
食塩の含有量を少なくした食事。浮腫や高血圧性疾患の治療に用いる。
⇒げん‐えん【減塩】
けんえん‐の‐なか【犬猿の仲】‥ヱン‥
犬と猿のように、非常に仲が悪いことのたとえ。犬と猿。
⇒けん‐えん【犬猿】
げん‐うん【玄雲】
黒い雲。くろくも。
げん‐うん【眩暈】
目がくらんで頭のふらふらする感じ。めまい。
げんえ【玄慧・玄恵】‥ヱ
(ゲンネとも)鎌倉後期・南北朝時代の学僧。京都の人。一説に虎関師錬こかんしれんの弟。天台・禅・宋学を究め、足利尊氏・直義に用いられ、建武式目の制定に参与。「太平記」「庭訓往来」の著者に擬せられる。(1279〜1350)
けん‐えい【巻纓】
纓を巻き、黒塗りまたは白木の夾木はさみぎでとめたもの。武官用。まきえい。→冠(図)→纓(図)
けんえい【建永】
(ケンヨウとも)[文選]鎌倉前期、土御門天皇朝の年号。元久3年4月27日(1206年6月5日)改元、建永2年10月25日(1207年11月16日)承元に改元。
けん‐えい【県営】
県が経営または設置・管理すること。
けん‐えい【兼営】
本業のほかに別の営業を兼ねて行うこと。
⇒けんえい‐ぎんこう【兼営銀行】
けん‐えい【牽曳】
ひくこと。ひっぱること。牽引。
けん‐えい【献詠】
詩歌を詠んで宮中・神社などにたてまつること。また、その詩歌。
けん‐えい【顕栄】
名があらわれ、身の栄えること。位高く立身すること。
げんえい【元永】
平安後期、鳥羽天皇朝の年号。永久6年4月3日(1118年4月25日)改元、元永3年4月10日(1120年5月9日)保安に改元。
げん‐えい【幻影】
そこにいない人間や霊魂の幻覚。本当は存在しないのに、あるように見えるもの。まぼろし。「―におびえる」
⇒げんえい‐し【幻影肢】
けんえい‐ぎんこう【兼営銀行】‥カウ
短期資金と長期資金とをあわせて取り扱う銀行。特に、銀行業務と証券業務とをあわせ行う銀行。ドイツの銀行がその典型。
⇒けん‐えい【兼営】
げんえい‐し【幻影肢】
失った腕や脚がまだ存在するかのように、痛み・かゆみや運動感覚を感ずる現象。幻肢。
⇒げん‐えい【幻影】
げんえい‐じん【玄英神】
冬をつかさどる神。浄瑠璃、天神記「冬の神は北方の天に立ち給ひ、―と申すとかや」
けん‐えき【検疫】
伝染病を予防するため、病原体の有無につき人・貨物・家畜などを診断・検案し、必要な場合には隔離・消毒などの措置をとること。
⇒けんえき‐かんせんしょう【検疫感染症】
⇒けんえき‐こう【検疫港】
⇒けんえき‐せん【検疫船】
けん‐えき【権益】
権利と利益。特に、ある国が他国の領土内で得た権利と利益。「―を守る」
げん‐えき【原液】
製造・加工のもとになる液体。
げん‐えき【現役】
①常備兵役の一つ。常時軍務に服し、戦時部隊の骨幹とされる役種。
②現にある職務に従事して活躍している人。「―投手」
③浪人4に対して、在校中の受験生。「―で合格する」
げん‐えき【減益】
利益が減ること。↔増益
けんえき‐かんせんしょう【検疫感染症】‥シヤウ
検疫の対象となる感染症。日本では検疫法により、感染症法の1類感染症(エボラ出血熱・ラッサ熱・クリミア‐コンゴ出血熱・SARSサーズ・マールブルグ病・ペスト・痘瘡)とコレラ・黄熱・H5N1型インフルエンザ・マラリア・デング熱と定められている。
⇒けん‐えき【検疫】
けんえき‐こう【検疫港】‥カウ
外航船の乗客・船員・貨物の検疫・消毒を行い、検疫済の証明書を交付できる港。
⇒けん‐えき【検疫】
けんえき‐せん【検疫船】
検疫を行う検疫官を沖合の船に送り迎えする小型船。
⇒けん‐えき【検疫】
けん‐えつ【検閲】
①調べあらためること。特に、出版物・映画などの内容を公権力が審査し、不適当と認めるときはその発表などを禁止する行為をいい、日本国憲法はこれを禁止。
→参照条文:日本国憲法第21条
②〔心〕自我、とくに超自我の機能の一つ。快楽原則に従って無意識の欲求を解放しようとするイドがそのままの形では出現しないように、超自我による社会的規範と自我の防衛機制とを通じて、抑圧したり、変形して放出させたりすること。精神分析の用語。
けん‐えん【犬猿】‥ヱン
犬と猿。互いに仲の悪いことをたとえていう。
⇒けんえん‐の‐なか【犬猿の仲】
⇒犬猿もただならず
けん‐えん【妍艶】
あでやかで美しいこと。
けん‐えん【倦厭】
あきていやになること。
けん‐えん【嫌煙】
(「禁煙」をもじって)近くで他人が喫煙するのをきらって拒否すること。「―権」
けん‐えん【慊焉】
(「慊」には満足と不満足との両意がある)
①あきたらず思うさま。慊如けんじょ。「―たるものがある」
②(多く打消の語を伴う)満足に思うさま。慊然。「―とせぬ顔」
けんえん【蘐園】‥ヱン
荻生徂徠おぎゅうそらいの書斎と塾の名称。江戸日本橋茅場町にあり、「茅」と同義の「蘐」をもって命名。
⇒けんえん‐がくは【蘐園学派】
げん‐えん【玄猿】‥ヱン
(顔が黒いからいう)手長猿てながざる。
げん‐えん【減塩】
①循環器疾患などの治療や予防のために、食塩の摂取量をひかえること。
②醤油・味噌などの食塩の含有量を少なめにすること。「―醤油」
⇒げんえん‐しょく【減塩食】
げんえん【諺苑】‥ヱン
辞書。太田全斎著。7巻。1797年(寛政9)成る。俗語・俚諺をいろは順に編集。これを増修したのが「俚言集覧」。
けんえん‐がくは【蘐園学派】‥ヱン‥
荻生徂徠の門流。徂徠学派・古文辞派ともいう。
⇒けんえん【蘐園】
けんえん‐き【検塩器】
比重計の一種で、水中の塩分の含量を測る器具。
げんえん‐しょく【減塩食】
食塩の含有量を少なくした食事。浮腫や高血圧性疾患の治療に用いる。
⇒げん‐えん【減塩】
けんえん‐の‐なか【犬猿の仲】‥ヱン‥
犬と猿のように、非常に仲が悪いことのたとえ。犬と猿。
⇒けん‐えん【犬猿】
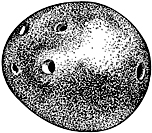 けん【鍵】
オルガン・ピアノ・タイプライターなどの指で押さえるところ。キー。また、それを数える語。
けん【顕】
顕教。↔密
けん【験】
(慣用音)
⇒げん(験)
ケン【羹】
(中国語)中国料理で、濃厚な汁物。あつもの。→かん(羹)
けん
〔助動〕
⇒けむ
けん
〔助詞〕
(中国・四国・九州地方で)から。故に。けに。きに。
げん【元】
(呉音はガン)
①もと。みなもと。
②王朝の始まり。年号の第1年。
③〔数〕
㋐方程式の未知数。「2―1次方程式」
㋑(element)集合の要素。
④中国の貨幣の単位。1元は10角。
げん【元】
中国の王朝の一つ。モンゴル帝国第5代の世祖フビライが建てた国。南宋を滅ぼし、高麗・吐蕃とばんを降し、安南・ビルマ・タイなどを服属させ、東アジアの大帝国を建設。都は大都(北京)。11代で明の朱元璋に滅ぼされた。大元。(1271〜1368)
げん【玄】
①黒色。くろ。
②微妙で深遠な理。老荘の道徳における微妙な道。「―の又た―」
③(名に「玄」の字の付くことが多かったから)江戸吉原で、医者・僧などの異称。玄さま。
げん【見】
見参げんざんの略。→けん(見)
げん【言】
(呉音はゴン)
①こと。ことば。語句。文句。
②ものをいうこと。「―を待つ」
⇒言近くして意遠し
⇒言を左右にする
⇒言を俟たない
げん【弦】
①弓のつる。つる。ゆづる。
②弦楽器に張りわたす線条。絹糸・鋼線・ガット・化学繊維などで作る。また、その楽器。→絃げん。
③枡ますの上部に対角線上に張りわたす鉄線。
④月相が半円形に見えるもの。弦月。月齢7〜8日頃のを上弦、22〜23日頃のを下弦という。
⑤〔数〕円または曲線の弧の両端を結ぶ線分。また、直角三角形の斜辺。→勾股弦こうこげん
げん【限】
①かぎること。さかいめ。くぎり。「時―立法」
②授業の時間割を数える語。「3―は体育」
げん【原】
①中国の古文の文体の一つ。本源をたずねて推論するもの。
②原子・原子力の略。
げん【現】
①〔仏〕現世または現在の略。「―当」
②今この世にあること。まのあたりにあること。実際にあること。狂言、墨塗「―のしようこを只今見せう」。「―に存在している」
③(名詞の上に付けて)現在の。
げん【絃】
(「弦」に通用)琴・三味線・バイオリン・ギターなどに張り渡す糸。絹糸・鋼線・ガット・ナイロンなどで作る。また、その楽器。「―が切れる」
げん【舷】
船の側面。ふなべり。ふなばた。
げん【減】
①へること。へらすこと。↔増。
②ひきざん。「加―乗除」
③古代、特定の身分ある者に対し、律が規定した刑法上の特典。議ぎや請しょうに次ぐ資格。七位以上の官人などに適用される。
げん【源】
みなもと氏の称。「―平藤橘」
げん【監】
①8世紀初め、畿内に置かれた特殊行政区。芳野よしの・和泉の2監があり、いずれも離宮所在地。740年(天平12)廃止。
②大宰府の第三等の官。大少がある。源氏物語玉鬘「大夫の―とて肥後の国に族ぞう広く」
げん【厳】
(呉音はゴン)
①きびしいこと。「―に言い渡す」
②父に対する尊称。
げん【験】
①仏道修行を積んだしるし。加持祈祷のききめ。枕草子157「―だにいちはやからばよかるべきを」
②ききめ。しるし。功能。効験。好色五人女1「はや揚屋には―を見せて手たたきても返事せず」
③縁起。前兆。「―がよい」
げん【甗】
中国の先史時代・古代に用いられた蒸し器の一種。甑そうと鬲れきとを結合した形で、土製または青銅製。
甗
けん【鍵】
オルガン・ピアノ・タイプライターなどの指で押さえるところ。キー。また、それを数える語。
けん【顕】
顕教。↔密
けん【験】
(慣用音)
⇒げん(験)
ケン【羹】
(中国語)中国料理で、濃厚な汁物。あつもの。→かん(羹)
けん
〔助動〕
⇒けむ
けん
〔助詞〕
(中国・四国・九州地方で)から。故に。けに。きに。
げん【元】
(呉音はガン)
①もと。みなもと。
②王朝の始まり。年号の第1年。
③〔数〕
㋐方程式の未知数。「2―1次方程式」
㋑(element)集合の要素。
④中国の貨幣の単位。1元は10角。
げん【元】
中国の王朝の一つ。モンゴル帝国第5代の世祖フビライが建てた国。南宋を滅ぼし、高麗・吐蕃とばんを降し、安南・ビルマ・タイなどを服属させ、東アジアの大帝国を建設。都は大都(北京)。11代で明の朱元璋に滅ぼされた。大元。(1271〜1368)
げん【玄】
①黒色。くろ。
②微妙で深遠な理。老荘の道徳における微妙な道。「―の又た―」
③(名に「玄」の字の付くことが多かったから)江戸吉原で、医者・僧などの異称。玄さま。
げん【見】
見参げんざんの略。→けん(見)
げん【言】
(呉音はゴン)
①こと。ことば。語句。文句。
②ものをいうこと。「―を待つ」
⇒言近くして意遠し
⇒言を左右にする
⇒言を俟たない
げん【弦】
①弓のつる。つる。ゆづる。
②弦楽器に張りわたす線条。絹糸・鋼線・ガット・化学繊維などで作る。また、その楽器。→絃げん。
③枡ますの上部に対角線上に張りわたす鉄線。
④月相が半円形に見えるもの。弦月。月齢7〜8日頃のを上弦、22〜23日頃のを下弦という。
⑤〔数〕円または曲線の弧の両端を結ぶ線分。また、直角三角形の斜辺。→勾股弦こうこげん
げん【限】
①かぎること。さかいめ。くぎり。「時―立法」
②授業の時間割を数える語。「3―は体育」
げん【原】
①中国の古文の文体の一つ。本源をたずねて推論するもの。
②原子・原子力の略。
げん【現】
①〔仏〕現世または現在の略。「―当」
②今この世にあること。まのあたりにあること。実際にあること。狂言、墨塗「―のしようこを只今見せう」。「―に存在している」
③(名詞の上に付けて)現在の。
げん【絃】
(「弦」に通用)琴・三味線・バイオリン・ギターなどに張り渡す糸。絹糸・鋼線・ガット・ナイロンなどで作る。また、その楽器。「―が切れる」
げん【舷】
船の側面。ふなべり。ふなばた。
げん【減】
①へること。へらすこと。↔増。
②ひきざん。「加―乗除」
③古代、特定の身分ある者に対し、律が規定した刑法上の特典。議ぎや請しょうに次ぐ資格。七位以上の官人などに適用される。
げん【源】
みなもと氏の称。「―平藤橘」
げん【監】
①8世紀初め、畿内に置かれた特殊行政区。芳野よしの・和泉の2監があり、いずれも離宮所在地。740年(天平12)廃止。
②大宰府の第三等の官。大少がある。源氏物語玉鬘「大夫の―とて肥後の国に族ぞう広く」
げん【厳】
(呉音はゴン)
①きびしいこと。「―に言い渡す」
②父に対する尊称。
げん【験】
①仏道修行を積んだしるし。加持祈祷のききめ。枕草子157「―だにいちはやからばよかるべきを」
②ききめ。しるし。功能。効験。好色五人女1「はや揚屋には―を見せて手たたきても返事せず」
③縁起。前兆。「―がよい」
げん【甗】
中国の先史時代・古代に用いられた蒸し器の一種。甑そうと鬲れきとを結合した形で、土製または青銅製。
甗
 ゲン【Gen ドイツ】
〔生〕(→)遺伝子。
けん‐あい【兼愛】
自他・親疎の差別なく平等に人を愛すること。墨子ぼくしの倫理説。「―説」
けん‐あい【涓埃】
しずくとちり。極めてわずかなことにたとえる。
けん‐あい【眷愛】
なさけをかけること。目をかけかわいがること。
けん‐あい【険隘】
けわしくせまいこと。また、その所。
けん‐あく【険悪】
道路・天候・人心などがけわしくわるいこと。「―な空模様」「―な戦況」「―な目で見る」
げん‐あく【元悪】
わるもののかしら。元凶。大悪人。
げん‐あつ【減圧】
圧力を減ずること。圧力がへること。
⇒げんあつ‐しょう【減圧症】
⇒げんあつ‐じょうりゅう【減圧蒸留】
⇒げんあつ‐べん【減圧弁】
けんあつ‐き【検圧器】
圧力・気圧などをはかる計器。
げんあつ‐しょう【減圧症】‥シヤウ
気圧の減少によって起こる症状。→ケーソン病。
⇒げん‐あつ【減圧】
げんあつ‐じょうりゅう【減圧蒸留】‥リウ
装置内部の圧力を1気圧以下に保って行う蒸留法。沸点が下がるため、熱的に不安定な物質の分解を防止できる。真空蒸留。
⇒げん‐あつ【減圧】
げんあつ‐べん【減圧弁】
①ボイラーからくる高圧蒸気を一定の圧力まで減じて使用する場合に用いる弁。
②一般に、高圧の流体の圧力を低下させるために用いる弁。
⇒げん‐あつ【減圧】
けんあん【建安】
後漢末の献帝朝の年号。(196〜220)
⇒けんあん‐しちし【建安七子】
⇒けんあん‐たい【建安体】
けん‐あん【検案】
①形跡・状況などを調べ考えること。
②〔法〕死体について死亡の事実を医学的に確認すること。
⇒けんあん‐しょ【検案書】
けん‐あん【懸案】
解決を迫られながら解決されずにある問題。「―の事項」
げん‐あん【原案】
もとの案。多く、修正案に対していう。「―通り可決する」
けんあん‐しちし【建安七子】
建安年中に輩出した7人の詩文家、すなわち孔融・陳琳・王粲おうさん・徐幹・阮瑀げんう・応瑒おうとう・劉楨りゅうてい。魏の都鄴ぎょうにいたので、鄴中の七子ともいう。
⇒けんあん【建安】
けんあん‐しょ【検案書】
医師の治療を受けずに死亡した者について、その死亡を確認する医師の証明書。
⇒けん‐あん【検案】
けんあん‐たい【建安体】
魏の曹操・曹丕そうひ・曹植父子および建安七子の詩風。民間の歌謡であった五言詩を作者個人の心情をうたうものとし、清新で気骨に富み、高い風格を備える。
⇒けんあん【建安】
けんあん‐ふ【建安府】
もと皇居内にあった戦役記念御府の一つ。日露戦争戦没将兵の名簿・写真・武器・戦利品などを天皇の御物として収めた。第二次大戦後廃止。
けん‐い【険夷】
①土地のけわしい所と、たいらな所。
②むずかしいことと、たやすいこと。険易。
けん‐い【険易】
①けわしいことと、たいらなこと。
②むずかしいことと、たやすいこと。険夷。
けん‐い【権威】‥ヰ
(authority)
①他人を強制し服従させる威力。人に承認と服従の義務を要求する精神的・道徳的・社会的または法的威力。「―が失墜する」
②その道で第一人者と認められていること。また、そのような人。大家。「数学の―」
⇒けんい‐しゅぎ【権威主義】
⇒けんい‐しゅぎ‐たいせい【権威主義体制】
⇒けんい‐すじ【権威筋】
⇒けんいてき‐せいかく【権威的性格】
⇒けんい‐どうとく【権威道徳】
けん‐い【顕位】‥ヰ
人目に立つ高い地位。
げん‐い【言意】
①ことばの意味。
②ことばと心。
げん‐い【原委・源委】‥ヰ
(「委」は流れのあつまるところの意)もととすえ。本末。首尾。
げん‐い【原意】
本来の意味。原義。
げん‐い【厳威】‥ヰ
おごそかで威光のあること。おごそかな威儀。
けん‐いき【圏域】‥ヰキ
あるまとまりとしてとらえた広い地域。
けんい‐ざい【健胃剤】‥ヰ‥
胃の機能を助け、胃液の分泌を促し、消化・吸収作用を盛んにさせる薬剤。橙皮とうひ・竜胆りんどう・当薬の類。
けん‐いし【剣石】
(→)要石かなめいし2に同じ。
けんい‐しゅぎ【権威主義】‥ヰ‥
もっぱら権威に価値を認める主義。権威に対する自己卑下や盲目的服従、また、権威をもって他を圧迫する態度や行動としてあらわれる。
⇒けん‐い【権威】
けんい‐しゅぎ‐たいせい【権威主義体制】‥ヰ‥
(authoritarian regime)非民主主義的な政治体制の一種。強権的な支配を行うが、指導者の権力行使範囲の限定性、明確な統治イデオロギーの欠如、一定の多元性・言論の自由の容認、民衆の政治的無関心への依拠などの点で全体主義と区別される。
⇒けん‐い【権威】
けんい‐すじ【権威筋】‥ヰスヂ
信頼するに足る方面。消息筋。報道で、公表できないが信頼できる情報源をいうのに用いる。
⇒けん‐い【権威】
けん‐いち【見一】
旧式珠算における2桁以上の割算。「見一の割」ともいい、「見一無頭作九一さくきゅうのいち」などの割声を用いたところからいう。見一無頭作九一より見九無頭作九九にいたる。
⇒けんいち‐むとう【見一無頭】
けんいち‐むとう【見一無頭】
見一無頭作九一の略。2桁以上の割算で、首位が同じで、しかも被除数が除数より小さいとき、まず商として9を立てる、その割声。
⇒けん‐いち【見一】
けんいてき‐せいかく【権威的性格】‥ヰ‥
権威や強者に服従する一方、弱者には自分の力を誇示する性格。
⇒けん‐い【権威】
けんい‐どうとく【権威道徳】‥ヰダウ‥
個人の意志の外にある国家や教会や政党のような権威による価値秩序への服従を道徳とする説。権威説ともいう。
⇒けん‐い【権威】
けん‐いん【見印】
「見留印みとめいん」(認印)の「留」を略して音読した語。
けん‐いん【牽引】
ひくこと。ひきよせること。
⇒けんいん‐じどうしゃ【牽引自動車】
⇒けんいん‐しゃ【牽引車】
⇒けんいん‐りょうほう【牽引療法】
けん‐いん【険韻】‥ヰン
漢詩を作るのに使用困難な韻字。
けん‐いん【検印】
①検査済みの証明としておす印いん。
②書籍の奥付に、著者が発行部数を確認するためにおす印。
けんいん【玁狁・獫允】
中国周代の異民族。西周滅亡の原因となったとされる犬戎けんじゅうは戦国時代にこれを言い換えたもの。のちの匈奴きょうどと同一視する説もある。
げん‐いん【原因】
(cause)
①ある物事を引き起こすもと。また、その働き。「火事の―」「―をつきとめる」
②事物の変化を引き起こすもの。アリストテレスは形相因・質料因・動力因(作用因)・目的因の4種を区別した。現在の科学でいう原因は動力因にあたる。↔結果。
⇒げんいん‐に‐おいて‐じゆうな‐こうい【原因において自由な行為】
げん‐いん【現員】‥ヰン
現在の人員。現在員。
げん‐いん【減員】‥ヰン
人員を減らすこと。人員が減ること。「経理部門を―する」↔増員
けんいん‐じどうしゃ【牽引自動車】
被牽引車に重量物を積載し、これを牽引運搬する自動車。トラクター。
⇒けん‐いん【牽引】
けんいん‐しゃ【牽引車】
①荷物などを積載した車両を牽引する機関車などの動力車。また、牽引自動車。
②比喩的に、先頭に立って推進する人。
⇒けん‐いん【牽引】
げんいん‐に‐おいて‐じゆうな‐こうい【原因において自由な行為】‥イウ‥カウヰ
〔法〕自らを責任能力のない状態におとしいれて犯罪結果を発生させること。泥酔状態を利用して他人を傷害する類。
⇒げん‐いん【原因】
けんいん‐りょうほう【牽引療法】‥レウハフ
躯幹くかんや四肢を牽引する治療法。骨折に対する持続牽引、頸部神経根由来の痛みに対する頸椎牽引、脊椎由来の腰痛に対する骨盤牽引など。
⇒けん‐いん【牽引】
げん‐う【幻有】
〔仏〕一切の存在は因縁の和合により、幻まぼろしのように仮の存在であるということ。仮有けう。
けん‐うん【巻雲】
十種雲級の一つ。上層雲に属し、繊維状にかかる白雲。中緯度帯では5〜13キロメートルの高さに現れる。極めて小さい氷の結晶から成る。すじ雲。まきぐも。記号Ci →雲級(表)
巻雲
撮影:高橋健司
ゲン【Gen ドイツ】
〔生〕(→)遺伝子。
けん‐あい【兼愛】
自他・親疎の差別なく平等に人を愛すること。墨子ぼくしの倫理説。「―説」
けん‐あい【涓埃】
しずくとちり。極めてわずかなことにたとえる。
けん‐あい【眷愛】
なさけをかけること。目をかけかわいがること。
けん‐あい【険隘】
けわしくせまいこと。また、その所。
けん‐あく【険悪】
道路・天候・人心などがけわしくわるいこと。「―な空模様」「―な戦況」「―な目で見る」
げん‐あく【元悪】
わるもののかしら。元凶。大悪人。
げん‐あつ【減圧】
圧力を減ずること。圧力がへること。
⇒げんあつ‐しょう【減圧症】
⇒げんあつ‐じょうりゅう【減圧蒸留】
⇒げんあつ‐べん【減圧弁】
けんあつ‐き【検圧器】
圧力・気圧などをはかる計器。
げんあつ‐しょう【減圧症】‥シヤウ
気圧の減少によって起こる症状。→ケーソン病。
⇒げん‐あつ【減圧】
げんあつ‐じょうりゅう【減圧蒸留】‥リウ
装置内部の圧力を1気圧以下に保って行う蒸留法。沸点が下がるため、熱的に不安定な物質の分解を防止できる。真空蒸留。
⇒げん‐あつ【減圧】
げんあつ‐べん【減圧弁】
①ボイラーからくる高圧蒸気を一定の圧力まで減じて使用する場合に用いる弁。
②一般に、高圧の流体の圧力を低下させるために用いる弁。
⇒げん‐あつ【減圧】
けんあん【建安】
後漢末の献帝朝の年号。(196〜220)
⇒けんあん‐しちし【建安七子】
⇒けんあん‐たい【建安体】
けん‐あん【検案】
①形跡・状況などを調べ考えること。
②〔法〕死体について死亡の事実を医学的に確認すること。
⇒けんあん‐しょ【検案書】
けん‐あん【懸案】
解決を迫られながら解決されずにある問題。「―の事項」
げん‐あん【原案】
もとの案。多く、修正案に対していう。「―通り可決する」
けんあん‐しちし【建安七子】
建安年中に輩出した7人の詩文家、すなわち孔融・陳琳・王粲おうさん・徐幹・阮瑀げんう・応瑒おうとう・劉楨りゅうてい。魏の都鄴ぎょうにいたので、鄴中の七子ともいう。
⇒けんあん【建安】
けんあん‐しょ【検案書】
医師の治療を受けずに死亡した者について、その死亡を確認する医師の証明書。
⇒けん‐あん【検案】
けんあん‐たい【建安体】
魏の曹操・曹丕そうひ・曹植父子および建安七子の詩風。民間の歌謡であった五言詩を作者個人の心情をうたうものとし、清新で気骨に富み、高い風格を備える。
⇒けんあん【建安】
けんあん‐ふ【建安府】
もと皇居内にあった戦役記念御府の一つ。日露戦争戦没将兵の名簿・写真・武器・戦利品などを天皇の御物として収めた。第二次大戦後廃止。
けん‐い【険夷】
①土地のけわしい所と、たいらな所。
②むずかしいことと、たやすいこと。険易。
けん‐い【険易】
①けわしいことと、たいらなこと。
②むずかしいことと、たやすいこと。険夷。
けん‐い【権威】‥ヰ
(authority)
①他人を強制し服従させる威力。人に承認と服従の義務を要求する精神的・道徳的・社会的または法的威力。「―が失墜する」
②その道で第一人者と認められていること。また、そのような人。大家。「数学の―」
⇒けんい‐しゅぎ【権威主義】
⇒けんい‐しゅぎ‐たいせい【権威主義体制】
⇒けんい‐すじ【権威筋】
⇒けんいてき‐せいかく【権威的性格】
⇒けんい‐どうとく【権威道徳】
けん‐い【顕位】‥ヰ
人目に立つ高い地位。
げん‐い【言意】
①ことばの意味。
②ことばと心。
げん‐い【原委・源委】‥ヰ
(「委」は流れのあつまるところの意)もととすえ。本末。首尾。
げん‐い【原意】
本来の意味。原義。
げん‐い【厳威】‥ヰ
おごそかで威光のあること。おごそかな威儀。
けん‐いき【圏域】‥ヰキ
あるまとまりとしてとらえた広い地域。
けんい‐ざい【健胃剤】‥ヰ‥
胃の機能を助け、胃液の分泌を促し、消化・吸収作用を盛んにさせる薬剤。橙皮とうひ・竜胆りんどう・当薬の類。
けん‐いし【剣石】
(→)要石かなめいし2に同じ。
けんい‐しゅぎ【権威主義】‥ヰ‥
もっぱら権威に価値を認める主義。権威に対する自己卑下や盲目的服従、また、権威をもって他を圧迫する態度や行動としてあらわれる。
⇒けん‐い【権威】
けんい‐しゅぎ‐たいせい【権威主義体制】‥ヰ‥
(authoritarian regime)非民主主義的な政治体制の一種。強権的な支配を行うが、指導者の権力行使範囲の限定性、明確な統治イデオロギーの欠如、一定の多元性・言論の自由の容認、民衆の政治的無関心への依拠などの点で全体主義と区別される。
⇒けん‐い【権威】
けんい‐すじ【権威筋】‥ヰスヂ
信頼するに足る方面。消息筋。報道で、公表できないが信頼できる情報源をいうのに用いる。
⇒けん‐い【権威】
けん‐いち【見一】
旧式珠算における2桁以上の割算。「見一の割」ともいい、「見一無頭作九一さくきゅうのいち」などの割声を用いたところからいう。見一無頭作九一より見九無頭作九九にいたる。
⇒けんいち‐むとう【見一無頭】
けんいち‐むとう【見一無頭】
見一無頭作九一の略。2桁以上の割算で、首位が同じで、しかも被除数が除数より小さいとき、まず商として9を立てる、その割声。
⇒けん‐いち【見一】
けんいてき‐せいかく【権威的性格】‥ヰ‥
権威や強者に服従する一方、弱者には自分の力を誇示する性格。
⇒けん‐い【権威】
けんい‐どうとく【権威道徳】‥ヰダウ‥
個人の意志の外にある国家や教会や政党のような権威による価値秩序への服従を道徳とする説。権威説ともいう。
⇒けん‐い【権威】
けん‐いん【見印】
「見留印みとめいん」(認印)の「留」を略して音読した語。
けん‐いん【牽引】
ひくこと。ひきよせること。
⇒けんいん‐じどうしゃ【牽引自動車】
⇒けんいん‐しゃ【牽引車】
⇒けんいん‐りょうほう【牽引療法】
けん‐いん【険韻】‥ヰン
漢詩を作るのに使用困難な韻字。
けん‐いん【検印】
①検査済みの証明としておす印いん。
②書籍の奥付に、著者が発行部数を確認するためにおす印。
けんいん【玁狁・獫允】
中国周代の異民族。西周滅亡の原因となったとされる犬戎けんじゅうは戦国時代にこれを言い換えたもの。のちの匈奴きょうどと同一視する説もある。
げん‐いん【原因】
(cause)
①ある物事を引き起こすもと。また、その働き。「火事の―」「―をつきとめる」
②事物の変化を引き起こすもの。アリストテレスは形相因・質料因・動力因(作用因)・目的因の4種を区別した。現在の科学でいう原因は動力因にあたる。↔結果。
⇒げんいん‐に‐おいて‐じゆうな‐こうい【原因において自由な行為】
げん‐いん【現員】‥ヰン
現在の人員。現在員。
げん‐いん【減員】‥ヰン
人員を減らすこと。人員が減ること。「経理部門を―する」↔増員
けんいん‐じどうしゃ【牽引自動車】
被牽引車に重量物を積載し、これを牽引運搬する自動車。トラクター。
⇒けん‐いん【牽引】
けんいん‐しゃ【牽引車】
①荷物などを積載した車両を牽引する機関車などの動力車。また、牽引自動車。
②比喩的に、先頭に立って推進する人。
⇒けん‐いん【牽引】
げんいん‐に‐おいて‐じゆうな‐こうい【原因において自由な行為】‥イウ‥カウヰ
〔法〕自らを責任能力のない状態におとしいれて犯罪結果を発生させること。泥酔状態を利用して他人を傷害する類。
⇒げん‐いん【原因】
けんいん‐りょうほう【牽引療法】‥レウハフ
躯幹くかんや四肢を牽引する治療法。骨折に対する持続牽引、頸部神経根由来の痛みに対する頸椎牽引、脊椎由来の腰痛に対する骨盤牽引など。
⇒けん‐いん【牽引】
げん‐う【幻有】
〔仏〕一切の存在は因縁の和合により、幻まぼろしのように仮の存在であるということ。仮有けう。
けん‐うん【巻雲】
十種雲級の一つ。上層雲に属し、繊維状にかかる白雲。中緯度帯では5〜13キロメートルの高さに現れる。極めて小さい氷の結晶から成る。すじ雲。まきぐも。記号Ci →雲級(表)
巻雲
撮影:高橋健司
 げん‐うん【玄雲】
黒い雲。くろくも。
げん‐うん【眩暈】
目がくらんで頭のふらふらする感じ。めまい。
げんえ【玄慧・玄恵】‥ヱ
(ゲンネとも)鎌倉後期・南北朝時代の学僧。京都の人。一説に虎関師錬こかんしれんの弟。天台・禅・宋学を究め、足利尊氏・直義に用いられ、建武式目の制定に参与。「太平記」「庭訓往来」の著者に擬せられる。(1279〜1350)
けん‐えい【巻纓】
纓を巻き、黒塗りまたは白木の夾木はさみぎでとめたもの。武官用。まきえい。→冠(図)→纓(図)
けんえい【建永】
(ケンヨウとも)[文選]鎌倉前期、土御門天皇朝の年号。元久3年4月27日(1206年6月5日)改元、建永2年10月25日(1207年11月16日)承元に改元。
けん‐えい【県営】
県が経営または設置・管理すること。
けん‐えい【兼営】
本業のほかに別の営業を兼ねて行うこと。
⇒けんえい‐ぎんこう【兼営銀行】
けん‐えい【牽曳】
ひくこと。ひっぱること。牽引。
けん‐えい【献詠】
詩歌を詠んで宮中・神社などにたてまつること。また、その詩歌。
けん‐えい【顕栄】
名があらわれ、身の栄えること。位高く立身すること。
げんえい【元永】
平安後期、鳥羽天皇朝の年号。永久6年4月3日(1118年4月25日)改元、元永3年4月10日(1120年5月9日)保安に改元。
げん‐えい【幻影】
そこにいない人間や霊魂の幻覚。本当は存在しないのに、あるように見えるもの。まぼろし。「―におびえる」
⇒げんえい‐し【幻影肢】
けんえい‐ぎんこう【兼営銀行】‥カウ
短期資金と長期資金とをあわせて取り扱う銀行。特に、銀行業務と証券業務とをあわせ行う銀行。ドイツの銀行がその典型。
⇒けん‐えい【兼営】
げんえい‐し【幻影肢】
失った腕や脚がまだ存在するかのように、痛み・かゆみや運動感覚を感ずる現象。幻肢。
⇒げん‐えい【幻影】
げんえい‐じん【玄英神】
冬をつかさどる神。浄瑠璃、天神記「冬の神は北方の天に立ち給ひ、―と申すとかや」
けん‐えき【検疫】
伝染病を予防するため、病原体の有無につき人・貨物・家畜などを診断・検案し、必要な場合には隔離・消毒などの措置をとること。
⇒けんえき‐かんせんしょう【検疫感染症】
⇒けんえき‐こう【検疫港】
⇒けんえき‐せん【検疫船】
けん‐えき【権益】
権利と利益。特に、ある国が他国の領土内で得た権利と利益。「―を守る」
げん‐えき【原液】
製造・加工のもとになる液体。
げん‐えき【現役】
①常備兵役の一つ。常時軍務に服し、戦時部隊の骨幹とされる役種。
②現にある職務に従事して活躍している人。「―投手」
③浪人4に対して、在校中の受験生。「―で合格する」
げん‐えき【減益】
利益が減ること。↔増益
けんえき‐かんせんしょう【検疫感染症】‥シヤウ
検疫の対象となる感染症。日本では検疫法により、感染症法の1類感染症(エボラ出血熱・ラッサ熱・クリミア‐コンゴ出血熱・SARSサーズ・マールブルグ病・ペスト・痘瘡)とコレラ・黄熱・H5N1型インフルエンザ・マラリア・デング熱と定められている。
⇒けん‐えき【検疫】
けんえき‐こう【検疫港】‥カウ
外航船の乗客・船員・貨物の検疫・消毒を行い、検疫済の証明書を交付できる港。
⇒けん‐えき【検疫】
けんえき‐せん【検疫船】
検疫を行う検疫官を沖合の船に送り迎えする小型船。
⇒けん‐えき【検疫】
けん‐えつ【検閲】
①調べあらためること。特に、出版物・映画などの内容を公権力が審査し、不適当と認めるときはその発表などを禁止する行為をいい、日本国憲法はこれを禁止。
→参照条文:日本国憲法第21条
②〔心〕自我、とくに超自我の機能の一つ。快楽原則に従って無意識の欲求を解放しようとするイドがそのままの形では出現しないように、超自我による社会的規範と自我の防衛機制とを通じて、抑圧したり、変形して放出させたりすること。精神分析の用語。
けん‐えん【犬猿】‥ヱン
犬と猿。互いに仲の悪いことをたとえていう。
⇒けんえん‐の‐なか【犬猿の仲】
⇒犬猿もただならず
けん‐えん【妍艶】
あでやかで美しいこと。
けん‐えん【倦厭】
あきていやになること。
けん‐えん【嫌煙】
(「禁煙」をもじって)近くで他人が喫煙するのをきらって拒否すること。「―権」
けん‐えん【慊焉】
(「慊」には満足と不満足との両意がある)
①あきたらず思うさま。慊如けんじょ。「―たるものがある」
②(多く打消の語を伴う)満足に思うさま。慊然。「―とせぬ顔」
けんえん【蘐園】‥ヱン
荻生徂徠おぎゅうそらいの書斎と塾の名称。江戸日本橋茅場町にあり、「茅」と同義の「蘐」をもって命名。
⇒けんえん‐がくは【蘐園学派】
げん‐えん【玄猿】‥ヱン
(顔が黒いからいう)手長猿てながざる。
げん‐えん【減塩】
①循環器疾患などの治療や予防のために、食塩の摂取量をひかえること。
②醤油・味噌などの食塩の含有量を少なめにすること。「―醤油」
⇒げんえん‐しょく【減塩食】
げんえん【諺苑】‥ヱン
辞書。太田全斎著。7巻。1797年(寛政9)成る。俗語・俚諺をいろは順に編集。これを増修したのが「俚言集覧」。
けんえん‐がくは【蘐園学派】‥ヱン‥
荻生徂徠の門流。徂徠学派・古文辞派ともいう。
⇒けんえん【蘐園】
けんえん‐き【検塩器】
比重計の一種で、水中の塩分の含量を測る器具。
げんえん‐しょく【減塩食】
食塩の含有量を少なくした食事。浮腫や高血圧性疾患の治療に用いる。
⇒げん‐えん【減塩】
けんえん‐の‐なか【犬猿の仲】‥ヱン‥
犬と猿のように、非常に仲が悪いことのたとえ。犬と猿。
⇒けん‐えん【犬猿】
げん‐うん【玄雲】
黒い雲。くろくも。
げん‐うん【眩暈】
目がくらんで頭のふらふらする感じ。めまい。
げんえ【玄慧・玄恵】‥ヱ
(ゲンネとも)鎌倉後期・南北朝時代の学僧。京都の人。一説に虎関師錬こかんしれんの弟。天台・禅・宋学を究め、足利尊氏・直義に用いられ、建武式目の制定に参与。「太平記」「庭訓往来」の著者に擬せられる。(1279〜1350)
けん‐えい【巻纓】
纓を巻き、黒塗りまたは白木の夾木はさみぎでとめたもの。武官用。まきえい。→冠(図)→纓(図)
けんえい【建永】
(ケンヨウとも)[文選]鎌倉前期、土御門天皇朝の年号。元久3年4月27日(1206年6月5日)改元、建永2年10月25日(1207年11月16日)承元に改元。
けん‐えい【県営】
県が経営または設置・管理すること。
けん‐えい【兼営】
本業のほかに別の営業を兼ねて行うこと。
⇒けんえい‐ぎんこう【兼営銀行】
けん‐えい【牽曳】
ひくこと。ひっぱること。牽引。
けん‐えい【献詠】
詩歌を詠んで宮中・神社などにたてまつること。また、その詩歌。
けん‐えい【顕栄】
名があらわれ、身の栄えること。位高く立身すること。
げんえい【元永】
平安後期、鳥羽天皇朝の年号。永久6年4月3日(1118年4月25日)改元、元永3年4月10日(1120年5月9日)保安に改元。
げん‐えい【幻影】
そこにいない人間や霊魂の幻覚。本当は存在しないのに、あるように見えるもの。まぼろし。「―におびえる」
⇒げんえい‐し【幻影肢】
けんえい‐ぎんこう【兼営銀行】‥カウ
短期資金と長期資金とをあわせて取り扱う銀行。特に、銀行業務と証券業務とをあわせ行う銀行。ドイツの銀行がその典型。
⇒けん‐えい【兼営】
げんえい‐し【幻影肢】
失った腕や脚がまだ存在するかのように、痛み・かゆみや運動感覚を感ずる現象。幻肢。
⇒げん‐えい【幻影】
げんえい‐じん【玄英神】
冬をつかさどる神。浄瑠璃、天神記「冬の神は北方の天に立ち給ひ、―と申すとかや」
けん‐えき【検疫】
伝染病を予防するため、病原体の有無につき人・貨物・家畜などを診断・検案し、必要な場合には隔離・消毒などの措置をとること。
⇒けんえき‐かんせんしょう【検疫感染症】
⇒けんえき‐こう【検疫港】
⇒けんえき‐せん【検疫船】
けん‐えき【権益】
権利と利益。特に、ある国が他国の領土内で得た権利と利益。「―を守る」
げん‐えき【原液】
製造・加工のもとになる液体。
げん‐えき【現役】
①常備兵役の一つ。常時軍務に服し、戦時部隊の骨幹とされる役種。
②現にある職務に従事して活躍している人。「―投手」
③浪人4に対して、在校中の受験生。「―で合格する」
げん‐えき【減益】
利益が減ること。↔増益
けんえき‐かんせんしょう【検疫感染症】‥シヤウ
検疫の対象となる感染症。日本では検疫法により、感染症法の1類感染症(エボラ出血熱・ラッサ熱・クリミア‐コンゴ出血熱・SARSサーズ・マールブルグ病・ペスト・痘瘡)とコレラ・黄熱・H5N1型インフルエンザ・マラリア・デング熱と定められている。
⇒けん‐えき【検疫】
けんえき‐こう【検疫港】‥カウ
外航船の乗客・船員・貨物の検疫・消毒を行い、検疫済の証明書を交付できる港。
⇒けん‐えき【検疫】
けんえき‐せん【検疫船】
検疫を行う検疫官を沖合の船に送り迎えする小型船。
⇒けん‐えき【検疫】
けん‐えつ【検閲】
①調べあらためること。特に、出版物・映画などの内容を公権力が審査し、不適当と認めるときはその発表などを禁止する行為をいい、日本国憲法はこれを禁止。
→参照条文:日本国憲法第21条
②〔心〕自我、とくに超自我の機能の一つ。快楽原則に従って無意識の欲求を解放しようとするイドがそのままの形では出現しないように、超自我による社会的規範と自我の防衛機制とを通じて、抑圧したり、変形して放出させたりすること。精神分析の用語。
けん‐えん【犬猿】‥ヱン
犬と猿。互いに仲の悪いことをたとえていう。
⇒けんえん‐の‐なか【犬猿の仲】
⇒犬猿もただならず
けん‐えん【妍艶】
あでやかで美しいこと。
けん‐えん【倦厭】
あきていやになること。
けん‐えん【嫌煙】
(「禁煙」をもじって)近くで他人が喫煙するのをきらって拒否すること。「―権」
けん‐えん【慊焉】
(「慊」には満足と不満足との両意がある)
①あきたらず思うさま。慊如けんじょ。「―たるものがある」
②(多く打消の語を伴う)満足に思うさま。慊然。「―とせぬ顔」
けんえん【蘐園】‥ヱン
荻生徂徠おぎゅうそらいの書斎と塾の名称。江戸日本橋茅場町にあり、「茅」と同義の「蘐」をもって命名。
⇒けんえん‐がくは【蘐園学派】
げん‐えん【玄猿】‥ヱン
(顔が黒いからいう)手長猿てながざる。
げん‐えん【減塩】
①循環器疾患などの治療や予防のために、食塩の摂取量をひかえること。
②醤油・味噌などの食塩の含有量を少なめにすること。「―醤油」
⇒げんえん‐しょく【減塩食】
げんえん【諺苑】‥ヱン
辞書。太田全斎著。7巻。1797年(寛政9)成る。俗語・俚諺をいろは順に編集。これを増修したのが「俚言集覧」。
けんえん‐がくは【蘐園学派】‥ヱン‥
荻生徂徠の門流。徂徠学派・古文辞派ともいう。
⇒けんえん【蘐園】
けんえん‐き【検塩器】
比重計の一種で、水中の塩分の含量を測る器具。
げんえん‐しょく【減塩食】
食塩の含有量を少なくした食事。浮腫や高血圧性疾患の治療に用いる。
⇒げん‐えん【減塩】
けんえん‐の‐なか【犬猿の仲】‥ヱン‥
犬と猿のように、非常に仲が悪いことのたとえ。犬と猿。
⇒けん‐えん【犬猿】
広辞苑 ページ 6285 での【○毛を以て馬を相す】単語。