複数辞典一括検索+![]()
![]()
○死ねがな目抉ろしねがなめくじろ🔗⭐🔉
○死ねがな目抉ろしねがなめくじろ
(「がな」は願望の助詞)死ねばよい、そうしたら目をくりぬいてやろうというような貪欲非道のたとえ。世間胸算用4「まことに―の男なり」
⇒し・ぬ【死ぬ】
シネ‐カメラ【cine-camera】
映画撮影用のカメラ。撮影機。
シネ‐コン
シネマ‐コンプレックスの略。
しね‐しね
(→)「しなしな」に同じ。
シネ‐スコ
シネマスコープの略。
じ‐ねずみ【地鼠】ヂ‥
モグラ目トガリネズミ科ジネズミ属の哺乳類の総称。14種以上を含み、東南アジアからアフリカに広く分布、日本にはジネズミ・コジネズミ・ワタセジネズミなど。ジネズミは、体長7センチメートルほど。体はネズミに似るが、吻が尖る。夜行性で、昆虫などを捕食。
じねずみ
 じ‐ねつ【地熱】ヂ‥
①地殻内の高温部から伝わる熱。ちねつ。
②地面の熱気。
⇒じねつ‐はつでん【地熱発電】
じねつ‐はつでん【地熱発電】ヂ‥
地下から噴出する蒸気の熱エネルギーを利用する発電。
⇒じ‐ねつ【地熱】
シネマ【cinéma フランス】
(cinématographeの略)映画。キネマ。
⇒シネマ‐ヴェリテ【cinéma vérité フランス】
⇒シネマ‐オルガン【cinema organ】
⇒シネマ‐コンプレックス【cinema complex】
シネマ‐ヴェリテ【cinéma vérité フランス】
記録映画から虚構を排しようとする主張。また、その方法による映画。ヴェルトフのキノ‐プラウダ(ロシア語)の仏訳。
⇒シネマ【cinéma フランス】
シネマ‐オルガン【cinema organ】
20世紀初頭、映画館・劇場で使われたオルガン。サイレント映画の伴奏用に開発。オーケストラ音・打楽器・効果音などが組み込まれている。→シアター‐オルガン。
⇒シネマ【cinéma フランス】
シネマ‐コンプレックス【cinema complex】
同一ビル内に数館の映画館があり、入場券売場などを1カ所にまとめた施設。シネコン。
⇒シネマ【cinéma フランス】
シネマスコープ【CinemaScope】
ワイド‐スクリーン映画の一つ。35ミリ撮影機に円柱レンズを含む特殊レンズをつけて、左右方向を圧縮して撮影し、同様のレンズで拡大して映写する。シネスコ。商標名。
シネマテーク【cinémathèque フランス】
映画のフィルム・資料などを収集・保存し、上映する公共的施設。フィルム‐ライブラリー。→フィルム‐アーカイブ
シネマトグラフ【cinématographe フランス】
映画。活動写真。シネマ。キネマ。→リュミエール
シネラマ【Cinerama】
ワイド‐スクリーン映画の一つ。3本のレンズ、3本のフィルムを用いて、上下55度、左右146度の画角で撮影し、半円形の横長巨大スクリーンに映写して立体感のある画面を得る。音響も立体化。現在は1本の広幅フィルムに撮影。商標名。
シネラリア【Cineraria ラテン】
キク科の観賞用草本。カナリア諸島原産。高さ約30センチメートル。早春、花茎を出し、紅・紫・藍・藍紫・白色などの美麗な頭状花を開く。サイネリア。フキザクラ。フキギク。
し‐ねん【思念】
常に心にかけること。考え思うこと。
じ‐ねん【自然】
(呉音。多く助詞「に」「と」を伴って副詞的に用いる)おのずからそうあること。本来そうであること。ひとりでに。源氏物語帚木「―に、そのけはひ、こよなかるべし」→しぜん。
⇒じねん‐げどう【自然外道】
⇒じねん‐ご【自然秔】
⇒じねん‐ごどう【自然悟道】
⇒じねん‐じょ【自然薯】
⇒じねん‐じょう【自然生】
⇒じねん‐せき【自然石】
⇒じねん‐ち【自然智】
⇒じねん‐どう【自然銅】
⇒じねん‐ばえ【自然生え】
⇒じねん‐ほうに【自然法爾】
じ‐ねん【持念】ヂ‥
〔仏〕正法しょうぼうを受持して失念しないこと。
じねん‐げどう【自然外道】‥ダウ
〔仏〕あらゆる結果は因縁によらず自然に生じたものと考える学派。六師外道のマッカリ=ゴーサーラやアジタ=ケーサカンバラの説に比定される。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐ご【自然秔】
①(→)「笹の実」に同じ。
②麦畑に生える雑草。
⇒じ‐ねん【自然】
し‐ねんごう【私年号】‥ガウ
朝廷が正式に定めた年号に対し、民間で私に用いた年号。法興・白鳳・朱雀など年号制確立以前の逸年号のほか、福徳・弥勒・命禄など中世の古社寺縁起や金石文などにみえるものがある。異年号。偽年号。
私年号(日本の主な私年号)
じ‐ねつ【地熱】ヂ‥
①地殻内の高温部から伝わる熱。ちねつ。
②地面の熱気。
⇒じねつ‐はつでん【地熱発電】
じねつ‐はつでん【地熱発電】ヂ‥
地下から噴出する蒸気の熱エネルギーを利用する発電。
⇒じ‐ねつ【地熱】
シネマ【cinéma フランス】
(cinématographeの略)映画。キネマ。
⇒シネマ‐ヴェリテ【cinéma vérité フランス】
⇒シネマ‐オルガン【cinema organ】
⇒シネマ‐コンプレックス【cinema complex】
シネマ‐ヴェリテ【cinéma vérité フランス】
記録映画から虚構を排しようとする主張。また、その方法による映画。ヴェルトフのキノ‐プラウダ(ロシア語)の仏訳。
⇒シネマ【cinéma フランス】
シネマ‐オルガン【cinema organ】
20世紀初頭、映画館・劇場で使われたオルガン。サイレント映画の伴奏用に開発。オーケストラ音・打楽器・効果音などが組み込まれている。→シアター‐オルガン。
⇒シネマ【cinéma フランス】
シネマ‐コンプレックス【cinema complex】
同一ビル内に数館の映画館があり、入場券売場などを1カ所にまとめた施設。シネコン。
⇒シネマ【cinéma フランス】
シネマスコープ【CinemaScope】
ワイド‐スクリーン映画の一つ。35ミリ撮影機に円柱レンズを含む特殊レンズをつけて、左右方向を圧縮して撮影し、同様のレンズで拡大して映写する。シネスコ。商標名。
シネマテーク【cinémathèque フランス】
映画のフィルム・資料などを収集・保存し、上映する公共的施設。フィルム‐ライブラリー。→フィルム‐アーカイブ
シネマトグラフ【cinématographe フランス】
映画。活動写真。シネマ。キネマ。→リュミエール
シネラマ【Cinerama】
ワイド‐スクリーン映画の一つ。3本のレンズ、3本のフィルムを用いて、上下55度、左右146度の画角で撮影し、半円形の横長巨大スクリーンに映写して立体感のある画面を得る。音響も立体化。現在は1本の広幅フィルムに撮影。商標名。
シネラリア【Cineraria ラテン】
キク科の観賞用草本。カナリア諸島原産。高さ約30センチメートル。早春、花茎を出し、紅・紫・藍・藍紫・白色などの美麗な頭状花を開く。サイネリア。フキザクラ。フキギク。
し‐ねん【思念】
常に心にかけること。考え思うこと。
じ‐ねん【自然】
(呉音。多く助詞「に」「と」を伴って副詞的に用いる)おのずからそうあること。本来そうであること。ひとりでに。源氏物語帚木「―に、そのけはひ、こよなかるべし」→しぜん。
⇒じねん‐げどう【自然外道】
⇒じねん‐ご【自然秔】
⇒じねん‐ごどう【自然悟道】
⇒じねん‐じょ【自然薯】
⇒じねん‐じょう【自然生】
⇒じねん‐せき【自然石】
⇒じねん‐ち【自然智】
⇒じねん‐どう【自然銅】
⇒じねん‐ばえ【自然生え】
⇒じねん‐ほうに【自然法爾】
じ‐ねん【持念】ヂ‥
〔仏〕正法しょうぼうを受持して失念しないこと。
じねん‐げどう【自然外道】‥ダウ
〔仏〕あらゆる結果は因縁によらず自然に生じたものと考える学派。六師外道のマッカリ=ゴーサーラやアジタ=ケーサカンバラの説に比定される。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐ご【自然秔】
①(→)「笹の実」に同じ。
②麦畑に生える雑草。
⇒じ‐ねん【自然】
し‐ねんごう【私年号】‥ガウ
朝廷が正式に定めた年号に対し、民間で私に用いた年号。法興・白鳳・朱雀など年号制確立以前の逸年号のほか、福徳・弥勒・命禄など中世の古社寺縁起や金石文などにみえるものがある。異年号。偽年号。
私年号(日本の主な私年号)
 じねんこじ【自然居士】
能。観阿弥作。一少女が両親供養のため人買いに身を売る。自然居士はその次第を知り、人買いの跡を追って少女を救う。
じねん‐ごどう【自然悟道】‥ダウ
〔仏〕教えによらず、自然に開悟すること。
⇒じ‐ねん【自然】
し‐ねんじょ【四念処】
〔仏〕三十七道品どうほんの一つで、原始仏教の修行法のうち最も代表的なもの。身を不浄と観ずる身念処、感覚をすべて苦と観ずる受念処、心を無常と観ずる心念処、法を無我と観ずる法念処の総称。四念処観。四念住。
じねん‐じょ【自然薯】
「自然生じねんじょう」の転。〈[季]秋〉
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐じょう【自然生】‥ジヤウ
①栽培されているナガイモに対して、山地に自生しているヤマノイモの称。自然薯じねんじょ。
②天然に生い出ること。また、その植物。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐せき【自然石】
天然のままの石。↔人造石。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐ち【自然智】
〔仏〕人為的努力によらず、自然に生ずる悟りの智慧。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐どう【自然銅】
⇒しぜんどう。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐ばえ【自然生え】
自然に生えでたこと。また、その草木。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐ほうに【自然法爾】‥ホフ‥
〔仏〕人為を加えず、一切の存在はおのずから真理にかなっていること。親鸞はこれを念仏信仰にあてはめ、人為を捨てて仏に任せきることとした。
⇒じ‐ねん【自然】
しの【篠】
①細くて群がり生える小さい竹。ヤダケ・メダケの類。篠の小笹。篠の葉草。万葉集7「近江のや矢ばせの―を矢矧がずて」
②綿糸紡績・毛糸紡績・絹糸紡績などの中間製品の一つ。不純物を除き十分に開かれた繊維を、糸にするためにほとんど撚よりの加わらない太い紐状にしたもの。
③甲冑に付属する籠手こて・脛当すねあてなどの材料。縦長の鉄板。
④篠笛の略。
⇒篠を束ねる
⇒篠を突く
⇒篠を乱す
しの【志野】
姓氏の一つ。
⇒しの‐そうしん【志野宗信】
しの‐いり【篠入】
歌舞伎囃子はやしの一つ。三味線の合方に篠笛を加え、切腹など愁嘆の場面に用いる。
し‐のう【子嚢】‥ナウ
①子嚢菌の胞子を入れる棍棒状の嚢状体。中に普通、8個の胞子を1列に並べ、胞子が成熟すれば子嚢は破れて胞子は散布する。
②コケ植物やシダ類の胞子を入れるふくろ。胞子嚢。→蒴さく。
③ヒドロ虫類の生殖体の一種。
⇒しのう‐きん【子嚢菌】
し‐のう【司農】
①中国古代の官名。農政をつかさどる。→大司農。
②宮内省の唐名。
⇒しのう‐けい【司農卿】
し‐のう【四能】
四つの芸能。琴・棋・書・画をいう。→きんきしょが
し‐のう【詩嚢】‥ナウ
漢詩の草稿を入れるふくろ。転じて、詩人の詩想。「―を肥やす」
しのう‐きん【子嚢菌】‥ナウ‥
菌類の一群。多種多形の胞子を生じ、有性胞子として子嚢内に子嚢胞子を形成する。無性的にも繁殖。コウジカビ・アカパンカビ・チャワンタケなど。
⇒し‐のう【子嚢】
しのう‐きん【志納金】‥ナフ‥
信仰への志から社寺に納める金。
しのう‐くんれんし【視能訓練士】
厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に、斜視や弱視など視機能に障害のある人に対し、機能回復のための矯正訓練やこれに必要な検査を行うことを業とする人。
しのう‐けい【司農卿】
宮内卿の唐名。
⇒し‐のう【司農】
し‐のう‐こう‐しょう【士農工商】‥シヤウ
士と農と工と商。江戸時代の封建社会の身分観念に従って、上位から順に並べたもの。なおこの下に、えた・非人があった。四民。
じ‐の‐うつわもの【瓷器】‥ウツハ‥
やきもの。土器かわらけ。じのつき。〈倭名類聚鈔16〉
ジノーヴィエフ【Grigorii E. Zinov'ev】
ソ連の政治家。ボリシェヴィキの一員。革命後、1919〜26年コミンテルン議長。左翼反対派にくみし、34年キーロフ暗殺事件を口実に逮捕、36年裁判で死刑。(1883〜1936)
しの‐おり【志野折】‥ヲリ
(→)「思い羽おもいば包み」に同じ。
しの‐がき【篠垣】
篠竹を編んでつくったまがき。
しの‐がなもの【篠金物】
鉄の細い板を篠竹を立てたように縦に並べた金具。武具などに用いる。
じ‐の‐かみ【地の神】ヂ‥
⇒じがみ(地神)
しのぎ
①茶道で、風炉ふろの灰を寄せるとき、山の灰角はいかどの名。
②柄杓ひしゃくの名所などころ。柄のけらくびにつづく所。→柄杓(図)
しのぎ【凌ぎ】
①しのぐこと。堪えること。
②(一時をしのぐ意)(→)非時ひじ2に同じ。
しのぎ【鎬】
①刀剣の名所などころ。刀身の刃と棟むねとの間を縦に走り、稜線をなして高くなったところ。また、両刃の剣の中間にある稜線。ある種の鏃やじりにもある。→刀(図)。
②建築の細部で、中央で高く両方へ低くなっているもの。例えば、隅木の上端中央の背峰形の部分など。→鎬彫(図)。
③近世後期の笄こうがいの一種。
⇒しのぎ‐さがり【鎬下り】
⇒しのぎ‐じ【鎬地】
⇒しのぎ‐すじ【鎬筋】
⇒しのぎ‐づくり【鎬造り】
⇒しのぎ‐ぼり【鎬彫】
⇒鎬を削る
しの‐ぎ【篠木】
便所で尻拭いに用いる竹片。かきぎ。
しのぎ‐さがり【鎬下り】
薙刀なぎなたなどの鎬の先端からやや下方の位置。太平記15「備前長刀の―に菖蒲形なるを脇に挟み」
⇒しのぎ【鎬】
しのぎ‐じ【鎬地】‥ヂ
鎬から刃先までの地に対して、鎬と棟むねとの間の高い部分。磨地みがきじ。→刀(図)。
⇒しのぎ【鎬】
しのぎ‐すじ【鎬筋】‥スヂ
刀剣の茎なかごに通っている鎬。
⇒しのぎ【鎬】
しのぎ‐づくり【鎬造り】
刃の幅が広く、鎬の幅が狭い刀剣のつくり。本造り。↔平ひら造り。
⇒しのぎ【鎬】
しのき‐は【しのき羽】
矢に矧はいだ鳥の風切羽。また、その矢。万葉集13「―を二つたばさみ」
しのぎ‐ぼり【鎬彫】
〔建〕彫り沈めた底に鎬をつける彫法。
鎬彫
じねんこじ【自然居士】
能。観阿弥作。一少女が両親供養のため人買いに身を売る。自然居士はその次第を知り、人買いの跡を追って少女を救う。
じねん‐ごどう【自然悟道】‥ダウ
〔仏〕教えによらず、自然に開悟すること。
⇒じ‐ねん【自然】
し‐ねんじょ【四念処】
〔仏〕三十七道品どうほんの一つで、原始仏教の修行法のうち最も代表的なもの。身を不浄と観ずる身念処、感覚をすべて苦と観ずる受念処、心を無常と観ずる心念処、法を無我と観ずる法念処の総称。四念処観。四念住。
じねん‐じょ【自然薯】
「自然生じねんじょう」の転。〈[季]秋〉
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐じょう【自然生】‥ジヤウ
①栽培されているナガイモに対して、山地に自生しているヤマノイモの称。自然薯じねんじょ。
②天然に生い出ること。また、その植物。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐せき【自然石】
天然のままの石。↔人造石。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐ち【自然智】
〔仏〕人為的努力によらず、自然に生ずる悟りの智慧。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐どう【自然銅】
⇒しぜんどう。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐ばえ【自然生え】
自然に生えでたこと。また、その草木。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐ほうに【自然法爾】‥ホフ‥
〔仏〕人為を加えず、一切の存在はおのずから真理にかなっていること。親鸞はこれを念仏信仰にあてはめ、人為を捨てて仏に任せきることとした。
⇒じ‐ねん【自然】
しの【篠】
①細くて群がり生える小さい竹。ヤダケ・メダケの類。篠の小笹。篠の葉草。万葉集7「近江のや矢ばせの―を矢矧がずて」
②綿糸紡績・毛糸紡績・絹糸紡績などの中間製品の一つ。不純物を除き十分に開かれた繊維を、糸にするためにほとんど撚よりの加わらない太い紐状にしたもの。
③甲冑に付属する籠手こて・脛当すねあてなどの材料。縦長の鉄板。
④篠笛の略。
⇒篠を束ねる
⇒篠を突く
⇒篠を乱す
しの【志野】
姓氏の一つ。
⇒しの‐そうしん【志野宗信】
しの‐いり【篠入】
歌舞伎囃子はやしの一つ。三味線の合方に篠笛を加え、切腹など愁嘆の場面に用いる。
し‐のう【子嚢】‥ナウ
①子嚢菌の胞子を入れる棍棒状の嚢状体。中に普通、8個の胞子を1列に並べ、胞子が成熟すれば子嚢は破れて胞子は散布する。
②コケ植物やシダ類の胞子を入れるふくろ。胞子嚢。→蒴さく。
③ヒドロ虫類の生殖体の一種。
⇒しのう‐きん【子嚢菌】
し‐のう【司農】
①中国古代の官名。農政をつかさどる。→大司農。
②宮内省の唐名。
⇒しのう‐けい【司農卿】
し‐のう【四能】
四つの芸能。琴・棋・書・画をいう。→きんきしょが
し‐のう【詩嚢】‥ナウ
漢詩の草稿を入れるふくろ。転じて、詩人の詩想。「―を肥やす」
しのう‐きん【子嚢菌】‥ナウ‥
菌類の一群。多種多形の胞子を生じ、有性胞子として子嚢内に子嚢胞子を形成する。無性的にも繁殖。コウジカビ・アカパンカビ・チャワンタケなど。
⇒し‐のう【子嚢】
しのう‐きん【志納金】‥ナフ‥
信仰への志から社寺に納める金。
しのう‐くんれんし【視能訓練士】
厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に、斜視や弱視など視機能に障害のある人に対し、機能回復のための矯正訓練やこれに必要な検査を行うことを業とする人。
しのう‐けい【司農卿】
宮内卿の唐名。
⇒し‐のう【司農】
し‐のう‐こう‐しょう【士農工商】‥シヤウ
士と農と工と商。江戸時代の封建社会の身分観念に従って、上位から順に並べたもの。なおこの下に、えた・非人があった。四民。
じ‐の‐うつわもの【瓷器】‥ウツハ‥
やきもの。土器かわらけ。じのつき。〈倭名類聚鈔16〉
ジノーヴィエフ【Grigorii E. Zinov'ev】
ソ連の政治家。ボリシェヴィキの一員。革命後、1919〜26年コミンテルン議長。左翼反対派にくみし、34年キーロフ暗殺事件を口実に逮捕、36年裁判で死刑。(1883〜1936)
しの‐おり【志野折】‥ヲリ
(→)「思い羽おもいば包み」に同じ。
しの‐がき【篠垣】
篠竹を編んでつくったまがき。
しの‐がなもの【篠金物】
鉄の細い板を篠竹を立てたように縦に並べた金具。武具などに用いる。
じ‐の‐かみ【地の神】ヂ‥
⇒じがみ(地神)
しのぎ
①茶道で、風炉ふろの灰を寄せるとき、山の灰角はいかどの名。
②柄杓ひしゃくの名所などころ。柄のけらくびにつづく所。→柄杓(図)
しのぎ【凌ぎ】
①しのぐこと。堪えること。
②(一時をしのぐ意)(→)非時ひじ2に同じ。
しのぎ【鎬】
①刀剣の名所などころ。刀身の刃と棟むねとの間を縦に走り、稜線をなして高くなったところ。また、両刃の剣の中間にある稜線。ある種の鏃やじりにもある。→刀(図)。
②建築の細部で、中央で高く両方へ低くなっているもの。例えば、隅木の上端中央の背峰形の部分など。→鎬彫(図)。
③近世後期の笄こうがいの一種。
⇒しのぎ‐さがり【鎬下り】
⇒しのぎ‐じ【鎬地】
⇒しのぎ‐すじ【鎬筋】
⇒しのぎ‐づくり【鎬造り】
⇒しのぎ‐ぼり【鎬彫】
⇒鎬を削る
しの‐ぎ【篠木】
便所で尻拭いに用いる竹片。かきぎ。
しのぎ‐さがり【鎬下り】
薙刀なぎなたなどの鎬の先端からやや下方の位置。太平記15「備前長刀の―に菖蒲形なるを脇に挟み」
⇒しのぎ【鎬】
しのぎ‐じ【鎬地】‥ヂ
鎬から刃先までの地に対して、鎬と棟むねとの間の高い部分。磨地みがきじ。→刀(図)。
⇒しのぎ【鎬】
しのぎ‐すじ【鎬筋】‥スヂ
刀剣の茎なかごに通っている鎬。
⇒しのぎ【鎬】
しのぎ‐づくり【鎬造り】
刃の幅が広く、鎬の幅が狭い刀剣のつくり。本造り。↔平ひら造り。
⇒しのぎ【鎬】
しのき‐は【しのき羽】
矢に矧はいだ鳥の風切羽。また、その矢。万葉集13「―を二つたばさみ」
しのぎ‐ぼり【鎬彫】
〔建〕彫り沈めた底に鎬をつける彫法。
鎬彫
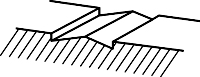 ⇒しのぎ【鎬】
⇒しのぎ【鎬】
 じ‐ねつ【地熱】ヂ‥
①地殻内の高温部から伝わる熱。ちねつ。
②地面の熱気。
⇒じねつ‐はつでん【地熱発電】
じねつ‐はつでん【地熱発電】ヂ‥
地下から噴出する蒸気の熱エネルギーを利用する発電。
⇒じ‐ねつ【地熱】
シネマ【cinéma フランス】
(cinématographeの略)映画。キネマ。
⇒シネマ‐ヴェリテ【cinéma vérité フランス】
⇒シネマ‐オルガン【cinema organ】
⇒シネマ‐コンプレックス【cinema complex】
シネマ‐ヴェリテ【cinéma vérité フランス】
記録映画から虚構を排しようとする主張。また、その方法による映画。ヴェルトフのキノ‐プラウダ(ロシア語)の仏訳。
⇒シネマ【cinéma フランス】
シネマ‐オルガン【cinema organ】
20世紀初頭、映画館・劇場で使われたオルガン。サイレント映画の伴奏用に開発。オーケストラ音・打楽器・効果音などが組み込まれている。→シアター‐オルガン。
⇒シネマ【cinéma フランス】
シネマ‐コンプレックス【cinema complex】
同一ビル内に数館の映画館があり、入場券売場などを1カ所にまとめた施設。シネコン。
⇒シネマ【cinéma フランス】
シネマスコープ【CinemaScope】
ワイド‐スクリーン映画の一つ。35ミリ撮影機に円柱レンズを含む特殊レンズをつけて、左右方向を圧縮して撮影し、同様のレンズで拡大して映写する。シネスコ。商標名。
シネマテーク【cinémathèque フランス】
映画のフィルム・資料などを収集・保存し、上映する公共的施設。フィルム‐ライブラリー。→フィルム‐アーカイブ
シネマトグラフ【cinématographe フランス】
映画。活動写真。シネマ。キネマ。→リュミエール
シネラマ【Cinerama】
ワイド‐スクリーン映画の一つ。3本のレンズ、3本のフィルムを用いて、上下55度、左右146度の画角で撮影し、半円形の横長巨大スクリーンに映写して立体感のある画面を得る。音響も立体化。現在は1本の広幅フィルムに撮影。商標名。
シネラリア【Cineraria ラテン】
キク科の観賞用草本。カナリア諸島原産。高さ約30センチメートル。早春、花茎を出し、紅・紫・藍・藍紫・白色などの美麗な頭状花を開く。サイネリア。フキザクラ。フキギク。
し‐ねん【思念】
常に心にかけること。考え思うこと。
じ‐ねん【自然】
(呉音。多く助詞「に」「と」を伴って副詞的に用いる)おのずからそうあること。本来そうであること。ひとりでに。源氏物語帚木「―に、そのけはひ、こよなかるべし」→しぜん。
⇒じねん‐げどう【自然外道】
⇒じねん‐ご【自然秔】
⇒じねん‐ごどう【自然悟道】
⇒じねん‐じょ【自然薯】
⇒じねん‐じょう【自然生】
⇒じねん‐せき【自然石】
⇒じねん‐ち【自然智】
⇒じねん‐どう【自然銅】
⇒じねん‐ばえ【自然生え】
⇒じねん‐ほうに【自然法爾】
じ‐ねん【持念】ヂ‥
〔仏〕正法しょうぼうを受持して失念しないこと。
じねん‐げどう【自然外道】‥ダウ
〔仏〕あらゆる結果は因縁によらず自然に生じたものと考える学派。六師外道のマッカリ=ゴーサーラやアジタ=ケーサカンバラの説に比定される。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐ご【自然秔】
①(→)「笹の実」に同じ。
②麦畑に生える雑草。
⇒じ‐ねん【自然】
し‐ねんごう【私年号】‥ガウ
朝廷が正式に定めた年号に対し、民間で私に用いた年号。法興・白鳳・朱雀など年号制確立以前の逸年号のほか、福徳・弥勒・命禄など中世の古社寺縁起や金石文などにみえるものがある。異年号。偽年号。
私年号(日本の主な私年号)
じ‐ねつ【地熱】ヂ‥
①地殻内の高温部から伝わる熱。ちねつ。
②地面の熱気。
⇒じねつ‐はつでん【地熱発電】
じねつ‐はつでん【地熱発電】ヂ‥
地下から噴出する蒸気の熱エネルギーを利用する発電。
⇒じ‐ねつ【地熱】
シネマ【cinéma フランス】
(cinématographeの略)映画。キネマ。
⇒シネマ‐ヴェリテ【cinéma vérité フランス】
⇒シネマ‐オルガン【cinema organ】
⇒シネマ‐コンプレックス【cinema complex】
シネマ‐ヴェリテ【cinéma vérité フランス】
記録映画から虚構を排しようとする主張。また、その方法による映画。ヴェルトフのキノ‐プラウダ(ロシア語)の仏訳。
⇒シネマ【cinéma フランス】
シネマ‐オルガン【cinema organ】
20世紀初頭、映画館・劇場で使われたオルガン。サイレント映画の伴奏用に開発。オーケストラ音・打楽器・効果音などが組み込まれている。→シアター‐オルガン。
⇒シネマ【cinéma フランス】
シネマ‐コンプレックス【cinema complex】
同一ビル内に数館の映画館があり、入場券売場などを1カ所にまとめた施設。シネコン。
⇒シネマ【cinéma フランス】
シネマスコープ【CinemaScope】
ワイド‐スクリーン映画の一つ。35ミリ撮影機に円柱レンズを含む特殊レンズをつけて、左右方向を圧縮して撮影し、同様のレンズで拡大して映写する。シネスコ。商標名。
シネマテーク【cinémathèque フランス】
映画のフィルム・資料などを収集・保存し、上映する公共的施設。フィルム‐ライブラリー。→フィルム‐アーカイブ
シネマトグラフ【cinématographe フランス】
映画。活動写真。シネマ。キネマ。→リュミエール
シネラマ【Cinerama】
ワイド‐スクリーン映画の一つ。3本のレンズ、3本のフィルムを用いて、上下55度、左右146度の画角で撮影し、半円形の横長巨大スクリーンに映写して立体感のある画面を得る。音響も立体化。現在は1本の広幅フィルムに撮影。商標名。
シネラリア【Cineraria ラテン】
キク科の観賞用草本。カナリア諸島原産。高さ約30センチメートル。早春、花茎を出し、紅・紫・藍・藍紫・白色などの美麗な頭状花を開く。サイネリア。フキザクラ。フキギク。
し‐ねん【思念】
常に心にかけること。考え思うこと。
じ‐ねん【自然】
(呉音。多く助詞「に」「と」を伴って副詞的に用いる)おのずからそうあること。本来そうであること。ひとりでに。源氏物語帚木「―に、そのけはひ、こよなかるべし」→しぜん。
⇒じねん‐げどう【自然外道】
⇒じねん‐ご【自然秔】
⇒じねん‐ごどう【自然悟道】
⇒じねん‐じょ【自然薯】
⇒じねん‐じょう【自然生】
⇒じねん‐せき【自然石】
⇒じねん‐ち【自然智】
⇒じねん‐どう【自然銅】
⇒じねん‐ばえ【自然生え】
⇒じねん‐ほうに【自然法爾】
じ‐ねん【持念】ヂ‥
〔仏〕正法しょうぼうを受持して失念しないこと。
じねん‐げどう【自然外道】‥ダウ
〔仏〕あらゆる結果は因縁によらず自然に生じたものと考える学派。六師外道のマッカリ=ゴーサーラやアジタ=ケーサカンバラの説に比定される。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐ご【自然秔】
①(→)「笹の実」に同じ。
②麦畑に生える雑草。
⇒じ‐ねん【自然】
し‐ねんごう【私年号】‥ガウ
朝廷が正式に定めた年号に対し、民間で私に用いた年号。法興・白鳳・朱雀など年号制確立以前の逸年号のほか、福徳・弥勒・命禄など中世の古社寺縁起や金石文などにみえるものがある。異年号。偽年号。
私年号(日本の主な私年号)
 じねんこじ【自然居士】
能。観阿弥作。一少女が両親供養のため人買いに身を売る。自然居士はその次第を知り、人買いの跡を追って少女を救う。
じねん‐ごどう【自然悟道】‥ダウ
〔仏〕教えによらず、自然に開悟すること。
⇒じ‐ねん【自然】
し‐ねんじょ【四念処】
〔仏〕三十七道品どうほんの一つで、原始仏教の修行法のうち最も代表的なもの。身を不浄と観ずる身念処、感覚をすべて苦と観ずる受念処、心を無常と観ずる心念処、法を無我と観ずる法念処の総称。四念処観。四念住。
じねん‐じょ【自然薯】
「自然生じねんじょう」の転。〈[季]秋〉
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐じょう【自然生】‥ジヤウ
①栽培されているナガイモに対して、山地に自生しているヤマノイモの称。自然薯じねんじょ。
②天然に生い出ること。また、その植物。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐せき【自然石】
天然のままの石。↔人造石。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐ち【自然智】
〔仏〕人為的努力によらず、自然に生ずる悟りの智慧。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐どう【自然銅】
⇒しぜんどう。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐ばえ【自然生え】
自然に生えでたこと。また、その草木。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐ほうに【自然法爾】‥ホフ‥
〔仏〕人為を加えず、一切の存在はおのずから真理にかなっていること。親鸞はこれを念仏信仰にあてはめ、人為を捨てて仏に任せきることとした。
⇒じ‐ねん【自然】
しの【篠】
①細くて群がり生える小さい竹。ヤダケ・メダケの類。篠の小笹。篠の葉草。万葉集7「近江のや矢ばせの―を矢矧がずて」
②綿糸紡績・毛糸紡績・絹糸紡績などの中間製品の一つ。不純物を除き十分に開かれた繊維を、糸にするためにほとんど撚よりの加わらない太い紐状にしたもの。
③甲冑に付属する籠手こて・脛当すねあてなどの材料。縦長の鉄板。
④篠笛の略。
⇒篠を束ねる
⇒篠を突く
⇒篠を乱す
しの【志野】
姓氏の一つ。
⇒しの‐そうしん【志野宗信】
しの‐いり【篠入】
歌舞伎囃子はやしの一つ。三味線の合方に篠笛を加え、切腹など愁嘆の場面に用いる。
し‐のう【子嚢】‥ナウ
①子嚢菌の胞子を入れる棍棒状の嚢状体。中に普通、8個の胞子を1列に並べ、胞子が成熟すれば子嚢は破れて胞子は散布する。
②コケ植物やシダ類の胞子を入れるふくろ。胞子嚢。→蒴さく。
③ヒドロ虫類の生殖体の一種。
⇒しのう‐きん【子嚢菌】
し‐のう【司農】
①中国古代の官名。農政をつかさどる。→大司農。
②宮内省の唐名。
⇒しのう‐けい【司農卿】
し‐のう【四能】
四つの芸能。琴・棋・書・画をいう。→きんきしょが
し‐のう【詩嚢】‥ナウ
漢詩の草稿を入れるふくろ。転じて、詩人の詩想。「―を肥やす」
しのう‐きん【子嚢菌】‥ナウ‥
菌類の一群。多種多形の胞子を生じ、有性胞子として子嚢内に子嚢胞子を形成する。無性的にも繁殖。コウジカビ・アカパンカビ・チャワンタケなど。
⇒し‐のう【子嚢】
しのう‐きん【志納金】‥ナフ‥
信仰への志から社寺に納める金。
しのう‐くんれんし【視能訓練士】
厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に、斜視や弱視など視機能に障害のある人に対し、機能回復のための矯正訓練やこれに必要な検査を行うことを業とする人。
しのう‐けい【司農卿】
宮内卿の唐名。
⇒し‐のう【司農】
し‐のう‐こう‐しょう【士農工商】‥シヤウ
士と農と工と商。江戸時代の封建社会の身分観念に従って、上位から順に並べたもの。なおこの下に、えた・非人があった。四民。
じ‐の‐うつわもの【瓷器】‥ウツハ‥
やきもの。土器かわらけ。じのつき。〈倭名類聚鈔16〉
ジノーヴィエフ【Grigorii E. Zinov'ev】
ソ連の政治家。ボリシェヴィキの一員。革命後、1919〜26年コミンテルン議長。左翼反対派にくみし、34年キーロフ暗殺事件を口実に逮捕、36年裁判で死刑。(1883〜1936)
しの‐おり【志野折】‥ヲリ
(→)「思い羽おもいば包み」に同じ。
しの‐がき【篠垣】
篠竹を編んでつくったまがき。
しの‐がなもの【篠金物】
鉄の細い板を篠竹を立てたように縦に並べた金具。武具などに用いる。
じ‐の‐かみ【地の神】ヂ‥
⇒じがみ(地神)
しのぎ
①茶道で、風炉ふろの灰を寄せるとき、山の灰角はいかどの名。
②柄杓ひしゃくの名所などころ。柄のけらくびにつづく所。→柄杓(図)
しのぎ【凌ぎ】
①しのぐこと。堪えること。
②(一時をしのぐ意)(→)非時ひじ2に同じ。
しのぎ【鎬】
①刀剣の名所などころ。刀身の刃と棟むねとの間を縦に走り、稜線をなして高くなったところ。また、両刃の剣の中間にある稜線。ある種の鏃やじりにもある。→刀(図)。
②建築の細部で、中央で高く両方へ低くなっているもの。例えば、隅木の上端中央の背峰形の部分など。→鎬彫(図)。
③近世後期の笄こうがいの一種。
⇒しのぎ‐さがり【鎬下り】
⇒しのぎ‐じ【鎬地】
⇒しのぎ‐すじ【鎬筋】
⇒しのぎ‐づくり【鎬造り】
⇒しのぎ‐ぼり【鎬彫】
⇒鎬を削る
しの‐ぎ【篠木】
便所で尻拭いに用いる竹片。かきぎ。
しのぎ‐さがり【鎬下り】
薙刀なぎなたなどの鎬の先端からやや下方の位置。太平記15「備前長刀の―に菖蒲形なるを脇に挟み」
⇒しのぎ【鎬】
しのぎ‐じ【鎬地】‥ヂ
鎬から刃先までの地に対して、鎬と棟むねとの間の高い部分。磨地みがきじ。→刀(図)。
⇒しのぎ【鎬】
しのぎ‐すじ【鎬筋】‥スヂ
刀剣の茎なかごに通っている鎬。
⇒しのぎ【鎬】
しのぎ‐づくり【鎬造り】
刃の幅が広く、鎬の幅が狭い刀剣のつくり。本造り。↔平ひら造り。
⇒しのぎ【鎬】
しのき‐は【しのき羽】
矢に矧はいだ鳥の風切羽。また、その矢。万葉集13「―を二つたばさみ」
しのぎ‐ぼり【鎬彫】
〔建〕彫り沈めた底に鎬をつける彫法。
鎬彫
じねんこじ【自然居士】
能。観阿弥作。一少女が両親供養のため人買いに身を売る。自然居士はその次第を知り、人買いの跡を追って少女を救う。
じねん‐ごどう【自然悟道】‥ダウ
〔仏〕教えによらず、自然に開悟すること。
⇒じ‐ねん【自然】
し‐ねんじょ【四念処】
〔仏〕三十七道品どうほんの一つで、原始仏教の修行法のうち最も代表的なもの。身を不浄と観ずる身念処、感覚をすべて苦と観ずる受念処、心を無常と観ずる心念処、法を無我と観ずる法念処の総称。四念処観。四念住。
じねん‐じょ【自然薯】
「自然生じねんじょう」の転。〈[季]秋〉
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐じょう【自然生】‥ジヤウ
①栽培されているナガイモに対して、山地に自生しているヤマノイモの称。自然薯じねんじょ。
②天然に生い出ること。また、その植物。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐せき【自然石】
天然のままの石。↔人造石。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐ち【自然智】
〔仏〕人為的努力によらず、自然に生ずる悟りの智慧。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐どう【自然銅】
⇒しぜんどう。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐ばえ【自然生え】
自然に生えでたこと。また、その草木。
⇒じ‐ねん【自然】
じねん‐ほうに【自然法爾】‥ホフ‥
〔仏〕人為を加えず、一切の存在はおのずから真理にかなっていること。親鸞はこれを念仏信仰にあてはめ、人為を捨てて仏に任せきることとした。
⇒じ‐ねん【自然】
しの【篠】
①細くて群がり生える小さい竹。ヤダケ・メダケの類。篠の小笹。篠の葉草。万葉集7「近江のや矢ばせの―を矢矧がずて」
②綿糸紡績・毛糸紡績・絹糸紡績などの中間製品の一つ。不純物を除き十分に開かれた繊維を、糸にするためにほとんど撚よりの加わらない太い紐状にしたもの。
③甲冑に付属する籠手こて・脛当すねあてなどの材料。縦長の鉄板。
④篠笛の略。
⇒篠を束ねる
⇒篠を突く
⇒篠を乱す
しの【志野】
姓氏の一つ。
⇒しの‐そうしん【志野宗信】
しの‐いり【篠入】
歌舞伎囃子はやしの一つ。三味線の合方に篠笛を加え、切腹など愁嘆の場面に用いる。
し‐のう【子嚢】‥ナウ
①子嚢菌の胞子を入れる棍棒状の嚢状体。中に普通、8個の胞子を1列に並べ、胞子が成熟すれば子嚢は破れて胞子は散布する。
②コケ植物やシダ類の胞子を入れるふくろ。胞子嚢。→蒴さく。
③ヒドロ虫類の生殖体の一種。
⇒しのう‐きん【子嚢菌】
し‐のう【司農】
①中国古代の官名。農政をつかさどる。→大司農。
②宮内省の唐名。
⇒しのう‐けい【司農卿】
し‐のう【四能】
四つの芸能。琴・棋・書・画をいう。→きんきしょが
し‐のう【詩嚢】‥ナウ
漢詩の草稿を入れるふくろ。転じて、詩人の詩想。「―を肥やす」
しのう‐きん【子嚢菌】‥ナウ‥
菌類の一群。多種多形の胞子を生じ、有性胞子として子嚢内に子嚢胞子を形成する。無性的にも繁殖。コウジカビ・アカパンカビ・チャワンタケなど。
⇒し‐のう【子嚢】
しのう‐きん【志納金】‥ナフ‥
信仰への志から社寺に納める金。
しのう‐くんれんし【視能訓練士】
厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に、斜視や弱視など視機能に障害のある人に対し、機能回復のための矯正訓練やこれに必要な検査を行うことを業とする人。
しのう‐けい【司農卿】
宮内卿の唐名。
⇒し‐のう【司農】
し‐のう‐こう‐しょう【士農工商】‥シヤウ
士と農と工と商。江戸時代の封建社会の身分観念に従って、上位から順に並べたもの。なおこの下に、えた・非人があった。四民。
じ‐の‐うつわもの【瓷器】‥ウツハ‥
やきもの。土器かわらけ。じのつき。〈倭名類聚鈔16〉
ジノーヴィエフ【Grigorii E. Zinov'ev】
ソ連の政治家。ボリシェヴィキの一員。革命後、1919〜26年コミンテルン議長。左翼反対派にくみし、34年キーロフ暗殺事件を口実に逮捕、36年裁判で死刑。(1883〜1936)
しの‐おり【志野折】‥ヲリ
(→)「思い羽おもいば包み」に同じ。
しの‐がき【篠垣】
篠竹を編んでつくったまがき。
しの‐がなもの【篠金物】
鉄の細い板を篠竹を立てたように縦に並べた金具。武具などに用いる。
じ‐の‐かみ【地の神】ヂ‥
⇒じがみ(地神)
しのぎ
①茶道で、風炉ふろの灰を寄せるとき、山の灰角はいかどの名。
②柄杓ひしゃくの名所などころ。柄のけらくびにつづく所。→柄杓(図)
しのぎ【凌ぎ】
①しのぐこと。堪えること。
②(一時をしのぐ意)(→)非時ひじ2に同じ。
しのぎ【鎬】
①刀剣の名所などころ。刀身の刃と棟むねとの間を縦に走り、稜線をなして高くなったところ。また、両刃の剣の中間にある稜線。ある種の鏃やじりにもある。→刀(図)。
②建築の細部で、中央で高く両方へ低くなっているもの。例えば、隅木の上端中央の背峰形の部分など。→鎬彫(図)。
③近世後期の笄こうがいの一種。
⇒しのぎ‐さがり【鎬下り】
⇒しのぎ‐じ【鎬地】
⇒しのぎ‐すじ【鎬筋】
⇒しのぎ‐づくり【鎬造り】
⇒しのぎ‐ぼり【鎬彫】
⇒鎬を削る
しの‐ぎ【篠木】
便所で尻拭いに用いる竹片。かきぎ。
しのぎ‐さがり【鎬下り】
薙刀なぎなたなどの鎬の先端からやや下方の位置。太平記15「備前長刀の―に菖蒲形なるを脇に挟み」
⇒しのぎ【鎬】
しのぎ‐じ【鎬地】‥ヂ
鎬から刃先までの地に対して、鎬と棟むねとの間の高い部分。磨地みがきじ。→刀(図)。
⇒しのぎ【鎬】
しのぎ‐すじ【鎬筋】‥スヂ
刀剣の茎なかごに通っている鎬。
⇒しのぎ【鎬】
しのぎ‐づくり【鎬造り】
刃の幅が広く、鎬の幅が狭い刀剣のつくり。本造り。↔平ひら造り。
⇒しのぎ【鎬】
しのき‐は【しのき羽】
矢に矧はいだ鳥の風切羽。また、その矢。万葉集13「―を二つたばさみ」
しのぎ‐ぼり【鎬彫】
〔建〕彫り沈めた底に鎬をつける彫法。
鎬彫
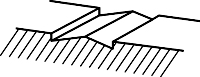 ⇒しのぎ【鎬】
⇒しのぎ【鎬】
広辞苑 ページ 8913 での【○死ねがな目抉ろ】単語。