複数辞典一括検索+![]()
![]()
つ(音節)🔗⭐🔉
つ
①舌端を上前歯のもとに密着して破裂摩擦させる無声子音〔ts〕と、母音〔u〕との結合した音節。〔tsu〕
②平仮名「つ」は「州」の略体の草体とも、「川」「津」「鬥」の草体とも。片仮名「ツ」は「州」の略体。
つ【津】🔗⭐🔉
つ【津】
①船舶の碇泊する所。ふなつき。港。万葉集19「君が船漕ぎ帰りきて―にはつるまで」
②わたしば。渡船場。
③人の集まる所。狂言、蚊相撲「いやこれは早、人々の通る―でござる」
つ【津】(地名)🔗⭐🔉
つ【津】
三重県の市。県庁所在地。古く伊勢海に臨む安濃津あのつの港で、もと藤堂氏32万石の城下町。津綟子つもじ・阿漕焼あこぎやきを産する。人口28万9千。
つ(助動詞)🔗⭐🔉
つ
〔助動〕
(活用は下二段型。活用語の連用形に付く。[活用]て/て/つ/つる/つれ/てよく)動詞「棄うつ」の約という。動作・作用が話し手など当事者の意図に基づき、作為的・意志的に成り立ったことを表し、無作為的・自然推移的意味で使われる「ぬ」と区別がある。室町時代からは用法が限られ、口語では衰える。→たり。
①動作・状態が完了する意。…してしまう。…した。後に推量の意味が続いた時は、強意と解釈されることもある。古事記中「新治にいばり筑波を過ぎて幾夜か寝つる」。万葉集8「沫雪に降らえて咲ける梅の花君がりやらばよそへてむかも」。保元物語「あはれ、取りもかふる物ならば、忠実が命にかへてまし」
②した人を責める思いを込めて、動作・事態の完了をいう。伊勢物語「みそかに通ふ女ありけり。それがもとよりこよひ夢になん見え給ひつるといへりければ」。源氏物語若紫「雀の子を犬君が逃がしつる」
③自分に責任があるという思いを込めて、動作・事態の完了をいう。万葉集5「手に持てる吾あが児飛ばしつ世の中の道」。古今和歌集恋「飛鳥川淵は瀬になる世なりとも思ひそめてむ人は忘れじ」
④(終止形だけの用法)対照的な動作を並列的に述べる。口語では並立助詞とする。中華若木詩抄「舞せつ歌せつする」。天草本平家物語「泣いつ笑うつせられた」
つ(助詞)🔗⭐🔉
つ
〔助詞〕
➊(格助詞)体言と体言を「の」の関係で結ぶ働きをする語。多く場所を示す名詞の後に付き、「の」よりも用法が狭い。上代の文献に見え、平安時代には「昼―方」「奥―方」と、複合語の中で見られるだけとなる。「天―神」「目ま―毛」「はじめ―方かた」
➋(接続助詞)(文語完了の助動詞「つ」から)動詞の連用形に付く。動作の並行・継起することを表す。前が撥音のときは「づ」となる。
①(「…つ…つ」の形で)…たり…たり。太平記6「追つ―返し―同士軍をぞしたりける」。浄瑠璃、心中天の網島「抜け―隠れ―なされても」。「組んづほぐれつ」
②(二つの動作・作用が同時に行われる時に、従属的な方の動作・作用に付ける)…ながら。方丈記「苦しむ時は休め―、まめなれば使ふ」
③…たりなどして。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「作病起して振つて見―、色々飽かるる工面して」
つ【箇・個】🔗⭐🔉
つ【箇・個】
〔接尾〕
数詞の下に添えて数を表す語。ち。古事記上「五百いお―真榊まさかき」。「ひと―」
ツァー【czar; tsar】🔗⭐🔉
ツァー【czar; tsar】
⇒ツァーリ
ツアー【tour】🔗⭐🔉
ツアー【tour】
①回遊。周遊旅行。小旅行。「―を組む」「スキー‐―」
②旅行会社などが企画する団体旅行。
③歌手・劇団などの巡業。「コンサート‐―」
⇒ツアー‐ガイド【tour guide】
⇒ツアー‐コンダクター【tour conductor】
ツアー‐ガイド【tour guide】🔗⭐🔉
ツアー‐ガイド【tour guide】
旅行案内人。添乗員。
⇒ツアー【tour】
ツアー‐コンダクター【tour conductor】🔗⭐🔉
ツアー‐コンダクター【tour conductor】
団体旅行を案内・誘導する人。添乗員。
⇒ツアー【tour】
ツァーリ【tsar' ロシア】🔗⭐🔉
ツァーリ【tsar' ロシア】
帝政時代のロシア君主の称号。ラテン語の皇帝の意になったカエサル(Caesar)から出た語。ツァー。ツァール。ザール。ザー。→ツァーリズム
ツァーリズム【tsarizm ロシア・czarism; tsarism イギリス】🔗⭐🔉
ツァーリズム【tsarizm ロシア・czarism; tsarism イギリス】
(ツァーリに基づく語)1917年二月革命以前のロシアの専制君主政体。ロシア特有の絶対王政。
ツァール【tsar' ロシア】🔗⭐🔉
ツァール【tsar' ロシア】
⇒ツァーリ
ツァイダム【柴達木・Tsaidam】🔗⭐🔉
ツァイダム【柴達木・Tsaidam】
中国青海省北西部にある盆地。南東部には沼沢・塩湖が多い。鉱物資源が豊富。
ツァイチェン【再見】🔗⭐🔉
ツァイチェン【再見】
(中国語)さようなら。御機嫌よう。
ツァイト【Die Zeit】🔗⭐🔉
ツァイト【Die Zeit】
(「時」の意)ドイツの週刊新聞。1946年創刊。論調はリベラル。
ツァイトガイスト【Zeitgeist ドイツ】🔗⭐🔉
ツァイトガイスト【Zeitgeist ドイツ】
時代精神。
ツァッケ【Zacke ドイツ】🔗⭐🔉
ツァッケ【Zacke ドイツ】
(尖端の意)主としてフォーク・ピッケルなどの、尖とがった先の部分。
つ‐あて【唾当て】🔗⭐🔉
つ‐あて【唾当て】
(「つ」は、つばの意)幼児のよだれかけ。
ツァラ【Tristan Tzara】🔗⭐🔉
ツァラ【Tristan Tzara】
フランスの詩人。ルーマニア生れ。ダダイスムの創始者の一人。詩集「近似的人間」など。(1896〜1963)
ツァラトゥストラ【Zarathustra】🔗⭐🔉
ツァラトゥストラ【Zarathustra】
ゾロアスター教の開祖ゾロアスターのドイツ語名。
つい【終】ツヒ🔗⭐🔉
つい【終】ツヒ
①おわり。はて。源氏物語帚木「―のたのみ所には思ひおくべかりける」。「―のすみか」
②特に、人生のおわり。死。最期さいご。源氏物語椎本「―の別れをのがれぬわざなめれど」
③(副詞的に)(→)「ついぞ」に同じ。
つい(副詞)🔗⭐🔉
つい
〔副〕
①はからず。思わず。「―過あやまって」
②時間や距離がわずかなさま。ちょっと。「―先程」「―近くまで」
③動作のすばやいさま。狂言、月見座頭「歌の一首や二首は―詠む事でおりやる」
つい(接頭)🔗⭐🔉
つい
〔接頭〕
(ツキ(突)の音便)動詞に添えて語勢を強め、また、「ちょっと」「そのまま」「突然」などの意を表す。落窪物語1「―かがまりて」。源氏物語若紫「―ゐたり」
ツイード【tweed】🔗⭐🔉
ツイード【tweed】
(→)スコッチ1に同じ。
つい・いる【つい居る】‥ヰル🔗⭐🔉
つい・いる【つい居る】‥ヰル
〔自上一〕
(ツイは接頭語)
①ひざまずく。かしこまる。源氏物語夕顔「御随身―・ゐて」
②ちょっといる。そのままにいる。源氏物語野分「端の方に―・ゐ給ひて」
つい‐いん【追院】‥ヰン🔗⭐🔉
つい‐いん【追院】‥ヰン
江戸時代、僧に科した刑の一種。犯罪の宣告を受けた僧を、居住の寺院に帰ることを許さず直ちに追放すること。いったん寺院に帰ることを許す退院より重い。
ついえ【費え・弊え・潰え】ツヒエ🔗⭐🔉
ついえ【費え・弊え・潰え】ツヒエ
(動詞ツイユの連用形から)
①くずれやぶれること。悪くなること。
②つかれ苦しむこと。弱ること。太平記37「あはれ―に乗る(弱点につけこむ)処やと思ひければ」
③かかり。費用。入費。今昔物語集7「軽物を分ちて交易するに、その―多かり」。「思わぬ―」
④無用の入費。損害。むだづかい。方丈記「七珍万宝さながら灰燼となりにき。その―いくそばくぞ」。「国家の―」
◇3・4は、ふつう「費え」と書く。
つい・える【費える・弊える・潰える】ツヒエル🔗⭐🔉
つい・える【費える・弊える・潰える】ツヒエル
〔自下一〕[文]つひ・ゆ(下二)
①へる。乏しくなる。皇極紀「損おとり―・ゆること極めて甚だし」。「貯えが―・える」
②やつれ、おとろえる。疲れる。源氏物語蓬生「年ごろいたう―・えたれど」
③くずれる。また、潰走する。〈色葉字類抄〉。「優勝の夢が―・える」
④いたずらに経過する。「無駄に一日が―・える」
◇1・4には、ふつう「費」を使う。
つい‐えん【追遠】‥ヱン🔗⭐🔉
つい‐えん【追遠】‥ヱン
[論語学而「終りを慎み遠きを追えば、民の徳厚きに帰す」]先祖の徳を追慕して心をこめて供養すること。
つい‐おう【堆黄】‥ワウ🔗⭐🔉
つい‐おう【堆黄】‥ワウ
堆朱ついしゅの一種。黄色の漆を主体とするもの。
つい‐おく【追憶】🔗⭐🔉
つい‐おく【追憶】
過ぎ去ったことを思い出すこと。追懐。「―にひたる」
ツィオルコフスキー【Konstantin Tsiolkovskii】🔗⭐🔉
ツィオルコフスキー【Konstantin Tsiolkovskii】
ロシアのロケット理論学者。独学で宇宙飛行の理論を研究。主著「ロケットの運動原理」。(1857〜1935)
つい‐か【追加】🔗⭐🔉
つい‐か【追加】
①後から増し加えること。また、その加えられたもの。
②連歌・俳諧で、千句・万句などのあとに当季の句を発句とした表一順をつけ加えること。また、そのもの。
⇒ついか‐はいとう【追加配当】
⇒ついか‐よさん【追加予算】
つい‐か【墜下】🔗⭐🔉
つい‐か【墜下】
下におちること。墜落。落下。
つい‐かい【追悔】‥クワイ🔗⭐🔉
つい‐かい【追悔】‥クワイ
事の終わった後からくやむこと。後悔。
つい‐かい【追懐】‥クワイ🔗⭐🔉
つい‐かい【追懐】‥クワイ
昔の事や人などをあとから思い出してしのぶこと。追憶。追想。「―の情」「故人を―する」
つい‐がき【築垣・築牆】🔗⭐🔉
つい‐がき【築垣・築牆】
(ツキカキの音便。ツイカキとも)(→)築地ついじに同じ。
つい‐がさね【衝重】🔗⭐🔉
つい‐がさね【衝重】
(ツキガサネの音便)神供じんぐや食器をのせるのに用いる膳具。折敷おしきの下に台をつけたもの。普通、白木を用いる。三方に穴をあけたのを三方さんぼう、四方に穴をあけたのを四方、穴をあけないのを供饗くぎょうという。
衝重
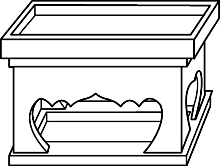
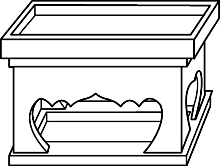
ついか‐はいとう【追加配当】‥タウ🔗⭐🔉
ついか‐はいとう【追加配当】‥タウ
破産手続で、最後の配当の通知を発した後に、新たに配当にあてるべき財産があった時に行う配当。
⇒つい‐か【追加】
ツー【two】🔗⭐🔉
ツー【two】
2。ふたつ。
広辞苑に「つ」で始まるの検索結果 1-45。もっと読み込む