複数辞典一括検索+![]()
![]()
か‐ざ【冠者】クワ‥🔗⭐🔉
か‐ざ【冠者】クワ‥
(カンザの約)(→)「かんじゃ」に同じ。源氏物語少女「―の君のおんさま」
か‐じゃ【冠者】クワ‥🔗⭐🔉
か‐じゃ【冠者】クワ‥
⇒かんじゃ。「太郎―」
かぶ‐き【冠木】🔗⭐🔉
かぶ‐き【冠木】
①門柱の上部を貫く横木。柱の頂上より少し下にある点で笠木と異なる。
②冠木門の略。
⇒かぶき‐もん【冠木門】
かぶき‐もん【冠木門】🔗⭐🔉
かぶき‐もん【冠木門】
冠木を2柱の上方に渡した屋根のない門。衡門こうもん。
冠木門
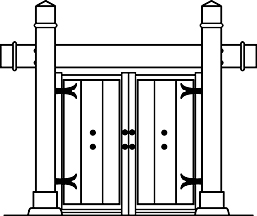 ⇒かぶ‐き【冠木】
⇒かぶ‐き【冠木】
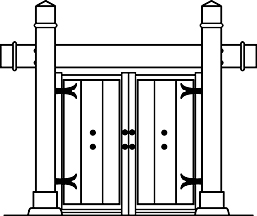 ⇒かぶ‐き【冠木】
⇒かぶ‐き【冠木】
かぶり【冠・被り】🔗⭐🔉
かぶり【冠・被り】
①かぶること。かぶるもの。「頬―」
②(→)「こうぶり」に同じ。舒明紀(図書寮本)永治点「冠位カブリ一級ひとしな」
③芝居の大入り。
④芝居の打出し。終演。
⑤写真感光材料を現像した際、画像とは関係なく、全面または部分的に生じた曇り。光線漏れ、不適当な保管・現像処理、古い材料の使用などにより生ずる。
⇒かぶり‐おけ【冠桶】
⇒かぶり‐がさ【被り笠】
⇒かぶり‐きもの【被り着物】
⇒かぶり‐の‐いた【冠の板】
⇒かぶり‐もの【被り物】
⇒かぶり‐もの【被り者】
かぶり‐おけ【冠桶】‥ヲケ🔗⭐🔉
かぶり‐おけ【冠桶】‥ヲケ
かんむりを入れる箱。冠箱かぶりばこ。
⇒かぶり【冠・被り】
かぶり‐の‐いた【冠の板】🔗⭐🔉
かぶり‐の‐いた【冠の板】
鎧よろいの袖や栴檀せんだんの板の上部の金具廻かなぐまわり。また籠手こての最も上の板。→大鎧(図)。
⇒かぶり【冠・被り】
かむり【冠】🔗⭐🔉
かむり【冠】
①⇒かんむり。
②和歌・俳諧で、第1句の5文字。
⇒かむり‐いし【冠石】
⇒かむり‐いた【冠板】
⇒かむり‐く【冠句】
⇒かむり‐ざ【冠座】
⇒かむり‐し【冠師】
⇒かむりじ‐れんが【冠字連歌】
⇒かむり‐だな【冠棚】
⇒かむり‐づけ【冠付】
かむり‐いし【冠石】🔗⭐🔉
かむり‐いた【冠板】🔗⭐🔉
かむり‐く【冠句】🔗⭐🔉
かむり‐く【冠句】
(→)冠付かむりづけに同じ。
⇒かむり【冠】
かむりじ‐れんが【冠字連歌】🔗⭐🔉
かむりじ‐れんが【冠字連歌】
連歌の一体。毎句の初めに、「いろは」など定められた各音を配ってよみこむもの。
⇒かむり【冠】
かむり‐だな【冠棚】🔗⭐🔉
かむり‐だな【冠棚】
①冠をのせて置く棚。のち、香炉や水指も置く。
②床脇の棚の一形式。
⇒かむり【冠】
かむり‐づけ【冠付】🔗⭐🔉
かむり‐づけ【冠付】
雑俳で、点者が出した句の上5字すなわち冠に対し、中7字・下5字を付けて1句とするもの。元禄(1688〜1704)頃から行われた。笠付かさづけ。烏帽子付えぼしづけ。冠句。
⇒かむり【冠】
かむ・る【被る・冠る】🔗⭐🔉
かむ・る【被る・冠る】
〔他五〕
「かぶる(被る)」に同じ。
かん【冠】クワン🔗⭐🔉
かん【冠】クワン
①かんむり。
②最もすぐれていること。首位。第一。「世界に―たり」「三―達成」
かん‐い【冠位】クワンヰ🔗⭐🔉
かん‐い【冠位】クワンヰ
冠によって表示された位階。日本では7世紀末まで、位記のような辞令でなく、朝廷でかぶるべき冠そのものを与えて身分すなわち位階を表示させた。
⇒かんい‐じゅうにかい【冠位十二階】
かんい‐じゅうにかい【冠位十二階】クワンヰジフ‥🔗⭐🔉
かんい‐じゅうにかい【冠位十二階】クワンヰジフ‥
冠位の最初のもの。603年に聖徳太子・蘇我馬子らが制定した冠による位階。冠名は儒教の徳目を参考にして徳・仁・礼・信・義・智とし、おのおのを大・小に分けて十二階とした。各冠は色(紫・青・赤・黄・白・黒)とその濃淡で区別、功労によって昇進。蘇我氏は皇室と共に授ける側にあった。
⇒かん‐い【冠位】
かん‐う【冠羽】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐う【冠羽】クワン‥
レンジャク類・ヤツガシラ・ヤマセミ・カンムリヅルなどの鳥の頭頂部に生える飾り羽。多く雄の性徴で、繁殖期にのみ見られる種もある。フクロウ類のものは羽角という。羽冠。→鳥類(図)
かん‐えい【冠纓】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐えい【冠纓】クワン‥
冠かんむりのひも。
かん‐ぎ【冠儀】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐ぎ【冠儀】クワン‥
元服の儀式。
かん‐く【冠句】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐く【冠句】クワン‥
かむりく。かむりづけ。
かん‐こん‐そう‐さい【冠婚葬祭】クワン‥サウ‥🔗⭐🔉
かん‐こん‐そう‐さい【冠婚葬祭】クワン‥サウ‥
古来の四大礼式。元服(=冠)と婚礼(=婚)と葬儀(=葬)と祖先の祭祀(=祭)のこと。
かん‐ざ【冠者】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐ざ【冠者】クワン‥
⇒かんじゃ
かん‐し【冠詞】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐し【冠詞】クワン‥
(article)英語のaやtheのように名詞の前(稀に後)に現れ、その名詞の表す事物の特定性を示す語。定冠詞ならば名詞の表す類の中の特定のものであることを、不定冠詞ならば任意のものであることを示す。
かん‐じ【冠辞】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐じ【冠辞】クワン‥
①他の語の上に付けて修飾する語。
②枕詞まくらことば。
かんじこう【冠辞考】クワン‥カウ🔗⭐🔉
かんじこう【冠辞考】クワン‥カウ
語学書。賀茂真淵著。10巻。1757年(宝暦7)刊。記紀・万葉集の枕詞326語をあげ、五十音順に配列し、その懸かる詞を記して一々出典を示し、精密な解釈をなす。
かん‐じゃ【冠者】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐じゃ【冠者】クワン‥
(カジャとも)
①元服して冠をつけた男子。今昔物語集29「元服などし…その―然るべき所に宮仕へしける程に」
②六位で無官の人。十訓抄「匡房卿いまだ無官にて、江ごう―とて有りけるを」
③わかもの。「猿面―」
④召使の若者。従者。「太郎―」
⇒かんじゃ‐ひじり【冠者聖】
かんじゃ‐ひじり【冠者聖】クワン‥🔗⭐🔉
かんじゃ‐ひじり【冠者聖】クワン‥
年若い僧。狂言、不聞座頭きかずざとう「ああ―や」
⇒かん‐じゃ【冠者】
○館舎を捐つかんしゃをすつ
[史記范雎伝・戦国策趙策](住んでいた館をすてる意から)貴人が死去することにいう。館を捐つ。捐館えんかん。
⇒かん‐しゃ【館舎】
かん‐しょう【冠省】クワンシヤウ🔗⭐🔉
かん‐しょう【冠省】クワンシヤウ
(カンセイは誤読)手紙で、時候の挨拶など前文を省略すること。また、その際に書く語。
かん‐しょう【冠称】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐しょう【冠称】クワン‥
(→)角書つのがきに同じ。
かん‐じょう【冠状】クワンジヤウ🔗⭐🔉
かん‐じょう【冠状】クワンジヤウ
冠のような形。
⇒かんじょう‐どうみゃく【冠状動脈】
かんじょう‐どうみゃく【冠状動脈】クワンジヤウ‥🔗⭐🔉
かんじょう‐どうみゃく【冠状動脈】クワンジヤウ‥
大動脈起始部から起こり心筋に血液を供給する動脈。左右2本あり、心臓の周囲を冠状に取り巻いている。この動脈の狭窄きょうさく・閉塞・痙攣けいれんは冠不全・狭心症・心筋梗塞の原因となる。冠動脈。
⇒かん‐じょう【冠状】
かん‐すい【冠水】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐すい【冠水】クワン‥
洪水などのために田畑や作物などが水をかぶること。「大水で国道が―する」
かん・する【冠する】クワン‥🔗⭐🔉
かん・する【冠する】クワン‥
〔他サ変〕[文]冠す(サ変)
①冠かんむりをかぶせる。(自動詞的に)冠をかぶる。転じて、元服する。「王冠を―・する」「沐猴もっこうにして―・す」
②修飾語・接頭語、また称号などを、上にかぶせる。「企業名を―・した試合」
かん‐せつ【冠雪】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐せつ【冠雪】クワン‥
上に雪が積もること。また、その雪。「初―」
かん‐ぜつ【冠絶】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐ぜつ【冠絶】クワン‥
とびぬけてすぐれていること。「世界に―する」
かん‐たい【冠帯】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐たい【冠帯】クワン‥
①冠と帯。
②冠をかぶり帯を結ぶ礼儀ある風俗。
かん‐たる【冠たる】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐たる【冠たる】クワン‥
〔連体〕
(多く「…に冠たる」の形で)最もすぐれた。最高と認められる。「世界に―日本の技術」
かん‐ちゅう【冠注】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐ちゅう【冠注】クワン‥
(→)頭注に同じ。
かん‐どうみゃく【冠動脈】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐どうみゃく【冠動脈】クワン‥
(→)冠状動脈に同じ。
かん‐ふぜん【冠不全】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐ふぜん【冠不全】クワン‥
心臓の冠状動脈の血行が妨げられ、心臓に十分な酸素が供給されない状態。高度のものは狭心症の発作を起こし、また、心筋梗塞の原因となる。
かん‐べん【冠冕】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐べん【冠冕】クワン‥
(「冕」は、大夫以上が朝儀に着用する冠)
①かんむり。太平記24「臣下は北面にして、階下に―を低うちたる」
②転じて、首位。第1等。
③役人づとめを指す。
かん‐ぼう【冠帽】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐ぼう【冠帽】クワン‥
頭部をおおうもの。冠は鉢巻状に額部を巻く幅広い帯状のもの、帽は袋状に頭全体にかぶせるもの。
かんぼうずえ【冠帽図会】クワン‥ヅヱ🔗⭐🔉
かんぼうずえ【冠帽図会】クワン‥ヅヱ
冕冠べんかん・宝冠・礼冠・武礼冠・三山冠など38種の冠帽を図解した書。松岡辰方ときかた著。1巻。1806年(文化3)成る。
かんむり【冠】🔗⭐🔉
かんむり【冠】
(カウブリの音便)
①頭にかぶるものの総称。こうむり。かむり。かんぶり。かがふり。かぶり。
②束帯・衣冠の時に用いたかぶりもの。礼服に用いるものはカンと音読し、冕べん冠・礼らい冠・武礼ぶらい冠などがあり、金属製。平安時代の束帯のものは令制の頭巾ときんの形式化で、黒の羅で作り漆をひいたもので、額・磯・簪かんざし・巾子こじ・纓えいなどの部分名がある。形状にも、厚額あつびたい・薄額・透額すきびたい・半透額などの種類がある。
冠
 ③漢字の部首のうち、上にかぶせるもの。「家」字の「宀」(ウ冠)、「花」字の「艹」(草冠)の類。
④競技会や催しの呼称に、スポンサー企業などの名をかぶせること。「―大会」
⑤⇒おかんむり。
⇒かんむりおとし‐づくり【冠落し造り】
⇒かんむり‐がた【冠形】
⇒かんむり‐ざ【冠座】
⇒かんむり‐し【冠師】
⇒かんむり‐した【冠下】
⇒かんむり‐だな【冠棚】
⇒かんむり‐づけ【冠付】
⇒かんむり‐づる【冠鶴】
⇒かんむり‐のうし【冠直衣】
⇒かんむり‐わし【冠鷲】
⇒冠旧けれど沓に履かず
⇒冠を挂く
⇒冠を曲げる
③漢字の部首のうち、上にかぶせるもの。「家」字の「宀」(ウ冠)、「花」字の「艹」(草冠)の類。
④競技会や催しの呼称に、スポンサー企業などの名をかぶせること。「―大会」
⑤⇒おかんむり。
⇒かんむりおとし‐づくり【冠落し造り】
⇒かんむり‐がた【冠形】
⇒かんむり‐ざ【冠座】
⇒かんむり‐し【冠師】
⇒かんむり‐した【冠下】
⇒かんむり‐だな【冠棚】
⇒かんむり‐づけ【冠付】
⇒かんむり‐づる【冠鶴】
⇒かんむり‐のうし【冠直衣】
⇒かんむり‐わし【冠鷲】
⇒冠旧けれど沓に履かず
⇒冠を挂く
⇒冠を曲げる
 ③漢字の部首のうち、上にかぶせるもの。「家」字の「宀」(ウ冠)、「花」字の「艹」(草冠)の類。
④競技会や催しの呼称に、スポンサー企業などの名をかぶせること。「―大会」
⑤⇒おかんむり。
⇒かんむりおとし‐づくり【冠落し造り】
⇒かんむり‐がた【冠形】
⇒かんむり‐ざ【冠座】
⇒かんむり‐し【冠師】
⇒かんむり‐した【冠下】
⇒かんむり‐だな【冠棚】
⇒かんむり‐づけ【冠付】
⇒かんむり‐づる【冠鶴】
⇒かんむり‐のうし【冠直衣】
⇒かんむり‐わし【冠鷲】
⇒冠旧けれど沓に履かず
⇒冠を挂く
⇒冠を曲げる
③漢字の部首のうち、上にかぶせるもの。「家」字の「宀」(ウ冠)、「花」字の「艹」(草冠)の類。
④競技会や催しの呼称に、スポンサー企業などの名をかぶせること。「―大会」
⑤⇒おかんむり。
⇒かんむりおとし‐づくり【冠落し造り】
⇒かんむり‐がた【冠形】
⇒かんむり‐ざ【冠座】
⇒かんむり‐し【冠師】
⇒かんむり‐した【冠下】
⇒かんむり‐だな【冠棚】
⇒かんむり‐づけ【冠付】
⇒かんむり‐づる【冠鶴】
⇒かんむり‐のうし【冠直衣】
⇒かんむり‐わし【冠鷲】
⇒冠旧けれど沓に履かず
⇒冠を挂く
⇒冠を曲げる
かんむり【冠】(姓氏)🔗⭐🔉
かんむり【冠】
姓氏の一つ。
⇒かんむり‐まつじろう【冠松次郎】
かんむりおとし‐づくり【冠落し造り】🔗⭐🔉
かんむりおとし‐づくり【冠落し造り】
短刀などで、刀身の先の方3分の2ほどの鎬地しのぎじを薄く削り取った形の造り。横手3のないものを「鵜の頸造り」といい、区別することがある。
⇒かんむり【冠】
かんむり‐がた【冠形】🔗⭐🔉
かんむり‐がた【冠形】
仮面の上端に、冠・烏帽子えぼし等の下端の形を墨で描くか彫り出すかした部分。
⇒かんむり【冠】
かんむり‐ざ【冠座】🔗⭐🔉
かんむり‐ざ【冠座】
(Corona Borealis ラテン)ヘルクレス座と牛飼座の間にある星座。7星が半円形に並んで美しい冠の形をなす。7月中旬の夕刻に天頂にくる。
⇒かんむり【冠】
かんむり‐し【冠師】🔗⭐🔉
かんむり‐し【冠師】
冠を作ることを業とする人。
⇒かんむり【冠】
かんむり‐した【冠下】🔗⭐🔉
かんむり‐した【冠下】
公卿などが冠の下に結った髻もとどり。頭髪を後頭部で棒の形に紐で巻き立て、先端を房にして出したもの。巻立て。かむりした。
⇒かんむり【冠】
かんむり‐だな【冠棚】🔗⭐🔉
かんむり‐づけ【冠付】🔗⭐🔉
かんむり‐づる【冠鶴】🔗⭐🔉
かんむり‐づる【冠鶴】
ツルの一種。体色はほぼねずみ色で、頭頂に黄色の球状の冠羽がある。アフリカに分布し、そのうち東・南アフリカ産のものはホオジロカンムリヅルと呼ばれる。
カンムリヅル
撮影:小宮輝之
 ⇒かんむり【冠】
⇒かんむり【冠】
 ⇒かんむり【冠】
⇒かんむり【冠】
○冠旧けれど沓に履かずかんむりふるけれどくつにはかず🔗⭐🔉
○冠旧けれど沓に履かずかんむりふるけれどくつにはかず
[韓非子外儲説左下]上下・貴賤の別は乱すことができないの意。
⇒かんむり【冠】
かんむり‐まつじろう【冠松次郎】‥ラウ
登山家。東京生れ。黒部渓谷を踏査し、その美を紹介。著「黒部渓谷」など。(1883〜1970)
⇒かんむり【冠】
かん‐むりょう【感無量】‥リヤウ
(→)感慨無量に同じ。
かんむりょうじゅ‐きょう【観無量寿経】クワン‥リヤウ‥キヤウ
浄土三部経の一つ。西域の畺良耶舎きょうりょうやしゃの訳。1巻。釈尊が韋提希夫人いだいけぶにんに阿弥陀仏とその浄土の荘厳を説いたもの。観無量寿仏経。観経。→十六観。
⇒かんむりょうじゅきょう‐しょ【観無量寿経疏】
かんむりょうじゅきょう‐しょ【観無量寿経疏】クワン‥リヤウ‥キヤウ‥
仏書。唐僧、善導の著。4巻。観経四帖疏・観経疏ともいう。観無量寿経の注釈書で、本願念仏による浄土往生を説き、法然にも大きな影響を与えた。
⇒かんむりょうじゅ‐きょう【観無量寿経】
かんむり‐わし【冠鷲】
タカ目タカ科の一種。全長約55センチメートル。成鳥は全体に濃褐色で胸から腹に小さい白斑がある。頭頂は黒色で、白黒まだらの長い冠羽が伸びる。東南アジアに広く分布、日本では琉球諸島南部に分布。森林性でヘビやカエル、その他の小動物を食べる。特別天然記念物。
カンムリワシ(1)
提供:OPO
 カンムリワシ(2)
撮影:小宮輝之
カンムリワシ(2)
撮影:小宮輝之
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
⇒かんむり【冠】
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
⇒かんむり【冠】
 カンムリワシ(2)
撮影:小宮輝之
カンムリワシ(2)
撮影:小宮輝之
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
⇒かんむり【冠】
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
⇒かんむり【冠】
かんむり‐まつじろう【冠松次郎】‥ラウ🔗⭐🔉
かんむり‐まつじろう【冠松次郎】‥ラウ
登山家。東京生れ。黒部渓谷を踏査し、その美を紹介。著「黒部渓谷」など。(1883〜1970)
⇒かんむり【冠】
かんむり‐わし【冠鷲】🔗⭐🔉
○冠を挂くかんむりをかく🔗⭐🔉
○冠を曲げるかんむりをまげる🔗⭐🔉
○冠を曲げるかんむりをまげる
機嫌を悪くする。
⇒かんむり【冠】
かん‐め【貫目】クワン‥
①めかた。
②尺貫法の目方の単位。貫。
③身に備わる威厳。貫禄。
⇒かんめ‐あらため‐しょ【貫目改所】
⇒かんめ‐づつ【貫目筒】
かんめ‐あらため‐しょ【貫目改所】クワン‥
江戸時代、荷物の重量を検査するため、幕府が五街道の問屋場に置いた施設。
⇒かん‐め【貫目】
かん‐めい【官名】クワン‥
官職の名称。
かん‐めい【官命】クワン‥
官府の命令。
かん‐めい【感銘・肝銘】
心に刻みつけて忘れないこと。また、忘れられないほど深く感動すること。「―を受ける」
かん‐めい【漢名】
(カンミョウとも)中国での名称。ハゲイトウを「雁来紅」という類。からな。→和名
かん‐めい【簡明】
簡単ではっきりしていること。簡単明瞭。「―に記す」「―な返答」
がん‐めい【頑迷】グワン‥
かたくなで正しい判断ができないこと。「―な人」
⇒がんめい‐ころう【頑迷固陋】
がん‐めい【頑冥】グワン‥
かたくなで物事の道理にくらいこと。「―な男」
⇒がんめい‐ふれい【頑冥不霊】
がんめい‐ころう【頑迷固陋】グワン‥
自分の考えや古い習慣にかたくなに執着し、新しい時代に合った判断ができないこと。
⇒がん‐めい【頑迷】
がんめい‐ふれい【頑冥不霊】グワン‥
頑冥で無知なこと。
⇒がん‐めい【頑冥】
ガン‐メタル【gun-metal】
(→)砲金ほうきん。
かんめ‐づつ【貫目筒】クワン‥
嘉永(1848〜1854)年間、日本で鋳造した円筒形の火砲。弾丸の重量により百目玉筒・五貫目玉筒などといった。
⇒かん‐め【貫目】
かん‐めん【乾麺】
ほした麺類めんるい。干しうどん・そうめんなど。
がん‐めん【岩綿】
(rock wool)高温で溶融したケイ酸塩を強風で空気中に吹きとばして作った綿状のもの。断熱材・吸音材などに用いる。
がん‐めん【顔面】
顔。おもて。「―を強打する」
⇒がんめん‐かく【顔面角】
⇒がんめん‐きん【顔面筋】
⇒がんめん‐こつ【顔面骨】
⇒がんめん‐しんけい【顔面神経】
⇒がんめん‐しんけいつう【顔面神経痛】
⇒がんめん‐しんけい‐まひ【顔面神経麻痺】
がん‐めん【願面】グワン‥
願書の文面。
がんめん‐かく【顔面角】
口辺部の前方突出の度合を示す角度。すなわち耳眼面(左右の外耳孔上縁と左の眼窩下縁とを通る平面)が顔の前面となす角。18〜19世紀の人種学で人種を分類するために用いられた。
⇒がん‐めん【顔面】
がんめん‐きん【顔面筋】
(→)表情筋に同じ。
⇒がん‐めん【顔面】
がんめん‐こつ【顔面骨】
顔面を形成する骨の総称。
⇒がん‐めん【顔面】
がんめん‐しんけい【顔面神経】
橋きょうの後縁から出て顔の皮膚を動かす表情筋を支配する運動神経。そのほか、唾液・涙の分泌および味覚をつかさどる神経線維をも含む。第7脳神経。
⇒がん‐めん【顔面】
がんめん‐しんけいつう【顔面神経痛】
(→)三叉さんさ神経痛の俗称。
⇒がん‐めん【顔面】
がんめん‐しんけい‐まひ【顔面神経麻痺】
顔面神経の麻痺。中枢性と末梢性があり、前者は脳出血・脳梗塞など脳の病変により、後者はウイルス・寒冷・リウマチ性・外傷・耳や脳底の疾患によって起こる。顔の片側または両側がゆがみ、皺しわを作ることができず、口角が下がり、眼は広く開いて閉じることが不可能になり、咀嚼そしゃくがしにくくなるなどの症状を呈する。
⇒がん‐めん【顔面】
かんめん‐ぞう【完面像】クワン‥ザウ
一つの結晶系に属する結晶のなかで、最も複雑な対称性をもつもの。
かん‐めんぽう【乾麺麭】‥パウ
旧日本陸軍で、乾パンのこと。
がん‐も
「がんもどき(雁擬き)」の略。
かん‐もう【冠毛】クワン‥
萼がくの一型で、毛状となったもの。風を受けて種子の散布の用をなす。タンポポ・アザミなどの果実等に見られる。
かん‐もう【換毛】クワン‥
毛がぬけかわること。人間や一部の家畜では絶えず行われるが、他の哺乳類では毎年一定期に毛衣もうい全体の更新が行われるものが多い。
かん‐もう【寛猛】クワンマウ
ゆるやかなことときびしいこと。寛厳。
⇒寛猛相済う
がん‐もう【頑蒙】グワン‥
かたくなで事理にくらいこと。頑冥。
がん‐もう【願望】グワンマウ
(モウは呉音)
⇒がんぼう
かん‐もう【冠毛】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐もう【冠毛】クワン‥
萼がくの一型で、毛状となったもの。風を受けて種子の散布の用をなす。タンポポ・アザミなどの果実等に見られる。
かん‐り【冠履】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐り【冠履】クワン‥
かんむりとくつ。転じて、上位と下位。尊卑。日葡辞書「クヮンリザウ(蔵)ヲヲナジウセズ」
⇒かんり‐てんとう【冠履顛倒】
かんり‐てんとう【冠履顛倒】クワン‥タウ🔗⭐🔉
かんり‐てんとう【冠履顛倒】クワン‥タウ
上下の順序が逆なこと。
⇒かん‐り【冠履】
かん‐れい【冠礼】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐れい【冠礼】クワン‥
加冠の礼式。元服の式。
こうぶり【冠】カウブリ🔗⭐🔉
こうぶり【冠】カウブリ
(カガフリの音便)
①かんむり。源氏物語紅葉賀「―などうちゆがめて」
②位階。敏達紀「高き爵こうぶりを賜はらむ」
③特に、五位に叙せられること。叙爵。源氏物語若紫「蔵人より今年―得たるなりけり」
④元服してはじめて冠をつけること。ういこうぶり。仲哀紀「朕未だ―に逮いたらずして」
⑤年爵ねんしゃく。栄華物語玉の村菊「上の御前の…よろづのつかさ―を得させ給ひなどして」
⇒こうぶり‐のうし【冠直衣】
⇒こうぶり‐の‐お【冠の緒】
⇒冠を掛く
○冠を掛くこうぶりをかく🔗⭐🔉
○冠を掛くこうぶりをかく
(「挂冠かいかん」の訓読語)官を辞する。源氏物語若菜下「年ふかき身のかうぶりを掛けむ、何か惜しからむ」→挂冠
⇒こうぶり【冠】
こうぶ・る【被る】カウブル
〔他四〕
(カガフルの音便)
⇒こうむる。土佐日記「神仏の恵み―・れるに似たり」
こう‐ふん【口吻】
①口さき。くちばし。
②くちぶり。言いぶり。「恐怖もさめやらぬ―」
⇒口吻を洩らす
こう‐ふん【公憤】
正義感から発する、公の事に関するいきどおり。「―にかられる」「―を覚える」↔私憤
こう‐ふん【昂奮・亢奮】カウ‥
感情のたかぶること。興奮。
こう‐ふん【紅粉】
べにとおしろい。脂粉。化粧。
こう‐ふん【荒墳】クワウ‥
あれはてた墓。
こう‐ふん【香粉】カウ‥
①香りのよいおしろい。転じて、化粧品。
②香料とおしろい。
③花粉。
こう‐ふん【黄吻】クワウ‥
(→)黄口こうこうに同じ。
こう‐ふん【興奮】
①感情の高まること。「―のあまり眠れない」
②〔生〕刺激によって細胞や生体が休止状態から活動状態へ変化すること。感覚細胞や神経細胞では、活動電位が発生することと同じ。個々の細胞の興奮は、物質代謝の変化、筋収縮、分泌などを伴い、全身的な活動状態へと導かれる。
③精神活動がある限度をこえること。精神病者や飲酒の際などに見られるもの。
⇒こうふん‐ざい【興奮剤】
こう‐ぶん【公文】
公儀の文書。政府や諸官庁の発布した文書。「交換―」
こう‐ぶん【行文】カウ‥
文章の筆のはこび方。「―流麗」
こう‐ぶん【告文】カウ‥
⇒こうもん
こう‐ぶん【後聞】
後日のうわさ・評判。源平盛衰記38「定めて―に其れ隠れ無く候はんか」
こう‐ぶん【高文】カウ‥
高等文官試験の略称。→高等文官試験
こう‐ぶん【高聞】カウ‥
他人が聞いてくれることを敬意をこめていう語。「―に達する」
こう‐ぶん【構文】
文章の構成。文のくみたて。
⇒こうぶん‐ろん【構文論】
ごう‐ぶん【合文】ガフ‥
(→)重文じゅうぶん1に同じ。
こうぶん‐いん【弘文院】‥ヰン
和気清麻呂の子広世が、父の志を継いで9世紀初頭に私宅を教育施設としたもの。
こうぶん‐かん【弘文館】‥クワン
①唐代の学校。始め昭文館、時には修文館と称した。皇族・外戚・高官の子弟を収容。
②江戸初期の林家の学問所。1630年(寛永7)林羅山が将軍家光から上野忍ヶ岡の敷地を給せられて創建した書院が起源。林春斎が徳川家から受けた弘文館学士の称が命名の由来。後の昌平黌しょうへいこうの基礎。
こうぶんこ【広文庫】クワウ‥
百科史料事典の一つ。物集もずめ高見編。20冊。1916〜18年(大正5〜7)刊。和漢書・仏書中から五万余項目の関連記事を抄出して五十音順に配列。
こうふん‐ざい【興奮剤】
脳を興奮させる薬剤。カフェイン・カンフルなど。
⇒こう‐ふん【興奮】
こう‐ぶんし【高分子】カウ‥
分子量の大きい分子。すなわち、高分子化合物の分子。巨大分子。
⇒こうぶんし‐かがく【高分子化学】
⇒こうぶんし‐かごうぶつ【高分子化合物】
こうぶんし‐かがく【高分子化学】カウ‥クワ‥
高分子化合物の合成・反応・構造・物性(固体および溶液)などを研究する化学の一部門。
⇒こう‐ぶんし【高分子】
こうぶんし‐かごうぶつ【高分子化合物】カウ‥クワガフ‥
分子量の大きい化合物の総称。天然の澱粉・セルロース・蛋白質・ゴムなどのほか、合成ゴム・合成繊維・合成樹脂(プラスチック)など。
⇒こう‐ぶんし【高分子】
こう‐ぶんしょ【公文書】
国または地方公共団体の機関、または公務員がその職務上作成した文書。その偽造および変造によって公文書偽造罪が成立する。公書。↔私文書
こうぶん‐てい【好文亭】カウ‥
水戸市偕楽園にある亭。江戸後期、藩主徳川斉昭の創建。再度焼失したが、そのつど復元。
こうぶん‐てい【孝文帝】カウ‥
北魏第6代の皇帝。高祖。名は宏。拓跋たくばつ氏。均田法・三長制を施行。中国化政策をとり、平城から洛陽に遷都。鮮卑人と漢人の通婚を奨励。(在位471〜499)(467〜499)
こうぶん‐てんのう【弘文天皇】‥ワウ
大友皇子の諡号しごう。→天皇(表)
こう‐ぶんぼ【公分母】
〔数〕二つ以上の分数を、分母が同一である分数として表すときの分母。
こうぶん‐ぼく【好文木】カウ‥
梅の異称。十訓抄「帝、文を好み給ひければ開き、学問怠り給へば散りしをれける梅は有りける。―とぞいひける」
こうぶん‐ろん【構文論】
(シンタックスの訳語)(→)統語論に同じ。
⇒こう‐ぶん【構文】
さか【冠】🔗⭐🔉
さか【冠】
とさか。鶏冠。天武紀下「その―海石榴つばきの華の似ごとし」
[漢]冠🔗⭐🔉
冠 字形
 筆順
筆順
 〔冖部7画/9画/常用/2007・3427〕
〔音〕カン〈クヮン〉(呉)(漢)
〔訓〕かんむり・かぶる
[意味]
①かんむり(をかぶる)。「王冠・衣冠・月桂げっけい冠・冠位」「沐猴もっこうにして冠す」(→沐猴(成句))
②成年となる。元服。「冠婚葬祭・弱冠」▶昔、中国では、男子は二十歳で成人式を挙げ、かんむりをつけた。
③上にかぶせる。かぶる。「題名に角書つのがきを冠する」「冠詞・冠水」
④首位。第一等。「世界に冠たれ」「冠絶」
[解字]
形声。「冖」(=おおい)+「寸」(=手)+音符「元」(=あたま)。かんむりを手で頭にのせる意。
[下ツキ
衣冠・栄冠・王冠・加冠・花冠・極冠・金冠・荊冠・挂冠・桂冠・鶏冠・月桂冠・弱冠・戴冠・宝冠・無冠
〔冖部7画/9画/常用/2007・3427〕
〔音〕カン〈クヮン〉(呉)(漢)
〔訓〕かんむり・かぶる
[意味]
①かんむり(をかぶる)。「王冠・衣冠・月桂げっけい冠・冠位」「沐猴もっこうにして冠す」(→沐猴(成句))
②成年となる。元服。「冠婚葬祭・弱冠」▶昔、中国では、男子は二十歳で成人式を挙げ、かんむりをつけた。
③上にかぶせる。かぶる。「題名に角書つのがきを冠する」「冠詞・冠水」
④首位。第一等。「世界に冠たれ」「冠絶」
[解字]
形声。「冖」(=おおい)+「寸」(=手)+音符「元」(=あたま)。かんむりを手で頭にのせる意。
[下ツキ
衣冠・栄冠・王冠・加冠・花冠・極冠・金冠・荊冠・挂冠・桂冠・鶏冠・月桂冠・弱冠・戴冠・宝冠・無冠
 筆順
筆順
 〔冖部7画/9画/常用/2007・3427〕
〔音〕カン〈クヮン〉(呉)(漢)
〔訓〕かんむり・かぶる
[意味]
①かんむり(をかぶる)。「王冠・衣冠・月桂げっけい冠・冠位」「沐猴もっこうにして冠す」(→沐猴(成句))
②成年となる。元服。「冠婚葬祭・弱冠」▶昔、中国では、男子は二十歳で成人式を挙げ、かんむりをつけた。
③上にかぶせる。かぶる。「題名に角書つのがきを冠する」「冠詞・冠水」
④首位。第一等。「世界に冠たれ」「冠絶」
[解字]
形声。「冖」(=おおい)+「寸」(=手)+音符「元」(=あたま)。かんむりを手で頭にのせる意。
[下ツキ
衣冠・栄冠・王冠・加冠・花冠・極冠・金冠・荊冠・挂冠・桂冠・鶏冠・月桂冠・弱冠・戴冠・宝冠・無冠
〔冖部7画/9画/常用/2007・3427〕
〔音〕カン〈クヮン〉(呉)(漢)
〔訓〕かんむり・かぶる
[意味]
①かんむり(をかぶる)。「王冠・衣冠・月桂げっけい冠・冠位」「沐猴もっこうにして冠す」(→沐猴(成句))
②成年となる。元服。「冠婚葬祭・弱冠」▶昔、中国では、男子は二十歳で成人式を挙げ、かんむりをつけた。
③上にかぶせる。かぶる。「題名に角書つのがきを冠する」「冠詞・冠水」
④首位。第一等。「世界に冠たれ」「冠絶」
[解字]
形声。「冖」(=おおい)+「寸」(=手)+音符「元」(=あたま)。かんむりを手で頭にのせる意。
[下ツキ
衣冠・栄冠・王冠・加冠・花冠・極冠・金冠・荊冠・挂冠・桂冠・鶏冠・月桂冠・弱冠・戴冠・宝冠・無冠
広辞苑に「冠」で始まるの検索結果 1-75。