複数辞典一括検索+![]()
![]()
○金言耳に逆らうきんげんみみにさからう🔗⭐🔉
○金言耳に逆らうきんげんみみにさからう
金言は正しく立派すぎて、ややもすれば人の感情をそこない聞き入れられない。
⇒きん‐げん【金言】
きん‐こ【今古】
今と昔。古今。
きん‐こ【光参・金海鼠】
キンコ目(樹手類)のナマコ。長楕円形で、長さは15〜20センチメートル。背面は平らで、腹面は強く湾曲。体色は灰褐色が普通。三陸地方から北海道・千島・サハリンに産し、煮干しにして食用。冬が旬しゅん。昔から陸前(宮城県)金華山沖産が賞味された。フジコ。〈[季]冬〉
きんこ
 キンコ
提供:東京動物園協会
キンコ
提供:東京動物園協会
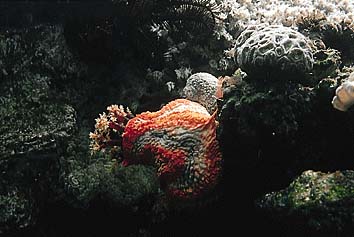 ジイガセキンコの仲間
提供:東京動物園協会
ジイガセキンコの仲間
提供:東京動物園協会
 きん‐こ【近古】
日本史の時代区分の一つ。鎌倉・室町時代を指す。
きん‐こ【金庫】
①金銀財宝を入れておく倉庫。かねぐら。「―番」
②金銭その他重要書類をおさめ、盗難や火難を防ぐための鉄製の箱。
③国または地方公共団体の現金出納機関。国庫金の出納者としての日本銀行の類。
④特別法によって設立された特殊金融機関の名称。例えば農林中央金庫・労働金庫など。
⇒きんこ‐かぶ【金庫株】
⇒きんこ‐やぶり【金庫破り】
きん‐こ【金粉】
①黄金の粉末。金砂きんしゃ。きんぷん。
②ばくちに用いる一種の采さい。穴をあけて中に金粉を入れ、その重量によって、必ず定まった目の出るように作ったいかさまもの。
きん‐こ【金鼓】
①陣鉦じんがねと陣太鼓。陣中の号令に用いるもの。
②鉦または鉦鼓しょうこ。
③⇒こんく
きん‐こ【禁錮・禁固】
①[漢書貢禹伝「皆禁錮して吏為たるを得ず」]仕官の途をふさぎとめて仕えさせないこと。
②[後漢書党錮伝「其れ位に在る者は官を免じ禁錮す」]一室内に閉じ籠めて外出を禁ずること。
③自由刑の一つ。刑務所に拘置するだけで定役には服させない刑。無期と有期(1カ月以上20年以内)とがあり、有期は30年まで加重、1カ月未満に減軽できる。
きんご
①カルタばくちの一つ。手の札とめくり札と合わせて15またはそれに最も近い数を勝ちとする。
②(→)囲かこい女郎に同じ。
きん‐ご【金吾】
(漢代に宮門の警衛をつかさどった武官である執金吾の略)衛門府の唐名。また、衛門督えもんのかみの称。
⇒きんご‐こうい【金吾校尉】
⇒きんご‐じしょう【金吾次将】
⇒きんご‐しょうぐん【金吾将軍】
ぎん‐こ【銀狐】
⇒ぎんぎつね
ぎん‐こ【銀粉】
銀の粉末。銀砂。ぎんぷん。
ギンゴイテス【Ginkgoites ラテン】
絶滅したイチョウ類の一つ。葉は現在のイチョウに似、高さ30メートルに達する。世界各地の三畳紀〜白亜前期の地層から出土。
きん‐こう【均衡】‥カウ
(「衡」は、はかりのさお、の意)二つ以上の物・事の間に、つりあいが取れていること。つりあい。平衡。平均。「―を保つ」「―が破れる」
⇒きんこう‐よさん【均衡予算】
⇒きんこう‐りろん【均衡理論】
きん‐こう【近郊】‥カウ
都市に近い郊外。「―の住宅地」
⇒きんこう‐のうぎょう【近郊農業】
きん‐こう【欣幸】‥カウ
よろこび、しあわせに思うこと。
きん‐こう【金口】
①器物の口部を金属で作ったもの。
②〔仏〕
⇒こんく。
③よい言葉を出す口。立派な言葉。また、他人の言葉の尊敬語。
⇒きんこう‐もくぜつ【金口木舌】
きん‐こう【金工】
金属に細工を施す美術工芸。また、その職人。金匠。
きん‐こう【金光】‥クワウ
黄金の光。金色の光。
きん‐こう【金坑】‥カウ
金を採掘するために掘った穴。また、金鉱、金山。
きん‐こう【金鉱】‥クワウ
金を含有する鉱石。また、それを埋蔵している鉱山。
きん‐こう【金膏】‥カウ
こがね色の口紅。高貴な化粧品。太平記37「瓊粉けいふん―の仮なる色を事とせん」
きん‐こう【勤功】
勤務上の功労。
きん‐こう【欽仰】‥カウ
(キンゴウとも)
⇒きんぎょう
きん‐こう【噤口】
口をつぐむこと。ものを言わないこと。
きんこう【錦江】‥カウ
①(Kŭm-gang)韓国全羅北道長水郡に発源し、湖南平野北部を流れて黄海に入る川。全長400キロメートル。クムガン。古名、白村江はくそんこう。
②(Jin Jiang)中国江西省北西部を流れ、新建県の南で贛かん江に注ぐ川。全長280キロメートル。
きん‐こう【謹厚】
つつしみ深くて温厚なこと。枕草子8「いと―なるものを」
きん‐ごう【近郷】‥ガウ
近くの村。また、都市に近い村里。近在。
⇒きんごう‐きんざい【近郷近在】
ぎん‐こう【吟行】‥カウ
①詩歌をうたいながら歩くこと。
②作句・作歌などのため、同好者が野外や名所旧跡に出かけて行くこと。
ぎん‐こう【銀光】‥クワウ
銀色の光。
ぎん‐こう【銀行】‥カウ
(bank)
①一方で貯蓄者から預金を預かり、他方で貸付・手形割引および証券の引受けなどを業務とする金融機関。普通銀行(都市銀行・地方銀行など)と特殊銀行(日本銀行・日本政策投資銀行など)に分かれる。石川啄木、書簡「生れて初めて―に金をとりにゆく新経験に御座候」
②比喩的に、貴重なものを確保・保管し、求めに応じてそれを供給する組織。「血液―」「人材―」
⇒ぎんこう‐いん【銀行印】
⇒ぎんこう‐か【銀行家】
⇒ぎんこう‐かわせ【銀行為替】
⇒ぎんこう‐きょうこう【銀行恐慌】
⇒ぎんこう‐けん【銀行券】
⇒ぎんこう‐こぎって【銀行小切手】
⇒ぎんこう‐しゅぎ【銀行主義】
⇒ぎんこう‐じゅんびきん【銀行準備金】
⇒ぎんこう‐しんよう【銀行信用】
⇒ぎんこう‐てがた【銀行手形】
⇒ぎんこう‐ほう【銀行法】
⇒ぎんこう‐ぼき【銀行簿記】
⇒ぎんこう‐わりびき【銀行割引】
ぎん‐こう【銀坑】‥カウ
銀を採掘するために掘った穴。また、銀鉱・銀山。
ぎん‐こう【銀鉱】‥クワウ
銀を含有する鉱石。また、それを埋蔵している鉱山。
濃紅銀鉱
撮影:松原 聰
きん‐こ【近古】
日本史の時代区分の一つ。鎌倉・室町時代を指す。
きん‐こ【金庫】
①金銀財宝を入れておく倉庫。かねぐら。「―番」
②金銭その他重要書類をおさめ、盗難や火難を防ぐための鉄製の箱。
③国または地方公共団体の現金出納機関。国庫金の出納者としての日本銀行の類。
④特別法によって設立された特殊金融機関の名称。例えば農林中央金庫・労働金庫など。
⇒きんこ‐かぶ【金庫株】
⇒きんこ‐やぶり【金庫破り】
きん‐こ【金粉】
①黄金の粉末。金砂きんしゃ。きんぷん。
②ばくちに用いる一種の采さい。穴をあけて中に金粉を入れ、その重量によって、必ず定まった目の出るように作ったいかさまもの。
きん‐こ【金鼓】
①陣鉦じんがねと陣太鼓。陣中の号令に用いるもの。
②鉦または鉦鼓しょうこ。
③⇒こんく
きん‐こ【禁錮・禁固】
①[漢書貢禹伝「皆禁錮して吏為たるを得ず」]仕官の途をふさぎとめて仕えさせないこと。
②[後漢書党錮伝「其れ位に在る者は官を免じ禁錮す」]一室内に閉じ籠めて外出を禁ずること。
③自由刑の一つ。刑務所に拘置するだけで定役には服させない刑。無期と有期(1カ月以上20年以内)とがあり、有期は30年まで加重、1カ月未満に減軽できる。
きんご
①カルタばくちの一つ。手の札とめくり札と合わせて15またはそれに最も近い数を勝ちとする。
②(→)囲かこい女郎に同じ。
きん‐ご【金吾】
(漢代に宮門の警衛をつかさどった武官である執金吾の略)衛門府の唐名。また、衛門督えもんのかみの称。
⇒きんご‐こうい【金吾校尉】
⇒きんご‐じしょう【金吾次将】
⇒きんご‐しょうぐん【金吾将軍】
ぎん‐こ【銀狐】
⇒ぎんぎつね
ぎん‐こ【銀粉】
銀の粉末。銀砂。ぎんぷん。
ギンゴイテス【Ginkgoites ラテン】
絶滅したイチョウ類の一つ。葉は現在のイチョウに似、高さ30メートルに達する。世界各地の三畳紀〜白亜前期の地層から出土。
きん‐こう【均衡】‥カウ
(「衡」は、はかりのさお、の意)二つ以上の物・事の間に、つりあいが取れていること。つりあい。平衡。平均。「―を保つ」「―が破れる」
⇒きんこう‐よさん【均衡予算】
⇒きんこう‐りろん【均衡理論】
きん‐こう【近郊】‥カウ
都市に近い郊外。「―の住宅地」
⇒きんこう‐のうぎょう【近郊農業】
きん‐こう【欣幸】‥カウ
よろこび、しあわせに思うこと。
きん‐こう【金口】
①器物の口部を金属で作ったもの。
②〔仏〕
⇒こんく。
③よい言葉を出す口。立派な言葉。また、他人の言葉の尊敬語。
⇒きんこう‐もくぜつ【金口木舌】
きん‐こう【金工】
金属に細工を施す美術工芸。また、その職人。金匠。
きん‐こう【金光】‥クワウ
黄金の光。金色の光。
きん‐こう【金坑】‥カウ
金を採掘するために掘った穴。また、金鉱、金山。
きん‐こう【金鉱】‥クワウ
金を含有する鉱石。また、それを埋蔵している鉱山。
きん‐こう【金膏】‥カウ
こがね色の口紅。高貴な化粧品。太平記37「瓊粉けいふん―の仮なる色を事とせん」
きん‐こう【勤功】
勤務上の功労。
きん‐こう【欽仰】‥カウ
(キンゴウとも)
⇒きんぎょう
きん‐こう【噤口】
口をつぐむこと。ものを言わないこと。
きんこう【錦江】‥カウ
①(Kŭm-gang)韓国全羅北道長水郡に発源し、湖南平野北部を流れて黄海に入る川。全長400キロメートル。クムガン。古名、白村江はくそんこう。
②(Jin Jiang)中国江西省北西部を流れ、新建県の南で贛かん江に注ぐ川。全長280キロメートル。
きん‐こう【謹厚】
つつしみ深くて温厚なこと。枕草子8「いと―なるものを」
きん‐ごう【近郷】‥ガウ
近くの村。また、都市に近い村里。近在。
⇒きんごう‐きんざい【近郷近在】
ぎん‐こう【吟行】‥カウ
①詩歌をうたいながら歩くこと。
②作句・作歌などのため、同好者が野外や名所旧跡に出かけて行くこと。
ぎん‐こう【銀光】‥クワウ
銀色の光。
ぎん‐こう【銀行】‥カウ
(bank)
①一方で貯蓄者から預金を預かり、他方で貸付・手形割引および証券の引受けなどを業務とする金融機関。普通銀行(都市銀行・地方銀行など)と特殊銀行(日本銀行・日本政策投資銀行など)に分かれる。石川啄木、書簡「生れて初めて―に金をとりにゆく新経験に御座候」
②比喩的に、貴重なものを確保・保管し、求めに応じてそれを供給する組織。「血液―」「人材―」
⇒ぎんこう‐いん【銀行印】
⇒ぎんこう‐か【銀行家】
⇒ぎんこう‐かわせ【銀行為替】
⇒ぎんこう‐きょうこう【銀行恐慌】
⇒ぎんこう‐けん【銀行券】
⇒ぎんこう‐こぎって【銀行小切手】
⇒ぎんこう‐しゅぎ【銀行主義】
⇒ぎんこう‐じゅんびきん【銀行準備金】
⇒ぎんこう‐しんよう【銀行信用】
⇒ぎんこう‐てがた【銀行手形】
⇒ぎんこう‐ほう【銀行法】
⇒ぎんこう‐ぼき【銀行簿記】
⇒ぎんこう‐わりびき【銀行割引】
ぎん‐こう【銀坑】‥カウ
銀を採掘するために掘った穴。また、銀鉱・銀山。
ぎん‐こう【銀鉱】‥クワウ
銀を含有する鉱石。また、それを埋蔵している鉱山。
濃紅銀鉱
撮影:松原 聰
 ぎん‐こう【銀鉤】
①銀製の針。銀製の、すだれのかけがね。
②力強い草書の形容。
③三日月の形容。
ぎん‐ごう【銀号】‥ガウ
中国で、銀行の称。特に、旧式の両替店風の小規模な金融機関。
ぎんこう‐いん【銀行印】‥カウ‥
銀行との取引きに使用する印章。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐か【金紅花】‥クワ
ユリ科の多年草。高山の湿原に群生。高さ約20センチメートル。葉は剣状。8月頃、星形6弁の小黄色花を総状に密生。金光花。
ぎんこう‐か【銀行家】‥カウ‥
銀行業を営む者。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐かわせ【銀行為替】‥カウカハセ
銀行で取り扱う送金方法。為替手形によるもの、電信送金為替、当座振込などがある。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐きょうこう【銀行恐慌】‥カウ‥クワウ
恐慌状態が甚だしくなって銀行が取付けをうけ、預金引出しに応じられなくなり、銀行の破産が続出する状態。→金融恐慌。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんごう‐きんざい【近郷近在】‥ガウ‥
近くのすべての村。「―に名をとどろかす」
⇒きん‐ごう【近郷】
きんこう‐けい【近交系】‥カウ‥
(近交は、近親交配の意)実験動物で、兄妹交配を20代以上続けることで得られる系統。一組の両親にさかのぼることができる。全遺伝子座のうちホモである割合を近交系数という。
ぎんこう‐けん【銀行券】‥カウ‥
発券銀行(日本銀行・イングランド銀行など)の発行する紙幣で、代表的な現金通貨。本来、兌換だかん銀行券であったが、金本位制から管理通貨制度への移行とともに、いずれの国でも不換銀行券となっている。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐けんがく【勤工倹学】
労働しながら勉強すること。第一次大戦期、周恩来・鄧小平など多くの中国青年がこの方法により、フランスなどで学んだ。
ぎんこう‐こぎって【銀行小切手】‥カウ‥
銀行の預金者から銀行に宛てて振り出される支払の委託書。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐しゅぎ【銀行主義】‥カウ‥
銀行券の発行に際し、正貨準備などの制限を設けず、自由に発行させても、兌換だかんが維持される限り、貨幣は決して過度に流通せず、物価は騰貴しないとする説。19世紀の初め、イギリスで唱えられた。↔通貨主義。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐じゅんびきん【銀行準備金】‥カウ‥
市中銀行が預金の支払いに備えて保有している資金。支払準備金。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐しんよう【銀行信用】‥カウ‥
銀行がその取引先に対して与える信用。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐せき【金紅石】
酸化チタンから成る鉱物。正方晶系、柱状結晶。赤褐色または黄赤色で、花崗岩・片麻へんま岩などの中に存する。ルチル。
きんこう‐せんにん【琴高仙人】‥カウ‥
(画題)中国、周代の仙人。琴の名手で、仙術を使い、鯉に乗って現れるという。
きんこうたい‐しょう【菌交代症】‥カウ‥シヤウ
抗生物質などの使用により、生体内に常在する菌種が減少・死滅し、それに代わって常時は少ない菌または他の菌種が増殖してひき起こされる病症。カンジダ症など。
ぎんこう‐てがた【銀行手形】‥カウ‥
銀行によって振り出され、または銀行が支払を引き受けた手形。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きん‐こうどう【金弘道】‥ダウ
朝鮮李朝の画家。金海の人。風俗画・山水画に優れる。代表作「風俗図帖」「騎驢聴鶯図」など。(1745〜1815以後)
きんこう‐のうぎょう【近郊農業】‥カウ‥ゲフ
都市近郊で行われる農業。消費地に近いので、主に高級生鮮食料品や花の生産が行われ、また、地価が高いので小規模集約的な経営が行われる。
⇒きん‐こう【近郊】
ぎんこう‐ほう【銀行法】‥カウハフ
普通銀行の免許・業務などを監督・規制する法律。1927年(昭和2)制定。81年に全面改正。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐ぼき【銀行簿記】‥カウ‥
複式簿記を銀行の業務に適用したもの。現金仕訳法と完全な伝票制を用い、多くの統括勘定を総勘定元帳に記載すること、日次にちじ残高試算表(日計表)を作成することなどが特徴。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐もくぜつ【金口木舌】
(木舌はボクゼツとも)言説で社会を指導する人物。木鐸ぼくたく。
⇒きん‐こう【金口】
きんこう‐よさん【均衡予算】‥カウ‥
歳入(公債金を除く)と歳出とがつりあっていて、赤字がない予算のこと。
⇒きん‐こう【均衡】
きんこう‐りろん【均衡理論】‥カウ‥
〔経〕財・サービスの需要量・供給量・価格など、経済的諸変数の間の相互関係が安定した状態にあるための条件を分析することを中心とした経済理論。→一般均衡理論
⇒きん‐こう【均衡】
ぎんこう‐わりびき【銀行割引】‥カウ‥
手形などの割引をする際に、期日支払金額をもととして割引料を計算する方法。内うち割引。↔真しん割引
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐わん【錦江湾】‥カウ‥
(→)鹿児島湾に同じ。
きんこ‐かぶ【金庫株】
(treasury stock)株式会社が発行後に再取得して保有する自己株式。株価維持などを目的とする。2001年の商法改正で原則自由化された。→貯蔵株。
⇒きん‐こ【金庫】
きんこきかん【今古奇観】‥クワン
中国の短編白話小説集。明末、抱甕ほうよう老人編。馮夢竜ひょうぼうりゅうの「三言」、凌濛初の「二拍」として集大成された小説から計40編を選ぶ。
きん‐こく【金穀】
金銭と穀物。金品。
きん‐こく【謹告】
(「つつしんでお知らせする」の意)公示の文章などの冒頭に用いる語。
きん‐ごく【近国】
①近くの国。
②律令制で、遠国おんごく・中国に対して京都に近い国々の称。延喜式では伊賀・伊勢・志摩・尾張・三河・丹波・丹後・因幡・備前・紀伊・近江・美濃・若狭・但馬・播磨・美作・淡路の17カ国。
きん‐ごく【禁国】
平安中期以後、食封じきふにあてることを禁じられた国。伊賀・伊勢・三河・近江・美濃・越中・石見・備前・周防・長門・紀伊・阿波など。
きん‐ごく【禁獄】
囚人を獄中に拘禁すること。禁牢。
ぎん‐ごけ【銀苔】
蘚類ハリガネゴケ科の一種。茎葉体は直立し、高さ1〜2センチメートル。葉の上半分が透明で、乾くと植物体全体が銀白色に見える。雌雄同株。世界各地に広く分布。
きんご‐こうい【金吾校尉】‥カウヰ
左右衛門尉えもんのじょうの唐名。
⇒きん‐ご【金吾】
きん‐こざね【金小札】
金箔塗りの小札こざね。
ぎん‐こざね【銀小札】
銀箔塗りの小札こざね。
きん‐こじ【金巾子】
①金箔を押した巾子紙こじがみ。
②「金巾子の冠」の略。
⇒きんこじ‐の‐かんむり【金巾子の冠】
きんご‐じしょう【金吾次将】‥シヤウ
左右衛門佐えもんのすけの唐名。
⇒きん‐ご【金吾】
きんこじ‐の‐かんむり【金巾子の冠】
金巾子をつけた冠。もと天皇の常用。御引直衣・紅袴着用の時に用いる。おきんこじのかんむり。きんこじ。
金巾子の冠
ぎん‐こう【銀鉤】
①銀製の針。銀製の、すだれのかけがね。
②力強い草書の形容。
③三日月の形容。
ぎん‐ごう【銀号】‥ガウ
中国で、銀行の称。特に、旧式の両替店風の小規模な金融機関。
ぎんこう‐いん【銀行印】‥カウ‥
銀行との取引きに使用する印章。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐か【金紅花】‥クワ
ユリ科の多年草。高山の湿原に群生。高さ約20センチメートル。葉は剣状。8月頃、星形6弁の小黄色花を総状に密生。金光花。
ぎんこう‐か【銀行家】‥カウ‥
銀行業を営む者。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐かわせ【銀行為替】‥カウカハセ
銀行で取り扱う送金方法。為替手形によるもの、電信送金為替、当座振込などがある。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐きょうこう【銀行恐慌】‥カウ‥クワウ
恐慌状態が甚だしくなって銀行が取付けをうけ、預金引出しに応じられなくなり、銀行の破産が続出する状態。→金融恐慌。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんごう‐きんざい【近郷近在】‥ガウ‥
近くのすべての村。「―に名をとどろかす」
⇒きん‐ごう【近郷】
きんこう‐けい【近交系】‥カウ‥
(近交は、近親交配の意)実験動物で、兄妹交配を20代以上続けることで得られる系統。一組の両親にさかのぼることができる。全遺伝子座のうちホモである割合を近交系数という。
ぎんこう‐けん【銀行券】‥カウ‥
発券銀行(日本銀行・イングランド銀行など)の発行する紙幣で、代表的な現金通貨。本来、兌換だかん銀行券であったが、金本位制から管理通貨制度への移行とともに、いずれの国でも不換銀行券となっている。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐けんがく【勤工倹学】
労働しながら勉強すること。第一次大戦期、周恩来・鄧小平など多くの中国青年がこの方法により、フランスなどで学んだ。
ぎんこう‐こぎって【銀行小切手】‥カウ‥
銀行の預金者から銀行に宛てて振り出される支払の委託書。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐しゅぎ【銀行主義】‥カウ‥
銀行券の発行に際し、正貨準備などの制限を設けず、自由に発行させても、兌換だかんが維持される限り、貨幣は決して過度に流通せず、物価は騰貴しないとする説。19世紀の初め、イギリスで唱えられた。↔通貨主義。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐じゅんびきん【銀行準備金】‥カウ‥
市中銀行が預金の支払いに備えて保有している資金。支払準備金。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐しんよう【銀行信用】‥カウ‥
銀行がその取引先に対して与える信用。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐せき【金紅石】
酸化チタンから成る鉱物。正方晶系、柱状結晶。赤褐色または黄赤色で、花崗岩・片麻へんま岩などの中に存する。ルチル。
きんこう‐せんにん【琴高仙人】‥カウ‥
(画題)中国、周代の仙人。琴の名手で、仙術を使い、鯉に乗って現れるという。
きんこうたい‐しょう【菌交代症】‥カウ‥シヤウ
抗生物質などの使用により、生体内に常在する菌種が減少・死滅し、それに代わって常時は少ない菌または他の菌種が増殖してひき起こされる病症。カンジダ症など。
ぎんこう‐てがた【銀行手形】‥カウ‥
銀行によって振り出され、または銀行が支払を引き受けた手形。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きん‐こうどう【金弘道】‥ダウ
朝鮮李朝の画家。金海の人。風俗画・山水画に優れる。代表作「風俗図帖」「騎驢聴鶯図」など。(1745〜1815以後)
きんこう‐のうぎょう【近郊農業】‥カウ‥ゲフ
都市近郊で行われる農業。消費地に近いので、主に高級生鮮食料品や花の生産が行われ、また、地価が高いので小規模集約的な経営が行われる。
⇒きん‐こう【近郊】
ぎんこう‐ほう【銀行法】‥カウハフ
普通銀行の免許・業務などを監督・規制する法律。1927年(昭和2)制定。81年に全面改正。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐ぼき【銀行簿記】‥カウ‥
複式簿記を銀行の業務に適用したもの。現金仕訳法と完全な伝票制を用い、多くの統括勘定を総勘定元帳に記載すること、日次にちじ残高試算表(日計表)を作成することなどが特徴。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐もくぜつ【金口木舌】
(木舌はボクゼツとも)言説で社会を指導する人物。木鐸ぼくたく。
⇒きん‐こう【金口】
きんこう‐よさん【均衡予算】‥カウ‥
歳入(公債金を除く)と歳出とがつりあっていて、赤字がない予算のこと。
⇒きん‐こう【均衡】
きんこう‐りろん【均衡理論】‥カウ‥
〔経〕財・サービスの需要量・供給量・価格など、経済的諸変数の間の相互関係が安定した状態にあるための条件を分析することを中心とした経済理論。→一般均衡理論
⇒きん‐こう【均衡】
ぎんこう‐わりびき【銀行割引】‥カウ‥
手形などの割引をする際に、期日支払金額をもととして割引料を計算する方法。内うち割引。↔真しん割引
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐わん【錦江湾】‥カウ‥
(→)鹿児島湾に同じ。
きんこ‐かぶ【金庫株】
(treasury stock)株式会社が発行後に再取得して保有する自己株式。株価維持などを目的とする。2001年の商法改正で原則自由化された。→貯蔵株。
⇒きん‐こ【金庫】
きんこきかん【今古奇観】‥クワン
中国の短編白話小説集。明末、抱甕ほうよう老人編。馮夢竜ひょうぼうりゅうの「三言」、凌濛初の「二拍」として集大成された小説から計40編を選ぶ。
きん‐こく【金穀】
金銭と穀物。金品。
きん‐こく【謹告】
(「つつしんでお知らせする」の意)公示の文章などの冒頭に用いる語。
きん‐ごく【近国】
①近くの国。
②律令制で、遠国おんごく・中国に対して京都に近い国々の称。延喜式では伊賀・伊勢・志摩・尾張・三河・丹波・丹後・因幡・備前・紀伊・近江・美濃・若狭・但馬・播磨・美作・淡路の17カ国。
きん‐ごく【禁国】
平安中期以後、食封じきふにあてることを禁じられた国。伊賀・伊勢・三河・近江・美濃・越中・石見・備前・周防・長門・紀伊・阿波など。
きん‐ごく【禁獄】
囚人を獄中に拘禁すること。禁牢。
ぎん‐ごけ【銀苔】
蘚類ハリガネゴケ科の一種。茎葉体は直立し、高さ1〜2センチメートル。葉の上半分が透明で、乾くと植物体全体が銀白色に見える。雌雄同株。世界各地に広く分布。
きんご‐こうい【金吾校尉】‥カウヰ
左右衛門尉えもんのじょうの唐名。
⇒きん‐ご【金吾】
きん‐こざね【金小札】
金箔塗りの小札こざね。
ぎん‐こざね【銀小札】
銀箔塗りの小札こざね。
きん‐こじ【金巾子】
①金箔を押した巾子紙こじがみ。
②「金巾子の冠」の略。
⇒きんこじ‐の‐かんむり【金巾子の冠】
きんご‐じしょう【金吾次将】‥シヤウ
左右衛門佐えもんのすけの唐名。
⇒きん‐ご【金吾】
きんこじ‐の‐かんむり【金巾子の冠】
金巾子をつけた冠。もと天皇の常用。御引直衣・紅袴着用の時に用いる。おきんこじのかんむり。きんこじ。
金巾子の冠
 ⇒きん‐こじ【金巾子】
きんごしゅう【琴後集】‥シフ
⇒ことじりしゅう
きんご‐しょうぐん【金吾将軍】‥シヤウ‥
衛門督えもんのかみの唐名。
⇒きん‐ご【金吾】
きん‐こじり【金鐺】
金または金色の金属で飾った鐺。
ぎん‐こじり【銀鐺】
銀または銀色の金属で飾った鐺。
きん‐こつ【金骨】
凡俗を脱した風骨。仙骨。太平記37「―返て本の肉身と成りしかば」
きん‐こつ【筋骨】
①筋肉と骨格。体格。「―たくましい青年」「―隆々」
②からだ。体力。
⇒きんこつ‐がた【筋骨型】
きんこつ‐がた【筋骨型】
〔心〕クレッチマーが提案した体型による気質分類の一つ。やせ型や肥り型に対して、筋骨の特に発達した体型で、気質的には粘着質が多い。闘士型ともいう。
⇒きん‐こつ【筋骨】
きんこ‐やぶり【金庫破り】
金庫をこわして中の財物を盗むこと。また、その人。
⇒きん‐こ【金庫】
きんこ‐りゅう【琴古流】‥リウ
尺八楽の一流派。18世紀後半に初世黒沢琴古が江戸で創始。都山流とざんりゅうと並ぶ二大流派。
きん‐こん【菌根】
菌類との複合体となった根。菌糸が高等植物の根に共生して形成される。養分の相互補給などが行われている。
きん‐こん【禁閫】
(「閫」は、しきみの意)禁裏の門。転じて、禁裏。御所。
きん‐こん【緊褌】
褌ふんどしをしっかりしめること。
⇒きんこん‐いちばん【緊褌一番】
ぎん‐こん【吟魂】
詩人のうた心。詩情。吟情。
きんこん‐いちばん【緊褌一番】
心を大いに引きしめて、ふるいたって事に当たること。
⇒きん‐こん【緊褌】
きんこん‐しき【金婚式】
(golden wedding)夫婦が結婚後、50年目に行う記念祝賀の式。→結婚記念日(表)
ぎんこん‐しき【銀婚式】
(silver wedding)夫婦が結婚後、25年目に行う記念祝賀の式。→結婚記念日(表)
きん‐さ【欽差】
(「差」は、つかわす意)天子の命令で使者をおくること。また、その使者。
⇒きんさ‐だいじん【欽差大臣】
きん‐さ【僅差】
ほんの少しの差。「―で敗れる」
きん‐ざ【金座】
江戸幕府直轄の、金貨の鋳造・鑑定・発行所。初め江戸・駿府・佐渡・京都の4カ所にあったが、江戸常磐橋門外(中央区本石町二丁目、今の日本銀行の地)の江戸座以外は、中期までに廃止または縮小された。勘定奉行の支配。長を金改役といい、後藤家が世襲。狭義の金座は座人の事務所で、勘定場・天秤前・出来方色改場に分かれ、別に吹所ふきしょと呼ばれた鋳造工場が付属していた。1868年(明治1)封鎖され廃止。
ぎん‐ざ【銀座】
江戸幕府直轄の、銀貨の鋳造・発行所。初め伏見・駿府に設置したが、まもなく京都・江戸に移し、また大坂・長崎にも設置。1800年(寛政12)不正事件のため四座ともに廃止し、江戸1カ所のみ再興。銀貨の極印・包装は大黒常是だいこくじょうぜ家が世襲。68年(明治1)封鎖され廃止。(地名別項)
ぎんざ【銀座】
東京都中央区の繁華街。京橋から新橋まで北東から南西に延びる街路を中心として高級店が並ぶ。駿府の銀座を1612年(慶長17)にここに移したためこの名が残った。地方都市でも繁華な街区を「…銀座」と土地の名を冠していう。
きん‐さい【金釵】
金製のかんざし。
きん‐ざい【近在】
都市に近い村里。「近郷―」
ぎん‐さい【銀釵】
銀製のかんざし。
きん‐さいきん【金再禁】
いったん金輸出禁止を解いた(金解禁)後、再び金輸出を禁ずること。
きんさき‐ぼり【斤先掘り】
鉱業権者が第三者と私的貸借契約を結び、採掘事業を請け負わせること。→租鉱権
きん‐さく【近作】
最近作った作品。特に文学・芸術作品などにいう。
きん‐さく【金策】
さまざまに工夫して入用なかねをととのえること。「―に駆けずり回る」
きん‐さく【金錯】
金属器の表面に金で文様や文字を象嵌ぞうがんし、または塗ったもの。
ぎん‐ざけ【銀鮭】
サケ科の硬骨魚。サケに似るが、頭や体の背面に多数の小黒点がある。川で孵化、数年して春に海に降りて成熟。このとき体色が青緑から銀灰色に変わる(銀毛あるいは銀化ぎんげ)。北太平洋に分布。美味。
ぎん‐ささげ【銀豇豆】
隠元豆の別称。
きんさ‐だいじん【欽差大臣】
清代、官制に定めのない臨時特設の官職の一つ。皇帝から臨時に権限を与えられ、特定事項の処理にあたった三品以上の官。略称、欽使。外国へ派遣される外交官にもこの称を用いた。
⇒きん‐さ【欽差】
きん‐さつ【金札】
①金製または金色の札。謡曲、金札「天より―の降り下りて候」
②閻魔えんまの庁で、善人を極楽に送る時の金製の札。金紙。↔鉄札。
③金貨に代わるべき紙幣。
㋐江戸時代、諸藩で発行した金貨代用の藩札。
㋑明治初年発行の紙幣。太政官だじょうかん金札・民部省金札がある。
きんさつ【金札】
能。観阿弥作の神物。平安遷都に際し、伏見に神社を造営すると、天から金札が降り、神が太平を祝福する。
きん‐さつ【禁札】
禁止する事柄を記した立てふだ。制札。
きん‐さつ【禁殺】
禁錮して殺すこと。おしこめて殺すこと。太平記14「兵部卿親王を―し奉る由」
ぎん‐さつ【銀札】
①銀製または銀色の札。
②江戸時代、諸藩で発行した銀貨代用の紙幣。
ぎん‐ざめ【銀鮫】
ギンザメ科の海産の軟骨魚。全長約1〜2メートル。頭が大きく、尾は細長く、尾びれは糸状。雄の腹びれには交接器がある。体には銀色の光沢がある。太平洋岸の深所に産する。銀鱶ぎんぶか。
ギンザメ
提供:東京動物園協会
⇒きん‐こじ【金巾子】
きんごしゅう【琴後集】‥シフ
⇒ことじりしゅう
きんご‐しょうぐん【金吾将軍】‥シヤウ‥
衛門督えもんのかみの唐名。
⇒きん‐ご【金吾】
きん‐こじり【金鐺】
金または金色の金属で飾った鐺。
ぎん‐こじり【銀鐺】
銀または銀色の金属で飾った鐺。
きん‐こつ【金骨】
凡俗を脱した風骨。仙骨。太平記37「―返て本の肉身と成りしかば」
きん‐こつ【筋骨】
①筋肉と骨格。体格。「―たくましい青年」「―隆々」
②からだ。体力。
⇒きんこつ‐がた【筋骨型】
きんこつ‐がた【筋骨型】
〔心〕クレッチマーが提案した体型による気質分類の一つ。やせ型や肥り型に対して、筋骨の特に発達した体型で、気質的には粘着質が多い。闘士型ともいう。
⇒きん‐こつ【筋骨】
きんこ‐やぶり【金庫破り】
金庫をこわして中の財物を盗むこと。また、その人。
⇒きん‐こ【金庫】
きんこ‐りゅう【琴古流】‥リウ
尺八楽の一流派。18世紀後半に初世黒沢琴古が江戸で創始。都山流とざんりゅうと並ぶ二大流派。
きん‐こん【菌根】
菌類との複合体となった根。菌糸が高等植物の根に共生して形成される。養分の相互補給などが行われている。
きん‐こん【禁閫】
(「閫」は、しきみの意)禁裏の門。転じて、禁裏。御所。
きん‐こん【緊褌】
褌ふんどしをしっかりしめること。
⇒きんこん‐いちばん【緊褌一番】
ぎん‐こん【吟魂】
詩人のうた心。詩情。吟情。
きんこん‐いちばん【緊褌一番】
心を大いに引きしめて、ふるいたって事に当たること。
⇒きん‐こん【緊褌】
きんこん‐しき【金婚式】
(golden wedding)夫婦が結婚後、50年目に行う記念祝賀の式。→結婚記念日(表)
ぎんこん‐しき【銀婚式】
(silver wedding)夫婦が結婚後、25年目に行う記念祝賀の式。→結婚記念日(表)
きん‐さ【欽差】
(「差」は、つかわす意)天子の命令で使者をおくること。また、その使者。
⇒きんさ‐だいじん【欽差大臣】
きん‐さ【僅差】
ほんの少しの差。「―で敗れる」
きん‐ざ【金座】
江戸幕府直轄の、金貨の鋳造・鑑定・発行所。初め江戸・駿府・佐渡・京都の4カ所にあったが、江戸常磐橋門外(中央区本石町二丁目、今の日本銀行の地)の江戸座以外は、中期までに廃止または縮小された。勘定奉行の支配。長を金改役といい、後藤家が世襲。狭義の金座は座人の事務所で、勘定場・天秤前・出来方色改場に分かれ、別に吹所ふきしょと呼ばれた鋳造工場が付属していた。1868年(明治1)封鎖され廃止。
ぎん‐ざ【銀座】
江戸幕府直轄の、銀貨の鋳造・発行所。初め伏見・駿府に設置したが、まもなく京都・江戸に移し、また大坂・長崎にも設置。1800年(寛政12)不正事件のため四座ともに廃止し、江戸1カ所のみ再興。銀貨の極印・包装は大黒常是だいこくじょうぜ家が世襲。68年(明治1)封鎖され廃止。(地名別項)
ぎんざ【銀座】
東京都中央区の繁華街。京橋から新橋まで北東から南西に延びる街路を中心として高級店が並ぶ。駿府の銀座を1612年(慶長17)にここに移したためこの名が残った。地方都市でも繁華な街区を「…銀座」と土地の名を冠していう。
きん‐さい【金釵】
金製のかんざし。
きん‐ざい【近在】
都市に近い村里。「近郷―」
ぎん‐さい【銀釵】
銀製のかんざし。
きん‐さいきん【金再禁】
いったん金輸出禁止を解いた(金解禁)後、再び金輸出を禁ずること。
きんさき‐ぼり【斤先掘り】
鉱業権者が第三者と私的貸借契約を結び、採掘事業を請け負わせること。→租鉱権
きん‐さく【近作】
最近作った作品。特に文学・芸術作品などにいう。
きん‐さく【金策】
さまざまに工夫して入用なかねをととのえること。「―に駆けずり回る」
きん‐さく【金錯】
金属器の表面に金で文様や文字を象嵌ぞうがんし、または塗ったもの。
ぎん‐ざけ【銀鮭】
サケ科の硬骨魚。サケに似るが、頭や体の背面に多数の小黒点がある。川で孵化、数年して春に海に降りて成熟。このとき体色が青緑から銀灰色に変わる(銀毛あるいは銀化ぎんげ)。北太平洋に分布。美味。
ぎん‐ささげ【銀豇豆】
隠元豆の別称。
きんさ‐だいじん【欽差大臣】
清代、官制に定めのない臨時特設の官職の一つ。皇帝から臨時に権限を与えられ、特定事項の処理にあたった三品以上の官。略称、欽使。外国へ派遣される外交官にもこの称を用いた。
⇒きん‐さ【欽差】
きん‐さつ【金札】
①金製または金色の札。謡曲、金札「天より―の降り下りて候」
②閻魔えんまの庁で、善人を極楽に送る時の金製の札。金紙。↔鉄札。
③金貨に代わるべき紙幣。
㋐江戸時代、諸藩で発行した金貨代用の藩札。
㋑明治初年発行の紙幣。太政官だじょうかん金札・民部省金札がある。
きんさつ【金札】
能。観阿弥作の神物。平安遷都に際し、伏見に神社を造営すると、天から金札が降り、神が太平を祝福する。
きん‐さつ【禁札】
禁止する事柄を記した立てふだ。制札。
きん‐さつ【禁殺】
禁錮して殺すこと。おしこめて殺すこと。太平記14「兵部卿親王を―し奉る由」
ぎん‐さつ【銀札】
①銀製または銀色の札。
②江戸時代、諸藩で発行した銀貨代用の紙幣。
ぎん‐ざめ【銀鮫】
ギンザメ科の海産の軟骨魚。全長約1〜2メートル。頭が大きく、尾は細長く、尾びれは糸状。雄の腹びれには交接器がある。体には銀色の光沢がある。太平洋岸の深所に産する。銀鱶ぎんぶか。
ギンザメ
提供:東京動物園協会
 きん‐ザラサ【金更紗】
金泥で模様を彩色した更紗。
ぎん‐ザラサ【銀更紗】
銀泥で模様を彩色した更紗。
きん‐さん【菌傘】
きのこの、傘状の部分。裏面には多数のひだ(菌褶きんしゅう)または小孔があって、胞子を発生させ、繁殖の用をなす。かさ。菌帽。菌蓋。蓋。→きのこ
きん‐ざん【金山】
①金鉱石を埋蔵・産出する鉱山。
②金属で造ったような堅固な山。
③アルタイ山の異称。
⇒きんざん‐てっぺき【金山鉄壁】
ぎん‐ざん【銀山】
銀鉱石を埋蔵・産出する鉱山。
ぎんざん‐おんせん【銀山温泉】‥ヲン‥
山形県尾花沢市、銀山川沿いにある温泉。泉質は塩化物泉。
きんざん‐じ【径山寺】
中国五山の一つ。浙江省臨安市天目山の北東峰にある。8世紀中頃法欽の開創。禅の道場として栄える。興聖万寿禅寺。
⇒きんざんじ‐みそ【径山寺味噌・金山寺味噌】
きんざん‐じ【金山寺】
①朝鮮全羅北道金堤郡母岳山中の仏寺。百済時代(599年)の創建。新羅様式の六重石塔・五角多層石塔・舎利塔がある。
②中国江蘇省鎮江市にある仏寺。東晋時代の開創。宋代以後、江南における文人の遊行所。八角七層の塔は明・清時代の再建。
きんざんじ‐みそ【径山寺味噌・金山寺味噌】
(中国の径山寺の製法を伝えたのでこの名があるという)嘗味噌なめみその一種。大豆と大麦の麹こうじに塩を加え、これに細かく刻んだ茄子・瓜などを入れ、密閉して熟成させたもの。和歌山県有田郡湯浅町の名産。熟成後、砂糖や水飴などで調味することがある。
⇒きんざん‐じ【径山寺】
きんざん‐てっぺき【金山鉄壁】
(→)金城鉄壁に同じ。
⇒きん‐ざん【金山】
きん‐し【近思】
自分の身に省みて考えてみること。
きん‐し【近視】
(myopia)眼の水晶体の焦点距離が短すぎる、あるいは網膜に至る距離が長すぎるため、遠方の物体が網膜より前方に像を結び、そのため鮮明に物を見ることができないこと。凹レンズによって矯正。近視眼。近眼。ちかめ。↔遠視。
⇒きんし‐がん【近視眼】
⇒きんしがん‐てき【近視眼的】
きんし【金史】
二十四史の一つ。金の史書。本紀19巻、志39巻、表4巻、列伝73巻。元の托克托トクトすなわち脱脱らが奉勅撰。1344年成る。
きん‐し【金糸】
①銀または銅の針金に金着きんきせした細い金属線。または、金箔をおいた薄い紙を細く切ったもの、金箔を糸によりつけたもの。細く切ったものを「ひらきん」、よったものを「よりきん」という。金襴きんらんを織る時や、刺繍その他種々の飾り物に用いる。
②堆朱ついしゅの一種。色赤く、彫目厚く、彫目に黄色漆と赤色漆とを塗り重ねたもの。
③皮を除いて精製した繊維の太いフカのひれを1本ずつ糸状にほぐしたもの。
⇒きんし‐こう【金糸猴】
⇒きんし‐ごぼう【金糸牛蒡・錦糸牛蒡】
⇒きんし‐こんぶ【金糸昆布】
⇒きんし‐たまご【金糸卵・錦糸卵】
⇒きんし‐とう【金糸桃】
⇒きんし‐ばい【金糸梅】
きん‐し【金紙】
①金箔を押したり金泥を塗ったりした紙。
②(→)金札きんさつ2に同じ。謡曲、鵜飼「―を汚すこともなく」
きん‐し【金紫】
①金印と紫綬。
②転じて、それを帯びる者。高官。
きん‐し【金鵄】
神武天皇東征の時に、弓の先にとまったという金色のトビ。
⇒きんし‐くんしょう【金鵄勲章】
きん‐し【菌糸】
菌類の体を構成する本体で、繊細な糸状の細胞または細胞列。
きん‐し【勤仕】
勤め仕えること。
きん‐し【禁止】
禁じとどめること。することを許さないこと。禁制。法度はっと。「立入りを―する」「駐車―」
⇒きんし‐えいぎょう【禁止営業】
⇒きんし‐かんぜい【禁止関税】
⇒きんし‐きてい【禁止規定】
⇒きんし‐ぎょぎょう【禁止漁業】
⇒きんし‐ぜい【禁止税】
⇒きんし‐ちょう【禁止鳥】
⇒きんし‐ほう【禁止法】
⇒きんし‐ぼん【禁止本】
きん‐じ【近似】
ものごとが非常によく似通っていること。へだたりがほとんどないこと。「幕末の日本に―している」
⇒きんじ‐けいさん【近似計算】
⇒きんじ‐ち【近似値】
きん‐じ【近事】
近ごろのできごと。最近起きた事件。
きん‐じ【近侍】
主君のそば近く仕えること。また、その人。おそば。扈従こしょう。
⇒きんじ‐の‐ひと【近侍の人】
きん‐じ【近時】
近ごろ。このごろ。↔往時
きん‐じ【金地】‥ヂ
金箔・金泥をおいた布・紙など。金色の地。
きん‐じ【金字】
金泥きんでいで書いた文字。また、金色の文字。
⇒きんじ‐とう【金字塔】
きん‐じ【矜恃】
(キョウジの慣用読み)
⇒きょうじ
きんじ【君】キンヂ
〔代〕
(二人称。キミムチ(君貴)の転。本来は敬意を表したが、のちには多く目下の者にいう)きみ。源氏物語少女「―は同じ年なれど」
ぎん‐し【銀糸】
①銀箔を薄紙に押したのを細く切ったもの、またはそれを糸によりつけたもの。細く切ったのを「ひらぎん」、よったのを「よりぎん」という。装飾用。
②(→)金糸きんし3に同じ。
ぎん‐じ【銀地】‥ヂ
銀箔・銀泥をおいた布・紙など。銀色の地。
ぎん‐じ【銀字】
銀泥で書いた文字。また、銀色の文字。
きんし‐えいぎょう【禁止営業】‥ゲフ
行政上または財政上の目的から禁止した営業。売春・猥褻わいせつ文書図画販売、貨幣・紙幣・国債証券に紛らわしいものの製造・販売など。
⇒きん‐し【禁止】
きんし‐がん【近視眼】
近視の眼。近眼。近視。
⇒きん‐し【近視】
きんし‐かんぜい【禁止関税】‥クワン‥
事実上、輸入禁止制度とほとんど同様の効果を発揮する保護主義輸入関税。禁止税。
⇒きん‐し【禁止】
きんしがん‐てき【近視眼的】
近いところ、狭いところにだけ気をとられて、大局の見通しのないさま。「―な施策」
⇒きん‐し【近視】
きんしかん‐やく【筋弛緩薬】‥クワン‥
筋肉の緊張を緩和する薬物。神経筋接合部や骨格筋に作用する末梢性のものと、脳や脊髄に作用する中枢性のものとがある。
きん‐じき【禁色】
①位階により袍ほうの色の規定があって、上位の位色いしょくの使用を禁じられたこと。また、その色。天皇以下公卿以上所用の袍の色、すなわち黄櫨染こうろぜん・麹塵きくじん・赤色・黄丹色・深紫色などを殿上人以下の諸臣が用いることは禁じられた。続日本紀37「恣ほしいままに―を着て、既に貴賤の殊わかち無く」↔許色ゆるしいろ。
②有文うもんの織物・表袴うえのはかまに、霰地あられじに窠かの文のある浮織物うきおりものを禁じられたこと。
⇒きんじき‐せんげ【禁色宣下】
⇒きんじき‐の‐ひと【禁色の人】
きんじき‐せんげ【禁色宣下】
禁色を用いることを許す宣旨せんじを下すこと。
⇒きん‐じき【禁色】
きんし‐きてい【禁止規定】
一定の行為を禁止する規定。警察の取締規則の類。
⇒きん‐し【禁止】
きんじき‐の‐ひと【禁色の人】
禁色を許された人。
⇒きん‐じき【禁色】
きんし‐ぎょぎょう【禁止漁業】‥ゲフ
水産動植物の繁殖保護などのために、場所・方法・時期・漁船などにつき法律で禁止する漁業。
⇒きん‐し【禁止】
きんし‐ぎょくよう【金枝玉葉】‥エフ
(「金玉の枝葉」の意。枝葉は子孫)天子の一門。皇族。
きんじきんほんい‐せい【金地金本位制】‥ヂ‥ヰ‥
(gold bullion standard)金本位制度の一つ。金の基礎の上に立つが、金貨を市場に流通させず、国内では紙幣・銀貨などを用い、金準備はもっぱら対外的支払のために政府または中央銀行に集中保有され、兌換だかんに際しては金地金を与える貨幣制度。
きんし‐くんしょう【金鵄勲章】‥シヤウ
武功抜群の陸海軍軍人に下賜された勲章。功1級から功7級まで。1890年(明治23)制定。年金または一時金の支給を伴う。1947年廃止。正岡子規、鶴物語「―といふものを朝日に輝かせあたりを払ひて参る」
⇒きん‐し【金鵄】
きんじ‐けいさん【近似計算】
真の値に近い値を算出すること。
⇒きん‐じ【近似】
きんし‐こう【金糸猴】
オナガザル科の哺乳類。ニホンザルよりやや小形で、金色の細く美しい毛を持つ。中国南西部と北西部の極めて限られた地域に分布。貴重な動物とされる。シシバナザル。ゴールデンモンキー。チベットコバナテングザル。イボハナザル。
キンシコウ(雄)
提供:東京動物園協会
きん‐ザラサ【金更紗】
金泥で模様を彩色した更紗。
ぎん‐ザラサ【銀更紗】
銀泥で模様を彩色した更紗。
きん‐さん【菌傘】
きのこの、傘状の部分。裏面には多数のひだ(菌褶きんしゅう)または小孔があって、胞子を発生させ、繁殖の用をなす。かさ。菌帽。菌蓋。蓋。→きのこ
きん‐ざん【金山】
①金鉱石を埋蔵・産出する鉱山。
②金属で造ったような堅固な山。
③アルタイ山の異称。
⇒きんざん‐てっぺき【金山鉄壁】
ぎん‐ざん【銀山】
銀鉱石を埋蔵・産出する鉱山。
ぎんざん‐おんせん【銀山温泉】‥ヲン‥
山形県尾花沢市、銀山川沿いにある温泉。泉質は塩化物泉。
きんざん‐じ【径山寺】
中国五山の一つ。浙江省臨安市天目山の北東峰にある。8世紀中頃法欽の開創。禅の道場として栄える。興聖万寿禅寺。
⇒きんざんじ‐みそ【径山寺味噌・金山寺味噌】
きんざん‐じ【金山寺】
①朝鮮全羅北道金堤郡母岳山中の仏寺。百済時代(599年)の創建。新羅様式の六重石塔・五角多層石塔・舎利塔がある。
②中国江蘇省鎮江市にある仏寺。東晋時代の開創。宋代以後、江南における文人の遊行所。八角七層の塔は明・清時代の再建。
きんざんじ‐みそ【径山寺味噌・金山寺味噌】
(中国の径山寺の製法を伝えたのでこの名があるという)嘗味噌なめみその一種。大豆と大麦の麹こうじに塩を加え、これに細かく刻んだ茄子・瓜などを入れ、密閉して熟成させたもの。和歌山県有田郡湯浅町の名産。熟成後、砂糖や水飴などで調味することがある。
⇒きんざん‐じ【径山寺】
きんざん‐てっぺき【金山鉄壁】
(→)金城鉄壁に同じ。
⇒きん‐ざん【金山】
きん‐し【近思】
自分の身に省みて考えてみること。
きん‐し【近視】
(myopia)眼の水晶体の焦点距離が短すぎる、あるいは網膜に至る距離が長すぎるため、遠方の物体が網膜より前方に像を結び、そのため鮮明に物を見ることができないこと。凹レンズによって矯正。近視眼。近眼。ちかめ。↔遠視。
⇒きんし‐がん【近視眼】
⇒きんしがん‐てき【近視眼的】
きんし【金史】
二十四史の一つ。金の史書。本紀19巻、志39巻、表4巻、列伝73巻。元の托克托トクトすなわち脱脱らが奉勅撰。1344年成る。
きん‐し【金糸】
①銀または銅の針金に金着きんきせした細い金属線。または、金箔をおいた薄い紙を細く切ったもの、金箔を糸によりつけたもの。細く切ったものを「ひらきん」、よったものを「よりきん」という。金襴きんらんを織る時や、刺繍その他種々の飾り物に用いる。
②堆朱ついしゅの一種。色赤く、彫目厚く、彫目に黄色漆と赤色漆とを塗り重ねたもの。
③皮を除いて精製した繊維の太いフカのひれを1本ずつ糸状にほぐしたもの。
⇒きんし‐こう【金糸猴】
⇒きんし‐ごぼう【金糸牛蒡・錦糸牛蒡】
⇒きんし‐こんぶ【金糸昆布】
⇒きんし‐たまご【金糸卵・錦糸卵】
⇒きんし‐とう【金糸桃】
⇒きんし‐ばい【金糸梅】
きん‐し【金紙】
①金箔を押したり金泥を塗ったりした紙。
②(→)金札きんさつ2に同じ。謡曲、鵜飼「―を汚すこともなく」
きん‐し【金紫】
①金印と紫綬。
②転じて、それを帯びる者。高官。
きん‐し【金鵄】
神武天皇東征の時に、弓の先にとまったという金色のトビ。
⇒きんし‐くんしょう【金鵄勲章】
きん‐し【菌糸】
菌類の体を構成する本体で、繊細な糸状の細胞または細胞列。
きん‐し【勤仕】
勤め仕えること。
きん‐し【禁止】
禁じとどめること。することを許さないこと。禁制。法度はっと。「立入りを―する」「駐車―」
⇒きんし‐えいぎょう【禁止営業】
⇒きんし‐かんぜい【禁止関税】
⇒きんし‐きてい【禁止規定】
⇒きんし‐ぎょぎょう【禁止漁業】
⇒きんし‐ぜい【禁止税】
⇒きんし‐ちょう【禁止鳥】
⇒きんし‐ほう【禁止法】
⇒きんし‐ぼん【禁止本】
きん‐じ【近似】
ものごとが非常によく似通っていること。へだたりがほとんどないこと。「幕末の日本に―している」
⇒きんじ‐けいさん【近似計算】
⇒きんじ‐ち【近似値】
きん‐じ【近事】
近ごろのできごと。最近起きた事件。
きん‐じ【近侍】
主君のそば近く仕えること。また、その人。おそば。扈従こしょう。
⇒きんじ‐の‐ひと【近侍の人】
きん‐じ【近時】
近ごろ。このごろ。↔往時
きん‐じ【金地】‥ヂ
金箔・金泥をおいた布・紙など。金色の地。
きん‐じ【金字】
金泥きんでいで書いた文字。また、金色の文字。
⇒きんじ‐とう【金字塔】
きん‐じ【矜恃】
(キョウジの慣用読み)
⇒きょうじ
きんじ【君】キンヂ
〔代〕
(二人称。キミムチ(君貴)の転。本来は敬意を表したが、のちには多く目下の者にいう)きみ。源氏物語少女「―は同じ年なれど」
ぎん‐し【銀糸】
①銀箔を薄紙に押したのを細く切ったもの、またはそれを糸によりつけたもの。細く切ったのを「ひらぎん」、よったのを「よりぎん」という。装飾用。
②(→)金糸きんし3に同じ。
ぎん‐じ【銀地】‥ヂ
銀箔・銀泥をおいた布・紙など。銀色の地。
ぎん‐じ【銀字】
銀泥で書いた文字。また、銀色の文字。
きんし‐えいぎょう【禁止営業】‥ゲフ
行政上または財政上の目的から禁止した営業。売春・猥褻わいせつ文書図画販売、貨幣・紙幣・国債証券に紛らわしいものの製造・販売など。
⇒きん‐し【禁止】
きんし‐がん【近視眼】
近視の眼。近眼。近視。
⇒きん‐し【近視】
きんし‐かんぜい【禁止関税】‥クワン‥
事実上、輸入禁止制度とほとんど同様の効果を発揮する保護主義輸入関税。禁止税。
⇒きん‐し【禁止】
きんしがん‐てき【近視眼的】
近いところ、狭いところにだけ気をとられて、大局の見通しのないさま。「―な施策」
⇒きん‐し【近視】
きんしかん‐やく【筋弛緩薬】‥クワン‥
筋肉の緊張を緩和する薬物。神経筋接合部や骨格筋に作用する末梢性のものと、脳や脊髄に作用する中枢性のものとがある。
きん‐じき【禁色】
①位階により袍ほうの色の規定があって、上位の位色いしょくの使用を禁じられたこと。また、その色。天皇以下公卿以上所用の袍の色、すなわち黄櫨染こうろぜん・麹塵きくじん・赤色・黄丹色・深紫色などを殿上人以下の諸臣が用いることは禁じられた。続日本紀37「恣ほしいままに―を着て、既に貴賤の殊わかち無く」↔許色ゆるしいろ。
②有文うもんの織物・表袴うえのはかまに、霰地あられじに窠かの文のある浮織物うきおりものを禁じられたこと。
⇒きんじき‐せんげ【禁色宣下】
⇒きんじき‐の‐ひと【禁色の人】
きんじき‐せんげ【禁色宣下】
禁色を用いることを許す宣旨せんじを下すこと。
⇒きん‐じき【禁色】
きんし‐きてい【禁止規定】
一定の行為を禁止する規定。警察の取締規則の類。
⇒きん‐し【禁止】
きんじき‐の‐ひと【禁色の人】
禁色を許された人。
⇒きん‐じき【禁色】
きんし‐ぎょぎょう【禁止漁業】‥ゲフ
水産動植物の繁殖保護などのために、場所・方法・時期・漁船などにつき法律で禁止する漁業。
⇒きん‐し【禁止】
きんし‐ぎょくよう【金枝玉葉】‥エフ
(「金玉の枝葉」の意。枝葉は子孫)天子の一門。皇族。
きんじきんほんい‐せい【金地金本位制】‥ヂ‥ヰ‥
(gold bullion standard)金本位制度の一つ。金の基礎の上に立つが、金貨を市場に流通させず、国内では紙幣・銀貨などを用い、金準備はもっぱら対外的支払のために政府または中央銀行に集中保有され、兌換だかんに際しては金地金を与える貨幣制度。
きんし‐くんしょう【金鵄勲章】‥シヤウ
武功抜群の陸海軍軍人に下賜された勲章。功1級から功7級まで。1890年(明治23)制定。年金または一時金の支給を伴う。1947年廃止。正岡子規、鶴物語「―といふものを朝日に輝かせあたりを払ひて参る」
⇒きん‐し【金鵄】
きんじ‐けいさん【近似計算】
真の値に近い値を算出すること。
⇒きん‐じ【近似】
きんし‐こう【金糸猴】
オナガザル科の哺乳類。ニホンザルよりやや小形で、金色の細く美しい毛を持つ。中国南西部と北西部の極めて限られた地域に分布。貴重な動物とされる。シシバナザル。ゴールデンモンキー。チベットコバナテングザル。イボハナザル。
キンシコウ(雄)
提供:東京動物園協会
 キンシコウ(雌)
提供:東京動物園協会
キンシコウ(雌)
提供:東京動物園協会
 ⇒きん‐し【金糸】
きんし‐ごぼう【金糸牛蒡・錦糸牛蒡】‥バウ
牛蒡を針のように細くきざみ、油で炒りつけたもの。汁物の材料とする。
⇒きん‐し【金糸】
きんし‐こんぶ【金糸昆布】
昆布の中心部だけを取って細く金糸状に切ったもの。料理の口取に用いる。切水晶昆布。
⇒きん‐し【金糸】
きん‐じさ【均時差】
真太陽時と平均太陽時との差。すなわち、真の太陽と仮想の平均太陽との時角の差。時差率。時差。
きん‐しじょう【金市場】‥ヂヤウ
世界的貨幣であると同時に世界的商品である金の取引が行われる市場。ロンドン金市場が有名。
きん‐ジストロフィー‐しょう【筋ジストロフィー症】‥シヤウ
(muscular dystrophy)筋肉の萎縮と脱力が徐々に進行し、歩行や運動が困難となる疾病。進行性筋ジストロフィー症と筋緊張性ジストロフィー症とがある。
きんし‐ぜい【禁止税】
(→)禁止関税に同じ。
⇒きん‐し【禁止】
きんし‐たまご【金糸卵・錦糸卵】
薄い卵焼きを細く切ったもの。
⇒きん‐し【金糸】
きんじ‐ち【近似値】
近似計算により得られる数値。例えば、3.1416は円周率(π)の近似値で、誤差は0.0001より小さい。
⇒きん‐じ【近似】
きんし‐ちょう【禁止鳥】‥テウ
(→)禁鳥に同じ。
⇒きん‐し【禁止】
きん‐しつ【均質】
性質が同じであること。一つの物体中のどの部分をとっても、成分・性質の一定していること。等質。「―な製品」
きん‐しつ【金漆】
奈良・平安時代に、金属や革に塗られた乾性の樹脂。コシアブラ(またはゴンゼツ)の実をしぼって濾こしたもの。続日本紀宝亀8年5月23日「―一缶・漆一缶…」
きん‐しつ【琴瑟】
琴ことと瑟おおごと。
⇒琴瑟相和す
きん‐じつ【近日】
今より後、程遠くない日。近いうち。ちかぢか。「―中にうかがいます」「―開店」
⇒きん‐し【金糸】
きんし‐ごぼう【金糸牛蒡・錦糸牛蒡】‥バウ
牛蒡を針のように細くきざみ、油で炒りつけたもの。汁物の材料とする。
⇒きん‐し【金糸】
きんし‐こんぶ【金糸昆布】
昆布の中心部だけを取って細く金糸状に切ったもの。料理の口取に用いる。切水晶昆布。
⇒きん‐し【金糸】
きん‐じさ【均時差】
真太陽時と平均太陽時との差。すなわち、真の太陽と仮想の平均太陽との時角の差。時差率。時差。
きん‐しじょう【金市場】‥ヂヤウ
世界的貨幣であると同時に世界的商品である金の取引が行われる市場。ロンドン金市場が有名。
きん‐ジストロフィー‐しょう【筋ジストロフィー症】‥シヤウ
(muscular dystrophy)筋肉の萎縮と脱力が徐々に進行し、歩行や運動が困難となる疾病。進行性筋ジストロフィー症と筋緊張性ジストロフィー症とがある。
きんし‐ぜい【禁止税】
(→)禁止関税に同じ。
⇒きん‐し【禁止】
きんし‐たまご【金糸卵・錦糸卵】
薄い卵焼きを細く切ったもの。
⇒きん‐し【金糸】
きんじ‐ち【近似値】
近似計算により得られる数値。例えば、3.1416は円周率(π)の近似値で、誤差は0.0001より小さい。
⇒きん‐じ【近似】
きんし‐ちょう【禁止鳥】‥テウ
(→)禁鳥に同じ。
⇒きん‐し【禁止】
きん‐しつ【均質】
性質が同じであること。一つの物体中のどの部分をとっても、成分・性質の一定していること。等質。「―な製品」
きん‐しつ【金漆】
奈良・平安時代に、金属や革に塗られた乾性の樹脂。コシアブラ(またはゴンゼツ)の実をしぼって濾こしたもの。続日本紀宝亀8年5月23日「―一缶・漆一缶…」
きん‐しつ【琴瑟】
琴ことと瑟おおごと。
⇒琴瑟相和す
きん‐じつ【近日】
今より後、程遠くない日。近いうち。ちかぢか。「―中にうかがいます」「―開店」
 キンコ
提供:東京動物園協会
キンコ
提供:東京動物園協会
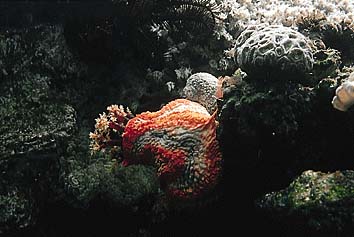 ジイガセキンコの仲間
提供:東京動物園協会
ジイガセキンコの仲間
提供:東京動物園協会
 きん‐こ【近古】
日本史の時代区分の一つ。鎌倉・室町時代を指す。
きん‐こ【金庫】
①金銀財宝を入れておく倉庫。かねぐら。「―番」
②金銭その他重要書類をおさめ、盗難や火難を防ぐための鉄製の箱。
③国または地方公共団体の現金出納機関。国庫金の出納者としての日本銀行の類。
④特別法によって設立された特殊金融機関の名称。例えば農林中央金庫・労働金庫など。
⇒きんこ‐かぶ【金庫株】
⇒きんこ‐やぶり【金庫破り】
きん‐こ【金粉】
①黄金の粉末。金砂きんしゃ。きんぷん。
②ばくちに用いる一種の采さい。穴をあけて中に金粉を入れ、その重量によって、必ず定まった目の出るように作ったいかさまもの。
きん‐こ【金鼓】
①陣鉦じんがねと陣太鼓。陣中の号令に用いるもの。
②鉦または鉦鼓しょうこ。
③⇒こんく
きん‐こ【禁錮・禁固】
①[漢書貢禹伝「皆禁錮して吏為たるを得ず」]仕官の途をふさぎとめて仕えさせないこと。
②[後漢書党錮伝「其れ位に在る者は官を免じ禁錮す」]一室内に閉じ籠めて外出を禁ずること。
③自由刑の一つ。刑務所に拘置するだけで定役には服させない刑。無期と有期(1カ月以上20年以内)とがあり、有期は30年まで加重、1カ月未満に減軽できる。
きんご
①カルタばくちの一つ。手の札とめくり札と合わせて15またはそれに最も近い数を勝ちとする。
②(→)囲かこい女郎に同じ。
きん‐ご【金吾】
(漢代に宮門の警衛をつかさどった武官である執金吾の略)衛門府の唐名。また、衛門督えもんのかみの称。
⇒きんご‐こうい【金吾校尉】
⇒きんご‐じしょう【金吾次将】
⇒きんご‐しょうぐん【金吾将軍】
ぎん‐こ【銀狐】
⇒ぎんぎつね
ぎん‐こ【銀粉】
銀の粉末。銀砂。ぎんぷん。
ギンゴイテス【Ginkgoites ラテン】
絶滅したイチョウ類の一つ。葉は現在のイチョウに似、高さ30メートルに達する。世界各地の三畳紀〜白亜前期の地層から出土。
きん‐こう【均衡】‥カウ
(「衡」は、はかりのさお、の意)二つ以上の物・事の間に、つりあいが取れていること。つりあい。平衡。平均。「―を保つ」「―が破れる」
⇒きんこう‐よさん【均衡予算】
⇒きんこう‐りろん【均衡理論】
きん‐こう【近郊】‥カウ
都市に近い郊外。「―の住宅地」
⇒きんこう‐のうぎょう【近郊農業】
きん‐こう【欣幸】‥カウ
よろこび、しあわせに思うこと。
きん‐こう【金口】
①器物の口部を金属で作ったもの。
②〔仏〕
⇒こんく。
③よい言葉を出す口。立派な言葉。また、他人の言葉の尊敬語。
⇒きんこう‐もくぜつ【金口木舌】
きん‐こう【金工】
金属に細工を施す美術工芸。また、その職人。金匠。
きん‐こう【金光】‥クワウ
黄金の光。金色の光。
きん‐こう【金坑】‥カウ
金を採掘するために掘った穴。また、金鉱、金山。
きん‐こう【金鉱】‥クワウ
金を含有する鉱石。また、それを埋蔵している鉱山。
きん‐こう【金膏】‥カウ
こがね色の口紅。高貴な化粧品。太平記37「瓊粉けいふん―の仮なる色を事とせん」
きん‐こう【勤功】
勤務上の功労。
きん‐こう【欽仰】‥カウ
(キンゴウとも)
⇒きんぎょう
きん‐こう【噤口】
口をつぐむこと。ものを言わないこと。
きんこう【錦江】‥カウ
①(Kŭm-gang)韓国全羅北道長水郡に発源し、湖南平野北部を流れて黄海に入る川。全長400キロメートル。クムガン。古名、白村江はくそんこう。
②(Jin Jiang)中国江西省北西部を流れ、新建県の南で贛かん江に注ぐ川。全長280キロメートル。
きん‐こう【謹厚】
つつしみ深くて温厚なこと。枕草子8「いと―なるものを」
きん‐ごう【近郷】‥ガウ
近くの村。また、都市に近い村里。近在。
⇒きんごう‐きんざい【近郷近在】
ぎん‐こう【吟行】‥カウ
①詩歌をうたいながら歩くこと。
②作句・作歌などのため、同好者が野外や名所旧跡に出かけて行くこと。
ぎん‐こう【銀光】‥クワウ
銀色の光。
ぎん‐こう【銀行】‥カウ
(bank)
①一方で貯蓄者から預金を預かり、他方で貸付・手形割引および証券の引受けなどを業務とする金融機関。普通銀行(都市銀行・地方銀行など)と特殊銀行(日本銀行・日本政策投資銀行など)に分かれる。石川啄木、書簡「生れて初めて―に金をとりにゆく新経験に御座候」
②比喩的に、貴重なものを確保・保管し、求めに応じてそれを供給する組織。「血液―」「人材―」
⇒ぎんこう‐いん【銀行印】
⇒ぎんこう‐か【銀行家】
⇒ぎんこう‐かわせ【銀行為替】
⇒ぎんこう‐きょうこう【銀行恐慌】
⇒ぎんこう‐けん【銀行券】
⇒ぎんこう‐こぎって【銀行小切手】
⇒ぎんこう‐しゅぎ【銀行主義】
⇒ぎんこう‐じゅんびきん【銀行準備金】
⇒ぎんこう‐しんよう【銀行信用】
⇒ぎんこう‐てがた【銀行手形】
⇒ぎんこう‐ほう【銀行法】
⇒ぎんこう‐ぼき【銀行簿記】
⇒ぎんこう‐わりびき【銀行割引】
ぎん‐こう【銀坑】‥カウ
銀を採掘するために掘った穴。また、銀鉱・銀山。
ぎん‐こう【銀鉱】‥クワウ
銀を含有する鉱石。また、それを埋蔵している鉱山。
濃紅銀鉱
撮影:松原 聰
きん‐こ【近古】
日本史の時代区分の一つ。鎌倉・室町時代を指す。
きん‐こ【金庫】
①金銀財宝を入れておく倉庫。かねぐら。「―番」
②金銭その他重要書類をおさめ、盗難や火難を防ぐための鉄製の箱。
③国または地方公共団体の現金出納機関。国庫金の出納者としての日本銀行の類。
④特別法によって設立された特殊金融機関の名称。例えば農林中央金庫・労働金庫など。
⇒きんこ‐かぶ【金庫株】
⇒きんこ‐やぶり【金庫破り】
きん‐こ【金粉】
①黄金の粉末。金砂きんしゃ。きんぷん。
②ばくちに用いる一種の采さい。穴をあけて中に金粉を入れ、その重量によって、必ず定まった目の出るように作ったいかさまもの。
きん‐こ【金鼓】
①陣鉦じんがねと陣太鼓。陣中の号令に用いるもの。
②鉦または鉦鼓しょうこ。
③⇒こんく
きん‐こ【禁錮・禁固】
①[漢書貢禹伝「皆禁錮して吏為たるを得ず」]仕官の途をふさぎとめて仕えさせないこと。
②[後漢書党錮伝「其れ位に在る者は官を免じ禁錮す」]一室内に閉じ籠めて外出を禁ずること。
③自由刑の一つ。刑務所に拘置するだけで定役には服させない刑。無期と有期(1カ月以上20年以内)とがあり、有期は30年まで加重、1カ月未満に減軽できる。
きんご
①カルタばくちの一つ。手の札とめくり札と合わせて15またはそれに最も近い数を勝ちとする。
②(→)囲かこい女郎に同じ。
きん‐ご【金吾】
(漢代に宮門の警衛をつかさどった武官である執金吾の略)衛門府の唐名。また、衛門督えもんのかみの称。
⇒きんご‐こうい【金吾校尉】
⇒きんご‐じしょう【金吾次将】
⇒きんご‐しょうぐん【金吾将軍】
ぎん‐こ【銀狐】
⇒ぎんぎつね
ぎん‐こ【銀粉】
銀の粉末。銀砂。ぎんぷん。
ギンゴイテス【Ginkgoites ラテン】
絶滅したイチョウ類の一つ。葉は現在のイチョウに似、高さ30メートルに達する。世界各地の三畳紀〜白亜前期の地層から出土。
きん‐こう【均衡】‥カウ
(「衡」は、はかりのさお、の意)二つ以上の物・事の間に、つりあいが取れていること。つりあい。平衡。平均。「―を保つ」「―が破れる」
⇒きんこう‐よさん【均衡予算】
⇒きんこう‐りろん【均衡理論】
きん‐こう【近郊】‥カウ
都市に近い郊外。「―の住宅地」
⇒きんこう‐のうぎょう【近郊農業】
きん‐こう【欣幸】‥カウ
よろこび、しあわせに思うこと。
きん‐こう【金口】
①器物の口部を金属で作ったもの。
②〔仏〕
⇒こんく。
③よい言葉を出す口。立派な言葉。また、他人の言葉の尊敬語。
⇒きんこう‐もくぜつ【金口木舌】
きん‐こう【金工】
金属に細工を施す美術工芸。また、その職人。金匠。
きん‐こう【金光】‥クワウ
黄金の光。金色の光。
きん‐こう【金坑】‥カウ
金を採掘するために掘った穴。また、金鉱、金山。
きん‐こう【金鉱】‥クワウ
金を含有する鉱石。また、それを埋蔵している鉱山。
きん‐こう【金膏】‥カウ
こがね色の口紅。高貴な化粧品。太平記37「瓊粉けいふん―の仮なる色を事とせん」
きん‐こう【勤功】
勤務上の功労。
きん‐こう【欽仰】‥カウ
(キンゴウとも)
⇒きんぎょう
きん‐こう【噤口】
口をつぐむこと。ものを言わないこと。
きんこう【錦江】‥カウ
①(Kŭm-gang)韓国全羅北道長水郡に発源し、湖南平野北部を流れて黄海に入る川。全長400キロメートル。クムガン。古名、白村江はくそんこう。
②(Jin Jiang)中国江西省北西部を流れ、新建県の南で贛かん江に注ぐ川。全長280キロメートル。
きん‐こう【謹厚】
つつしみ深くて温厚なこと。枕草子8「いと―なるものを」
きん‐ごう【近郷】‥ガウ
近くの村。また、都市に近い村里。近在。
⇒きんごう‐きんざい【近郷近在】
ぎん‐こう【吟行】‥カウ
①詩歌をうたいながら歩くこと。
②作句・作歌などのため、同好者が野外や名所旧跡に出かけて行くこと。
ぎん‐こう【銀光】‥クワウ
銀色の光。
ぎん‐こう【銀行】‥カウ
(bank)
①一方で貯蓄者から預金を預かり、他方で貸付・手形割引および証券の引受けなどを業務とする金融機関。普通銀行(都市銀行・地方銀行など)と特殊銀行(日本銀行・日本政策投資銀行など)に分かれる。石川啄木、書簡「生れて初めて―に金をとりにゆく新経験に御座候」
②比喩的に、貴重なものを確保・保管し、求めに応じてそれを供給する組織。「血液―」「人材―」
⇒ぎんこう‐いん【銀行印】
⇒ぎんこう‐か【銀行家】
⇒ぎんこう‐かわせ【銀行為替】
⇒ぎんこう‐きょうこう【銀行恐慌】
⇒ぎんこう‐けん【銀行券】
⇒ぎんこう‐こぎって【銀行小切手】
⇒ぎんこう‐しゅぎ【銀行主義】
⇒ぎんこう‐じゅんびきん【銀行準備金】
⇒ぎんこう‐しんよう【銀行信用】
⇒ぎんこう‐てがた【銀行手形】
⇒ぎんこう‐ほう【銀行法】
⇒ぎんこう‐ぼき【銀行簿記】
⇒ぎんこう‐わりびき【銀行割引】
ぎん‐こう【銀坑】‥カウ
銀を採掘するために掘った穴。また、銀鉱・銀山。
ぎん‐こう【銀鉱】‥クワウ
銀を含有する鉱石。また、それを埋蔵している鉱山。
濃紅銀鉱
撮影:松原 聰
 ぎん‐こう【銀鉤】
①銀製の針。銀製の、すだれのかけがね。
②力強い草書の形容。
③三日月の形容。
ぎん‐ごう【銀号】‥ガウ
中国で、銀行の称。特に、旧式の両替店風の小規模な金融機関。
ぎんこう‐いん【銀行印】‥カウ‥
銀行との取引きに使用する印章。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐か【金紅花】‥クワ
ユリ科の多年草。高山の湿原に群生。高さ約20センチメートル。葉は剣状。8月頃、星形6弁の小黄色花を総状に密生。金光花。
ぎんこう‐か【銀行家】‥カウ‥
銀行業を営む者。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐かわせ【銀行為替】‥カウカハセ
銀行で取り扱う送金方法。為替手形によるもの、電信送金為替、当座振込などがある。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐きょうこう【銀行恐慌】‥カウ‥クワウ
恐慌状態が甚だしくなって銀行が取付けをうけ、預金引出しに応じられなくなり、銀行の破産が続出する状態。→金融恐慌。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんごう‐きんざい【近郷近在】‥ガウ‥
近くのすべての村。「―に名をとどろかす」
⇒きん‐ごう【近郷】
きんこう‐けい【近交系】‥カウ‥
(近交は、近親交配の意)実験動物で、兄妹交配を20代以上続けることで得られる系統。一組の両親にさかのぼることができる。全遺伝子座のうちホモである割合を近交系数という。
ぎんこう‐けん【銀行券】‥カウ‥
発券銀行(日本銀行・イングランド銀行など)の発行する紙幣で、代表的な現金通貨。本来、兌換だかん銀行券であったが、金本位制から管理通貨制度への移行とともに、いずれの国でも不換銀行券となっている。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐けんがく【勤工倹学】
労働しながら勉強すること。第一次大戦期、周恩来・鄧小平など多くの中国青年がこの方法により、フランスなどで学んだ。
ぎんこう‐こぎって【銀行小切手】‥カウ‥
銀行の預金者から銀行に宛てて振り出される支払の委託書。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐しゅぎ【銀行主義】‥カウ‥
銀行券の発行に際し、正貨準備などの制限を設けず、自由に発行させても、兌換だかんが維持される限り、貨幣は決して過度に流通せず、物価は騰貴しないとする説。19世紀の初め、イギリスで唱えられた。↔通貨主義。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐じゅんびきん【銀行準備金】‥カウ‥
市中銀行が預金の支払いに備えて保有している資金。支払準備金。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐しんよう【銀行信用】‥カウ‥
銀行がその取引先に対して与える信用。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐せき【金紅石】
酸化チタンから成る鉱物。正方晶系、柱状結晶。赤褐色または黄赤色で、花崗岩・片麻へんま岩などの中に存する。ルチル。
きんこう‐せんにん【琴高仙人】‥カウ‥
(画題)中国、周代の仙人。琴の名手で、仙術を使い、鯉に乗って現れるという。
きんこうたい‐しょう【菌交代症】‥カウ‥シヤウ
抗生物質などの使用により、生体内に常在する菌種が減少・死滅し、それに代わって常時は少ない菌または他の菌種が増殖してひき起こされる病症。カンジダ症など。
ぎんこう‐てがた【銀行手形】‥カウ‥
銀行によって振り出され、または銀行が支払を引き受けた手形。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きん‐こうどう【金弘道】‥ダウ
朝鮮李朝の画家。金海の人。風俗画・山水画に優れる。代表作「風俗図帖」「騎驢聴鶯図」など。(1745〜1815以後)
きんこう‐のうぎょう【近郊農業】‥カウ‥ゲフ
都市近郊で行われる農業。消費地に近いので、主に高級生鮮食料品や花の生産が行われ、また、地価が高いので小規模集約的な経営が行われる。
⇒きん‐こう【近郊】
ぎんこう‐ほう【銀行法】‥カウハフ
普通銀行の免許・業務などを監督・規制する法律。1927年(昭和2)制定。81年に全面改正。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐ぼき【銀行簿記】‥カウ‥
複式簿記を銀行の業務に適用したもの。現金仕訳法と完全な伝票制を用い、多くの統括勘定を総勘定元帳に記載すること、日次にちじ残高試算表(日計表)を作成することなどが特徴。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐もくぜつ【金口木舌】
(木舌はボクゼツとも)言説で社会を指導する人物。木鐸ぼくたく。
⇒きん‐こう【金口】
きんこう‐よさん【均衡予算】‥カウ‥
歳入(公債金を除く)と歳出とがつりあっていて、赤字がない予算のこと。
⇒きん‐こう【均衡】
きんこう‐りろん【均衡理論】‥カウ‥
〔経〕財・サービスの需要量・供給量・価格など、経済的諸変数の間の相互関係が安定した状態にあるための条件を分析することを中心とした経済理論。→一般均衡理論
⇒きん‐こう【均衡】
ぎんこう‐わりびき【銀行割引】‥カウ‥
手形などの割引をする際に、期日支払金額をもととして割引料を計算する方法。内うち割引。↔真しん割引
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐わん【錦江湾】‥カウ‥
(→)鹿児島湾に同じ。
きんこ‐かぶ【金庫株】
(treasury stock)株式会社が発行後に再取得して保有する自己株式。株価維持などを目的とする。2001年の商法改正で原則自由化された。→貯蔵株。
⇒きん‐こ【金庫】
きんこきかん【今古奇観】‥クワン
中国の短編白話小説集。明末、抱甕ほうよう老人編。馮夢竜ひょうぼうりゅうの「三言」、凌濛初の「二拍」として集大成された小説から計40編を選ぶ。
きん‐こく【金穀】
金銭と穀物。金品。
きん‐こく【謹告】
(「つつしんでお知らせする」の意)公示の文章などの冒頭に用いる語。
きん‐ごく【近国】
①近くの国。
②律令制で、遠国おんごく・中国に対して京都に近い国々の称。延喜式では伊賀・伊勢・志摩・尾張・三河・丹波・丹後・因幡・備前・紀伊・近江・美濃・若狭・但馬・播磨・美作・淡路の17カ国。
きん‐ごく【禁国】
平安中期以後、食封じきふにあてることを禁じられた国。伊賀・伊勢・三河・近江・美濃・越中・石見・備前・周防・長門・紀伊・阿波など。
きん‐ごく【禁獄】
囚人を獄中に拘禁すること。禁牢。
ぎん‐ごけ【銀苔】
蘚類ハリガネゴケ科の一種。茎葉体は直立し、高さ1〜2センチメートル。葉の上半分が透明で、乾くと植物体全体が銀白色に見える。雌雄同株。世界各地に広く分布。
きんご‐こうい【金吾校尉】‥カウヰ
左右衛門尉えもんのじょうの唐名。
⇒きん‐ご【金吾】
きん‐こざね【金小札】
金箔塗りの小札こざね。
ぎん‐こざね【銀小札】
銀箔塗りの小札こざね。
きん‐こじ【金巾子】
①金箔を押した巾子紙こじがみ。
②「金巾子の冠」の略。
⇒きんこじ‐の‐かんむり【金巾子の冠】
きんご‐じしょう【金吾次将】‥シヤウ
左右衛門佐えもんのすけの唐名。
⇒きん‐ご【金吾】
きんこじ‐の‐かんむり【金巾子の冠】
金巾子をつけた冠。もと天皇の常用。御引直衣・紅袴着用の時に用いる。おきんこじのかんむり。きんこじ。
金巾子の冠
ぎん‐こう【銀鉤】
①銀製の針。銀製の、すだれのかけがね。
②力強い草書の形容。
③三日月の形容。
ぎん‐ごう【銀号】‥ガウ
中国で、銀行の称。特に、旧式の両替店風の小規模な金融機関。
ぎんこう‐いん【銀行印】‥カウ‥
銀行との取引きに使用する印章。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐か【金紅花】‥クワ
ユリ科の多年草。高山の湿原に群生。高さ約20センチメートル。葉は剣状。8月頃、星形6弁の小黄色花を総状に密生。金光花。
ぎんこう‐か【銀行家】‥カウ‥
銀行業を営む者。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐かわせ【銀行為替】‥カウカハセ
銀行で取り扱う送金方法。為替手形によるもの、電信送金為替、当座振込などがある。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐きょうこう【銀行恐慌】‥カウ‥クワウ
恐慌状態が甚だしくなって銀行が取付けをうけ、預金引出しに応じられなくなり、銀行の破産が続出する状態。→金融恐慌。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんごう‐きんざい【近郷近在】‥ガウ‥
近くのすべての村。「―に名をとどろかす」
⇒きん‐ごう【近郷】
きんこう‐けい【近交系】‥カウ‥
(近交は、近親交配の意)実験動物で、兄妹交配を20代以上続けることで得られる系統。一組の両親にさかのぼることができる。全遺伝子座のうちホモである割合を近交系数という。
ぎんこう‐けん【銀行券】‥カウ‥
発券銀行(日本銀行・イングランド銀行など)の発行する紙幣で、代表的な現金通貨。本来、兌換だかん銀行券であったが、金本位制から管理通貨制度への移行とともに、いずれの国でも不換銀行券となっている。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐けんがく【勤工倹学】
労働しながら勉強すること。第一次大戦期、周恩来・鄧小平など多くの中国青年がこの方法により、フランスなどで学んだ。
ぎんこう‐こぎって【銀行小切手】‥カウ‥
銀行の預金者から銀行に宛てて振り出される支払の委託書。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐しゅぎ【銀行主義】‥カウ‥
銀行券の発行に際し、正貨準備などの制限を設けず、自由に発行させても、兌換だかんが維持される限り、貨幣は決して過度に流通せず、物価は騰貴しないとする説。19世紀の初め、イギリスで唱えられた。↔通貨主義。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐じゅんびきん【銀行準備金】‥カウ‥
市中銀行が預金の支払いに備えて保有している資金。支払準備金。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐しんよう【銀行信用】‥カウ‥
銀行がその取引先に対して与える信用。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐せき【金紅石】
酸化チタンから成る鉱物。正方晶系、柱状結晶。赤褐色または黄赤色で、花崗岩・片麻へんま岩などの中に存する。ルチル。
きんこう‐せんにん【琴高仙人】‥カウ‥
(画題)中国、周代の仙人。琴の名手で、仙術を使い、鯉に乗って現れるという。
きんこうたい‐しょう【菌交代症】‥カウ‥シヤウ
抗生物質などの使用により、生体内に常在する菌種が減少・死滅し、それに代わって常時は少ない菌または他の菌種が増殖してひき起こされる病症。カンジダ症など。
ぎんこう‐てがた【銀行手形】‥カウ‥
銀行によって振り出され、または銀行が支払を引き受けた手形。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きん‐こうどう【金弘道】‥ダウ
朝鮮李朝の画家。金海の人。風俗画・山水画に優れる。代表作「風俗図帖」「騎驢聴鶯図」など。(1745〜1815以後)
きんこう‐のうぎょう【近郊農業】‥カウ‥ゲフ
都市近郊で行われる農業。消費地に近いので、主に高級生鮮食料品や花の生産が行われ、また、地価が高いので小規模集約的な経営が行われる。
⇒きん‐こう【近郊】
ぎんこう‐ほう【銀行法】‥カウハフ
普通銀行の免許・業務などを監督・規制する法律。1927年(昭和2)制定。81年に全面改正。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐ぼき【銀行簿記】‥カウ‥
複式簿記を銀行の業務に適用したもの。現金仕訳法と完全な伝票制を用い、多くの統括勘定を総勘定元帳に記載すること、日次にちじ残高試算表(日計表)を作成することなどが特徴。
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐もくぜつ【金口木舌】
(木舌はボクゼツとも)言説で社会を指導する人物。木鐸ぼくたく。
⇒きん‐こう【金口】
きんこう‐よさん【均衡予算】‥カウ‥
歳入(公債金を除く)と歳出とがつりあっていて、赤字がない予算のこと。
⇒きん‐こう【均衡】
きんこう‐りろん【均衡理論】‥カウ‥
〔経〕財・サービスの需要量・供給量・価格など、経済的諸変数の間の相互関係が安定した状態にあるための条件を分析することを中心とした経済理論。→一般均衡理論
⇒きん‐こう【均衡】
ぎんこう‐わりびき【銀行割引】‥カウ‥
手形などの割引をする際に、期日支払金額をもととして割引料を計算する方法。内うち割引。↔真しん割引
⇒ぎん‐こう【銀行】
きんこう‐わん【錦江湾】‥カウ‥
(→)鹿児島湾に同じ。
きんこ‐かぶ【金庫株】
(treasury stock)株式会社が発行後に再取得して保有する自己株式。株価維持などを目的とする。2001年の商法改正で原則自由化された。→貯蔵株。
⇒きん‐こ【金庫】
きんこきかん【今古奇観】‥クワン
中国の短編白話小説集。明末、抱甕ほうよう老人編。馮夢竜ひょうぼうりゅうの「三言」、凌濛初の「二拍」として集大成された小説から計40編を選ぶ。
きん‐こく【金穀】
金銭と穀物。金品。
きん‐こく【謹告】
(「つつしんでお知らせする」の意)公示の文章などの冒頭に用いる語。
きん‐ごく【近国】
①近くの国。
②律令制で、遠国おんごく・中国に対して京都に近い国々の称。延喜式では伊賀・伊勢・志摩・尾張・三河・丹波・丹後・因幡・備前・紀伊・近江・美濃・若狭・但馬・播磨・美作・淡路の17カ国。
きん‐ごく【禁国】
平安中期以後、食封じきふにあてることを禁じられた国。伊賀・伊勢・三河・近江・美濃・越中・石見・備前・周防・長門・紀伊・阿波など。
きん‐ごく【禁獄】
囚人を獄中に拘禁すること。禁牢。
ぎん‐ごけ【銀苔】
蘚類ハリガネゴケ科の一種。茎葉体は直立し、高さ1〜2センチメートル。葉の上半分が透明で、乾くと植物体全体が銀白色に見える。雌雄同株。世界各地に広く分布。
きんご‐こうい【金吾校尉】‥カウヰ
左右衛門尉えもんのじょうの唐名。
⇒きん‐ご【金吾】
きん‐こざね【金小札】
金箔塗りの小札こざね。
ぎん‐こざね【銀小札】
銀箔塗りの小札こざね。
きん‐こじ【金巾子】
①金箔を押した巾子紙こじがみ。
②「金巾子の冠」の略。
⇒きんこじ‐の‐かんむり【金巾子の冠】
きんご‐じしょう【金吾次将】‥シヤウ
左右衛門佐えもんのすけの唐名。
⇒きん‐ご【金吾】
きんこじ‐の‐かんむり【金巾子の冠】
金巾子をつけた冠。もと天皇の常用。御引直衣・紅袴着用の時に用いる。おきんこじのかんむり。きんこじ。
金巾子の冠
 ⇒きん‐こじ【金巾子】
きんごしゅう【琴後集】‥シフ
⇒ことじりしゅう
きんご‐しょうぐん【金吾将軍】‥シヤウ‥
衛門督えもんのかみの唐名。
⇒きん‐ご【金吾】
きん‐こじり【金鐺】
金または金色の金属で飾った鐺。
ぎん‐こじり【銀鐺】
銀または銀色の金属で飾った鐺。
きん‐こつ【金骨】
凡俗を脱した風骨。仙骨。太平記37「―返て本の肉身と成りしかば」
きん‐こつ【筋骨】
①筋肉と骨格。体格。「―たくましい青年」「―隆々」
②からだ。体力。
⇒きんこつ‐がた【筋骨型】
きんこつ‐がた【筋骨型】
〔心〕クレッチマーが提案した体型による気質分類の一つ。やせ型や肥り型に対して、筋骨の特に発達した体型で、気質的には粘着質が多い。闘士型ともいう。
⇒きん‐こつ【筋骨】
きんこ‐やぶり【金庫破り】
金庫をこわして中の財物を盗むこと。また、その人。
⇒きん‐こ【金庫】
きんこ‐りゅう【琴古流】‥リウ
尺八楽の一流派。18世紀後半に初世黒沢琴古が江戸で創始。都山流とざんりゅうと並ぶ二大流派。
きん‐こん【菌根】
菌類との複合体となった根。菌糸が高等植物の根に共生して形成される。養分の相互補給などが行われている。
きん‐こん【禁閫】
(「閫」は、しきみの意)禁裏の門。転じて、禁裏。御所。
きん‐こん【緊褌】
褌ふんどしをしっかりしめること。
⇒きんこん‐いちばん【緊褌一番】
ぎん‐こん【吟魂】
詩人のうた心。詩情。吟情。
きんこん‐いちばん【緊褌一番】
心を大いに引きしめて、ふるいたって事に当たること。
⇒きん‐こん【緊褌】
きんこん‐しき【金婚式】
(golden wedding)夫婦が結婚後、50年目に行う記念祝賀の式。→結婚記念日(表)
ぎんこん‐しき【銀婚式】
(silver wedding)夫婦が結婚後、25年目に行う記念祝賀の式。→結婚記念日(表)
きん‐さ【欽差】
(「差」は、つかわす意)天子の命令で使者をおくること。また、その使者。
⇒きんさ‐だいじん【欽差大臣】
きん‐さ【僅差】
ほんの少しの差。「―で敗れる」
きん‐ざ【金座】
江戸幕府直轄の、金貨の鋳造・鑑定・発行所。初め江戸・駿府・佐渡・京都の4カ所にあったが、江戸常磐橋門外(中央区本石町二丁目、今の日本銀行の地)の江戸座以外は、中期までに廃止または縮小された。勘定奉行の支配。長を金改役といい、後藤家が世襲。狭義の金座は座人の事務所で、勘定場・天秤前・出来方色改場に分かれ、別に吹所ふきしょと呼ばれた鋳造工場が付属していた。1868年(明治1)封鎖され廃止。
ぎん‐ざ【銀座】
江戸幕府直轄の、銀貨の鋳造・発行所。初め伏見・駿府に設置したが、まもなく京都・江戸に移し、また大坂・長崎にも設置。1800年(寛政12)不正事件のため四座ともに廃止し、江戸1カ所のみ再興。銀貨の極印・包装は大黒常是だいこくじょうぜ家が世襲。68年(明治1)封鎖され廃止。(地名別項)
ぎんざ【銀座】
東京都中央区の繁華街。京橋から新橋まで北東から南西に延びる街路を中心として高級店が並ぶ。駿府の銀座を1612年(慶長17)にここに移したためこの名が残った。地方都市でも繁華な街区を「…銀座」と土地の名を冠していう。
きん‐さい【金釵】
金製のかんざし。
きん‐ざい【近在】
都市に近い村里。「近郷―」
ぎん‐さい【銀釵】
銀製のかんざし。
きん‐さいきん【金再禁】
いったん金輸出禁止を解いた(金解禁)後、再び金輸出を禁ずること。
きんさき‐ぼり【斤先掘り】
鉱業権者が第三者と私的貸借契約を結び、採掘事業を請け負わせること。→租鉱権
きん‐さく【近作】
最近作った作品。特に文学・芸術作品などにいう。
きん‐さく【金策】
さまざまに工夫して入用なかねをととのえること。「―に駆けずり回る」
きん‐さく【金錯】
金属器の表面に金で文様や文字を象嵌ぞうがんし、または塗ったもの。
ぎん‐ざけ【銀鮭】
サケ科の硬骨魚。サケに似るが、頭や体の背面に多数の小黒点がある。川で孵化、数年して春に海に降りて成熟。このとき体色が青緑から銀灰色に変わる(銀毛あるいは銀化ぎんげ)。北太平洋に分布。美味。
ぎん‐ささげ【銀豇豆】
隠元豆の別称。
きんさ‐だいじん【欽差大臣】
清代、官制に定めのない臨時特設の官職の一つ。皇帝から臨時に権限を与えられ、特定事項の処理にあたった三品以上の官。略称、欽使。外国へ派遣される外交官にもこの称を用いた。
⇒きん‐さ【欽差】
きん‐さつ【金札】
①金製または金色の札。謡曲、金札「天より―の降り下りて候」
②閻魔えんまの庁で、善人を極楽に送る時の金製の札。金紙。↔鉄札。
③金貨に代わるべき紙幣。
㋐江戸時代、諸藩で発行した金貨代用の藩札。
㋑明治初年発行の紙幣。太政官だじょうかん金札・民部省金札がある。
きんさつ【金札】
能。観阿弥作の神物。平安遷都に際し、伏見に神社を造営すると、天から金札が降り、神が太平を祝福する。
きん‐さつ【禁札】
禁止する事柄を記した立てふだ。制札。
きん‐さつ【禁殺】
禁錮して殺すこと。おしこめて殺すこと。太平記14「兵部卿親王を―し奉る由」
ぎん‐さつ【銀札】
①銀製または銀色の札。
②江戸時代、諸藩で発行した銀貨代用の紙幣。
ぎん‐ざめ【銀鮫】
ギンザメ科の海産の軟骨魚。全長約1〜2メートル。頭が大きく、尾は細長く、尾びれは糸状。雄の腹びれには交接器がある。体には銀色の光沢がある。太平洋岸の深所に産する。銀鱶ぎんぶか。
ギンザメ
提供:東京動物園協会
⇒きん‐こじ【金巾子】
きんごしゅう【琴後集】‥シフ
⇒ことじりしゅう
きんご‐しょうぐん【金吾将軍】‥シヤウ‥
衛門督えもんのかみの唐名。
⇒きん‐ご【金吾】
きん‐こじり【金鐺】
金または金色の金属で飾った鐺。
ぎん‐こじり【銀鐺】
銀または銀色の金属で飾った鐺。
きん‐こつ【金骨】
凡俗を脱した風骨。仙骨。太平記37「―返て本の肉身と成りしかば」
きん‐こつ【筋骨】
①筋肉と骨格。体格。「―たくましい青年」「―隆々」
②からだ。体力。
⇒きんこつ‐がた【筋骨型】
きんこつ‐がた【筋骨型】
〔心〕クレッチマーが提案した体型による気質分類の一つ。やせ型や肥り型に対して、筋骨の特に発達した体型で、気質的には粘着質が多い。闘士型ともいう。
⇒きん‐こつ【筋骨】
きんこ‐やぶり【金庫破り】
金庫をこわして中の財物を盗むこと。また、その人。
⇒きん‐こ【金庫】
きんこ‐りゅう【琴古流】‥リウ
尺八楽の一流派。18世紀後半に初世黒沢琴古が江戸で創始。都山流とざんりゅうと並ぶ二大流派。
きん‐こん【菌根】
菌類との複合体となった根。菌糸が高等植物の根に共生して形成される。養分の相互補給などが行われている。
きん‐こん【禁閫】
(「閫」は、しきみの意)禁裏の門。転じて、禁裏。御所。
きん‐こん【緊褌】
褌ふんどしをしっかりしめること。
⇒きんこん‐いちばん【緊褌一番】
ぎん‐こん【吟魂】
詩人のうた心。詩情。吟情。
きんこん‐いちばん【緊褌一番】
心を大いに引きしめて、ふるいたって事に当たること。
⇒きん‐こん【緊褌】
きんこん‐しき【金婚式】
(golden wedding)夫婦が結婚後、50年目に行う記念祝賀の式。→結婚記念日(表)
ぎんこん‐しき【銀婚式】
(silver wedding)夫婦が結婚後、25年目に行う記念祝賀の式。→結婚記念日(表)
きん‐さ【欽差】
(「差」は、つかわす意)天子の命令で使者をおくること。また、その使者。
⇒きんさ‐だいじん【欽差大臣】
きん‐さ【僅差】
ほんの少しの差。「―で敗れる」
きん‐ざ【金座】
江戸幕府直轄の、金貨の鋳造・鑑定・発行所。初め江戸・駿府・佐渡・京都の4カ所にあったが、江戸常磐橋門外(中央区本石町二丁目、今の日本銀行の地)の江戸座以外は、中期までに廃止または縮小された。勘定奉行の支配。長を金改役といい、後藤家が世襲。狭義の金座は座人の事務所で、勘定場・天秤前・出来方色改場に分かれ、別に吹所ふきしょと呼ばれた鋳造工場が付属していた。1868年(明治1)封鎖され廃止。
ぎん‐ざ【銀座】
江戸幕府直轄の、銀貨の鋳造・発行所。初め伏見・駿府に設置したが、まもなく京都・江戸に移し、また大坂・長崎にも設置。1800年(寛政12)不正事件のため四座ともに廃止し、江戸1カ所のみ再興。銀貨の極印・包装は大黒常是だいこくじょうぜ家が世襲。68年(明治1)封鎖され廃止。(地名別項)
ぎんざ【銀座】
東京都中央区の繁華街。京橋から新橋まで北東から南西に延びる街路を中心として高級店が並ぶ。駿府の銀座を1612年(慶長17)にここに移したためこの名が残った。地方都市でも繁華な街区を「…銀座」と土地の名を冠していう。
きん‐さい【金釵】
金製のかんざし。
きん‐ざい【近在】
都市に近い村里。「近郷―」
ぎん‐さい【銀釵】
銀製のかんざし。
きん‐さいきん【金再禁】
いったん金輸出禁止を解いた(金解禁)後、再び金輸出を禁ずること。
きんさき‐ぼり【斤先掘り】
鉱業権者が第三者と私的貸借契約を結び、採掘事業を請け負わせること。→租鉱権
きん‐さく【近作】
最近作った作品。特に文学・芸術作品などにいう。
きん‐さく【金策】
さまざまに工夫して入用なかねをととのえること。「―に駆けずり回る」
きん‐さく【金錯】
金属器の表面に金で文様や文字を象嵌ぞうがんし、または塗ったもの。
ぎん‐ざけ【銀鮭】
サケ科の硬骨魚。サケに似るが、頭や体の背面に多数の小黒点がある。川で孵化、数年して春に海に降りて成熟。このとき体色が青緑から銀灰色に変わる(銀毛あるいは銀化ぎんげ)。北太平洋に分布。美味。
ぎん‐ささげ【銀豇豆】
隠元豆の別称。
きんさ‐だいじん【欽差大臣】
清代、官制に定めのない臨時特設の官職の一つ。皇帝から臨時に権限を与えられ、特定事項の処理にあたった三品以上の官。略称、欽使。外国へ派遣される外交官にもこの称を用いた。
⇒きん‐さ【欽差】
きん‐さつ【金札】
①金製または金色の札。謡曲、金札「天より―の降り下りて候」
②閻魔えんまの庁で、善人を極楽に送る時の金製の札。金紙。↔鉄札。
③金貨に代わるべき紙幣。
㋐江戸時代、諸藩で発行した金貨代用の藩札。
㋑明治初年発行の紙幣。太政官だじょうかん金札・民部省金札がある。
きんさつ【金札】
能。観阿弥作の神物。平安遷都に際し、伏見に神社を造営すると、天から金札が降り、神が太平を祝福する。
きん‐さつ【禁札】
禁止する事柄を記した立てふだ。制札。
きん‐さつ【禁殺】
禁錮して殺すこと。おしこめて殺すこと。太平記14「兵部卿親王を―し奉る由」
ぎん‐さつ【銀札】
①銀製または銀色の札。
②江戸時代、諸藩で発行した銀貨代用の紙幣。
ぎん‐ざめ【銀鮫】
ギンザメ科の海産の軟骨魚。全長約1〜2メートル。頭が大きく、尾は細長く、尾びれは糸状。雄の腹びれには交接器がある。体には銀色の光沢がある。太平洋岸の深所に産する。銀鱶ぎんぶか。
ギンザメ
提供:東京動物園協会
 きん‐ザラサ【金更紗】
金泥で模様を彩色した更紗。
ぎん‐ザラサ【銀更紗】
銀泥で模様を彩色した更紗。
きん‐さん【菌傘】
きのこの、傘状の部分。裏面には多数のひだ(菌褶きんしゅう)または小孔があって、胞子を発生させ、繁殖の用をなす。かさ。菌帽。菌蓋。蓋。→きのこ
きん‐ざん【金山】
①金鉱石を埋蔵・産出する鉱山。
②金属で造ったような堅固な山。
③アルタイ山の異称。
⇒きんざん‐てっぺき【金山鉄壁】
ぎん‐ざん【銀山】
銀鉱石を埋蔵・産出する鉱山。
ぎんざん‐おんせん【銀山温泉】‥ヲン‥
山形県尾花沢市、銀山川沿いにある温泉。泉質は塩化物泉。
きんざん‐じ【径山寺】
中国五山の一つ。浙江省臨安市天目山の北東峰にある。8世紀中頃法欽の開創。禅の道場として栄える。興聖万寿禅寺。
⇒きんざんじ‐みそ【径山寺味噌・金山寺味噌】
きんざん‐じ【金山寺】
①朝鮮全羅北道金堤郡母岳山中の仏寺。百済時代(599年)の創建。新羅様式の六重石塔・五角多層石塔・舎利塔がある。
②中国江蘇省鎮江市にある仏寺。東晋時代の開創。宋代以後、江南における文人の遊行所。八角七層の塔は明・清時代の再建。
きんざんじ‐みそ【径山寺味噌・金山寺味噌】
(中国の径山寺の製法を伝えたのでこの名があるという)嘗味噌なめみその一種。大豆と大麦の麹こうじに塩を加え、これに細かく刻んだ茄子・瓜などを入れ、密閉して熟成させたもの。和歌山県有田郡湯浅町の名産。熟成後、砂糖や水飴などで調味することがある。
⇒きんざん‐じ【径山寺】
きんざん‐てっぺき【金山鉄壁】
(→)金城鉄壁に同じ。
⇒きん‐ざん【金山】
きん‐し【近思】
自分の身に省みて考えてみること。
きん‐し【近視】
(myopia)眼の水晶体の焦点距離が短すぎる、あるいは網膜に至る距離が長すぎるため、遠方の物体が網膜より前方に像を結び、そのため鮮明に物を見ることができないこと。凹レンズによって矯正。近視眼。近眼。ちかめ。↔遠視。
⇒きんし‐がん【近視眼】
⇒きんしがん‐てき【近視眼的】
きんし【金史】
二十四史の一つ。金の史書。本紀19巻、志39巻、表4巻、列伝73巻。元の托克托トクトすなわち脱脱らが奉勅撰。1344年成る。
きん‐し【金糸】
①銀または銅の針金に金着きんきせした細い金属線。または、金箔をおいた薄い紙を細く切ったもの、金箔を糸によりつけたもの。細く切ったものを「ひらきん」、よったものを「よりきん」という。金襴きんらんを織る時や、刺繍その他種々の飾り物に用いる。
②堆朱ついしゅの一種。色赤く、彫目厚く、彫目に黄色漆と赤色漆とを塗り重ねたもの。
③皮を除いて精製した繊維の太いフカのひれを1本ずつ糸状にほぐしたもの。
⇒きんし‐こう【金糸猴】
⇒きんし‐ごぼう【金糸牛蒡・錦糸牛蒡】
⇒きんし‐こんぶ【金糸昆布】
⇒きんし‐たまご【金糸卵・錦糸卵】
⇒きんし‐とう【金糸桃】
⇒きんし‐ばい【金糸梅】
きん‐し【金紙】
①金箔を押したり金泥を塗ったりした紙。
②(→)金札きんさつ2に同じ。謡曲、鵜飼「―を汚すこともなく」
きん‐し【金紫】
①金印と紫綬。
②転じて、それを帯びる者。高官。
きん‐し【金鵄】
神武天皇東征の時に、弓の先にとまったという金色のトビ。
⇒きんし‐くんしょう【金鵄勲章】
きん‐し【菌糸】
菌類の体を構成する本体で、繊細な糸状の細胞または細胞列。
きん‐し【勤仕】
勤め仕えること。
きん‐し【禁止】
禁じとどめること。することを許さないこと。禁制。法度はっと。「立入りを―する」「駐車―」
⇒きんし‐えいぎょう【禁止営業】
⇒きんし‐かんぜい【禁止関税】
⇒きんし‐きてい【禁止規定】
⇒きんし‐ぎょぎょう【禁止漁業】
⇒きんし‐ぜい【禁止税】
⇒きんし‐ちょう【禁止鳥】
⇒きんし‐ほう【禁止法】
⇒きんし‐ぼん【禁止本】
きん‐じ【近似】
ものごとが非常によく似通っていること。へだたりがほとんどないこと。「幕末の日本に―している」
⇒きんじ‐けいさん【近似計算】
⇒きんじ‐ち【近似値】
きん‐じ【近事】
近ごろのできごと。最近起きた事件。
きん‐じ【近侍】
主君のそば近く仕えること。また、その人。おそば。扈従こしょう。
⇒きんじ‐の‐ひと【近侍の人】
きん‐じ【近時】
近ごろ。このごろ。↔往時
きん‐じ【金地】‥ヂ
金箔・金泥をおいた布・紙など。金色の地。
きん‐じ【金字】
金泥きんでいで書いた文字。また、金色の文字。
⇒きんじ‐とう【金字塔】
きん‐じ【矜恃】
(キョウジの慣用読み)
⇒きょうじ
きんじ【君】キンヂ
〔代〕
(二人称。キミムチ(君貴)の転。本来は敬意を表したが、のちには多く目下の者にいう)きみ。源氏物語少女「―は同じ年なれど」
ぎん‐し【銀糸】
①銀箔を薄紙に押したのを細く切ったもの、またはそれを糸によりつけたもの。細く切ったのを「ひらぎん」、よったのを「よりぎん」という。装飾用。
②(→)金糸きんし3に同じ。
ぎん‐じ【銀地】‥ヂ
銀箔・銀泥をおいた布・紙など。銀色の地。
ぎん‐じ【銀字】
銀泥で書いた文字。また、銀色の文字。
きんし‐えいぎょう【禁止営業】‥ゲフ
行政上または財政上の目的から禁止した営業。売春・猥褻わいせつ文書図画販売、貨幣・紙幣・国債証券に紛らわしいものの製造・販売など。
⇒きん‐し【禁止】
きんし‐がん【近視眼】
近視の眼。近眼。近視。
⇒きん‐し【近視】
きんし‐かんぜい【禁止関税】‥クワン‥
事実上、輸入禁止制度とほとんど同様の効果を発揮する保護主義輸入関税。禁止税。
⇒きん‐し【禁止】
きんしがん‐てき【近視眼的】
近いところ、狭いところにだけ気をとられて、大局の見通しのないさま。「―な施策」
⇒きん‐し【近視】
きんしかん‐やく【筋弛緩薬】‥クワン‥
筋肉の緊張を緩和する薬物。神経筋接合部や骨格筋に作用する末梢性のものと、脳や脊髄に作用する中枢性のものとがある。
きん‐じき【禁色】
①位階により袍ほうの色の規定があって、上位の位色いしょくの使用を禁じられたこと。また、その色。天皇以下公卿以上所用の袍の色、すなわち黄櫨染こうろぜん・麹塵きくじん・赤色・黄丹色・深紫色などを殿上人以下の諸臣が用いることは禁じられた。続日本紀37「恣ほしいままに―を着て、既に貴賤の殊わかち無く」↔許色ゆるしいろ。
②有文うもんの織物・表袴うえのはかまに、霰地あられじに窠かの文のある浮織物うきおりものを禁じられたこと。
⇒きんじき‐せんげ【禁色宣下】
⇒きんじき‐の‐ひと【禁色の人】
きんじき‐せんげ【禁色宣下】
禁色を用いることを許す宣旨せんじを下すこと。
⇒きん‐じき【禁色】
きんし‐きてい【禁止規定】
一定の行為を禁止する規定。警察の取締規則の類。
⇒きん‐し【禁止】
きんじき‐の‐ひと【禁色の人】
禁色を許された人。
⇒きん‐じき【禁色】
きんし‐ぎょぎょう【禁止漁業】‥ゲフ
水産動植物の繁殖保護などのために、場所・方法・時期・漁船などにつき法律で禁止する漁業。
⇒きん‐し【禁止】
きんし‐ぎょくよう【金枝玉葉】‥エフ
(「金玉の枝葉」の意。枝葉は子孫)天子の一門。皇族。
きんじきんほんい‐せい【金地金本位制】‥ヂ‥ヰ‥
(gold bullion standard)金本位制度の一つ。金の基礎の上に立つが、金貨を市場に流通させず、国内では紙幣・銀貨などを用い、金準備はもっぱら対外的支払のために政府または中央銀行に集中保有され、兌換だかんに際しては金地金を与える貨幣制度。
きんし‐くんしょう【金鵄勲章】‥シヤウ
武功抜群の陸海軍軍人に下賜された勲章。功1級から功7級まで。1890年(明治23)制定。年金または一時金の支給を伴う。1947年廃止。正岡子規、鶴物語「―といふものを朝日に輝かせあたりを払ひて参る」
⇒きん‐し【金鵄】
きんじ‐けいさん【近似計算】
真の値に近い値を算出すること。
⇒きん‐じ【近似】
きんし‐こう【金糸猴】
オナガザル科の哺乳類。ニホンザルよりやや小形で、金色の細く美しい毛を持つ。中国南西部と北西部の極めて限られた地域に分布。貴重な動物とされる。シシバナザル。ゴールデンモンキー。チベットコバナテングザル。イボハナザル。
キンシコウ(雄)
提供:東京動物園協会
きん‐ザラサ【金更紗】
金泥で模様を彩色した更紗。
ぎん‐ザラサ【銀更紗】
銀泥で模様を彩色した更紗。
きん‐さん【菌傘】
きのこの、傘状の部分。裏面には多数のひだ(菌褶きんしゅう)または小孔があって、胞子を発生させ、繁殖の用をなす。かさ。菌帽。菌蓋。蓋。→きのこ
きん‐ざん【金山】
①金鉱石を埋蔵・産出する鉱山。
②金属で造ったような堅固な山。
③アルタイ山の異称。
⇒きんざん‐てっぺき【金山鉄壁】
ぎん‐ざん【銀山】
銀鉱石を埋蔵・産出する鉱山。
ぎんざん‐おんせん【銀山温泉】‥ヲン‥
山形県尾花沢市、銀山川沿いにある温泉。泉質は塩化物泉。
きんざん‐じ【径山寺】
中国五山の一つ。浙江省臨安市天目山の北東峰にある。8世紀中頃法欽の開創。禅の道場として栄える。興聖万寿禅寺。
⇒きんざんじ‐みそ【径山寺味噌・金山寺味噌】
きんざん‐じ【金山寺】
①朝鮮全羅北道金堤郡母岳山中の仏寺。百済時代(599年)の創建。新羅様式の六重石塔・五角多層石塔・舎利塔がある。
②中国江蘇省鎮江市にある仏寺。東晋時代の開創。宋代以後、江南における文人の遊行所。八角七層の塔は明・清時代の再建。
きんざんじ‐みそ【径山寺味噌・金山寺味噌】
(中国の径山寺の製法を伝えたのでこの名があるという)嘗味噌なめみその一種。大豆と大麦の麹こうじに塩を加え、これに細かく刻んだ茄子・瓜などを入れ、密閉して熟成させたもの。和歌山県有田郡湯浅町の名産。熟成後、砂糖や水飴などで調味することがある。
⇒きんざん‐じ【径山寺】
きんざん‐てっぺき【金山鉄壁】
(→)金城鉄壁に同じ。
⇒きん‐ざん【金山】
きん‐し【近思】
自分の身に省みて考えてみること。
きん‐し【近視】
(myopia)眼の水晶体の焦点距離が短すぎる、あるいは網膜に至る距離が長すぎるため、遠方の物体が網膜より前方に像を結び、そのため鮮明に物を見ることができないこと。凹レンズによって矯正。近視眼。近眼。ちかめ。↔遠視。
⇒きんし‐がん【近視眼】
⇒きんしがん‐てき【近視眼的】
きんし【金史】
二十四史の一つ。金の史書。本紀19巻、志39巻、表4巻、列伝73巻。元の托克托トクトすなわち脱脱らが奉勅撰。1344年成る。
きん‐し【金糸】
①銀または銅の針金に金着きんきせした細い金属線。または、金箔をおいた薄い紙を細く切ったもの、金箔を糸によりつけたもの。細く切ったものを「ひらきん」、よったものを「よりきん」という。金襴きんらんを織る時や、刺繍その他種々の飾り物に用いる。
②堆朱ついしゅの一種。色赤く、彫目厚く、彫目に黄色漆と赤色漆とを塗り重ねたもの。
③皮を除いて精製した繊維の太いフカのひれを1本ずつ糸状にほぐしたもの。
⇒きんし‐こう【金糸猴】
⇒きんし‐ごぼう【金糸牛蒡・錦糸牛蒡】
⇒きんし‐こんぶ【金糸昆布】
⇒きんし‐たまご【金糸卵・錦糸卵】
⇒きんし‐とう【金糸桃】
⇒きんし‐ばい【金糸梅】
きん‐し【金紙】
①金箔を押したり金泥を塗ったりした紙。
②(→)金札きんさつ2に同じ。謡曲、鵜飼「―を汚すこともなく」
きん‐し【金紫】
①金印と紫綬。
②転じて、それを帯びる者。高官。
きん‐し【金鵄】
神武天皇東征の時に、弓の先にとまったという金色のトビ。
⇒きんし‐くんしょう【金鵄勲章】
きん‐し【菌糸】
菌類の体を構成する本体で、繊細な糸状の細胞または細胞列。
きん‐し【勤仕】
勤め仕えること。
きん‐し【禁止】
禁じとどめること。することを許さないこと。禁制。法度はっと。「立入りを―する」「駐車―」
⇒きんし‐えいぎょう【禁止営業】
⇒きんし‐かんぜい【禁止関税】
⇒きんし‐きてい【禁止規定】
⇒きんし‐ぎょぎょう【禁止漁業】
⇒きんし‐ぜい【禁止税】
⇒きんし‐ちょう【禁止鳥】
⇒きんし‐ほう【禁止法】
⇒きんし‐ぼん【禁止本】
きん‐じ【近似】
ものごとが非常によく似通っていること。へだたりがほとんどないこと。「幕末の日本に―している」
⇒きんじ‐けいさん【近似計算】
⇒きんじ‐ち【近似値】
きん‐じ【近事】
近ごろのできごと。最近起きた事件。
きん‐じ【近侍】
主君のそば近く仕えること。また、その人。おそば。扈従こしょう。
⇒きんじ‐の‐ひと【近侍の人】
きん‐じ【近時】
近ごろ。このごろ。↔往時
きん‐じ【金地】‥ヂ
金箔・金泥をおいた布・紙など。金色の地。
きん‐じ【金字】
金泥きんでいで書いた文字。また、金色の文字。
⇒きんじ‐とう【金字塔】
きん‐じ【矜恃】
(キョウジの慣用読み)
⇒きょうじ
きんじ【君】キンヂ
〔代〕
(二人称。キミムチ(君貴)の転。本来は敬意を表したが、のちには多く目下の者にいう)きみ。源氏物語少女「―は同じ年なれど」
ぎん‐し【銀糸】
①銀箔を薄紙に押したのを細く切ったもの、またはそれを糸によりつけたもの。細く切ったのを「ひらぎん」、よったのを「よりぎん」という。装飾用。
②(→)金糸きんし3に同じ。
ぎん‐じ【銀地】‥ヂ
銀箔・銀泥をおいた布・紙など。銀色の地。
ぎん‐じ【銀字】
銀泥で書いた文字。また、銀色の文字。
きんし‐えいぎょう【禁止営業】‥ゲフ
行政上または財政上の目的から禁止した営業。売春・猥褻わいせつ文書図画販売、貨幣・紙幣・国債証券に紛らわしいものの製造・販売など。
⇒きん‐し【禁止】
きんし‐がん【近視眼】
近視の眼。近眼。近視。
⇒きん‐し【近視】
きんし‐かんぜい【禁止関税】‥クワン‥
事実上、輸入禁止制度とほとんど同様の効果を発揮する保護主義輸入関税。禁止税。
⇒きん‐し【禁止】
きんしがん‐てき【近視眼的】
近いところ、狭いところにだけ気をとられて、大局の見通しのないさま。「―な施策」
⇒きん‐し【近視】
きんしかん‐やく【筋弛緩薬】‥クワン‥
筋肉の緊張を緩和する薬物。神経筋接合部や骨格筋に作用する末梢性のものと、脳や脊髄に作用する中枢性のものとがある。
きん‐じき【禁色】
①位階により袍ほうの色の規定があって、上位の位色いしょくの使用を禁じられたこと。また、その色。天皇以下公卿以上所用の袍の色、すなわち黄櫨染こうろぜん・麹塵きくじん・赤色・黄丹色・深紫色などを殿上人以下の諸臣が用いることは禁じられた。続日本紀37「恣ほしいままに―を着て、既に貴賤の殊わかち無く」↔許色ゆるしいろ。
②有文うもんの織物・表袴うえのはかまに、霰地あられじに窠かの文のある浮織物うきおりものを禁じられたこと。
⇒きんじき‐せんげ【禁色宣下】
⇒きんじき‐の‐ひと【禁色の人】
きんじき‐せんげ【禁色宣下】
禁色を用いることを許す宣旨せんじを下すこと。
⇒きん‐じき【禁色】
きんし‐きてい【禁止規定】
一定の行為を禁止する規定。警察の取締規則の類。
⇒きん‐し【禁止】
きんじき‐の‐ひと【禁色の人】
禁色を許された人。
⇒きん‐じき【禁色】
きんし‐ぎょぎょう【禁止漁業】‥ゲフ
水産動植物の繁殖保護などのために、場所・方法・時期・漁船などにつき法律で禁止する漁業。
⇒きん‐し【禁止】
きんし‐ぎょくよう【金枝玉葉】‥エフ
(「金玉の枝葉」の意。枝葉は子孫)天子の一門。皇族。
きんじきんほんい‐せい【金地金本位制】‥ヂ‥ヰ‥
(gold bullion standard)金本位制度の一つ。金の基礎の上に立つが、金貨を市場に流通させず、国内では紙幣・銀貨などを用い、金準備はもっぱら対外的支払のために政府または中央銀行に集中保有され、兌換だかんに際しては金地金を与える貨幣制度。
きんし‐くんしょう【金鵄勲章】‥シヤウ
武功抜群の陸海軍軍人に下賜された勲章。功1級から功7級まで。1890年(明治23)制定。年金または一時金の支給を伴う。1947年廃止。正岡子規、鶴物語「―といふものを朝日に輝かせあたりを払ひて参る」
⇒きん‐し【金鵄】
きんじ‐けいさん【近似計算】
真の値に近い値を算出すること。
⇒きん‐じ【近似】
きんし‐こう【金糸猴】
オナガザル科の哺乳類。ニホンザルよりやや小形で、金色の細く美しい毛を持つ。中国南西部と北西部の極めて限られた地域に分布。貴重な動物とされる。シシバナザル。ゴールデンモンキー。チベットコバナテングザル。イボハナザル。
キンシコウ(雄)
提供:東京動物園協会
 キンシコウ(雌)
提供:東京動物園協会
キンシコウ(雌)
提供:東京動物園協会
 ⇒きん‐し【金糸】
きんし‐ごぼう【金糸牛蒡・錦糸牛蒡】‥バウ
牛蒡を針のように細くきざみ、油で炒りつけたもの。汁物の材料とする。
⇒きん‐し【金糸】
きんし‐こんぶ【金糸昆布】
昆布の中心部だけを取って細く金糸状に切ったもの。料理の口取に用いる。切水晶昆布。
⇒きん‐し【金糸】
きん‐じさ【均時差】
真太陽時と平均太陽時との差。すなわち、真の太陽と仮想の平均太陽との時角の差。時差率。時差。
きん‐しじょう【金市場】‥ヂヤウ
世界的貨幣であると同時に世界的商品である金の取引が行われる市場。ロンドン金市場が有名。
きん‐ジストロフィー‐しょう【筋ジストロフィー症】‥シヤウ
(muscular dystrophy)筋肉の萎縮と脱力が徐々に進行し、歩行や運動が困難となる疾病。進行性筋ジストロフィー症と筋緊張性ジストロフィー症とがある。
きんし‐ぜい【禁止税】
(→)禁止関税に同じ。
⇒きん‐し【禁止】
きんし‐たまご【金糸卵・錦糸卵】
薄い卵焼きを細く切ったもの。
⇒きん‐し【金糸】
きんじ‐ち【近似値】
近似計算により得られる数値。例えば、3.1416は円周率(π)の近似値で、誤差は0.0001より小さい。
⇒きん‐じ【近似】
きんし‐ちょう【禁止鳥】‥テウ
(→)禁鳥に同じ。
⇒きん‐し【禁止】
きん‐しつ【均質】
性質が同じであること。一つの物体中のどの部分をとっても、成分・性質の一定していること。等質。「―な製品」
きん‐しつ【金漆】
奈良・平安時代に、金属や革に塗られた乾性の樹脂。コシアブラ(またはゴンゼツ)の実をしぼって濾こしたもの。続日本紀宝亀8年5月23日「―一缶・漆一缶…」
きん‐しつ【琴瑟】
琴ことと瑟おおごと。
⇒琴瑟相和す
きん‐じつ【近日】
今より後、程遠くない日。近いうち。ちかぢか。「―中にうかがいます」「―開店」
⇒きん‐し【金糸】
きんし‐ごぼう【金糸牛蒡・錦糸牛蒡】‥バウ
牛蒡を針のように細くきざみ、油で炒りつけたもの。汁物の材料とする。
⇒きん‐し【金糸】
きんし‐こんぶ【金糸昆布】
昆布の中心部だけを取って細く金糸状に切ったもの。料理の口取に用いる。切水晶昆布。
⇒きん‐し【金糸】
きん‐じさ【均時差】
真太陽時と平均太陽時との差。すなわち、真の太陽と仮想の平均太陽との時角の差。時差率。時差。
きん‐しじょう【金市場】‥ヂヤウ
世界的貨幣であると同時に世界的商品である金の取引が行われる市場。ロンドン金市場が有名。
きん‐ジストロフィー‐しょう【筋ジストロフィー症】‥シヤウ
(muscular dystrophy)筋肉の萎縮と脱力が徐々に進行し、歩行や運動が困難となる疾病。進行性筋ジストロフィー症と筋緊張性ジストロフィー症とがある。
きんし‐ぜい【禁止税】
(→)禁止関税に同じ。
⇒きん‐し【禁止】
きんし‐たまご【金糸卵・錦糸卵】
薄い卵焼きを細く切ったもの。
⇒きん‐し【金糸】
きんじ‐ち【近似値】
近似計算により得られる数値。例えば、3.1416は円周率(π)の近似値で、誤差は0.0001より小さい。
⇒きん‐じ【近似】
きんし‐ちょう【禁止鳥】‥テウ
(→)禁鳥に同じ。
⇒きん‐し【禁止】
きん‐しつ【均質】
性質が同じであること。一つの物体中のどの部分をとっても、成分・性質の一定していること。等質。「―な製品」
きん‐しつ【金漆】
奈良・平安時代に、金属や革に塗られた乾性の樹脂。コシアブラ(またはゴンゼツ)の実をしぼって濾こしたもの。続日本紀宝亀8年5月23日「―一缶・漆一缶…」
きん‐しつ【琴瑟】
琴ことと瑟おおごと。
⇒琴瑟相和す
きん‐じつ【近日】
今より後、程遠くない日。近いうち。ちかぢか。「―中にうかがいます」「―開店」
こん‐げん【金言】🔗⭐🔉
こん‐げん【金言】
〔仏〕金口こんくすなわち仏陀の口から出た不滅の教え。きんげん。
広辞苑に「金言」で始まるの検索結果 1-3。