複数辞典一括検索+![]()
![]()
杷 え🔗⭐🔉
【杷】
 8画 木部
区点=3939 16進=4747 シフトJIS=9466
《音読み》 ハ
8画 木部
区点=3939 16進=4747 シフトJIS=9466
《音読み》 ハ /ベ
/ベ 〈p
〈p 〉
《訓読み》 さらい(さらひ)/え
《意味》
〉
《訓読み》 さらい(さらひ)/え
《意味》
 {名}さらい(サラヒ)。土をならしたり、穀物をかきあつめたりするのに用いる農具。〈類義語〉→耙ハ。
{名}さらい(サラヒ)。土をならしたり、穀物をかきあつめたりするのに用いる農具。〈類義語〉→耙ハ。
 {名}え。物のえ。つか。
{名}え。物のえ。つか。
 「枇杷ビワ」とは、(イ)楽器の名。琵琶ビワ。(ロ)果樹の名。楽器の琵琶の形に似ていることから呼ぶようになった。
《解字》
会意兼形声。「木+音符巴ハ(平らにのばす)」。土の面を平らにのばす木の柄つきの農具。
《単語家族》
把(てのひらで持つ)
「枇杷ビワ」とは、(イ)楽器の名。琵琶ビワ。(ロ)果樹の名。楽器の琵琶の形に似ていることから呼ぶようになった。
《解字》
会意兼形声。「木+音符巴ハ(平らにのばす)」。土の面を平らにのばす木の柄つきの農具。
《単語家族》
把(てのひらで持つ) 耙ハ(地面を平らにならす)と同系。
耙ハ(地面を平らにならす)と同系。
 8画 木部
区点=3939 16進=4747 シフトJIS=9466
《音読み》 ハ
8画 木部
区点=3939 16進=4747 シフトJIS=9466
《音読み》 ハ /ベ
/ベ 〈p
〈p 〉
《訓読み》 さらい(さらひ)/え
《意味》
〉
《訓読み》 さらい(さらひ)/え
《意味》
 {名}さらい(サラヒ)。土をならしたり、穀物をかきあつめたりするのに用いる農具。〈類義語〉→耙ハ。
{名}さらい(サラヒ)。土をならしたり、穀物をかきあつめたりするのに用いる農具。〈類義語〉→耙ハ。
 {名}え。物のえ。つか。
{名}え。物のえ。つか。
 「枇杷ビワ」とは、(イ)楽器の名。琵琶ビワ。(ロ)果樹の名。楽器の琵琶の形に似ていることから呼ぶようになった。
《解字》
会意兼形声。「木+音符巴ハ(平らにのばす)」。土の面を平らにのばす木の柄つきの農具。
《単語家族》
把(てのひらで持つ)
「枇杷ビワ」とは、(イ)楽器の名。琵琶ビワ。(ロ)果樹の名。楽器の琵琶の形に似ていることから呼ぶようになった。
《解字》
会意兼形声。「木+音符巴ハ(平らにのばす)」。土の面を平らにのばす木の柄つきの農具。
《単語家族》
把(てのひらで持つ) 耙ハ(地面を平らにならす)と同系。
耙ハ(地面を平らにならす)と同系。
柯 え🔗⭐🔉
柄 え🔗⭐🔉
【柄】
 9画 木部 [常用漢字]
区点=4233 16進=4A41 シフトJIS=95BF
《常用音訓》ヘイ/え/がら
《音読み》 ヘイ
9画 木部 [常用漢字]
区点=4233 16進=4A41 シフトJIS=95BF
《常用音訓》ヘイ/え/がら
《音読み》 ヘイ /ヒョウ(ヒャウ)
/ヒョウ(ヒャウ) 〈b
〈b ng・b
ng・b ng〉
《訓読み》 え/とる/がら
《名付け》 え・えだ・かい・かみ・つか・もと
《意味》
ng〉
《訓読み》 え/とる/がら
《名付け》 え・えだ・かい・かみ・つか・もと
《意味》
 {名}え。ぴんとのび出ている物のとって。〈類義語〉→把ハ。
{名}え。ぴんとのび出ている物のとって。〈類義語〉→把ハ。
 {動}とる。手にとって動かす。一手ににぎる。〈類義語〉→秉ヘイ。「柄政=政ヲ柄ル」
{動}とる。手にとって動かす。一手ににぎる。〈類義語〉→秉ヘイ。「柄政=政ヲ柄ル」
 {名}とらえて動かすことのできるところ。また、その力。支配する力のこと。原動力。権力。「政柄(政権)」「柄任儒術崇丘軻=柄ハ儒術ニ任ジテ丘軻ヲ崇ブ」〔→韓愈〕
{名}とらえて動かすことのできるところ。また、その力。支配する力のこと。原動力。権力。「政柄(政権)」「柄任儒術崇丘軻=柄ハ儒術ニ任ジテ丘軻ヲ崇ブ」〔→韓愈〕
 {名}つかまえて材料にするもの。「話柄(話題)」
〔国〕
{名}つかまえて材料にするもの。「話柄(話題)」
〔国〕 がら。人や物の性質。品位。「銘柄」「人柄」
がら。人や物の性質。品位。「銘柄」「人柄」 がら。布地などの模様。
《解字》
会意兼形声。「木+音符丙(ぴんとはる)」で、ぴんと張り出す意味を含む。
《単語家族》
病(危篤で足が硬直する)
がら。布地などの模様。
《解字》
会意兼形声。「木+音符丙(ぴんとはる)」で、ぴんと張り出す意味を含む。
《単語家族》
病(危篤で足が硬直する) 妨(両手を張って通せんぼする)と同系。また、秉ヘイ(ぴんとはった物を手に持つ)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
妨(両手を張って通せんぼする)と同系。また、秉ヘイ(ぴんとはった物を手に持つ)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 9画 木部 [常用漢字]
区点=4233 16進=4A41 シフトJIS=95BF
《常用音訓》ヘイ/え/がら
《音読み》 ヘイ
9画 木部 [常用漢字]
区点=4233 16進=4A41 シフトJIS=95BF
《常用音訓》ヘイ/え/がら
《音読み》 ヘイ /ヒョウ(ヒャウ)
/ヒョウ(ヒャウ) 〈b
〈b ng・b
ng・b ng〉
《訓読み》 え/とる/がら
《名付け》 え・えだ・かい・かみ・つか・もと
《意味》
ng〉
《訓読み》 え/とる/がら
《名付け》 え・えだ・かい・かみ・つか・もと
《意味》
 {名}え。ぴんとのび出ている物のとって。〈類義語〉→把ハ。
{名}え。ぴんとのび出ている物のとって。〈類義語〉→把ハ。
 {動}とる。手にとって動かす。一手ににぎる。〈類義語〉→秉ヘイ。「柄政=政ヲ柄ル」
{動}とる。手にとって動かす。一手ににぎる。〈類義語〉→秉ヘイ。「柄政=政ヲ柄ル」
 {名}とらえて動かすことのできるところ。また、その力。支配する力のこと。原動力。権力。「政柄(政権)」「柄任儒術崇丘軻=柄ハ儒術ニ任ジテ丘軻ヲ崇ブ」〔→韓愈〕
{名}とらえて動かすことのできるところ。また、その力。支配する力のこと。原動力。権力。「政柄(政権)」「柄任儒術崇丘軻=柄ハ儒術ニ任ジテ丘軻ヲ崇ブ」〔→韓愈〕
 {名}つかまえて材料にするもの。「話柄(話題)」
〔国〕
{名}つかまえて材料にするもの。「話柄(話題)」
〔国〕 がら。人や物の性質。品位。「銘柄」「人柄」
がら。人や物の性質。品位。「銘柄」「人柄」 がら。布地などの模様。
《解字》
会意兼形声。「木+音符丙(ぴんとはる)」で、ぴんと張り出す意味を含む。
《単語家族》
病(危篤で足が硬直する)
がら。布地などの模様。
《解字》
会意兼形声。「木+音符丙(ぴんとはる)」で、ぴんと張り出す意味を含む。
《単語家族》
病(危篤で足が硬直する) 妨(両手を張って通せんぼする)と同系。また、秉ヘイ(ぴんとはった物を手に持つ)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
妨(両手を張って通せんぼする)と同系。また、秉ヘイ(ぴんとはった物を手に持つ)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
江 え🔗⭐🔉
【江】
 6画 水部 [常用漢字]
区点=2530 16進=393E シフトJIS=8D5D
《常用音訓》コウ/え
《音読み》 コウ(カウ)
6画 水部 [常用漢字]
区点=2530 16進=393E シフトJIS=8D5D
《常用音訓》コウ/え
《音読み》 コウ(カウ) /コウ
/コウ 〈ji
〈ji ng〉
《訓読み》 かわ(かは)/え
《名付け》 え・きみ・ただ・のぶ
《意味》
ng〉
《訓読み》 かわ(かは)/え
《名付け》 え・きみ・ただ・のぶ
《意味》
 {名}中国大陸を東西に貫いて流れる揚子江のこと。▽中国ではこの川全体を長江といい、揚子江とはその下流を呼ぶことば。
{名}中国大陸を東西に貫いて流れる揚子江のこと。▽中国ではこの川全体を長江といい、揚子江とはその下流を呼ぶことば。
 {名}かわ(カハ)。大きなかわ。
〔国〕え。海や湖の水が陸地に入りこんだところ。「入り江」
《解字》
会意兼形声。工は、上下の面に穴をあけてつき通すことをあらわす指事文字。江は「水+音符工」で、つき通す意味を含む。大陸をつらぬく大河。
《単語家族》
口(くち)
{名}かわ(カハ)。大きなかわ。
〔国〕え。海や湖の水が陸地に入りこんだところ。「入り江」
《解字》
会意兼形声。工は、上下の面に穴をあけてつき通すことをあらわす指事文字。江は「水+音符工」で、つき通す意味を含む。大陸をつらぬく大河。
《単語家族》
口(くち) 空(あな)と同系。
《類義》
→河
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
空(あな)と同系。
《類義》
→河
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
 6画 水部 [常用漢字]
区点=2530 16進=393E シフトJIS=8D5D
《常用音訓》コウ/え
《音読み》 コウ(カウ)
6画 水部 [常用漢字]
区点=2530 16進=393E シフトJIS=8D5D
《常用音訓》コウ/え
《音読み》 コウ(カウ) /コウ
/コウ 〈ji
〈ji ng〉
《訓読み》 かわ(かは)/え
《名付け》 え・きみ・ただ・のぶ
《意味》
ng〉
《訓読み》 かわ(かは)/え
《名付け》 え・きみ・ただ・のぶ
《意味》
 {名}中国大陸を東西に貫いて流れる揚子江のこと。▽中国ではこの川全体を長江といい、揚子江とはその下流を呼ぶことば。
{名}中国大陸を東西に貫いて流れる揚子江のこと。▽中国ではこの川全体を長江といい、揚子江とはその下流を呼ぶことば。
 {名}かわ(カハ)。大きなかわ。
〔国〕え。海や湖の水が陸地に入りこんだところ。「入り江」
《解字》
会意兼形声。工は、上下の面に穴をあけてつき通すことをあらわす指事文字。江は「水+音符工」で、つき通す意味を含む。大陸をつらぬく大河。
《単語家族》
口(くち)
{名}かわ(カハ)。大きなかわ。
〔国〕え。海や湖の水が陸地に入りこんだところ。「入り江」
《解字》
会意兼形声。工は、上下の面に穴をあけてつき通すことをあらわす指事文字。江は「水+音符工」で、つき通す意味を含む。大陸をつらぬく大河。
《単語家族》
口(くち) 空(あな)と同系。
《類義》
→河
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
空(あな)と同系。
《類義》
→河
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
矜 え🔗⭐🔉
【矜】
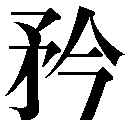 9画 矛部
区点=6666 16進=6262 シフトJIS=E1E0
《音読み》
9画 矛部
区点=6666 16進=6262 シフトJIS=E1E0
《音読み》  キン
キン /ゴン
/ゴン 〈q
〈q n〉/
n〉/ キョウ
キョウ
 /キン
/キン 〈j
〈j ng・j
ng・j n〉
《訓読み》 え/あわれむ(あはれむ)/ほこる
《意味》
n〉
《訓読み》 え/あわれむ(あはれむ)/ほこる
《意味》

 {名}え。ほこのえ。刃物をかたくとりつけるえ。「伐棘棗而為矜=棘棗ヲ伐リテ矜ト為ス」〔→淮南子〕
{名}え。ほこのえ。刃物をかたくとりつけるえ。「伐棘棗而為矜=棘棗ヲ伐リテ矜ト為ス」〔→淮南子〕
 {動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思う。くよくよと思い悩む。〈類義語〉→憐レン。「哀矜アイキン」「矜不能=不能ヲ矜ム」〔→論語〕
{動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思う。くよくよと思い悩む。〈類義語〉→憐レン。「哀矜アイキン」「矜不能=不能ヲ矜ム」〔→論語〕
 {名}あわれな人。▽鰥カン(男やもめ)に当てた用法。カン(クワン)(現代音gu
{名}あわれな人。▽鰥カン(男やもめ)に当てた用法。カン(クワン)(現代音gu n)と読むのが正しいが、日本では、慣用音で、キンと読む。「矜寡キンカ」
n)と読むのが正しいが、日本では、慣用音で、キンと読む。「矜寡キンカ」

 {動}ほこる。かたく自信を持って自負する。「矜持キョウジ・キンジ」「君子矜而不争=君子ハ矜ナレドモ争ハズ」〔→論語〕
{動}ほこる。かたく自信を持って自負する。「矜持キョウジ・キンジ」「君子矜而不争=君子ハ矜ナレドモ争ハズ」〔→論語〕
 {動}かたくまもる。
{動}かたくまもる。
 「矜矜キョウキョウ」とは、しっかりと構えて自信あるさま。
《解字》
「矜矜キョウキョウ」とは、しっかりと構えて自信あるさま。
《解字》
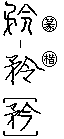 形声。「あわれむ」という意味は、憐レンに当てたもので、「矛+音符令レイ・レン」。矛の柄や自信が強いの意に用いるのは「矛+音符今キン」。今では両者を混同して同一の字で書く。矜はかたく締めてとりつけた矛の柄。かたく固定することから、自信のかたいことをもあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
形声。「あわれむ」という意味は、憐レンに当てたもので、「矛+音符令レイ・レン」。矛の柄や自信が強いの意に用いるのは「矛+音符今キン」。今では両者を混同して同一の字で書く。矜はかたく締めてとりつけた矛の柄。かたく固定することから、自信のかたいことをもあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
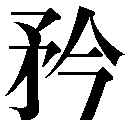 9画 矛部
区点=6666 16進=6262 シフトJIS=E1E0
《音読み》
9画 矛部
区点=6666 16進=6262 シフトJIS=E1E0
《音読み》  キン
キン /ゴン
/ゴン 〈q
〈q n〉/
n〉/ キョウ
キョウ
 /キン
/キン 〈j
〈j ng・j
ng・j n〉
《訓読み》 え/あわれむ(あはれむ)/ほこる
《意味》
n〉
《訓読み》 え/あわれむ(あはれむ)/ほこる
《意味》

 {名}え。ほこのえ。刃物をかたくとりつけるえ。「伐棘棗而為矜=棘棗ヲ伐リテ矜ト為ス」〔→淮南子〕
{名}え。ほこのえ。刃物をかたくとりつけるえ。「伐棘棗而為矜=棘棗ヲ伐リテ矜ト為ス」〔→淮南子〕
 {動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思う。くよくよと思い悩む。〈類義語〉→憐レン。「哀矜アイキン」「矜不能=不能ヲ矜ム」〔→論語〕
{動}あわれむ(アハレム)。かわいそうに思う。くよくよと思い悩む。〈類義語〉→憐レン。「哀矜アイキン」「矜不能=不能ヲ矜ム」〔→論語〕
 {名}あわれな人。▽鰥カン(男やもめ)に当てた用法。カン(クワン)(現代音gu
{名}あわれな人。▽鰥カン(男やもめ)に当てた用法。カン(クワン)(現代音gu n)と読むのが正しいが、日本では、慣用音で、キンと読む。「矜寡キンカ」
n)と読むのが正しいが、日本では、慣用音で、キンと読む。「矜寡キンカ」

 {動}ほこる。かたく自信を持って自負する。「矜持キョウジ・キンジ」「君子矜而不争=君子ハ矜ナレドモ争ハズ」〔→論語〕
{動}ほこる。かたく自信を持って自負する。「矜持キョウジ・キンジ」「君子矜而不争=君子ハ矜ナレドモ争ハズ」〔→論語〕
 {動}かたくまもる。
{動}かたくまもる。
 「矜矜キョウキョウ」とは、しっかりと構えて自信あるさま。
《解字》
「矜矜キョウキョウ」とは、しっかりと構えて自信あるさま。
《解字》
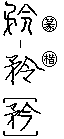 形声。「あわれむ」という意味は、憐レンに当てたもので、「矛+音符令レイ・レン」。矛の柄や自信が強いの意に用いるのは「矛+音符今キン」。今では両者を混同して同一の字で書く。矜はかたく締めてとりつけた矛の柄。かたく固定することから、自信のかたいことをもあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
形声。「あわれむ」という意味は、憐レンに当てたもので、「矛+音符令レイ・レン」。矛の柄や自信が強いの意に用いるのは「矛+音符今キン」。今では両者を混同して同一の字で書く。矜はかたく締めてとりつけた矛の柄。かたく固定することから、自信のかたいことをもあらわす。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
荏 え🔗⭐🔉
重 え🔗⭐🔉
【重】
 9画 里部 [三年]
区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64
《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる
《音読み》 ジュウ(ヂュウ)
9画 里部 [三年]
区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64
《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる
《音読み》 ジュウ(ヂュウ) /チョウ
/チョウ 〈zh
〈zh ng〉〈ch
ng〉〈ch ng〉
《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)
《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ
《意味》
ng〉
《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)
《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ
《意味》
 {形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」
{形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」
 {形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
{形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
 {動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕
{動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕
 {動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」
{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」
 {単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」
〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」
《解字》
{単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」
〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」
《解字》
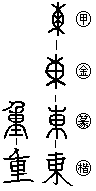 会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東
《単語家族》
動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける)
会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東
《単語家族》
動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける) 衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。
《類義》
申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。
《類義》
申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 9画 里部 [三年]
区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64
《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる
《音読み》 ジュウ(ヂュウ)
9画 里部 [三年]
区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64
《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる
《音読み》 ジュウ(ヂュウ) /チョウ
/チョウ 〈zh
〈zh ng〉〈ch
ng〉〈ch ng〉
《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)
《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ
《意味》
ng〉
《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)
《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ
《意味》
 {形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」
{形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」
 {形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
{形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
 {動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕
{動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕
 {動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」
{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」
 {単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」
〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」
《解字》
{単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」
〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」
《解字》
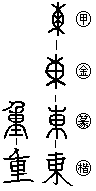 会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東
《単語家族》
動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける)
会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東
《単語家族》
動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける) 衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。
《類義》
申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。
《類義》
申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
餌 え🔗⭐🔉
【餌】
 14画 食部
区点=1734 16進=3142 シフトJIS=8961
《音読み》 ジ
14画 食部
区点=1734 16進=3142 シフトJIS=8961
《音読み》 ジ /ニ
/ニ 〈
〈 r〉
《訓読み》 え/えさ(ゑさ)
《意味》
r〉
《訓読み》 え/えさ(ゑさ)
《意味》
 {名}米の粉をこね、まるめて柔らかくむしたもの。ねりもち。〈類義語〉→餠ヘイ。
{名}米の粉をこね、まるめて柔らかくむしたもの。ねりもち。〈類義語〉→餠ヘイ。
 {名}米と肉を混ぜて柔らかく煮た食べ物。
{名}米と肉を混ぜて柔らかく煮た食べ物。
 ジス{動}食べる。食べさせる。
ジス{動}食べる。食べさせる。
 ジス{動}えさでつる。「餌敵=敵ニ餌ス」
ジス{動}えさでつる。「餌敵=敵ニ餌ス」
 {名}柔らかくした食べ物。「食餌ショクジ」
{名}柔らかくした食べ物。「食餌ショクジ」
 {名}え(
{名}え( )。えさ(
)。えさ( サ)。柔らかいねりえ。魚や獣を誘って捕らえるためのえさ。転じて、人をつるために与える利益。
〔国〕え(
サ)。柔らかいねりえ。魚や獣を誘って捕らえるためのえさ。転じて、人をつるために与える利益。
〔国〕え( )。えさ(
)。えさ( サ)。鳥・獣・虫・魚の食べ物。
《解字》
会意兼形声。「食+音符耳(ねっとり、柔らかい)」。
《単語家族》
耳(柔らかい耳たぶ)
サ)。鳥・獣・虫・魚の食べ物。
《解字》
会意兼形声。「食+音符耳(ねっとり、柔らかい)」。
《単語家族》
耳(柔らかい耳たぶ) 恥(心がひるんで軟らかくなる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
恥(心がひるんで軟らかくなる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 14画 食部
区点=1734 16進=3142 シフトJIS=8961
《音読み》 ジ
14画 食部
区点=1734 16進=3142 シフトJIS=8961
《音読み》 ジ /ニ
/ニ 〈
〈 r〉
《訓読み》 え/えさ(ゑさ)
《意味》
r〉
《訓読み》 え/えさ(ゑさ)
《意味》
 {名}米の粉をこね、まるめて柔らかくむしたもの。ねりもち。〈類義語〉→餠ヘイ。
{名}米の粉をこね、まるめて柔らかくむしたもの。ねりもち。〈類義語〉→餠ヘイ。
 {名}米と肉を混ぜて柔らかく煮た食べ物。
{名}米と肉を混ぜて柔らかく煮た食べ物。
 ジス{動}食べる。食べさせる。
ジス{動}食べる。食べさせる。
 ジス{動}えさでつる。「餌敵=敵ニ餌ス」
ジス{動}えさでつる。「餌敵=敵ニ餌ス」
 {名}柔らかくした食べ物。「食餌ショクジ」
{名}柔らかくした食べ物。「食餌ショクジ」
 {名}え(
{名}え( )。えさ(
)。えさ( サ)。柔らかいねりえ。魚や獣を誘って捕らえるためのえさ。転じて、人をつるために与える利益。
〔国〕え(
サ)。柔らかいねりえ。魚や獣を誘って捕らえるためのえさ。転じて、人をつるために与える利益。
〔国〕え( )。えさ(
)。えさ( サ)。鳥・獣・虫・魚の食べ物。
《解字》
会意兼形声。「食+音符耳(ねっとり、柔らかい)」。
《単語家族》
耳(柔らかい耳たぶ)
サ)。鳥・獣・虫・魚の食べ物。
《解字》
会意兼形声。「食+音符耳(ねっとり、柔らかい)」。
《単語家族》
耳(柔らかい耳たぶ) 恥(心がひるんで軟らかくなる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
恥(心がひるんで軟らかくなる)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「え」で完全一致するの検索結果 1-8。
 9画 木部
区点=5941 16進=5B49 シフトJIS=9E68
《音読み》 カ
9画 木部
区点=5941 16進=5B49 シフトJIS=9E68
《音読み》 カ 〉
《訓読み》 え/えだ
《意味》
〉
《訓読み》 え/えだ
《意味》
 型に曲がった斧オノのえ。〈類義語〉
型に曲がった斧オノのえ。〈類義語〉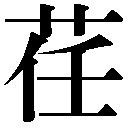 9画 艸部
区点=1733 16進=3141 シフトJIS=8960
《音読み》 ジン(ジム)
9画 艸部
区点=1733 16進=3141 シフトJIS=8960
《音読み》 ジン(ジム)