複数辞典一括検索+![]()
![]()
呪 のろい🔗⭐🔉
【呪】
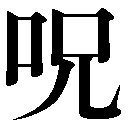 8画 口部
区点=2886 16進=3C76 シフトJIS=8EF4
【咒】異体字異体字
8画 口部
区点=2886 16進=3C76 シフトJIS=8EF4
【咒】異体字異体字
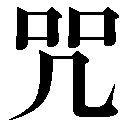 8画 口部
区点=5080 16進=5270 シフトJIS=99EE
《音読み》 ジュ
8画 口部
区点=5080 16進=5270 シフトJIS=99EE
《音読み》 ジュ /シュ
/シュ /シュウ(シウ)
/シュウ(シウ) 〈zh
〈zh u〉
《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/まじない(まじなひ)
《意味》
u〉
《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/まじない(まじなひ)
《意味》
 {動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。神にのりとを告げて祈る。また、そのこと。▽相手が不吉な目にあうように祈る意に用いる。〈対語〉→祝シュク/シュウ。「呪術ジュジュツ」
{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。神にのりとを告げて祈る。また、そのこと。▽相手が不吉な目にあうように祈る意に用いる。〈対語〉→祝シュク/シュウ。「呪術ジュジュツ」
 {名}まじない(マジナヒ)。仏教で、経文のほかにある、短い祈りの文句。転じて、悪気や病魔を追い払う文句。「念呪ネンジュ」
《解字》
会意。「口+兄(大きい頭の人)」。もと、祝と同じで、人が神前で祈りの文句を唱えること。のち、祝は幸いを祈る場合、呪は不幸を祈る場合に分用されるようになった。
《単語家族》
呪と祝はともに祷トウと同系で、長く尾を引いてのりとを告げる意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}まじない(マジナヒ)。仏教で、経文のほかにある、短い祈りの文句。転じて、悪気や病魔を追い払う文句。「念呪ネンジュ」
《解字》
会意。「口+兄(大きい頭の人)」。もと、祝と同じで、人が神前で祈りの文句を唱えること。のち、祝は幸いを祈る場合、呪は不幸を祈る場合に分用されるようになった。
《単語家族》
呪と祝はともに祷トウと同系で、長く尾を引いてのりとを告げる意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
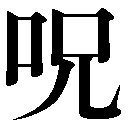 8画 口部
区点=2886 16進=3C76 シフトJIS=8EF4
【咒】異体字異体字
8画 口部
区点=2886 16進=3C76 シフトJIS=8EF4
【咒】異体字異体字
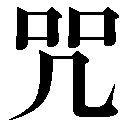 8画 口部
区点=5080 16進=5270 シフトJIS=99EE
《音読み》 ジュ
8画 口部
区点=5080 16進=5270 シフトJIS=99EE
《音読み》 ジュ /シュ
/シュ /シュウ(シウ)
/シュウ(シウ) 〈zh
〈zh u〉
《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/まじない(まじなひ)
《意味》
u〉
《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/まじない(まじなひ)
《意味》
 {動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。神にのりとを告げて祈る。また、そのこと。▽相手が不吉な目にあうように祈る意に用いる。〈対語〉→祝シュク/シュウ。「呪術ジュジュツ」
{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。神にのりとを告げて祈る。また、そのこと。▽相手が不吉な目にあうように祈る意に用いる。〈対語〉→祝シュク/シュウ。「呪術ジュジュツ」
 {名}まじない(マジナヒ)。仏教で、経文のほかにある、短い祈りの文句。転じて、悪気や病魔を追い払う文句。「念呪ネンジュ」
《解字》
会意。「口+兄(大きい頭の人)」。もと、祝と同じで、人が神前で祈りの文句を唱えること。のち、祝は幸いを祈る場合、呪は不幸を祈る場合に分用されるようになった。
《単語家族》
呪と祝はともに祷トウと同系で、長く尾を引いてのりとを告げる意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}まじない(マジナヒ)。仏教で、経文のほかにある、短い祈りの文句。転じて、悪気や病魔を追い払う文句。「念呪ネンジュ」
《解字》
会意。「口+兄(大きい頭の人)」。もと、祝と同じで、人が神前で祈りの文句を唱えること。のち、祝は幸いを祈る場合、呪は不幸を祈る場合に分用されるようになった。
《単語家族》
呪と祝はともに祷トウと同系で、長く尾を引いてのりとを告げる意を含む。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
烽 のろし🔗⭐🔉
詛 のろい🔗⭐🔉
【詛】
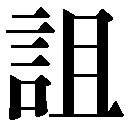 12画 言部
区点=7539 16進=6B47 シフトJIS=E666
《音読み》 ソ
12画 言部
区点=7539 16進=6B47 シフトJIS=E666
《音読み》 ソ /ショ
/ショ 〈z
〈z 〉
《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/そしる
《意味》
〉
《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/そしる
《意味》
 {動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。恨みのある人に、災いがふりかかるように、ことばをとなえて神にいのる。また、のろうこと。のろいのことば。「呪詛ジュソ」
{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。恨みのある人に、災いがふりかかるように、ことばをとなえて神にいのる。また、のろうこと。のろいのことば。「呪詛ジュソ」
 {動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。こまごました事がらをちかう。また、そのちかい。ちかいのことば。▽大きな事がらをちかうのを盟という。
{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。こまごました事がらをちかう。また、そのちかい。ちかいのことば。▽大きな事がらをちかうのを盟という。
 {動}そしる。他人のする事をことばでじゃまをする。〈類義語〉→阻。
《解字》
会意兼形声。且ショは、俎(つみかさねた供えの肉)や阻(石をつみかさねてじゃまをする)の原字で、ものを積みかさねるさまを示す。詛は「言+音符且」で、ことばをかさねて神に祈ったり、ちかったりすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}そしる。他人のする事をことばでじゃまをする。〈類義語〉→阻。
《解字》
会意兼形声。且ショは、俎(つみかさねた供えの肉)や阻(石をつみかさねてじゃまをする)の原字で、ものを積みかさねるさまを示す。詛は「言+音符且」で、ことばをかさねて神に祈ったり、ちかったりすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
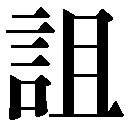 12画 言部
区点=7539 16進=6B47 シフトJIS=E666
《音読み》 ソ
12画 言部
区点=7539 16進=6B47 シフトJIS=E666
《音読み》 ソ /ショ
/ショ 〈z
〈z 〉
《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/そしる
《意味》
〉
《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/そしる
《意味》
 {動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。恨みのある人に、災いがふりかかるように、ことばをとなえて神にいのる。また、のろうこと。のろいのことば。「呪詛ジュソ」
{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。恨みのある人に、災いがふりかかるように、ことばをとなえて神にいのる。また、のろうこと。のろいのことば。「呪詛ジュソ」
 {動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。こまごました事がらをちかう。また、そのちかい。ちかいのことば。▽大きな事がらをちかうのを盟という。
{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。こまごました事がらをちかう。また、そのちかい。ちかいのことば。▽大きな事がらをちかうのを盟という。
 {動}そしる。他人のする事をことばでじゃまをする。〈類義語〉→阻。
《解字》
会意兼形声。且ショは、俎(つみかさねた供えの肉)や阻(石をつみかさねてじゃまをする)の原字で、ものを積みかさねるさまを示す。詛は「言+音符且」で、ことばをかさねて神に祈ったり、ちかったりすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}そしる。他人のする事をことばでじゃまをする。〈類義語〉→阻。
《解字》
会意兼形声。且ショは、俎(つみかさねた供えの肉)や阻(石をつみかさねてじゃまをする)の原字で、ものを積みかさねるさまを示す。詛は「言+音符且」で、ことばをかさねて神に祈ったり、ちかったりすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
麕 のろ🔗⭐🔉
【麕】
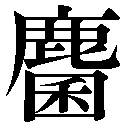 19画 鹿部
区点=8343 16進=734B シフトJIS=EA6A
《音読み》 キン
19画 鹿部
区点=8343 16進=734B シフトJIS=EA6A
《音読み》 キン /コン
/コン 〈j
〈j n・q
n・q n〉
《訓読み》 のろ
《意味》
n〉
《訓読み》 のろ
《意味》
 {名}のろ。獣の名。鹿シカの一種。角がなく、きばがある。群れをなして集まる。
{名}のろ。獣の名。鹿シカの一種。角がなく、きばがある。群れをなして集まる。
 {動}むらがる。「麕集キンシュウ」
《解字》
会意兼形声。下部の字(音キン)は、まるくまとまるの意を含む。麕はそれを音符とし、鹿を加えたもの。群れをなして集まること。
{動}むらがる。「麕集キンシュウ」
《解字》
会意兼形声。下部の字(音キン)は、まるくまとまるの意を含む。麕はそれを音符とし、鹿を加えたもの。群れをなして集まること。
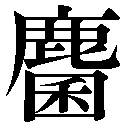 19画 鹿部
区点=8343 16進=734B シフトJIS=EA6A
《音読み》 キン
19画 鹿部
区点=8343 16進=734B シフトJIS=EA6A
《音読み》 キン /コン
/コン 〈j
〈j n・q
n・q n〉
《訓読み》 のろ
《意味》
n〉
《訓読み》 のろ
《意味》
 {名}のろ。獣の名。鹿シカの一種。角がなく、きばがある。群れをなして集まる。
{名}のろ。獣の名。鹿シカの一種。角がなく、きばがある。群れをなして集まる。
 {動}むらがる。「麕集キンシュウ」
《解字》
会意兼形声。下部の字(音キン)は、まるくまとまるの意を含む。麕はそれを音符とし、鹿を加えたもの。群れをなして集まること。
{動}むらがる。「麕集キンシュウ」
《解字》
会意兼形声。下部の字(音キン)は、まるくまとまるの意を含む。麕はそれを音符とし、鹿を加えたもの。群れをなして集まること。
漢字源に「のろ」で始まるの検索結果 1-4。
 11画 火部
区点=6366 16進=5F62 シフトJIS=E082
《音読み》 ホウ
11画 火部
区点=6366 16進=5F62 シフトJIS=E082
《音読み》 ホウ ng〉
《訓読み》 のろし/とぶひ
《意味》
{名}のろし。昔、辺境の屯所で警戒を知らせるのに用いたのろし。敵が侵入してきたら、火をもやし煙をあげて味方に急を知らせた。「烽火ホウカ」
〔国〕とぶひ。上代、異変を知らせるために火をたき、煙をあげて合図をした設備。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音ホウ)は、△型を呈する意。烽はそれを音符とし、火を加えた字で、火煙が△型に燃えあがるのろし。
《単語家族》
峰(△型のみね)と同系。
《熟語》
ng〉
《訓読み》 のろし/とぶひ
《意味》
{名}のろし。昔、辺境の屯所で警戒を知らせるのに用いたのろし。敵が侵入してきたら、火をもやし煙をあげて味方に急を知らせた。「烽火ホウカ」
〔国〕とぶひ。上代、異変を知らせるために火をたき、煙をあげて合図をした設備。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音ホウ)は、△型を呈する意。烽はそれを音符とし、火を加えた字で、火煙が△型に燃えあがるのろし。
《単語家族》
峰(△型のみね)と同系。
《熟語》