複数辞典一括検索+![]()
![]()
寺 てら🔗⭐🔉
【寺】
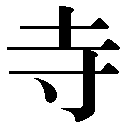 6画 寸部 [二年]
区点=2791 16進=3B7B シフトJIS=8E9B
《常用音訓》ジ/てら
《音読み》 ジ
6画 寸部 [二年]
区点=2791 16進=3B7B シフトJIS=8E9B
《常用音訓》ジ/てら
《音読み》 ジ /シ
/シ 〈s
〈s 〉
《訓読み》 てら/はべる
《意味》
〉
《訓読み》 てら/はべる
《意味》
 {名}てら。仏教で、仏道の修行や仏事を行うところ。「寺院」
{名}てら。仏教で、仏道の修行や仏事を行うところ。「寺院」
 {名}庶務・雑用をとり扱う役所。「寺署」
{名}庶務・雑用をとり扱う役所。「寺署」
 {動}はべる。身分の高い人のそばに付き添う。▽侍ジに当てた用法。「寺人(身辺にはべって雑用をする臣。転じて宦官カンガン)」
《解字》
{動}はべる。身分の高い人のそばに付き添う。▽侍ジに当てた用法。「寺人(身辺にはべって雑用をする臣。転じて宦官カンガン)」
《解字》
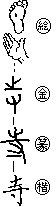 会意兼形声。「寸(て)+音符之(足で進む)」。手足を動かして働くこと。侍(はべる)や接待の待の原字。転じて、雑用をつかさどる役所のこと。また、漢代に西域から来た僧を鴻臚寺コウロジという接待所に泊めたため、のち寺を仏寺の意に用いるようになった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意兼形声。「寸(て)+音符之(足で進む)」。手足を動かして働くこと。侍(はべる)や接待の待の原字。転じて、雑用をつかさどる役所のこと。また、漢代に西域から来た僧を鴻臚寺コウロジという接待所に泊めたため、のち寺を仏寺の意に用いるようになった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
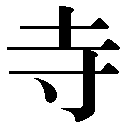 6画 寸部 [二年]
区点=2791 16進=3B7B シフトJIS=8E9B
《常用音訓》ジ/てら
《音読み》 ジ
6画 寸部 [二年]
区点=2791 16進=3B7B シフトJIS=8E9B
《常用音訓》ジ/てら
《音読み》 ジ /シ
/シ 〈s
〈s 〉
《訓読み》 てら/はべる
《意味》
〉
《訓読み》 てら/はべる
《意味》
 {名}てら。仏教で、仏道の修行や仏事を行うところ。「寺院」
{名}てら。仏教で、仏道の修行や仏事を行うところ。「寺院」
 {名}庶務・雑用をとり扱う役所。「寺署」
{名}庶務・雑用をとり扱う役所。「寺署」
 {動}はべる。身分の高い人のそばに付き添う。▽侍ジに当てた用法。「寺人(身辺にはべって雑用をする臣。転じて宦官カンガン)」
《解字》
{動}はべる。身分の高い人のそばに付き添う。▽侍ジに当てた用法。「寺人(身辺にはべって雑用をする臣。転じて宦官カンガン)」
《解字》
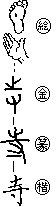 会意兼形声。「寸(て)+音符之(足で進む)」。手足を動かして働くこと。侍(はべる)や接待の待の原字。転じて、雑用をつかさどる役所のこと。また、漢代に西域から来た僧を鴻臚寺コウロジという接待所に泊めたため、のち寺を仏寺の意に用いるようになった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意兼形声。「寸(て)+音符之(足で進む)」。手足を動かして働くこと。侍(はべる)や接待の待の原字。転じて、雑用をつかさどる役所のこと。また、漢代に西域から来た僧を鴻臚寺コウロジという接待所に泊めたため、のち寺を仏寺の意に用いるようになった。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
昭 てらす🔗⭐🔉
【昭】
 9画 日部 [三年]
区点=3028 16進=3E3C シフトJIS=8FBA
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ(セウ)
9画 日部 [三年]
区点=3028 16進=3E3C シフトJIS=8FBA
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ(セウ)
 〈zh
〈zh o〉
《訓読み》 あきらか(あきらかなり)/あきらかにする(あきらかにす)/てる/てらす
《名付け》 あき・あきら・いか・てる・はる
《意味》
o〉
《訓読み》 あきらか(あきらかなり)/あきらかにする(あきらかにす)/てる/てらす
《名付け》 あき・あきら・いか・てる・はる
《意味》
 {形}あきらか(アキラカナリ)。ぐるりと照らしたように、すみまでよくわかる。〈対語〉→昧マイ・→暗。〈類義語〉→明。「昭昭」「昭著」「敢昭告于皇皇后帝=アヘテ昭カニ皇皇タル后帝ニ告グ」〔→論語〕
{形}あきらか(アキラカナリ)。ぐるりと照らしたように、すみまでよくわかる。〈対語〉→昧マイ・→暗。〈類義語〉→明。「昭昭」「昭著」「敢昭告于皇皇后帝=アヘテ昭カニ皇皇タル后帝ニ告グ」〔→論語〕
 {動}あきらかにする(アキラカニス)。すみずみまで照らし出す。隠れた所をあきらかにする。「昭雪」「昭陛下平明之治=陛下ノ平明ノ治ヲ昭カニス」〔→諸葛亮〕
{動}あきらかにする(アキラカニス)。すみずみまで照らし出す。隠れた所をあきらかにする。「昭雪」「昭陛下平明之治=陛下ノ平明ノ治ヲ昭カニス」〔→諸葛亮〕
 {動}てる。てらす。▽照に当てた用法。
{動}てる。てらす。▽照に当てた用法。
 {名}祖先をまつる廟ビョウの順序の名。始祖廟シソビョウを中央に置き、初代をその左に置いて昭といい、その子を右に置いて穆ボクという。→昭穆
《解字》
会意兼形声。刀は、曲線をなしたかたな。召は、口でまねき寄せること。昭は「日+音符召」で、光をぐるりと回して、すみまでてらすこと。照の原字。→召
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{名}祖先をまつる廟ビョウの順序の名。始祖廟シソビョウを中央に置き、初代をその左に置いて昭といい、その子を右に置いて穆ボクという。→昭穆
《解字》
会意兼形声。刀は、曲線をなしたかたな。召は、口でまねき寄せること。昭は「日+音符召」で、光をぐるりと回して、すみまでてらすこと。照の原字。→召
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 9画 日部 [三年]
区点=3028 16進=3E3C シフトJIS=8FBA
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ(セウ)
9画 日部 [三年]
区点=3028 16進=3E3C シフトJIS=8FBA
《常用音訓》ショウ
《音読み》 ショウ(セウ)
 〈zh
〈zh o〉
《訓読み》 あきらか(あきらかなり)/あきらかにする(あきらかにす)/てる/てらす
《名付け》 あき・あきら・いか・てる・はる
《意味》
o〉
《訓読み》 あきらか(あきらかなり)/あきらかにする(あきらかにす)/てる/てらす
《名付け》 あき・あきら・いか・てる・はる
《意味》
 {形}あきらか(アキラカナリ)。ぐるりと照らしたように、すみまでよくわかる。〈対語〉→昧マイ・→暗。〈類義語〉→明。「昭昭」「昭著」「敢昭告于皇皇后帝=アヘテ昭カニ皇皇タル后帝ニ告グ」〔→論語〕
{形}あきらか(アキラカナリ)。ぐるりと照らしたように、すみまでよくわかる。〈対語〉→昧マイ・→暗。〈類義語〉→明。「昭昭」「昭著」「敢昭告于皇皇后帝=アヘテ昭カニ皇皇タル后帝ニ告グ」〔→論語〕
 {動}あきらかにする(アキラカニス)。すみずみまで照らし出す。隠れた所をあきらかにする。「昭雪」「昭陛下平明之治=陛下ノ平明ノ治ヲ昭カニス」〔→諸葛亮〕
{動}あきらかにする(アキラカニス)。すみずみまで照らし出す。隠れた所をあきらかにする。「昭雪」「昭陛下平明之治=陛下ノ平明ノ治ヲ昭カニス」〔→諸葛亮〕
 {動}てる。てらす。▽照に当てた用法。
{動}てる。てらす。▽照に当てた用法。
 {名}祖先をまつる廟ビョウの順序の名。始祖廟シソビョウを中央に置き、初代をその左に置いて昭といい、その子を右に置いて穆ボクという。→昭穆
《解字》
会意兼形声。刀は、曲線をなしたかたな。召は、口でまねき寄せること。昭は「日+音符召」で、光をぐるりと回して、すみまでてらすこと。照の原字。→召
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
{名}祖先をまつる廟ビョウの順序の名。始祖廟シソビョウを中央に置き、初代をその左に置いて昭といい、その子を右に置いて穆ボクという。→昭穆
《解字》
会意兼形声。刀は、曲線をなしたかたな。召は、口でまねき寄せること。昭は「日+音符召」で、光をぐるりと回して、すみまでてらすこと。照の原字。→召
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
照 てらす🔗⭐🔉
【照】
 13画 火部 [四年]
区点=3040 16進=3E48 シフトJIS=8FC6
《常用音訓》ショウ/て…らす/て…る/て…れる
《音読み》 ショウ(セウ)
13画 火部 [四年]
区点=3040 16進=3E48 シフトJIS=8FC6
《常用音訓》ショウ/て…らす/て…る/て…れる
《音読み》 ショウ(セウ)
 〈zh
〈zh o〉
《訓読み》 てれる/てる/てらす
《名付け》 あき・あきら・あり・てらし・てらす・てり・てる・とし・のぶ・みつ
《意味》
o〉
《訓読み》 てれる/てる/てらす
《名付け》 あき・あきら・あり・てらし・てらす・てり・てる・とし・のぶ・みつ
《意味》
 {動・形}てる。てらす。右から左まで、または上から下まで、円を描くようにてらす。すみずみまで光がなでるさま。また、鏡にうつす。「反照(てり返し)」「照鏡=鏡ニ照ラス」「日月所照=日月ノ照ラストコロ」〔→中庸〕
{動・形}てる。てらす。右から左まで、または上から下まで、円を描くようにてらす。すみずみまで光がなでるさま。また、鏡にうつす。「反照(てり返し)」「照鏡=鏡ニ照ラス」「日月所照=日月ノ照ラストコロ」〔→中庸〕
 {動}てらす。手本や事がらを基準にする。よる。〈類義語〉→依。「照旧=旧ニ照ラス」
{動}てらす。手本や事がらを基準にする。よる。〈類義語〉→依。「照旧=旧ニ照ラス」
 {動}てらしあわす。問いあわせる。「照会」「照合」「査照(調べあわせる。またてらしあわせる旅券や許可証)」
{動}てらしあわす。問いあわせる。「照会」「照合」「査照(調べあわせる。またてらしあわせる旅券や許可証)」
 {名・動}〔俗〕写真。写真をとる。「照相チャオシアン(写真)」
〔国〕てる。晴れる。
《解字》
会意兼形声。召は「口+音符刀」からなり、刀の刃の曲線のように、半円を描いてまねきよせること。昭は「日+音符召」の会意兼形声文字で、半円を描いて、右から左へと光がなでること。照は「火+音符昭」。昭があきらかの意の形容詞に用いられるため、さらに火印を加えて、すみからすみまで半円形にてらすことを示す。→召
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{名・動}〔俗〕写真。写真をとる。「照相チャオシアン(写真)」
〔国〕てる。晴れる。
《解字》
会意兼形声。召は「口+音符刀」からなり、刀の刃の曲線のように、半円を描いてまねきよせること。昭は「日+音符召」の会意兼形声文字で、半円を描いて、右から左へと光がなでること。照は「火+音符昭」。昭があきらかの意の形容詞に用いられるため、さらに火印を加えて、すみからすみまで半円形にてらすことを示す。→召
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 13画 火部 [四年]
区点=3040 16進=3E48 シフトJIS=8FC6
《常用音訓》ショウ/て…らす/て…る/て…れる
《音読み》 ショウ(セウ)
13画 火部 [四年]
区点=3040 16進=3E48 シフトJIS=8FC6
《常用音訓》ショウ/て…らす/て…る/て…れる
《音読み》 ショウ(セウ)
 〈zh
〈zh o〉
《訓読み》 てれる/てる/てらす
《名付け》 あき・あきら・あり・てらし・てらす・てり・てる・とし・のぶ・みつ
《意味》
o〉
《訓読み》 てれる/てる/てらす
《名付け》 あき・あきら・あり・てらし・てらす・てり・てる・とし・のぶ・みつ
《意味》
 {動・形}てる。てらす。右から左まで、または上から下まで、円を描くようにてらす。すみずみまで光がなでるさま。また、鏡にうつす。「反照(てり返し)」「照鏡=鏡ニ照ラス」「日月所照=日月ノ照ラストコロ」〔→中庸〕
{動・形}てる。てらす。右から左まで、または上から下まで、円を描くようにてらす。すみずみまで光がなでるさま。また、鏡にうつす。「反照(てり返し)」「照鏡=鏡ニ照ラス」「日月所照=日月ノ照ラストコロ」〔→中庸〕
 {動}てらす。手本や事がらを基準にする。よる。〈類義語〉→依。「照旧=旧ニ照ラス」
{動}てらす。手本や事がらを基準にする。よる。〈類義語〉→依。「照旧=旧ニ照ラス」
 {動}てらしあわす。問いあわせる。「照会」「照合」「査照(調べあわせる。またてらしあわせる旅券や許可証)」
{動}てらしあわす。問いあわせる。「照会」「照合」「査照(調べあわせる。またてらしあわせる旅券や許可証)」
 {名・動}〔俗〕写真。写真をとる。「照相チャオシアン(写真)」
〔国〕てる。晴れる。
《解字》
会意兼形声。召は「口+音符刀」からなり、刀の刃の曲線のように、半円を描いてまねきよせること。昭は「日+音符召」の会意兼形声文字で、半円を描いて、右から左へと光がなでること。照は「火+音符昭」。昭があきらかの意の形容詞に用いられるため、さらに火印を加えて、すみからすみまで半円形にてらすことを示す。→召
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{名・動}〔俗〕写真。写真をとる。「照相チャオシアン(写真)」
〔国〕てる。晴れる。
《解字》
会意兼形声。召は「口+音符刀」からなり、刀の刃の曲線のように、半円を描いてまねきよせること。昭は「日+音符召」の会意兼形声文字で、半円を描いて、右から左へと光がなでること。照は「火+音符昭」。昭があきらかの意の形容詞に用いられるため、さらに火印を加えて、すみからすみまで半円形にてらすことを示す。→召
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
衒 てらう🔗⭐🔉
漢字源に「てら」で始まるの検索結果 1-4。
 11画 行部
区点=7442 16進=6A4A シフトJIS=E5C8
《音読み》 ゲン
11画 行部
区点=7442 16進=6A4A シフトJIS=E5C8
《音読み》 ゲン