複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (50)
まえ【前】マヘ🔗⭐🔉
まえ【前】マヘ
(「目方まへ」の意)
➊物の正面にあたるところ。
①顔の向いている方。おもて。万葉集18「針袋取り上げ―に置き」。「―を見る」「黒板を―にする」「2階の1番―の席」「―へならえ」↔うしろ。
②物・建物の正面。また、そこにある庭。庭前。大和物語「―に荻薄いとおほかる所になむありける」。「黒板の―に立つ」
③幾つかある中の自分に近い方。手前。「一つ―の駅」「着物を左―に着せる」
④進んで行く先にある方。前方。「遥か―を見る」「途中で―の席に移る」
⑤着物の(→)前1にあたる部分。狂言、空腕「先づ―をくわつと取りお太刀のはばき元二、三寸抜きくつろげ」
⑥陰部。まえのもの。
⑦(神を直接指すのを避けて添える語)神の御身。古事記上「能く我が―を治めば」
⑧前神まえがみの略。
⑨(多く「お」「おほ」「み」などの接頭語を添えて)神・天子・貴人の尊敬語。古事記下「誰そ大―に申す」
⑩貴人のそばに出ること。後撰和歌集春「正月のついたちころに―許されたりけるに」
⑪貴女の名に添えていう敬称。「玉藻の―」
➋ある時点より早いこと。
①以前。さき。「―に聞いた話」「―の戦争」「30分ほど―」「食事の―に手を洗う」↔あと↔のち。
②前科。「―がある」
③前相撲まえずもうの略。
④僧侶に対しての食膳・饗応。源氏物語蜻蛉「七僧の―の事せさせ給ひけり」
⑤(手前の略)他人や世間に対する体裁・面目。狂言、居杭「此の―が迷惑にござる」
➌①それ相当のもの。また、そのものとしての面目。「男―」「一人―」「腕―」
②割りあてたものの分量の意。「5人―の料理」
ま‐え【麻衣】🔗⭐🔉
ま‐え【麻衣】
あさのころも。まい。太平記39「玉体を―草鞋にやつし」
マエ【Mahé】🔗⭐🔉
マエ【Mahé】
インド南西部、ケーララ州北部の旧フランス植民地。1954年インド領となる。
まえ‐あがり【前上がり】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐あがり【前上がり】マヘ‥
物の前部が後部よりも上がっていること。「―の着付け」
まえ‐あき【前開き】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐あき【前開き】マヘ‥
衣服で、前の部分にあきがあること。ボタン・ファスナーなどでとめる。
まえ‐あし【前足・前脚・前肢】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐あし【前足・前脚・前肢】マヘ‥
①獣や虫などの、頭に近い方の一対の足。
②足を踏み出したとき、前の方になる足。「―に重心を置く」
まえ‐いた【前板】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐いた【前板】マヘ‥
①牛車ぎっしゃの前後の口に横に敷き渡した板。ふみいた。しきいた。→牛車(図)。
②鎧よろいの胴正面に垂れる草摺くさずり。揺ゆるぎの板。きんかくし。
まえ‐いわい【前祝】マヘイハヒ🔗⭐🔉
まえ‐いわい【前祝】マヘイハヒ
ある事の成立・成功を期して前もって祝うこと。「―に1杯やる」
まえうけ‐きん【前受金】マヘ‥🔗⭐🔉
まえうけ‐きん【前受金】マヘ‥
簿記で、商品を引き渡す前に受け取る売上代金の一部。負債として計上する。
まえうけ‐しゅうえき【前受収益】マヘ‥シウ‥🔗⭐🔉
まえうけ‐しゅうえき【前受収益】マヘ‥シウ‥
簿記で、すでに受け取った金額のうち次期以降の収益としなければならないもの。負債として計上する。前受家賃・前受利息など。
まえ‐うしろ【前後ろ】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐うしろ【前後ろ】マヘ‥
①まえとうしろ。あとさき。ぜんご。
②衣服などの、前後の位置があべこべになっていること。うしろまえ。
まえ‐うた【前歌・前唄】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐うた【前歌・前唄】マヘ‥
地歌・箏曲の手事物で、手事に先立つ歌の部分。↔あとうた
まえ‐うり【前売り】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐うり【前売り】マヘ‥
入場券・指定乗車券などを、それを使う日よりも前に売ること。「―券」
まえ‐お【前緒】マヘヲ🔗⭐🔉
まえ‐お【前緒】マヘヲ
履物の緒の、前の方の部分。前壺。
まえ‐おき【前置き】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐おき【前置き】マヘ‥
本題に入る前に述べること。また、その言葉や文章。「―が長い」
まえ‐おび【前帯】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐おび【前帯】マヘ‥
①女が帯を前で結ぶこと。江戸時代、はじめは老女が用いたが、後には遊女などが用いた。かかえ帯。前結び。
②江戸時代、上方で、眉を剃り歯をそめた年増としまの女の称。↔後ろ帯
まえ‐かがみ【前屈み】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐かがみ【前屈み】マヘ‥
体を前へ曲げてかがむこと。まえこごみ。
まえ‐がき【前書】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐がき【前書】マヘ‥
本文の前に書き添えること。また、その文章。緒言。
まえ‐がき【前掻】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐がき【前掻】マヘ‥
①頭の曲がった鑿のみ。かぶらえり。
②馬などが前脚で地を掻くこと。あがき。
まえ‐かけ【前掛け】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐かけ【前掛け】マヘ‥
着物の汚れを防ぐため、体の前面、主に腰から下にあてて用いる布。まえだれ。エプロン。「―をして働く」
まえ‐がし【前貸し】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐がし【前貸し】マヘ‥
給料などを、支払うべき期日以前に貸し与えること。先貸し。
まえ‐がしら【前頭】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐がしら【前頭】マヘ‥
相撲の力士の階級で、小結の次位、十両の上位にある位の称。平幕ひらまく。
まえ‐かた【前方】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐かた【前方】マヘ‥
①その時より以前。従前。狂言、墨塗「―から御沙汰の無いと申す事はござるまいに」
②旧式なこと。時代おくれなこと。好色一代男6「すこし―なるおかた狂ひのやうに見えて」
③初心。うぶ。未熟。傾城禁短気「―なる若手の男」
④控え目であること。傾城禁短気「ものは―に言ふべし」
まえ‐がたり【前語り】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐がたり【前語り】マヘ‥
寄席よせなどの前座で語ること。また、その人。
まえ‐かど【前廉】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐かど【前廉】マヘ‥
①その時より前。まえまえ。まえかた。好色一代男6「宿よりは―の書出し」
②(副詞的に)前もって。あらかじめ。
まえ‐がね【前金・前銀】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐がね【前金・前銀】マヘ‥
⇒まえきん
まえ‐がみ【前神】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐がみ【前神】マヘ‥
2座以上を祭った神社で、主たる神を除いたそのほかの神の称。前まえ。
まえ‐がみ【前髪】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐がみ【前髪】マヘ‥
①童男または婦人の額上の毛を束ねたもの。ぬかがみ。ひたいがみ。向髪。好色五人女4「この―の散るあはれ、坊主も剃刀投げ捨て」→日本髪(図)。
②元服以前の童男の称。
③額に垂れ下がる髪。
⇒まえがみ‐おや【前髪親】
⇒まえがみ‐ざかり【前髪盛り】
⇒まえがみ‐だて【前髪立て】
まえがみ‐おや【前髪親】マヘ‥🔗⭐🔉
まえがみ‐おや【前髪親】マヘ‥
(能登地方で)男子19歳の成年式(昔は前髪をおとし、月代さかやきを立てた)の後見人。
⇒まえ‐がみ【前髪】
まえがみ‐ざかり【前髪盛り】マヘ‥🔗⭐🔉
まえがみ‐ざかり【前髪盛り】マヘ‥
元服前の男子の若衆らしい盛りの時期。
⇒まえ‐がみ【前髪】
まえがみ‐だて【前髪立て】マヘ‥🔗⭐🔉
まえがみ‐だて【前髪立て】マヘ‥
①男が前髪を立てていること。すなわち、まだ元服しないこと。また、その男。前髪立ち。
②結髪用具の一つ。鯨骨でつくり、前髪に入れて高く張り出すのに用いる。浮世草子、好色盛衰記「かうがい、さし櫛、―」
⇒まえ‐がみ【前髪】
まえ‐がり【前借り】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐がり【前借り】マヘ‥
給料などを、受け取るべき期日以前に借りること。先借り。ぜんしゃく。「月給を―する」
まえ‐かんじょう【前勘定】マヘ‥ヂヤウ🔗⭐🔉
まえ‐かんじょう【前勘定】マヘ‥ヂヤウ
代金を前もって払うこと。前払い。前金払い。まえかん。
まえ‐がんな【前鉋】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐がんな【前鉋】マヘ‥
桶屋の用いる、短いかんなの一種。
ま‐えき【麻疫】🔗⭐🔉
ま‐えき【麻疫】
麻疹ましん。はしか。
まえ‐きょうげん【前狂言】マヘキヤウ‥🔗⭐🔉
まえ‐きょうげん【前狂言】マヘキヤウ‥
①歌舞伎の本狂言の前の狂言。脇狂言。
②京坂歌舞伎で、一番目狂言をいう。
まえ‐ぎょうじ【前行司】マヘギヤウ‥🔗⭐🔉
まえ‐ぎょうじ【前行司】マヘギヤウ‥
(→)「呼出し」4の別称。
まえ‐ぎり【前桐】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐きん【前金】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐きん【前金】マヘ‥
代金を前もって支払うこと。また、その金。ぜんきん。まえがね。↔後金あときん
まえ‐ぎんちゃく【前巾着】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐ぎんちゃく【前巾着】マヘ‥
(→)「まえさげ」に同じ。
まえ‐く【前句】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐く【前句】マヘ‥
①付合つけあいで、付句の前に位する句。
②前句付まえくづけの略。
⇒まえく‐づけ【前句付】
まえく‐づけ【前句付】マヘ‥🔗⭐🔉
まえく‐づけ【前句付】マヘ‥
七・七の短句に五・七・五の長句を付ける俳諧の一分野。例えば「斬りたくもあり斬りたくもなし」に「盗人を捕へて見ればわが子なり」と付ける。元禄頃から庶民間に大流行。のちの川柳はこれを母胎とする。
⇒まえ‐く【前句】
まえ‐げい【前芸】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐げい【前芸】マヘ‥
本芸に入る前にする小手調べの芸。
まえ‐げいき【前景気】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐げいき【前景気】マヘ‥
事が始まる前の景気。「―をあおる」
まえ‐こうじょう【前口上】マヘ‥ジヤウ🔗⭐🔉
まえ‐こうじょう【前口上】マヘ‥ジヤウ
本題に入る前に述べる口上。前置きのことば。前ことば。「―が長い」
まえ‐こぐち【前小口】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐こぐち【前小口】マヘ‥
本の背と反対側の部分。小口。
まえ‐こごみ【前屈み】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐こごみ【前屈み】マヘ‥
(→)「まえかがみ」に同じ。
まえ‐こさく【前小作】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐こさく【前小作】マヘ‥
小作米を前納する契約を結んだ上でする小作。
まえ‐ごし【前腰】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐ごし【前腰】マヘ‥
袴はかまの前方の腹に当たる部分。
まえ‐さがり【前下がり】マヘ‥🔗⭐🔉
まえ‐さがり【前下がり】マヘ‥
①物の前部が後部よりも下がっていること。
②特に、羽織などで、前身頃を後ろ身頃より長めに仕立てること。また、その部分。
大辞林の検索結果 (96)
まえ【前】🔗⭐🔉
まえ マヘ 【前】
〔「ま(目)へ(辺)」の意より〕
■一■ [1] (名)
(1)顔や視線の向いている方向,または場所。
⇔うしろ
⇔しりえ
「―を見て歩く」「お父さんの―でもう一度言ってみなさい」
(2)(ア)(事物に方向があると考えて)正面の方向,または場所。
⇔うしろ
⇔しりえ
「家の―に空き地がある」「計画の―に立ちはだかる障害」(イ)事物の前方の部分。「バスの―の方の席につく」(ウ)身体の正面の部分。着物などを着たとき,身体の正面にくる部分。「―がはだける」(エ)人間の陰部。「―を隠して風呂にはいる」
(3)順序の先の方。初めの方。さき。「電話帳では青田より青木の方が―にある」
(4)(時間的に)(ア)現在またはある時点より以前。「三十分ほど―に電話があった」「この話は―から変だと思っていた」(イ)ある行為・事態が成立する以前。「食事の―に手を洗う」「客が来る―に準備を調えておいた」(ウ)(「前の」の形で)さきの。直前の。
⇔あと
⇔のち
「―の首相」「―の正月」
(5)前歴。特に,過去の罪。前科。「―がある」
(6)(人を指す語句を受けて)その人に対する気がね・遠慮・体面などを示す。「たたきつけてかへらうと思つたけれどなかやどの―もあるから/安愚楽鍋(魯文)」
(7)形式名詞として用い,かねて思っていたとおりであること,ある判断に基づいていることを表す。「それは元から覚悟の―であるのだ/魔風恋風(天外)」
(8)(ア)貴人の面前。また,貴人に伺候すること。「正月(ムツキ)のついたち頃に―許されたりけるに/後撰(春上詞)」(イ)(上に「おお」「お」「み」を付けて)貴人その人をさす。「お―にこそわりなく思さるらめ/源氏(夕顔)」(ウ)(「…のまえ」の形で)女性の名に添えて敬意を表す。「名をば千手の―と申し候ふ/平家 10」
(9)僧侶に対するもてなしの食膳。「講師の―,人にあつらへさせなどして/宇治拾遺 9」
■二■ (接尾)
(1)名詞や動詞の連用形などに付いて,それに相当する分量や部分などを表す。ぶん(分)。「一人―」「分け―」
(2)人に関する名詞に付いて,その属性・機能などを強調する意を表す。「男―」「腕―」「気―」
ま-え【麻衣】🔗⭐🔉
ま-え 【麻衣】
「まい(麻衣)」に同じ。[日葡]
まえ-あき【前開き】🔗⭐🔉
まえ-あき マヘ― [0] 【前開き】
衣服の前部にあきがあること。
まえ-あし【前足・前脚・前肢】🔗⭐🔉
まえ-あし マヘ― [0][2] 【前足・前脚・前肢】
(1)獣や昆虫などの前方の二本の足。
⇔うしろあし
(2)前に踏み出した方の足。「―に重心をかける」
まえ-いし【前石】🔗⭐🔉
まえ-いし マヘ― [0][1] 【前石】
(1)茶室の露地で,蹲(ツクバイ)の前に据えた石。この上で手水(チヨウズ)を使う。
→蹲
(2)石灯籠(イシドウロウ)の前に据えた石。普通の飛び石より少し高めに据える。
まえ-いた【前板】🔗⭐🔉
まえ-いた マヘ― [0] 【前板】
(1)「帯板」に同じ。
(2)牛車(ギツシヤ)の前後の口に横に渡した板。踏み板。
(3)「揺(ユルギ)の板」に同じ。
まえ-いわい【前祝(い)】🔗⭐🔉
まえ-いわい マヘイハヒ [3] 【前祝(い)】
ある事がよい結果になるようにと,前もって祝うこと。また,その祝い。「合格の―」
まえ-うしろ【前後ろ】🔗⭐🔉
まえ-うしろ マヘ― [1][3] 【前後ろ】
(1)まえとうしろ。ぜんご。
(2)「うしろまえ」に同じ。「シャツを―に着る」
まえ-うた【前歌・前唄】🔗⭐🔉
まえ-うた マヘ― [0] 【前歌・前唄】
地歌・箏曲(ソウキヨク)の手事物(テゴトモノ)の曲の,手事の前の歌の部分。
⇔後歌(アトウタ)
まえ-うり【前売り】🔗⭐🔉
まえ-うり マヘ― [0] 【前売り】 (名)スル
入場券・乗車券などを,当日よりも前に売ること。また,その券。「―券」
まえ-お【前緒】🔗⭐🔉
まえ-お マヘヲ [0] 【前緒】
履物の前壺(マエツボ)にすげるほうの緒。
まえ-おき【前置き】🔗⭐🔉
まえ-おき マヘ― [0] 【前置き】 (名)スル
本題にはいる前に関連のあることなどを述べること。また,その言葉。前口上。「彼の話は―が長い」「長々と―する」
まえ-かがみ【前屈み】🔗⭐🔉
まえ-かがみ マヘ― [3][0] 【前屈み】
上半身を前の方にかがめること。前こごみ。「―になって歩く」
まえ-がき【前書き】🔗⭐🔉
まえ-がき マヘ― [0] 【前書き】
書物・論文などで,本文の前に書き添える文。序。端書き。
⇔後書き
まえ-かけ【前掛(け)】🔗⭐🔉
まえ-かけ マヘ― [0][3] 【前掛(け)】
帯のあたりから体の前面に下げて,衣服の汚れを防ぐ布。室町末期頃から女子の仕事着。近世以降,商家の男子にも広く用いられた。前垂れ。
まえかけ-なわ【前懸け縄】🔗⭐🔉
まえかけ-なわ マヘカケナハ [4] 【前懸け縄】
和船で,舵(カジ)の前へまわして車立(シヤタツ)にとめる綱。おおまわし。
まえ-がし【前貸し】🔗⭐🔉
まえ-がし マヘ― [0] 【前貸し】 (名)スル
決められた期日以前に給料などを支払うこと。
⇔前借り
まえ-がしら【前頭】🔗⭐🔉
まえ-がしら マヘ― [3] 【前頭】
力士の位の一。小結の下,十両の上。平幕。「―筆頭」
まえ-かた【前方】🔗⭐🔉
まえ-かた マヘ― [0] 【前方】
■一■ (名)
(1)その時より前。以前。副詞的に用いる。「―拝見致いた事がござる/狂言・比丘貞(虎寛本)」
(2)時間的に二分した,早いほう。また,早いほうに属する人や物。「賭弓(ノリユミ)あれば―うしろ方と/栄花(歌合)」
■二■ (名・形動ナリ)
(1)時代おくれであること。古くさいこと。また,そのさま。「そんな―なる仕掛の涙などにふれと乗る男にあらず/浮世草子・色三味線」
(2)熟達していないこと。未熟であること。また,そのさま。「そりや―なる若手の男にして見せられたがよい筈/浮世草子・禁短気」
(3)ひかえめな・こと(さま)。「調子に乗りても物は―に言ふべし/浮世草子・禁短気」
まえ-かど【前簾】🔗⭐🔉
まえ-かど マヘ― 【前簾】
(1)以前。前々。「宿よりは―の書き出し/浮世草子・一代男 6」
(2)(副詞的に用いて)前もって。あらかじめ。「―北国へお飛脚に行かれた足の軽い足軽殿か/浄瑠璃・忠臣蔵」
まえ-がみ【前神】🔗⭐🔉
まえ-がみ マヘ― [1] 【前神】
二柱以上の神をまつってある神社で,主神を除いたその他の神のこと。
まえ-がみ【前髪】🔗⭐🔉
まえ-がみ マヘ― [0] 【前髪】
(1)額に垂らした頭髪。
⇔後ろ髪
「―をかきあげる」
(2)昔,童子や婦人が額の上の部分の頭髪を束ねていたもの。向こう髪。「この―の散るあはれ/浮世草子・五人女 4」
(3)元服前の少年。「や―めにまけうか/浄瑠璃・平家女護島」
前髪(2)
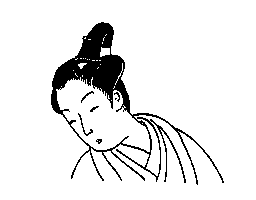 [図]
[図]
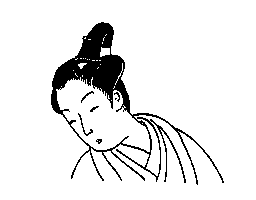 [図]
[図]
まえがみ-だち【前髪立ち】🔗⭐🔉
まえがみ-だち マヘ― 【前髪立ち】
元服前の少年が,その前髪をまだ残していること。また,その者。「子細は―の時/浮世草子・男色大鑑 2」
まえ-がり【前借り】🔗⭐🔉
まえ-がり マヘ― [0] 【前借り】 (名)スル
決められた期日より前に給料などを借りること。
⇔前貸し
「退職金を―する」
まえかわ【前川】🔗⭐🔉
まえかわ マヘカハ 【前川】
姓氏の一。
まえかわ-くにお【前川国男】🔗⭐🔉
まえかわ-くにお マヘカハクニヲ 【前川国男】
(1905-1986) 建築家。新潟県生まれ。東京帝大卒。ル=コルビュジエの下に学ぶ。日本の近代建築の動向に大きな影響を与えた。代表作に東京文化会館・東京海上火災ビル本館・東京都美術館など。
まえかわ-レポート【前川―】🔗⭐🔉
まえかわ-レポート マヘカハ― [6] 【前川―】
中曾根康弘元首相の私的諮問機関であった経済構造調整研究会が1986年(昭和61)に提出した報告。内需拡大の必要が主張された。座長の前川春雄元日銀総裁の名から。
まえ-かんじょう【前勘定】🔗⭐🔉
まえ-かんじょう マヘカンヂヤウ [3] 【前勘定】
前もって代金を支払うこと。前勘。前金。
まえ-きょうげん【前狂言】🔗⭐🔉
まえ-きょうげん マヘキヤウゲン [3] 【前狂言】
(1)江戸時代,歌舞伎で三番叟(サンバソウ)と大序との間に演じられた狂言。脇狂言。
(2)明治末頃まで京坂の歌舞伎で,一番目狂言の称。中(ナカ)狂言・切(キリ)狂言に対していう。
まえ-きん【前金】🔗⭐🔉
まえ-きん マヘ― [0] 【前金】
売買や貸借に際して,前もって代金を支払うこと。また,その金。ぜんきん。まえせん。「―を納める」
まえ-ぎんちゃく【前巾着】🔗⭐🔉
まえ-ぎんちゃく マヘ― [3] 【前巾着】
「前提(マエサ)げ」に同じ。
まえ-く【前句】🔗⭐🔉
まえ-く マヘ― [0] 【前句】
(1)連歌・俳諧で,付句の直前に位置する句。
(2)「前句付け」の古称。
まえく-づけ【前句付け】🔗⭐🔉
まえく-づけ マヘ― [0] 【前句付け】
(1)俳諧で,七・七または五・七・五の前句に句を付けること。江戸前期に俳諧の入門・稽古のため流行。前句付俳諧。
(2)雑俳の一。出題された前句に付句を付けて点取りを競う遊戯的な俳諧。元禄(1688-1704)頃より盛んとなり,江戸中期に流行。のちに川柳となる。「ぬらりくらりとぬらりくらりと」に「団(ウチワ)では思ふやうには叩かれず」と付ける類。
まえ-げい【前芸】🔗⭐🔉
まえ-げい マヘ― [0] 【前芸】
曲芸・手品などで,本芸にはいる前に小手調べとして行う軽い芸。
まえ-げいき【前景気】🔗⭐🔉
まえ-げいき マヘ― [3] 【前景気】
事が始まる前の景気。「―をあおる」「―は上々」
マエケナス Gaius Maecenas
Gaius Maecenas 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
マエケナス  Gaius Maecenas
Gaius Maecenas (前70頃-前8) ローマの政治家。オクタビアヌスの親友。ホラティウスやウェルギリウスなど文人を援助した。
(前70頃-前8) ローマの政治家。オクタビアヌスの親友。ホラティウスやウェルギリウスなど文人を援助した。
 Gaius Maecenas
Gaius Maecenas (前70頃-前8) ローマの政治家。オクタビアヌスの親友。ホラティウスやウェルギリウスなど文人を援助した。
(前70頃-前8) ローマの政治家。オクタビアヌスの親友。ホラティウスやウェルギリウスなど文人を援助した。
まえ-こうじょう【前口上】🔗⭐🔉
まえ-こうじょう マヘコウジヤウ [3] 【前口上】
本題にはいる前に述べる言葉。まえおき。「―が長い」「芝居の―」
まえ-こごみ【前屈み】🔗⭐🔉
まえ-こごみ マヘ― [3][0] 【前屈み】
「まえかがみ(前屈)」に同じ。「―になって細かい仕事をする」
まえ-さがり【前下(が)り】🔗⭐🔉
まえ-さがり マヘ― [3] 【前下(が)り】
(1)前の部分が,後ろの部分より下がっていること。
(2)婦人服の製図で,前身頃の中央で背丈の基礎線よりも下がっている部分。また,その長さ。和服では,羽織などの前身丈を後ろ身丈より長くすること。また,その寸法。
まえ-さき【前先】🔗⭐🔉
まえ-さき マヘ― 【前先】
これから先。先の見通し。また,先の見通しがきくこと。「―の見えねえことは言ひやせん/滑稽本・早変胸機関」
まえ-さく【前作】🔗⭐🔉
まえ-さく マヘ― [0] 【前作】
「ぜんさく(前作){(2)}」に同じ。
まえ-さげ【前提げ】🔗⭐🔉
まえ-さげ マヘ― 【前提げ】
ひもをつけて帯の前にさげる巾着(キンチヤク)。安永(1772-1781)頃,京坂で流行した。まえぎんちゃく。
まえ-ざし【前挿(し)・前差(し)】🔗⭐🔉
まえ-ざし マヘ― [0] 【前挿(し)・前差(し)】
女の髷(マゲ)の前の方にさすかんざし。
⇔後ろ挿し
まえ-さばき【前捌き】🔗⭐🔉
まえ-さばき マヘ― [3] 【前捌き】
相撲で,立ち合い後,自分の得意の体勢になるために,両者が互いに相手の手をはねかえして争うこと。「―のうまい力士」
まえさわ【前沢】🔗⭐🔉
まえさわ マヘサハ 【前沢】
岩手県南部,胆沢(イサワ)郡の町。北上川中流の河港,陸羽街道の宿駅として栄えた。
まえじた-ぼいん【前舌母音】🔗⭐🔉
まえじた-ぼいん マヘジタ― [5] 【前舌母音】
〔front vowel〕
前舌面を持ち上げることによって調音する母音。日本語のイは,この典型。
まえ-じて【前仕手】🔗⭐🔉
まえ-じて マヘ― [0] 【前仕手】
〔「まえして」とも〕
前後二場面の能・狂言で,中入りの前に出るシテ。
⇔後仕手(ノチジテ)
〔普通「前ジテ」と書く〕
まえじま【前島】🔗⭐🔉
まえじま マヘジマ 【前島】
姓氏の一。
まえじま-ひそか【前島密】🔗⭐🔉
まえじま-ひそか マヘジマ― 【前島密】
(1835-1919) 政治家。越後の人。維新後,渡英して郵便制度を調査,「郵便」「切手」などの名称を定め日本の郵便事業を創始。国字改良論者としても知られる。
まえ-しりえ【前後】🔗⭐🔉
まえ-しりえ マヘシリヘ 【前後】
前方と後方。また,競技などの左方と右方。「―分きて装束(ソウゾ)けば/蜻蛉(下)」
まえ-すだれ【前簾】🔗⭐🔉
まえ-すだれ マヘ― [3] 【前簾】
牛車(ギツシヤ)や輿(コシ)の前面にかける簾。
⇔後ろ簾
マエストーソ (イタリア) maestoso
(イタリア) maestoso 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
マエストーソ [4]  (イタリア) maestoso
(イタリア) maestoso 音楽の発想標語の一。「威厳をもって」「堂々とした」の意を表す。
音楽の発想標語の一。「威厳をもって」「堂々とした」の意を表す。
 (イタリア) maestoso
(イタリア) maestoso 音楽の発想標語の一。「威厳をもって」「堂々とした」の意を表す。
音楽の発想標語の一。「威厳をもって」「堂々とした」の意を表す。
マエストロ (イタリア) maestro
(イタリア) maestro 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
マエストロ [2]  (イタリア) maestro
(イタリア) maestro (音楽の)巨匠。
(音楽の)巨匠。
 (イタリア) maestro
(イタリア) maestro (音楽の)巨匠。
(音楽の)巨匠。
まえ-ずもう【前相撲】🔗⭐🔉
まえ-ずもう マヘズマフ [3] 【前相撲】
まだ番付にのらない,入門したばかりの力士の取組。二連勝で一つの勝ち星となり,その勝ち星二つで本中(ホンチユウ)へ進む。
まえ-せつ【前説】🔗⭐🔉
まえ-せつ マヘ― [0] 【前説】
〔「前説明」の略〕
実況生(ナマ)中継や公開録画などの番組が始まる前に,全体の構成や軽い話などをして会場の雰囲気を盛り上げる役。
まえ-せん【前銭】🔗⭐🔉
まえ-せん マヘ― [0] 【前銭】
「前金(マエキン)」に同じ。
まえ-せんでん【前宣伝】🔗⭐🔉
まえ-せんでん マヘ― [3] 【前宣伝】
売り出し・催し物などの,始まる前に行う宣伝。事前宣伝。
まえだ【前田】🔗⭐🔉
まえだ マヘダ 【前田】
姓氏の一。
まえだ-かんじ【前田寛治】🔗⭐🔉
まえだ-かんじ マヘダクワンヂ 【前田寛治】
(1896-1930) 洋画家。鳥取県生まれ。東京美術学校卒。渡仏してクールベに傾倒。帰国後「1930年協会」を創立。独自の写実主義を目指した。
まえだ-げんい【前田玄以】🔗⭐🔉
まえだ-げんい マヘダ― 【前田玄以】
(1539-1602) 安土桃山時代の武将。名は宗向。美濃の人。初め比叡山の僧。のち織田信忠・豊臣秀吉に仕え,丹波亀山五万石を領した。豊臣氏五奉行の一人。
まえだ-せいそん【前田青邨】🔗⭐🔉
まえだ-せいそん マヘダ― 【前田青邨】
(1885-1977) 日本画家。岐阜県生まれ。本名,廉造。新しい感覚で歴史画・人物・武者絵・花鳥など幅広く描いた。東京芸大教授。代表作「洞窟の頼朝」「唐獅子」など。
まえだ-つなのり【前田綱紀】🔗⭐🔉
まえだ-つなのり マヘダ― 【前田綱紀】
(1643-1724) 加賀第五代藩主。幼名,犬千代。諡号(シゴウ),松雲公。三歳で藩主となる。農政改革を推進。文書・典籍を収集保存し,尊経閣文庫の基礎を築いた。
まえだ-としいえ【前田利家】🔗⭐🔉
まえだ-としいえ マヘダトシイヘ 【前田利家】
(1538-1599) 安土桃山時代の武将。加賀藩の祖。尾張の人。幼名,犬千代。幼少より織田信長に仕える。賤ヶ岳の戦いでは柴田勝家についたが,のち豊臣秀吉と和を結び,金沢に封ぜられた。五大老の一人として秀頼を補佐したが,秀吉没後一年にして死んだ。
まえだ-なつかげ【前田夏蔭】🔗⭐🔉
まえだ-なつかげ マヘダ― 【前田夏蔭】
(1793-1864) 江戸末期の国学者。江戸の人。清水浜臣に師事。徳川慶喜に国学を講じた。「蝦夷(エゾ)志料」編集の命を受けるが,業半ばにして没した。
まえだ-まさな【前田正名】🔗⭐🔉
まえだ-まさな マヘダ― 【前田正名】
(1850-1921) 明治期の官僚・農政家。薩摩の人。松方正義の上からの殖産興業政策に反対し,下からの地方産業振興を提唱。著「興業意見」など。
まえだ-ゆうぐれ【前田夕暮】🔗⭐🔉
まえだ-ゆうぐれ マヘダユフグレ 【前田夕暮】
(1883-1951) 歌人。神奈川県生まれ。本名,洋造。「詩歌」を主宰。「明星」の浪漫主義に対抗し自然主義を標榜(ヒヨウボウ),若山牧水と並び称された。のちに口語自由律短歌をも手がける。歌集「収穫」「生くる日に」など。
まえだ-りゅう【前田流】🔗⭐🔉
まえだ-りゅう マヘダリウ 【前田流】
平曲の流派の一。江戸初期の総検校前田九一を祖とし,江戸・名古屋を中心に行われた。江戸中期に荻野検校がこの流儀の譜本を整えて「平家正節(ヘイケマブシ)」を著した。
まえ-だおし【前倒し】🔗⭐🔉
まえ-だおし ―ダフシ [3][0] 【前倒し】
(1)前にたおすこと。
(2)予算で,主要な収入支出が,年度の早い時期に計上されていること。
まえだこう【前田河】🔗⭐🔉
まえだこう マヘダカウ 【前田河】
姓氏の一。
まえだこう-ひろいちろう【前田河広一郎】🔗⭐🔉
まえだこう-ひろいちろう マヘダカウヒロイチラウ 【前田河広一郎】
(1888-1957) 小説家。宮城県生まれ。徳富蘆花に師事。1921年(大正10)小説「三等船客」を発表,プロレタリア作家として立つ。「種蒔く人」「文芸戦線」の同人。他に「赤い馬車」「大暴風雨時代」「蘆花伝」など。
まえ-だち【前立ち】🔗⭐🔉
まえ-だち マヘ― 【前立ち】
(1)前に立つもの。特に,仏像を守護するために前に立つもの。「―にあるは楊柳観世音/柳多留 49」
(2)名義上,表面に立てておく人。「揚巻の―,白酒の糟兵衛といふ者/歌舞伎・助六」
まえ-たて【前立て】🔗⭐🔉
まえ-たて マヘ― [0] 【前立て】
洋裁で,ブラウスやズボンの前開きの上前につける細長い布。
まえ-だて【前立】🔗⭐🔉
まえ-だて マヘ― [0][4] 【前立】
「前立物」の略。
まえだて-もの【前立物】🔗⭐🔉
まえだて-もの マヘ― [0] 【前立物】
兜(カブト)の立物(タテモノ)のうち前面に付けられたもの。鍬形(クワガタ)・半月・天衝(テンツキ)など。前立。
まえ-だれ【前垂(れ)】🔗⭐🔉
まえ-だれ マヘ― [0] 【前垂(れ)】
「前掛け」に同じ。
まえだれ-がけ【前垂(れ)掛け】🔗⭐🔉
まえだれ-がけ マヘ― [0] 【前垂(れ)掛け】
(1)前垂れをかけている姿。「紺の筒袖にめくら縞の―/歌行灯(鏡花)」
(2)商家に奉公している身分。
まえだれ-かずき【前垂れ被】🔗⭐🔉
まえだれ-かずき マヘ―カヅキ 【前垂れ被】
〔雨よけに前垂れをかぶるところから〕
奉公人たちの出替わりの頃降る雨。陰暦の三月,九月に降る雨。「―の雨に涙こぼすを見るやうな/浮世草子・織留 5」
まえ-つ-きみ【公卿】🔗⭐🔉
まえ-つ-きみ マヘ― 【公卿】
〔「前つ君」の意〕
天皇の御前に仕える身分の高い人を敬っていう語。もうちぎみ。まちぎみ。「―い渡らすも御木(ミケ)のさ小橋/日本書紀(景行)」
まえ-づけ【前付け】🔗⭐🔉
まえ-づけ マヘ― [0] 【前付け】
書籍の本文の前につける題字・序文・目次・凡例など。
⇔後付(アトヅ)け
まえ-つ-と【前つ戸】🔗⭐🔉
まえ-つ-と マヘ― 【前つ戸】
家の表口。前方の戸口。「―よい行き違ひ/古事記(中)」
まえ-つぼ【前壺】🔗⭐🔉
まえ-つぼ マヘ― [2][1] 【前壺】
下駄や草履(ゾウリ)の前緒。
まえ【前】(和英)🔗⭐🔉
まえあし【前足】(和英)🔗⭐🔉
まえいわい【前祝い】(和英)🔗⭐🔉
まえいわい【前祝い】
celebration in advance.〜をする celebrate beforehand.
まえうけきん【前受金】(和英)🔗⭐🔉
まえうけきん【前受金】
an advance.→英和
まえうり【前売りする】(和英)🔗⭐🔉
まえうり【前売りする】
sellin advance.前売券 an advance[a reserved]ticket.
まえおき【前置き】(和英)🔗⭐🔉
まえおき【前置き】
an introduction;→英和
preliminary remarks.〜として by way of introduction.
まえかがみ【前屈みになる】(和英)🔗⭐🔉
まえかがみ【前屈みになる】
bend forward;stoop.→英和
まえがき【前書】(和英)🔗⭐🔉
まえかけ【前掛け】(和英)🔗⭐🔉
まえかけ【前掛け】
an apron.→英和
まえがし【前貸し】(和英)🔗⭐🔉
まえがし【前貸し】
[金]an advance (of money).→英和
〜をする advance;payin advance.
まえがみ【前髪】(和英)🔗⭐🔉
まえがみ【前髪】
the forelock;→英和
bangs[<英>a fringe](切り下げた).
まえがり【前借りをする】(和英)🔗⭐🔉
まえがり【前借りをする】
have an advance.→英和
まえきん【前金】(和英)🔗⭐🔉
広辞苑+大辞林に「マエ」で始まるの検索結果。もっと読み込む