複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (52)
よう【夭】エウ🔗⭐🔉
よう【夭】エウ
若死に。
よう【用】🔗⭐🔉
よう【用】
①もちいること。つかうこと。「―に供する」
②役に立つこと。はたらくこと。はたらき。源氏物語桐壺「かかる―もやと残し給へりける御装束ひとくだり」。日葡辞書「シュジンノヨウニタツ」。「―が足りる」
③行う必要があること。しごと。徒然草「―ありて行きたりともその事果てなばとく帰るべし」。狂言、引敷聟「何事なり共―があらばおしやれ」。「―を言い付ける」「―が済む」
④(古くはユウと読む)芸術論などで、体たいが作用の本源を意味するのに対して、その作用。働きとして存在すること。また、働かせること。至花道「能に体・用ゆうの事を知るべし。体は花、用は匂のごとし」
⑤必要な金品。入費。また、金銭のかかる高価なこと。今昔物語集14「此の衾を見て、極めて―に思ひて」。御文章「一心に弥陀を帰命する衆生を、―もなくたすけたまへるいはれが、すなはち、阿弥陀仏の四の字のこころなり」
⑥大小便をすること。
⑦ある目的のためであること。ため。枕草子84「なにの―に、心もなう遠からぬ門をかたくたたくらん」。史記抄「かう云ふは斉の君をわるいと云はう―ぞ」
⑧(接尾語的に)…に使うためのものの意を表す。「実験―」
⑨生花の中段の役枝やくえだの称。
⇒用に立つ
⇒用を足す
⇒用を成さない
⇒用を弁ずる
よう【杳】エウ🔗⭐🔉
よう【杳】エウ
暗いさま。深く広いさま。はるかなさま。はっきりわからないさま。「―として行方が知れない」
よう【俑】🔗⭐🔉
よう【容】🔗⭐🔉
よう【容】
かたち。すがた。「―を改める」
よう【益】ヤウ🔗⭐🔉
よう【益】ヤウ
(ヤクの音便。「用」とみる説もある)えき。甲斐かい。入用。竹取物語「―もなしとて薬も食はず」
よう【庸】🔗⭐🔉
よう【庸】
律令制の現物納租税の一種。大化改新では、仕丁しちょう・采女うねめの衣食用として1戸につき布1丈2尺・米5斗。大宝律令制定後は、唐の制度にならって毎年10日間の歳役さいえきの代納物とし、成年男子一人につき布2丈6尺または米6斗。奈良・平安時代を通じては、布1丈4尺または米3斗が一般。ちからしろ。
よう【葉】エフ🔗⭐🔉
よう【葉】エフ
①木の葉の先や縁のようにとがっているところ。徒然草「これは―の入りて、木にて縁をしたりければ」
②葉のように薄く平たいもの。また、それを数える語。「写真1―」
③時代。世。「5世紀中―」
④千葉の略。
よう【陽】ヤウ🔗⭐🔉
よう【陽】ヤウ
①日に向かっている方。日の当たっている側。山の南面の地。川の北岸の地。「山―」
②あらわ。表面。うわべ。「陰に―に」
③易学で、天地の2元気の一つ。天・男・君・日・昼・動・剛・奇数など、すべて積極的・能動的な事物の性質を表す。
↔陰
よう【徭】エウ🔗⭐🔉
よう【徭】エウ
公役につとめること。夫役ぶやく。えだち。
よう【様】ヤウ🔗⭐🔉
よう【様】ヤウ
①きまったかたち。型。てほん。源氏物語帚木「人の調度の、かざりとする、定まれる―あるものを」
②さま。かたち。形状。図柄。すがた。枕草子103「真名まんなの―、文字の、世に知らずあやしきを」
③おもむき。体裁。源氏物語夕顔「女がたも、あやしう―たがひたる物思ひをなんしける」
④流儀。風儀。紫式部日記「宮の―として、色めかしきをばいとあはあはしとおぼしめいたれば」
⑤わけ。しさい。理由。事情。今昔物語集4「此の二人は―ある者ならん」。狂言、武悪「討ちもせいで討つたと偽らう―が御座らぬ」
⑥施すべき方法。しかた。手段。竹取物語「その山見るに、さらに登るべき―なし」。日葡辞書「ヒャクヤウヲシッテモ、イチヤウヲシラズンバ、アラソウコトナカレ」
⑦ことがら。こと。源氏物語帚木「まことかと見もてゆくに、見劣りせぬ―はなくなんあるべき」
⑧引用文を導き、「…ことには」「…には」の意を表す。土佐日記「楫取りのいふ―、『黒鳥のもとに白き波を寄す』とぞいふ」
⑨㋐同じさま。似た状態。大鏡師輔「御兄をば親の―に頼み申させ給ひ」
㋑(口語では比況の助動詞「ようだ」の形になる)その状態にあること。また、その状態にあると思われること。ふう。徒然草「このごろは深く案じ、才覚をあらはさんとしたる―に聞ゆる」。→ようだ。
⑩意図・希望を表す。「成功する―にと祈る」
⑪(接尾語的に)
㋐…らしく見えるもの。…といったもの。紫式部日記「上達部の随身など―のものども」。「刀剣―の凶器」
㋑(動詞の連用形に付いて)…するしかた。…するぐあい。「口のきき―が悪い」「彼の喜び―といったらない」
⇒様に依りて葫蘆を画く
よう【窯】エウ🔗⭐🔉
よう【窯】エウ
陶磁器を焼くかま。かまど。また、陶磁器。
よう【曜】エウ🔗⭐🔉
よう【曜】エウ
①日・月と火・水・木・金・土の五星の称。
②七曜を1週間の日に配して呼ぶ時の称。「―日」
よう【癰】🔗⭐🔉
よう【癰】
〔医〕皮膚や皮下組織に生じる急性化膿性炎症。隣接する多数の毛包・皮脂腺などが化膿菌に侵されたもので、癤せつの集合したもの。局所に多くの膿栓を生じ、周辺から腫脹して赤色を呈する。痛みが激しくて、悪化すると死に至ることがある。項うなじ・背・顔などによくできる。〈日葡辞書〉
よ・う【酔う】ヨフ🔗⭐🔉
よ・う【酔う】ヨフ
〔自五〕
(ヱフの転)
①酒を飲んで酒気が全身にまわる。酒気のために理性や感覚が乱れる。狂言、素襖落「大盃で三つ五つ、ほつてと―・うた」。「ビール1杯で―・う」
②魚肉などに中毒する。日葡辞書「イヲニヨウ」
③圧倒されてめまいを感じる。日葡辞書「チ(血)ニヨウ」「ユキニヨウ」「ヒトニヨウ」
④乗物にゆられたために気持が悪くなる。今昔物語集28「未だ車にも乗らざりける者共にて…三人乍ら―・ひぬれば踏板に物突き散らして」。「バスに―・う」
⑤魅せられて心を奪われる。恍惚こうこつとなる。「妙技に―・う」
⑥いい気になって、正常な判断ができなくなる。「緒戦の勝利に―・う」
よう【善う・良う・能う】🔗⭐🔉
よう【善う・良う・能う】
〔副〕
(ヨクの音便)
①(→)「よく(善く)」に同じ。
②(下に否定の語を伴って)とても…できない。狂言、鶯「そりや、―ささぬは」
③容易にあってはならないことにいう語。どうしてなかなか。狂言、聾座頭「―盗人がゐようぞ」
よう(助動詞)🔗⭐🔉
よう
〔助動〕
(文語の「見む」「せむ」(「む」は推量の助動詞)の類の音便ミウ・セウがミョウ・ショウと音転し、「見よう」「しよう」と書かれるようになって、1語として扱われるようになったもの。江戸時代以後の語。[活用]○/○/よう/(よう)/○/○)五段活用以外の動詞および下一段型活用の助動詞の未然形に接続して、話し手の推量・意志を表す。「受け―」「見―」「書かせ―」→う
よう(感動詞)🔗⭐🔉
よう
〔感〕
挨拶や感動を表す時の声。多く男性が親しい間柄で用いる。「―、しばらく」
よう‐あ【養痾】ヤウ‥🔗⭐🔉
よう‐あ【養痾】ヤウ‥
病を療養すること。
よう‐あん【溶暗】🔗⭐🔉
よう‐あん【溶暗】
(→)フェード‐アウトに同じ。↔溶明
よう‐い【用意】🔗⭐🔉
よう‐い【用意】
①意を用いること。心づかい。注意。用心。源氏物語紅葉賀「大殿の頭中将、かたち―人には異なるを」
②準備。したく。大鏡道隆「筑紫にはかねて―もなく」。「―が整う」「食事を―する」
③(感動詞的に)競技・競走などの開始の構えをととのえさせる合図の声。「―、スタート」
⇒ようい‐しゅうとう【用意周到】
⇒ようい‐どん【用意どん】
よう‐い【妖異】エウ‥🔗⭐🔉
よう‐い【妖異】エウ‥
あやしいできごと。あやしいばけもの。妖怪。
よう‐い【洋医】ヤウ‥🔗⭐🔉
よう‐い【洋医】ヤウ‥
①漢方医方に対して、西洋医方による医師。
②西洋人の医師。
よう‐い【容易】🔗⭐🔉
よう‐い【容易】
たやすいこと。やさしいこと。「―に解決できる」「―ならざる事態」
よう‐い【庸医】🔗⭐🔉
よう‐い【庸医】
凡庸な医者。やぶいしゃ。
よう‐イオン【陽イオン】ヤウ‥🔗⭐🔉
よう‐イオン【陽イオン】ヤウ‥
〔化〕(cation)陽電気を帯びたイオン。元素記号の右肩に「+」または「・」を付けて表す。Na+,Ba2+またはNa・など。カチオン。
よう‐いく【養育】ヤウ‥🔗⭐🔉
よう‐いく【養育】ヤウ‥
養い育てること。はぐくむこと。「―費」
ようい‐しゅうとう【用意周到】‥シウタウ🔗⭐🔉
ようい‐しゅうとう【用意周到】‥シウタウ
用意が十分にととのって手抜かりのないこと。
⇒よう‐い【用意】
ようい‐どん【用意どん】🔗⭐🔉
ようい‐どん【用意どん】
(「どん」はピストルの音)駆けっこなどで、開始の掛け声。また、駆けっこのこと。
⇒よう‐い【用意】
よう‐いん【要因】エウ‥🔗⭐🔉
よう‐いん【要因】エウ‥
物事の成立に必要な因子・原因。主要な原因。
⇒よういん‐しょうけん【要因証券】
よう‐いん【要員】エウヰン🔗⭐🔉
よう‐いん【要員】エウヰン
ある物事のために必要な人員。「保安―」
よういん‐しょうけん【要因証券】エウ‥🔗⭐🔉
よういん‐しょうけん【要因証券】エウ‥
証券上の権利の発生が、証券発行の原因である法律関係が有効であることを要件とする有価証券。船荷証券・倉庫証券など。有因証券。↔無因証券
⇒よう‐いん【要因】
よう‐うん【妖雲】エウ‥🔗⭐🔉
よう‐うん【妖雲】エウ‥
あやしい雲。不吉を予感させるような雲。
よう‐えい【揺曳】エウ‥🔗⭐🔉
よう‐えい【揺曳】エウ‥
ゆらゆらとなびくこと。また、あとあとまで長く、その気分や痕跡などが残ること。
よう‐えい【耀映】エウ‥🔗⭐🔉
よう‐えい【耀映】エウ‥
てりかがやくこと。
よう‐えき【用益】🔗⭐🔉
よう‐えき【用益】
使用と収益。
⇒ようえき‐けん【用益権】
⇒ようえき‐ぶっけん【用益物権】
よう‐えき【要駅】エウ‥🔗⭐🔉
よう‐えき【要駅】エウ‥
重要な宿駅。重要な鉄道駅。
よう‐えき【葉腋】エフ‥🔗⭐🔉
よう‐えき【葉腋】エフ‥
植物の葉が茎と接続している部分。葉の付け根。
よう‐えき【傭役】🔗⭐🔉
よう‐えき【傭役】
やとって使うこと。また、やとわれて使われること。
よう‐えき【徭役】エウ‥🔗⭐🔉
よう‐えき【徭役】エウ‥
①律令時代の雑徭ぞうようと歳役さいえき。公用に使役するため人夫として徴発すること。また、その労役。えだち。
②中世、荘園領主や地頭がその領民に課した労役。夫役ぶやく。
③近世、おやかた(御館)百姓が被官百姓・名子なごに奉仕させた労役。
よう‐えき【溶液】🔗⭐🔉
よう‐えき【溶液】
〔化〕(solution)液体状態の均一な混合物。一つの液体に他の物質(固体・液体または気体)が溶解して溶液ができたと考えるとき、もとの液体を溶媒、溶解した物質を溶質という。
ようえき‐けん【用益権】🔗⭐🔉
ようえき‐けん【用益権】
他人の所有物をその用方に従って一定期間使用・収益しうる旧民法上の物権。
⇒よう‐えき【用益】
ようえき‐さいばい【養液栽培】ヤウ‥🔗⭐🔉
ようえき‐さいばい【養液栽培】ヤウ‥
土壌を用いず、培養液で作物を栽培する方法。礫耕法・砂耕法など固形培地を使う方法と、水耕法のように使わない方法とがある。除草や土壌消毒が不要で、連作障害が回避できる。葉菜・果菜類や花卉かきなどに適する。
ようえき‐ち【要役地】エウ‥🔗⭐🔉
ようえき‐ち【要役地】エウ‥
〔法〕その便益のために地役権が設定される土地。→承役地しょうえきち
ようえき‐ぶっけん【用益物権】🔗⭐🔉
ようえき‐ぶっけん【用益物権】
地上権・永小作権・地役権・入会いりあい権の総称。
⇒よう‐えき【用益】
よう‐えん【妖婉】エウヱン🔗⭐🔉
よう‐えん【妖婉】エウヱン
(→)妖艶ようえんに同じ。
よう‐えん【妖艶】エウ‥🔗⭐🔉
よう‐えん【妖艶】エウ‥
なまめかしくあでやかなこと。あやしいほど美しいこと。(多く女性の形容に使う)
よう‐えん【遥遠】エウヱン🔗⭐🔉
よう‐えん【遥遠】エウヱン
はるかに遠いこと。
よう‐えん【陽炎】ヤウ‥🔗⭐🔉
よう‐えん【陽炎】ヤウ‥
かげろう。
大辞林の検索結果 (99)
よう【用】🔗⭐🔉
よう [1] 【用】
■一■ (名)
(1)しなくてはならない事柄。用事。「―を言い付ける」「―が済む」
(2)役に立つこと。はたらきをすること。「公衆の―に供する」「これでも―が足りる」
(3)大小便をすること。用便。「―を足す」
(4)費用。入費。「御内証の御―は何程にても是の内義に申付けておきまする/浮世草子・織留 3」
(5)〔「ゆう」とも〕
(事物の本体を「体」というのに対して)作用。現象。「衆生の心も…情識は―也,波に似たり/沙石 2」
(6)作用を表す言葉。また,活用する言葉。「むしは惣名也。躰也。むすはその―也/名語記」
(7)(形式名詞的に用いて)ため。ゆえ。「何の―に心もなう遠からぬ門を高く叩くらむ/枕草子 84」「かう云は斉の君をわるいと云わう―ぞ/史記抄 10」
(8)名詞に付いて,…のために使用するもの,…において使用するもの,…が使用するもの,などの意を表す。「実験―」「家庭―」「生徒―」
■二■ (名・形動ナリ)
必要な・こと(さま)。入用。有用。「いづれもいづれも―果てなば賜(タ)びてむ/落窪 1」「かやうの所に馬など―なる物ぞかし/宇治拾遺 7」
よう【幼】🔗⭐🔉
よう エウ [1] 【幼】
おさないこと。また,おさない子ども。「―にして詩にすぐれ」
よう【俑】🔗⭐🔉
よう [1] 【俑】
中国で副葬品として用いられた,人間を模した像。木・土・金属・陶などで作る。殷(イン)代から明代にわたって見られ,各時代の風俗を反映して美術的にも価値が高い。
→泥象(デイシヨウ)
よう【洋】🔗⭐🔉
よう ヤウ [1] 【洋】
西洋と東洋。特に,西洋。「和漢―」
よう【要】🔗⭐🔉
よう エウ [1] 【要】
(1)物事の大切な部分。物事のかなめ。
(2)必要であること。なくてはならないこと。「再考の―がある」「―のないお饒舌(シヤベリ)をするわけではない/婦系図(鏡花)」
→ようは
(3)名詞などの上に付いて,そのものが必要である意を表す。「―注意」「―確認」「―書類」
よう【容】🔗⭐🔉
よう [1] 【容】
かたち。すがた。「―を正す」
よう【庸】🔗⭐🔉
よう [1] 【庸】
(1)律令制の租税の一。年一〇日の歳役(サイエキ)の代納物(布が主,米・塩・綿など)。養老令では,正丁で布二丈六尺と規定。調とともに農民による運脚(ウンキヤク)が義務。中央では,仕丁・衛士などの食糧(大粮)や土木事業の経費などに使用。ちからしろ。
(2)平凡であること。凡庸。「才と―との別も亦甚矣(ハナハダシ)であるが/思出の記(蘆花)」
よう【葉】🔗⭐🔉
よう エフ 【葉】
■一■ [1] (名)
木の葉の縁のようにとがって角(カド)をなしているところ。「これ(=櫛形ノ穴)は―の入りて,木にて縁をしたりければ/徒然 33」
■二■ (接尾)
助数詞。
(1)木の葉や紙など,薄いものを数えるのに用いる。「一―の写真」
(2)小舟を数えるのに用いる。「一―の舟の中の万里の身/和漢朗詠(雑)」
よう【陽】🔗⭐🔉
よう【様】🔗⭐🔉
よう ヤウ [1] 【様】
(1)ありさま。様子。すがた。「書きたる真名(マンナ)の―,文字の,世に知らずあやしきを/枕草子 103」
(2)決まったかたち。様式。「人の調度のかざりとする,定まれる―あるものを/源氏(帚木)」
(3)やり方。方法。「ふないくさは―ある物ぞとて,鎧直垂は着給はず/平家 11」
(4)事情。理由。わけ。「かせぎ(=鹿)恐るる事なくして来れり。定めて―あるらん/宇治拾遺 7」
(5)同様。同類。「必ずさしも―の物と争ひ給はむもうたてあるべし/源氏(夕霧)」
(6)(形式名詞的に用いて)(ア)発言や思考の内容。こと。「ただ押鮎の口をのみぞ吸ふ。この吸ふ人々の口を押鮎もし思ふ―あらむや/土左」(イ)発言や思考の引用を導く言葉。…こと(には)。「かぢとりの言ふ―,黒鳥のもとに白き波を寄す,とぞいふ/土左」
(7)動詞の連用形の下に付いて,複合語をつくる。(ア)ありさま,様子などの意を表す。「喜び―」「あわて―」(イ)しかた,方法などの意を表す。「言い―」「やり―」
(8)名詞の下に付いて,複合語をつくる。(ア)様式,型などの意を表す。「天平―」「唐(カラ)―」(イ)そういう形をしている,それに似ているなどの意を表す。「寒天―の物体」「カーテン―のもの」
→ようだ
→ようです
よう【瘍】🔗⭐🔉
よう ヤウ [1] 【瘍】
できもの。「―ができる」
よ・う【酔う】🔗⭐🔉
よ・う ヨフ [1] 【酔う】 (動ワ五[ハ四])
〔「ゑふ(酔)」の転〕
(1)酒を飲んで通常の状態でなくなる。酔っ払う。酩酊(メイテイ)する。「―・うと泣き出すくせがある」
(2)乗り物に揺られて気分が悪くなる。また,刺激が強すぎたりして気分が悪くなる。「血ニ―・ウ/日葡」「船に―・う」
(3)物事や雰囲気などに引き込まれ,うっとりとした状態になる。「名演奏に―・う」「雰囲気に―・う」
[可能] よえる
よう【杳】🔗⭐🔉
よう エウ [1] 【杳】 (ト|タル)[文]形動タリ
暗くてはっきりしないさま。はるかなさま。はっきりわからないさま。「―として行方が知れない」「其二箇月が過去つた十月にも筆をとらず,…つい紙上へは―たる有様で暮して仕舞つた/彼岸過迄(漱石)」
よう【良う・善う・能う】🔗⭐🔉
よう [1] 【良う・善う・能う】 (副)
〔「よく」のウ音便〕
(1)十分に。巧みに。上手に。「まだ―は書かずとて/源氏(若紫)」
(2)大層。はなはだ。「いと―似給へり/源氏(桐壺)」
(3)しばしば。たびたび。「おめえたちやあ―喧嘩あするぜえなあ/滑稽本・浮世風呂(前)」
(4)下に推量または反語の語句を伴って,容易にあり得ないことの意を表す。どうして。なかなか。「―,われがやうな者が,ゆるさうわいな/狂言記・胸突」
(5)下に打ち消しの語句を伴って,不可能の意を表す。…することができない。「これほどの所を―飛ばいで,あのなりは/狂言記・飛越新発意」
よう🔗⭐🔉
よう [1] (感)
呼び掛けの語。多く親しい間柄の男どうしが使う。やあ。「―,しばらく」
よう🔗⭐🔉
よう (助動)(○・○・よう・(よう)・○・○)
推量の助動詞。上一段・下一段・カ行変格・サ行変格の動詞,および「れる・られる」「せる・させる」などの助動詞の未然形に接続する。ただし,サ行変格活用の動詞では「し」の形に付く。その意味・用法は,接続のしかた以外の点では,推量の助動詞「う」に同じ。
(1)話し手の意志・決意を表す。「今度こそはテストを受けてみ〈よう〉」「勉強を片付けてから,バイオリンの練習をすることにし〈よう〉」
(2)勧誘や婉曲な命令を表す。下に「か」「じゃないか」などが付いて,意味を強めることがある。「いっしょにジョギングでもし〈よう〉」「少しおなかがすいてきた。すしでも食べ〈よう〉か」
(3)話し手の推量や想像を表す。また,婉曲表現をつくる。「いまは雲が多いが,午後には晴れ〈よう〉」「景気も来年あたりには好転し〈よう〉」
(4)疑問を表す語を伴って,疑問・質問・反語などを表す。「こんな防寒具できびしい冬の寒さが防げ〈よう〉か」「受け入れ準備も,来月には完了し〈よう〉かといったところです」「だれがそんな遠くまで子供を行かせられ〈よう〉」
(5)許容の意を表す。「かねで解決でき〈よう〉ものなら,いくらでも出す」
(6)(連体形を用いて)仮想の意を表す。「このがけがくずれ〈よう〉はずがない」「もう少しで優勝でき〈よう〉ところを,ほんとうに惜しかった」
(7)(「ようとする」の形で)それが実現する直前であることを表す。「家を出〈よう〉とするところに,電話がかかってきた」「助成金がうち切られ〈よう〉としている」
〔一段活用・二段活用の動詞に推量の助動詞「む」を伴ったもの,例えば,「見む」「受けむ」などは,中世末期までに「みう」「うけう」から「みょう」「うきょう」の形に変化していたが,そこから,動詞未然形「み」「うけ」と助動詞「よう」とが分かれて,助動詞「よう」が生ずるに至った。現代語のように,五段活用の動詞には「う」が,その他の活用の動詞には「よう」が付くというように,接続のしかたを補い合うような用法が一般的になるのは近世江戸語以降のことである〕
→う(助動)
よう🔗⭐🔉
よう
〔「よ」の転。「よ」の強く発音されたもの。話し言葉でのくだけた言い方などに用いられる〕
■一■ (終助)
「よ(終助)」に同じ。「すこしは手伝って―」「疲れたぐらいで,何だ―」「もっと早く歩け―」「公園に行こう―」
■二■ (間投助)
「よ(間投助)」に同じ。「中村君―,もう起きろ」「映画を見に行ったら―,きょうは休みだった」
→よ(終助・間投助)
よう-あぶみ【洋鐙】🔗⭐🔉
よう-あぶみ ヤウ― [3] 【洋鐙】
輪(ワ)鐙の一種。明治中頃伝わり,従来の舌長(シタナガ)鐙に代わって用いられるようになった。
洋鐙
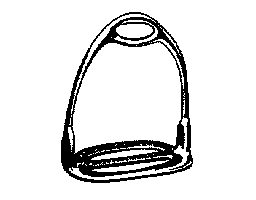 [図]
[図]
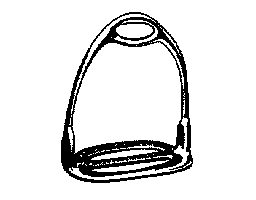 [図]
[図]
よう-い【用意】🔗⭐🔉
よう-い [1] 【用意】 (名)スル
(1)ある行為・行動をする前に,あらかじめ必要なものをとりそろえること。準備。したく。「食事を―する」「旅行の―」
(2)意を用いること。深い心づかいのあること。「女御の御けはひ,ねびにたれど,あくまで―あり/源氏(花散里)」
ようい-しゅうとう【用意周到】🔗⭐🔉
ようい-しゅうとう ―シウタウ [1] 【用意周到】 (名・形動)[文]ナリ
用意が十分にととのっていること。手ぬかりなく用意すること。また,そのさま。
ようい-どん【用意どん】🔗⭐🔉
ようい-どん [1] 【用意どん】
かけっこなどで,出発を告げる合図の言葉。また,かけっこ。転じて,何人かが同時に一斉に物事をし始めることにもいう。
よう-い【妖異】🔗⭐🔉
よう-い エウ― [1] 【妖異】
あやしく不思議なこと。また,そのもの。妖怪。
よう-い【洋医】🔗⭐🔉
よう-い ヤウ― [1] 【洋医】
(1)西洋医学を学んだ医師。「医と云へば,漢医も―も/福翁百話(諭吉)」
(2)西洋人の医師。
よう-い【容易】🔗⭐🔉
よう-い [0] 【容易】 (名・形動)[文]ナリ
たやすいこと。やさしいこと。また,そのさま。「―に行ける」「―ではない」
[派生] ――さ(名)
よう-い【庸医】🔗⭐🔉
よう-い [1] 【庸医】
凡庸な医者。平凡な医者。やぶ医者。
よう-イオン【陽―】🔗⭐🔉
よう-イオン ヤウ― [3] 【陽―】
正の電気を帯びた原子または原子団。カチオン。
⇔陰イオン
よう-いく【養育】🔗⭐🔉
よう-いく ヤウ― [0] 【養育】 (名)スル
(1)子供をそだてること。「―費」
(2)老人・孤児・病人などを保護すること。「―院」
よう-いん【要因】🔗⭐🔉
よう-いん エウ― [0] 【要因】
〔agent〕
物事が生じた,主要な原因。
よういん-しょうけん【要因証券】🔗⭐🔉
よういん-しょうけん エウ― [5] 【要因証券】
証券上の権利の発生に,証券発行の原因となった法律関係が有効であることを必要とする有価証券。船荷証券・倉庫証券など。有因証券。
⇔無因証券
よう-いん【要員】🔗⭐🔉
よう-いん エウ ン [0] 【要員】
ある事をなすのに必要な人員。
ン [0] 【要員】
ある事をなすのに必要な人員。
 ン [0] 【要員】
ある事をなすのに必要な人員。
ン [0] 【要員】
ある事をなすのに必要な人員。
よう-うん【妖雲】🔗⭐🔉
よう-うん エウ― [0] 【妖雲】
不吉な事の起こるのを暗示しているような気味の悪い雲。
よう-えい【揺曳】🔗⭐🔉
よう-えい エウ― [0] 【揺曳】 (名)スル
(1)ゆらゆらとたなびくこと。「水平線に―する船の煙」
(2)音などがあとあとまで尾を引いて残ること。「楽音の―は/うづまき(敏)」
よう-えき【用役】🔗⭐🔉
よう-えき [1] 【用役】
(1)社会に役立つはたらき。
(2)サービス{(4)}に同じ。
よう-えき【用益】🔗⭐🔉
よう-えき [0] 【用益】
使用と収益。
ようえき-けん【用益権】🔗⭐🔉
ようえき-けん [4][3] 【用益権】
〔法〕
(1)「使用収益権」に同じ。また,そのもととなる用益物権・賃借権などの権利をさす。
(2)民法旧規定上,他人の所有物をその本体を変えずに一定期間使用する権利。
ようえき-ぶっけん【用益物権】🔗⭐🔉
ようえき-ぶっけん [5] 【用益物権】
他人の土地を使用・収益する物権。民法上は地上権・永小作権・地役権・入会権。
よう-えき【要駅】🔗⭐🔉
よう-えき エウ― [0] 【要駅】
交通上,重要な宿場や鉄道の駅。
よう-えき【葉腋】🔗⭐🔉
よう-えき エフ― [0][1] 【葉腋】
植物の葉が茎に付着する部分で,芽ができるところ。
よう-えき【傭役】🔗⭐🔉
よう-えき [0] 【傭役】 (名)スル
人を雇って使うこと。また,雇われて使われること。
よう-えき【徭役】🔗⭐🔉
よう-えき エウ― [0] 【徭役】
律令制下の労役の総称。特に,雑徭(ゾウヨウ)と歳役(サイエキ)。
よう-えき【溶液】🔗⭐🔉
よう-えき [1] 【溶液】
液体状態にある均一な混合物。その成分のうち,最も多量に存在する液体物質(溶かしている物質)を溶媒,その他の物質(溶けている物質)を溶質という。水が溶媒の場合は水溶液というが,水溶液であることが明らかな場合は,単に溶液という。
→溶体
ようえき-さいばい【養液栽培】🔗⭐🔉
ようえき-さいばい ヤウエキ― [5] 【養液栽培】
土を使わずに液肥で栽培すること。気温・湿度・照明などを調節できるので周年栽培が可能。石油・電気などのエネルギーを大量に消費する。
ようえき-ち【要役地】🔗⭐🔉
ようえき-ち エウエキ― [4][3] 【要役地】
〔法〕 地役権が設定されたとき,承役地から便益を受ける土地。
よう-えん【妖婉・妖艶】🔗⭐🔉
よう-えん [0] エウ ン 【妖婉】 ・ エウエン 【妖艶】 (名・形動)[文]ナリ
あでやかで美しいこと。男性を惑わすようなあやしい美しさのあるさま。「黒髪を乱した―な女/或る女(武郎)」
[派生] ――さ(名)
ン 【妖婉】 ・ エウエン 【妖艶】 (名・形動)[文]ナリ
あでやかで美しいこと。男性を惑わすようなあやしい美しさのあるさま。「黒髪を乱した―な女/或る女(武郎)」
[派生] ――さ(名)
 ン 【妖婉】 ・ エウエン 【妖艶】 (名・形動)[文]ナリ
あでやかで美しいこと。男性を惑わすようなあやしい美しさのあるさま。「黒髪を乱した―な女/或る女(武郎)」
[派生] ――さ(名)
ン 【妖婉】 ・ エウエン 【妖艶】 (名・形動)[文]ナリ
あでやかで美しいこと。男性を惑わすようなあやしい美しさのあるさま。「黒髪を乱した―な女/或る女(武郎)」
[派生] ――さ(名)
よう-えん【陽炎】🔗⭐🔉
よう-えん ヤウ― [0] 【陽炎】
かげろう。
よう-えん【楊炎】🔗⭐🔉
よう-えん ヤウ― 【楊炎】
(727-781) 中国,唐の政治家。徳宗のとき宰相になり,安史の乱で破綻した財政回復のため,780年両税法を施行,中国税制史上に一大改革を行なったが,のち失脚,殺された。
よう-えん【遥遠】🔗⭐🔉
よう-えん エウ ン [0] 【遥遠】 (形動)[文]ナリ
はるかで遠いさま。「其位置の相異なる―なれば/花柳春話(純一郎)」
ン [0] 【遥遠】 (形動)[文]ナリ
はるかで遠いさま。「其位置の相異なる―なれば/花柳春話(純一郎)」
 ン [0] 【遥遠】 (形動)[文]ナリ
はるかで遠いさま。「其位置の相異なる―なれば/花柳春話(純一郎)」
ン [0] 【遥遠】 (形動)[文]ナリ
はるかで遠いさま。「其位置の相異なる―なれば/花柳春話(純一郎)」
よう-おく【楊億】🔗⭐🔉
よう-おく ヤウ― 【楊億】
(974-1020) 中国,北宋の文学者・詩人。福建省の人。「冊府元亀(サツプゲンキ)」の編纂にあたる。唱和詩をまとめた「西崑酬唱集」は西崑体と称され,宋初の詩壇に大きな影響を及ぼした。
→冊府元亀
よう-おん【拗音】🔗⭐🔉
よう-おん エウ― [1] 【拗音】
日本語の音節のうち,「キャ」「シュ」「チョ」「クヮ」のように二字の仮名で書き表すもの。例えば,カ [ka] の子音と母音の間に,半母音 [j] が入ってキャ [kja] となり,半母音 [w] が入ってクヮ [kwa] となるの類。本来の日本語の音節にはなく,漢字音をとり入れたために生じたもの。ヤ・ユ・ヨを添えて表す開拗音と,ワ(ヰ・ヱ)を添えて表す合拗音との二種類がある。現代仮名遣いでは,前者は,イ段の仮名に小文字の「や」「ゆ」「よ」を添えて書く(「きゃ」「しゅ」「ちょ」など)が,後者は特にこれを表記することはしない。もっとも,歴史的仮名遣いでは,「く」「ぐ」に「わ」を添えて書く(「くゎ」「ぐゎ」の類)。
⇔直音
よう-か【八日】🔗⭐🔉
よう-か ヤウ― [0] 【八日】
(1)八つの日数。
(2)月の八番目の日。
よう-か【妖花】🔗⭐🔉
よう-か エウクワ [1] 【妖花】
美しいが,人にあやしく不吉な感じを与える花。また,あやしい美しさをもつ女性。
よう-か【沃化】🔗⭐🔉
よう-か エウクワ [0] 【沃化】 (名)スル
ヨウ素と化合すること。また,ヨウ素と化合した物質。
〔自然科学では「ヨウ化」と書く〕
よう-か【洋貨】🔗⭐🔉
よう-か ヤウクワ [1] 【洋貨】
(1)西洋の貨幣。
(2)西洋から舶来した貨物。また,その物品。
よう-か【溶化・熔化】🔗⭐🔉
よう-か ―クワ [0] 【溶化・熔化】 (名)スル
熱してとかすこと。熱でとけること。「玻質を―すべき火炉/新聞雑誌 45」
よう-か【楊家】🔗⭐🔉
よう-か ヤウ― [1] 【楊家】
楊朱の学説を受け継ぐ学者。
よう-か【蛹化】🔗⭐🔉
よう-か【養価】🔗⭐🔉
よう-か ヤウ― [1] 【養価】
栄養価。
よう-か【養家】🔗⭐🔉
よう-か ヤウ― [1] 【養家】
養子として入籍した家。養子先の家。
よう-が【幼芽】🔗⭐🔉
よう-が エウ― [1][0] 【幼芽】
(1)生え出たばかりの芽。
(2)種子の胚にできる芽。発芽して地上茎になる。
よう-が【葉芽】🔗⭐🔉
よう-が エフ― [0][1] 【葉芽】
発達して葉や茎になる芽。花芽より小形でふくらみ方が少ない。
よう-かい【妖怪】🔗⭐🔉
よう-かい エウクワイ [0] 【妖怪】
日常の経験や理解を超えた不思議な存在や現象。山姥・天狗・一つ目小僧・海坊主・河童・雪女など。ばけもの。
よう-かい【要解】🔗⭐🔉
よう-かい エウ― [0] 【要解】
要点をかいつまんで解説すること。多く書名などに用いられる。「―世界史」
よう-かい【容喙】🔗⭐🔉
よう-かい [0] 【容喙】 (名)スル
〔「喙」は,くちばし〕
横から口を出すこと。くちばしを入れること。「私の―する限ではないが/坊っちゃん(漱石)」
よう-かい【溶解】🔗⭐🔉
よう-かい [0] 【溶解】 (名)スル
(1)とけること。とかすこと。
(2)気体・液体・固体状の物質が,ほかの物質(液体・固体)に溶けて,均一な混合物をつくる現象。
→溶体
(3)転じて,疑いや心のしこりなどがすっかりとけてなくなること。「次第に其敵意を―するを得べし/文明論之概略(諭吉)」
よう-かい【熔解・鎔解】🔗⭐🔉
よう-かい [0] 【熔解・鎔解】 (名)スル
固体が加熱により液体状態になること。溶融。融解。
よう-がい【瑩貝】🔗⭐🔉
よう-がい ヤウガヒ [0] 【瑩貝】
紙・布などをこすって光沢を出すための貝がら。竹や金属で作ったものもいう。
よう-がい【幼孩】🔗⭐🔉
よう-がい エウ― [0] 【幼孩】
〔「孩」は赤んぼうの意〕
ちのみご。おさなご。
よう-がい【要害】🔗⭐🔉
よう-がい エウ― [0] 【要害】
(1)険しい地形で,敵の攻撃を防ぐのに便利なこと。また,その土地。「―の地」
(2)城塞。城郭。とりで。「天然の―」
(3)防御をかためること。用心すること。「様体みるに厳しく―して/浮世草子・武道伝来記 7」
ようがい-けんご【要害堅固】🔗⭐🔉
ようがい-けんご エウ― [5] 【要害堅固】
地形がけわしく防備が固く,容易には破られないこと。「―の城」
ようかいち【八日市】🔗⭐🔉
ようかいち ヤウカイチ 【八日市】
滋賀県中東部の市。古くから市場町として発達。繊維・化学工業などが立地。
よう(和英)🔗⭐🔉
よう
[呼びかけ]Hello there!/Hi!
よう【酔う】(和英)🔗⭐🔉
よう【酔う】
[酒に]get drunk[tipsy];[乗物に]get seasick[carsick,airsick];be a bad[poor]sailor;[夢中になる]be intoxicated.
よう【用】(和英)🔗⭐🔉
よう【用】
(1)[用事]business.→英和
〜がある have something to do;be busy.〜がない nothing to do;be free.〜を足す do one's business.〜をなさない be no good;be useless.(2) ⇒用便.
‖家庭用 for home use.公(私,商)用で on official (private,commercial) business.男子(婦人)用 men's (ladies').
よう【幼にして】(和英)🔗⭐🔉
よう【幼にして】
in one's early life;as a child.→英和
よう【洋の東西を問わず】(和英)🔗⭐🔉
よう【洋の東西を問わず】
both in the West and the East;everywhere in the world.→英和
よう【陽の】(和英)🔗⭐🔉
よう【陽の】
positive.→英和
ようあん【溶暗】(和英)🔗⭐🔉
ようあん【溶暗】
《映》fade-out.〜になる fade out.
ようい【用意する】(和英)🔗⭐🔉
ようい【用意する】
prepare;→英和
getready;prepare[arrange,provide];make preparations;make arrangements;get[make]ready.〜が出来ている be prepared[ready].‖用意周到な cautious;careful;prudent.
ようい【容易な】(和英)🔗⭐🔉
よういん【要因】(和英)🔗⭐🔉
よういん【要因】
a[an important]factor.→英和
よういん【要員】(和英)🔗⭐🔉
ようえき【溶液】(和英)🔗⭐🔉
ようえき【溶液】
asolution.→英和
ようえん【妖艶な】(和英)🔗⭐🔉
ようえん【妖艶な】
fascinating;bewitching.→英和
ようおん【拗音】(和英)🔗⭐🔉
ようおん【拗音】
a contracted sound.
ようか【養家】(和英)🔗⭐🔉
ようか【養家】
the adoptive family.
ようか【沃化】(和英)🔗⭐🔉
ようか【沃化】
《化》iodation.沃化銀 silver iodide.
ようが【洋画】(和英)🔗⭐🔉
ようが【洋画】
a Western-style painting (絵画);a foreign film (映画).洋画家 an artist in the Western style.
ようが【陽画】(和英)🔗⭐🔉
ようが【陽画】
《写》a positive (picture).→英和
ようかい【妖怪】(和英)🔗⭐🔉
ようかい【妖怪】
⇒お化け.
ようかい【容喙】(和英)🔗⭐🔉
ようかい【容喙】
⇒でしゃばる.
広辞苑+大辞林に「ヨウ」で始まるの検索結果。もっと読み込む
 (セツ)
(セツ)