複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (10)
おしまずき【几】オシマヅキ🔗⭐🔉
おしまずき【几】オシマヅキ
①脇息きょうそく。斉明紀「―自づからに断おれぬ」
②(女房詞)机。
③牛車の前の横木。軾しょく。〈類聚名義抄〉
き‐あん【几案】🔗⭐🔉
き‐あん【几案】
机つくえ。
き‐か【机下・几下】🔗⭐🔉
き‐か【机下・几下】
(「几」も机)書簡で、宛名に添えて書く語。相手の机の下まで差し出すという意で、敬意を表す。案下。おそば。おてもと。「山田太郎先生―」
き‐ちょう【几帳・木丁】‥チヤウ🔗⭐🔉
き‐ちょう【几帳・木丁】‥チヤウ
(几おしまずきに帳とばりをかけたところからの名)屏障具の一つ。室内に立てて隔てとし、また座側に立ててさえぎるための具。土居つちいと呼ぶ台に2本の円柱を立て、柱の上に1本の長い横木をわたし、その横木に縦はぎのとばりと幅筋のすじを掛けたもの。御帳台、壁代、御簾のつら、女性の座側などに立てる。冬は練絹に朽木形、夏は生絹すずしに花鳥など。また裾濃すそご・香染・綾・白・鈍色にびいろなどがあり、4尺・3尺の几帳、枕几帳・寄几帳・指几帳など、種々ある。
几帳
 ⇒きちょう‐ごし【几帳越し】
⇒きちょう‐じゃく【几帳尺】
⇒きちょう‐めん【几帳面】
⇒きちょう‐ごし【几帳越し】
⇒きちょう‐じゃく【几帳尺】
⇒きちょう‐めん【几帳面】
 ⇒きちょう‐ごし【几帳越し】
⇒きちょう‐じゃく【几帳尺】
⇒きちょう‐めん【几帳面】
⇒きちょう‐ごし【几帳越し】
⇒きちょう‐じゃく【几帳尺】
⇒きちょう‐めん【几帳面】
きちょう‐ごし【几帳越し】‥チヤウ‥🔗⭐🔉
きちょう‐ごし【几帳越し】‥チヤウ‥
几帳を隔てていること。源氏物語花宴「―に手をとらへて」
⇒き‐ちょう【几帳・木丁】
きちょう‐じゃく【几帳尺】‥チヤウ‥🔗⭐🔉
きちょう‐じゃく【几帳尺】‥チヤウ‥
(平安時代以後、几帳の寸法をはかるのに用いたからいう)曲尺かねじゃくの古称。
⇒き‐ちょう【几帳・木丁】
きちょう‐めん【几帳面】‥チヤウ‥🔗⭐🔉
きちょう‐めん【几帳面】‥チヤウ‥
①〔建〕面の一種。方形の角を撫角なでかくに削り、その両側に段をつけたもの。もと几帳の柱に多く用いたからいう。
几帳面
 ②物事をすみずみまで気をつけ、きちんとするさま。「―な性格」「―に家計簿をつける」
⇒き‐ちょう【几帳・木丁】
②物事をすみずみまで気をつけ、きちんとするさま。「―な性格」「―に家計簿をつける」
⇒き‐ちょう【几帳・木丁】
 ②物事をすみずみまで気をつけ、きちんとするさま。「―な性格」「―に家計簿をつける」
⇒き‐ちょう【几帳・木丁】
②物事をすみずみまで気をつけ、きちんとするさま。「―な性格」「―に家計簿をつける」
⇒き‐ちょう【几帳・木丁】
きとう【几董】🔗⭐🔉
きとう【几董】
⇒たかいきとう(高井几董)
《几部》🔗⭐🔉
《几部》
(きにょう)
物をのせる台の意を表す。また、「風」の省略形「 」(「かぜがまえ」「かぜがしら」と通称)を持つ字もこの部に収める。
」(「かぜがまえ」「かぜがしら」と通称)を持つ字もこの部に収める。
 」(「かぜがまえ」「かぜがしら」と通称)を持つ字もこの部に収める。
」(「かぜがまえ」「かぜがしら」と通称)を持つ字もこの部に収める。
[漢]几🔗⭐🔉
几 字形
 〔几部0画/2画/4960・515C〕
〔音〕キ(呉)(漢)
〔訓〕つくえ
[意味]
①つくえ。(同)机。「几案・浄几」
②ひじかけ。「几杖きじょう」
③台。腰掛け。「床几」
[解字]
脚付きの四角い台の象形文字。「机」の原字。現代中国語では「幾」の簡体字。
〔几部0画/2画/4960・515C〕
〔音〕キ(呉)(漢)
〔訓〕つくえ
[意味]
①つくえ。(同)机。「几案・浄几」
②ひじかけ。「几杖きじょう」
③台。腰掛け。「床几」
[解字]
脚付きの四角い台の象形文字。「机」の原字。現代中国語では「幾」の簡体字。
 〔几部0画/2画/4960・515C〕
〔音〕キ(呉)(漢)
〔訓〕つくえ
[意味]
①つくえ。(同)机。「几案・浄几」
②ひじかけ。「几杖きじょう」
③台。腰掛け。「床几」
[解字]
脚付きの四角い台の象形文字。「机」の原字。現代中国語では「幾」の簡体字。
〔几部0画/2画/4960・515C〕
〔音〕キ(呉)(漢)
〔訓〕つくえ
[意味]
①つくえ。(同)机。「几案・浄几」
②ひじかけ。「几杖きじょう」
③台。腰掛け。「床几」
[解字]
脚付きの四角い台の象形文字。「机」の原字。現代中国語では「幾」の簡体字。
大辞林の検索結果 (8)
おしまずき【几】🔗⭐🔉
おしまずき オシマヅキ 【几】
(1)脇息(キヨウソク)。[和名抄]
(2)机のこと。「ただ―にかかりて夕の空に向ふのみ/笈日記」
(3)牛車(ギツシヤ)の前後の口の下に張った低い仕切りの板。軾(シヨク)。戸閾(トジキミ)。[名義抄]
き-あん【几案・机案】🔗⭐🔉
き-あん [0] 【几案・机案】
〔「几」「案」とも机(ツクエ)の意〕
机。
き-か【机下・几下】🔗⭐🔉
き-か [1][2] 【机下・几下】
〔相手の机の下に差し出す意〕
書簡文で,相手を敬ってあて名に添える脇付(ワキヅケ)の一。案下。
き-ちょう【几帳】🔗⭐🔉
き-ちょう ―チヤウ [0] 【几帳】
〔「几(オシマズキ)にかけた帳(トバリ)」の意〕
寝殿造りに用いた室内調度の一。室内に立てて間仕切りとし,また座のわきに立てて隔てとした。台に二本の柱を立て,その上に一本の横木をわたし,帳を垂らしたもの。高さ三尺のものと四尺のものとがあり,三尺には四幅(ヨノ),四尺には五幅(イツノ)の帳を垂らす。基帳。木丁。
几帳
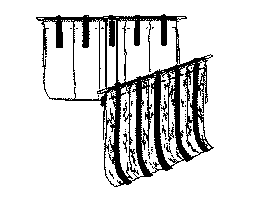 [図]
[図]
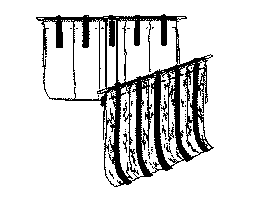 [図]
[図]
きちょう-じゃく【几帳尺】🔗⭐🔉
きちょう-じゃく ―チヤウ― [2] 【几帳尺】
曲尺(カネジヤク)の古称。平安時代以降,几帳の寸法を測るのに用いたのでいう。
きちょう-めん【几帳面】🔗⭐🔉
きちょう-めん ―チヤウ― [4][0] 【几帳面】
■一■ (形動)[文]ナリ
きちんとしているさま。すみずみまで規則正しくするさま。「―な性格」
■二■ (名)
柱などの角に施した面の一。方形の角を落として鋭角に削り,その両側に刻みを入れたもの。もと几帳の柱に用いられたことからいう。
几帳面■二■
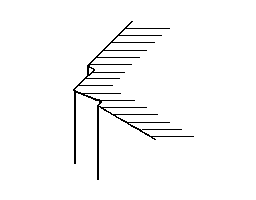 [図]
[図]
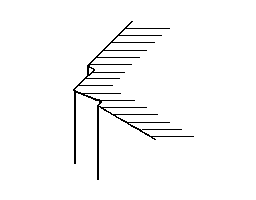 [図]
[図]
きとう【几董】🔗⭐🔉
きとう 【几董】
⇒高井(タカイ)几董
広辞苑+大辞林に「几」で始まるの検索結果。