複数辞典一括検索+![]()
![]()
あみ【網】🔗⭐🔉
あみ [2] 【網】
(1)糸や針金などを編んで枡形(マスガタ)の目を表したもの。(ア)魚や鳥などを捕らえるのに用いるもの。(イ)食べ物を焼くのに用いるもの。「―で餅を焼く」
(2)人や物を捕らえるために張りめぐらされたもの。「捜査の―をしぼる」「法律の―をくぐる」
→網の目
(3)印刷で,規則的に並んでいる小さな点のこと。網点。
あみ【醤蝦・糠蝦】🔗⭐🔉
あみ [2] 【醤蝦・糠蝦】
甲殻綱アミ目のエビに似た節足動物の一群の総称。体長1〜2センチメートル。体は透明。雌には哺育嚢(ホイクノウ)がある。ほとんどが海産で,日本近海で約一三〇種が知られるが,汽水・淡水にすむ種もある。飼料や釣りのまき餌にしたり,塩辛・佃煮(ツクダニ)など食用にする。
あみ【阿弥】🔗⭐🔉
あみ [1] 【阿弥】
⇒阿弥陀号(アミダゴウ)
アミ (フランス) ami; amie
(フランス) ami; amie 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
アミ [2]  (フランス) ami; amie
(フランス) ami; amie 親しい友人。また,愛人。
親しい友人。また,愛人。
 (フランス) ami; amie
(フランス) ami; amie 親しい友人。また,愛人。
親しい友人。また,愛人。
アミア (ラテン) Amia
(ラテン) Amia 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
アミア [1]  (ラテン) Amia
(ラテン) Amia アミア目の淡水魚。全長90センチメートルに達する。中生代のジュラ紀から白亜紀にかけて栄えた下等な硬骨魚類で,シーラカンス・肺魚・チョウザメと並んで原始的な形質を残す。北アメリカ東部に分布。
アミア目の淡水魚。全長90センチメートルに達する。中生代のジュラ紀から白亜紀にかけて栄えた下等な硬骨魚類で,シーラカンス・肺魚・チョウザメと並んで原始的な形質を残す。北アメリカ東部に分布。
 (ラテン) Amia
(ラテン) Amia アミア目の淡水魚。全長90センチメートルに達する。中生代のジュラ紀から白亜紀にかけて栄えた下等な硬骨魚類で,シーラカンス・肺魚・チョウザメと並んで原始的な形質を残す。北アメリカ東部に分布。
アミア目の淡水魚。全長90センチメートルに達する。中生代のジュラ紀から白亜紀にかけて栄えた下等な硬骨魚類で,シーラカンス・肺魚・チョウザメと並んで原始的な形質を残す。北アメリカ東部に分布。
あみあげ-ぐつ【編(み)上げ靴】🔗⭐🔉
あみあげ-ぐつ [4] 【編(み)上げ靴】
靴のひもを編み上げて,足首や脛(スネ)を締めるようにしてはく半長靴。軍靴など。編上靴(ヘンジヨウカ)。あみあげ。
あみ-あ・げる【編(み)上げる】🔗⭐🔉
あみ-あ・げる [4][0] 【編(み)上げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 あみあ・ぐ
(1)編み物を編み終える。「セーターを―・げる」
(2)本などを編集しおえる。「アンソロジーを―・げる」
あみ-あぶら【網脂】🔗⭐🔉
あみ-あぶら [3] 【網脂】
豚や牛の内臓を包んでいる網状の脂肪。肉などを包んで焼いたり揚げたりする。クレピーヌ。
アミアン Amiens
Amiens 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
アミアン  Amiens
Amiens フランス北部の都市。ラシャ地製造など繊維工業が盛ん。
フランス北部の都市。ラシャ地製造など繊維工業が盛ん。
 Amiens
Amiens フランス北部の都市。ラシャ地製造など繊維工業が盛ん。
フランス北部の都市。ラシャ地製造など繊維工業が盛ん。
アミアン-だいせいどう【―大聖堂】🔗⭐🔉
アミアン-だいせいどう ―セイダウ 【―大聖堂】
アミアンにあるゴシック様式の代表的建築。1220年起工。全長145メートル,身廊高43メートルで,フランスのゴシック大聖堂中最大。
アミアン-の-わやく【―の和約】🔗⭐🔉
アミアン-の-わやく 【―の和約】
1802年英仏間に結ばれたナポレオン戦争中の講和条約。両国の占領地を旧主に返還することを約し,これにより第二回対仏大同盟は解体。
あみ-あんどん【網行灯】🔗⭐🔉
あみ-あんどん [3] 【網行灯】
鉄の枠に金網を張った行灯。
アミーゴ (スペイン) amigo
(スペイン) amigo 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
アミーゴ [2]  (スペイン) amigo
(スペイン) amigo 友達。友人。仲間。
友達。友人。仲間。
 (スペイン) amigo
(スペイン) amigo 友達。友人。仲間。
友達。友人。仲間。
アミーバ amoeba
amoeba 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
あみいり-ガラス【網入り―】🔗⭐🔉
あみいり-ガラス [5] 【網入り―】
格子・亀甲(キツコウ)・縞状の金網を封じ込んだ板ガラス。破損しても破片が散乱しにくく,防火用ガラスなどに使用される。ワイヤ-グラス。
あみ-うち【網打ち】🔗⭐🔉
あみ-うち [0] 【網打ち】
(1)投網(トアミ)を打ち,魚を取ること。また,その人。
(2)相撲の決まり手の一。相手の差し手を両手でかかえ,差し手の側へひねり倒す技。
あみうち-ば【網打場】🔗⭐🔉
あみうち-ば 【網打場】
江戸深川にあった下級の遊里の一。
あみ-えり【網 】🔗⭐🔉
】🔗⭐🔉
あみ-えり [0] 【網 】
】
 (エリ)の一種。竹や葦(アシ)の簀(ス)の代わりに網地を立て回したもの。琵琶湖・霞ヶ浦などで用いられる。
(エリ)の一種。竹や葦(アシ)の簀(ス)の代わりに網地を立て回したもの。琵琶湖・霞ヶ浦などで用いられる。
 】
】
 (エリ)の一種。竹や葦(アシ)の簀(ス)の代わりに網地を立て回したもの。琵琶湖・霞ヶ浦などで用いられる。
(エリ)の一種。竹や葦(アシ)の簀(ス)の代わりに網地を立て回したもの。琵琶湖・霞ヶ浦などで用いられる。
アミエル Henri Fr
Henri Fr d
d ric Amiel
ric Amiel 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
アミエル  Henri Fr
Henri Fr d
d ric Amiel
ric Amiel (1821-1881) スイスの哲学者・文学者。ベルリン滞在を通じてヘーゲル・シェリングの影響を受ける。三十数年間にわたる真摯(シンシ)な内省の記録「日記」で名高い。
(1821-1881) スイスの哲学者・文学者。ベルリン滞在を通じてヘーゲル・シェリングの影響を受ける。三十数年間にわたる真摯(シンシ)な内省の記録「日記」で名高い。
 Henri Fr
Henri Fr d
d ric Amiel
ric Amiel (1821-1881) スイスの哲学者・文学者。ベルリン滞在を通じてヘーゲル・シェリングの影響を受ける。三十数年間にわたる真摯(シンシ)な内省の記録「日記」で名高い。
(1821-1881) スイスの哲学者・文学者。ベルリン滞在を通じてヘーゲル・シェリングの影響を受ける。三十数年間にわたる真摯(シンシ)な内省の記録「日記」で名高い。
あみ-がさ【編み笠】🔗⭐🔉
あみ-がさ [3] 【編み笠】
藁(ワラ)・菅(スゲ)・藺草(イグサ)などを編んで作った笠。[季]夏。
あみがさ-そう【編笠草】🔗⭐🔉
あみがさ-そう ―サウ [0] 【編笠草】
エノキグサの別名。
あみがさ-たけ【編笠茸】🔗⭐🔉
あみがさ-たけ [4] 【編笠茸】
子嚢菌(シノウキン)類チャワンタケ目のきのこ。五月頃庭先などに生える。高さ約10センチメートル。頭部は淡褐色で,球形または卵形。表面一面に網目状のくぼみがある。柄は太く頭部とともに中空。欧米では食用とする。
編笠茸
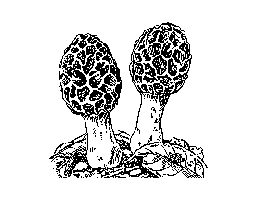 [図]
[図]
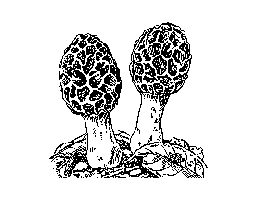 [図]
[図]
あみがさ-ぢゃや【編み笠茶屋】🔗⭐🔉
あみがさ-ぢゃや 【編み笠茶屋】
江戸時代,遊里に通う客に顔をかくすための編み笠を貸した茶屋。「泥町の―に一歩/浮世草子・諸艶大鑑 2」
あみがさ-もち【編み笠餅】🔗⭐🔉
あみがさ-もち [4] 【編み笠餅】
 粉(シンコ)を練って編み笠の形に作り,中に餡(アン)を入れた菓子。編み笠団子。
粉(シンコ)を練って編み笠の形に作り,中に餡(アン)を入れた菓子。編み笠団子。
 粉(シンコ)を練って編み笠の形に作り,中に餡(アン)を入れた菓子。編み笠団子。
粉(シンコ)を練って編み笠の形に作り,中に餡(アン)を入れた菓子。編み笠団子。
あみがさ-ゆり【編笠百合】🔗⭐🔉
あみがさ-ゆり [4] 【編笠百合】
ユリ科の多年草。中国原産。高さ約50センチメートル。葉は広線形。晩春,茎頂に淡黄緑色で鐘形の花を下向きに数個つける。花の内面に紫色の網状の紋がある。鱗茎を煎(セン)じて咳止めに用いる。貝母(バイモ)。古名ハハクリ。
編笠百合
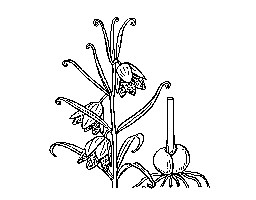 [図]
[図]
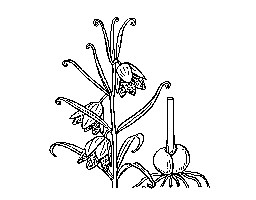 [図]
[図]
あみ-がしら【網頭・罔頭】🔗⭐🔉
あみ-がしら [3] 【網頭・罔頭】
漢字の頭(カシラ)の一。「罕」の「 」,「罪」「署」などの「
」,「罪」「署」などの「 」の部分。網の種類・状態などを表す文字を作る。
」の部分。網の種類・状態などを表す文字を作る。
 」,「罪」「署」などの「
」,「罪」「署」などの「 」の部分。網の種類・状態などを表す文字を作る。
」の部分。網の種類・状態などを表す文字を作る。
あみ-き【編(み)機】🔗⭐🔉
あみ-き [2] 【編(み)機】
編み物をする機械。
あみ-ぎぬ【網衣】🔗⭐🔉
あみ-ぎぬ [3] 【網衣】
(1)網のように粗く織った布で作った衣服。経帷子(キヨウカタビラ)などに用いる。
(2)時宗の僧の着た目の粗い法衣。衆生(シユジヨウ)を救う網の意からとも,また阿弥の着る法衣の意からともいう。阿弥衣。
アミグダリン amygdalin
amygdalin 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
アミグダリン [4]  amygdalin
amygdalin 杏仁・アーモンドなどに含まれる配糖体。分解して有毒の青酸塩を生ずる。
杏仁・アーモンドなどに含まれる配糖体。分解して有毒の青酸塩を生ずる。
 amygdalin
amygdalin 杏仁・アーモンドなどに含まれる配糖体。分解して有毒の青酸塩を生ずる。
杏仁・アーモンドなどに含まれる配糖体。分解して有毒の青酸塩を生ずる。
あみ-ぐみ【網組】🔗⭐🔉
あみ-ぐみ [0] 【網組】
漁網・労力を提供し合って,共同で網漁業を行うための組織。
あみ-こ【網子】🔗⭐🔉
あみ-こ [0] 【網子】
網元(網主)に労力を提供し,実際に網漁業に従事する者。あご。
あみ-こ・む【編(み)込む】🔗⭐🔉
あみ-こ・む [3] 【編(み)込む】 (動マ五[四])
糸・籐(トウ)・髪などを編む時に,異なる色や素材のものを一緒にして編む。また,別の色のもので模様を表す。「花模様を―・む」
あみ-さ・す【網さす】🔗⭐🔉
あみ-さ・す 【網さす】 (動サ四)
鳥網を張る。「ほととぎす夜声なつかし―・さば/万葉 3917」
あみじ-ぐさ【網地草】🔗⭐🔉
あみじ-ぐさ アミヂ― [3] 【網地草】
褐藻類アミジグサ目の海藻。各地の海岸に普通に見られる。全長5〜30センチメートルの細いリボン状で,規則的に二またに分枝している。
あみ-ジバン【網―】🔗⭐🔉
あみ-ジバン [3] 【網―】
(1)こよりで粗く編んだ汗取り用の肌襦袢(ジバン)。また,綿・麻などでレース編みにした夏用の襦袢。[季]夏。
(2)歌舞伎衣装の一。鎖帷子(クサリカタビラ)に似せたもので,武士や盗人の扮装に用いる。黒糸で編み,筒袖としたもの。
あみじま【網島】🔗⭐🔉
あみじま 【網島】
大阪市都島区内の地名。淀川と寝屋川の合流点付近。近松門左衛門の「心中天の網島」で知られる。
あみ-じゃくし【網杓子】🔗⭐🔉
あみ-じゃくし [3] 【網杓子】
すくい取る部分が金網になっている杓子。汁の実・かすなどを取るのに用いる。
あみ-シャツ【網―】🔗⭐🔉
あみ-シャツ [0][3] 【網―】
網目のように織った布地のシャツ。主に,夏の肌着に用いる。
あみ-じょう【網状】🔗⭐🔉
あみ-じょう ―ジヤウ [0] 【網状】
網の目のような形状をなしていること。
あみじょう-こうぶんし【網状高分子】🔗⭐🔉
あみじょう-こうぶんし ―ジヤウカウ― [7] 【網状高分子】
原子が三次元的な化学結合によって配列している高分子物質。分子どうしが三つ以上の基で結合したり,鎖状高分子間の架橋結合によって生ずる。フェノール樹脂・アルキド樹脂・加硫ゴムなど。
あみじょう-せいうん【網状星雲】🔗⭐🔉
あみじょう-せいうん ―ジヤウ― [5] 【網状星雲】
白鳥座にある星雲の一。数万年前に爆発した超新星の残骸。繊維状に光って見え,膨張し続けているガス体。
あみ-しろ【網代】🔗⭐🔉
あみ-しろ [0] 【網代】
漁業経営で,漁網に対する漁獲物の配分。
あみ・す【浴みす】🔗⭐🔉
あみ・す 【浴みす】 (動サ下二)
あびせる。あむす。「新しき湯ぶね構へて,三位中将に―・せ奉らむとす/平家(一七・長門本)」
あみ・す【網す】🔗⭐🔉
あみ・す 【網す】 (動サ変)
魚・鳥などを捕らえるために網をかける。また,クモが網を張る。「きすごといふうをを―・して/笈の小文」
あみ-すき【網結】🔗⭐🔉
あみ-すき [0][4] 【網結】
網を編むこと。また,それを業とする人。
あみすき-ばり【網結針】🔗⭐🔉
あみすき-ばり [5] 【網結針】
網を編む時に使う扁平な船形の針。竹・プラスチックなどで作る。網針。あばり。
網結針
 [図]
[図]
 [図]
[図]
あみすて-かご【編(み)捨て籠】🔗⭐🔉
あみすて-かご [4] 【編(み)捨て籠】
竹籠の一種。中央を編んで周囲は編まないままにしたもの。魚などを形を崩さず煮るのに用いる。
アミセチン amicetin
amicetin 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
アミセチン [0]  amicetin
amicetin グラム陽性菌および抗酸菌の発育を抑制する抗生物質。抗腫瘍性もある。アロマイシン。サクロマイシン。
グラム陽性菌および抗酸菌の発育を抑制する抗生物質。抗腫瘍性もある。アロマイシン。サクロマイシン。
 amicetin
amicetin グラム陽性菌および抗酸菌の発育を抑制する抗生物質。抗腫瘍性もある。アロマイシン。サクロマイシン。
グラム陽性菌および抗酸菌の発育を抑制する抗生物質。抗腫瘍性もある。アロマイシン。サクロマイシン。
あみ-そ【網麻】🔗⭐🔉
あみ-そ [0] 【網麻】
網をすく材料として用いる麻糸。
あみだ【阿弥陀】🔗⭐🔉
あみだ [0] 【阿弥陀】
〔梵 Amit yus(無量寿と漢訳)・Amit
yus(無量寿と漢訳)・Amit bha(無量光と漢訳)の音訳〕
(1)〔仏〕 大乗仏教の浄土教の中心をなす仏。法蔵比丘(ビク)として修行中に衆生(シユジヨウ)救済の願をたて,現在は成仏し西方の極楽浄土で教化しているとされる。自力で成仏できない人も,念仏を唱えればその救済力によって,極楽に往生すると説く。平安時代に信仰が高まり,浄土宗・浄土真宗の本尊となる。弥陀(ミダ)。阿弥陀仏。阿弥陀如来。無量寿仏(ムリヨウジユブツ)。無量光仏。無碍光仏(ムゲコウブツ)。清浄光仏。尽十方無碍光如来(ジンジツポウムゲコウニヨライ)。
(2)「あみだくじ」の略。
(3)「あみだかぶり」の略。
(4)「あみだがさ」の略。
阿弥陀(1)
bha(無量光と漢訳)の音訳〕
(1)〔仏〕 大乗仏教の浄土教の中心をなす仏。法蔵比丘(ビク)として修行中に衆生(シユジヨウ)救済の願をたて,現在は成仏し西方の極楽浄土で教化しているとされる。自力で成仏できない人も,念仏を唱えればその救済力によって,極楽に往生すると説く。平安時代に信仰が高まり,浄土宗・浄土真宗の本尊となる。弥陀(ミダ)。阿弥陀仏。阿弥陀如来。無量寿仏(ムリヨウジユブツ)。無量光仏。無碍光仏(ムゲコウブツ)。清浄光仏。尽十方無碍光如来(ジンジツポウムゲコウニヨライ)。
(2)「あみだくじ」の略。
(3)「あみだかぶり」の略。
(4)「あみだがさ」の略。
阿弥陀(1)
 [図]
[図]
 yus(無量寿と漢訳)・Amit
yus(無量寿と漢訳)・Amit bha(無量光と漢訳)の音訳〕
(1)〔仏〕 大乗仏教の浄土教の中心をなす仏。法蔵比丘(ビク)として修行中に衆生(シユジヨウ)救済の願をたて,現在は成仏し西方の極楽浄土で教化しているとされる。自力で成仏できない人も,念仏を唱えればその救済力によって,極楽に往生すると説く。平安時代に信仰が高まり,浄土宗・浄土真宗の本尊となる。弥陀(ミダ)。阿弥陀仏。阿弥陀如来。無量寿仏(ムリヨウジユブツ)。無量光仏。無碍光仏(ムゲコウブツ)。清浄光仏。尽十方無碍光如来(ジンジツポウムゲコウニヨライ)。
(2)「あみだくじ」の略。
(3)「あみだかぶり」の略。
(4)「あみだがさ」の略。
阿弥陀(1)
bha(無量光と漢訳)の音訳〕
(1)〔仏〕 大乗仏教の浄土教の中心をなす仏。法蔵比丘(ビク)として修行中に衆生(シユジヨウ)救済の願をたて,現在は成仏し西方の極楽浄土で教化しているとされる。自力で成仏できない人も,念仏を唱えればその救済力によって,極楽に往生すると説く。平安時代に信仰が高まり,浄土宗・浄土真宗の本尊となる。弥陀(ミダ)。阿弥陀仏。阿弥陀如来。無量寿仏(ムリヨウジユブツ)。無量光仏。無碍光仏(ムゲコウブツ)。清浄光仏。尽十方無碍光如来(ジンジツポウムゲコウニヨライ)。
(2)「あみだくじ」の略。
(3)「あみだかぶり」の略。
(4)「あみだがさ」の略。
阿弥陀(1)
 [図]
[図]
あみだ-がさ【阿弥陀笠】🔗⭐🔉
あみだ-がさ [4] 【阿弥陀笠】
笠を後ろ下がりにかぶること。笠の内側の骨が仏像の光背の形に見えることからいう。あみだ。
あみだ-かぶり【阿弥陀被り】🔗⭐🔉
あみだ-かぶり [4] 【阿弥陀被り】
帽子などを,後ろ下がりにかぶること。あみだ。
あみだ-きょう【阿弥陀経】🔗⭐🔉
あみだ-きょう ―キヤウ 【阿弥陀経】
浄土三部経の一。一巻。原典はほぼ一世紀頃成立。402年,鳩摩羅什(クマラジユウ)漢訳。阿弥陀仏の極楽浄土の美しい光景を述べ,往生を勧める。仏説阿弥陀経。小経。
あみだ-くじ【阿弥陀籤】🔗⭐🔉
あみだ-くじ [3][4] 【阿弥陀籤】
人数分の線を引き,一端にそれぞれ異なる金額を書いて隠し,各自が引き当てた金額を出させるくじ。集めた金で茶菓子などを買い,平等に分配する。あみだ。
〔線の引き方が放射状で,阿弥陀仏の後光に似ていたからという〕
あみだ-こう【阿弥陀講】🔗⭐🔉
あみだ-こう ―カウ [0] 【阿弥陀講】
阿弥陀如来の功徳(クドク)を説き聞かせる法会(ホウエ)。平安後期から行われた。
あみだ-ごう【阿弥陀号】🔗⭐🔉
あみだ-ごう ―ガウ [3] 【阿弥陀号】
鎌倉時代以降,浄土宗各派や時宗の僧・信者の法号の一種で,下部に「阿弥陀仏」やその略である「阿弥陀」「阿弥」「阿」を含むもの。仏師・画工・能役者の名にも使われ,中世に特に多くみられる。頓阿・世阿弥など。阿号。
あみだ-ごま【阿弥陀護摩】🔗⭐🔉
あみだ-ごま [4][3] 【阿弥陀護摩】
密教で阿弥陀如来を本尊に,無病息災・延命を祈って焚(タ)く護摩。
あみだ-さんぞん【阿弥陀三尊】🔗⭐🔉
あみだ-さんぞん 【阿弥陀三尊】
(1)阿弥陀仏と,その左右に脇侍(キヨウジ)する左の観音と右の勢至の二菩薩。弥陀三尊。三尊の弥陀。
(2)阿弥陀三尊{(1)}の仏像。阿弥陀三尊像。
あみだ-どう【阿弥陀堂】🔗⭐🔉
あみだ-どう ―ダウ [0] 【阿弥陀堂】
(1)阿弥陀如来を本尊として安置した堂。
(2)千利休好みの釜(カマ)。豊臣秀吉が有馬温泉で開いた茶会でも用いられた。阿弥陀堂釜。
あみだ-にじゅうご-ぼさつ【阿弥陀二十五菩薩】🔗⭐🔉
あみだ-にじゅうご-ぼさつ ―ニジフゴ― 【阿弥陀二十五菩薩】
⇒二十五菩薩(ニジユウゴボサツ)
あみだ-にょらい【阿弥陀如来】🔗⭐🔉
あみだ-にょらい 【阿弥陀如来】
阿弥陀{(1)}の尊称。
あみだ-の-ひじり【阿弥陀の聖】🔗⭐🔉
あみだ-の-ひじり 【阿弥陀の聖】
(1)空也(クウヤ)上人の尊称。あみだひじり。
(2)空也に始まる踊り念仏の徒で,鹿角の杖をつき,金鼓(ゴング)をたたきながら阿弥陀仏の名号を唱え,極楽往生の教えを民衆の間にひろめて歩いた僧。
あみだ-ぶつ【阿弥陀仏】🔗⭐🔉
あみだ-ぶつ [3] 【阿弥陀仏】
「阿弥陀{(1)}」に同じ。
あみだ-ほう【阿弥陀法】🔗⭐🔉
あみだ-ほう ―ホフ [0][3] 【阿弥陀法】
密教で,阿弥陀を本尊に無病息災・延命を祈る修法。
あみだ-ぼとけ【阿弥陀仏】🔗⭐🔉
あみだ-ぼとけ 【阿弥陀仏】
「阿弥陀{(1)}」に同じ。
あみだ-まんだら【阿弥陀曼荼羅】🔗⭐🔉
あみだ-まんだら [4] 【阿弥陀曼荼羅】
阿弥陀如来を中心に描いた曼荼羅。阿弥陀法を修する際に用いる。
あみだ-わさん【阿弥陀和讃】🔗⭐🔉
あみだ-わさん [4] 【阿弥陀和讃】
阿弥陀の功徳をたたえた和讃。
あみだ-わり【阿弥陀割(り)】🔗⭐🔉
あみだ-わり [0] 【阿弥陀割(り)】
道路の配置を阿弥陀の後光に似せて,中心点から放射状に配する地割りの方法。
⇔碁盤割り
あみ-だいく【網大工】🔗⭐🔉
あみ-だいく [3] 【網大工】
網を作ったり,修理したりする人。網棟梁(アミトウリヨウ)。
あみだ-が-みね【阿弥陀ヶ峰】🔗⭐🔉
あみだ-が-みね 【阿弥陀ヶ峰】
京都市東山区,東山三十六峰の一。もと,山腹と山麓に阿弥陀堂があった。山頂に豊臣秀吉の廟(ビヨウ)(豊国廟)がある。
あみ-たけ【網茸】🔗⭐🔉
あみ-たけ [2] 【網茸】
担子菌類ハラタケ目のきのこ。夏から秋にかけマツ林などに群生する。傘の裏に多数の穴が生じて網状に見えるのでこの名がある。食用。
網茸
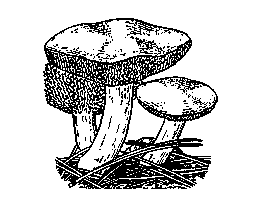 [図]
[図]
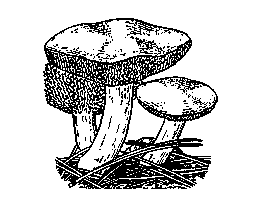 [図]
[図]
あみだ-じ【阿弥陀寺】🔗⭐🔉
あみだ-じ 【阿弥陀寺】
(1)山口県防府市牟礼(ムレ)にある真言宗御室(オムロ)派の寺。1187年重源(チヨウゲン)の建立。東大寺別所。浄土教発展の一拠点となった。
(2)山口県下関市阿弥陀町にあった寺。中世には浄土宗,近世では真言宗に転じた。安徳天皇鎮魂のため1191年に建立。1875年(明治8)寺を廃して赤間宮となる。
→赤間神宮
あみ-だ・す【編(み)出す】🔗⭐🔉
あみ-だ・す [3][0] 【編(み)出す】 (動サ五[四])
(1)編みはじめる。
(2)工夫して新しい物事や方法を考え出す。「新戦術を―・す」
[可能] あみだせる
あみ-だな【網棚】🔗⭐🔉
あみ-だな [0] 【網棚】
手荷物をのせるため,電車・バスなどの天井近くに網を張って作った棚。
あみだのむねわり【阿弥陀胸割】🔗⭐🔉
あみだのむねわり 【阿弥陀胸割】
古浄瑠璃,本地物の一。1614年の上演記録がある。因果応報と仏を信ずる者は大慈悲に浴しうることを説く。
あみ【網】(和英)🔗⭐🔉
あみあげ【編上げ(靴)】(和英)🔗⭐🔉
あみあげ【編上げ(靴)】
lace boots.
あみうち【網打ち】(和英)🔗⭐🔉
あみうち【網打ち】
net fishing.
あみがさ【編み笠】(和英)🔗⭐🔉
あみがさ【編み笠】
a braided hat.
あみき【編機】(和英)🔗⭐🔉
あみき【編機】
a knitting machine.
あみざいく【網細工】(和英)🔗⭐🔉
あみざいく【網細工】
network.→英和
あみしゃつ【網シャツ】(和英)🔗⭐🔉
あみしゃつ【網シャツ】
a netted shirt.
あみだ【阿彌陀】(和英)🔗⭐🔉
あみだ【阿彌陀】
Amitabha.〜(くじ)をやる draw lots for clubbing money.
あみだな【網棚】(和英)🔗⭐🔉
あみだな【網棚】
a rack.→英和
大辞林に「アミ」で始まるの検索結果 1-86。もっと読み込む