複数辞典一括検索+![]()
![]()
した【舌】🔗⭐🔉
した [2] 【舌】
(1)脊椎動物の口腔底にあって粘膜におおわれた骨格筋性の器官。魚類は筋肉を欠き粘膜状,一般の動物では筋肉・腺をそなえ,可動性。ヒトでは唾液腺が開口し,味覚・触覚をつかさどるほか,咀嚼(ソシヤク)嚥下(エンゲ)を助け,発声器の一部でもある。べろ。
(2)物を言うこと。また,その言い方。くち。「その―にあひては,すなほに心よき人も/浴泉記(喜美子)」
(3)舌に似た形のもの。「鐙(アブミ)の―」
→簧(シタ)
した=が回・る🔗⭐🔉
――が回・る
すらすらとよどみなくしゃべる。口が達者である。「よく―・る男だ」
した=が縺(モツ)・れる🔗⭐🔉
――が縺(モツ)・れる
舌が自由に動かなくなって,言葉がうまくしゃべれなくなる。
した=の剣(ツルギ)は命(イノチ)を絶つ🔗⭐🔉
――の剣(ツルギ)は命(イノチ)を絶つ
言動を慎まないために命を落とすたとえ。「口の虎は身を破ぶる。―/十訓 4」
した=の根(ネ)の乾(カワ)かぬうち🔗⭐🔉
――の根(ネ)の乾(カワ)かぬうち
言い終えてすぐに。
〔前言に反する発言を非難するときに用いる〕
「―に約束をたがえては困る」
した=は禍(ワザワ)いの根(ネ)🔗⭐🔉
――は禍(ワザワ)いの根(ネ)
〔老子「夫舌禍福之門」〕
災いは多く言葉から起こるものである。口は禍いの門。
した=も引かぬ🔗⭐🔉
――も引かぬ
まだ言い終わらない。言い終えてすぐ。「愚痴文盲のお名が流れん笑止
 と,―に六波羅よりはや使/浄瑠璃・平家女護島」
と,―に六波羅よりはや使/浄瑠璃・平家女護島」

 と,―に六波羅よりはや使/浄瑠璃・平家女護島」
と,―に六波羅よりはや使/浄瑠璃・平家女護島」
した=を食(ク)・う🔗⭐🔉
――を食(ク)・う
舌をかみ切って死ぬ。「―・ふか身を投げるか/浄瑠璃・丹波与作(下)」
した=を出(ダ)・す🔗⭐🔉
――を出(ダ)・す
(1)陰でばかにする。心の中であざわらう。「腹の中で―・しているにちがいない」
(2)自分の失敗を恥じたり,ごまかしたりするしぐさにいう。
した=を鳴ら・す🔗⭐🔉
――を鳴ら・す
舌を上顎(ウワアゴ)に当ててはじき鳴らす。
(1)感嘆するさま。
(2)おいしい物を食べて満足しているさま。
(3)不満や軽蔑の気持ちを表すさま。
した=を吐(ハ)・く🔗⭐🔉
――を吐(ハ)・く
ひどくあきれる。「直行は―・きて独語(ヒトリゴ)ちぬ/金色夜叉(紅葉)」
した=を振る・う🔗⭐🔉
――を振る・う
(1)弁舌を振るう。雄弁を振るう。
(2)「舌(シタ)を振(フ)る」に同じ。「見聞の人―・はして懼(オソ)れ思はぬ者は無りけり/太平記 21」
した=を巻・く🔗⭐🔉
――を巻・く
〔漢書(揚雄伝)〕
(相手に圧倒されて)非常に驚く。感心する。「見事な采配(サイハイ)ぶりに―・く」
した-うち【舌打ち】🔗⭐🔉
した-うち [0][4] 【舌打ち】 (名)スル
舌を上顎(ウワアゴ)に当ててはじき鳴らすこと。
(1)残念な気持ちや不愉快な気持ちなどを表す動作。「口惜しそうに―する」
(2)美味なものを味わったりするときの動作。舌鼓(シタツヅミ)。
したうち-おん【舌打ち音】🔗⭐🔉
したうち-おん [4] 【舌打ち音】
⇒吸着音(キユウチヤクオン)
した-がわ【舌革】🔗⭐🔉
した-がわ ―ガハ [0] 【舌革】
靴の部分の名。つま先から履き口に向かって,ひもの下側を舌状に延びている革。
したきりすずめ【舌切り雀】🔗⭐🔉
したきりすずめ [5] 【舌切り雀】
昔話の一。動物報恩譚。雀に糊(ノリ)をなめられた老婆が怒って,雀の舌を切って追い出す。心配した老爺が雀の宿を訪問して歓待され,宝の入った軽いつづらをもらって帰る。うらやんだ老婆が行って重いつづらをもらうが,開けてみると中から蛇・化け物などが出るというのが荒筋。明治時代に国定教科書に採用され一般化。古典では「宇治拾遺物語」にみえる。
した-さき【舌先】🔗⭐🔉
した-さき [0][4] 【舌先】
(1)舌の先。「―で味わう」
(2)口先。言葉。弁舌。「―が達者な人」
したさき-さんずん【舌先三寸】🔗⭐🔉
したさき-さんずん [5] 【舌先三寸】
口先だけの巧みな弁舌。舌三寸。「―で言いくるめる」
した-ざわり【舌触り】🔗⭐🔉
した-ざわり ―ザハリ [3] 【舌触り】
(食べ物や飲み物などが)舌に触れたときの感じ。「とろけるような―」
した-さんずん【舌三寸】🔗⭐🔉
した-さんずん [3] 【舌三寸】
「舌先三寸(シタサキサンズン)」に同じ。「男も女もつつしむべきは―/浄瑠璃・嫗山姥」
した-だい【舌代】🔗⭐🔉
した-だい [0] 【舌代】
〔口で言うべきところを代わりに文字で示した,の意〕
飲食店などで,客に示す挨拶(アイサツ)・値段表などの初めに記す語。口上。口上書き。ぜつだい。
しただしさんば【舌出し三番】🔗⭐🔉
しただしさんば 【舌出し三番】
歌舞伎舞踊の一。長唄・清元。本名題「再春菘種蒔(マタクルハルスズナノタネマキ)」。二世桜田治助作詞。1812年江戸中村座初演。志賀山流の三番叟で復活した軽妙な踊り。舌出し三番叟。志賀山三番。種蒔三番。
した-たらず【舌足らず】🔗⭐🔉
した-たらず [3] 【舌足らず】 (名・形動)[文]ナリ
(1)舌がよく回らず,発音がはっきりしない・こと(さま)。「―でよく聞き取れない」
(2)言葉・表現などが不十分なこと。十分に言い表していないこと。また,そのさま。「―な文章」
した-たる・い【舌たるい】🔗⭐🔉
した-たる・い [4] 【舌たるい】 (形)[文]ク したたる・し
〔近世以降の語〕
(1)物の言いようが甘えたようである。また,態度がべたべたしている。「益々寄添ひつつ,―・いまでに語(コトバ)を和げて/金色夜叉(紅葉)」
(2)物の言い方がくどくどしている。したるし。「―・い愚痴沢山な自惚やら楽屋落やら列べれば/社会百面相(魯庵)」
した-つき【舌つき】🔗⭐🔉
した-つき 【舌つき】 (名・形動ナリ)
物の言い方がはっきりしないこと。またそのさま。舌たらず。「声(コワ)づかひの,さすがに―にて,うちざれむとは,なほ思へり/源氏(朝顔)」
した-つづみ【舌鼓】🔗⭐🔉
した-つづみ [3] 【舌鼓】
〔「したづつみ」とも〕
おいしい物を味わったときに鳴らす舌の音。
したつづみ=を打・つ🔗⭐🔉
――を打・つ
(1)おいしい物を味わった満足感を舌を鳴らして表す。
(2)不愉快な気持ちを,舌を鳴らして表す。「さりとは憎い奴と―・つ所へ帰りぬ/浮世草子・新色五巻書」
した-ど【舌疾】🔗⭐🔉
した-ど 【舌疾】 (形動ナリ)
早口なさま。舌速(シタバヤ)。「のたまふけはひの―にあはつけきを/源氏(賢木)」
した-ど・し【舌疾し】🔗⭐🔉
した-ど・し 【舌疾し】 (形ク)
物言いがはやい。早口だ。「小賽(シヨウサイ)小賽とこふ声ぞ,いと―・きや/源氏(常夏)」
した-なが【舌長】🔗⭐🔉
した-なが 【舌長】 (形動ナリ)
身のほどもわきまえず大きなことを言うさま。口はばったいさま。「やあ,畜生とは―な梅王/浄瑠璃・菅原」
したなが-あぶみ【舌長鐙】🔗⭐🔉
したなが-あぶみ [5] 【舌長鐙】
鐙の一。足を乗せる所(舌)が長い鐙。
⇔舌短(シタミジカ)鐙
舌長鐙
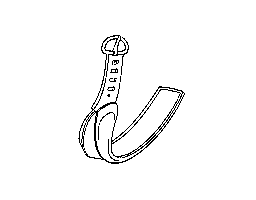 [図]
[図]
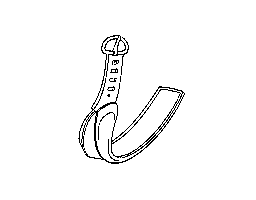 [図]
[図]
した-なが・し【舌長し】🔗⭐🔉
した-なが・し 【舌長し】 (形ク)
はばからない言いぶりである。「身が生国は大日本風来とは―・し/浄瑠璃・国性爺合戦」
した-なめずり【舌舐めずり】🔗⭐🔉
した-なめずり ―ナメヅリ [3][4] 【舌舐めずり】 (名)スル
(1)おいしい食物を前にしたり想像したときや食事の前後に,舌で唇をなめること。
(2)何かしようと獲物を待ち構えているようす。
した-の-ね【舌の根】🔗⭐🔉
した-の-ね [4] 【舌の根】
舌の付け根。
→舌の根の乾(カワ)かぬうち(「舌」の句項目)
した-ばや【舌速】🔗⭐🔉
した-ばや 【舌速】 (形動ナリ)
物言いのはやいさま。口ばや。早口。舌疾(シタド)。「此の恨は尽きすまじ。尽きせじ晴れじ忘れじ止まじと,―に/浄瑠璃・用明天皇」
した-びらめ【舌鮃・舌平目】🔗⭐🔉
した-びらめ [3] 【舌鮃・舌平目】
カレイ目ウシノシタ科とササウシノシタ科の海魚の総称。全長約10〜30センチメートル。体形は扁平で,牛の舌に似る。体色が赤いアカシタビラメや,黒いクロウシノシタなど日本近海に二八種がいる。大形のものはムニエルやバター焼きにして美味。本州中部以南の沿岸に分布。
→ウシノシタ
舌鮃
 [図]
[図]
 [図]
[図]
した-ぶり【舌風・舌振り】🔗⭐🔉
した-ぶり 【舌風・舌振り】
(1)物の言い方。口のききよう。「―いと物さわやかなり/源氏(行幸)」
(2)「舌振(シタブ)るい」に同じ。「―ヲスル/日葡」
した-ぶるい【舌振るひ】🔗⭐🔉
した-ぶるい ―ブルヒ 【舌振るひ】
驚き恐れて,舌を震わせること。舌振り。「東国の兵これを見て,―して進まざりければ/盛衰記 35」
→舌を振る
した-へん【舌偏】🔗⭐🔉
した-へん [0] 【舌偏】
漢字の偏の一。「辞」「舐」などの「舌」。
したみじか-あぶみ【舌短鐙】🔗⭐🔉
したみじか-あぶみ [6] 【舌短鐙】
鐙の一。足を乗せる所(舌)が短い鐙。
⇔舌長(シタナガ)鐙
した-もじり【舌捩り】🔗⭐🔉
した-もじり ―モヂリ [3] 【舌捩り】
言葉遊びの一。発音しづらい言葉を連ねて言わせるもの。「お綾(アヤ)や親にお謝り。お綾や親にお謝りとお言い」など。
ぜつあつ-し【舌圧子】🔗⭐🔉
ぜつあつ-し [4] 【舌圧子】
口腔内や咽頭を見るとき,舌を押し下げるために用いる篦(ヘラ)状の器具。圧舌子。
ぜついん-しんけい【舌咽神経】🔗⭐🔉
ぜついん-しんけい [5] 【舌咽神経】
延髄の上部より発し,舌根・咽頭に分布する,知覚および運動神経から成る神経。第九脳神経。
ぜつ-えん【舌炎】🔗⭐🔉
ぜつ-えん [0] 【舌炎】
舌の炎症。各種口腔疾患,胃炎,全身の感染症,ビタミン欠乏症の際にみられる。
ぜつ-おん【舌音】🔗⭐🔉
ぜつ-おん [2] 【舌音】
(1)舌先を歯または歯茎につけて発音する音。タ・ダ・ナ・ラ行などの各音。
(2)中国古代の音韻学で五音(ゴイン)の一。舌先を上の歯茎ないし硬口蓋につけて調音される音。「端」「定」「知」「娘」などの子音をさす。
ぜっ-か【舌下】🔗⭐🔉
ぜっ-か [1] 【舌下】
舌の下。
ぜっか-じょう【舌下錠】🔗⭐🔉
ぜっか-じょう ―ヂヤウ [3] 【舌下錠】
医薬品の迅速な全身への作用を目的とした錠剤。舌下に置いて舌でこね,素早く溶かして粘膜から吸収させる。狭心症の発作をコントロールするためなどに用いる。
→バッカル
ぜっか-しんけい【舌下神経】🔗⭐🔉
ぜっか-しんけい [4] 【舌下神経】
舌筋に分布する純運動性の神経。延髄の腹側から出る。第一二脳神経。
ぜっか-せん【舌下腺】🔗⭐🔉
ぜっか-せん [0] 【舌下腺】
舌の下部にあり,唾液を分泌する器官。
ぜっ-か【舌禍】🔗⭐🔉
ぜっ-か ―クワ [1][0] 【舌禍】
演説や講演などの内容が法律や他人の怒りにふれたために,災いにあうこと。「―をまねく」
ぜつ-がん【舌癌】🔗⭐🔉
ぜつ-がん [2] 【舌癌】
舌に発生する癌腫。
ぜっ-きん【舌筋】🔗⭐🔉
ぜっ-きん [0] 【舌筋】
舌を構成する筋肉。横紋筋で構成され,舌下神経の支配をうける。
ぜっ-こう【舌口】🔗⭐🔉
ぜっ-こう [0] 【舌口】
(1)舌と口。
(2)くちさき。くちまえ。
ぜっ-こう【舌耕】🔗⭐🔉
ぜっ-こう ―カウ [0] 【舌耕】
〔拾遺記「賈逵(カキ)非 力耕所
力耕所 得,誦
得,誦 経口倦。世所謂舌耕也」〕
弁舌によって生計をたてること。講義・演説などによって生活費を得ること。
経口倦。世所謂舌耕也」〕
弁舌によって生計をたてること。講義・演説などによって生活費を得ること。
 力耕所
力耕所 得,誦
得,誦 経口倦。世所謂舌耕也」〕
弁舌によって生計をたてること。講義・演説などによって生活費を得ること。
経口倦。世所謂舌耕也」〕
弁舌によって生計をたてること。講義・演説などによって生活費を得ること。
ぜっ-こつ【舌骨】🔗⭐🔉
ぜっ-こつ [0] 【舌骨】
舌根の下部にある馬蹄形の小骨。
ぜっ-こん【舌根】🔗⭐🔉
ぜっ-こん [0] 【舌根】
(1)舌の最も奥の部分。舌の付け根。
(2)〔仏〕 五根,また六根の一。味覚を生ずる器官である舌,およびその味覚能力。
ぜつ-じょう【舌状】🔗⭐🔉
ぜつ-じょう ―ジヤウ [0] 【舌状】
舌のような形状。
ぜつじょう-かかん【舌状花冠】🔗⭐🔉
ぜつじょう-かかん ―ジヤウクワクワン [5] 【舌状花冠】
合弁花冠の一。一つの花の全花弁が融合して筒状となり,上部のみが平らで舌のような形をしたもの。タンポポなどの花冠。
ぜつ-じん【舌人】🔗⭐🔉
ぜつ-じん [0] 【舌人】
通訳をする人。通弁。通事。「長崎―の事跡に精(クワ)しい人の教を得た/伊沢蘭軒(鴎外)」
ぜっせん-おん【舌尖音】🔗⭐🔉
ぜっせん-おん [3] 【舌尖音】
舌尖と歯,歯茎,前部硬口蓋などで狭めが形成される言語音。日本語の「サ」の発音では,舌尖が下の門歯の裏についていれば舌尖音とはならないが,上の門歯に向かって持ち上がったような調音の場合には舌尖的となる。
ぜっ-せん【舌戦】🔗⭐🔉
ぜっ-せん [0] 【舌戦】
言葉で争うこと。口論。論戦。「激しい―が繰り広げられた」
ぜっ-そ【舌疽】🔗⭐🔉
ぜっ-そ [1] 【舌疽】
舌にできる腫(ハ)れ物。
ぜっ-たい【舌苔】🔗⭐🔉
ぜっ-たい [0] 【舌苔】
舌の表面にできる白色または褐色の苔(コケ)状のもの。胃腸障害・熱性疾患などの際に見られる。
ぜつ-だい【舌代】🔗⭐🔉
ぜつ-だい [0] 【舌代】
口で告げる代わりに文字で簡単に書き表したもの。口上書きや飲食店の値段表などに書く。
ぜっ-たん【舌端】🔗⭐🔉
ぜっ-たん [0] 【舌端】
(1)舌の先。特に調音点として,舌の最先端部(舌尖)のすぐ後ろの上面の部分。
(2)くちさき。弁舌。ものいい。
ぜったん=火を吐・く🔗⭐🔉
――火を吐・く
勢い鋭く論じたてるさまにいう。
ぜったん-おん【舌端音】🔗⭐🔉
ぜったん-おん [3] 【舌端音】
舌端が閉鎖もしくは狭められて形成される言語音。日本語のツは,舌端の前部と歯茎および歯による調音。
ぜっ-とう【舌頭】🔗⭐🔉
ぜっ-とう [0] 【舌頭】
(1)舌の先端。
(2)言葉。弁舌。「そんな大議論を―に弄(ロウ)する以上は/吾輩は猫である(漱石)」
ぜつない-おん【舌内音】🔗⭐🔉
ぜつない-おん [3] 【舌内音】
悉曇(シツタン)学で,三内音の一。舌によって調音される音。[t][d][n]の類。
→三内音
ぜつ-にゅうとう【舌乳頭】🔗⭐🔉
ぜつ-にゅうとう [3] 【舌乳頭】
舌の表面の粘膜にある固い小突起。
ぜっ-ぽう【舌鋒】🔗⭐🔉
ぜっ-ぽう [0] 【舌鋒】
鋭い弁舌。弁舌・議論などの鋭いことを鋒(ホコ)にたとえていう。「―鋭く攻撃する」
した【舌】(和英)🔗⭐🔉
した【舌】
the tongue.→英和
〜が荒れている One's tongue is rough.〜が回らない be tongue-tied.〜がもつれる have difficulty in articulation.〜を出(鳴ら)す put[stick]out (clack) one's tongue.〜を巻く be astounded.
したうち【舌打ちする】(和英)🔗⭐🔉
したうち【舌打ちする】
click one's tongue;tut.→英和
したさき【舌先】(和英)🔗⭐🔉
したさき【舌先】
the tip of the tongue.→英和
〜でごまかす explain away.
したつづみ【舌鼓を打つ】(和英)🔗⭐🔉
したつづみ【舌鼓を打つ】
smack one's lips;eat with much gusto (食べる).
したなめずり【舌舐りする】(和英)🔗⭐🔉
したなめずり【舌舐りする】
lick one's lips.〜して食べる eat with much relish.
したびらめ【舌平目】(和英)🔗⭐🔉
したびらめ【舌平目】
《魚》a sole.→英和
ぜっか【舌禍】(和英)🔗⭐🔉
ぜっか【舌禍】
an unfortunate slip of the tongue.→英和
ぜつがん【舌癌】(和英)🔗⭐🔉
ぜつがん【舌癌】
cancer on the tongue.→英和
ぜっせん【舌戦】(和英)🔗⭐🔉
ぜっせん【舌戦】
⇒言論(戦).
ぜったい【舌苔】(和英)🔗⭐🔉
ぜったい【舌苔】
《医》fur.→英和
ぜつだい【舌代】(和英)🔗⭐🔉
ぜつだい【舌代】
a brief note.
大辞林に「舌」で始まるの検索結果 1-85。