複数辞典一括検索+![]()
![]()
かしこ【賢・畏】🔗⭐🔉
かしこ [1] 【賢・畏】
(形容詞「かしこし」の語幹)
□一□〔おそれ慎む意〕
女性が手紙の末尾に書いて敬意を表す語。あらかしこ。あらあらかしこ。かしく。
〔中古には仮名文の消息で男女共に用いた。近世頃から女性のみが用いる〕
□二□
(1)おそれ多いこと。はばかられること。
→あなかしこ
(2)頭がよく知能がすぐれていること。「われ―に思ひたる人/紫式部日記」
(3)技能がすぐれていること。「―の御手やと空を仰ぎてながめ給ふ/源氏(葵)」
かしこ-だて【賢立て】🔗⭐🔉
かしこ-だて 【賢立て】
賢そうにふるまうこと。「多分,人ワ―ヲシテシソコナウモノヂャ/天草本伊曾保」
かしこ・い【賢い・畏い】🔗⭐🔉
かしこ・い [3] 【賢い・畏い】 (形)[文]ク かしこ・し
□一□
(1)頭の働きがよく知恵がすぐれている。賢明だ。《賢》「―・い子」「犬は―・い動物だ」
(2)要領がよい。抜け目がない。《賢》「―・い男だから,その辺はうまく処理するだろう」「―・く立ち回る」
□二□
(1)自然や神など威力・霊力を備えているものに対して脅威を感ずるさま。恐ろしい。畏怖の念に堪えない。「海人娘子(アマオトメ)玉求むらし沖つ波―・き海に船出せり見ゆ/万葉 1003」
(2)高貴な者に対する畏敬の気持ちを表す。おそれ多い。もったいない。「勅なればいとも―・し鶯の宿はと問はば/拾遺(雑下)」
(3)身分・血筋などがきわめてすぐれている。高貴だ。「―・き筋と聞ゆれど/源氏(若菜上)」
(4)立派だ。素晴らしい。「―・き玉の枝をつくらせ給ひて/竹取」
(5)都合がよい。具合がよい。「―・くも(良イ婿ヲ)取りつるかな/落窪 2」
(6)(連用形を副詞的に用いて)はなはだしく。ひどく。「これかれ―・く嘆く/土左」
〔「かしこまる」と同源で,恐るべき威力に対して身のすくむような思いがするさまを表す□二□(1)が原義。そこから恐れ敬う意が生じ,さらに畏敬すべき性質や能力が備わっているさまを表す意ともなった〕
[派生] ――げ(形動)――さ(名)
かしこ・し【賢し・畏し】🔗⭐🔉
かしこ・し 【賢し・畏し】 (形ク)
⇒かしこい
かしこ-じま【賢島】🔗⭐🔉
かしこ-じま 【賢島】
三重県東部,英虞(アゴ)湾北部にある小島。志摩観光の一中心。
かしこ-どころ【賢所】🔗⭐🔉
かしこ-どころ [4] 【賢所】
(1)宮中で天照大神の御霊代(ミタマシロ)として神鏡八咫鏡(ヤタノカガミ)を安置している所。平安時代には内裏の温明殿(ウンメイデン)の南側にあり,内侍が奉仕したので内侍所(ナイシドコロ)ともいった。現在は皇居の吹上御苑にある。けんしょ。
(2)神鏡。「―をいだし奉るにも及ばず/平家 11」
かしこどころ-おおまえ-の-ぎ【賢所大前の儀】🔗⭐🔉
かしこどころ-おおまえ-の-ぎ ―オホマヘ― 【賢所大前の儀】
即位礼に際して,天皇が即位したことを賢所に告げる儀式。
かしこどころ-みかぐら【賢所御神楽】🔗⭐🔉
かしこどころ-みかぐら [8] 【賢所御神楽】
皇室の小祭の一。毎年12月中旬,賢所の前庭で行われる神楽。内侍所御神楽。
けん【賢】🔗⭐🔉
けん [1] 【賢】 (名・形動)[文]ナリ
学徳がすぐれかしこい・こと(さま)。「彼れ美にして且つ―なり/花柳春話(純一郎)」
けん-おう【賢王】🔗⭐🔉
けん-おう ―ワウ [0][3] 【賢王】
賢明な君主。才知と徳を兼ね備えた立派な君主。
けん-ぐ【賢愚】🔗⭐🔉
けん-ぐ [1] 【賢愚】
賢いことと愚かなこと。賢者と愚者。
けん-くん【賢君】🔗⭐🔉
けん-くん [0] 【賢君】
賢明な君主。
けん-けい【賢兄】🔗⭐🔉
けん-けい [0] 【賢兄】
■一■ (名)
かしこい兄。また,他人の兄を敬っていう語。「―愚弟」
■二■ (代)
二人称。男子が手紙などで同輩を敬っていう語。大兄。貴兄。
けん-さい【賢才】🔗⭐🔉
けん-さい [0] 【賢才】
すぐれた才能。賢明な人。
けん-さい【賢妻】🔗⭐🔉
けん-さい [0] 【賢妻】
かしこい妻。「―ぶりを発揮する」
けん-さつ【賢察】🔗⭐🔉
けん-さつ [0] 【賢察】 (名)スル
他人が推察することを敬っていう語。高察。お察し。「御―の通りです」
けん-し【賢士】🔗⭐🔉
けん-し [1] 【賢士】
かしこい人。賢人。
けんじゃ=ひだるし伊達(ダテ)寒し🔗⭐🔉
――ひだるし伊達(ダテ)寒し
賢者は世俗に妥協しないために飢え,伊達者は薄着をするので寒い。俗人とちがった生き方をするものはつらい目にあうというたとえ。
けんじゃ-の-いし【賢者の石】🔗⭐🔉
けんじゃ-の-いし 【賢者の石】
中世ヨーロッパの錬金術師たちが,あらゆる物を金に変え,またあらゆる病気を治す力があると信じて探し求めた物質。哲学者の石。
けん-しゅ【賢主】🔗⭐🔉
けん-しゅ [1] 【賢主】
賢明な君主。
けん-しょ【賢所】🔗⭐🔉
けん-しょ [1] 【賢所】
⇒かしこどころ(賢所)
けん-じょ【賢女】🔗⭐🔉
けん-じょ ―ヂヨ [1] 【賢女】
かしこい女。
けんじょ-だて【賢女立て】🔗⭐🔉
けんじょ-だて ―ヂヨ― 【賢女立て】
賢女らしく振る舞うこと。「おのれが縁を切らずんば,―して我心に従ふまじと思うて/浄瑠璃・井筒業平」
けん-しょう【賢相】🔗⭐🔉
けん-しょう ―シヤウ [0] 【賢相】
賢明な宰相。賢宰。
けん-しょう【賢将】🔗⭐🔉
けん-しょう ―シヤウ [0] 【賢将】
かしこくすぐれた将軍。
けん-じょう【賢聖】🔗⭐🔉
けん-じょう ―ジヤウ [0] 【賢聖】
(1)〔仏〕
〔「げんじょう」とも〕
(ア)悪を去ったが凡夫にとどまっている者(=賢)と,真理をさとった者(=聖)。けんせい。
→見道(ケンドウ)
(イ)仏道修行を積んだ高徳の僧。
(2)「賢聖(ケンセイ){(1)}」に同じ。
けんじょう-の-そうじ【賢聖の障子】🔗⭐🔉
けんじょう-の-そうじ ―ジヤウ―サウジ 【賢聖の障子】
紫宸殿(シシンデン)の母屋と北廂(キタビサシ)を隔てる障子。九枚あり,中央には獅子・狛犬と文書を負った亀を,左右各四枚には中国唐代までの聖賢・名臣を一枚に四人ずつ三二人の肖像を描く。
けん-しん【賢臣】🔗⭐🔉
けん-しん [0] 【賢臣】
かしこい臣下。「―二君に仕えず」
けん-じん【賢人】🔗⭐🔉
けん-じん [0] 【賢人】
(1)知識が豊かで徳のある人。聖人に次いで徳のある人。「竹林の七―」
(2)(清酒を聖人というのに対して)濁り酒。賢酒。
けんじん-だて【賢人立て】🔗⭐🔉
けんじん-だて 【賢人立て】
賢人らしく見せかけること。「ただ一人まじりたまはざりつれば,―かと思ひて侍つるに/著聞 12」
けん-せい【賢聖】🔗⭐🔉
けん-せい [0] 【賢聖】
(1)賢人と聖人。また,知恵と徳を兼ねそなえた人。聖賢。けんじょう。
(2)〔仏〕「賢聖(ケンジヨウ){(1)}」に同じ。
(3)にごり酒(=賢)と清酒(=聖)。
けん-そく【賢息】🔗⭐🔉
けん-そく [0] 【賢息】
他人を敬ってその子息をいう語。また,かしこい子息。
けん-だい【賢台】🔗⭐🔉
けん-だい [1][0] 【賢台】 (代)
二人称。男子が手紙などで,同輩または先輩を敬っていう語。貴兄。貴台。
けん-ち【賢智】🔗⭐🔉
けん-ち [1] 【賢智】
賢く知恵のあること。また,その人。
けん-てい【賢弟】🔗⭐🔉
けん-てい [0] 【賢弟】
■一■ (名)
かしこい弟。また,他人の弟に対する敬称。「愚兄―」
■二■ (代)
二人称。男子が手紙などで,年下の男子を敬っていう語。
けん-てつ【賢哲】🔗⭐🔉
けん-てつ [0] 【賢哲】 (名・形動)[文]ナリ
(1)賢人と哲人。
(2)賢明で道理に通じていること。また,そうした人やさま。「―なる者其信ずる所を明かにして/明六雑誌 8」
けん-とう【賢答】🔗⭐🔉
けん-とう ―タフ [0] 【賢答】
(1)賢明な答え。立派な答え。「愚問―」
(2)相手を敬ってその答えをいう語。
けん-とく【賢徳】🔗⭐🔉
けん-とく [0] 【賢徳】
狂言面の一。鬼畜面で,「犬山伏」の犬,「止動方角」の馬,また蟹(カニ)・蛸(タコ)などに用いる。
賢徳
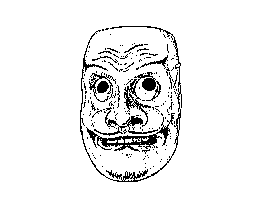 [図]
[図]
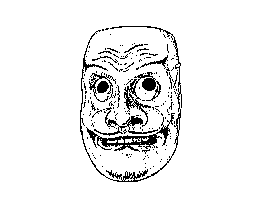 [図]
[図]
けん-のう【賢能】🔗⭐🔉
けん-のう [0] 【賢能】
賢くて才能のあること。また,その人。
けん-ぷ【賢婦】🔗⭐🔉
けん-ぷ [1] 【賢婦】
かしこくしっかりした婦人。賢婦人。
けん-ぷじん【賢夫人】🔗⭐🔉
けん-ぷじん [3] 【賢夫人】
かしこくてしっかりした夫人。
けん-ぼ【賢母】🔗⭐🔉
けん-ぼ [1] 【賢母】
賢明な母。かしこい母。「良妻―」
けん-めい【賢明】🔗⭐🔉
けん-めい [0] 【賢明】 (名・形動)[文]ナリ
賢くて,適切な判断を下せる・こと(さま)。「―な判断」
[派生] ――さ(名)
けん-らん【賢覧】🔗⭐🔉
けん-らん [0] 【賢覧】
相手が見ることを敬っていう語。高覧。「―を願う」
けん-りょ【賢慮】🔗⭐🔉
けん-りょ [1] 【賢慮】
(1)賢い考え。賢明な思慮。
(2)相手の考え・判断などを敬っていう語。
けん-りょう【賢良】🔗⭐🔉
けん-りょう ―リヤウ [0] 【賢良】 (名・形動)[文]ナリ
(1)賢くて善良なこと。また,その人やさま。「君主宰臣の―なりしを/日本開化小史(卯吉)」
(2)中国漢代,官吏登用試験の科目の名。また,それに推挙された才学のある者。
けん-ろ【賢路】🔗⭐🔉
けん-ろ [1] 【賢路】
賢者の昇進するみち。
けんろ=を塞(フサ)ぐ🔗⭐🔉
――を塞(フサ)ぐ
〔潘岳(「河陽県作」)〕
不徳不才の者が官職にとどまって,賢者の昇進の邪魔になること。
さか-き【榊・賢木】🔗⭐🔉
さか-き [0] 【榊・賢木】
〔栄える木の意〕
(1)神域に植える常緑樹の総称。また,神事に用いる木。
(2)ツバキ科の常緑小高木。暖地の山中に自生。高さ約10メートル。葉は互生し,長楕円状倒卵形。濃緑色で質厚く光沢がある。六,七月,白色の小花を開く。枝葉を神事に用いる。
〔「榊の花」は [季]夏〕
→ひさかき
(3)源氏物語の巻名。第一〇帖。
さかさか・し【賢賢し】🔗⭐🔉
さかさか・し 【賢賢し】 (形シク)
〔「さかざかし」とも〕
機転がきく。しっかりしている。「奴は合戦におきては,以ての外―・しき者にて候/保元(上)」
さかし・い【賢しい】🔗⭐🔉
さかし・い [3] 【賢しい】 (形)[文]シク さか・し
(1)かしこい。利口だ。「それが―・い生き方というものなのだろう」
(2)小利口で,なまいきだ。こざかしい。「へんに―・いところが人に嫌われる」
(3)盛んである。栄えている。「斑鳩のなみきの宮にたてし憲法(ノリ)今の―・しき御代にあふかな/日本紀竟宴和歌」
(4)気が強い。勇ましい。心がしっかりしている。「中に心―・しき者,念じて射むとすれども/竹取」
(5)すぐれている。巧みだ。じょうずだ。「ことひとびとのもありけれど,―・しきもなかるべし/土左」
(6)健康だ。じょうぶだ。「をのが―・しからむときこそ,いかでもいかでもものしたまはめ/蜻蛉(上)」
[派生] ――げ(形動)
さかし-だ・つ【賢し立つ】🔗⭐🔉
さかし-だ・つ 【賢し立つ】 (動タ四)
かしこそうに振る舞う。利口ぶる。さかしがる。「さばかり―・ち真名書き散らして侍るほども/紫式部日記」
さかし-ら【賢しら】🔗⭐🔉
さかし-ら [0] 【賢しら】 (名・形動)[文]ナリ
〔「ら」は接尾語〕
(1)利口ぶること。いかにもわかっているというふうに振る舞うこと。また,そのさま。「―を言う」「―をする」「―な顔つき」
(2)自分の考えで行動すること。「大君の遣はさなくに―に行きし荒雄ら沖に袖振る/万葉 3860」
(3)差し出口をきくこと。「―する親ありて,思ひもぞつくとて,この女をほかへ追ひやらむとす/伊勢 40」
(4)でしゃばる・こと(さま)。「まだ夜は深からむものを。葛城の神の―にや/狭衣 4」
さかしら-ぐち【賢しら口】🔗⭐🔉
さかしら-ぐち [4] 【賢しら口】
利口ぶった口ぶり。「―をきく」
さかしら-びと【賢しら人】🔗⭐🔉
さかしら-びと 【賢しら人】
でしゃばる人。利口ぶった人。「―すくなくて良き折りにこそ,と思へば/源氏(手習)」
かしこい【賢い】(和英)🔗⭐🔉
かしこさ【賢さ】(和英)🔗⭐🔉
けんじゃ【賢者】(和英)🔗⭐🔉
けんじゃ【賢者】
⇒賢人.
けんじん【賢人】(和英)🔗⭐🔉
けんじん【賢人】
a wise man;a sage.→英和
大辞林に「賢」で始まるの検索結果 1-64。